 |
武蔵の五輪書を読む 五輪書研究会版テクスト全文 現代語訳と注解・評釈 |
|
解 題 目 次 地 之 巻 水 之 巻 火 之 巻 風之巻巻頭 空 之 巻 異本集
| 五輪書 風之巻 3 | Back Next |
7 他流批判・目付け
|
【原 文】 一 他流に目付と云事。 目付と云て、其流により、敵の太刀に 目を付るも有、又ハ手に目を付る流も有。 或ハ顔に目を付、或ハ足などに目を付るも有。 其ごとくに、とりわけて目をつけんとしてハ、 まぎるゝ心有て、兵法の病と云物になる也。 其子細ハ、鞠をける人ハ、 まりによく目をつけねども、びんずりをけ、 おひまりをしながしても、けまわりても、 ける事、物になるゝと云所あれバ、 たしかに目に見るに及ばず。 又、ほうかなどするものゝわざにも、 其道に馴てハ、戸びらを鼻にたて、 刀をいくこしもたまなどに取事、 是皆、たしかに目付ハなけれども、 不断手にふれぬれバ、 おのづからミゆる所也。(1) 兵法の道におゐても、其敵/\としなれ、 人の心の軽重を覚へ、道をおこなひ得てハ、 太刀の遠近遅速も、皆見ゆる儀也。 兵法の目付ハ、大かた 其人の心に付たる眼也。 大分の兵法に至ても、 其敵の人数の位に付たる眼也。 観見二つの見様、観の目強くして、 敵の心を見、其場の位を見、 大に目を付て、其戦の景氣を見、 そのをり節の強弱を見て、 まさしく勝事を得事、専也。 大小の兵法におゐて、 ちいさく目を付る事なし。 前にも記すごとく、こまかにちいさく目を 付るによつて、大きなる事をとりわすれ、 目まよふ心出て、たしかなる勝をぬかすもの也。 此利能々吟味して、鍛練有べき也。(2) |
【現代語訳】 一 他流で目付という事 目付〔めつけ〕といって、その流派により、敵の太刀に目を付けるものもあり、または手に目を付ける流派もある。あるいは顔に目をつけ、あるいは足などに目を付けるものもある。そのように、とりわけて(特定の部位に)目を付けようとしては、(肝心なことを)見失う心があって、兵法の病というものになるのである。 そのわけは、鞠を蹴る人は、鞠によく目を付けないけれど、「びんずり」*を蹴り、負鞠*を(背中で)仕流しても、蹴りまわっても、(自在に蹴るのは)ものごとに慣れるというところがあるので、しっかりと目で見るまでもない。 また、ほうか*(放下、曲芸)などする者の業にも、その道に慣れると、扉を鼻先に立て、刀を何本も手玉にとる。これはすべて、しっかり目を付けることはないけれども、ふだん手にしなれているので、おのづから見えるところである。 兵法の道においても、さまざまな敵と戦い慣れ、相手の心の軽重〔気が早い、遅い〕を認識し、道〔正しい方法〕を行えるようになれば、太刀の遠い近い、遅い速いも、すべて見えるものである。 兵法の目付は、だいたいその相手の心に付けた眼である。大分の兵法〔合戦〕に至っても(事は同じで)、その敵の人数〔軍隊〕の位〔態勢〕に付けた眼である。 「観」と「見」、二つの見方(があるが)、観の目を強くして敵の心を見、その場の位〔状況〕を見、大きく目を付けて、その戦いの景気〔様相〕を見、その時々で変る強弱(の変化)を見て、確かに勝つことを得る、それが専〔せん〕である。 大小の兵法〔多数少数の集団戦〕においても、小さく目を付けることはない。前にも記すごとく、細かに小さく目を付けると、それによって、大きな事を取り忘れ、(あちこち)目迷う心が出て、確実な勝ちを取り逃がすものである。この利〔理〕をよくよく吟味して、鍛練あるべきである。 |
|
【註 解】 (1)兵法の病と云物になる也 目付〔めつけ〕とは、現代日常語でも「目の付けどころ」というが、注意・注視点のことである。 この場合、もちろん太刀での戦闘であるから、相手の心の動きや身体の動き全体に注意して戦うのは言うまでもない。が、それでは教えの具体性に欠けると思われたのか、具体的にどこに注意/注視すべきかを教えた。 現代剣道でも、相手の切先と拳に注意しろと言ったり、他には相手の目の動き、肩の動きに注意しろとも言う。動作の起こり、攻撃意志の起動がどこに表出されやすいかを教えるのである。 周知の通り、縄田忠雄『剣道の理論と実際』(六盟館 昭和十三年)では、目付けを八つ提示している――「二星の目付」(二星、両目)、「谷の目付」(目の色とともに顔つき、表情)、「二つの目付」(剣の切先と拳)、「楓の目付」(切先と拳のうちでも、とくに拳を「楓の目付」という)、「蛙の目付」(肩の表情)、「遠山の目付」(遠くの山を見るがごとく、相手の搆え全体を見る)、「有無の目付」(相手の全体を見て心底を見抜く)、「観見二つの視様」(相手の動きの全体と部分が自然に目に入るように見る)。 さて、武蔵の教えに目を向ければ、――その流派により、敵の太刀に目を付けるものもあり、または手に目を付けるものもある。あるいは顔に目をつけ、あるいは足などに目を付けるものもある――という。そうしてみると、太刀(切先)、手(拳)、顔については共通するところがあるが、足については現代剣道では目付けを言わないらしい。 ともあれ、武蔵は、目付そのものに対し否定的である。つまり、そのように、目や顔や切先や手といった特定部位に、とくに目を付けようとするのは、まぎれる(大事なことを見失う)心があって、「兵法の病」というものになる、――というのである。いわば兵法の症候群である。 どうして兵法の病になるのか。そのわけは、二つの例えで示される。 一つはこうだ。――蹴鞠の上手は、鞠によく目を付けないけれど、さまざまな曲芸をして自由自在に蹴る。ものごとに慣れるというところがあるのだから、蹴り慣れていれば、しっかり鞠を見るまでもないのである、云々。この話は、現代の蹴鞠たるサッカーのことを想起すればいい。 蹴鞠は古代からの遊戯であった。蹴鞠については、難波・飛鳥井両系統や、御子左流や賀茂流の伝承がある。戦国期から武蔵の時代まで、能と並んで武将に人気があった遊戯である。 織豊期の記録として興味深いルイス・フロイス(1532〜97)の「日本覚書」のなかに、「我々の間では球戯は手でする。日本人は足を使って遊ぶ」という記事がある。これは蹴鞠のことで、当時ヨーロッパではまだ蹴球技はなかったらしい。 武蔵には蹴鞠の逸話がある。それは、当流七代の丹羽信英が越後で書いた『兵法先師伝記』にみえるところである。――筑前の箱崎宮へ参詣した武蔵が、門前で鞠を借り受けて、鞠を蹴って楼門を飛び越し、武蔵は宮内にすばやく入って、拝殿の前でその鞠を片膝折って受けとめた。その話を聞いた鞠の名人が、それはすごいと感嘆した――という話。 なお、この部分について注意が必要なのは、「びんずり」「おひまり」という語である。武蔵がここで例に挙げているのは、「鬢ずり」「負鞠」という蹴鞠の技名である。おそらく飛鳥井流、御子左流、あるいは賀茂流の曲足のことであろう。江戸中期の難波宗城(1724〜1805)の『蹴鞠名足類聚』でその名を確認できるところをみると、もちろんそれより早い江戸初期の武蔵の時代では、流行の技であったかもしれぬ。 ただし、武蔵の時代には、蹴鞠の曲足が大道芸になっていたふしもある。時代は下がるが、松浦静山『甲子夜話』には、浅草の蹴鞠芸人の話が出ているが、負鞠は、高く蹴上げた鞠を背中で受け止め、その鞠を背中でポンポン跳ねさせる芸である。他には、蹴り上げた鞠を体で受け、襷を掛けるように体に添わせて鞠を転がす「襷掛」、蹴り上げて落ちてくる鞠を肩で受けとめて腕の方へ流し、またこれを跳ね上げて額の上で弾ませ、さらに頭頂部でも衝いて鞠を跳ねさせる「八重桜」という業、その他、右足で鞠を蹴上げながら左足の足袋を脱ぐ「足袋脱」、鞠を蹴上げながら紙に字を書く「文字書」、鞠を蹴上げながら乱杭の上を渡る「乱杭渡」等々の曲芸を記録している。蹴鞠芸人にはこれに類似にいろいろな業があったものらしい。 武蔵が、もう一つ挙げているのは、「ほうか」(放下)という曲芸のことである。 もともと「放下」は、仏教語である。放下は「ほうげ」と読み、諸縁を捨てて執着しないことを言う。日本の仏教習俗に「放下僧」があるが、これは、曲手毬や輪鼓を操る芸人のこと、もとは諸国を回って法を説き、人寄せにさまざまな芸を見せた説教僧である。仏僧と芸能は大衆的次元では容易に混淆した。 武蔵がこの放下の例を挙げるについては、謡曲「放下僧」のことも念頭にあったと思われる。それよりも、五輪書の説き方としては、当時だれでも知っているこうした大衆芸能にことよせて、分かりやすい話をしているということである。 先の蹴鞠の例と同じく、ここでも武蔵は――曲芸などする者の術〔わざ〕でも、その道に慣れると、扉を鼻先に立て、刀を何本も手玉にとるなどするが、これはすべて、確かに目を付けることはない。ふだん手に慣れているから、おのづから見えるのである――と語る。 特定の身体部位に目付をしろと教えることに対しては、武蔵は批判的である。 この箇処に関して、語釈の問題がある。それは、やはり、
《びんずりをけ、おひまりをしながしても、けまわりても》
とある箇処である。この「びんずり」「おひまり」については、上述のごとく、蹴鞠の技名であることを知っておかねばならない。この部分に関連することでは、――岩波版に、「おいまりをしながしてもけ、まわりてもける事」という具合に句読点を入れて読ませているが、これは不適切な作為である。 これでは、負鞠を背中で仕流しても蹴り、ということになって、何のことだか意味不明である。これは、「おいまり」を「追い鞠」と錯覚したらしく、鞠を追って蹴りまわるものと誤解釈に及んだものらしい。ただし、戦前の石田外茂一訳を見れば、同じ句切りをしており、この岩波版の句読点は、戦前からの読み方を、何の考えもなくそのまま踏襲したものと思われる。 ところで、この部分は、「びんずり」「おひまり」など、見慣れない蹴鞠用語があって、従来から問題の部分である。だれもこれまで正しい語訳をしたことがないという、いわくつきの箇所なのである。 戦後の現代語訳を見ると、案の定、神子訳は、語の意味が解らなかったとみえて、語訳から逃げ、何の断りもなしに、右掲のごとき省略訳文を出している。このように神子が翻訳から逃走してしまったので、神子訳以後の大河内訳も鎌田訳も、詮方なく、ご覧のとおり、不細工な反復を演じている。 こうした訳者の振舞いは、細川家本を底本とすると称する以上、テクストと読者に対し不誠実な仕儀である。これに対し、昔の石田訳は(間違いながら)一応、一字一句訳そうとしている点、まだ誠実な訳文であろう。 もちろん、石田訳が「追ひ鞠をし流しても蹴り、廻っても蹴る」としたのは誤訳である。ここは我々の語訳のように、「負鞠を背中で仕流しても、蹴りまわっても」とすべきところである。 この箇所もそうだが、我々の語訳を除いては、現代語訳にはまともなものがない、というありさまである。 ――――――――――――
|
○此条諸本参照 → 異本集 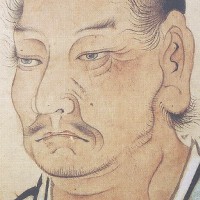 武蔵像  蹴鞠奉納 藤森神社 京都市伏見区深草鳥居崎町
*【兵法先師伝記】  謡曲「放下僧」 下野国の牧野兄弟は放下僧に 身をやつして父の仇を探す
ツレ「某がきつと案じ出したる事の候。この頃人の玩び候ふは放下にて候ふ程に。某は放下になり候ふべし。御身は放下僧に御なり候へ。彼の者禅法に好きたる由申し候ふ程に。禅法を仰せられうずるにて候。
 祇園祭山鉾「放下鉾」 京都市京区新町通四条上ル 鉾の名は「天王座」に放下僧の 像を祀るのに由来する
*【現代語訳事例】 |
|
この部分の校異の問題についていえば、筑前系のうち、越後系諸本に前後二箇所脱文がある。これに対し、早川系の吉田家本・中山文庫本はその部分を保全しており、肥後系諸本との照合でこれを確認しうる。つまり、この脱文は、越後系諸本でのみ見られるところである。 その越後系諸本の脱文箇処は、下掲例の位置であり、脱落せしめているのは、右掲吉田家本の文章の赤字で記す箇処である。  越後系写本の脱文箇処 渡辺家本 これが二天流が越後へ入ってから発生した脱落なのか、あるいは、それが、渡部信行の系統だけのものか、他の系統にもあるのか、写本発掘の途上だったので、何とも云えなかった。しかし、後に、村上赤見系の写本を発掘して、この脱文がそこにもあるとわかった。 越後の両系統に共にこの脱文がある。それゆえ、この脱文は、すでに丹羽信英の段階であったものである。しかるに、この脱文が、丹羽信英の師・立花増寿にまで遡れるか、それは、隨翁本風之巻が発掘できていないので、何とも確言はできない。したがって、筑前の立花系までこの脱文が遡及できるのか否か、それも今後の史料発掘次第である。 また別に、指摘しておくべき校異箇処が一つある。それは、筑前系写本に、
《其ごとくに、とりわけて目をつけんとしてハ、まぎるゝ心有て》
とあって、《其ごとくに》とするところ、肥後系諸本には、《其ごとく》として「に」字を欠くものがある。ただし、これも肥後系諸本すべてが、というわけではなく、富永家本のように、《その如くに》として、この「に」字を付すものがある。富永家本は、早期に派生した系統の子孫であるから、他例にもあるように早期の形態を伝えている場合もある。ここもそのケースであり、したがって、肥後系早期にこの「に」字を付すものがあったとみえる。 《其ごとくに》が筑前系諸本に共通の語句であるところから、これを筑前系初期にあったかたちとみなしうるが、またこのように筑前系/肥後系を横断して存在するものであるから、これは寺尾孫之丞段階にまで遡りうる古型である。 こうしたことも、肥後系諸本ばかりを見ていてはわからぬことである。富永家本のような派生系統の校異は、従来、例外として処遇されてきた。しかしながら、筑前系諸本を視野に入れると、それは本末転倒であったことが知れるのである。 したがって、五輪書諸本校異において諸本の字句を評価をするには、まず第一に広く諸本を参照照合することが必要である。その大前提が、これまでの五輪書研究には欠けていたのである。それゆえに、嗤うべき本末転倒が生じてきたというわけである。 Go Back |
*【吉田家本】
《目付と云て、其流により、敵の太刀に目を付も有、又ハ手に目を付る流も有。或ハ顔にめを付、或ハ足などに目を付るも有。其ごとくに、とりわけて目をつけんとしてハ、まぎるゝ心有て、兵法の病と云物になる也》 《兵法の目付ハ、大かた其人の心に付たる眼也。大分の兵法に至ても、其敵の人数の位に付たる眼也。観見二ツの見様、観の目強くして》
*【立花=越後系伝系図】 ○新免武蔵守玄信―寺尾信正┐ ┌―――――――――――┘ └柴任美矩―吉田実連―┐ ┌――――――――――┘ |立花系 └立花峯均―立花増寿―┐ ┌――――――――――┘ |越後系 └丹羽信英┬赤見有久 | └渡部信行
*【吉田家本】
《其ごとくに、とりわけて目を》 *【中山文庫本】 《其ごとくに、とりわけて目を》 *【渡辺家本】 《其ごとくに、とりわけて目を》 *【近藤家丙本】 《其ごとくに、とりわけて目を》 *【赤見家乙本】 《其ごとくに、とりわけて目を》 *【楠家本】 《其ごとく【★】、とりわけて目を》 *【細川家本】 《其ごとく【★】、とりわけて目を》 *【富永家本】 《その如くに、取分て目を》 *【多田家本】 《其ごとく【★】、取分て目を》 |
|
この部分の校異の問題について、指摘しておくべき箇処がある。その一つは、筑前系諸本に、
《道をおこなひ得てハ、太刀の遠近遅速も、皆ミゆる儀也》
とあって、《遠近遅速も》とするところ、肥後系諸本は、《遠近遅速迄も》とあって「迄」字を入れる。これは、肥後系諸本に共通しているから、この校異は、筑前系/肥後系を区分する指標的相異である。これについては、筑前系諸本はどれも共通してこの「迄」字を記さない。とすれば、筑前系初期にはこの字は存在しなかったのである。寺尾孫之丞が柴任美矩に伝授した五輪書には、この字はなかったと見るべきところである。 他方、肥後系諸本には共通して「迄」字を入れるから、これは肥後系早期にあったものとみなしうる。しかし、これが寺尾孫之丞段階にまで遡ることはありえない。こうした前期になかった文字が寺尾後期に発生することはなきしもあらずだが、文意からして、「迄」字は余計な文字である。《太刀の遠近遅速》という程度のことなら、「迄」も、とするまでもないからである。これは、遅速の「速」字に引かされて発生した衍字であろう。我々の所見では、これは後になって発生した肥後ローカルの誤記である。 また他の校異では、これとは別種のタイプがある。それは、筑前系/肥後系を截然区分する相異ではなく、肥後系諸本の一部に筑前系諸本と共通する語句があって、いわば筑前系/肥後系を横断して共通するもののあるケースである。筑前系吉田家本に、
《大小の兵法におゐて、ちいさく目を付事なし》
とあって、《大小の兵法におゐて》とするところ、越後諸本には、《におゐても》として「も」字を付す。これは筑前系/肥後系を横断して検れば、共通するのは、この「も」を欠くケースなので、越後系の語句は衍字誤記である。それは別にして、《大小の兵法》とするところは、筑前系諸本に共通する。それに対し、肥後系諸本には、《大小兵法》とあって「の」字を欠くものがある。 これは単純な脱字であろう。もし「の」字がなければ、《大小、兵法におゐて》ではなく、《兵法、大小におゐて》とあるべきところである。したがって《大小、兵法》では、文意の点から見ても「の」字が脱けているのである。 同じ肥後系でも、円明流系統では、《大小の兵法》と記すから、肥後系でも早期にはそう記す時期があったとみえる。その後に、この「の」字を落とした写本が発生し、現存諸写本の元祖となったのである。 筑前系の方は、《大小の兵法》で共通している。したがって、これは筑前系初期に存在した字句であり、さらには寺尾孫之丞前期へ遡りうる初期形態である。したがって、これを古型とみなし、我々のテクストでは、《大小の兵法》としている。 同じタイプの校異で、もう一つ挙げておくべき箇処がある。それは、すなわち、筑前系諸本に、
《大きなる事をとりわすれ、目まよふ心出て》
とあって、《目(め)まよふ》とするところ、肥後系諸本には、《まよふ》とあって「め」(目)を欠くものがある。また、肥後系では、《まよふ心出きて》として、「き」字を付するケースもあるから、この箇処は相異が二重である。ただし、同じ肥後系でも、富永家本には《目まよふ心出て》とあって、筑前系諸本と同じ字句が、肥後系にもあったと知れる。したがって、この「目」字の有無は、筑前系と肥後系を分つ指標ではない。むしろ、肥後系早期にあったものと見た方がよい。 この《目まよふ心出て》は、筑前系諸本に共通するところから、筑前系初期にすでにあったものである。それと同じ字句が肥後系にもあるとすれば、筑前系/肥後系を横断するゆえに、これが古型なのである。それゆえ、我々のテクストでは、《目まよふ心出て》と採用している。 Go Back |
*【吉田家本】
*【吉田家本】
*【吉田家本】
《めまよふ心出て》 |
8 他流批判・足づかい
|
【原 文】 一 他流に足つかひ有事。 足の踏様に、浮足、飛足、はぬる足、 踏つむる足、からす足などいひて、 いろ/\さつそくをふむ事有。 是ミな、わが兵法より見てハ、 不足に思ふ所也。(1) 浮足を嫌ふ事、其故ハ、 戦になりてハ、かならず足のうきたがるものなれバ、 いかにもたしかに踏道也。 又、飛足をこのまざる事、 飛足ハ、とぶにおこり有て、飛ていつく心有、 いくとびも飛といふ利のなきによつて、飛足悪し。 又、はぬる足、はぬるといふ心にて、 はかのゆかぬもの也。 踏つむる足ハ、待足とて、殊に嫌ふ事也。 其外からす足、いろ/\のさつそくなど有。 或ハ、沼ふけ、或ハ、山川、石原、 細道にても、敵ときり合ものなれバ、 所により、飛はぬる事もならず、 さつそくのふまれざる所有もの也。 我兵法におゐて、足に替る事なし。 常に道をあゆむがごとし。 敵のひやうしにしたがひ、 いそぐ時ハ、静なるときの身のくらゐを得て、 たらずあまらず、足のしどろになきやうに有べき也。(2) 大分の兵法にして、足をはこぶ事、肝要也。 其故ハ、敵の心をしらず、むざとはやくかゝれバ、 ひやうしちがひ、かちがたきもの也。 又、足ふみ静にてハ、敵うろめき有て くづるゝと云所を見つけずして、 勝事をぬかして、はやく勝負付ざる*もの也。 うろめき崩るゝ場を見わけてハ、 少も敵をくつろがせざるやうに勝事、肝要也。 能々鍛錬有べし。(3) |
【現代語訳】 一 他流に足つかいのある事 足の踏み方に、浮き足、飛び足、跳ねる足、踏みつめる足、からす足などといって、いろいろ左足*〔さそく・特殊な足つかい〕を踏むことがある。これはすべて、我が兵法から見れば、不足に〔ダメだと〕思うところである。 浮き足を嫌うこと、そのわけは、戦いになっては、必ず足の浮きたがるものだから、できるだけ確かに足を踏む、それが道〔正しい方法〕である。また、飛び足を好まないのは、飛び足は、飛ぶときに起り*があり、飛んで居付く心があり、何回も飛ぶという利〔理〕もないのだから、飛足はよくない。また、跳ねる足は、跳ねるという(着実ではない)心があって捗の行かぬものだ。踏みつめる足は、「待つ足」といって、とくに嫌うことである。 その他、からす足、色々の左足〔さそく〕などがある。あるいは、沼、ふけ〔湿原〕、あるいは、山、川、石原、細道においても、敵と切り合うものであるから、場所によっては飛びはねることもできず、左足〔さそく〕を踏むことができない所があるものである。 我が兵法では、足(の踏み方)に変ったことはしない。常に道を歩むがごとし。敵の拍子に応じて、急ぐ時でも、静かな時の身体の位〔態勢〕になって、足らず余らず、足がしどろに(乱れ)ない、そのようにあるべきである。 大分の兵法〔集団戦〕にしても、足を運ぶ*ことは肝要である。そのゆえは、敵の心〔企図〕を知らず、むやみに早く(攻撃に)かかると、拍子がはずれて、勝てないものであるからだ。 また(逆に)、足踏みがのんびりしすぎていては、敵にうろめき〔動揺〕があって崩れるというところを見つけず、そして勝機を取り逃がして、早く勝負がつかないものだ。(敵が)うろめき崩れるところを見わけたならば、少しも敵に余裕を与えないようにして勝つこと、それが肝要である。よくよく鍛練あるべし。 |
|
【註 解】 (1)いろ/\さつそくをふむ事有 足遣い、足の踏み方の話である。見た通り、いろいろ見慣れない特殊な用語が出てくるから、ここはまず、語釈が必要であろう。 類似の記述ということでは、前に水之巻「足づかひの事」において、――爪先を少し浮かせて、踵〔かかと〕を強く踏むべし。足の使い方は、状況によって、大きい小さい、遅い速い(の違い)はあっても、ふだん歩くのと同じようにする。足に、飛足〔とびあし〕、浮足〔うきあし〕、踏み据える足というのがあるが、この三つは、(我が流派では)嫌う足である。――とあったところである。 この「爪先を少し浮かして踵を強く踏む」というのは、足の親指を中心に爪先を浮かせて踵を浮かさない歩き方である。下肢に力の入った歩き方で、足半〔あしなか〕など履いた当時の日常の足遣いとは違うだろう、と前に述べておいた。 ここでは、まず「浮足」〔うきあし〕である。これは、足の爪先が地面につき踵が浮いた足で、下肢に力を入れないで、ふわっと踏む足というところであろう。この点、「爪先を少し浮かして踵を強く踏む」というのとは反対である。 次に、「飛足」〔とびあし〕。これは現代剣道でも遠間から打突する「飛び込み足」ということをいうが、それだけではなく、逆に、後方へ飛び退くのも飛足である。 また、「はぬる足」。これは跳ねる足であり、ジャンプすることである。この場合は、垂直に飛び上がるのである。 あるいは、「踏つむる足」。この「つむる」は「詰める」「積もる」である。前に出た「踏すゆる足」である。腰を落として、じわっという感じで踏む足のことである。踏つむるといって、ドスドス踏みつける足ではない。 そして問題は、「さつそく」である。これは「さそく」の促音転訛。通例は「早足」とされるものである。すなわち、
《足踏も、さそくをつかふ心根を持ちて》(拾玉得花)
とある用例である。「さそく」は、急ぎ足、はや足のことである。現代語の「早速」はこの「さそく」「さつそく」から来ているものらしいという話があるが、本来「早速」は「さうそく」と読んだもので、これとは違う。ところが、この「さそく」は「左足」のことでもある。現代剣道で「一眼二足三胆四力」というが、大正期には、「一眼二早足三胆四力」、あるいは「一眼二左足三胆四力」と言った。早足・左足ともに「さそく」と読む。左足のすばやい引き付けが肝心だという教えだとされているが、その解釈は別にしても、剣術において左右両足のうち、後に引いて軸足にする左足が重要なのである。 このように、近代へ伝承された「さそく」という語は、早足・左足いづれか不確定のままである。言い換えれば、「さそく」は、その語用においてその両義性を失っていないという用語なのである。こうした両義性については、「さそくを踏む」が成語であるだけに、必ずしも字義通りではない点を念頭におくべきである。 それはともあれ、武蔵の使った成語「さつそくを踏む」では、これは早足なのか、それとも左足なのか――それを見極めなければならない。 三橋鑑一郎は『劍道秘要』(明治42年)で、「さそく」を「左足」と校訂している。少なくとも明治の剣道家にとっては「さそくを踏む」は「左足を踏む」である。これは考慮しておいてよいであろう。 つまり、世間一般では「早足」の意味であった「さそく」は、武芸において伝統的に左足とする特殊な語義であったということである。「さそくを踏む」という成語は、一般には「早足を踏む」であるが、剣術の世界では「左足を踏む」として使用されてきたのではないか、と推量しうるのである。 しかも、武蔵の教えは、両足均等遣いが原則であるから、こうした「左足」を踏んで起動する足遣いを批判していると文脈上も読めるのである。水之巻の「足づかひの事」に、
《かへす/\、片足踏事有べからず》
とあったところである。この「片足を踏む」と「さそくを踏む」は同じ意味の別表現である。これによって、我々は兵法語彙として「さそく」を扱い、これを「左足」としたのである。ただし、それに付け加えて云えば、「左足」の「左」という語には、「変則的な」という語義のあることは、一応念頭におくべきである。というのも、武蔵は、この「さそく」を批判する側に立っているからだ。そして、「からす足」。これはまたまた難解用語である。これまで、明確な語釈を見たことがないのである。 「からす足」については、烏が歩くように、ひたひた歩くのだという説があり、また、烏は斜めに飛ぶというところから、斜いに飛ぶのを「からす足」と云ったという説、『碧巖録』に《南北東西、烏飛び、兔走ること急なり》とあって「烏飛兔走」の言葉あるごとく、あわただしく速く踏む足という説等々あるが、本当はよくわからない。 能楽の中でも神さびて最も祭祀的な「翁」で、シテの翁が退場して後の揉みの段、三番叟(さんばそう)が「えい、えい」と声をかけて跳びはねる舞の型を「烏飛」という。これも原型は神楽舞であろう。現存神楽でも、大股で飛び跳ねて回るのを「烏飛」というのである。 ともあれ、この「からす足」、かの天狗たちの足元を見ればわかるが、烏の足とはこれかと思わせるのである。これが足の踏み方のことだとすれば、烏が飛ぶように大股で飛び跳ねるものというよりも、柳生十兵衛三厳『月之抄』(寛永十九年)が右のごとく書いているの記事を根拠として、「左足」の一種で、小足で素早く動く足遣いとしておく。一部古流伝書にある如く、それを「斜めに飛ぶ」とまではしない。 柳生十兵衛によれば、すなわち――足の運びは、いつも後の足(左足)を素早く引寄せる事が第一である。当流(柳生新陰流)においては「からす左足」というのである。これは、亡父(宗矩)の目録には何とも書いていない。また云う、左足は浮き立って軽いのがよい。足の運びは、できるだけ静かに、「小足」なのがよい。おおかた、約一尺(30cm)ほどづつ、拾い歩く感じである、云々。 これによって見るかぎりは、柳生新陰流では、さそく(左足)を用いていたばかりか、「からす足」もあったようである。とくに、左足は浮き立って軽いのがよい、足の運びは小足なのがよい、というあたりは注意すべき記事である。 そうだとすれば、ここで武蔵が批判している足遣いは、まさにこうした柳生流のそれをはじめとする諸流派の足踏みであったということになる。我々はそのことを念頭において、この箇処を読む必要がある。武蔵が言うには、
《是みな、わが兵法より見ては、不足に思ふ所也》
武蔵の兵法からみて、こういう色々な足遣いは、すべて不足だと思う。「不足」というのは、足つかいの話だから、とくに召喚された字句だが、欠陥があってダメだ、ということである。
Go Back
|
○此条諸本参照 → 異本集
*【足づかひの事】  軍法兵法記劔術之巻 部分 足元に浮足・沈足の文字あり  吉田家本 「さつそく」  黒川能 三番叟
*【月之抄】 |
|
この部分の校異は、さまざまある。問題にしておきたいのは、次の箇処である。すなわち、筑前系諸本に、
《はぬる足、はぬると云こゝろにて、はかのゆかぬもの也。蹈つむる足ハ、待足とて、殊に嫌事也》
とあるところ、肥後系とは種々相異がある。第一に、筑前系が、はかの《ゆかぬ》とするところ、肥後系諸本には、はかの《行かぬる》とあって「行きかねる」とする。《行かぬ》に「る」字が付いたのだが、表現が違ってしまう。これは、《ゆかぬ》を《行かぬ》と漢字表記するようになった後のことで、肥後で伝写過程で発生した誤記である。また第二に、筑前系が《待足》とするところ、これは「待つ足」ということだが、肥後系では、《待の足》として「の」字を入れる。「待」〔たい〕という名詞とする解釈である。 この点で興味深いのは、肥後系富永家本である。そこでは、《行ぬ》と《待足》の二箇所が、筑前系諸本と共通する。肥後系にも、早期には、この字句のヴァージョンがあったと知れる。つまりは、富永家本の先祖が派生分岐した後、書写過程で生じたのが、はかの《行かぬる》や、《待の足》という語句なのである。 また、筑前系が《踏つむる足ハ》と助詞「ハ」を入れるところ、肥後系は、これを入れない。つまり、脱字である。《行ぬ》と《待足》の二箇所において正しかった富永家本も、こちらは、他の諸本と同じくこれを落としているから、肥後系早期にこの「ハ」字が脱落したものであろう。 また、次のところでは、筑前系諸本間での相異もある。早川系の吉田家本・中山文庫本・伊丹家本では、
《我兵法におゐて、足に替る事なし。常に道をあゆむがごとし。》
とするところ、ひとつには、この「道を」二字を、越後系の諸本では落としている。これは、筑前系/肥後系を横断してみれば、これが脱字だと知れる。本来は「道を」二字を入れるのが正しい。それは筑前系諸本間の相異であるが、もう一つ、ここで筑前系では《常に》とするのに対し、肥後系では、これを《常の》とする。仮名一字の相異で、文意はやや違ってくるが、意味の相違は大したものではないから、《常に》と《常の》が相互に遷移しやすい。したがって、誤写も生じやすい。 また、次のところでは、筑前系諸本には、
《いそぐ時ハ、静なるときの身のくらゐを得て》
とあって、《いそぐ時ハ》として「ハ」字を付すところ、肥後系では、この「ハ」字を欠落せしめている。以上の校異は、文章内容の点では、とくに甲乙つけるほどの問題はない。しかしながら、正誤是非判定をつけるとすれば、以下の点を見るべきであろう。 つまり、同じ肥後系でも富永家本が、筑前系と同じ字句を有するケースがある。つまり、筑前系/肥後系を横断して存在するケースであるが、ここは既出例と同様のパターンであり、古型とみなすことができる。しかも、その字句については、肥後系早期にもそれが存在したらしいとみることができる。その痕跡が富永家本の字句である。 そして、それ以外の語句について云えば、それらは筑前系/肥後系を区分する指標的相異である。このケースは、越後系を含む筑前系諸本に共通するところであるから、その初期性を勘案しなければならない。既述他例のように、寺尾孫之丞段階まで遡りうる語句である。肥後系諸本の上記の諸語句は、その点、後に発生したもの、後発性の変異である。 以上の諸校異について云えば、肥後系諸本の中には古型をとどめる例もあるが、他はおおむね門外流出後発生した語句変異である。これも、肥後系諸本のみを見ていては、そのことにすら気がつかない問題箇処である。問題のあることにさえ気がつかないようでは、そもそもテクスト校訂もありえない。かようなわけで、五輪書には、これまで、まともな校訂研究さえ存在しなかったのである。 Go Back |
*【吉田家本】 |
|
校異の問題としては、この部分にはいくつかあろう。まず、越後系諸本には、相当の脱落がある。直前には、上記の《常に道をあゆむがごとし》の「道を」という文字の脱落があったのだが、さらにここでは、前文からの《足のしどろになきやうに有べき也。大分の兵法にして》という文字列が脱落している。これは、越後へ入って以後の変異なのかどうか。 越後系諸本の風之巻について言えば、丹羽信英門人のうち、渡部信行系統の伝書しか発掘していない段階では、何とも云えなかったが、赤見家本の発掘により、これらの脱字について、丹羽信英の段階まで遡及できることが判明した。しかし、これが筑前の立花系にまで遡る誤記であるか否か、それは未確定である。なお他の写本の発掘が必要である。 しかし、全体に言えることだが、越後系諸本は、他の諸巻は比較的正確なのだが、この風之巻に限って、その脱字・脱文が目立つ。それがいかなるわけか、それを解明するのも、五輪書研究の今後の課題である。後学の諸君には、この点につき注意を喚起しておく。 さて、ここで指摘しておくべきは、次の箇処である。すなわち、筑前系の吉田家本・中山文庫本に、
《大分の兵法にして、足をはこぶ事、肝要也》
とあって、《にして》とするところ、肥後系諸本には、これを《にしても》として、「も」字を入れるものがある。この「も」字の有無が、その相異である。ただし、肥後系諸本のなかにも、富永家本のように、「も」字を入れない《にして》と記すものがある。このケースは、筑前系/肥後系を横断して共通するというところでは、「も」字を入れない《にして》のが古型である。したがって、これも前出例と同じパターンで、肥後系早期には、「も」字を入れず《にして》と記していた可能性がある。 このことからすると、《にして》に「も」字を付すようになったのは、富永家本系統の祖先が派生する以後のことであり、もとより後に発生した衍字誤記である。したがって、肥後系現存写本の多くは、この写本の子孫なのである。 この《にして》という語句には「も」字が付きやすい。しかも、五輪書にも《にして》《にしても》が混在している。そういう具合であるから、ここは筆写者が、つい「も」字を入れてしまったらしい。 次は、すこし難題である。すなわち、筑前系諸本に、
《敵うろめき有てくずるゝと云ところを見つけずして、勝事をぬかして、はやく勝負つけざるもの也》
とあって、《つけざる》とするところ、肥後系諸本には、これを《つけ得ざる》として、「得」字を入れる。まずは、この字の有無が問題である。肥後系諸本を中心に見る者たちだと、その問題の解決は簡単である。これは「得」字の脱字である。《つけ得ざる》−《得》=《つけざる》。それで一件落着である。しかし、そんなことで問題が片付くのなら、五輪書研究は要らないのである。ここはもう少し迂回を必要とする。 そこで、《つけざる》《つけ得ざる》と分かれる筑前系/肥後系を横断して共通の文字「つけ」があることに注目すべきである。今日の現代語でも、「勝負つけざる」となると、勝負をつけない、決着をつけない、という意味合いである。また、「勝負が」とするなら、ここは《勝負つかざる》ということである。「つけ」ではなく「つか」とするところである。 おそらく、オリジナルは「勝負がつかない」という文意ではなかったか、という推測が可能であろう。ただし、それも、仮名ではなく、《付ざる》と書いたものである。それを仮名に開いたのが《つけざる》という字句になった。とすれば、筑前系の《つけざる》という語句は、《付ざる》を仮名に変換した結果の産物ということである。 他方、肥後系の《つけ得ざる》は、おそらくこの《つけざる》に異和を覚えて、後になってこれに「得」字を挿入したものであろう。そうすると、ここは「はやく勝負をつけることができない」となって、文意は整序される。その点、肥後系諸本は、この修正後のヴァージョンである。 これに対し、筑前系の《つけざる》は、それ以前のもので、初期形態をそのまま伝えたもののようである。しかしこれが誤写だとすれば、それはいつの段階のことか。 そこで再度、《つけざる》《つけ得ざる》と分布する筑前系/肥後系を横断して、共通の文字「つけ」があることに注目すべきである。つまり、寺尾孫之丞の段階で、「つけ」という仮名字句がすでにあったのである。 言い換えれば、そこで「つけ」が発生した。武蔵草稿に《付ざる》とあったものを仮名に開いたのは、寺尾孫之丞だったというわけである。 おそらく五輪書に仮名書きが多いのは、武蔵が和文入門書としての本書のためにそうしたのだが、寺尾孫之丞の段階で増えた仮名書きも相当あると思われる。もちろん、寺尾がこう書いたのは、《勝負つけざる》でもとくに異和を感じなかったからである。《勝負つけざる》でも文意は通るからである。 これが「つけ」になったのは、編集段階での偶発だろうが、それが後々までも伝わったのである。しかるに、肥後系では後に、《つけざる》に異を感じて、《つけ得ざる》と修正してしまったが、他方、筑前系の方は、寺尾の書字そのままの《つけざる》という字句を伝えたのである。 したがって、我々のテクストでは、寺尾孫之丞段階に遡りうるこの古型の《勝負つけざる》を認知した上で、それに止まらず、想定しうるオリジナルの形、つまり、《勝負付ざる》を復元して提示しておいた。申すまでもなく、この場合、《付ざる》は、「つけざる」ではなく、「つかざる」と読むのである。 さて、別の校異については、続く文に、筑前系諸本には、
《うろめき崩るゝ場を見わけてハ、すこしも敵をくつろがせざるやうに勝事、肝要也》
とあって、《見わけてハ》とするところ、肥後系諸本には、これを《見わけて》として、「ハ」字をつけない。また、この字の有無が問題である。文意の相異は些細なものだが、文脈をたどれば、ここは「ハ」字があった方が文の輪郭が明確になる。つまり、足踏みがのんびりしすぎていては、敵にうろめき〔動揺〕があって崩れるというところを見つけず、そして勝機を取り逃がして、早く勝負をつけない、ということになるものだ。敵がうろめき崩れるところを見わけたら、少しも敵に余裕を与えないようにして勝つこと。――このように、「敵がうろめき崩れる」のを見分けたら、すぐさま、という文章内容の方が妥当であろう。 肥後系のように、《うろめきくづるゝ場を見わけて、少も敵をくつろがせざるやうに勝事》というように、《見わけて》で切るのは、文の脈絡が平板である。やはり、ここは、《見わけてハ》とあった方がよい。 というわけで、内容の点では、「ハ」字がある方がよろしい。しかし、ここはそういう文意で是非が決まるわけではなく、間テクスト的分析の結果による。すなわち、筑前系において諸本共通して、これを記すことが判定のポイントである。 言い換えれば、ここで「ハ」字を付すのが筑前系初期の形であり、同時に寺尾孫之丞前期にそうあった可能性が高い。したがって、我々のテクストにおいては、この《見わけてハ》という「ハ」字がある方を採るというわけである。 Go Back |
 渡辺家本 脱字箇処
*【吉田家本】
*【吉田家本】  吉田家本 校異箇処 |




