 |
�����̌ܗ֏���ǂ� �ܗ֏�������Ńe�N�X�g�S�� ������ƒ����E�]�� |
|
���@�@ �@�ځ@���@�@ �@�n �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@�@�@ �@�ٖ{�W�@
| �܁@�ց@���@�@���@��@�@�@ | �@Next�@ |
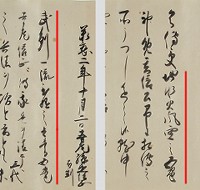 �g�c�Ɩ{�@���`�ؕ� �u�n���Ε���V�܊��v�i�����M���j �u���B�ꗬ���ɔV�����܊��v�i�ĔC����j  �א�Ɩ{  ��Ɩ{  ��ˊω��@��ޓ� �F�{�s���������R�@�_�ޑT�� |
�@�{�{�����Ƃ����A�ܗ֏��A�ܗ֏��Ƃ����A�{�{�����B�����̑��̕��@�҂̒�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��҂ł������A�{�{�����̌ܗ֏��̖��͒m���Ă���B����͂���Ӗ��ňُ�Ȏ��Ԃł����āA���̂悤�ɐ��Ԃ̑��ꂪ���܂��Ă���̂��A�s�v�c�ȗ��j�̐���s���ł���B �@�ܗ֏��͋{�{���������������@���{�ł���B�ܗ֏��́u�����̂���v�ƁA�u�́v�����ēǂށB�����������́A�u�ܗ֏��v�Ƃ����薼�̖{���������̂ł͂Ȃ��B�u�ܗ֏��v�Ƃ����̂́A��l������ɂ����ĂԂ悤�ɂȂ����܂ł̂��ƂŁA�����{�l�͂��̒���Ɂu�ܗ֏��v�Ƃ����^�C�g����t�����킯�ł͂Ȃ��B �@���ꂪ�u�ܗ֏��v�Ɖ]���Ēʗp�����ʓI�ʏ̂ɂȂ����̂́A��͂薾���Ȍ�ł���B�]�ˎ���܂ł́A�����ނ˂��̒���́u�܊��̏��v�Ƃ��u�����܊��v�Ƃ��A���邢�́u�n���Ε���̌܊��v�Ƃ��u���@�������v�Ƃ����܂��܂Ȗ��O�ŌĂ�Ă����B���̂Ȃ��ŁA���ł�����u�ܗ֏��v�ƌĂԗ�����������A���ꂪ��ʉ����Ă����̂ł͂Ȃ��B�ނ���u�ܗ֏��v�ƌĂԂ̂͂�������ꂽ�͈͂̂��ƂŁA�ˑR�Ƃ��Ă��̒���͕ʂ̖��ŌĂꑱ�����̂ł���B �@���m�̂��Ƃ��������́w��������x�ɂ��Ă��A���҂����̃^�C�g����t�����킯�ł͂Ȃ��B������u�����̕���v�u���錹���̕���v�u���̕���v�u���̂䂩��̕���v�Ȃǂ��܂��܂Ȗ��ŌĂ�Ă����B������]�ˎ���ɂ͊����Ɂu����v�u�����v�Ƃ��ĂԂ悤�ɂȂ����B���������āA�����̃^�C�g���́A�㐢�̑��l������������̂Ƃ����`���̓����ɁA�����́u�ܗ֏��v���������Ƃ����킯�ł���B �@�}�O�n�����`�L�w�O�����ϕM�L�x���L���悤�ɁA���Ƃ��ƕ����͂��̌܊��̕��@���{�����������Ď��̂ł͂Ȃ��B���������āA�����S�̂��w���������������킯�ł͂Ȃ����A�܂������ʖ{�̂悤�Ɍ܊��̗��h�ȑ���̊������₳�ꂽ�̂ł��Ȃ������B �@�������A�����^�C�g�����Ȃ��������Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��A�����͌܊��̂��ꂼ��Ɂu�n�E���E�E���E��v�̖���t���Ă����B�S�̂̃^�C�g���͂Ȃ����A�e���̖��͂��łɂ������B���������āA��l�͂܂�������A�u�܊��̕����v�Ƃ��u�����܊��v�ƌĂ̂ł���B �@�ǂ����Ă��ꂪ�u�ܗ֏��v�ƌĂ��悤�ɂȂ������Ƃ����ƁA�u�n���Ε���v���F�����\������܌��f�ł����āA�����͂������珑���̖����̂����A��������������A��ɏq�ׂ�悤�ɁA�܂��ɂ��ꂪ�ܗ֓��̍\���v�f�A�e�p�[�c�Ɋ���U��ꂽ��������ł���B����������A�����͏����Ƃ��Ă̌ܗ֓���������̂ł���B�ܗ֓��́A�\���܂ł��Ȃ���̐Γ��ł���B����䂦��X�́A�����̂��̈�u������ŁA���̒�����u�ܗւ̏��v���ĂԂ̂ł���B �@�ܗ֏��̎��������ɂ��A�����Z�\�̂Ƃ��A���i��\�N�i1643�j�\���A���̌ܗ֏��������n�߂��炵���B���M�ɂ������āA�\����{�A�F�{���x�̊�ˎR�ɓo���ċF�肵���B�����ɂ͊�ˊω��Ƃ��Ēm����ω���ꂪ����A��ޓ��Ƃ����A������B�������������Ȃ̂ŁA�����ŕ������ܗ֏����������Ƃ����`�����㐢���������B �@����͂Ƃ������Ƃ��āA�����́A���i��\�N�\���ɖ{���������͂��߂��B���̍��́A�F�{�̉��~�ɂ͋��炸�A�F�{����قNj߂����ɕʑ��ł������āA�����ɏZ��ł����悤�ł���B�������A�����i��\��N�^���ی��N�i1644�j�̉Ă���ɔ��a���āA���M���v���悤�ɂ����Ȃ��Ȃ����B��t���h�����ꎡ�Â��Ă������A�a���͂܂��܂��������A�ݏ��ł͎��ÂɌ��E�����邩��A�a�l�̍א������ƘV�̒��������͂��߁A�F���F�{�֖߂�Ƃ����̂ɓ��ӂ����A�U�X���͂��肱���点���������A�����͓��N�\�ꌎ�ɂȂ��ČF�{�̉��~�֘A��߂���Ă���B �@�����͎��ʂ܂ŏ��e�Ɏ�����Ă�����������Ȃ����A���̂悤�Ȏ����A���ۂɂ́A���i��\�N�\�����炻�̗��N�Ă������͏H����̔��a�܂ł́A��N���炸���{���̎��M���Ԃł��낤�B�Ƃ��Ɋ��i��\��N�̏\�ꌎ�ȍ~�́A���M�͂قƂ�Ǖs�\�ɂȂ��Ă����Ǝv����B �@���ꂩ�甼�N��̐��ۓ�N�i1645�j�܌��\����ɕ����͎��ʂ̂����A���̎��̎����O�ɁA�{������̎������V��ɑ������Ƃ����B�{���e���ɋL���ꂽ����Ɗ������炻�̂悤�ȓ`�����������̂����A�����A���̎������V��ȊO�ɂ͎��^���ꂽ�҂����Ȃ��̂́A�{�����������������ł͂Ȃ��A�B�ꕔ�����̑��e����������ł���B �@���Ƃ��A�ܗ֏��͖������̏��ł���B�������ܗ֏����A�S���𒍂��Łu�����グ�v�Ď��A�Ƃ����ߑ�̓`���́A�ނ���Ȃ��T���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B |





|
�@���āA�{�{�����̌ܗ֏��́A���܂�ɂ��L���Ȕނ̒���ł���B��O�����g���ɂɂ��������Ă���ÓT�ł���B���ɏ��яG�Y���w�E�����悤�ɁA���̏��͔����_��`�I�Ȃ����̎��p��`�E���H��`�̎v�z�ł����āA����Ɍ����ߐ��I�ȍ����I���_�̒a�������m������̂ł������B���Ȃ��Ƃ����{�v�z�j����邩����A�������Ēʂ�ʎv�z�ƂƂ��āA�{�{�����Ƃ������݂�����B �@�Ƃ͂����A����̉����邩���\���m���Ă���킯�ł͂Ȃ����A���̂����A���̓��e�����A����܂ł������ǂ̘Q�ɐ���ė��āA���łɕ�������C�̕t���������̂ɂȂ��Ă��܂��Ă���B �@�������A�����牽���ܗ֏��Ȃ̂��A�Ƃ����������́A��X�̎������������ł��A���ꂱ������l�\�N�O�ɂ͕�������ʂɂ������̂ł���B���������ܗ֏��ւ̔����́A���܂�ɂ��ʑ��I�Ȍܗ֏������ƌܗ֏����̂��̂Ƃ������������̂ł������B���邢�̓I�[�\���e�B��ʂւ̔����ł��������̂����A����ɂ̓G�X�^�u���b�V�������g�����������̂��̎咘�����D����A�Ƃ������X�������݂����̂ł���B �@���ꂪ����łȂ��ĉ��ł��낤���B�����Ɍ��炸�A������ʂ̒S���肪�ЂƂ����E���I�ł���Ƃ����̂́A�����ł���Ƃ��Ă��A �@�@�@�\�\ Right is right.�i�u�E�v �́u�������v�j �Ƃ����`���I�ȃi�V���i���X�g�E�|�W�V�����͈͓̔��ɂ����ۂ�Ɣ[�܂�̂��A�����Ƃ����킯�ł��Ȃ������B���́u�E�v�̕��������ɑ��ẮA���Ȃ��Ƃ����{�̌ÓT�I�`���̒��ł́A�u�E�v���u���v�̕����ゾ�Ƃ�����k���\�����A�������̐l�́A�E�ł����ł��Ȃ��A���E�̌����肽�邱�Ƃ�錾���Ă����Əq�ׂ�Ώ\���ł��낤�B���炩�ɕ����́A�ނ̓�����ɂ����Ĉ�E�ҁE���O�҂Ƃ��Đ������̂ł���B �@�����̌ܗ֏��́A�폟��搂����H�I�Ȏ��p�{�̂ӂ�����Ă��邪�A�����ꂽ�����̏��炷��A���͓r�����Ȃ�����p�{���Ƃ������Ƃ́A��ǂ���Ζ��炩�ł���B�����Ƃ́A����x��œo�ꂵ���\�͂̎v�z�ł���A����Β������E�Ɉ��Z���鉽�l����e�s�\�ȃn�[�h�Ȋj�S��L���Ă����B �@�ނ̌ܗ֏��̎��Ƃ͉����H�\�\������ꌾ�ł����A�E�l�Ƃ����u�������v�̖��ł���B�ނ͂�����ϔO�I�Ȍ��t�ł͂Ȃ��A�����ɏ����𐧂��邩�A�����ɓG��ł��E���邩�A�Ƃ����Z�p�_�Ƃ��Č�邱�Ƃɂ���āA�ŏI�I�ɕ��̐��_��`�A���̃t�F�e�B�V�Y���ւ̓����A���炩���ߕ������Ă����̂ł���B �@����䂦�A���̂�����ɂ����āA�ܗ֏��قnj�ǂ���Ă����e�N�X�g�͑��݂��Ȃ��ƌ����Ă悢�B��X�̌������ɂ����āA�ܗ֏����܂Ƃ��ɓǂ߂��҂͖w�NJF���ɓ��������A�����܂��܂���ǂ̈����͐����Ă���̂ł���B�����Ă܂��A���Ȃ��w�t�B�x�ƌܗ֏���ɘ_���Ĝ݂�ʂƂ����X���͑������Ă���̂ł���B�����ł���ȏ�A�������ܗ֏������߂Đ��m�ɓǂݒ������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B |
|
�@�������Ȃ���A���͌ܗ֏����M���{����������킯�ł͂Ȃ����Ƃ��B�����A�ڂɂ����錻���e�N�X�g�͉�����ʖ{�ł����āA�����̌��{�ł͂Ȃ��B���̎ʖ{�����������B�S���ɎU�݂��܂���������Ă���ܗ֏��ʖ{�́A���ꂱ��������Ȃ��قǑ��݂��邾�낤�B �@�������A��X���m�F���������{�Ɍ����Ă��A�ٖ{�Ԃ̎���̑���͏��Ȃ��Ȃ��B����͓`�ʂ̉ߒ��Ō�ʂ��������Ƃ������Ƃł���B����͌����Ē��������ƂłȂ��A�`�ʂ��ꂽ�Õ����ވ�ʂɌ����邱�Ƃł���B�ܗ֏��ɂ��Ă��A�{���́A�F���ꂽ����̎҂Ɍ����ď��ʂ��Ď��^����A�Ƃ������Ƃœ`�����Ă����̂ł���B �@�ܗ֏��̃P�[�X�ł́A���������@�ꗬ���`�ɂ������āA�t�����ܗ֏������ʂ��āA������q�Ɏ��^������̂ł������悤���B��q�͎t�������ʂ������̂Ղ���̂ł���B���ꂪ�A�e�����������ǂ��āA�Ƃ������Ƃ�����A�܊��ꊇ�`���Ƃ������������肦���B �@������Ɍܗ֏��ɂ́A��L�̑��`�`�����Ƃ炸�A���`�`���̑̍ق̐���Ȃ��K�Ŏʖ{�̕����ނ��둽���B����͂����Ȃ�d�V���Ƃ����A���ƌܗ֏��Ɍ����āA���ꂪ�����̒��q�Ƃ������ƂŁA�嗬�O�ɗ��o���āA�`�ʂ���Ă����Ƃ����o�H��H�����̂ł���B�ܗ֏��ʖ{�́A���������̔K�̊C���Łipirated edditions�j�ł���B �@�Ƃ�����A�����ܗ֏��ʖ{�Ԃɂ͈قȂ�_����������قǑ����B����Ȃ�A���̂����ł��M���ł����{�������ĕ����ܗ֏��Ƃ��Ĉ����悢�̂����A���{�Ƃ��đ��݂��咣��������̂��Ȃ��B���������́A���ۂɂ́A�j���Ƃ��đe���ȃe�N�X�g�����u�ܗ֏��v�Ƃ��ė��ʂ��Ă��Ȃ����Ƃł���B������������ȊO�̃��@�[�W�����́A�ǎ҂̊Ⴉ�牓�������Ă��邩�̂悤�Ȏ��ԂȂ̂ł���B �@��̓I�ɂ��������x�z�I�ȃe�N�X�g�̖���������A���s�̊�g�Ōܗ֏��i�w���{�v�z��n61�@�ߐ��Y���_�x�n�ӈ�Y�E�Z���j�ł���B�����ɕ����́u�ܗ֏��v�����^���Ă��邪�A����́u�ߐ��Y���_�v�Ƃ������ł���B����ҁi�����Ɓj�A�\�|�ҁA�A�̎t���邢�͊G�t�Ƃ��������|�̈�����|�҂ł���B���@�ҁE���������̏��|�Ɠ������A�|�ҁA�|�\�҂ł������A���̂����肨���āA���̕ҏW�͐������B �@�Ƃ��낪�A�����ɒ�{�Ƃ��Ď��^����Ă���̂́A�א�Ɩ{�Ƃ�������̃e�N�X�g�ŁA��X�̏����ł́A�Ƃ��Ă������ł��Ȃ���ʖ{�Ȃ̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̏��ʕ��ɂ͌�ʂ�����ΒE��������Ƃ����㔭�I�ʖ{�ł���A�܂����̑̍ق́A���K�̑��`�����̑̂��Ȃ��ʂ��̂ł���A�܂��ɏ�L�̊C���ł̖��Ⴝ������������Ă��邩��ł���B �@�������A�ʔ����̂́A�l�\�N�قǑO����A��������ܗ֏���������ꂽ�Ƃ����������V�傪�A�ܗ֏���ҏW���������ł͂Ȃ��A����ɏ���Ɏ����ꂽ�A�n�삵���A�Ƃ����u�^�f�v���ꕔ�ɏo�Ă��邱�Ƃł���B����͖ϑz�Ƃ����ׂ��^�f�����A���̂��̎���̂ЂƂ́A��L�̊�g�Ōܗ֏������^����w���{�v�z��n61�@�ߐ��Y���_�x�̉���ł���B �@���͂�ΎE���ׂ��A�����Ȃ��ߋ��̋Y�_���낤���A�]���A����ɉ��ڂ����ܗ֏��������o�Ȃ������̂����ł���B����䂦�A���܉��߂āA���̋U�����ɕt�������Ă݂�A�\�\���R���V���̘_���́A�������V�傪�ܗ֏���n�삵���Ƃ̂��Ƃł���B����́A����A�z�ɂ��ȊO�ɂ́A���̗��R�ɂ͂܂�ō������Ȃ��B �@���Ȃ킿�A���܂��܁A�����i�ߐ��Y���_�j�����̒����w����^�x�����Ԏ��R�̎���E���Ԑꑾ�v���ςɂ�邢����u�J�ٖ{�v���Ƃ������Ƃ�����̂����A���́w����^�x�����Ԏ��R�Ҏ[�ɂ��U���ł���Ƃ���������㋻�s����āA���łɓ����Ȃ��ʐ��ɂ܂łȂ��Ă���B����͋ߐ������ɑ��閳�m�ɂ��e�G�Ȓf�ĂȂ̂����A���R���V���̘_���́A���Ɓw����^�x�U�������A�ܗ֏��Ɂu�K�p�v�����̂ł���B�܂�A�w����^�x�ɂ����闧�Ԏ��R�̖������A�ܗ֏��ɂ����Ď������V�傪�������Ƃ����킯�ł���B�ނ��A���̃A�v���P�[�V�����́A����Ȃ�A�z���炭��e���Ȓ��z�ɂ������A�����Ȃ���z�ɂ����Ȃ��B �@���ɐ��R��������Ƃ���́A���{���Ȃ��ʖ{�����Ȃ��Ƃ������Ԃ́A������ł����ɗႪ���邱�ƂŁA�������V��̑n��]�X�Ƃ͉��̊W���Ȃ��B����͂��Ƃ��A��������̌��{�����݂��Ȃ��Ƃ������R�ŁA����������U�����Ƃ���̂Ɠ����Y�_�ł���B �@���ɁA�����@��́w���@�Ɠ`���x�Ɣ�ׂČܗ֏��̎��Z�̋L�^���Ⴆ�Ă��Ȃ��Əq�ׂāA�����̕��͂ł͂Ȃ��ƌ��������悤�����A����͐�O�����Ă����ᔻ�̓��e�����Ă���ɂ����Ȃ��B���ׂ̑����א�Ɩ{�̏d���̋���˕t�����I�O��̔ᔻ�ł������B����������́A�ܗ֏����ɈӔ�`����炸�A�������狳���镁�ՓI�ȕ��@���{�Ƃ��ď����ꂽ���Ƃ�m��ʎ҂̌������ł���B �@����u���T��@�v�̃C�f�I���M�[�������āA�����@�闬�̐S�@�_�łȂ���Β��x���Ⴂ�Ƃ����v�����݂��A���Ďx�z�I�������B�������A�����@�闬�̊��l���́A�T�ƌ��̌����ɂ�鐸�_��`�I�u���̂悤�ɂ݂��邪�A���̎��A���̐��_��`�͐����x�@�̘_�����炷����̂ł���B����A�x�z�����̂��߂̐����I�C�f�I���M�[�̘g�g�ɑ��Ȃ炸�A�ނ�����핺�@���牓���̂ł���B �@��O�ɂ����A�����̐g�̂̐����I�����Ƃ́A�������������̂��A�Ӗ��s���̗��R�ł���B�����͐����Ȃ������Ɏ��a�����A�u�܊��V���v�𑐈Ă̂܂����M���ɗ^�����A�Ƃ����w�O�����ϕM�L�x�̋L���ɂ��Č��y���Ȃ��Ƃ��������A������m��Ȃ����̂Ƃ݂���B �@��l�ɂ����Ƃ���́A���@�ς̎���ɂ�闎���A�Ƃ����̂́A��������@����ɁA���������̎E�l����������@�闬�̊��l���ւ̕ω��Ƃ����}���ɂ����̂炵�����A����Ȏ���C���[�W�̓t�B�N�V�����ł���B�������A�����̌ܗ֏��ɂ��鑼���ᔻ�┽����I�ȃX�^���X���݂Ă��Ȃ��B �@�悤����ɁA���R�̌ܗ֏��U����̗��R���̂��̂��A�ǂ���������Ȃ��̂ł���B�������A�u��N�א쒉���̖��ɂ���āA�������݂����琮���L�^�����w���@�O�\�܉ӏ��x�v�ȂǂƂ����^������f�����B�ܗ֏��̑O�ɕ��@����������Ă����Ƃ����킯�����A��l�ɂ�镶���ȊO�ɁA�ǂ��ɁA����ȏ؋�������̂��B�u�O�\�܉ӏ��v�Ƃ������A�w�����`�x�́u�O�\��ӏ��v�̕��@���͂ǂ����B�悤����ɁA��㕺�@���̍��{�I����m�炸�ɏ����Ă���̂ł���B �@���̂����Ō�ɁA�������V��́u�n��v�́A�������犰������܂Łi1660�N��j�ɏ����������Ƃ����������J���Ă��邪�A����͂���ɖ��m��I�悵�Ă���ɂ����Ȃ��B���Ƃ��A�������V�傩��ĔC����ւ̌ܗ֏����`��������N�i1653�j�������A�Ƃ����킸�����̎��������ŁA���̖������������ɂȂ��Ă��܂���̂��̂ł���B �@�悤����ɁA�����W�j�����낭�ɓǂ�ł����Ȃ��f�l�k�`�A�O��̎���������m�炸�ɏ����Ă���̂ł���B������ׂ����m�Ɖ]���ׂ��B |
 ��g���ɋ��Ōܗ֏� ��O����̍�������Z���� ��g���X�@���ŏ��a17�N  ���{�v�z��n61�@�ߐ��Y���_ ���s��g�Ōܗ֏������߂� ��g���X�@���a47�N  ��g���Ɍ��s�Ōܗ֏� ��f�v�z��n�ł������ ��g���X�@���a60�N
*�y���{�v�z��n�{����z
�s���ĕ��@�̃s�[�N�Ƃ����ނ��������{�{�����́A���̂悤�ȕ��@�̕ϖe������������ʂĂɁA���̔ӔN�̐��ۓ�N�i��Z�l�܁j�A�{���Ɏ��߂��ܗ֏����������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A����͂����Ԃ邠�₵���B����͕����̎��M�{���`����Ă��Ȃ����ƁA�����@��́w���@�Ɠ`���x�Ɣ�ׂāA�ܗ֏��̎��Z�̋L�^���Ⴆ�Ă��Ȃ����ƁA�����̐g�̂̐����I�����A�킯�Ă��A���@�ς̎���ɂ�闎���Ȃǂ��炷��A�ނ��ŔӔN�ɁA���̂悤�ȏ����������Ƃ������Ƃ́A�܂��Ƃɋ^�킵���B�����炭��N�א쒉���̖��ɂ���āA�������݂����琮���L�^�����w���@�O�\�܉ӏ��x�����Ƃɂ��āA�����̖v��A���̍��펛�����V�傪�A�t�����̋������~�����āA�������犰������܂��ɏ������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����t�i���R���V���u�ߐ��|���v�z�̓����Ƃ��̓W�J�v�j |
|
�@�������Ȃ���A�����⓯���Z���҂̓n�ӈ�Y�̘_�i�u�l�@�w�ܗ֏��x�̖��_�v�j�͂Ƃ����A���r���[�Ȋ��D�Ő��R�U�����̐K�n�ɂ̂������̂ŁA���̓��e�����A��O�̑e���ȃe�N�X�g��ǂg�c�����⍕�c���̐������p��䍂��Ă��邾���ł���B�ܗ֏������Ƃ͖����̂��̂ł���B �@�������A���̈��p�ɂ��Ă��A���Ƃ��g�c���������N�́w���B�{�{���U�x�ɂ����āA�ܗ֏��̓��e�����G���Ƃ����O���̘_�������A�s�����A�����œ��ɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̕��G�ƌ����A�m��Ǝv�͂�鏊�ɁA�p�ĕ��U�̎v�z�̓��F�����݂��Ă�邱�Ƃł���t�Ə����āA����Ȃ�̃t�H���[�����Ă���B�n�ӂ͂���ɂ͖j���ނ肵�āA�����������[�Ȉ��p�������ċg�c�̏�����c�Ȃ��Ă���B �@���邢�́A�n�ӂ̉���́A�u���@���`�v�u���������X�o���v�Ȃ���������āA�����ɂ���܊��̕����i�ܗ֏��j�́u���v�̒�������v���X�Ƃ����]�_�ɓǎ҂̖ڂ����������邪�A������ꂪ�����Ȃ闬�h�̕������邩�A�����Ȃ镶���ŏ�����Ă��邩���m�炸�Ɉ��p���Ă���B �@��X�̒m���͈̔͂ł́A���̌��`�ɂ͂������ٖ{������B�n�ӂ����ĕ������ʂ����̂́A���̈��p���̎���̓������炷��ƁA��㓡�c�������肵�ĕۗL���Ă����ʖ{�̂悤�ł���B�����̎ʖ{�ŁA�뎚�E�����A�ʂ�����̂���ʖ{�ł���B �@���̌��`�ɂ��Ă͖{�T�C�g�ŕʂɖ|��������o��ł��낤���A��̓I�ɒm��҂��قƂ�ǂ��Ȃ��̂�����ł��邩��A�����Ŏ�q�ׂĂ����A�\�\����͌����́A�z��֒}�O��V����`�����O�H�M�p�剺�̕����ł���B�n�ӂ����p�����̂͂��̂����̈�{�ŁA�O�H�M�p�̑\����q�E�\��ɓ����M���t���̓n�����M����`������Ĉɓ��Ƃɂ������������ʂ������̂ŁA���ꂪ���܂���Đ��Ε��ɂɔ[�܂������̂炵���B �@���̌��`�́A�{���s�������̌��`���������Ƃ����ς����㕨�ł���B�}�O��V���Ȃ�A���`�́A������u�O���̑厖�v�Ƃ����ܗ֏��ɂ�����`�ȊO�ɂȂ��͂��Ȃ̂ɁA���̂悤�ɑ������ʂ́A�������u���������ꂽ���`�v���A���́u�������v�Ƃ��Ĕ��������̂ł���B �@���̕����S�̂�����ɁA�����i�����j��p���Ėʎ������փV�t�g�������Ƃ���A���`��`�I�Ȗ��������Z���ŁA�����͂��납�O�H�M�p�̓�V�����炵�Ă��A���Ȃ��E�������͕ϑԂ��Ă���B���Ƃ��A�E�f�̂��Ƃ��A���q�̕��щΎR�ɋ[���āA�ٍ��V�̓��q���单�V�̓��m��疀���x�V�̓��E���ƌ��̂����A�܂��Ƃɂ��ꂱ���A�܊��̕����p�̒��������ƕ]���������́u���_�v�Ȃ̂ł���B �@�ނ��A����ȏ������������������̕��@��������o�Ă���킯���Ȃ��B�܂��ɑ����̕����̂��Ƃ��ł���B�����h�̗��_�I�F�����������Ȃ̂ŁA��������̂܂ܕ����嗬�����ƌ��Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B����A���̌��`��������闝�_�̑����͖}�f�Ȃ��̂����A������肩�A���悻�����I�łȂ��B�ܗ֏��̖����ȗ��_�ɋt�s���āA�Ђ����牜�閧�����ɑ����Ă���B����䂦�A�u���v�̒������v�Ƃ͉䎖�Ȃ��A�Ɲ��������Ƃ���ł���B �@���������ނ̕������O�H�M�p�剺�̈�h���甭�������̂́A���ꎩ�̋����[���Ƃ��낾���A�������A����Ȍ��`�̉A���������Ă��A�z��̖嗬�ł͌ܗ֏��͂�����Ƒ��`����A�����Ɏ�����ܗ֏��̑��`�����������̂ł���B���Ƃ��s���ɂ̕����܊��t�ƋL����邲�Ƃ��A�ܗ֏����ȉ����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����͂ނ���t�ł������B �@���Ƃ���g�ʼn���҂̓n�ӂ́A���̂悤�Ȏ����m�炸�A�܂����̌��`�������Ȃ�ʒu�Â��̕����������m�炸�A������̕����ٖ̈{�̏��݂��m�炸�A�����A���܂��܌��������ʖ{����A�����̌������ɍ��������������Љ���̂ł���B�ٍ��V�̓��q���̑单�V�̓��m���̖����x�V�̓��E���̂ƌ�镶���ɁA���̖��v�̒������Ƃ����]�������邱�ƂL���Ȃ��B�\���܂ł��Ȃ��A����ł͂����炩�ɕs�����Ȏj���g�p�ł���B �@�n�ӂ͂��̌��`�̕��������p����̂����A����͑O�̋g�c�����̐��̈��p�Ɠ������A�Ќ��̘c�ȓI���p�ł���B���̌��_�������Ȃ镶���ŏ����ꂽ�̂��A���邢�́A���̕������̂��̂������Ȃ������ʒu�Â���L����̂��A������ɂ��Ĕ��[�Ȉ��p�����Ă���B����������������́A�����Ƃ��̖嗬�ɂ��ēn�ӂ����m�������䂦�̏��Ƃł���B �@���ہA���̓n�ӂ̈��p���́A���̌�A���������ő������̍Ĉ��p���J��Ԃ��ꂽ�B�n�ӂƓ��������̎����̉����邩���m��ʘA�����A�ܗ֏��͕����嗬�ł��]�����Ⴉ�����Ƃ����؏��ʼn��p����Ƃ����n���ł���A�����A���ꂪ�ٓV���܂�单���܂�M���镶�����Ƃ��m��Ȃ��̂ł���B�������A���́A���{�ɓ����Ă��݂Ȃ�����A�n�ӂ̌�Ǖ��������̂܂ܓ]�L���Ă���B�����������m�ȑ�����������Ĉ��p�҂̔y�o�ɂ����āA���܂��ɓn�ӂ̌�Y�͌��͂����āA�V���ȋ������s���Đ��Y����Ă���̂ł���B �@���������A���{�v�z��n�{�̂��̓n�ӂ̉�����݂�ɁA�V�A���ɂ��Ă͑����m���Ă͂���悤�����A������ܗ֏��̂��Ƃ͑S���m�炸�ɏ����Ă���̂ł���B�������A�����̓����ɂ��Ĕ��n�j�������m��Ȃ��Ƃ����̂́A���Ă����Ƃ��Ă��A�����j���̌��T�����Ă���̂ł͂Ȃ��A�������������̖|���������ǂ�ł��Ȃ��B �@�悤����ɁA�����ƌܗ֏��̌����Ɋւ��āA�܂������̑f�l�Ȃ̂ł���B�����̒�q�ɁA�������V��E�����n���E�Ë��y���q��̎O�l�̖���������Ƃ��납�炷��A�Ë��n�̎�앶�ɖ{�̌ܗ֏������Ă���炵�����A��앶�ɂ�`���Č��{�������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�n�ӂ̃P�[�X�ł́A�R�c���N�g�|���{�̑������ł���B �@�������ĉ��ƁA�������V�傪�A�����V�A���̌��p�������Ɩϑz���Ă��܂��B�������A�n�ӂ́A�������V�傪���U�d�������A��S�̘\��H���Ƃ��Ȃ��A�Ƃ���������m��Ȃ��B���邢�́A�w��V�L�x���������V��n�̓`�����ƁA�˔��q���Ȃ����Ƃ������o���B�w��V�L�x���������L�c�i�p���A�i�������n���n������h�́j���㔪�Y�E�q��̒�q�������Ƃ������Ƃ���m��Ȃ��̂ł���B �@���́A�����������x���̎҂��A��g�Ōܗ֏��̍Z���҂Ȃ̂ł���B���Ƃ��A�ܗ֏��ٖ{�Ԃ̉��f�I�ƍ��Ƃ����Œ���̎葱���������s���Ă��Ȃ��B����䂦�A�e�N�X�g�Ƃ��Ă̍א�Ɩ{�̈ʒu�Â����ł��Ă��Ȃ��B�Z���҂Ƃ��Ă��肤�ׂ��炴��m��ƈ����ׂ��B �@����ɂ܂��A�ȉ��̉�X�̓lj��ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA�e�N�X�g�Ɋւ��Čӗ��Ȓ�����Ă���B����A�u�ܗ֏���������ɓǂށv�Ƃ������m�ȐU�����������Ă���B�������画�f����A�n�ӂ��ܗ֏���ǂ߂Ă���Ƃ݂͂����A���������ܗ֏��Z���҂Ƃ��Ă̓K�i�����^�킵�߂�B �@�����āA�ȏ�̊�g���{�v�z��n�w�ߐ��Y���_�x�̉�����Ɋւ��錋�_�������A�������V�傪���҂��A���ꂷ��m��Ȃ����ŁA���̊�g�Ōܗ֏��̉����������Ă���͖̂��炩�ł���B���̍ł�����̂́A�������V�������V�A���̌�����ɂ��Ă��܂��n�ӂ̒��������A�����A��L�̒ʂ�A�ނ�R�̌ܗ֏��U����ɂ͍����͂Ȃ��B �@�ܗ֏�������n�삳�ꂽ���̂Ȃ�A�����ܗ֏��́A�����Ɗ������ꂽ�̍ق��������ł��낤�B�ܗ֏����������������Ƃ������ƂƁA�������V�傪�ܗ֏���n�삵���Ƃ��������͌��т��Ȃ��B��X�̌���Ƃ���A�ܗ֏��͐�������Ă��Ȃ�����e��Ԃ�I�悵���܂܂�����A�ނ��낻��́A�������V��͑n��Ȃǂ����A�����̑��e���ҏW�����ɂƂǂ܂�A�Ƃ������Ƃ̏؋��ł���B�ܗ֏��ɂ��ĉ����m�炸�ɁA���R�̌ܗ֏��U��������鈟�����Ȃ����ł��Ă��Ȃ��Ƃ���A���̂��Ƃ͉��߂ċ������Ă����Ă悢���낤�B �@����Ȃ��Ƃɓ����i�ߐ��Y���_�j�ɂ́A�ܗ֏��U������U�������w����^�x�A������J�ٖ{�����^����Ă���B�܂�A�Z�E���Ԏ��R���珑�ʂ������ꂽ���Ԑꑾ�v���ςɂ��ʖ{�ł���B�\�\�Ɖ]���A�����Ɏv��������ǎ҂����낤���A���̗��ԕ��ς����A�}�O�ɂ����镐�������@�A��V���ܑ̌�A���Ȃ킿�V�ƕ����猺�M���������V��M�����ĔC�O���q����遨�g�c���Y�E�q����A�����Ԑꑾ�v���ςƎ��悷�闬�n�ɑ�����҂ł���B �@���ԕ��ς̒��q�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�ܗ֏������R�����A���ꂪ���e�̂܂����M���ɓ`�����ꂽ���Ƃ��L����Ă���B���ꂪ�ܗ֏����������ɂ�����̐t�̎j���Ȃ̂����A���R��ܗ֏��U����_�҂͂����m�炸�A���p�����Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A���ԕ��σ��@�[�W��������J�ٖ{�w����^�x�����^���������i�ߐ��Y���_�j�ɁA�ܗ֏��U�����t���Čܗ֏������^���Ă���Ƃ́A�������݂��܂������̃W���[�N�Ƃ��������悤���Ȃ��B �@���ԕ��ς��A�܂��������I��ɁA����Ȋ��m��������Ƃ́A���ɂ��v��Ȃ������ɂ������Ȃ��B�悤����ɁA�����i�ߐ��Y���_�j�̑��݂��̂��̂��A���������j�ɂ����锚�V�[���Ȃ̂ł���B �@�������������������̌ܗ֏��U����ȑO�ɂ́A���a�܂ł��炭�̊ԁA�א�Ɩ{���������M���{���ƐM�����Ă����A�Ƃ��������ׂ����Ԃ��������B�ܗ֏��U����́A����Ȏ��Ԃւ̒P���Ȕ����ł���B���̈ꎞ���A�u���������v�ւ̔����Ƌ����j���s�����Ƃ�������̋�C�����������Ƃ͋L�����Ă����Ă悢�B�����������Ƃ͂悭���邱�ƂŁA�T���͂�������悤�Ƃ���܂��ʂ̕T���ނ̂ł���B |
*�y���{�v�z��n�{����z
�s���������܊��̕��ނƏ������ẮA���R�Ƒg�ݗ��Ă��Ă��邪�A���e�͈ӊO�ɎG�R�Ƃ����Ƃ��낪����A�܂��������Ƃ����X�ŌJ�Ԃ���Ă���B�O��ɉ��̘A�����Ȃ����Ƃ�����Ă���Ƃ��낪����B�܂��Ј���ł͋��낵�����C�Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ���A�����ł͂ƂĂ���C�ȂƂ��낪����B�啪�̕��@�E�����̕��@�Ƃ����Ă����Ȃ���A�啪�̕��@�̋L�q���R�@�Ƃ��Ă͖��ɂȂ�Ȃ��قǗc�t�ł���i�g�c�����w�������x���a�\�Z�N�j�Ƃ����B�܂��S�̂ɕ��͂̕\�����B���ŁA�s���Ăȓ_�������t�i�n�ӈ�Y�u���@�`���`���ɂ��Ă̈ꎎ�_�v�j  ���@���`�@���Y�ӏ�
*�y���@���`�z
�s�G�Ɍ��ցi�Ёj���}���Ȃ鎖�A���̔@���B�������ɉA�̐S������A�����V�̌䓿�q�Ȃ�B�G�𐿂đ��������邱�ƁA�R�̔@���B�����ɗz�̐S������A�单�V�̌䓿�m�Ȃ�B�G�ɂ��Ђđ��N�����邱�ƁA�̔@���B�����ɗz�i�A�j�̐S������A�����x�V�̌䓿�E��B�G����Ă��̐Ì����鎖�A�т̂��Ƃ��B�������j�z�̐S������B�F����Ҋ����p�̈ʖ�t�i���������X�o���j *�y�ܗ֏����`�ؕ��z �s�V�����Ԃ̕��@�A�\�s�т���Ƃ��ւǂ��A���ԑ�����营��B�ւāA�߂Ɏ���̐Ղ��p�B�K���a�ɂ��ĕ��@�ɐS��s�����A���Ɏ��Č\�N�A������ςĎv�Ќ���A��t�A������В��ʂ����ЂāA�͂𗧂�ꂵ���A���ɐ_�ʂ̖��Ƃ��ӂׂ��B�D�����̎��ɉ��āA�Ńo���������A�U��o���s��B��Ɍ`���肷�鎖�Ȃ��A����ɂ��āA�S铛܂̂��Ƃ��ɐ��āA�G���v�ӂ܁T�ɉ����R�ɏ����A������A���ʖ�B�M�a�[�����Ɏu�A���N���s�L�V�ɂ�āA�\������|�A�܊��̕����A�O���̑厖�����A�S�����B�����ߕL�ʁB�P�ϔN�ɒb�B�H�v���Ȃ��A��t�̈ӂ��p�āA��푴�@��������҂��~�A����B�ցA���ɕs�⎖���ߍs�ӂׂ�����t�i����O�H�ܕ��q�M�p�A�����O�N�j �s��V�ꗬ���@�̓��ɁA�M�a�[�u���N�ˌ䎷�s�A�O�H�M�p���\���鎊�ɔV�����܊��A�O���̑厖�����A�ߙB���L�B��͕ΓV�n�l�����D�j���Č���B�����̕s�m���Ȃ��B�ȍ��ӓG���т����n�A��x�s�킵�Đ�x�����A�҂ɂ���B������A�ʖ�B���̒��ɂ����鎖�̐�ϖ����A�F�@�z�B�ѓ��s�^�Җ�t�i����n���Z�E�q��M�s�A�������N�j
*�y���{�v�z��n�{����z
�s��̒�q�ł��鑷�V��͂����錕�p�����i�����炭��N�̒����Ɠ��������V�A���ł��낤�j�ŁA�m�s��S�A�����̎��v�����O�\�܍A��̒�q���n���͏����̏o�g�Łc�t�i�n�ӈ�Y�A����j  �g�c�Ɩ{�@��V������ �@�@�i�N�������j���ۓ�N�܌��\��� �@�@�i���@���j�@��������a
*�y�O�����ϕM�L�z
�s�����܊����L�T���B�n���Ε���g���X�B�����i�L���j�a���Y�t �s�܊��m���A���ăm�}�R�j�e�M���j���P�����V���w���\���i�V�B�˔V�A��N���B�m���A���╗���Ȏ��\�����c�P�Y�t |
|
*�y��앶�ɖ{�t�L�z
�s�܌��\����Ɏ����L�l���A�O���\����A�O�l���Ċ�A����趒k�����鎖�n�A�莧�o�L�V��B����A�������Ɖ]���͂Ȃ��A�������ꌩ�V��A���ׂ̂��R�A��\�n��R�t  ��앶�ɖ{�@���Y����  �Ë��n�^�S�������`�n |
�@���邢�́A����Ɋ֘A���āA��앶�ɖ{�̖����́u���H�v�Ƃ����t�L�̂��Ƃ�����B����͌Ë��y���q��́u��̎ҁv�Ƃ����Ҏ[�҂��t�L�������̂ŁA�\�����I����̍앶�Ƃ݂�ׂ����̂ł��邪�A�����ɂ́A�u�������v�Ƃ������ƂŌܗ֏��Ɋւ���L��������B �@��앶�ɖ{�ɂ͒E���뎚�������āA���̕��͂ɂ��A�����������ꂪ���肻���ȂƂ���Ȃ̂����A���̋L������ǂݎ���̂́A�\�\�����͌܌��\����Ɏ����A���̑O�ɏ\����ɁA�O�l�i�������V��A���n���A�Ë��j���Ă�ŁA�u������趒k�������Ƃ́A��߂Ċo���Ă��邱�Ƃł��낤�B����ɂ́A���̏����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���̏����ꌩ�̌�A�Ă��̂Ă�ׂ��v�Ɛ\���n���ꂽ�����ȁB�\�\�Ƃ������̂ł���B �@�܂�A���̏����i�ܗ֏��j���ꌩ������͏Ă��̂Ă�A�Ƃ����̂������̈⌾���Ƃ����炵���̂����A����ł͏ċp���ׂ������������̈⌾�ɔw���Ďc���ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�܂��A����ȏċp���ׂ������ɁA�ǂ����Ď������V��E�Ë��y���q��A���̈���������̂��A�悤����ɘb���������Ă���̂����A���̕t�L�����������l�́A����Ȃ��Ƃ͋C�ɂ��Ă��Ȃ��悤�ł���B �@�����������A����́u�R�v�Ƃ���`���L���ł���B�Ƃ藧�ĂāA�]���ׂ����e�ł��Ȃ��B�������A���́u����ɂ́A���̏����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���̏����ꌩ�̌�A�Ă��̂Ă�ׂ��v�Ƃ����Ȕ����A��Ɉ�l�������Ă��܂����̂ł���B �@�܂�A�������ċp����ƌ������̂�����A���̏������c���Ă���͂����Ȃ��B���������āA���ܗ֏��Ƃ��Ďc���Ă���̂́A�U�����Ƃ����킯�ł���B �@������́A��앶�ɖ{�̋L���A�s����A�������Ɖ]���͂Ȃ��t�Ƃ����������A�w���Y�p���x�i�A�J�Y���Y�ҁE�吳�\�l�N�j���A�u�䏑���Ɖ]���͂Ȃ��v�ƌ�L�����B����ƁA��앶�ɖ{�̌��������Ă��Ȃ��҂炪�A���́w���Y�p���x�̎�����̂�グ�āA�����́A�����ɂ͒����͑��݂��Ȃ��A�Ɩ������Ă���Ƌ��ق����̂ł���B�ނ��A�O��̕�������A���������ċp���ׂ��ƈ⌾���ꂽ�����̒��삪�������A�Ƃ������Ƃ͖��炩�Ȃ̂����A����Ȃ��Ƃ͖�������̂ł���B �@�����������A���̎�앶�ɖ{�̕t�L���甭�������Ƃł���B���̕t�L���A�`���L���������Ƃ߂��̂��A�ǂ������킯���A�������V�傪�ܗ֏����U�삵���Ƃ�������Ȑ��̍����ƂȂ������̂ł���B���ۂɁA��앶�ɖ{�̕t�L�ɁA�������V�傪�ܗ֏����������ƋL���Ă���̂Ȃ�܂������A����Ȃ��Ƃ͕t�L�ɂ͏����Ă��Ȃ��B���̕t�L����A�������V�傪�ܗ֏����������Ƃ������_���o�����Ƃ͂ł��Ȃ����k�ł���B �@�ނ���A���̓`���̓��e�́A���̏������ꌩ�̌�A�ċp����ƕ������⌾�����A�Ƃ������Ƃɂ������A����͔����~�����́A�u�\�q�v�Ƃ��������ɂ܂��`���Ɠ��^�̂��̂ł���B�ċp���ׂ��Ƃ̈⌾�ɂ�������炸�A���ꂪ�c�����A�Ƃ������b�p�^�[���ł���B �@�Ƃ�����A���̉~�����n�ܗ֏��ɂ͂��̋L���͂Ȃ��B��앶�ɖ{�̌n���̓��ًL���ł���B����䂦�A�{���L���������ɂ��Čܗ֏��̐�������肦�Ȃ��̂͐\���܂ł��Ȃ��B �@�����A�Ë��n���̗��h�͊e�n�ɑ����������A���̌n���̑��`�ܗ֏��͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���̎�앶�ɖ{�̏ꍇ�A�㐢�ɂȂ��ČË��̎�̎҂��A�ǂ����Ōܗ֏����ʂ��āA�Ë��̖����������V��̖��̘e�ɕt�����������̂ł��낤�B���ہA��앶�ɖ{�͂��Ȃ�ʂ�����̂���ʖ{�ł���A�J�ԗ��z���Ă����ʖ{���ʂ������̂̂悤�ł���B �@������ɁA�j���ᔻ���ł��Ȃ��҂�́A�ǂ̒i�K�ł��̕t�L�������������A���̓`���ɐM�ߐ��͂���̂��A����Ȃ��Ƃ��ӂɉ�Ȃ��B�������V��U����Ƃ́A�悤����ɖ��m�ɂ�鋭�قȂ̂ł���B���̎�̂��͕̂����Ă����Ώ��ł�����̂ŁA�������Ɂw���Y�p���x�|���̌ܗ֏����M�p���Ȃ����Ă��܂��ƁA������F�A���̂��Ƃ�Y��Ă��܂����̂ł���B |
|
�@���������U����̂�����̘_���́A�ܗ֏��̕��͂��ٗƂ��������ɂ������B����A�����ɂ���܂������͂ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ƃ��납��b���͂��܂����̂ł���B���̓_�͂ǂ����B �@���Ƃ��A�g�c�����w�������x�i���a�\�Z�N�j�ɂ́A�ܗ֏��̕��͂��G�R�Ƃ��Ă��Đ�������Ă��Ȃ����ƁA�d�����������薬�������������̗����邱�ƁA�뎚���c��������A���t�̎g�������σe�R���A�Ƃ������悤�Ȋ��z���q�ׂ��Ă���B �@���Ƃ��A�g�c�����ȑO�ɂ��A���Ƃ��Β��؎O�\�܂̌ܗ֏����������������B���͕����̋����j��̐��҂ƌ����ׂ��ŁA�ܗ֏��̈���������������隅��ƂȂ����B�g�c�͂��̐K�n�ɏ������������B�������A�א�Ɩ{�̑e�G�Ȗ|�������Ƃ��Ă��A���������ܗ֏���ǂ����Ȋ��z�Ȃ̂ł���B���̂�����ɂ����āA�g�c�͐������B �@�������A�g�c���m��Ȃ������̂́A�ܗ֏����������̑��e���������Ƃł���B���͂̐������s���͂��Ȃ��̂́A���ꂪ�������ꂽ�����e�ł͂Ȃ��������߂ł���B�������V��̕ҏW�ɂ���Ă܂Ƃ܂��������̑̍قɂ͂Ȃ������A�������ҏW�ҁE�������V��́A�������݂�}�����̈ʒu�����܂킸�A�����ɑ��e��]�ʂ����̂ŁA�������č��������܂܂ɂȂ����̂ł���B �@���邢�͂܂��A�뎚�ⓖ�Ď�������A���t�̎g�������ς��A�Ƃ����B����́A�g�c�̌Õ����{�̖������邪�A��͂�g�c�������ܗ֏��e�N�X�g�ɖ�肪�������ƌ����ׂ��ł��낤�B�悤����ɕ��p�p���łł����g�łł���A�����ܗ֏��̖|�����������m��ʎ҂ɂ́A���̌뎚�E���ɂ͋C�Â��Ȃ�����A���͂̍���������A�ٗ�ȕ��͂��ƌ�����B�����ܗ֏��|�������ܗ֏����̂��̂��Ǝv������ł���̂����A�����������o�́A���ꂪ���o���Ƃ͒m��Ȃ����o�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ͂����A�g�c�����̊��z�́A�����{�ܗ֏����܂Ƃ��ɓǂ�ł̗����Ȃ��̂ł���B�ܗ֏������҂̑����ߔN�ł����A���̂悤�ɗ����Ȕ�]������҂͂��Ȃ��B�悤����ɁA�ܗ֏��e�N�X�g���܂Ƃ��ɓǂ�ł��Ȃ��̂ł���B�������܂Ƃ��ɓǂ܂��ɁA�₽��]�����q�ׂ�A���������̂ł���B �@�悤����ɁA�ܗ֏��̕��͂ɂ��ẮA�ʗ_�J�Ȃ��������B���Ȃ��҂�����A�ق߂�҂��������B���Ȃ��҂͐�O���炠�����B���������Đ��́A�ق߂�ɂ��V�j�J���ȗ��ۂ�����悤�ɂȂ����B���ق߂Ă݂������̂ł́A���Ƃ��A�i�n�ɑ��Y�i�u�^���{�{�����v�j������B����ȂLjꌩ��^�ɋ߂����Ⴞ���A����͂܂�œI�O��ȕ]���ł���B�������������j��̎��ォ�炷��A����͂���Ȃ�^�ł͂Ȃ��A���قߎE���ł��邪�A����ł��A��͂�ܗ֏����낭�낭�ǂ�ł��Ȃ��҂̉Ȕ��ł���B�ق߂�҂�����Ƃ��Ă��A���悤�Ȃ��肳�܂ł���B���Ƃ��͂�A���Ȃ��҂Ƃق߂�҂̂��̗������A�ܗ֏���ǂ߂Ă��Ȃ��̂ł���B �@��L�̋g�c�����̂悤�Ȉӌ��́A�ܗ֏��ɂ͈Ӗ����ʂ�Ȃ��s���Ăȕ��͂����Ȃ��Ȃ��A���͂Ƃ��Đٗ�Ȃ��̂��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B����́A�Ⴋ�i�n�ɑ��Y�̏Ύ~�ȕ��͊Ӓ���͂܂��}�V�ȋq�ϓI��]�Ɖ]������̂́A�������Ȃ���A�ܗ֏������Ă̂܂c���ꂽ�������Ƃ��������w�I������m��Ȃ��̂ł���B �@�������A�悭�悭���Ă݂�A�����̓ǂݎ肪�ǂ�ł���̂́A�����ɂ����u�ܗ֏��v�Ȃ̂ł͂Ȃ��B���Ƃ���͏��Ƃ��א�Ɩ{���앶�ɖ{��|���������{�ł����Ȃ��B�ނ��A���̃��@�[�W�����̏��ʖ{���Ă݂邱�Ƃ��炵�Ȃ��ӑĂƂ������A���������ܗ֏��Ȃ�j���ɖ��m�Ȕ�]�ł������B�����ܗ֏��̑e���ȃe�N�X�g��ǂ�ł��邩����A�����̌ܗ֏���ǂ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�ܗ֏��قǁA�ɂ��₩�ɘ_�c�̑����������@��������܂��B�ܗ֏���^�_�A����ɑ��ܗ֏��������A�Ȃ��ł��������V��U������X�A�悤����ɁA�����Ɏ���܂ŁA�܂Ƃ��Ȍܗ֏��_�ȂǏo�����߂����Ȃ������B�ܗ֏����߂��錾�_�ɂ́A�܂��ƂɗȂ��̂�����B |
*�y�g�c�����z
�s�e�ɂ̓��e������ƁA���ꓙ���ӊO��趑R�Ƃ��Ă��̂́A��铂ǂ�����桂��炤���B��ɂЂǂ��̂́A�����������A���X�ɌJ��Ԃւ���Ă��A�O��ɉ���̘A���̂Ȃ��������A�ЕГI�ɗ���Ă�āA�����̐���������Ă�Ȃ��y�ł���B�i�����j���ɜ��܂����̂́A�ނ̕��͂��B���U�̕��͂͌�����椂ݗǂ����̂ł͂Ȃ��B�뎚���c���͓e�Ɋp�Ƃ��āA���t�̎g�Е����̞��q�Ȃ̂ł���B�����Ӗ��������ɂȂ�ꍇ��������A�]�Е\�����ɕs���Ă��y�������̂ł���B���U�̎���ɂ́A���͂���Ȍ��t�̎g��������Ă�̂����m��Ȃ����A����ɂ��ẮA�c�������ꂽ���̕��ق�����ɁA���Ɨp��̐��m�ș���̂悢���͂���������̂����A��ə��@���̒��ɂ��A�ܗ֏��Ɋr�ׂ���A���͓I�ɂ͗D�ꂽ���̂�������̂�����A����͖�蕐�U�̕��͂��ق��̂��ƌ���ׂ����炤�t�i�w�������x�j
*�y�i�n�ɑ��Y�z |
 �א�Ɩ{�@��V������ �����L����恁u���M�v�Ȃ� �������V�告�`�ؕ��Ȃ� 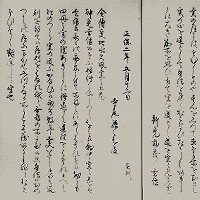 ���R���ɖ{�@��V������  �g�c�Ɩ{�ܗ֏��Ɗ֘A����
*�y�O�����ϕM�L�z
�s�E���A�O�p���n�A�܊��m���A���M�j�����V�e���V�A��̓w�n�A���A�����\�j�o�t���|�m���j�A���������w�e���V�B�B���m�㓁���A��̓j�n�V�u���t  �z��Έ�Ɩ{�@�O������ ���q�{�ƍ��q�{  ����笉��{�@��������
*�y�}�O�n�ܗ֏��`�n�}�z ���V�ƕ����猺�M�\�������V�儢 �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���ĔC����\�g�c���A�\�� �@�@�@�@�g�c�Ɩ{��V���@�b �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b���Ԍn �@�����ԕ����\���ԑ�����笉��{ �@�b���\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b�����Ԏ�с\���ԑ����\�� �@�b�b���\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b�b���g�c�o�N �g�c�Ɩ{���`�ؕ� �@�b�b �@�b���O�H�M�p�c���i�z��嗬�j �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z��n���{ �@�b �@���i�g�c���N�j�c�g�c�Ɩ{�l�� �@�b �@�b����n�@�@�@�@�@�@�@���H �@����������\�������v�\�� �@�@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�@����ˏd�J�\��˓����\�� �@�@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�@����ˏd�f�\��ˏ����q�偨 �@�@�@�@�@�@�@���R���ɖ{
*�y���n�ܗ֏��n���h���}�z ���������V��\�����ʖ{�c���o�c�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���c�c�c�c�c�c�c�c�x�i�Ɩ{ �@�b �@���c���c���c�c�c��Ɩ{ �@�b�@�b�@�b �@�b�@�b�@���c���c�c�c�핐���{ �@�b�@�b�@�@�@�b �@�b�@�b�@�@�@���c�א�Ɩ{ �@�b�@�b �@�b�@���c���c�c�c�ۉ��Ɩ{ �@�b�@�@�@�b �@�b�@�@�@���c���c�c�c�R���S�M�{ �@�b�@�@�@�@�@�b �@�b�@�@�@�@�@���c�c�c���Ɩ{ �@�b �@���c���o�c�c�c�c�c�~�����n���{ |
�@�������e���ɓ��������A�����Ŗ{���ɂ��ǂ�B��O����ʂ��Ă����Ƃ����z�����ܗ֏��e�N�X�g�́A��g�Ōܗ֏��ł��邪�A��X�͂�����A���炩�̗D�z���̂���u�ܗ֏��v�e�N�X�g�Ƃ��ĔF���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��g�Ŋ��s�ɂ���ē��������ꂽ�א�Ɩ{���������ꂽ�ܗ֏��ʖ{�͑��ɂ���������B�א�Ɩ{�ɓ��ʂȃX�e�C�^�X�^����͖̂����ȍ���ł���B�Ƃ͂������́A�����̃I���W�i���Ɂu���ڂ���v�قǂ̊i�ʂ̃��@�[�W��������������킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ԂȂ̂ł���B �@�������A�����̃I���W�i�������������A�ʖ{�������݂��Ȃ��Ƃ��Ă��A����ňꌏ��������킯�ł͂Ȃ��B���������M�̌������ꂪ�Ȃ��ƒQ���Ă���̂Ɠ��������ł���B�ܗ֏������ł���ȏ�A�����̃I���W�i����T������A�v���[�`�Ɏ�肩����K�v������B���̂��߂ɂ́A���{���L�������Ĕ�r�ΏƂ��A��茴�^�ɋ߂�������z�肵�A�u���ܗ֏��v�̕��������݂��Ƃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�������Ȃ���A���{���L�������Ĕ�r�ΏƂ��s���ɂ��Ă��A�]���̌����ɂ͖��炩�ɐ��������B����Ƃ����̂��A��O���m���Ă����א�Ɩ{���앶�ɖ{�ɉ����āA��Ɩ{��ۉ��Ɩ{�����@�����悤�ɂȂ��Ă��A�ˑR�Ƃ��Ă���́A���n�̎ʖ{�ł���A�������ٌ̍`���̐���Ȃ��C���ł̎q���ł���Ƃ����_�ł́A�ς�Ȃ���������ł���B �@�܂�A���̉������݂�A���n�ʖ{�̃X�e�C�^�X���m���̂����A���Â���������V�傪���`�����ܗ֏��̌`���������Ă���B�܂�ܗ֏����`�Ƃ͖����Ȋ��ŁA�`�ʂ��J��Ԃ��Ă������̂ł���B�������n���{�́A��O���o�㔭�������C���Ŏʖ{�����c�Ƃ�����̂ł���B �@���݂܂łɔ�������Ă�����n���{�ɂ́A���̂悤�ȔK�ł������݂��Ȃ��B����͂Ȃ����Ƃ����ɁA���ł͎������n���̌n�����嗬�ƂȂ�A�{���ܗ֏���Ɛ�I�ɓ`�������������V��̖嗬�����S��������ł���B �@���Ƃ��A�������n���́A�Z���V�傩��ܗ֏��𑊓`���ꂽ�̂ł͂Ȃ���������A���n���̌n���ɂ͖{���C���ł����Ȃ������B���V��̌n�������O�֗��o�����ʖ{�����{�Ƃ��āA�ȉ������ʂ��Ă����̂ł���B���ɂ͊̐S�́u�������V��a�v�Ƃ������������������̂�����B�������n���{�̑̍ق�����Βm���悤�ɁA����ȔK���[�g�ŁA���{���n���h�������̂ł���B �@����ɑ��A�ܗ֏��𑊓`�c�[���Ƃ��Ă����̂́A�}�O��V���̌n���ł���B������͎������V��ɔ�����嗬�ł���A�������V�傩��ĔC����w�A�����ĎĔC���g�c���A�Ɉꗬ���`�������ʁA�}�O�����œ�V���̓������������B �@�ܗ֏��Ɋւ��ĉ]���A�}�O��V���ł͌ܗ֏����t�����q�ɓ`�����Ă����B����䂦����Ɏ���܂ŁA���̑��`�o�H�͖��炩�ł���B�����Ă��ꂾ���ł͂Ȃ��A���ڂ��ׂ��́A�������V��ȉ��A��X���`�ؕ���t�����Ƃł���B���̕����������͎̂������V��ł��낤���A���̌`����ۑS���ē`�����ꂽ�̂��A�}�O�n�ܗ֏��ł���B �@����́A���n���{�ɂ͌����ʂ��Ƃł���B�}�O�n���{�Ɣ�r����Β����ɒm��邱�Ƃ����A�������n���{�̋�V�������ɂ́A�ǂ��Ƃ��Đ��K�̑��`�`������������̂��Ȃ��B���Ȃ킿�A���n���{�̊C���ł���䂦��ł���B �@���߂Č����A�����ܗ֏��ʖ{�ɂ́A�傫�������āA���n�ƒ}�O�n�̓�n��������B������ɁA�ܗ֏������̏]���̈����́A�א�Ɩ{���͂��߂Ƃ�����n���{�𒆐S�Ƃ��������������Ȃ��Ƃ����Ό��ɂ������B�����ł́A���n�ƒ}�O�n�̓�n���������āA���ꂪ���{�I�ɂǂ��Ⴄ�̂��A�Ƃ������Ƃ����A�F������Ă��Ȃ������B �@�������ɁA�}�O�n�ܗ֏��́A���Ă͒��R���ɖ{�݂̂��m���Ă���A����������Ԃł́A�}�O�n�͗�O�I�Ȉٖ{�ɂ������A�����Ⴊ���������n���{�𒆐S�Ƃ��錩���ɌX�������ł������B���ہA���R���ɖ{�͐��̂����ɓ��炸�A�������ʂ�lj͂��������҂������Ȃ������B���R���ɖ{�����m���ʊ��ł́A�}�O�n�ܗ֏��̑��݂͂قƂ�ǖ�������Ă����̂ł���B �@����䂦�A�������V��ȗ��̌ܗ֏��̑��`�`�����m���Ă��Ȃ������B�ނ���A���n���{�̉����������K�̂��̂��ƍ��o����Ă����̂ł���B����������A�C���ł𐳋K�łƎ��Ⴆ�Ă����̂ł���B �@�}�O�n�ܗ֏��ł́A���̌�A�w�g�c�Ɠ`�^�x�i���a�\�Z�N�@���ɕ{�V���{���j�����Ɏʐ^���f�ڂ����Ȃǂ��āA���̏��݂��m��ꂽ�g�c�Ɩ{�ɂ��Ă��A���ۂɂ��̓��e���ǂ܂��悤�ɂȂ����̂́A���ꂩ���\�N�ȏ����̂��Ƃł������B �@�������A�g�c�Ɩ{�̌����͎�����F���ł���A��V���������ċg�c�Ɩ{�l���͌㐢�̎ʖ{�ł���A���̓��e�͒��R���ɖ{�Ƌߎ��������̂ł��邱�Ƃ����A�m���Ȃ������B�����āA�}�O��V���嗬�̗��ԕ��όn���̎ʖ{�́A���@����Ȃ��܂܂ł������B �@���ԕ��ς́w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A���ς��A���ԗE���ƋˎR�O�p�ւ́A�܊��̏������M�ŏ��ʂ��Ď����A���Ԏ�́i�����j�ւ́A���ς����A����^����ꂽ���ɉ����������ď������A�Ƃ���B�����������āA�Ƃ����̂́A���ς��痧�Ԏ�́i�����j�ւ̑��`�ؕ������������āA�Ƃ������Ƃł���B�Ƃ���A���\�\�Z�N�i1703�j�ɋg�c���A�����ԕ��ς֓`�������ܗ֏��́A���ێ��N�i1722�j�ɗ��Ԗ핺�q�����̎茳�֓n�����̂ł���B�������A���̌�̍s���͒ǔ��ł��Ȃ��B�悤����ɁA�������s���s���Ȃ̂ł���B �@�g�c�Ɩ{��V���ɂ́A�p�������������āA���ԑ������g�c�o�N�Ɏʂ��ė^�����������́A���ԕ��όn���̑��`�ؕ��W���t����Ă���B����䂦�A�g�c�Ɩ{�̒n���Ε��l���̈�������肪�c�����B���ԑ������땶�ɂ��A�����l�����A�g�c���A���g�c���N�֑������ܗ֏����ƌ��������A���邢�͗��Ԍn�̌ܗ֏����ƍ��o������������������A���ۂɂ͂����łȂ����Ƃ���ɔ��������B �@���ꂪ�ߔN�܂ł̌ܗ֏����߂��錤���ł������B�����Ȃ�A�g�c�Ɩ{�̓��e���m����悤�ɂȂ��Ē}�O�n�ʖ{�ւ̖ڂ��J����Ă��A����ȑO�̒��R���ɖ{�̓��e����F������Ă��Ȃ��ł����Ă݂�A�}�O�n�ܗ֏��̈ʒu�Â������Ȃ���Ă��Ȃ������̂ł���B����ȗL�l�ł́A���n���{�𒆐S�Ƃ��邻��܂ł̕Ό������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł���B �@������ɁA�ŋ߁A������\�N�̂��Ƃł��邪�A��X�͉z��ňٌn���̌ܗ֏����{�Ƒ������邱�Ƃ��ł����̂ł���B����͒n���W�ҏ����̋��͂ĉ\�ɂȂ����̂ł��邪�A�ȗ����x�̌��n�����ɂ��A�������鏔���Ƃ���ʂ����āA�ܗ֏����{�y�ѓ����W�j���@�ł����̂ł���B���̒����Ώۂɂ́A���łɉz��𗣂�Ă���M�B���̎q�����Ə����{���܂ށB �@���̉z��n���{�����A�܂��ɁA��X���T���Ă����}�O�̗��ԕ��όn���̌ܗ֏��ł������B�{���}�O�ł͖����@���������Ԍn�̌ܗ֏����A�܂������̉����A�z��Ɍ������Ă����̂ł���B �@���Ȃ킿�z��n���{�́A�ܑ㗧�ԕ��ρA�Z�㗧�ԑ����Ɠ`������A�����Ď���O�H�M�p�Ɏ����āA�z��֓`�������ܗ֏��́u�q���v�ł���B�}�O�̗��Ԍn�̌ܗ֏����z��ɑ��݂���Ƃ����̂́A���������R���ɂ��̂ł���B �@�z��n���{�ɂ��Ĉ�A�̔��@��Ƃ��i�ނ����ɁA���̌�A������\��N�H�ɂȂ��āA���ɒ}�O���Ԍn�̌ܗ֏����̂��̂ɑ������邱�Ƃ��ł����B����́A���e������ɁA��L�̒O�H�M�p���A�t�����ԑ�������`�����ꂽ�ܗ֏��̈ꕔ�ł������B����������A�}�O����z��֓`�d�������ԁ��z��n�̑c�{�̌������m�F�ł����̂ł���B �@�����ŁA���ԁ��z��n���{�̓��e�͂��Ă݂�ɁA�g�c�Ɩ{�⒆�R���ɖ{�Ƃ͈قȂ���̂�����A���҂̌�L����Ƃ�����A�z��n���{�ɐ��L������̂�����B����������A�z��n���{�́A�g�c�Ɩ{�l���⒆�R���ɖ{�Ƃ͌n�����قɂ���ʖ{�ƒm�ꂽ�B�z��n���{�ƑΏƂ���A�g�c�Ɩ{�l���ƒ��R���ɖ{�́A�ʌn���̂��̂ł���A���̎���̗ގ����痼�{�͈�̃O���[�v�Ɋ����̂ł���B �@�܂�A�g�c�Ɩ{��V���������āA�}�O�n���{�ɂ͓�n�������āA��͋g�c���A���痧�ԕ��ς֓`�������n���̎q���A������́A�g�c���A���瑁������ɓ`�������n���̎q���ł���B�O�҂́A�z��n���{�ł���A��҂��g�c�Ɩ{�l���ƒ��R���ɖ{�A��ˉƖ{�A�ɒO�Ɩ{���ł���B �@�������āA�]���ЂƐF�Ɍ��邵���Ȃ������}�O�n���{�̓��I�\���������������ƂŁA�ܗ֏��ʖ{�Q�̎��E���ς����B�ܗ֏����{�́A�܂��}�O�n�^���n�ɑ�ʂ���A�����Ē}�O�n�́A���̓��e���͂��瑁��n�Ɨ��ԁ��z��n�ɕ��ނł���B �@�����A���n���{�́A���Ƃ��ƊC���łł��邽�߂ɓ`�ʌo�H�͖��炩�ł͂Ȃ��B��������Ɩ{��א�Ɩ{�ɉ����������Ă��A����́A�`���̍ق̕��ꂽ���̂ŁA���`�����̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ��B�Ƃ���A���̎�����ʂɓ��e���͂���ȊO�ɁA���{�̎j���Ƃ��Ă̈ʒu�Â��͂ł��Ȃ��B�������āA������ꎚ���͂������ʁA�����������Ƃ�����B �@���Ȃ킿�A���n���{�́A��O���o�㑁���ɔ��������ʖ{�����c�Ƃ��āA�ȉ����n���ɔh�������ʖ{�̖���ł���B���̂����A�x�i�Ɩ{��~�����n���{�́A�����ɔh���������̂ł���A���̌�̓`�ʉ����������ƌ����āA�ʂ����ꂪ�傫���B���������ʁA�����ɔh�������n���̎q���䂦�A���̑����`�Ԃ̍��Ղ�f�ГI�Ɉ₵�Ă���B �@����ɑ��A�������n�ł��A��Ɩ{�E�א�Ɩ{�E�ۉ��Ɩ{�́A���̌�L�E���̏l�Ԃ�����ɁA���ɔ䂵�ėގ��_�������A�߉����̂�����̂ł���B�����Ă��̎O�{�̂����A����ɋ߉����̂���̂��A��Ɩ{�E�א�Ɩ{�ł���B���������āA���̓�{�̌n���h���́A�ۉ��Ɩ{���h��������̂��Ƃł���B �@�܂��A�]���m���Ă��Ȃ��������Ƃ����A�R�{����������Ƃ���א�Ɩ{�Ɠ��n���̎ʖ{�ɁA�핐���{������B����͖����̎ʖ{�ŁA���ꂶ�����V�����ʖ{�ł��邪�A�א�Ɩ{���ʂ������̂ł͂Ȃ��B����A�א�Ɩ{�����c�{����h�������ʌn���̎ʖ{�ł���B�������A����̉^�p�ɂ����āA�א�Ɩ{������Ɩ{�ɋ߂��P�[�X������B �@���̏핐���{�Ƃ̏ƍ��ɂ�蔻������̂́A�ЂƂɂ́A�핐���{�ƍא�Ɩ{�����L����c�{�̑��݂ł���B������́A�א�Ɩ{������Ȏ�����^�p���Ă��邱�Ƃł���B�א�Ɩ{�͂��̑c�{���ʂ����̂����A�M�ʎ҂͎��ܒE�����āA���̎ʖ{�ɂ͂Ȃ����قȕ�����p���Ďʂ��Ă���B����������A�א�Ɩ{�̍쐬�҂́A���̑c�{�ɂ��܂蒉���ł͂Ȃ������悤�ł���B �@���̌n�������ߒ��ɂ����āA��Ɩ{��א�Ɩ{�́A���ꂼ��ʂ̉�����t�������ҏW����c�{�Ƃ�����̂ł���B�����������ɂ��A�㐢�̖�O�҂̍�ׂ䂦�A���̉����͌��^�𗯂߂Ȃ��܂łɌ`���̍ق̕��ꂽ���̂ł���B������ʂ�����Ɩ{��א�Ɩ{�́A���̌`���̕�������̂܂p���ł���B �@�������A���n���{�̒��ł́A��Ɩ{�E�א�Ɩ{�A�����Ċۉ��Ɩ{�́A��r�I�ʂ�����̏��Ȃ��ʖ{�ł���B���Ƃ��A���̂��Ƃ��m���̂́A�}�O�n���{�Ƃ̉��f�I�ƍ��ɂ���Ăł���B�����炭�A���̎O�{�́A���n�嗬�ɂ����Ĕh���`�ʂ��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ�����B �@�������A����ɂ��Ă��A�㔭�I�Ȍ�L�𑽐��܂ނ��Ƃ��炷��A�����ČÂ��ʖ{�Ƃ͌����Ȃ��B����̐��m�x�͎ʖ{�̌Â��Ƃ͕K���������ւ��Ȃ��B�ނ��낱�̎O�{�ɓ��L�̌�L�̗l�Ԃ�����A���̔����͑����̂��̂ł͂Ȃ��A�㔭�����������̂ł���B���̓_�A�]���̌�����j���]���͉��߂�ׂ��ł���B �@�ȏ�̏��_�́A����܂ł̌ܗ֏������ł͌��o���ꂽ���Ƃ̂Ȃ����Ƃ���ł���B����䂦�A�͂��߂Č��m�����Ƃ����ǎ҂������낤�B�悤����ɁA�ܗ֏������̍őO���Ɋւ�邱�Ƃ���ł���B |
|
�@�����ܗ֏��ʖ{�ɂ����āA�\�����I���̕����ƔF�߂���̂́A�}�O�n�̋g�c�Ɩ{��V���i���N�E1680�j�݂̂ł���B���̋g�c�Ɩ{�ɂ��Ă��A���̎l���͏\�����I�̂��̂ł���B�܂��A���n���{�́A�����������\�����I��k����̂��Ȃ��B���悤�Ȏ���Ȃ̂ŁA�����j���ɂ́A�����̑��e���{�ǂ��납�A�������V�傪��l�ɓ`�����������Ŏʖ{���������݂��Ȃ��B �@���������āA�ܗ֏��̌��^�֑k�s���邽�߂ɂ́A���ڂ̃A�v���[�`�͂ł��Ȃ��B�����ŁA�����ʖ{���肪����ɂ��āA�܂��́A�������V��̒i�K�܂ők�邱�Ƃ����ł���B �@���̂��߂ɂ́A�ԃe�N�X�g�I���́iinter-textual analysis�j���K�v�ł���B���Ȃ킿�A�}�O�n�^���n���{�����f���čZ�ق���肵�A���̈ꎚ��匟�����A�Ì^�����͏o����Ƃ����葱���ޕK�v������B �@��X�͂��̓lj������ɂ����āA���������ԃe�N�X�g�I�ȕ��͎葱����ł���B����ɂ́A��̓I�Ɍ����A�������̃p�^�[��������B������ȉ��ɂ܂Ƃ߂Ă����B �@�i�}�O�n�^���n���{���ʂ̃P�[�X�j �@��́A�}�O�n�^���n�����f���ď��{���ʂ̌��B����͏��Ȃ��Ƃ��A�������V��i�K�ɑk��Ì^�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B �@���̃P�[�X�ɂ͓�p�^�[��������B��͑S�ʓI�ɋ��ʂ�������B����͕���Ȃ��A��{�I�ɌÌ^�ł���B�܂莛�����V��̒i�K�ɂ��łɂ��������ł���B���ꂪ�قƂ�ǂ̃P�[�X�ł���B �@�������A���̂������ׂĂ����������ƌ����A�K�����������ł͂Ȃ��B��X�̓lj��������͂��߂Đ͏o�����悤�ɁA���炩�Ɏ������V��̌�ʌ�L�Ƃ݂Ȃ���������ꕔ�ɂ���B �@���Ƃ��A���̑�\�I�Ȏ����������A�ΔV���́u�܂���Ɖ]���v�ł���B���́u�܂���v�́u�Ԑ�v�̂��ƂŁA�����́u�܂���v�Ə������̂����A�������V��͂����������āA�u�܂���T�v�i����T�j�ƌ�L�����̂ł���B �@�������āA�����ł������������ƂȂ̂ŁA�Ȍ�̌ܗ֏��͂��ׂāu�܂���T�v�Ə����悤�ɂȂ��āA���̖��Ⴝ���ł��錻���ʖ{�ɂ́A���ׂāu�܂���T�v�i����T�j�ƋL���Ă���B �@���̃P�[�X�ł́A��X�́A�����ʖ{�̉���ɂ��Ȃ����ɂ���āA�����̑��e�ɂ������������邱�ƂɂȂ����B����Ɠ����ɁA����������L�̐͏o�ɂ���āA�͂��Ȃ����A�������V�傪�ܗ֏��̓��e�����ׂĒm�����Ă����킯�ł͂Ȃ����Ƃ����������̂ł���B �@���ɁA�}�O�n�^���n�����f���ď��{���ʂ̂����́A������̃p�^�[���́A�����I�ɋ��ʂ�������ł���B���Ƃ��A�}�O�n���{�ŁA���ԁ��z��n�Ƒ���n�ɂ����đ��ق�����Ƃ��A����͔��n���{�Əƍ����Ă݂āA�����ɋ��ʂ����傪����A���ꂪ�������B�܂��A���n���{�ԂŌ��ɑ��ق̂�������A�}�O�n�Ɠ������ł�������������B�����Ȃ�A�ꕔ��O�͂�����̂́A�}�O�n�^���n�����f���đ��݂����傪�A��{�I�ɌÌ^�Ȃ̂ł���B �@���̃P�[�X�ł́A�����[�����ʂ�������B �@���Ƃ��A���n�̒��ł��x�i�Ɩ{��~�����n���{�͎ʂ����ꂪ�傫���A�]���A�j���]�����Ⴍ���ς��Ă����B��Ɩ{��א�Ɩ{�ƌ�傪�قȂ�����A�������̂͂�����ŁA�x�i�Ɩ{��~�����n���{�̌��́A���ƌ��Ȃ���Ă����̂ł���B �@������ɁA�@��̕]�������ł́A�K��������Ɩ{��א�Ɩ{���������̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�S�ʂɎʂ�����̑����x�i�Ɩ{��~�����n���{�ł����Ă��A���̌�傪����������������B �@���Ƃ��Βn�V���u���@�̓��Ƃ��ӎ��v�́A�E�f�́u�p���Ă炵�v�̏ꍇ�A�}�O�n�^���n�����f���ċ��ʂ���̂́A���n�ł͕x�i�Ɩ{�ł���B��Ɩ{�E�א�Ɩ{�E�ۉ��Ɩ{�͂��ꂼ��܂��܂��ł���B���������P�[�X�ł́A���n���{�݂̂����Ă��Ă͔��f�����Ȃ��B�E�f����ł͋g�c�Ɩ{�E�n�ӉƖ{�E�Έ�Ɩ{�Ȃǒ}�O���z��n���{�Əƍ����āA�x�i�Ɩ{���������ƒm���B�����āA��Ɩ{�E�א�Ɩ{�E�ۉ��Ɩ{�͂��ꂼ�ꂪ��L�ł���B �@���̃P�[�X�̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂́A�x�i�Ɩ{��~�����n���{�Ȃǔh���n���̎ʖ{�́A���n�̂Ȃ��ł������ɔh�������n���̖��Ⴞ����ł���B�܂�A�����ɔh�������n���ɌÌ^�̍��Ղ��c�����Ƃ����P�[�X������ł���B���������āA�S�ʂɎʂ�����̑����x�i�Ɩ{��~�����n���{�ł����Ă��A�K�����������͂ł��Ȃ��̂ł���B �@�����������Ƃ́A�������A���n���{�݂̂����Ă��Ă͕���Ȃ����Ƃł���B�}�O�n�ɂ܂ʼnz�����Ă͂��߂āA�������邱�Ƃł���B�������A���������}�O�n�^���n�����f����ƍ��ɂ���āA���n���{�̎j���]�����\�ɂȂ�̂ł���B |
 �g�c�Ɩ{�@��V�� �ĔC���遨�g�c���A ���`�ؕ� 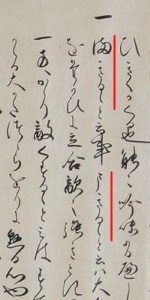 �g�c�Ɩ{�@�u�܂���T�v
�i�}�O�n�^���n�����f���ċ��ʁj |
|
�@�i�}�O�n�^���n�Ԃɑ��ق̂���P�[�X�j �@���āA��ڂ́A�}�O�n�^���n�ɂ����Č��ɈႢ������P�[�X�B�Ƃ��ɁA�}�O�n���{�ɋ��ʂ����傪����A�����āA����Ƃ͈قȂ��傪�A���n���{�ɂ͋��ʂ��đ��݂���ꍇ�ł���B�܂�A�}�O�n�^���n��B�R�Ƃ��ċ敪����w�W�I���قł���B �@���̃P�[�X�ł́A�}�O�n���{�ɋ��ʂ��邱�Ƃ��|�C���g�ł���B���Ȃ킿�A�}�O�n�ɋ��ʂ���Ƃ́A���ԁ��z��n�Ƒ���n�Ƃ������n���ɂ킽���ċ��ʂ���Ƃ������Ƃł���A����͒}�O�n�̏����`�Ԃ��������̂ł���B�������A����͎������V�傪�ĔC����ɓ`�������ܗ֏��ɂ��������ł���\���������B�܂�A�����N�ԁA�������V��O���̂������ł���B����䂦�A�}�O�n���{�ɋ��ʂ��邱�̃P�[�X�ł́A���̌��ɏ����̌`�Ԃ�������Ă���Ƃ݂Ȃ�����B �@���Ƃ��A���̃P�[�X�̑�\�I�Ȏ���́A��V�������̎���̗L���ł��낤�B���n���{�ɂ́A���m�́s��L�P�����A�q�җL��A���җL��A���җL��A�S�ҋ��t�Ƃ������ꂪ����̂����A�}�O�n���{�ɂ́A���ꂪ�Ȃ��B���̎����́A�ܗ֏������ɂ����ď]���ʼn߂���Ă����̂����A�{�T�C�g�̓lj������ł͂��߂Ďw�E���Ȃ��ꂽ���_�ł���B �@���̎���̗L���ɂ��ẮA�������A�}�O�n���{�ɒE��������̂ł͂Ȃ��B�}�O�n���{�ɂ��ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��A�������V��O���ɂ́A���̎��ꂪ�Ȃ������̂ł���B����������A����ɂ����ɂȂ��Ĕ����������ł���A�������e�ɂ͑��݂��Ȃ������A�ƌ��_��������Ƃ���ł���B �@���̎���ɂ����炸�A�}�O�n�^���n�̊Ԃő��ق�����͑����B���̂����A���n���{�ɋ��ʂ�����ɂ́A��̉\��������B �@���Ȃ킿�A��ɂ́A���ꂪ�������V��O���ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���Ƃ��Ί����N�Ԃ̎������V�����ɗR������\���ł���B���̂����A�����͂��̑O���Ƃ͈قȂ�����L�������ƂɂȂ�B��������肻���Ȃ��Ƃł���B���̎������V�����̌��\���́A�}�O�n���{�̊֒m������Ƃ���ł���A����䂦�A�}�O�n�͌Â��ق��̌���`�����̂ł���B�������A�ʂɍZ�ق���A���n�ʖ{���������V�����̂������������Ƃ������̃P�[�X�͏��Ȃ��B �@�����āA���̉\���́A���n���ʂ̌�傪�A�������V��̒i�K�ɂ܂ők��Ȃ��Ƃ����\���ł���B�܂�A���n���{�ɋ��ʂ��邱�Ƃ���A���n�����ɂ��ꂪ���łɂ������Ƃ݂Ȃ�������̂́A����͎������V��i�K�̂��̂ł͂Ȃ��A����Ȍ�̖�O���o��ɔ��������ٕς��`�d�����P�[�X�ł���B���ꂼ��̍Z�َ���ɂ��Čʂɕ��͂���A���̃P�[�X�������B �@�ȏ�̂悤�ɁA�}�O�n�^���n��B�R�Ƃ��ċ敪����w�W�I���ق̂���P�[�X�ł́A���n���{�̌��́A�}�O�n���{���ʂ̌��ɑ��āA�I�Ȉʒu�ɂ���B���Ƃ��������V��i�K�ɋA������Ƃ��Ă��A����͑��V�����̌��ł����āA���V��O���̏����`�Ԃ������}�O�n�̌��ɔ䂷��A�v���C�I���e�B�������̂ł͂Ȃ��B���������āA���̃P�[�X�ł́A����ɂ��Ă��A�}�O�n���{���ʂ̌����Ì^�Ƃ��č̂�ׂ��ł���B �@��{�I�Ɉȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��A���{�Z�قɊւ����X�̊ԃe�N�X�g�I���͂̎葱���ł���B���̂����A�}�O�n�^���n�ɑ�ʂ���鏔�{���A�L�����f���Ĕ�r�ƍ����邱�Ƃ��A�����d�v�ł���B���̌��ʁA�]���̌ܗ֏������̃��x���͑啝�ɑO�i�����B���̍őO���ɂ����鐬�ʂ́A�ȉ��̌ܗ֏��lj������Ɏ�����Ă���B �@���̓lj������ł́A�ł��邩����L�͂ɏ��{���Z�����邱�ƂɂƂ߂��B�Q�Ƃ����ܗ֏��ʖ{�́A�E�f�̒}�O�n�\�Z�{��\����A���n�\�{�A�����Ĉ�{�́A�v��\���{�O�\����ł���B�����ܗ֏����ʖ{�̓��e�y�шʒu�Â��Ɋւ��ẮA�ʌf�u�ܗ֏��ٖ{�W�v�ɉ�������邩��A������Q�Ƃ��ꂽ���B �@���߂Ă��肩�����A�I���W�i�������������ʖ{�������݂��Ȃ��Ƃ��Ă��A���{���L�������Ĕ�r�ΏƂ��A��茴�^�ɋ߂�����������o���A�ܗ֏��̕��������݂�K�v������B���ꂪ�A�ȉ��ɒ��ēǂށA�ܗ֏�������Ōܗ֏��e�N�X�g�ł���B �@���̌ܗ֏�������Ńe�N�X�g�́A���������āA�����ɂ͎��݂��Ȃ����A����͂���A�sthe possible original�t�ł���A�sthe supposed original�t�ł���B�M�߂����Ȃ������ʖ{�Ɉˋ����ēǂނ��́A�����̌��ʁA����I�ɕ����������������e�N�X�g�ɋ����ēǂޕ����A�lj��̂��߂ɂ͂Ȃ낤�B���Ȃ킿�A�e�N�X�g�͓lj��ɐ�݂���̂ł͂Ȃ��A�lj��ɂ���Đ��Y�����̂ł���B���̋t���̎��H�����A�܂��ɉ�X�̍�Ƃł������B �@�������āA��X�̃e�N�X�g�lj��̎��H�́A�ܗ֏����ʖ{�̉��f�ɂ�蓾���e�N�X�g�̍č\���ƂȂ��Č��������B���������āA���ݗ��z���Ă��郔�@�[�W�����ȊO�̌ܗ֏��e�N�X�g��ǂ݂����Ƃ��������ɂ́A���̉�X�̃e�N�X�g���Q�l�ɂȂ낤�B �@�����ł͉�X�̍\�����������ܗ֏��e�N�X�g����A���킹�āA���{�̍Z�ق�K�X���邱�Ƃɂ���B����ɂ���ĉ�X�̃e�N�X�g�̃A�h���@���e�[�W�����Ƃ����ł��낤�B |
 ��Ɩ{�@��V������ �ꂠ��  �g�c�Ɩ{�@��V������ ��Ȃ�
*�y�Q�ƌܗ֏����{�z |
 ��V�ꗬ���@�O�\�܉Ӟ� �����M�s�ܖ@�Z�j���� ��������g�͎O�\�ブ���  �g�c�Ɩ{�ܗ֏��@�n�V�ɖ`��
*�y�����`�z
�s���i�\���N�m�h���n�������m���j�˃e�A�n�e���@�m���O�\��ӏ����^�V�e���V�t *�y��V�L�z �s���i�\���N�j���L�e�A�����e���@�m���O�\�܃P���m�S�����^�V�e���ド���B�����O���\�����A������������i���B��Ό\�l�B��@�j�����@�a�i�_�@�ޑ勏�m�t 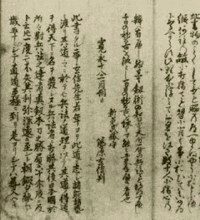 �O�\��ӏ@���@���� ���i�\���N����̓��t
*�y�������n�������z
�s�����^�����A���M�搶�A��N���������j�u�V�A���\���Y�j�n���A�����X�j�I�q�e���A���@�m�������ȃe�����m���A�������A�V���j����ᢃX�����@�҃j�ŏ��`�A������{�������X�A�����@�V�B�ҁA�����ؓ��m�����Z�\�]�x�j�y�g�]���A��x���s�������B��[���j�������g�A���b�[���V�e�A�Ό\�j�V�e���ʎ��Ƀj�����A�������V�e�n�q���x�L�����i�N���A�������B�����}�f�n���@�m���^�������s�����B��䢁A�O�����V�������ђ������A��������ʃt�́A�����m���@�m�ÃV�ʃq�e�A����V�����o�m���փA�����p�m���@�A�����A�n��ꗬ�m���`���Ƀ������A�����N�n�����j�N�J�@�N�҃A�����g���^�V�ʃq�A�搶�k�����l�g�����N���x�����R�j�A��x�����i�V�B��䢏��e���e�A���@���搶�j�q�ʃt�B�搶�m�H�A���@�m�S�A�����m���j�����Y�A�����m���n�A��i�X���j笃n�U���o�A�������B���H�A��s�q�i���g�]���A�������B��Z���g�B��䢁A���e��������A����o�A���j���@�m�������B���K�j���@�m�q�݃j�����A�����j�����ʒB�V�A���N�������p�j�u�V�A���������~�b���Z�V���A��c�����m���j�A���Y�B���N�m�C�s�A���j�s�V�A���g�X���ƃg�A���W�x�r�ʃt���s�t |
�@��X�̌ܗ֏��lj��́A���̕����̌��e�N�X�g������ڎw���Ƃ���ł��邪�A����ɂƂ��Ȃ��A���ɂ�����u���@�O�\�܉ӏ��v�Ȃ镶���ɂ��Ă��A�j���ᔻ�����{���邱�ƂɂȂ������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B����͖{�T�C�g�̑����Ō����Ȃ���Ă���Ƃ���ł��邩��A�����ł͌J��Ԃ��Ȃ����A�������A�ȉ��̓_�����w�E���Ă����B �@���i�\���N�i1641�j�̓��t��L����A���̎O�\�܉ӏ@���́A�ܗ֏��ɐ旧�����̒���ł���A�ܗ֏��̌��^�Ƃ���Ă����B���邢�́A��������A���@�O�\�܉ӏ��͕s���S�Ȍܗ֏��ł���A�ܗ֏��͕��@�O�\�܉ӏ����甭�W�������⊮�S�łł���Ƃ����A����܂�������������悤�ɂȂ����B�܂�A �@�@�@�@���@�O�\�܉ӏ��@���@�ܗ֏� �@���@�O�\�܉ӏ��ƌܗ֏��̊Ԃɂ́A����A���������u�i���_�v�I�v���Z�X��z�肷��̂��A����܂ł̌ܗ֏������́u�펯�v�ł������B�������A�����܂ł��Ȃ��A����͎j���ᔻ�����̃i�C�[���ȍl���ł���B��X�̏����ł́A����͋p�����ׂ��T���ł���B���@�O�\�܉ӏ��A���邢�͎O�\��ӏ��ł��悢���A���̗ނ��̕��@�����A�����������Ă����Ƃ����؋��͂Ȃ��B����̂́A�㐢���ɂ����ē`���������������݂̂ł���B �@���̂����A�}�O�n��V���ɂ́A�ܗ֏��ɐ旧�����������@���Ɋւ��錾���`���͂Ȃ��B�Ƃ���A�O�\��i�܁j�ӏ@���Ƃ́A��ネ�[�J���ȁA�㐢�̎Y���ł���B �@�������V��̒�q�ł���O��ĔC����́A�N��炵�āA���F�{�Ő��O�̕������̐l��������������ł���A��������������N�Ԃ܂Ŕ��ɂ��āA�������V��Ɏt�������B����A�����ӔN�̂��Ƃ�m���Ă���l���ł���B�}�O��V���ɁA�ܗ֏��Ƃ͕ʂ̕��@���̌����`�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́A���̕��@���͎ĔC���������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��㕨�Ȃ̂ł���B �@�������A�O�̓��������ƂɁA���̌㐢�����ɂ��́A���ꂪ���i�\���N�ɕ������א쒉���Ɍ��サ���������Ƃ������Ƃł���B�����A����ȓ��L���ׂ����ւ��������Ƃ���A�Ȃ�����A�ĔC���邪����������`���Ă���͂��ł���B�Ƃ��낪�A�d�B���ŎĔC�ɒ��ږʉ�Ęb�������ԕ��ς́A����Ȃ��Ƃ��ꌾ�������Ă��Ȃ��B�ĔC���炻��Șb�͂Ȃ������̂ł���B �@�ĔC���邪�m��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�悤����ɁA�ĔC�����ɋ��������N�Ԃ܂ŁA����ȏ����͔��ɂ͑��݂��Ȃ������̂ł���B�܂�A�O�\��ӏ��ł���O�\�܉ӏ��ł���A�������ܗ֏��ȑO�ɏ������Ƃ������@���́A���Ȃ��Ƃ��A�����N�ԈȌ�ɁA���ŏo�����������Ȃ̂ł���B�������āA����͂ނ������̂��Ƃ�����A�����̊֒m���Ȃ������ł���B�܂�́A��N�ɂȂ��ĕ����ɉ������ꂽ�U���Ȃ̂ł���B �@�ĔC���邪������������ɏo�����������ł����Ă݂�A�ĔC�������m��Ȃ��͓̂��R�ł���B�����Ă܂��A�}�O��V���ɂ���ȏ����Ɋւ������`�����Ȃ��̂��A��������R�ł���B���̂悤�ɔ��Ŏ���ɔ����������[�J���ȕ����ł��邱�Ƃ���A��X�͂�����u��㕺�@���v�ƌĂ�ł���B �@�����́A�ܗ֏��ȑO�ɁA�u�����v�Ƃ��Ă̕��@�������������Ƃ͂Ȃ������B�Ƃ����̂��A�������Ɍܗ֏��ɕ������g���ĎO�q�ׂĂ��邱�Ƃ����A���������@�_�������ɂ��ď����̂́A�ܗ֏����ŏ����Ƃ����̂ł���B
�s���@�̓��A��V�ꗬ�ƍ����A���N�b���V���A�n�ď����Ɍ������Ǝv�ӁB�����i��\�N�\����{�̔�t�i�n�V���E�����j
�@�����ŕ����́A���g�̕��@���_�������ɂ����̂́A���ꂪ�ŏ��ł���Ɩ������Ă���B�����炭�A����܂ł͌����ł̋��������������낤�B����Ȃ��v�z�Ƃ́A�ߑ���E�q�Ȃǂ��̗�͑����B���ꂪ���m�I�`���ł���B�s�E�A�ꗬ�̕��@�̓��A�i�����j�����ꕪ�̕��@�Ƃ��Đ��əB�鏊�A�n�ď��������A�n���Ε���A����܊��Ȃ�t�i�n�V���E�㏑�j �s�E�A���t�鏊�A�ꗬ���p�̏�ɂ��āA���ւ��v�Ђ�鎖�̂݁A�������u���̖�B���n�č������L�����̂Ȃ�A�Ր�Ə�����T�S����āA���܂₩�ɂ́A���Ђ킯�������t�i�ΔV���E�㏑�j �@�����ɂ��Ă��A�ܗ֏��ȑO�́A�����������@�_�u�`�͂������̂́A����͏����ꂴ�鋳���iunwritten teachings�j�ł������B�����͂��̂悤�ȃX�^�C���Œʂ��Ă������A����O�ɂ��āA���i��\�N�\���ɁA���@�_���u�����v�Ƃ��Ď��M���n�߂��B���ꂪ���߂Ă̕��@�_���삾�Ɩ������Ă���̂ł���B �@�������āA�������ܗ֏��ɁA��x�Ȃ炸�ĎO�ɂ킽���āA���@�_�������ɏ����͎̂n�߂Ă��Ə����Ă��邱�Ƃ��A�����ʼn��߂Ċm�F���ׂ��ł���B �@������ɁA����܂ŁA���̌ܗ֏��̕�������������Ă����̂ł���B�������āA�ܗ֏��ȑO�ɁA���@����������Ă����Ƃ����ϐ����������ċv�����B�܂��Ɋ�����ɂȌ��ۂł���B����́w�����`�x�ȂǏ\�����I�̔��n�����`�L�ɂ��łɌ���Ă���B���������́A�����ł����̓`�����L�ۂ݂ɂ���҂��������Ƃł���B �@�ܗ֏��͕����̒��q�ł���A���͍����u���Ă��A�������ւ̈ꎟ�j���ł���B�،��Ƃ��āA����ȏ�̂��̂͑��ɂ͂Ȃ��B���������āA���̌ܗ֏��ɁA��x�Ȃ炸�A�ĎO�ɂ킽���āA���@�_�������ɏ����̂͏��߂Ă��Ə�����Ă���ȏ�A���̌ܗ֏��ȑO�ɂ́A�����Ƃ��Ă̕��@���́A�����ɂ͑��݂��Ȃ��̂ł���B �@�Ƃ���A�ܗ֏��ȑO�ɏ�����A�������א쒉���Ɍ��悳�ꂽ�Ƃ������@���ȂǁA�����������݂��Ȃ��̂ł���B��������o�����̂͌㐢�̍�ׂł���`���ł���B �@���n�����`�L�w�����`�x�͎O�\��ӏ��Ƃ����A��p�́w��V�L�x�͎O�\�܉ӏ��Ƃ��邩��A�ނ��A�O�\�܉ӏ����O�\��ӏ�ł̕�����ɂ������B�������A���̗R�������`��������āA�o�������m�łȂ��B�������n�����ɂ���L�ɂ��A���n���͕�������l�����I���o���āA����𐢊ԂɎ����o���Ă����̂ł���A���̊����N�ԈȑO�ɂ͑k�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ȃ̂ł���B �@���̕��@���́A�������n���n���̒��Ŕ������������ł���B����͍ŏ��A�ܗ֏����V���ƉΔV���𒆐S�Ƃ��Ă��̓��e��E�v�������̂ł��������낤�B�Ȃ��ܗ֏��ۂ��Ƃł͂Ȃ��A���������E�v�����ł��������Ƃ����A���̋��n���n���͌ܗ֏����`�Ƃ͖����Ȍn�����������炾�B���n���͌Z���V�傩��A�ܗ֏���`������Ȃ������̂ł���B �@�������A�����A�ܗ֏��̈ꕔ��E�v�������̂ł��������A���ꂪ���������ɂ�āA���̕�������t�����ɉ��������悤�ɂȂ����̂ł���B����ɂ͎������n���n���́u�K�v�v���������B�Ƃ����̂��A���V��̌n���͌ܗ֏��𑊓`�c�[���Ƃ��Ă������A���n���n���ɂ́A���V��n���̌ܗ֏��ɑ�������悤�ȍ����������Ȃ������B �@�Ƃ��낪�A���n���̎q�⑷�̐���ɂȂ�ƁA���n���n������㕐�����̎嗬�ɂȂ����B������ɁA�̐S�̑��`�c�[���Ƃ��Ă̕������Ȃ��B�����ŁA�ܗ֏��ɑR���邩�����Ŕ��������̂��A�������������Ƃ������̉��������ł���B �@�������A����͑��V��n���̌ܗ֏��ɑ��A�����艿�l�̏�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�ܗ֏�����ɏ����ꂽ�����Ƃ����ݒ�ɂ����B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�������א쒉���Ɍ��悵���Ƃ������ЂÂ��������B���ꂪ�A���������̑O���A���i�\���N�Ƃ������t�ł���B�ܗ֏����M�ɐ旧���A�܂��ܗ֏��̌��^�ƂȂ镺�@���Ƃ������̂��A�������ďo���オ�����̂ł���B���ꂪ�A�O�\��ӏ@���A��X�̂����u��㕺�@���v�ł���B �@���̌�A���n���n���͔�㕐�����嗬�Ƃ��ď��h�ɔh������Ɏ���̂����A���̕����ɓY�t���ꂽ�R�������������Ď��h�̗R���Ƃ���_�ł͋��ʂ��Ă����B���c�E�������n���́A����V��̌ܗ֏��Ɠ������ɕ�������`�����ꂽ�B�������A���̕����͌ܗ֏��ɐ旧���A����ȑO�ɍא쒉���ɕ��������悵�����̂ł���B����قǂ̕����ł��邪�䂦�ɏd�v�ȍ��������ł���B��㕺�@���́A�ܗ֏��ȏ�̉��l�^�����悤�ɂȂ����B �@����䂦�A�ܗ֏��͓�̎��̕����A����ΎQ�l�����̈ʒu�ɗ����A�܂����̂悤�Ȏ����Ƃ��ē`�ʂ��ꂽ�B���̂����A���n�ܗ֏��ʖ{�ɂ͎������V��Ƃ������������������̂������ꂽ�B���V��̖��������̂́A���Ƃ�苁�n���𐳓��Ɛݒ肷��㐢�̓}�h�I���@�ł���B�������āA�������e��ҏW�������̐l�������A�Y�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�\�\�Ƃ�����A���n�ܗ֏��̔w�i�͂��̂悤�Ȃ��̂ł���B �@�������āA��㕺�@���́A�������n���嗬�Ŕ��������Ƃ���́A�����ɉ������ꂽ�U���ł���B�������A������邽�߂Ɍ����Ă����ׂ����Ƃ�����B �@��㕺�@���͕����ɂ͖����̌㐢�̍앨���Ƃ͂����A���̓��e�́A���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��ƌܗ֏��̉��߂��甭�������̂ł����āA��������̔��̖嗬�̍l�������������ł���B���̌���ɂ����āA����͌ܗ֏��̉��߂ɂƂ��ďd�v�Ȏj���ƈ����ׂ��A�����Đ��}���ȉ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ�A�����̒��q�Ƃ����̍قɂ��Ă��܂�������A���ꂪ�U���ƂȂ��������ŁA���̓_�������́A���̕������A�������n���嗬�j���Ƃ��ďd�v�Ȉʒu���߂���̂ł���B �@���́A�㐢�̍����ɂ���B��㕺�@���ɂ܂��`�����L�ۂ݂ɂ��A�܂��O�\��ӏ��ł���O�\�܉ӏ��ł���A���̌㐢�����ɉ������ꂽ���̕����̉������A�i�C�[���ɂ��M����Ƃ����A�����Ȃ����͂�����Ȃ��T��������B���̈���ŁA�ܗ֏��ɂ���قǂ܂łɖ������Ă��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��B�ܗ֏��ȑO�ɕ��@���Ȃ��A�\�\���̐^���͖����ł���ɂ��ւ�炸�A���̂�̐�����ɋC�Â����֖������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������������҂���������̂ł���B �@�܂��ɁA�ܗ֏��̊̐S�ȕ����́A���܂��ɓǂ܂�Ă��Ȃ������R�Ȃ̂ł���B���������āA�����ŋ������ׂ��́A�\�\�����͌ܗ֏��ȑO�ɂ͏����Ƃ��Ă̕��@�������������Ƃ͂Ȃ������B�ܗ֏������A�������ŏ��ɂ��čŌ�����@���ł������A�Ƃ������Ƃł���B |
|
�@�ܗ֏������܂�ɂ��L���Ȃ̂ŁA���������@�����������Ƃ������Ƃɂ��āA���̋������Ȃ��̂������ł���B�������A�ق�Ƃ��́A���������@�����������Ƃ������Ƃɋ����ׂ��Ȃ̂ł���B �@�Ƃ����̂��A���������������@�����������Ƃ������Ƃ́A�����H�������B���@�_����̂��铯����̐l�Ƃ��ẮA�w���@�Ɠ`���x�������������@���A���̑��q�A�w���V���x�̒��ҁE�����O���Ȃǂ����邪�A�����������O�I�Ȏ����ł��邱�Ƃ͂������ł���B����ł���Ƃ��Ȃ��قǂ̎҂Ȃ璘�q����������Ǝv���͍̂��o�ł���B�����������ɂ��Ďc���ȂǁA�����܂�������O�I�Ȃ��Ƃł���B���̂��ƂɎv����v���ׂ��ł���B �@�Ƃ�킯�A���ł���|�p�ɂ́A�s�������̌��`���s�������āA��̓I�Ȃ��Ƃ͕����ɏ����Ȃ��B���`�ژ^�ɂ͏p���Ɩ������݂̂ł���B �@���m�I�`���ł́A���q�Ȃ��t���͑����B����Ƃ͕ʂɖ��̕����Ƃ����������������āA�@���䕷�A�q�H���A�̃X�^�C���̕����ł���B���������̗�ŁA���@���_�����Ō�苳���A���̓��e�������́u�啪�ꕪ�v�̕��@�Ƃ��Đ��ɒm���Ă������A�����q����Ƃ������Ƃ܂ł͍l���Ȃ������B �@����A�Ȃ������Ɏ����āA�����͕��@���������C�ɂȂ����̂��B����ɂ́A���̓�̓_�������A�p�͑����ł��낤�B�\�\���Ȃ킿�A��͐V�������q�X�^�C�����������ƁA������́A�⏑���c�����Ƃł���B �@����������܂ŕ��@���������Ȃ������̂́A�����̒ʗ�A�s�������̌��`���s�ɂ����������ɂ����Ȃ����A�����A���@���������A���`��`���̊i�D�ɂȂ��Ă��܂��̂��������̂ł���B �@���������������`��`���A�����h�œ`������Ă��镶���ł���B�������܂��A�����@��́w���@�Ɠ`���x�̂悤�ȐV�����X�^�C���̉��`��`�����A�����̌����Ƃ���ł��������낤�B �@�����͕��V���ɁA����߂����Ă��������Ă���B�\�\���@�̎��ɂ����āA�ǂ���u�\�v�Ɖ]���A�ǂ���u���v�Ƃ����̂��B�|�\�ɂ���ẮA�����邲�ƂɁA�u�ɈӔ�`�v�ȂǂƂ����āA���Ɠ����͂��邯��ǂ��A�G�Ƒō����Ƃ��̗��k�킢���l�ɂ����ẮA�u�\�v�ɂ���Đ킢�A�u���v�������Đ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ƁB �@���ǁA�����������Ƃ��Ă̕��@���������Ȃ������̂́A���`��`���̖����e��m���Ă�������ł���B���`�Ƃ͂����q�˂Ă݂�A�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�邷�ׂ����Ƃɂ��炴�����̂�閧�ɂ��邱�Ƃɂ���āA���������鉜�̂���悤�Ɍ���������d�g�݂ł���B �@���邢�́A�����@��́w���@�Ɠ`���x�̂悤�ȐV�����X�^�C���ł́A�T�ƈ����̒ʑ��I�S�@�_�������Ĕ鉜�Ƃ���ɂ����Ȃ��B���`��`���ɂ́A�Ȗ����e�����Ȃ��B�u���v�̂Ȃ��̂����������Ƃ��ẮA���`��`���̂������̏����Ȃ�A�����K�v��F�߂Ȃ������B �@�������A�����ɗ��āA�����͐V�������q�X�^�C���������B����́A���`��`���Ƃ͂܂������t�̓��e�������@���ł���B����͉����Ƃ����A���S�҂ɂ������ł��镁�ՓI�ȕ��@���{�Ƃ����X�^�C���ł������B����𒅑z�����Ƃ��A����܂ł̕s�������̕����j���āA�����͏������������Ƃɂ����̂ł���B �@����͂���Ӗ��Ŗ��d�Ȏ��݂ł������B�Ƃ����̂��A��ɂ͂��ꂪ�O��̂Ȃ��X�^�C���ł��������炾�B�|�p�iarts�j�Ƃ��Ă̕��@�ɂ��āA���S�҂ɂ�����悤�ɏ����A�Ƃ������Ƃ����\�L�̂��Ƃ������̂ł���B�o����ς��B�̖������ɏ����̂͂���Ӗ��ł͗e�Ղ��B����͂��̏W�c�ɌŗL�̓��ꌾ��ő���邵�A���x�ɒ��ۓI�ȊT�O�ł��`��邩�炾�B�������A���S�҂ɂ����点��͓̂���B �@�ܗ֏��̓��e������A���̋�S�̂قǂ��킩��B�\��̏��N�����ɂ�����悤�ɁA���Ղ���Ƃ��ď����Ă���B���̂��߂ɁA����l�����X�ł��ǂ߂�Ƃ����H�L�ȏ����ɂȂ��Ă���̂����A���͂���ɂ́A���d�Ƃ�����قǓ�����Ƃ������Ă���Ă̂��������̑傫�ȓw�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�������A�����͂Ȃ��A����Ȗ��d�Ȃ��Ƃ܂ł��āA����ȏ��S�Ҍ����̕��@���{�������C�ɂȂ����̂��B �@����́A��������l�̂���ɂ����E���`�؏��̗ނ���^���Ă��Ȃ��A�Ƃ��������ɑz������킩�邱�Ƃ��B�����́A���̏����h�̎t���̂悤�ɑ��`�؏��s���Ă��Ȃ��B���ꂪ�����ł���B�����A�����������������`�؏����c���Ă�����A���̎ʂ��Ȃ�Ƃ��e�n�Ɏc���ē`����Ă������Ƃ��낤�B �@�����͓���̖�l���ɑ��`�؏������^����Ƃ������Ƃ����Ȃ������B�Ƃ����̂��A�����ɂ͓Ɠ��̍l���������āA���吾��������Ȃ������B�C�s�ɉ��������Ȃ��A��������Ƃ��Ȃ��A���ꂪ�������ł������B���@�̓��́A�������g�̔������ׂ����Ƃł���B�����ɂ͖�l�͑����������A�����ɂ����A�����ɂ́u�Ƌ���l�v�͈�l�����Ȃ��̂ł���B �@��������A���������@�̓����ǂ�قǕ��ՓI�Ȃ��̂ɍl���Ă������A���ꂪ�킩��B���V���ꊪ�͑����ᔻ�ł��邪�A����͑�����ᔻ�������̂ł͂Ȃ��A�����́u�Ό��v��ᔻ�������̂ł���B������Ԉ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ܗ֏��ŕ�������т��Đ����Ă���̂́A�u�������ȁv�A�Ό�����ȁA�Ƃ������Ƃł���B���̂�����ɂ����ẮA���h�����h���Ȃ��B�����͂Ђ����畁�ՓI�ȕ��@�̓����A�����ʂ�u�w��v�����̂ł���B �@�ܗ֏��̎��M�ɂ������āA�����̔O���ɂ������̂́A���B�̍���ł͂Ȃ��A��N�i���N�j�̏��S�҂̂��Ƃł���B�����炭�����́A���@�̓��̖������A��N���S�̎҂ɑ������̂ł���B�����Ă��ꂪ�A���@�����͂��߂ď����C�ɂȂ������R�ł���B �@�������͂��߂ĕ��@���������C�ɂȂ���������̗��R�́A������⏑�Ƃ��邽�߂ł���B �@�����́A���̕��@�����܊��ɕ����āA���ꂼ��Ɂu�n���Ε���v�̌܂̖���t�����B���m�̒ʂ�A���̌܂́A�F���������\�����铌�m�I�Ȍ܌��f�̂��Ƃ����A�����������Ƃ����A�����̔O���ɂ������̂́A�����K���ɂ���ܗ֓��̃C���[�W�ł���B �@�����́A���̌܊��̏������A���̌ܗ֓��Ɍ����ĂāA�������Ƃ������̂炵���B�����ɂ������炵�������ł���B �@����Ƃ����̂��A�����́A�u����ɂ͕�Ȃǂ����v�ƌ����Ă����l�ł���悤�ŁA����͗{�q�E�{�{�ɐD����ɏ��q�ԍ�R�Ɍ��Ă��Δ�̌`�Ԃ����Ēm��邱�Ƃł���B���ꂪ�������������郂�j�������g�ł��邱�Ƃ́A���̔蕶�ɖ��炩�����A����ɂ͑��N�����Ɩ@�����L���掏������B�ɐD�Ƃ��ẮA�������̕�����Ă����Ƃ��낾�����낤���A�����ɂ͕�ȂǑ���ȂƁA��X�����u����Ă����炵���A���ǁA���̂悤�ȐΔ�̂������ɂȂ������̂ł���B���ɂ��ĕ��ɂ��炴����́A���ꂪ���q�̕�����ł���B �@�����ɂ́A�s��V�����ɉ��đ����B���Ɏ��珑���A�V���������V���@�����s��̎��ɉ��āA�����ȂĈ��ਂ���B�̂ɍF�q��𗧂āc�t�i���������j�Ƃ���B���̕�����̓������ɂ́A���̒ʂ�A�u�V�����������@�����s��v�̏\������܂�Ă���B �@������́A�s�����ȂĈ��ਂ���t�ł���B�����ɂ������I�ȐU�����ƈ����ׂ��A������ɐD�͎���āA���q�ɕ����̕�Ȃ�ʕ�����Ă��̂ł���B�����̕�͌�Ɋe�n�ɐ݂���ꂽ���A�����̎v�z�ɒ����Ȃ̂́A�B��A���̈ɐD����̏��q������ł���B �@������A�ܗ֏��̕��́A�n���Ε���̌܊��\���ɍ��������A������͖��炩�Ɍܗ֓��̃C���[�W�ł���B�����͂��̏����������Ď��g�̈⏑�Ƃ��A���������Ƃ����̂ł���B �@�Ƃ������Ƃ́A���i��\�N�\���̖{�����M�J�n�ɂ������āA�����ɂ͂��łɎ��̗\�������������̂Ǝv����B����͋�̓I�ɂ́A���ɂ���ɂł��낤���A�����͎������Ԃ��Ȃ����ʂƂ������o���������B �@�������a�̏��ɂ��̂́A�����炭���ꂩ�甼�N�قnj�̂��Ƃł��낤�B�����́A�F�{�̉��~�ł͂Ȃ��A�x�O�̑��ɂ������ʑ��ɂ��āA��t���h������×{���Ă������A��قǕa�d���Ȃ����̂��A���i��\��N�i���ی��N�j�̏\�ꌎ�ɂȂ��āA���Â̂��ߌF�{�֘A��߂��ꂽ�B�������āA���N��Ɏ��S����B �@�������Ă݂�ƁA���i��\�N�\���̖{�����M�J�n�̎��_���玀���܂ŁA���N���ł���B���̊ԁA�a��͑��₩�ɐi�s���Ă��܂��B�������{�����M�Ɋւ�����̂́A�����炭��N���炸�Ƃ����Ƃ���ł��낤�B �@����ɂ��Ă��A�����͎��g�̕��@�ɂ��ċɂ߂Ď��o�I�������l�ł���B�Z�\�ɓ���܂łɁA�����̕��@�ɂ��Č�苳���Ă����̂ł���B�����ō�����⏑�ƂȂ���̂킷�ɂ��ẮA���ʂȈӐ}���������B �@����͌����āA����܂ŏ����Ȃ������ɔ�̉��`���͂��߂Ė��炩�ɂ���A���g�̕��@�̗��_���W�听����������A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ���t�ɁA���̕��@���ɂ͂Ȃ������A�܂�A�܂������̏��S�҂ɂ��ǂ܂����镁�ՓI�ȕ��@�����������Ƃ������Ƃł���B �@���̓_�͌������Ă����B�ܗ֏��͕����̋��ɂ̉��`���ł͂Ȃ��A�������狳���镁�ՓI�ȋ��{�Ȃ̂ł���B�����ł��邩�炱���A��X����l�ɂ��ǂ߂�e�N�X�g�Ƃ��Đ����Ă���킯�ł���B �@�ȏ�v��A�ܗ֏��́A���@���Ƃ��Ă͖��\�L�̏����������B����Ƃ����̂��A�ܗ֏��́A���`��`���Ƃ��ď����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�ނ���t�ɁA��N���S�̎҂ɂ�����悤�ɏ����ꂽ���ՓI�ȕ��@���{�ł���B���̕��Ր��䂦�ɁA����̖�l�Ɉ��Ăď����ꂽ���̂ł��Ȃ��B���������Ă܂��A���҂̈Ӑ}���āA����ɂ��ǂp�����Ƃ��������j�I�ȌÓT�ƂȂ����B �@�܂��A�����̌l�I����Ƃ��ẮA������\�����ď����ꂽ�⏑�ł���B������A��N���S�̎҂ɁA���@�̓��̖���������Ƃ������҂������Ă̂��Ƃł���B���q�̕�����́u�V�����������@�����s��v�̏\�����ɂ��邲�Ƃ��A�u�����~���̕��@�A�������Đ₦���v�Ƃ������Ƃł���B �@�������ċ{�{�����̖��ƂƂ��ɁA���̌܊��̕����A�ܗ֏��������ɓ`������̂ł���B�����́A�ŏ��ɂ��čŌ�̕��@�_���������B����͋��ɂ̉��`���ł͂Ȃ��A�܂��ɉ��������Ȃ����ՓI�ȕ��@���{�ł������B |
 ���@�Ɠ`���@���� ���ێO�N�O���@�瓇���Έ�
*�y�����ɉ��\�Ɖ]���z
�s���@�̎��ɂ���āA���Â��\�Ɖ]�A���Â�����Ƃ��͂�B�Y�ɂ��A���Ƃɂӂ�āA�ɈӔ�B�Ȃlj]�āA��������ǂ��A�G�Ƃ������ӎ��̗��ɂ���ẮA�\�ɂĐ�A�����ȂĂ���Ɖ]���ɂ��炸�t�i���V���j
*�y���@�Ɠ`���z  �ܗ֓�  ���q������ �k��B�s���q�k��@����R����  �`�{�{�������{���@������ �F�{�s�����@���c�R���R���� |
|
�@�ȏ�A�����ƌܗ֏��ɂ��āA��X��ʂ�q�ׂĂ����B���ɂ������ׂ����Ƃ͑������邪�A�ʂ̏������ɂ��ẮA�lj��������Y�ӏ��ŋL�����Ƃɂ���B �@�ܗ֏��ɂ��ẮA�]�����܂��܂Ȍ�F�������������B�����ł́A�ܗ֏��Ɋւ���T���E�ȉ����邽�߂ɁA��{�I�ȃ|�C���g���ȉ��ɐ������Ă��������B �@�i1�j���҂͋{�{���� �@�ܗ֏��́A�{�{�����̒���ł���B�ߋ��ɋU��������������A���Ƃ�蕐���W�j�����낭�ɒm��Ȃ��A���̖��m�Ɋ�Â������ł���A���̍������Ȃ��T���ł���B�����́A����Ȍ㐢�̖ϐ����A�ܗ֏��`���̎����ŕ����Ă���B�����́A���i��\�N�i1643�j�\������{���̎��M�Ɏ�肩�������B�����Z�\�̔N�ł���B �@�i2�j�ܗ֏��ȑO�ɕ��@���Ȃ� �@�����́A�{�����ōĎO�A�����Ƃ��Ă̕��@�����u�͂��߂āv�����ƋL���Ă���B�����ɂ͍u�`�ȂǂŌ���������̕��@�_������A���̗��_�͐��Ԃɂ��m���Ă������A����͏����ꂴ�镺�@�_�ł������B���@�_�������ɂ��ď����̂͌ܗ֏����ŏ��̂��Ƃł���B���������āA�ܗ֏��ȑO�ɕ��@���\�\�O�\��ӏ��ł���A�O�\�܉ӏ��ł���\�\���������Ă����Ƃ����̂́A�㐢���Ŕ����������[�J���ȓ`���ł���B�ܗ֏��́A�����́A�ŏ��ɂ��čŌ�̕��@���ł���B �@�i3�j�ܗ֏��͉��`��`���ł͂Ȃ� �@�ܗ֏���ʓǂ���Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�{���͗��B�A�ߒB�̎҂�Ώۂɂ��ď����ꂽ���`���ł͂Ȃ��B�܂��A����̖�l�Ɉ��Ĕ��s�����ɈӔ�`���ł��Ȃ��B�{���́A��N���S�̎҂ɂ�����悤�ɏ����ꂽ�A����߂ăI�[�v���ŕ��ՓI�ȕ��@���{�ł���B�������ɂ͉��������Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�O��̂Ȃ��X�^�C���������\�L�̕��@���ł������B �@�i4�j���@���{�Ƃ��Ă̌ܗ֏� �@�ܗ֏��͕��@���{�A�܂�퓬�ɂ����āA�����ɂ��ď����A����������鏑���ł���B���̎���ɂ����ẮA�G�ɏ��Ƃ͑�����E�����邱�Ƃł���A����Ε��@�Ƃ͎E�l�Z�p�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�퓬��E�ƂƂ��镐�m����҂̓��́A���ʂ��Ƃ��킫�܂��邱�Ƃł͂Ȃ��A�G���E���Z�p���C�����G�ɏ����Ƃɂ���B���������āA���@���{�Ƃ��Ă̌ܗ֏��͐��_�C�{�̂��߂̏��ł͂Ȃ��B���̓_�A���Ⴂ�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�i5�j�����Ƃ��Ă̕�� �@�u�ܗ֏��v�Ƃ����̂͌㐢�蒅�������ł��邪�A�����͂Ƃ��ɖ{���̂��閼�͂Ȃ������B�܊��̕����A�����܊��ȂǂƌĂ�Ă����B�������A�{�����u�n���Ε���v�ܑ̌�E�ܗւ��e���̃^�C�g���ɂ��ď����ꂽ�̂ł��邩��ɂ́A���炩�ɕ����K���̌ܗ֓���͂������̂ł���B�܂�́A�����߂�������������́A���@�̓��𖢗��ɑ������߁A�{�����⏑�Ƃ��ď����A����Ώ����Ƃ��Ă̕����A�������������̂��Ƃ����������̂ł���B �@�i6�j�ܗ֏��͖������̏� �@�����́A���M���J�n���āA�Ԃ��Ȃ��a�ɓ|��A�₪�ďd���a�̏��ɉ炷�悤�ɂȂ����B���̂��߁A�{���͒��҂̎��ɂ���Ċ�����j�~����A���ǁA�������̌��e�̂܂c���ꂽ�B�������ɁA�ܗ֏��������e�ł͂Ȃ��A���e���������Ƃ́A���̓��e�̒[�X�ɘI�����Ă���B���������āA�����͕L���̋Ɉӏ��E�ܗ֏����u�����v�����Ď��Ƃ����̂́A�����Ȃ������ł���B�����ł����A������������������邪�A����́A�悤����Ɍܗ֏����܂Ƃ��ɓǂ��Ƃ��Ȃ��҂�̂��팾�ł���B�܂��A�ܗ֏��̃I���W�i�������e�������Ƃ͒m�炸�A�����e���Ƃ����O����Ƃ邩����A�ܗ֏��lj��͍ŏ����玸�s����ł��낤�B �@���ɁA�����Ƃ��Ă̌ܗ֏��̐����Ɖ^�p�ɂ��ẮA�ȉ��̏��_���������Ă����K�v������B������A�]���̌ܗ֏������̎v���y�Ȃ��������Ƃł���B �@�i1�j�������V��ւ̈② �@�����͎���O�ɂ��āA���̑��e��Ԃ̒�����A���N笎d���Ă�����l�E�������V��ɑ��^�����B�������A����͂�����u���`�v�ł͂Ȃ��A�②�Ƃ����ׂ����^�ł���B�����͎��ɂ������āA����Ⓛ���Ȃǂ��A�W�҂Ɍ`�����������悤�����A�ܗ֏������������②���̈�ɂ������A�������V��ւ́u���`�v�Ƃ����������ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A���������ܗ֏��́A�������������ł͂Ȃ����e�Ȃ̂�����A������u���`�v�Ƃ����ɂ͓�����Ȃ��B �@�i2�j�ܗ֏��̍Z���ҏW �@��������{�����②���ꂽ�������V��́A���̑��e��Ԃ̕������Z�����ҏW���āA�̍ق������B�����A�������V��͂����܂ł����^���c�����Ƃɕ��S�������߁A���e�̏d�����܂߂āA�I���W�i���̑��e��Ԃ͂��̂܂c�����B�s�Ԃ���̈ꌾ������폜���Ȃ��������A���̔z��ɘf�������߂ɁA�����ɕ��͂̍������݂���B���������l�K�e�B���ȓ�������A�ނ���t�ɁA�I���W�i���ɒ����ȕҏW�҂̎p�������o�����B �@�i3�j�������V��̌����L �@�������V��͂������ɑ��e�ɒ����ȍZ���ҏW���s�������A�����A���炩�Ɏ������V��ɋA���ׂ������L������������B���̂�����nj���ɂ���L�Ƃ݂Ȃ��ׂ��Ƃ��������B���̂��Ƃ���A�������V��͕K�������{���̓��e��m�����Ă͂��Ȃ������A�Ƃ�����������������B�����炭�A�����͕�������{�����②����āA�͂��߂Ă��̑S�e�ɐڂ����̂ł���B���̂��߁A�ꕔ�Ɍ����ǂ���Ƃ�����������B�܂��A�ނ��{���̓��e��m�����Ă��Ȃ������Ƃ���A���̓_�ł��A�{���̎��^�́u���`�v�ł͂Ȃ��ƒm���B �@�i4�j���`�c�[���Ƃ��Ă̌ܗ֏� �@��������{���̈②�����������V��́A�����̍ŏ��ɂ��čŌ�́A���Ȃ킿���̗B�ꖳ��̕��@����Ɛ肷�邱�ƂɂȂ����B�����āA��������h�̑��`�c�[���Ƃ����B�܂�A��V���̊����ɉ����������āA���̋�̈Ӗ��ɂ��Ď��g�̌�B���ʂ������A�����̏h��Ƃ��ă����[����������J�������B�����ŁA�������V��̖嗬�ł́A��X�t���͈ꗬ���`�ɂ������āA���g����������ӂ��L���A����������đ��`�ؕ��Ƃ���悤�ɂȂ����B���ꂪ�A�ܗ֏����`�ɂ����鐳�K�̕����ł���B����䂦�܂��A���̑̍ق�������Ȃ��ܗ֏��ʖ{�́A�K�̊C���łł���B �@�ȏ�̌ܗ֏��̐����Ɖ^�p�Ɋ֘A���āA�ܗ֏��̃e�N�X�g�����ɂ��Č����A�ȉ��̏����������̃|�C���g�ł���B �@�i1�j�ܗ֏��ʖ{�̒}�O�n�^���n �@�������V�傪�J���������̌ܗ֏����`�����́A��l�ĔC������o�R���Ē}�O��V���ɓ`������A�܂�����ɂ͉����z��ɂ܂œ`������B����珔�{�̂��āA��X�́u�}�O�n�v�ܗ֏��ƌĂԂ��Ƃɂ��Ă���B�����A�{�����ł́A�������V��̖嗬�����X�ɐ��S�����炵���A���̎������V�嗬�̑��`�����͎c��Ȃ������B������ɁA��O�֗��o�����ʖ{�������āA��������`�ʂ��ꂽ�ʖ{���o���A�Ȍ㏔�n���ɔh�����Ďʖ{���Đ��Y����čs�����B���ꂪ�u���n�v���{�ł���B�������n�ʖ{�̉���������Β����ɔ������邱�Ƃ����A�ܗ֏����`�����̑̍ق����Ă���A���ׂĊC���Ŏʖ{�̖���ł���Ƃ��������������B �@�i2�j���n�ܗ֏��ւ̕Ό� �@�]���A�ܗ֏��Ƃ����A�א�Ɩ{���͂��߂Ƃ�����n�ܗ֏��𒆐S�Ƃ����������x�z�I�ł������B�������A���̔��n���{���A�K�̊C���łɔ����鏔�n���̖���ł���ȏ�A������ܗ֏��e�N�X�g�̃X�^���_�[�h�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���n���{���������Ă��ẮA����̐��딻�f�����ł��Ȃ��̂ł���B������ɁA����܂ŁA���n���{�𒆐S�Ƃ���Ό������������āA���̈����̂��߂Ɍܗ֏������͍����܂Œ�����܂܂ł������B �@�i3�j�}�O�n���{�̃v���[���X �@�}�O��V���œ`������ܗ֏��́A��L�̑��`�������ێ����ē`�����ꂽ�A�嗬�����̐��K�łł���B���ꂪ���n�ܗ֏��Ƃ̑���ł���B�Ƃ��ɁA�ŋߔ��@�̗��ԁ��z��n���{������������Ƃɂ��A�}�O�n�̎Q�Ǝʖ{���������B����珔�{���A�]���̒��R���ɖ{��g�c�Ɩ{�Ƃٌ͈n���̗��ԕ��όn�ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B����ɂ��A�}�O�n���{�Ԃ̈ʒu�Â����\�ɂȂ�A���܂��A�}�O�n�^���n�����f���čL�͂Ȕ�r�ƍ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B �@�i4�j�ܗ֏������̍đg�D�� �@���̍ŐV�̎j���ɂ��A�ܗ֏����{�̃e�N�X�g�E�N���e�B�[�N�i�j���ᔻ�j�́A�ŏ�����d�蒼�����Ƃ��K�v�ƂȂ����B�܂�A�ܗ֏������̃t�H�[���C�V�����̑S�ʓI�ȕύX�ƍđg�D���ł���B�]���̂悤�ɔ��n���{�ɕ����ܗ֏������ł́A���E�n���̐������āA��邱�Ƃ����������B�ܗ֏������̂����Ƃ���{�I�ȑO������́A�ł��邾���L�����{�������āA���̎�����r�ƍ����邱�Ƃɂ���B�܂�A�}�O�n�^���n�����f���ď��ʖ{�̕������q�ϓI�ɕ]�����f���A�z�肵���鎚�啶���̌Ì^�փA�v���[�`���邱�ƁA���ꂪ�ܗ֏������̗v���ł���B �@�i5�j�u���ܗ֏��v�̕��� �@�ܗ֏��e�N�X�g�����́A�܂��A�������V��i�K�̂������֑k�y���邱�ƁA�����Ă���ɂ́A�����ł̒i�K���z���āA�����̃I���W�i�������邱�Ƃł���B�ǂ�Ȏj���ł���A�I���W�i���̂����������Ă͂��߂āA���̓lj��ɐi�ނ��Ƃ��ł���B�������A���͕K�����������ł͂Ȃ��B���^�̕����ɂ́A�L�q���e�̉�͂��K�v�ł���B���ӂ𗝉��ł��Ȃ���A���̕������\�ł͂Ȃ��B����䂦�A��X�̌ܗ֏��������A���������e��ǂ݉����A�܂��t�ɁA�lj�����������Ƃ����o�����̓�d�����K�v�Ƃ����B���̂悤�ɂ��Ă͂��߂āA�ܗ֏��e�N�X�g�̌��^�m��ֈ�����O�i�ł���̂ł���B �@�ȏ�A��{�I�Ȋ֘A��������ėv���̂����A����Ō��݂̌ܗ֏������̍őO���̗l�������@���Ȃ���̂��A�T���͔c�����ꂽ���ƂƎv���B�������Ȃ���A�c�O�Ȃ��Ƃ́A��X�̂��̌������x���ɔ䌨������ܗ֏����������ɑ��݂��Ȃ����Ƃł���B �@�����Ȃ�A��X�͖ډ��̊J��n�������Ă����āA����̌����i�W�́A��w�̏��N�Ɋ��҂���ق��Ȃ��B���̌ܗ֏��lj����������\����ړI�̈�́A�㑱�̌����҂̈琬�ɂ���B �@���̂��߂ɁA�{�_�lj������ɂ����āA�]���̖{���Z�����ߓlj��ɂ��Ă��A������ʂɔᔻ���Ă������B�����ǂ��Ԉ���Ă���̂��A�����m��Ȃ���A�����̑O�i�͂��肦�Ȃ��B����͕��������V���ŋ����Ă��邱�Ƃł�����B �@���āA�ȉ��{���ɂ́A��X�̌ܗ֏�������Ńe�N�X�g�Ƃ��̌�����A�����ē��Y�e�N�X�g�̍Z�ق��������A�܂��lj��Ɋւ�钐�����B �@����͌ܗ֏������Ƃ��Ă͖��\�L�̖c��ȕ��ʂł���B���̂悤�ɐ��疇�ɋy�ԂƂ��������䂦�ɁA�n�[�h�R�s�[�̊��s���A�܂菑���ɂ���ɂ��Ă��A����͍����̏o�Ŏ���ł͂Ƃ��Ă������s�\�ł���B���ꂪ�A���̂悤�ɉ{���\�ɂȂ����Ƃ����̂��A�C���^�[�l�b�g�Ƃ����V�}�̂�������������ł���B�����Ď���Ɋ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂��B �@�������A���炩���ߒf����Ă������A����͈�ʌ����̌ܗ֏��T�C�g�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�ܗ֏������̍őO���ł���B���I�ȕ��͂⌟���Ɋւ��ڍׂȘ_���������̂ŁA��ʂ̓ǎ҂́A�ǂݒʂ��̂ɍ����������ł��낤�B �@���������āA�����Čx�����Ă������A�{�C�Ōܗ֏��ɂ��Ēm�肽���Ƃ��������̂���҂łȂ���A�����������ʓǂ��āA���̃T�C�g���������Ƒޏo��������悩�낤�B�����āA�����Ďc������o��̂���҂������A�ܗ֏��̐^���ɃA�N�Z�X�ł���ł��낤�B |
 ���ԏ��X�Ōܗ֏� �_�q����@���a38�N |
 ����ДŁw���{����� �ܗ֏��x ��͓�������@���a55�N |
 �u�k�Њw�p���ɔŌܗ֏� ���c�ΗY��@���a61�N |
 �w�{�{�����ܗ֏��ډ��x �Γc�O�Έ��@���a18�N |
|
�@���̓lj������ł́A�O�q�̂悤�Ɍ������t���̂ł��邪�A���ɂ��Č����A���ꂪ���߂Ɋւ����̂ł��邩��A����A�e�N�X�g�lj��̓����ł���A�����ďo���ł���B �@�����ŁA�]���̉��ߗ�Ƃ��āA�ʉӏ��ɂ����āA�����������_�]����K�v���������B�������A���_�������A����������͂��ׂė���ł���B �@���̌�����́A���ԏ��X�Ōܗ֏��i�_�q����E���a�O���N�j�A����ДŁi�V�ł̓j���[�g���v���X�j�w���{����� �ܗ֏��x�i��͓�������E���a�܌ܔN�j�A����эu�k�Њw�p���ɔŌܗ֏��i���c�ΗY��E���a�Z��N�j�����݂���B �@�܂��A��O�i�Ƃ������풆�j�̖�{�w�{�{�����ܗ֏��ډ��x�i�Γc�O�Έ��E���a�\���N�E��㉮�j���X�j���茳�ɂ���̂ŁA�������ɉ����Ă悩�낤�B�����[�����ƂɁA�����̃P�[�X�ɂ����āA���̌�����́A��O�̂��̐Γc��ɗ��B���A�ܗ֏��|��\�͂́A�ቺ�̈�r�����ǂ��Ă���̂ł���B �@�����{������́A�������g�Łi�א�Ɩ{�j�ɂ݈̂ˋ�����Ƃ����_�ŁA���{�I�ȕΌ�������B�����āA������{�ɂ́A�ǂ������ւ����Ȃ�������B�܂��A��g�Ōܗ֏����L�i�w���{�v�z��n61�@�ߐ��Y���_�x��g���X�@���a�l���N�j�ɂ��A���m�Ȍ�߂������Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B�ȉ��̓lj������ł́A��g�Œ��L���܂߁A���E��߂̖ڂɗ]����̂ɂ��Ă͂�����w�E���A�ǎ҂̒��ӂ����N���Ă����B �@�܂��ƂɁA�ܗ֏��قnj�ǂ���������Ă����e�N�X�g�́A���ɂȂ��B����͊��������������A���ꂪ�m��悤�B�����̊g�̂��ꂽ��������������������Ƃ́A�قƂ�Ǔk�J�ƌ����ׂ��B�������Ȃ���A�ܗ֏�����ǂ��������Ƃ����ߑ���L�̗ȏ�����B��������P��������ƔC���𐋍s����A�Ƃ����Ӌ`���A�����ɂ͂��낤�Ƃ������̂ł���B �@���v�Ȏw�e�ƌ����Ȃ���A���p�Ȕᔻ�ƌ����Ȃ���B�K�i�͈��������ŏオ��B����Ɠ����悤�ɁA��ЂƂ��݂��߂ĕЕt���čs���Ȃ���Ȃ�܂��B�痢�̓���������A�ł���B �@���̌ܗ֏��lj������́A�����\�ܔN�i2003�j�����J����Ă������A���̌���ܗ֏�������̊��s�͈�������ʂ��肳�܂ł���B�܂��ƂɌܗ֏��́u���v�v�͂��܂��ɑ����̂ł���B������ɁA�]���̃��x���������͈̂���Ȃ��B���������Đ��Y����Ă��邾���ł���B�܂��Ƃɚo���ׂ��A�܂������ɒQ���킵��������ł���B������ɂ���āA����������ɂ��ẮA��f���{��_���邱�ƂŁA���܂��ɏ\���ł���B �@�Ȃ��A��������A���̌ܗ֏��lj��ɂ́A�ʂ̖��ӏ��ł��ꂼ�ꏔ�{�Z�ق��������Ă��邪�A�ʂɁA�m�ܗ֏��ٖ{�W�n�Ƃ��āA�����ܗ֏��ʖ{�̂����Q�Ƃ��ׂ����{�����^���Ă���B�ŋߔ��@�̏��{���܂߂āA�Ǝ��ɖ|�������ʖ{�W�ł���B�ܗ֏��̑S���𒀏�ΏƂł���悤�ɂ��Ă���B�����́A�\���܂ł��Ȃ��A��X�̌ܗ֏������̊�b�����ł���B��X�̌����p���́A����Ίy�����܂ŃI�[�v���Ȃ̂ł���B�Q�l�ɂ��ꂽ���B �i�ܗ֏�������j
|
