 |
�����̌ܗ֏���ǂ� �ܗ֏�������Ńe�N�X�g�S�� ������ƒ����E�]�� |
|
�@���@��@ �@�ځ@���@�@ �@�n �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@���V�������@ �@�� �V ���@�@ �@�ٖ{�W�@
| �ܗ֏��@���V���@4 | �@Back�@�@�@Next�@ |
�@
�@�@�@9�@�����ᔻ�E���@�̑���
|
�y���@���z ��@�����ɂ͂₫����p�鎖�B ���@�̂͂₫�Ɖ]���A���̓��ɂ��炸�B �͂₫�Ƃ��ӎ��n�A �����̂Ђ₤���̊Ԃɂ��͂���ɂ�āA �͂₫�x���Ɖ]���T���B �������ɂȂ�ăn�A �͂₭���w������̖�B ���Ƃփo�A�l�ɂ͂⓹�Ɖ]�āA ����Ɏl�\�\���s�҂��L�B �����A�����Ӗ��A�͂₭�͂���ɂăn�Ȃ��B ���̂ӂ���Ȃ���̃n�A ������l�Ȃ�ǂ��A�͂��䂩������̖�B �����̓��ɁA���i��*�j�����ӗw�ɁA ����̂��Ă����փo�A������T���T��L�āA �������������̖�B ���A�ۑ��ۂɘV�������ɁA�ÂȂ�ʂȂ�ǂ��A ����n�A�����������A���������T���B �����n�A�����Ȃ�ʂȂ�ǂ��A �͂₫�Ƃ��ӎ��A�����B �͂₫�n������A�Ɖ]�āA�Ԃɂ��͂��B �ܘ_�A�������������B ����A���̂��鎖�n�A�ɁX�ƌ��w�āA �Ԃ̂ʂ����鏊��B ��������������́T���鎖�n�A �����������݃w������̖�B �����Ƃւ����āA���̗�������ׂ��B(1) ��ɕ��@�̓��ɂ���āA�͂₫�Ɖ]�������B �����A���q�ׂ́A���ɂ��āA ���ӂ��Ȃǂɂăn�A�g���Ƃ��ɂ͂₭�s�������B �����n�A����^�_�͂₭���鎖�����B �͂₭�����Ƃ���o�A����̗l�Ƀn����ŁA ���₭�Ƃ���o�A�������ꂴ����̖�B �\�X���ʂ��ׂ��B �啪�̕��@�ɂ��Ă��A�͂₭�}���S��邵�B ���������Ɖ]�S�ɂăn�A �����������������n�Ȃ�����B ���A�l�̂ނ��Ƃ͂₫���ȂǂɃn�A ���ނ��Ɖ]�āA�ÂɂȂ�A �l�ɂ����鏊�A�̗v��B �����T��A�H�v�b�B�L�ׂ�����B(2) |
�y������z ��@�����ő�������p����k�d������l�� �@���@�̑����Ƃ����Ƃ���A�i����́j�^���̓��ł͂Ȃ��B �@�����Ƃ������Ƃ́A�����Ƃł��A���q�̊ԁk�܁l�ɍ���Ȃ��k�͂����l�Ƃ������ƂŁA��������A�����x���Ƃ����킯�ł���B���̓��̏��ɂȂ�ƁA�i����́j���������Ȃ����̂ł���B �@���Ƃ��A�l�ɂ���ẮA�u�͂⓹�v�k��r�l�Ƃ����āA����Ɏl�\���\���s���҂�����B������A������ӂ܂Łi������j��������̂ł͂Ȃ��B���k�͂⓹�l�̕s���k���n�l�Ȃ�҂́A���������悤�ł����Ă��A�����s���Ȃ����̂ł���B �@����*�̓��ł́A��肪�������w�Ȃɉ��肪�t���Ă������ƁA�i����́j�x���S�������āA�}���������̂ł���B �@�܂��A�ۑ��ۂŁu�V���v�k�����܂l��łƂ��A������肵���Ȃł���̂ɁA����͂�����x��A�i�ł��āj�旧�Ƃ��Ƃ���̂ł���B�u�����v�k���������l�́i���Y�����j�}���ȋȂł��邯��ǁA�����Ƃ������Ƃ͂悭�Ȃ��B�u�����͂�����v�Ƃ����āA�Ԃɍ���Ȃ��B�������x���̂��悭�Ȃ��B �@����́A���̂��邱�Ƃ́A�����Ƃ݂��āA�Ԃ������Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł���B�ǂ�Ȃ��Ƃł��A�芵�ꂽ�҂̂��鎖�́A�}�����������Ȃ����̂ł���B���̚g���������āA���̗��k�����������l��m��ׂ��B �@�Ƃ��ɁA���@�̓��ɂ����āA�����Ƃ������Ƃ͂悭�Ȃ��B������A���̂킯�́A�ꏊ�ɂ���āA���A�ӂ��k�����l�Ȃǂł́A�g���������ɑ����i�߂Ȃ�����ł���B �@�����͂Ȃ�����A�����邱�Ƃ͂悭�Ȃ��B�����낤�Ƃ���A��⏬���̂悤�ɂ͂������A���Ⴍ��*�k�f�����l��A��������Ȃ����̂ł���B�悭�悭���ʂ��ׂ��B �@�啪�̕��@�k�W�c��l�ɂ��Ă��A�����}���S�͂悭�Ȃ��B�u������������v�Ƃ�������ɂȂ�A�������x�����Ƃ͂Ȃ��̂ł���B �@�܂��A���肪�ނ�݂ɑ�������ꍇ�Ȃǂɂ́A�u�w���v�Ƃ����āA�i�t�Ɂj�ɖ��ɂȂ��āA�i�����j����ɂ��Ȃ��k�������Ȃ��l���ƁA�������̗v�ł���B���̐S�A�H�v�A�b������ׂ����Ƃł���B |
|
�@ �@�@�y���@���z �@�i1�j���@�̂͂₫�Ɖ]���A���̓��ɂ��炸 �@�O�߂Ƃ��A�����āA����ǂ́A�����A�X�s�[�h���d�����邱�Ƃɑ���ᔻ�ł���B���������Ȃ苻���[�������ł���B �@�Ƃ����̂��A�퍑�����牽���Ƃ��A�X�s�[�h�A�@�����Ƃ����Ƃ��낪�d������A���̍s���ɂ����鑬�x���d������Ă����B����͍���Ȃǐ퓬�ɂ����Ă������ł��邵�A�܂��z��ȂǍH���ɂ����Ă������ł���B �@���ˑ̐��̐����������Œ肵�A�g���Љ���肵�Ă��܂��ƁA�^���͊ɖ��ɂȂ��Ă��܂����A������ȑO�̋ߐ������A�����́A�Ȃ��Ȃ��Z�������}�ɉ^�����鎞������̂ł���B
�s���@�̂͂₫�Ɖ]���A���̓��ɂ��炸�t
�Ƃ��������́A�X�s�[�h�ɑ���l�K�e�B���ȃe�[�[�́A���̒����X�s�[�h��M��Ȃ��ŁA�����g�������x���d������悤�ɂȂ��Ă��܂������Ƃւ̔ᔻ�ł���B�����ւ̋����ϔO�Ƃ������̂������āA�����Ƃ������̂��D��Ă���Ƃ����M���������̂ł���B�@����ɑ������́A�X�s�[�h�����ł͏��ĂȂ����A���邢�́A���x�M��҂ɏ��ɂ͂�����������A�Ƃ����b������킯�ł���B �@���̑O�ɕ����́A���������u�����v�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�Ƃ����Ȏ@�ireflection�j�����Ă݂���B���Ȃ킿�A�u�����v�Ƃ������Ƃ́A�����Ƃł��A���q�̊ԁk�܁l�ɍ���Ȃ��Ƃ������Ƃ���A�����x���Ƃ������Ƃ�����킯���A�Ƃ���B �@�����ł́A�u�Ԃɍ���Ȃ��v�Ƃ����̂́A�u�x���v�Ƃ�������I�ȈӖ��ɂȂ��Ă��邪�A�����̎���ɂ́A���`�ʂ�́u�Ԃɍ���Ȃ��v�A�u�͂����v�Ƃ����Ӗ��ł���B�܂�A��������̂��u�Ԃɍ���Ȃ��v�̂ł���B �@�����ŁA�悤����ɁA���q�̊Ԃɍ���Ȃ��A���q�O��̂��邱�Ƃ���A�����A�x���Ƃ������Ƃ����邾�����B�\�\���ꂪ�����I�Ȓ�`�ł���B �@����͒��ӂ����ׂ��v�l�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���́u�����v�̒�`�ɂ��A�����Ƃ������Ƃ��̂��̂����݂��Ȃ��B���̓��̏��ɂȂ�ƁA�i����́j���������Ȃ����̂ł���A�\�\�ƕ����͌����B �@����������A�����ɂ��A���q�̊Ԃɍ���Ȃ��i�͂����j�̂��A�����A�x���Ƃ������Ƃł���A�u�����v�Ƃ������Ƃ��܂��A���q�̊Ԃɍ��Ȃ��A���q�̊O�ꂽ���Ƃł���B���������w�E�́A���x�̃C�f�I���M�[�̂Ȃ��ŁA�u�����v�Ƃ������Ƃɐ�ΓI�ȉ��l��u�������ւ̔ᔻ�ł��邪�A�����̕����猾���A�����Ă����������Ȃ��A���ꂪ���̂��邱�ƂȂ̂ł���B
�s�������ɂȂ�ăn�A�͂₭���w������̖�t
�@�����ŕ����́A������������B��́u�͂⓹�v�i��r�j�A������͗����i�\�y�j�ł���B���Â���A���x��Y�����̐S�ł���B�@�����̘b�ł́A�����u�͂⓹�v�Ƃ����āA����ɂȂ�Ǝl�\���\���i160�`200km�j������҂��������炵���B����́A���������j�ł���݂̂Ȃ炸�A���Ȃ葁���B �@�}���\���̐��E�L�^�ł��A���ώ���20km���x�ł���B�\���i200km�j����ƂȂ�ƁA����ł��\���Ԃ͑���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ԂƏ��������ė͂��s����}���\���I��ł́A����͖����ł��낤�B����̒ʔO���炷��A�s�\�������A�����������̂�����A�����͂���Ȑl�Ԃ������������A����ȁu�͂⓹�v�Ƃ������s�p���������̂ł���B �@�����̌����ɂ́A������A������ӂ܂ŁA�����Ƃ��̊ԁA��������̂ł͂Ȃ��B�ނ炪�ǂ�����đ����Ă������A���������̂����A���́u�͂⓹�v�̓`���҂́A�������Ȃ����낤�B
�s�����A�����Ӗ��A�͂₭�͂���ɂăn�Ȃ��B���̂ӂ���Ȃ���̃n�A������l�Ȃ�Ƃ��A�͂��䂩������̖�t
�@���̓��̒B�҂́A������ӂ܂ŁA�����Ƃ��̊ԁA��������̂ł͂Ȃ����A�l�\���\���𑖔j����B���́u�ӂ���v�Ȃ�҂́A����������Ă��A����ɒ����s���Ȃ��B���ꂪ�u�����v�u�x���v�Ƃ������Ƃł���B�@���́u�ӂ���v�k�s���l�́A�|�p�Z�p�̖��n�Ȃ邱�Ƃł���B���́A
�s�s�����Y�������Ċ��\�̍��ɂ�Ȃ�t�i�k�R���j
�Ƃ��邲�Ƃ��ł���B���Ȃ݂ɁA�Õ����Ɍ�����u�s���c�v�k�ӂ��l�Ƃ́A�_��ł��Ȃ��r��c�̂��Ƃł���B�@�����������鎖��̂�����́A�����ł���B���́u�����v�Ƃ�����͑O�ɂ��o�����A�K�������u���ԁv�ł͂Ȃ��u����Ձv�Ƃ���ށB�����́u�����v�Ƃ͈Ӗ�������āA�\�̈�߂�w���������Ƃł���B �@�����́A��肪�������w���ɉ��肪�t����揂��ƁA�x���S�������ċ}���������̂ł���A�Ƃ����B�x��܂��Ƃ��āA�}�������Ȃ�̂ł���B �@���́u�����v�̂��ƂŁA���������ɗ�ɏo���Ă���̂́A�u�V���v�k�����܂l�Ɓu�����v�k���������l�A�Ƃ��ɐ�����̍�ł���B�܂��A�Ƃ��ɏj���̕��ȂŁA�����ɉ�����ꂽ�B�Ƃ��ɍł��L���ȗw�Ȃł��邩��A�����͂����ł��A����ł��m���Ă��镪����₷������o���Ă���̂ł���B���ꂪ�ܗ֏��̋����̃X�^���X�ł���B �@�u�V���v�ɂ��āA�����́A������肵���Ȃł���̂ɁA����͂���ɂ��x��ďł�C���ɂȂ�A�ƌ����Ă���B������́A���l�ŊՉ�A�ɑ��̋Ȃł���B �@������́u�����v�ɂ��ẮA�}�ȋȂł��邯��ǁA�����Ƃ������Ƃ͂悭�Ȃ��A�ƕ]���Ă���B�u�����v�͑S�ċ}�ȋȂƂ����킯�ł͂Ȃ��B�}�ȋȂƂ��������́A�^�V�_���̂Ƃ���ł��낤���B�����́A�����皒�q�������Ȃ��Ă��A�V�e�͂���ɍ��킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������قǂ̋}���ł���B �@���̂悤�Ɂu�V���v�u�����v�̊ɋ}��̗���o���āA������ɖ��ȋȂł�����͒x��ďł��Ă��܂����̂����A����ł�����ł��}�ł����Ă悢�Ȃł��A�����Ƃ����̂͂悭�Ȃ��A�Ƃ���̂ł���B�v����ɁA���q�̊Ԃɍ����^����Ȃ��Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł���B �@�����͉]���A�\�\�u�����͂�����v�Ƃ����āA�Ԃɍ���Ȃ��B���́u������v�́A����ł����ȂǂŌ�����@�ɂ��邪�A�]�k����l�ԁA�|��邱�Ƃł���B�u�����A�]�k�܂�l�тv�Ƃ����̂́A�|�ꂽ�肱��肵�āA����Ȓ��q�ŋ}���ő���l�q�ł���B�������A���́s�����͂�����t�́u������v�̂����́A�u����A�O���v�̈ӂł���A���q���O���Ƃ������Ƃł���B������A�����́s�Ԃɂ��͂��t�Ɖ]���̂ł���B
�s����A���̂��鎖�n�A�ɁX�ƌ��w�āA�Ԃ̂ʂ����鏊��B��������������́T���鎖�n�A�����������݃w������̖�t
�@���ꂪ�A�����̉���|�C���g�ł���B���̂��邱�Ƃ́A�����Ƃ݂��āA�Ԃ������Ȃ��B�u�Ԃ������Ȃ��v�Ƃ́A�Ԃɍ������Ƃł���B�u�Ԕ����v�Ƃ����̂́A�����A�ڔn�Ɠ��l�A�l�̋�݂�l���ĉ]���l�|��A�u�Ԃɍ���Ȃ��v�͌����ł͒x��邱�Ƃ��������A���Ƃ͔��q�̊Ԃɍ����^����Ȃ��Ƃ����b�������̂ł���B�@�Ȃ��A�܂���ߏ�̖��ł́A�O�o�́s�͂₫�n������t�́u������v�ł���B����́u����A�O���v�̈ӂ���A���q���O���Ƃ������Ƃł���B�����͔��q�̊Ԃɂ��Ă̐���ł��邩��A�u������v�͒ʏ�́u�]�ԁA�|���v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B �@����ɂ��Ċ��������������ɁA��O�̐Γc��́A�u�����͓̂|�k���l����v�Ƃ��āA���łɁu�|���v�Ƃ����������o���Ă���B���̐_�q��ɂȂ�ƁA�u�}���Γ]�ԁv�Ɓu�Ԃɂ͂���Ă��܂��v���o���Ă��邪�A�]�ԂƊԂɂ͂����̐H�Ⴂ�����̂܂܂ɂ��āA���ӕs�ʂ̖ƂȂ��Ă���B �@���̌�̊�g�Œ��L�ł́A�s�͂₫�n������t���u�͂₭����Γ]�|���邱�Ƃ������v�ƌ�߂��Ă���B����͏�L�̈Ӗ��ɂ����Č��ł���B�s�Ԃɂ��͂��t�ɂ́A�u���q�̊Ԃɂ҂���ƍ��킸�A�O��Ă��܂��v�ƌ�߂��Ă��邩��A�_�q��Ɠ������A�]�|����ƊO���̋Ⴂ���݂����܂܂ɂ��Ă���B �@��͓���́A�_�q��Ɗ�g�Œ��L�̖|�Ăł���A�����čH�v�͂Ȃ��B���c������̓_���l�ł����A��ɂ���Ċ�g�Œ��L�����̂܂ܓ]�L�������̂ŁA�������s�͂₫�n������t���x��ł���̂������ł���B �@�Ƃ���ŁA�א�Ɩ{�́A�s�����Ƃւ����āA���̗�������ׂ��t�Ƃ��āA���́u���v�Ƃ��Ă��邪�A����́A�}�O�n���{���Q�Ƃ���A���́u���v�Ƃ��ׂ��Ƃ���ł���B��Ɩ{�́A���n�̒��ł͒������A���́u���v�Ə����Ă��邪�A���͂����ނ˓��́u���v�ɍ��B �@�����́u���v�u���v�̌݊����������āA�u���v���u���v�Ɉ��Ď����������Ƃ��悭����̂����A���n���{�̌X���Ƃ��āA�u���v���u���v�ɏ��������Ă��܂��Ⴊ�����B���̓��́u���v�����̈��ł���B �@�Ƃ���ŁA�א�Ɩ{�����̏��{�Ɠ������A���́u���v�Ə��������Ƃɂ��A����������ɗ��������������������B �@��O�̐Γc��́A�u���̗��v�Ƃ��āA�ꎚ�ʂ�ǂ܂��悤�Ƃ��Ă��邪�A���́A���̐_�q��ł���B�����̂��Ƃ��A������Ȃ�Ɓu�����v�Ƃ��Ă��܂����̂ł���B�u���̗��v������A�u�����v�B�������u���̓����v�ł���B�ǂ̓����Ƃ����̂��A���ꂽ�u�|��v�ł���B �@�����Ȃ�͂��߂���u�����v�Ƃ��邾�낤�ɁA�ǂ����āu���̗��v�Ə����Ă���̂��A����Ɏv������Ȃ������̂ł���B�������A���ꂪ�u���̗��v�ł��邱�Ƃ́A��҂͒m��Ȃ��̂ł���B �@�������A����ɖ��́A��͓���E���c��ł���B���҂͐_�q��Ղ��āA�u���̓����v�u���̓����v�Ƃ��Ă���B�_�q��̑n�ӂɂ����钿��́A�������čĐ��Y����Ă���킯�ł���B �@���łɁA�����ł��������������邱�Ƃ��ł���B������A�_�q��̑n�ӂɂ����̂ł���B �@�܂�A�����͌��ɂȂ������A�ނ炪�ˋ������א�Ɩ{�ɁA�s�l�ɂ͂⓹�Ƃ��ЂāA�l�\���\���s���̂�����t�Ƃ���Ƃ���A�Γc��͂��̂܂܂̖�ł��邪�A���ɂȂ�ƁA�_�q�u����Ɂv�Ɠ��ꂽ�B �@������̌��́A�א�Ɩ{�i��g�Łj�����ɂ͂Ȃ����̂ł���B�����ɂȂ���������̂́A����ł͂Ȃ��Ӗ��炾���A���́u����Ɂv�Ƃ����_�q��̔����́A�Ȍ�̑�͓���E���c��ɂ������p���ꔽ������Ă���B������A������m��ʓǎ҂́A�א�Ɩ{�ɂ��́u����Ɂv�Ƃ���������������̂ƍ��o����̂ł���B �@�������A�א�Ɩ{�ɂ́A�u����Ɂv�l�\���\���s���Ƃ͏����Ă��Ȃ�����A�O���ōs�����Ƃ��A�ܓ��ōs�����Ƃ�����͂��ł���B�Γc��͂������������ł��낤�B���������āA�א�Ɩ{�Ɉˋ����邩����ɂ����āA�Ӗ�Ƃ͂����A���́u����Ɂv�͌����ɕs�����Ȉ�E�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ��낪�A�ȉ��̍Z�قɌ��邲�Ƃ��A�}�O�n���{�ɂ́A�s����Ɏl�\���\���s�҂��L�t�Ƃ����āA�u����Ɂv�Ɗm���ɏ����Ă���̂ł���B�������_�q���A�}�O�n�ܗ֏��܂Ō��Ă���͂��͂Ȃ�����A����͒m�炸�ɏ���ɕt���������̂ł���B�܂�͌�������E�����Ă��܂����̂����A����������E���A���ʂƂ��Đ������Ƃ����킯�ł���B������܂��A�ܗ֏��|��j��̒����̈�ƈ����ׂ��ł��낤�B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
���������{�Q�� �� �@�ٖ{�W�@ �n������@���j������ �u����v���x�_�b�̗h�Ւn
*�y�ԕ䎖�������̑����z  ������r �����k�ցu�x�m�S��Ńm�s��v����  �\�u�V���v  �\�u�����v
*�y������z
*�y������z
*�y������z |
|
�@���̉ӏ��Ɋւ��āA���Ȃ��炸�Z�ق�����B�w�E���Ă����ׂ��́A�ȉ��̏��_�ł���B �@�܂��A�`���^�C�g�������A�}�O�n���{�ɁA
�s�����ɂ͂₫����p�鎖�t
�Ƃ����āA�s�����t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s���̕��@�t�Ƃ�����̂�����B�܂��A�������n�ł��A�����h���n���̎q���A�x�i�Ɩ{���앶�ɖ{�Ȃǂ́A�s�����̕��@�t�Ƃ��Ă���A����Β��Ԍ`�Ԃ������B�@�����́A���V�������̑̍ق��炵�āA�}�O�n���{�̂悤�Ɂs�����t�Ƃ���̂��Ó��ł��낤�B���ł́A�u���@�v�Ƃ����ꂪ���ꍞ�ގʂ����ꂪ�A�����ɂ��������̂炵���B �@���ɁA�}�O�n���{�ɁA
�s���������Ђ₤���̊Ԃɂ��͂���ɂ�āt
�Ƃ����āA�s�����Ɓu�́v�t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�א�Ɩ{�̂悤�ɁA�s�����u�Ɂv�t�Ƃ�����̂�����B�܂��A�������n�ł��A��Ɩ{��x�i�Ɩ{�ȂǁA������s�����u�́v�t�Ƃ�����̂�����B�@���̂悤�ɒ}�O�n���{�����ł͂Ȃ��A���n�ɂ��u�́v���̂���Ƃ��납�炷��ƁA�}�O�n�^���n�����f���ċ��ʂ���̂́A�u�́v���ł���A���ꂪ�Ì^�ł���B������u�Ɂv���ɍ��̂́A���n�Ō�ɔ���������ʂł���B �@�Ƃ���ŁA�����Ɂu�Ɂv�����L���̂́A�א�Ɩ{��ۉ��Ɩ{�����A�����͏]���Ì^�������ʖ{���Ƒz�肳��Ă������̂ł���B�������A���炩�ɂ��������㔭����������ʂ�L������̂ł���ȏ�A�א�Ɩ{��ۉ��Ɩ{���Ì^�������ʖ{�ł���킯���Ȃ��B���������T���͋p�����ׂ��ł���B �@�܂����ɂ́A�u�����v�ւ̌��y�ӏ��ŁA�}�O�n���{�ɁA
�s���ƂւA�l�ɂ͂⓹�Ɖ]�āA������l�\���\���s�҂��L�t
�Ƃ��āA�s����Ɂt�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A���̌�傪�Ȃ��B����́A�}�O�n�Ɣ��n�ɕ�����Ė��m�ɕ��z���Ă��邩��A���҂��敪����w�W�I���قł���B�@�������A�\���܂ł��Ȃ��A��͂̂���l�m�łȂ��Ƃ����łɋC�Â���Ă��邱�Ƃ��낤���A�����Ɂs����Ɂt�Ƃ�����傪�Ȃ��ƁA���ӂ��B���ł���B�Ƃ����̂��A�l�\���\���s���҂�����Ƃ��āA���ꂪ���Ƃ��ΎO����ܓ��̂��Ƃł́A�����Ƃ͉]���Ȃ�����ł���B�����́A�u����Ɂv�l�\���\���s���҂�����A�Ƃ������͂łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@���n���{�͋��ʂ��āA���́u����Ɂv�Ƃ�������E�������߂Ă��邩��A����͔��n�����ɔ��������ٕςł��낤�B�������A������P���ȒE����ʂł͂Ȃ��A����Ŏl�\���\���s���ȂǁA����Ȃ��Ƃ͍r�����m�ł͂Ȃ����ƍl�����҂��A������폜�������̂̂悤�ł���B �@�Ƃ���A���n���{�ɂ�邩����A�u����Ɂv�l�\���\���s���҂�����Ƃ������Ǝ��̂���������Ă���킯�ŁA���̕����ł́A�����āA�u����Ɏl�\���\���s���ҁv�ȂǑ��݂��Ȃ��̂ł���B �@�������A���������������ł���Ƃ����̂��A�������ɂ͂ł��Ȃ��B�܂�A�����Ɂs����Ɂt�Ƃ������̋����I�ȁu�E���v�ł͂Ȃ��A�u�����v�̍�ׂ�����Ƃ���A����͌ܗ֏����`�Ƃ������ł͂��肦�Ȃ����ƂŁA��O���o��̑���Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł���B �@�����āA������A�\�\����͏d�v�ȃ|�C���g�ł��邪�\�\���������E���������������ӏ����A���n���{�ɋ��ʂ��đ��݂���Ƃ���A����́A���n�����ʖ{�͂��ׂāA��O���o��ɔ��������C���Ŏʖ{�̎q�����Ƃ������ƂɂȂ�B���̓_�́A���n���{�̎j���]���ɂ�����̐S�ł���B �@���āA�Z�ىӏ��Ƃ��ẮA���ɁA�}�O�n���{�Ԃ̑��ق̂���Ƃ���A���Ȃ킿�A�����̓��Ɍ��y����������A�}�O�n���{�̂����A����n�̋g�c�Ɩ{�E���R���ɖ{�ɁA�s�����̓��ɁA��肤���ӗw�ɁA����̂��Ă����ւt�Ƃ��邪�A����ɑ��A��������n�ł��ɒO�Ɩ{�ɂ́A�s����������Ӂt�Ƃ��āu�́v�������A�܂����ԁ��z��n���{�ł��A�u�́v��������Ƃ���ł���B �@�܂�A�}�O�n���{�Ԃɂ́A���́u�́v���̗L���Ƃ������Ⴊ����B�������A����n�̈ɒO�Ɩ{�Ɂu�́v�������邾����A����͗��Ԍn�^����n�̑��قł͂Ȃ��B �@���n���{���݂�ɁA�������u�́v����������̂����邵�A�܂��A���n�ɂ��A�x�i�Ɩ{�̂悤�ɁA�u�́v�����������̂�����B����䂦�A���̗������A�}�O�n�^�z��n�����f���đ��݂���Ƃ����i�D�ł���B�}�O�n�^�z��n�����f���ċ��ʂ�������A����͎������V��̒i�K�ɑk�肤����ł��邪�A����͂ǂ�������̎��i������Ƃ������Ƃł���B �@���������āA���̒}�O�n���{�Ԃ̑��فA�u�́v���̗L���Ɋւ��ẮA���������Ƃ��Ă����ׂ��ł���B�܂�����ɐV�����j�������@�ł���A���̖��̉����ɐi�ނ��Ƃ��ł��悤�B���������āA���ʁA��X�̃e�N�X�g�ł́A���̖�����Ԃ��������߂ɁA�s���i�́j�����Ӂt�ƋL���Ă���B �@�Ƃ���ŁA�܂��Z�ىӏ�������B���̂�����Z�ق��A�����Ă���̂ŁA�ȉ��A����ɏ�����ǂ��Ď����Ă����B �@���Ȃ킿�A��́A�}�O�n���{�ɁA
�s�V�������ɁA�ÂȂ�ʂȂ�ǂ��A����n�A������������A���������T���Ȃ��t
�Ƃ��āA�s������t�s���T��Ȃ�t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s����ɂ��t�s�S����t�Ƃ��āA�o�����Ⴊ����B�����������́A�}�O�n�^���n��B�R�Ƌ敪����w�W�I���قł���B�@�������A�}�O�n���{�ɂ͋��ʂ��đ��݂���Ƃ��납��A�O�o��Ɠ��ނ̂��Ƃł���A�����ɂ�����́A�܂��͏�������L������̂ł���B�������A�ꉞ�A�ʂɍ��ق��������Ă����ׂ��ł���B �@���̂����A�s������t�^�s����ɂ��t�́A�u�Ɂv���̗L���ł��邪�A����͔��n�Ɍ����镶�Ӌ����̃p�^�[���ł���B�������A���ꂪ�������V��i�K�ɑk��\��������B�܂�A�������V�����A�s����ɂ��t�Ƃ��������L�����ܗ֏��������Ƃ������Ƃ����肤��B �@�������A���̏ꍇ�ł��A�}�O�n�́s������t�̏����`�Ԃ��邱�Ƃ͓����Ȃ��B������͎������V��O���̉\�������邩��ł���B �@���ɁA�s���T��Ȃ�t�^�s�S����t�̑��قł��邪�A����́u�Ȃ�v�^�u����v�̑��قł���A���Âꂩ�̌�L�ł���B�܂�A�����u��v�^�u�L�v�̌�L�ł͂Ȃ��A�����u�ȁv���Ɓu���v���̗ގ����琶������ʂł���B �@����ɂ��ẮA�}�O�n�̏��������炵�āA�{���́u�Ȃ�v�ł������Ƃ݂���B����ɑ��A���n�́u����v�́A���{���ʂ���Ƃ͂����A����͎������V��i�K�ɑk�肦�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͕��ӂ��ς��Ă��܂��ύX�Ȃ̂ŁA�����{�l���A�O���^����ŁA�u�Ȃ�v�Ɓu����v�����������邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B �@�u�S�Ȃ�v�Ɓu�S����v�Ƃł͕��ӂ��قȂ�B�u�S����v�Ȃ�A���̐S������A�Ƃ������Ƃł���B���̂����ł́A�旧�S������A�Ƃ������Ƃł���B����ɑ��A�u�S�Ȃ�v�ł���A���̐S�ł���A�Ƃ������ƁB�ł́A�u�S����v�ɑ��āu�S�Ȃ�v�͈ٗႩ�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�u�S�Ȃ�v�̌��͑����B�E�f�̂��Ƃ��A���̕��V���ł��A���Ȃ��炸�o�ꂵ�Ă���B �@���̂����A�{��u�旧�S�Ȃ�v�Ɠ����悤�ȃl�K�e�B���ȈӖ����������̂́A�s����ꂴ��S��t�A�s���ɂ��T����S��t�A�s�܂�ӐS��t�Ȃǂ̌��ł���B���������āA�u�S�Ȃ�v�̌��͏��Ȃ��Ȃ��B �@���̂��Ƃ���A�����͖{���A�u�Ȃ�v�ł����ĕs�s���͂Ȃ��B�s���������T��Ȃ�t�ł���B�������A���ӂ������̂́A��L����ɂ����āA�s�S��t�Ƃ��āA�����u�Ȃ�v�ł͂Ȃ��A�����u��v���������Ƃł���B�Ƃ���A�����Ɍ�ʂ̗v��������킯�ł���B �@�܂�A�������V��͂������u�Ȃ�v�Ɖ����ŏ������B�}�O�n�ł́A��������̂܂ܓ`�������A���n�́A��O���o��ɁA���́u�Ȃ�v���u����v�ƌ�ʂ����ʖ{�����������B���̂��߂ɁA��̎ʖ{�͂����`���āA���邢�͊����u�L�v�Ƃ������悤�ɂȂ����B �@���̌�ʂ͖�O���o�㑁�X�̂��Ƃł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�����ɔh�������n���̎q������x�i�Ɩ{��~�����n���{�ɂ��A���́u����v�u�L�v�������邩��ł���B �@�Ƃ���A���n���{�́A��O���o�㑁���ɂ��̌�ʂ������ʖ{�̖���ł���B����������A���n�����ʖ{�̐�c�́A���̌�ʂ������C���Ŏʖ{�ł���B�����āA��ʂƂ������R�������ɓ����ɔ������邱�Ƃ��H���Ƃ���A���n���{�͕����̐�c���ʂɗL����̂ł͂Ȃ��A����̌��c��{�ɋA�ꂷ����̂ł���A���̌��c�����ꂽ��A���n���ɔh�������̂ł���B �@���̔��n���{�̌��c�Ƃ́A�ނ��A�������V�傪��l�ɓ`�������ܗ֏��ł͂Ȃ��B�܂��A���̌��c��{�́A��O�֗��o�����ʂ��ł��Ȃ��A���̎q�����ł���B�܂�A�ܗ֏����`�Ƃ͖����Ȗ�O�҂��쐬�����ʖ{�Ȃ̂ł���B �@�������āA���n�ʖ{�̂��́s�S����t�̎����Ƃ���́A�����ď������͂Ȃ����Ƃ��m��悤�B�����������Ƃ́A�ʖ{�̈ꎚ�������ƍ����Ă͂��߂Đ͏o����鎖���ł���B���{�����̈����������Ă��Ȃ��悤�ł́A�킩��Ȃ����Ƃł���B �@���邢�́A��̕ʂ̉ӏ��ŁA�}�O�n���{�ɁA
�s�͂₫�n������Ɖ]�āA�Ԃɂ��͂��B�ܘ_�A�������������B�����A���̂��鎖�n�A�ɁX�ƃ~�w�āA�Ԃ̂ʂ�����Ƃ����t
�Ƃ����āA�s����t�Ƃ���Ƃ���A���n�͋��ʂ��āA�s�����t�Ƃ��āA�u���v�Ɗ����ŋL���u���v����t���B���̑�����܂��A�}�O�n�Ɣ��n�ɕ�����ĕ��z���Ă��邩��A���҂w�W�ł���B
�@���ꂾ���ł͂Ȃ��A�������V�傪�s����t�Ɖ������������̂́A�����s���t���A�����u���v����t���ꂪ���Ȃ̂ŁA�����͓��ɉ��������ɂ��āA�\�h���������̂炵���B�Ƃ��낪�A��ɔ��n�ł́A���̉����������u���v�ɍ��A�������Ă��̌�ɁA�Ă̒�u���v����t���ʖ{���o���Ƃ������Ƃł���B �@�������Ă݂�ƁA�s����t�Ɓs�����t�̊Ԃɂ́A�u���v�Ɗ����ϊ�����i�K���������炵���B�܂�A �@�@�@�@�u����v�@���@�u���v�@���@�u�����v �Ƃ����v���Z�X�ł���B��O���o��A�܂��u���v�Ɗ����ϊ�����āA���̌�ɁA�u���v����t���āA���ӂ��������鑀�삪�Ȃ���A�s�����t�Ɖ������̂ł��������낤�B �@���́s�����t�Ƃ��������A���n���{�̋��L����Ƃ���ł���B�O�L����Ɠ������A���c��{�ɋA��������̂Ƃ���A���̌��c��{�́A�������V��̌ܗ֏����炷��A���Ȃ��Ƃ��u���v�ł����āu�q�v�ł͂Ȃ��B����������A��O���o��ɔ��������ʖ{�̎q�����ł���B �@�ȏ�̂悤�ɁA���n�����̎ʖ{�͈ʒu�Â�����ł��낤�B�����ʖ{�́A��������h���������n���̖���ł���B��L�Ƃ�����`�q�����L���邱�Ƃ���A�����͓��c�q���ł���B��c���������݂����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B �@ Go Back |
*�y�g�c�Ɩ{�z  �ɒO�Ɩ{�@�Z�ىӏ�
*�y�g�c�Ɩ{�z
*�y�g�c�Ɩ{�z
*�y���V�����z  ��Ɩ{�@�Z�ىӏ�  �g�c�Ɩ{�@�Z�ىӏ� |
|
�@ �@�i2�j��ɕ��@�̓��ɂ���āA�͂₫�Ɖ]������ �@�����Ƃ����̂́A���q�̊Ԃ̖��ł���B�O�i�ł̘b�ł́A�ǂ�Ȃ��Ƃł��A���̓��̏��̂��邱�Ƃ́A�����Ƃ݂��āA�Ԃ������Ȃ��B�芵�ꂽ�҂̂��鎖�́A�}�����������Ȃ����̂ł���A�\�\�Ƃ������Ƃł������B �@�����ŁA�����͌����B�\�\�Ƃ��ɕ��@�̓��ɂ����āA�����Ƃ������Ƃ͂悭�Ȃ��B���̂킯�́A�ꏊ�ɂ���āA���A�����Ȃǂł́A�g���������ɑ����i�߂Ȃ�����ł���c�B����͑O���u�������v�ŏo���u�������v�i�����j�Ƃ��֘A���邱�Ƃł��낤�B �@����͐키�ꏊ�̏����ɂ���āA������}�����Ƃ��Ă�������Ƃ����b�ł���B����ȕ����肫�����b������̂́A�ނ���̃��[���A�ł���B����Ȃɋ}���ł��A����ӂ��i���n�j�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�܂��A�Ƃ������ł���B �@�ł͑����́A�ƂȂ�ƁA�ǂ����B���������́A�����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �@�藧�i�藬�j�c�A垖�֏��э��n�V���i1593�`1667�j�́A�����Ɠ�����̐l�ł���B�ނ̈�b�i�u���˖�ҁv�j�ɁA���̐́A���`�o�������}���a���Ĕ��f�A�Ȃ����ɗ����Ȃ������A���̓`������垖�֎��s����ɁA���̎}�����ʂɗ�����܂łɏ\�O��ؒf�����B���̑����̑������Ƃ��̎^���ꂽ�Ƃ����B�������̔��������������A���\�܍Ŏ��ʂ܂ł����p�����A�Ƃ������B �@�Ƃ�����A���������͑��������悢�̂ł͂Ȃ����H�\�\�Ƃ��낪�A�����̋����́A���̔��ł���B �@�����ƂȂ�ƁA����͂Ȃ�����A�����̂͂����Ȃ��B�����͑����邱�Ƃ͂悭�Ȃ��B�����낤�Ƃ���A��⏬����U��悤�ɂ͍s�����A���Ⴍ�Ɓi�f�����j��A��������Ȃ����̂ł���B�ނ��A���}���̂Ɛl���a��̂Ƃł́A�b�����̂Â���Ⴄ�B �@����Ɨގ��̘b�͐��V���ɂ��������B�\�\�����𑁂��U�낤�Ƃ���ƁA�������đ����̋O�����t����āA�U��Ȃ����̂ł���B�����͐U��悢�������ɐU��Ƃ��������ɂ���B��⏬���Ȃǂ������悤�ɁA�����𑁂��U�낤�Ǝv���̂͂悭�Ȃ��B����́u���������݁v�Ƃ����āA�l�Ȃǐ�Ȃ����̂ł���B�\�\�Ƃ����̂��A���̋����ł���B �@�܂��A�啪�̕��@�k�W�c��l�ɂ��Ă��A�����ł����āA�����}���S�͂悭�Ȃ��B�u������������v�Ƃ����S�ɂȂ�A�������x�����Ƃ͂Ȃ��A�ƕ����͉]���B���́u������������v�Ƃ��������́A�O�ɉΔV���ŏo�Ă����Ƃ���ł���B �@���Ȃ킿�A������������Ƃ����̂́A�����Ƃł���G���v���������������ʓ��ɁA������͂�����@�m���āA�G�́u�łv�Ƃ������́u���v�̎��̓���}���āA���̌�������Ȃ����ƁA���ꂪ������������Ƃ����Ӗ��ł���B �@�L���ȁs�G�̑łƉ]�A���̎��̂�����������ւāt�Ƃ�����߂̂��邱���́A�\�\���q�̂悤�Ɂ\�\�Ӑ}�ƍs���̌��Ԃł͂Ȃ��A�ނ���u�łv�Ƃ����Ӑ}�̋N�����铪��}����Ƃ����b�ł���B�G�́u�s���v�̓���}����̂ł͂Ȃ��A���́u�Ӑ}�v�̓���}���Ă��܂��̂ł���B�������A����}����Ƃ͂����A�G�̂��悤�Ƃ��邱�Ƃ�}���悤�A�}���悤�Ƃ���ƁA���ɂȂ�B�Ӑ}���邱�Ǝ��̂����łɒx���̂ł���B�܂��A�G�̋Ƃ����悤�Ƃ��铪��}���āA�����Ƃ����ɗ��������A�G�����݂Ɉ����i���Ȃ��j�Ƃ���A���������@�̗��B�҂̒b���̐��ʂł���A�]�X�B �@���������u������������v�Ƃ����S�ɂȂ�A�}�����Ƃ͂Ȃ����A�������x�����Ƃ͂Ȃ��A�ƕ����͉]���킯�ł���B���͂�x�����Ƃ��瑶�݂��Ȃ��̂ł���B �@������A�����̌����̂́A����̔��q���O�����ƁA�ނ���u�w���v���Ƃł���B����̂ނ�݂Ƒ������q�ɑ��ẮA�u�w���v�Ƃ����āA�w�����邱�Ƃ�����B�܂�A������͋t�Ɋɖ��Ȕ��q�ɂȂ�B �@�v����ɁA����̔��q�ɓ����ǐ����Ȃ��Ƃ��낪�̗v�ł���B�w�Ȃł͂Ȃ��̂�����A�퓬�͑���Ɣ��q�����킹��̂ł͂Ȃ��A����̔��q���O���A���̔��q�Ƃ͔��̔��q���Ƃ�B���q�̑�������ɂ́A���q�ɔw���ď��̂ł���B �@�Ƃ����킯�ŁA�����͕��@�ɂ����鑬���ւ̐M��ᔻ���邾���ł͂Ȃ��A�����ł��j���ď����@�܂ŋ�����B�ᔻ�͌��t�̎��������ł͂Ȃ��A�s�ׂ̎����ɂ����Ď��؉\�ł���B �@�Ƃ���ŁA���ĉ�X�̒����e����g���Łi�����Z���j�ܗ֏��ł́A
�s�͂₭������A�������ꂴ����̖�t
�Ƃ������B���́u�͂₭�Ɓv�́A�u���v���u�́v�ƓǂZ���~�X�ŁA�������́u���₭�Ɓv�ł���B���̊�g�V�Łi���{�v�z��n�Ł@���a�l���N�j�ł́A������u���₭�Ɓv�Ɛ����������Ă���B�@�����܂ł͂悢���A���̊�g�V�ł̒��L�ɁA������u�����Łv�ƌ�߂����̂͌��ł���B�p���������A
�s���킿�₭�Ǝv�Ă��o���t�i��ڗ��E�S���\��j
�@���́u���₭�Ɓv�́A�����܂ł��Ȃ��A�u�f�����A�������Ɂv�̈ӂł���B�]���āA���܂萫�}�ɂ����āu���v���Ɂv�u��y������v�Ƃ����j���A���X���Ȃ��ł͂Ȃ��B�������u�����Łv�Ƃ�����`�͂Ȃ��B��g�Œ��L�͓T���������Ȃ�����A����͓��Đ��ʂł��낤�B�s�z������A�����������₭�Əo����̂��₪�t�i�ؓ�疗y�w�ˈ�t�x�j �@�����������ɁA�풆�̐Γc��Ɛ��̐_�q��́A��g���ł́u�͂₭�Ɓv�̐���ł���B�Γc��́u�����v�Ƃ��A�_�q����u�����v�Ƃ��āA������d���ƌ��ďȗ����Ă���B���҂̑�͓���Ɗ��c��́A��g�Œ��L�́u�����Łv�Ƃ�����߂Ղ��Ă���B�ނ��A����͌��ł���B �@���������āA���҂��������e�N�X�g�Ɉˋ����Ă���̂Ɍ�A������e�N�X�g�Ɉˋ������O��҂̌��̕������ʓI�ɂ͐������A�Ƃ�������Ȏp�ɂȂ��Ă���B������A�ܗ֏��|��j��̒����̈�ł���B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
 ����垖�ց@���m�S�l���
*�y�����̓��Ɖ]���z
*�y������z |
|
�@���̉ӏ��̍Z�قɊւ��āA�w�E���Ă����ׂ��͈ȉ��̏��_�ł���B �@�܂��A�}�O�n���{�ɁA
�s��ɕ��@�̓��ɂ���āA�͂₫�Ɖ]�������B�����A���q�ׂ��A���ɂ��āt
�Ƃ����āA�s�����A���q�ׂ́t�ƋL���Ƃ���A���n���{�ɂ͂��낢��ٕς�����B���{�ɂ���đ��Ⴊ����B��Ɩ{�Ȃǂ́A���́s�����t�Ƃ�������������B������ɁA�א�Ɩ{�́A�s�����t�Ƃ��������L�����A�s���q�ׂ́A�����t�Ƃ��Čꏇ������ւ���Ă���B���邢�́A��앶�ɖ{�ł́A�s�����t�͏���̈ʒu�ɂ��邪�A�s���q�ׂ́t�Ƃ������͌㕶�̓��Ɉړ����Ă���B�@�������A�������n�̊ۉ��Ɩ{��x�i�Ɩ{�ɂ́A�}�O�n���{�Ɠ��l�ɁA�s�����A���q�ׂ́t�ƋL���B����������ɁA���n�������ɂ́A�s�����A���q�ׂ́t�ƋL�������̂炵���B���ꂪ�A���̌�A�n���h�����邤���ɁA���܂��ʂ����ꂪ�����āA�������ʖ{�̂悤�ȗl���ɂȂ������̂ł���B �@���Ƃ��A�s�����A���q�ׂ́t�Ƃ���̂́A�}�O�n���{�ɋ��ʂ���Ƃ���ł���A�܂������ɁA�}�O�n�^���n�����f���đ��݂���̂ł��邩��A����͎������V��i�K�ɂ������Ƃ݂Ȃ�������ł���B���ꂪ�A��ɂ܂ő��݂��Ă������A����Ɍ�ɂȂ��āA�s�����t�Ƃ������傪�E����ւ�A���邢�͌ꏇ����ʂ���ē`������̂ł���B �@���������āA���Ƃɓ�Ɩ{�E�א�Ɩ{�́A���́s�����A���q�ׂ́t�ɂ��ĒE���ψق��Ă���_�ł́A�㔭���������Ă���B����ɑ��A�ʂ����ꂪ�����ʖ{�������x���Ƃ݂���x�i�Ɩ{�́A�����A�������������̍��Ղ��c���Ă��邱�Ƃ�����B����́A����܂łɋ��������̏���ɂ���Ă��m���ł��낤�B �@�܂������āA���̍Z�قł́A�}�O�n���{�ɂ́A
�s�����n�A��i����^�_�j�͂₭���鎖�����B�͂₭�����Ƃ���o�t
�Ƃ����āA�s�����t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s�Ȃ��t�ƋL���B���̎���́A���n�ɋ��ʂ���Ƃ���ł��邩��A�}�O�n�^���n���敪����w�W�I���ق̈�ł���B�@�����A�}�O�n���{�ɂ����āA�s�����t�����ʂ���Ƃ��납��A����͒}�O�n�����ɑ��݂�������ł���B�����āA����͎ĔC���邪�`�����ꂽ�������V��O���ɑk�肤����ł���B �@�����A���n���{�ɋ��ʂ��āA�s�Ȃ��t�ƋL���Ƃ��납�炷��A���ꂪ���n�����ɂ��łɔ������Ă����ψقł���B�Ƃ���A����͎������V��O���ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���̌���ɑk�肤����̂Ȃ̂��B �@�������Ȃ���A�s�����t�Ɓs�Ȃ��t�ł́A���ӂ�����Ă��܂��B�������V�傪�O���Ɂs�����t�ƋL���A����ɂȂ��āA����Ƃ͈Ⴄ��́s�Ȃ��t�ƋL�����Ƃ͂��肦�Ȃ��B �@��������̏�ł��A�����́s�Ȃ��t�ł͂Ȃ��s�����t�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A�O�o���Ƃ̑��֊W�����邩�炾�B
�s��ɁA���@�̓��ɂ���āA�͂₫�Ɖ]�������t
�@���@�̓��ɂ����āA�����Ƃ������Ƃ́u�����v�A�����́A�Ȃ�����A�����邱�Ƃ́u�����v�A�ł���B���́u��i����^�_�j�v�Ƃ����[�����݂�A���̘A���\���ɂ����āA����ׂ��́s�Ȃ��t�ł͂Ȃ��A�s�����t�ł���B�s�����́A��i����^�_�j�͂₭���鎖�����t �@���������āA�������V��̒i�K�ł́A���肦�Ȃ��ψقł���B��������ƁA���́s�Ȃ��t�́A�������V��Ȍ�̔����ł���A���������ӂ̕ύX�ɂ������ٕςł��邩��A����͖�O���o��ɐ�������ʂł���B���̃v���Z�X��z�肵�Ă݂�A������O��Ɠ������A�����u���v���Ɓu�ȁv���̗ގ��ɂ���ǂł���B �@�@�@�u�����T�v���u�Ȃ��i�T�j�v���u�Ȃ��v �@�܂�A���̃v���Z�X�́A���������s�����T�t�́u���v�����u�ȁv�ƌ�ǂ��āA���̌��ʁs�Ȃ��t�Ɏ��������̂ł���B �@���n�����ʖ{�ɋ��ʂ��āA���́s�Ȃ��t���L���Ƃ���A���n���{�́A��O���o�㑁���ɂ��̌�ʂ������ʖ{�̖���ł���A���n�����ʖ{�̐�c�́A���̌�ʂ������C���Ŏʖ{�ł���B�����āA���q��Ɠ������A�����ł��ǂݎ��ׂ��́A���n���{�͕����̐�c���ʂɗL����̂ł͂Ȃ��A����̌��c��{�ɋA�ꂷ����̂ł���A���̌��c�����ꂽ��A���n���ɔh�������Ƃ������Ƃł���B �@���āA�����ЂƂA�Z�ق��w�E���Ă����B����͖{���A�}�O�n���{�ɁA
�s�l�̂ނ��Ƃ͂₫���ȂǂɃn�A���ނ��Ɖ]�āA�ÂɂȂ�A�l�ɂ����鏊�A�̗v��B�����T���A�H�v�b���L�ׂ�����t
�Ƃ����āA�s�����T��t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́s���S�́t�Ƃ�����̂�����B���邢�́A�ۉ��Ɩ{�̂悤�Ɂs���S�A�\�X�t�Ƃ�����̂�����B�@���̂悤�ɔ��n���{�̒��ɂ́A�ψق��������̂����邪�A�����A�x�i�Ɩ{�Ȃǂ̂悤�ɁA�s���S�t�Ƃ��āA�}�O�n���{�Ɠ������u�́v�����̑������Ȃ�������݂���B�܂�A���n�ɂ��A�}�O�n�Ƌ��ʂ���P�[�X������B�Ƃ���A�}�O�n�^���n�����f���ċ��ʂ́A���́s�����T��t�s���S�t���A�Ì^�ł���A�������V��i�K�܂ők�肤����ł���B �@���������āA�s���S�́t�Ƃ��邩�����́A���Ō�ɔ��������A��ネ�[�J���ȟ�����L�ł���B���̔����v���Z�X�́A�����炭�A�����ɒ������s�H�v�b���t�Ƃ�����ꂪ�A�Ȃ�Ƃ���ɒނ��Ĕ��������ψقł��낤�B �@�������A�s���S�t���A���ځs���S�́t�ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�ŏ��̕ψق́A���̉ӏ��ɂ���悤�ɁA�s���S�A�\�X�H�v�L�ׂ�����t�s���S�A�\�X�b���L�ׂ�����t�Ƃ�������̃p�^�[���Ɉ�������āA���s�\�X�t�Ɠ���Ă��܂����̂�������Ȃ��B����́A�ۉ��Ɩ{�Ȃǂ��`���邩�����ł���B �@�܂��ŏ��ɁA�e���ɂ��s�\�X�t�����Ă��܂����ʖ{������A����ɂ��̌�A���́s�\�t���������u�́v�i�\�j�Ɍ�ǂ��āA�s���S�́t�Ƃ���悤�ɂȂ����B���̃v���Z�X�ł́A�s���S�́t�͓I�ψقł���B �@���邢�͋t�̃p�^�[�����l������B�s���S�H�v�b���L�ׂ�����t�ł́A�����������ēǂ݂ɂ����������A�s���S�̍H�v�t�Ɓu�́v�����������Ă��܂����B���̎ʖ{���c�{�ƂȂ��āA�Ȍ�n���h�����o�ē`������̂��A�������ʖ{�̂������ł���B �@���̂����ɁA�ۉ��Ɩ{�̂悤�ɁA�s���S�A�\�X�t�Ƃ�����̂��������B���́s�\�X�t�́A�s���S�́t�́u�́v�i�\�j�����A�����ł͂Ȃ������ɓǂ��̂ŁA�͂��߂́u���S�A�\�H�v�b���L�ׂ�����v�ł��������A�u�\�v�ꎚ�ł͕s���ƌ����āA���ꂪ����Ɂs�\�X�t�Ɖ������ƁB �@���Â�ɂ��Ă��A����͔�ネ�[�J���Ȍ㐢�̕ψقł���A�㔭�I�ȓI��L�ł���B�������V��̒i�K�ł́A�u�́v�����u�\�X�v�Ƃ��������Ȃ������B���n�ł����o�㑁���ɂ́A�܂��s�����T��t���邢�́s���S�t�Ƃ�������ł������B�\�\���ꂪ��X�̏����ł���B �@ Go Back |
*�y�g�c�Ɩ{�z  �g�c�Ɩ{�@�Z�ىӏ�
*�y�g�c�Ɩ{�z  �ۉ��Ɩ{�@�Z�ىӏ� |
�@
�@�@�@10�@�����ᔻ�E���ƕ\
|
�y���@���z ��@�����ɉ��\�Ɖ]���B ���@�̎��ɂ���āA ���Â��\�Ɖ]�A���Â�����Ƃ��͂�B �Y�ɂ��A���Ƃɂӂ�āA �ɈӔ�B�Ȃlj]�āA��������ǂ��A �G�Ƃ������ӎ��̗��ɂ���ăn�A �\�ɂĐ�A�����ȂĂ���Ɖ]���ɂ��炸�B �킪���@�̂����֗l�n�A �n�ē����w�Ԑl�Ƀn�A���킴�̂Ȃ�悫�����A �����Ȃ�͂��A���_�̂͂₭�䂭�����A �����ɂ����ցA�S�̂���т����������o�A ���l�̐S�̂قǂ��鏊�����킯�āA ����^�_�ɁA�[�����̗����A ��ɂ�����邱�T���B ����ǂ��A���ق����n�A ����*�ɛ������鎖�Ȃǂ��A�o������ɂ�āA �����Ƃ��ӏ��Ȃ�����B(1) ����o�A���̒��ɁA�R�̉������Âʂ�ɁA �P���ւ䂩��Ǝv�փo�A���A���֏o����̖�B �����̓��ɂ���Ă��A ���̏o���Ƃ�����L�A�����o���Ă悫�����L�B ����̓��ɂ���āA �������������A���Â����������B �R�ɂ�āA�䓹��B�ӂ�ɁA ����㭕��ȂǁT�]�������̂܂��B �������w�Ԑl�̒q�͂������U�ЁA���Ȃ铹�������ցA ���@�̌ܓ��Z���̂����������̂����A ���̂Â��畐�m�̖@�̛��̓��ɓ��A �������ЂȂ��S�ɂȂ����A�䕺�@�̂����ւ̓��Ȃ�B �\�X�b�B�L�ׂ��B(2) |
�y������z ��@�����ʼn��\�Ƃ����� �@���@�̎��ɂ����āA�ǂ���u�\�v�Ɖ]���A�ǂ���u���v�Ƃ����̂��B�|�\�ɂ���ẮA�����邲�ƂɁA�u�ɈӔ�`�v�ȂǂƂ����āA���Ɠ����͂��邯��ǂ��A�G�Ƒō����Ƃ��̗��k�킢���l�ɂ����ẮA�u�\�v�ɂ���Đ킢�A�u���v�������Đ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B �@�䂪���@�̋������́A���߂ē����w�Ԑl�ɂ́A���̋Ƃ̏K�����₷���Ƃ������K�����A�[���̑����s�����k���l���ɋ�����B�S�̋y�Ȃ��k�����ł��Ȃ��l���Ƃ́A���̐l�̐S���قǂ���Ƃ�����������āA���掟��ɐ[���Ƃ���̗��k���l���A��ŋ�����̂ł���B �@����ǂ��A�����Ă��̏ꍇ�A���Ɓk�l�ɑΉ������i���ۓI�ȁj���ƂȂǂ��o�������邩��A�����������Ƌ�ʂ��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B �@����A���̒��ɂ́A�R�̉���q�˂čs���ɁA�����Ɖ��֍s�����Ǝv���ƁA�܂��i�R�́j�����w�o�Ă��܂����Ƃ�������̂��B �@�����Ƃ̓��ɂ����Ă��A�u���v�����ɗ��ꍇ������A�u���v���o���Ă悢���Ƃ�����B�i�������j���̐킢�̓��ɂ����āA�����B���A����\�ɏo�������i����ȉ����������{�����݂��Ȃ��j�B �@���������āA�䂪����`����ɁA����㭕��k�������Ԃ�A���吾���l�ȂǂƂ������Ƃ��D�܂Ȃ��B �@�i����Ȃ��Ƃ����j���̓����w�Ԑl�̒q�͂��������āA�^�������ȓ��������A���@�̌ܓ��Z��*�̈����Ƃ���k����l���̂Ă����A���̂Â��畐�m�̖@�k���@�l�̐^���̓��֓���A�^���Ȃ��S�ɂ��邱�ƁA���ꂪ�䂪���@�̋����̓��ł���B �@�悭�悭�b������ׂ��B |
|
�@ �@�@�y���@���z �@�i1�j���@�̎��ɂ���āA���Â��\�Ɖ]�A���Â�����Ƃ��͂� �@�����͌ܗ֏��̈�v���Ƃ݂�ׂ����ł���B���̈ꕶ�����ł��A�ܗ֏���ǂޒl�ł�������B�܂����������̎v�z�I�|�W�V������v�镶�͂ł���B���ꂾ���ɁA��������A������Ɠǂ�ł��������Ƃ���ł���B �@�܂��`���A�����́A
�s���@�̎��ɂ���āA���Â��\�Ɖ]�A���Â�����Ƃ��͂�t
�Ƃ����B���̔���@�ŁA�u�\�v���u���v���ƌ������p�����h���ے肷��̂ł���B�@�|�\�ɂ���ẮA�����邲�ƂɁA�u�ɈӔ�`�v�ȂǂƂ����āA���Ɠ��������ʂ��镗�K�͂��邯��ǂ��A���@�̓��A�G�Ƒō����Ƃ��̗��ɂ����ẮA�u�\�v�ɂ���Đ킢�A�u���v�������Đ�A�ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��B�\�\�Ɖ]���āA���Ԃ��͈����̂ł���B �@�܂�A�s�G�Ƃ������ӎ��̗��ɂ���ăn�A�\�ɂĐ�A�����ȂĂ���Ɖ]���ɂ��炸�t�B�\�\�قق��A�G�Ɛ荇���Ƃ��A�u�\�v�Ő킢�A�u���v�Ő�Ƃł������̂��ˁH�\�\�����̂����炳�܂Ȕ���ł���B�������A����͒P�Ȃ����ł͂Ȃ��A��������Ɏ��炵�߂�قǂ̎a����ł���B �@���ƕ\�i���邢�͓����j�ʂ���̂́A�U��̃p�[�X�y�N�e�B�������A�ɈӔ�`�����݂���Ƃ������o�Y����Ƃ����_�ŁA�܂������|���I�ȐU�����ł���B�����ɂ��Ă݂�A���̔閧�́u�ɈӔ�`�v�Ȃ���̂̂���Ƃ���A���͋���ۂȋ����Ȃ��̂ł���B �@���Ȃ݂ɁA���́u�\�v�Ɓu���v�Ƃ������t�́A�Ɖ��̕\�Ɖ����炫���B�g�ł���B�Ƃ́u�\�v�Ƃ����̂͊O���̂��Ƃł͂Ȃ��A�����ɋ߂��ڋq�̊Ԃł���A�u���v�Ƃ����͓̂����̎��I��Ԃł���B�u�剜�v�ȂǂƂ����̂́A�܂��ɂ���ł���B �@�u���v�͊O�ɔ邷��Ԃł���B�u���v�Ƃ����̂͌����ł̓v���C���F�[�g�iprivate�j�Ƃ����ӂ����A���Ƃ́A�閧�isecret�j�E���iconfidential�j�̈ӂł����āA�u���Ɂv�Ƃ�������́u�Ђ����Ɂv�Ɠǂނ̂ł���B����䂦�A�E�f�̂悤�ȉA���`���i���Ɠ`�j�Ɂu�A�V���@���v�Ƃ����^�C�g���̈ꏑ�����肤��̂ł���B �@�������āA���@�̓��Ɂu�\�v���u���v���Ȃ��Ƃ��������́A���ꂾ���ł��A�]���I�isubversive�j�Ȏv�l�������̂ł��邪�A����ŁA�ɂ߂ăI�[�v���Ȑ��E���A���@�̓��ɍ\�z���Ă���̂ł���B �@�䂪���@�̋������́A�\�\�ƕ����͉]���\�\���߂ē����w�Ԑl�ɂ́A���̋Ƃ̏K�����₷���Ƃ������K�����A�[���̑����s�����k���l���ɋ����A�S�y���A�����ł��Ȃ����Ƃ́A���̐l�̐S���قǂ���Ƃ�����������āA���掟��ɐ[���Ƃ���̗��k���l���A��ŋ�����̂ł���A�ƁB �@�S�̋y�ѓ���Ƃ́A�����̋y�Ȃ����ƁA�����ł��Ȃ����ƁA���̐l�̐S���قǂ��鏊�Ƃ́A���̐l�������ł������ȂƂ���A�Ƃ����قǂ̈ӂł���B���́u�S���قǂ���v�́A�����[���\���ł���B�������邽�߂ɂ́A������W���Ă���S��������K�v������Ƃ����킯�ŁA����̗����T�O�Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�̂ł���B �@���āA���������������A����w�I�ipedagogical�j�ɓǂނ��Ƃ͉\�ł��낤���A���@���{�Ƃ����ܗ֏��̐��i���炵�āA���ۂ��̂悤�ɓǂ߂�Ƃ���ł���B�����������́A����Ε����́u�@�v�A����̋@���ɉ����ċ����������܂��܂���A�Ƃ���`���ɉ����Ă���ɂ����Ȃ��B���ꎩ�͕̂����I�Ƃ͈����Ȃ��B
�s����ǂ��A���ق����n�A���Ƃɛ������鎖�Ȃǂ��A�o������ɂ�āA�����Ɖ]���Ȃ�����t
�@�����͉]���A�\�\����ǂ��A�����Ă��̏ꍇ�A���Ɓi���ԁj�ɑΉ��������ƂȂǁA���ۓI�Ȃ��Ƃ��o�������邩��A�����������ƍ��ʁk����ׂl���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���A�ƁB�����������̃��W�b�N�̖ʔ����Ƃ���ł���B�@�Ƃ����̂́A����w�I�ȁu�@�v�ł���A����̋@���ɉ����ď��X�Ɏ����ǂ��ċ����Ă����Ƃ�������������킯�����A�����̌����̂́u�@�v�ł͂Ȃ��A�u�Ύ��v�Ȃ̂ł���B �@�����Ō������Ă͂Ȃ�Ȃ��|�C���g�́A�����̎����`���炷��A�G�Ɛ荇���Ƃ��́A���Ƃ����S�̎҂ł����Ă����ׂ����@�͂����āA�����������Ƃ������ƂȂ̂ł���B �@���Ƃ��A���w�̎�N�ł����Ă��A���ł́A�n���̒B�҂Ƒ������Đ키���Ƃ�����B���̂Ƃ��A���͎�N���n�ł��̂Łc�ƌ�������Ă͂���܂��B��N���n�ł����Ă��A�G�����Ƃ��ŎE�����Ƃ��ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�悤����ɁA��B�҂łȂ��ẮA������E���Ȃ��悤�ł́A����I�ȋ����Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B���S�҂ł����֏o��B�������ܐ퓬�ɎQ������B�����ł����Ă݂�A���̂Ƃ��A�r�O�̏�艺��͘_�O�ł���B�u���֏o��̂͏\�N�����v�ȂǂƗI���Ȃ��Ƃ͌����Ă͂���Ȃ��B���S�҂ł��G�ɏ����˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A���@�����̓��A���̝|�ł���B �@���̓_�ł́A���Ƃ��Ζ����@��w���@�Ɠ`���x�ɁA�\�\��i�����j�ƉƂ��ԈႦ��ȁA�Ƃ͖��ʂ��Ă��̉��ɂ�����̂����A�Ƃ��������Ɖ��ٕ̕ʂƂ͈قȂ��Ă���B�����͂����������Ɖ��̋�ʁA�\�\�U��̃p�[�X�y�N�e�B���ɂ�鉜�s���E�[�݁\�\��o���̂ł���B �@�Ƃ�����A�����ł͕����́A�u�@�v�ł͂Ȃ��A�u�Ύ��v�̋����ɂ���āA���H��`�I�ȍs�ט_�̑��ɗ����āA����Γڌ�@��̂���Ɏ����A�v���Z�X�Ȃ��v���Z�X�iprocess without process�j�������Ă���B���ꂪ�����̃I�[�v���ȓ��̋�̓I�Ȏp�ł���B�Ɠ����ɁA�����������ƍ��ʁ^��ʂ���A���������U�����������炷���o�́A�U��̃p�[�X�y�N�e�B����f�����āA���̌��z����������������̂ł���B �@���̈Ӗ��ŁA�ܗ֏��́A���Ղȓ��发�̊�������Ă��Ȃ���A������A���̂悤�ɑ��ɔ䌨������̂��Ȃ��قǃ��f�B�J���ł���B�������A�����̎v�l�������I�����炱���A���̂悤�Ɍ��������f�B�J���Ȃ̂ł���B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
���������{�Q�� �� �@�ٖ{�W�@ ����R�@���̉@  ����@���@�A�V���� �A���@���Ɠ`  ����E�ɈӁE�_���� �V�A�����@�ژ^
�s���� |
|
�@���̉ӏ��̍Z�قɂ��āA�w�E���Ă����͈̂ȉ��̏��_�ł���B �@�܂��A�}�O�n���{�ɁA
�s���T��̂���т����������o�A���l�̐S���قǂ��鏊�����킯�āt
�Ƃ����āA�s�S�́t�Ƃ���Ƃ���A�}�O�n�ł͓n�ӉƖ{�Ɣ��n�̎�앶�ɖ{���A�u�́v���𗎂Ƃ��Ă���B����͒P�Ȃ�E���ł��낤�B���n���{�ł��A�u�́v���̕����L���Ă���ʖ{������B�@������ɁA���́A���n�ʖ{�̒��ɂ́A������s�S���t�Ƃ��āu���v�ɍ����̂����邱�Ƃł���B���̓_�͂��������B �@�ނ��A�}�O�n�ɂ́s�S���t�Ƃ���Ⴊ�Ȃ��B�}�O�n�^���n�����f���ċ��ʂ���̂́A�s�S�́t�̕��ł���B���������āA���n�ł��{���́u�́v���ł��������A��X�ɂȂ��āA�u�́v�����u���v���Ɍ�L������̂����ꂽ�Ƃ������Ƃł���B����͌�ʂ̂������ł���B �@���̌�ʂ�L����̂́A��Ɩ{�ƍא�Ɩ{�ł���B����͂���A�Ǘ���ł���A���҂͌n���������炵�ċ߉��W�ɂ���A�u�́v�����u���v���ɕψق�����̎ʖ{�ł���B���������āA���́u���v�Ƃ����ꎚ����������̂́A���n���{�̂Ȃ��ł��㔭����������Ɩ{�E�א�Ɩ{�̃|�W�V�����ł���B �@�Z�قɊւ��āA������́A�}�O�n���{�ɁA
�s���ق����n�A�����ɛ������鎖�Ȃǂ��o������ɂ�āA�����Ɖ]���Ȃ�����t
�Ƃ����āA�s���Ƃɛ������鎖�t�Ƃ��āA�s���Ɓt�ƋL���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s�����Ɓt�Ƃ��āu���v�k���́l�Ƃ�������t����B���́A���̑��قɊւ��āA�ǂ����邩�A�ł���B�@�ЂƂ́A�}�O�n���{���z��n�܂ŋ��ʂ���Ƃ��납��A�s���Ɓt�͒}�O�n�����ɂ��łɂ��������̂Ƃ݂Ȃ����邱�ƁB����������A����͎������V��i�K�̑O���ʖ{�ɂ��������̂ŁA�{���͂��ꂪ�Ì^�ł��邱�ƁB �@����́A���n�x�i�Ɩ{�̎�����݂�킩��B�Ƃ����̂��A�x�i�Ɩ{�ł́A���̉ӏ����s��Ɂt�ƋL���Ă��邩��ł���B�܂�A����́u���ƂɁv�Ƃ��������̂��u��Ɂv�Ɠ��Ď��������̂ł��낤�B������A�s���Ɓt�Ƃ�����Ɉق��������҂��A�ʂ̏C�������݂��̂ł���B �@���������āA�x�i�Ɩ{�́s��Ɂt�Ƃ�������́A�َ��ɒu�������㔭�I�ψق����A�����A����́A�����̎ʖ{�ɂ́A�u���ƂɁv�Ƃ��������Ղ��������̂ł���B���n�ł��A�����ɂ́s���Ɓt�ƋL�����@�[�W�������������̂ł���B �@����������A�����Ɂu���v����t������̂́A���n�����ɂ͂Ȃ����������ł���B�܂�A�������V��i�K�Ȍ�̂��̂ł���͖̂ܘ_�A���o��Ɠ�������O���o�サ�炭�����Ă̍�ׂł���B���n���{�̑����͂���������āA�u���v����t�������̂�`�����q���Ȃ̂ł���B �@�������A�ǂ����Ă��́u���v����}������悤�ɂȂ����̂��B����́A���̕������s���Ƃɛ������鎖�t�Ƃ����āA�u���Ɓv�Ɓu���v�Ƃ������傪�d������̂Ɉ٘a���������҂��A���̂悤�ɂ����̂ł���B�Ƃ��낪�A�u���̂��Ɓv�Ƃ���ƁA���ꂪ�u�ǂ̂��Ɓv�Ȃ̂��A�������ĕ��ӂ��s�ʂɂȂ��Ă��܂��B �@���Ƃ��A�ŏ��́u���Ɓv�ƌ�́u���v�ł́A���̌�̈Ӗ����Ⴄ�B�O�́u���Ɓv�́A���Ƃ��A�u�܂ɂӂ�A���Ƃɐ��Ёv�ȂǂƂ����ꍇ�́u���Ɓv�ł���B�܂�A�s���Ƃɛ������鎖�t�Ƃ́A�u�ɑΉ��������v�Ƃ����Ӗ������ł���B�u���̎��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B �@���������āA�������e�̃I���W�i�������̂悤�ȈӖ��ŏ����ꂽ���̂ł��낤���A���Ȃ��Ƃ��A�������V�傪���������i�K�ł́A���ꂪ�ۑS����Ă����B�������V��́A�����Ɂu���v�Ƃ������傪�d������̂ɒ��ӂ��āA�킴�킴�O���u���Ɓv�Ɖ��������ɂ��āA�ԈႢ�Ȃ����Ƃ��������̂����A������Ă̒�A���n�̎q���́A�̐S�̂Ƃ�����Ԉ���Ă��܂����̂ł���B�������A������肩�A��ɁA�]�v�Ȃ��Ƃ��l����҂��o�āA�����Ɂu���v����}������悤�ɂȂ����̂ł���B �@�Ƃ�����A�ȏ�̂��Ƃ���A��X�̃e�N�X�g�́A�ނ��u���v���̂Ȃ����@�[�W�����ł���B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
*�y�g�c�Ɩ{�z�@�s���l�̐S���t
*�y�g�c�Ɩ{�z  �g�c�Ɩ{�@�u���Ƃɛ������鎖���v |
|
�@�ȏ�̉�͌��ʂ��ӂ܂��āA��߂̖���Еt���Ă������Ƃɂ���B�܂��́A��L�̉ӏ��\�\�܂�A�s���ق����n�A���Ƃɛ������鎖�Ȃǂ��A�o������ɂ�āA�����Ɖ]���Ȃ�����t�Ƃ��镔���ł���B �@��g�Œ��L�́A�u���Ɓv���u�����Ɓv�ƋL���א�Ɩ{�̕����ɂ��������āA�u�����Ɓv�Ƃ͉������l�����炵���A������u�G�Ƒł��������̗��v���Ɖ����Ă��邪�A����͌��ł���B �@���������A�א�Ɩ{����M���Ă��邩��A�����Ɂu���v�����Ȃ������ȂǂƂ������ƂɋC�Â������Ȃ��B������A�u�����Ɓv�Ƃ́u�ǂ̂��Ɓv���ƍl�����킯�ł���B�������āA�P�o�����̂��A�u�G�Ƒł��������̗��v�ł���B �@�������A�{�������ɂ́u���v���Ȃǂ͂Ȃ��B���ۂ́u���Ɓv�ł����āA��q�̂悤�ɁA�ɑΉ��������A�܂���ۓI�Ȃ��ƁA�Ƃ����Ӗ������ł���B �@��g�Œ��L�́A�ܗ֏��̐������ʖ{��ʗ���r����Ƃ����K�{�̑O���Ƃ����Ă��Ȃ�����A����Ȍ�ǂ����邱�ƂɂȂ�B�����������Ƃł́A��g�ł��u�ܗ֏��v���̂��鎑�i�͂Ȃ��B �@����ɁA���̕����̌����������ɁA�����͂ǂ���א�Ɩ{�i��g�Łj�����m��Ȃ�����A���́u���̂��Ɓv�ɓ�a�����悤�ł���B �@�܂��A��g�Œ��L�ȑO�́A��O�̐Γc��Ɛ��̐_�q����݂�A�Γc��́A�u���D���c�Ă̎����S��������v�Ƃ��Ă���A����͂����ɂ��Ӗ�ł����āA�u���̂��Ɓv�Ƃ�����L����ɁA���킵�Ă���B���̐_�q������l�̎d�V�ł����āA�u���ۂɑ̌��������Ƃ�ʂ��āA���������Ă���v�Ƃ��Ă���B�������u�ʂ��āv�ȂǂƂ������ӂ͂����ɂ͂Ȃ��B�_�q����L�̒���ł���B �@���̎���ŁA��҂ɂƂ��āA�����������ɓ�ł��邩����ł��낤�B���Ƃ��Ɓu���v�����Ȃ��Ă��A�Ӗ����ʂ��镶������A���ǁu���v�������āA�Γc���_�q��̂悤�ȈӖ�ɂȂ邵���Ȃ��B �@���́A��g�Œ��L�Ȍ�̌��҂ł����āA��͓���́A�Γc��Ɛ_�q�炻�ꂼ�꒸�Ղ��Ă��邪�A�u�G�Ƒł������Ƃ��ɑ̌��������Ɓv�ƋL���Ƃ�����݂�ɁA��g�Œ��L�̌��ɂ��Ȃ�N�H����Ă���B���̊��c��́A�_�q����p�N���A��g�ł̌�߂����Ղ����Ƃ����Ƃ���ł���B������܂��A�ߔN�̂��̂قnj��̓x������������Ă���Ƃ�������ł���B �@�܂��A�ʂ̖��ӏ�������A�s�Y�ɂ��A���Ƃɂӂ�āA�ɈӔ�B�Ȃlj]�āA��������ǂ��t�Ƃ���������ł���B �@���̂�����A����������́A�����ɖĂ��邩�B��O�̐Γc��́A�u��������v�Ƃ��āA�u���v�Ƃ���������Ă���B��O����A���́u�����v�ɂ͈ق�������P�[�X���������Ƃ݂���B����ɑ��A���̐_�q��͈Ӗ��A�������B �@������ɁA���̌�o����g�Œ��L�́A���́u�����v���u���������v�ƈ��ɓǂ݁A�u���V�ɒʂ�������v�Ɖ����Ă��邪�A��������炩�Ȍ��ł���B�^�C�g���Ɂu�����ɉ��\�Ɖ]�ӎ��v�Ƃ���悤�ɁA����́A�u���ƕ\�v�Ɠ������A�u���ƌ��v�A���^�����Ƃ����Βu�ł���B �@��g�Œ��L�����̂悤�Ɂu���V�ɒʂ�������v�Ƃ���̂́A��q�̂悤�ȁA���������Ȃ��Ƃ��������̘b�̋������Ă��Ȃ��؋��ł���B �@������͓���́A�������Ɋ�g�Œ��L�̖����Ȍ�߂͍̂炸�ɁA�_�q��Ղ��������̂��̂����A���c��́A��ɂ���ĉ��̍l�����Ȃ��ɁA��g�Œ��L�́u���V�ɒʂ�������v�𗬗p���āA�����Đ��Y���Ă���B �@�����ɂ��A����Ȗ��m�ȕ����ł��A��߂��˂��Ђ˂��āA�Ӗ����c�Ȃ����̂ł���B�����́A�����̌��ɂ��邲�Ƃ��A���ɁA�܂�܂������ɁA���`�ʂ萳�����ǂ߂悢�Ƃ���Ȃ̂ł���B �@ Go Back |
*�y������z
*�y������z |
|
�@ �@�i2�j����̓��ɂ���āA�������������A���Â���������� �@�őO�́A�����������ƍ��ʂ���A���������U�����������炷���o�́A�U��̃p�[�X�y�N�e�B�������q���������A�����������f�B�J���Ȍ����������Ƃ���܂Řb���i�B �@����A�\�\�ƕ����͉]���\�\�R�̉���q�˂čs���ɁA�����Ɖ��֍s�����Ǝv���ƁA�܂��R�̓����w�o�Ă��܂����Ƃ��A���Ԃɂ͂���A�Ƃ����B���i�����悤�Ƃ��āA���̂ق��֍s���Ă݂�ƁA���͂����͂��Ƃ̓����������\�\�B����́A�R�s�ɂ͂�������A�~�X�e���A�X�ȑ̌��ł���B����ł��o���������ȕs�v�c�ł���B���̂��Ƃ�O��ɕ����͌���Ă���̂ł���B �@�����������ŕ������������Ă���̂́A���̏C�s���A����Ɠ����\���������Ă���A�Ƃ������Ƃł���B����͌����āA���s���̂���p�[�X�y�N�e�B���̒��̃��j�A�ȃv���Z�X�ł͂Ȃ��B���������������ʂ��Ƃ������̋�ԂƂ́A����g�|���W�J���ȕ��ʋ�Ԃł���B �@���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�̂��猾���Ă������Ƃł���B�Ƃ��ɕ����̏C�s�_�ɂ͂��̎�̋����͑����������B�����Ɠ�����̐l�ł��A����@�d�Ȃ�\�\���������t�[�K�̂��Ƃ��\�\�E�f�̂悤�Ȍ��㑦�����̍\�������ł��낤�B���^�̍\���́A�����@��w���@�Ɠ`���v�ł��~���������Ă���B �@�������Ȃ���A���ꂪ�S�@�_�ɊҌ�����Ă��܂����Ƃɂ́A�����͓��ӂ��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B����Ӗ��ŁA���Ɠ����̖����فE�����ʂ���邱�Ƃ́A�������łɒʑ��I�Ȗ��^�����ł������B �@�O�Ɍ����悤�ɁA�ܗ֏��`���A�n�V�����������ɂ����Č���Ă����̂́A�\�\�O�\���z���ĉ䂪�ߋ���U��Ԃ��Ă݂�ƁA����͕��@���ɂ܂��Ă����̂ŏ������A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ������B���R�ƕ��@�̓��̓����������āA�V�̌����𗣂�Ȃ����������ł��낤���B���邢�́A����̑����̕��@�Ɍ��ׂ����������炾�낤���B���̌�A�Ȃ����[��������Ƃ��āA���ɗ[�ɒb�����Ă������A���ǁA���g�����@�̓��ɂ���ƓK���悤�ɂȂ����̂́A�\�̍��ł������B������ȗ��́A�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ��āA�Ό��𑗂��Ă����̂ł���A�]�X�B �@�ܗ֏��`���̕��͂ɂ݂��邱�̃��[�v�\���́A�ܗ֏��{�������̂����ɂ����āA�R���ƎR���̃��[�v�\���Ƃ��Ĕ�������Ă���̂ł���B�ܗ֏����\���I�ɓǂ܂��K�v�����鏊�Ȃł���B����䂦�ɁA���́u�����ɉ��\�Ɖ]���v�̈ꕶ�́A���V�������̕��ł��邪�A�ܗ֏��̋����S�̖̂�������ߊ���ɂӂ��킵�����e�ƂȂ��Ă���B
�s����̓��ɂ���āA�������������A���Â����������t
�@���́u�킢�̓��v�����āA�铽���B���ׂ������̂��Ȃ��B����͋ɂ߂āu�����I�v�Ȑ錾���e�ł���B���@�A�킢�̓��ɁA�������������Ȃ��B���Ȃ킿�A�킢�̓��̍������͕��ՓI�Ȃ��̂ŁA���l�ɂ��B����Ă͂Ȃ炸�A���炩�ɂ��ׂ����A�Ƃ����̂������̃|�W�V�����ł���B�@���̋���ׂ��J�����A�O�ꂵ���J�����iopenness�j�́A����܂ł̌��p�����h�̖������A���̒����I�Ȗ��������������������͂��̂��̂������B
�s�R�ɂ�āA�䓹��B�ӂ�ɁA����㭕��ȂǁT�]�������̂܂��t
�@����`����ɁA����㭕��k�������E�Ԃ�l�ȂǂƂ��������D�܂Ȃ��A�ƕ����͉]���B���Ȃ킿�A����ŕ����͉����������Ȃ��ƁA�{�C�Ō����Ă���̂��킩��B�@�����������Ȃ��Ƃ����̂��A�����̒m�I�t�@�b�V�����ł���B���������Ȃ���A���ۂɂ͓��傩�牜�`�֎��鉜�s���̂���p�[�X�y�N�e�B����\�ۉ��o���Ă�����̂��قƂ�ǂ������B�����������s�s��v�́A����������̂ŁA�܂��ɁA�s�ׂ����t�𗠐��Ă���̂ł���B �@�����ЂƂ́A�����������Ȃ��ƌ����Ȃ���A�`���̔閧����ێ����邱�Ƃł���B����ɑ��A�퓬�����̂����ɔ铽���B���ׂ������̂��Ȃ��Ƃ����A�����́u�閧�Ȃ��v�̃|�W�V�����́A�]���I�isubversive�j���v���I�irevolutional�j�Ȃ��̂ł���B���̃|�W�V�����ɑΉ����āA�����قǂ́A����㭕��ȂǍD�܂Ȃ��A�Ƃ����ꌾ������B �@�܂��ɁA���́u����㭕��v�����A���p�����h�̖������̏ؕ��Ȃ̂ł���B �@����̎��A���邢�͈���鎞�A��q�͋N�����i�����j�\�\��������L���A���������j������A�_�����Ă����܂Ȃ��A�Ƃ������e�̏���̕����\�\���t���ɒ�o����B�u���������v�Ƃ���̂́A�����������_�ɂ����Đ����A�u�E�̞��X�����w�ҁc�c�_�������e��֎Җ�B���N�����@���v�Ɛ錾����`���ł��邩�炾�B�ꗬ���`�ɂ����āA�Ƃ��Ɂu���v�ɂ��Ă͔閧����ŁA�e�q�Ƃ����ǂ����������邱�ƁA���ꂪ�d�v���ڂł���B �@�E�f�̓���ƍN�̐V�A�������i���\�O�N�܌��O���@�����A�n�����@�����j���ɂƂ�A�V�A�����`�̎��A������ȑO�A�e�q��嫂��������ׂ��炴�鎖�A�@���ɑ��đa�ӂ��炴�鎖�A���̎O�����ɂ��āA�������̐������U��ł���A���{�����̑召�̐_�X�A���Ƃɖ����x�V�k�܂肵�Ă�A���|�̐_�l�̐_���������͖ւ�ׂ��ł���A�Ƃ������e�ł���B �@���̕��K�́A���|�ɂ����炸�A�ǂ�Ȍ|�\�ł��A���邢�͊w��ɂ����Ă��A�d�v�ȋV���ł��������A����͕����Ȍ���A�ߐ���ʂ��đ��������̂ł���B �@����́A�u�����v�̂��Ƃ���ł͂Ȃ������B��������A�����o�߂��A���������@���`�d���L�܂��Ă����ɂ�A����������������㭕����s���A�����������ł��s����悤�ɂȂ����B���Ƃ��A�z��̓�V���ł͂��ꂪ�s���Ă����B�ߔN��X�����@�m�F�����j���̂Ȃ��ɁA�������̎��Ⴊ�݂���B  ��V���@���@������N �@��f�́u����v�́A�z�㍕��̂��̂ŁA���@��V���Ə̂������������t�̕����ł���B�����̌�����N�i1865�j�ɁA�t����ⷁk���т�l�╽�Ɉ��āA��l�Z�����A���Œ�o�������吾�ł���B��l���̉��ɂ��ꂼ�ꌌ���������Ă���B �@���̐���̓��e���݂�ɁA���`�����������Ȃ��Ɗ��ӂ���ɂ͂��܂�A���F�̓��Ɏ��ׂ����A���`���e�𑼂։k�炳�Ȃ����A�t�̖Ƌ��Ȃ����́A����q�Ƃ����ǂ��A���`�i�d�`�j���Ȃ����A�t�ɑ��A�������������Ձi�����ɐڂ���j�S���̂���܂������A���p�̍����������Ė��S�̌��������Ȃ����A��������Ȃ����A�\�\�ȏ�̏��X�ɂ����w���ꍇ�́A���V���ׁA�l��V���A�y���ē��{�����̑召�̐_�_�A�Ƃ��Ɏ����̎��_�̌�㭂�ւ�܂��悤�ɁB����Đ_��A���̔@���B�\�\�Ƃ����킯�ŁA�_�ɐ����Ă̐���ł���B �@���̒��g������ɁA���`���e�𑼂։k�炳�Ȃ����A�t�̖Ƌ��Ȃ����́A����q�Ƃ����ǂ��A���`�i�d�`�j���Ȃ����A�t�ɑ��A�������������Ձi�����ɐڂ���j�S���̂���܂������A�Ƃ���̂͑����̓��吾���ƕς�Ȃ��B �@�������A���F�̓��Ɏ��ׂ����Ƃ��������I�ȏ�����A���p�̍����������Ė��S�̌��������Ȃ����A��������Ȃ����A�Ƃ�������̍s���K�͂�����B����͋ߐ������̐���㭕��ɂ͂Ȃ��������A�����ɂȂ�Ƃ����������܂Ő��荞�ނ悤�ɂȂ����炵���B �@�Ƃ�����A����͈�Ⴞ���A���������@�̖���ɂȂ�ƁA�����������Ԃł��������Ƃ��m���B��t�����́A���������Ȃ��Ƃ��āA����㭕������������̂ɁA����𗠐銵�s���������̂ł���B �@�������A������������㭕��͑����ł͕��ՓI���s�ł����āA���������������ɓ��������܂łł���B������t�ɉ]���A�����̌ܗ֏��̌������A�����Ɉٗ�œˏo�������̂ł��������A���ꂪ�m����̂ł���B����͕��������������ł���ێ��s�\�ȁA���f�B�J���Ȕ��[��ł������B��قǁA�������̋���ׂ����J���́A�����I�Ȗ��������������������͂��̂��̂������Əq�ׂ��A���́u�͂��̂��̂������v�Ƃ́A���̂��Ƃł���B �@�܂�A�����͂��܂��܂ȋǖʂŁA�����Ƌߐ��̊Ԃ̕s�\�ȋ�Ԃ��J�����A���ł���}��ҁivanishing mediator�j�̃|�W�V�����������B�܂��ɂ��́A�����I�Ȗ��������������������͂��̂��̂��������A���̉\���̊J�������āA�s�\�ɂ��Ă��܂����̂��ߐ��̗��j�������B �@����䂦�A�����̎v�z��ǂނƂ́A�܂����������Ƌߐ��̊ԂɈ�u�o�������A����\���́A���肦������i��ڌ����邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�ܗ֏������A���������s�\���ւƕ��ꂽ�\���̏��݂���������_�A��ނȂ��j���Ȃ̂ł���B �@�����Ō�߂̖���������A�s���@�̌ܓ��Z���̂����������̂����t�Ƃ���u�ܓ��Z���v�̂��Ƃł���B �@���́u�ܓ��v�Ƃ͕�����ŁA�O�������O�̋ƈ��ɂ���Đ������i��������������̏����E�A�n���E��S�E�{���E�l�ԁE�V��̌܂ƂȂ�Όܓ��A����Ɉ��C����������ĘZ���B��A�Z��Ƃ������B����Ɏl�̌��̐��E�i�����A���o�A��F�A���E�j�����킹�ď\�E�ƌĂԁB �@�����ł����u�ܓ��Z���v���������������I�`���܂������t�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��邪�A�Ƃ��Ɂu���@�̌ܓ��Z���v�Ƃ́A���@�ɂ���������̏����E�Ƃ����ӂ��Ƃ��Ă��A����͂Ȃ��Ȃ��Ӗ��[���Ȃ�\���ł���B �@�Ƃ����̂��A�����͑O�ɐ���㭕��̂��Ƃ��L���Ă���킯������A�����j��ΐ_���̔����悤�Ƃ��������ɑ��āA�n���E��S�E�{���̎O������܂ދƈ��ʂ́u�ܓ��Z���v�Ȃ�����������Ă��邩��ł���B �@�u�ܓ��Z���v�̂悤�Ȃǂ��Ղ�l�Ԃ̏�O���܂��j�I�����I�`����w�i�ɂ����X�y�V�t�B�b�N�Ȍ�ł���B������A���̕����ł́A�u�ܓ��Z���v�Ƃ����ł̂����͖����ł��Ȃ��B �@������ɁA���������������ɁA����ǂ���ł͂Ȃ��B�t�ɁA�̐S�́u�ܓ��Z���v���瓦���Ă���̂ł���B �@��O�̐Γc��́A�s���@�̌ܓ��Z���̂��������t���A����Ɂu�l�X����y�v�ƖāA�Ŕ����ɂ��������B����ŁA�u�ܓ��Z���v�̌�ӂ����錻����̘H�����~�݂��ꂽ�悤�ł���B���ɂȂ�ƁA�_�q��́u�ܓ��Z���v���A�u���Ԃ̂��܂��܂ȗ��V�v�Ƙc�Ȃ��Č�߂����B �@����Ǝ��Ɋ�g�Œ��L�́A�s���@�̌ܓ��Z���̂��������t�ɂ��āA�u���@���w�Ԃ����ɐg�ɂ����_�A�ŕȁv�Ɖ��߂����B����́u�ܓ��Z���v�Ƃ����[����������߂ŁA�ނ��떾�炩�Ȍ��ł���B�������A��͓���E���c��́A���̊�g�Œ��L�̃p�N���ŁA�_�q����ނ�������g�����Ă���̂ł���B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
*�y�s���q�_���^�z
*�y�n�V�������z  �����x�V���@����R���ّ�  ����ƍN�@�V�A������ �����@�����@���\�O�N  ����ƌ��@�V�A������ �����@�鈶�@���i�Z�N
*�y����z  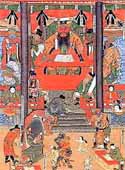 ����@���{���F�Z���G ���O���}����
*�y������z |
|
�@���āA�Z�قɂ��āA�����Ŏw�E���Ă����ׂ��͎��̓_�ł���B �@���Ȃ킿�A�}�O�n���{�ɁA
�s��������ɂ���āA�������������A���Â����������t
�Ƃ����āA�s��̓��t�Ƃ��āA�u���v�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s��̗��t�Ƃ��āA�u���v�ł͂Ȃ��u���v�i�܂��́u���v�j�Ƃ�������p���Ă���B����́A�}�O�n�Ɣ��n����悷�閾�m�Ȉ�����������ق̈��ł���B�@���̂����A���n���{�́A�x�i�Ɩ{��~�����n���{�Ɏ���܂ŁA�u���v�܂��́u���v�Ƃ������ł��邩��A����͔��n�����ɂ��������̂ł��낤�B�����A�}�O�n���{���A�z��n�܂Ŋ܂߂āA������u���v�Ƃ��邩��A�}�O�n�����ɂ�������ł���B�������������V�傪�ĔC����֓`�������O���ܗ֏��ɂ������Ƃ݂Ȃ�����Ƃ���ł���B �@���������āA���́u���v�Ɓu���v�̑��قɂ��ẮA�}�O�n�̏��������܂���ł���B�������A���ꂪ�������V��O���ƌ���̑��قƂ݂Ȃ����邩�A�ƂȂ�ƁA���̉\���͂Ȃ��B����́A�u���v���K�Ȍ�ł��邩�A���������ǂ�킩��B �@���Ȃ킿�A�����ŕ������]���Ă���̂́A�܂��Ɂu���v�̏C�s�̂��Ƃł���B�\�\���̐킢�́u���v�ɂ����āA�����B���A����\�ɏo�������i����ȉ����������{�����݂��Ȃ��j�B���������킯�ŁA�䂪�u���v��`����ɁA����㭕��ȂǂƂ������Ƃ��D�܂Ȃ��B�\�\�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�����ɂ́A�u���v���邢�́u���v�Ƃ�����̓���]�n�͂Ȃ��B �@����䂦�ɁA���ӂ��炵�Ă��A�s��̗��t���������V��ɂ�����̕ύX�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ނ��뎛���Ȍ�A�����Ė�O���o��̑����ɂɔ��������ψقł���B �@�ނ��A����͋����I�Ȍ�ʂł���B���n���{�������ȂׂĂ���ȋ����I�Ȍ�L����p���ł���Ƃ�����݂�ƁA��͂���n���{�̌��c��{�Ƃ������̂̑��݂��A�����ł��z�肹��������Ȃ��̂ł���B �@�܂�A�J��Ԃ��A���n���{�͕����̐�c�����̂ł͂Ȃ��A���錳�c�ɊҌ�������̂ł���B���̌��c�́A��O���o�㑁���ɔ���������ʖ{�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ�����A�����Ō�߂̖��Ɉڍs����A�א�Ɩ{���͂��ߔ��n�ʖ{��������āA���̏��{�Ƃ̔�r�ƍ���ӂ��Ă���悤�ł́A���ꂪ�s��̓��t���Ƃ͋C�����Ȃ��B������ɁA���̂悤�Ɂs��̗��t�Ƃ���א�Ɩ{�i��g�Łj�����m��ʂ͂��̊���������ɁA��̂Ȍ��ۂ������Ă���̂��ʔ������Ƃł���B �@�܂�A��O�̐Γc��ɂ����āA�s��̗��t�Ƃ�����傪�ǂ����֏����āA�u���@�̓��v�Ƃ��Ă���̂ł���B����͂����炭�Γc��̈Ӗ�Ƃ��������A�����𒉎����������߂ɐ����������I�ȍ���ł���A���u���@�̓��v�Ə����Ă��܂����̂��낤�B �@��������̂Ƃ����̂́A���́u���@�̓��v�Ƃ����ꂪ�A���̐_�q��ɍČ�����Ă��邱�Ƃł���B�_�q��́A������s��̗��t���Ӗāu���@�̓��v�Ƃ����Ƃ��v���Ȃ��B����ɁA�Γc��Ȃǐ�O��̌����Đ��Y�����ɂ����Ȃ��悤�ł���B �@��͓���́A�����ł́A�_�q��Ղ��邱�Ƃ͂Ȃ��A��g�Ńe�N�X�g�ɉ����āA�u�킢�̓����v�Ƃ����B�������ł͕��ӕs�ʂ����A����ɂ͈�����\���Ȃ��ł���B���c��́A��ɂ���Ă�����_�q��̃p�N���ŁA�u���@�̓��v�Ƃ���B��͓���̂悤�Ɋ�g�Ō��������邱�Ƃ��������ɁA�_�q����u��{�v�ɂ��Ė|�Ă��Ă���̂ł���B �@�Ƃ�����A�א�Ɩ{�́s��̗��t�Ƃ�������A�������Ă͂���ʁA�Ƃ���������̌X��������B�������A�ܗ֏��e�N�X�g�ɂ܂ők��A�s��̗��t�͌��Łs��̓��t���������̂�����A�����ł���Đ������Ɏ���Ƃ����t�����������Ă���̂ł���B������A�܂������ܗ֏��|��j��̒����̈�ł��낤�B �@ Go Back |
*�y�g�c�Ɩ{�z
*�y������z |
�@
�@�@�@11�@���V���@�㏑
|
�y���@���z �E�A�����̕��@���ブ���Ƃ��āA ���V���ɗL���������A ��X���X�A����艜�Ɏ����A �������ɏ������ׂ����Ȃ�ǂ��A �킴�Ɖ����̉��̑厖�Ƃ��������L�����B ���̃n�A�ꗬ�X�X�̌����A�����X�̉]���A �l�ɂ��S�ɂ܂����āA �v�^�_�̑����L���Ȃ�o�A �������ɂ��A���X�S�̂��͂���̂Ȃ�o�A ��X���̂��߂ɁA�����̋Ƃ����̂����B �����̑��[�A��ɂ��Е��A ���̒��̐l�̂����Ȃӂ킴������o�A �����ɂ������A�݂������𗘂ɂ��A �����Ƃ������A���炫�A���܂��Ȃ�Ɖ]���A �~�Ȃւ�Ȃ铹�Ȃ�o�A �����̌����Ƃ���͂����Ƃ��A�F�l�̂���ׂ��V��B ��ꗬ�ɂ���āA�����ɂ��������Ȃ��A���ɋɂ�Ȃ��B ���S�����āA�������킫�܂��A �����@�̊̐S��B(1) |
�y������z �@�ȏ�A�����̕��@����P���Ƃ��āA���̊��ɂ��̊T�v�������t�����̂ł��邪�A�����h�̂��ꂼ��ɂ��āA�������牜�`�Ɏ���܂ŁA�肩�ɏ����Ė��炩�ɂ��ׂ����낤���A�킴�Ɖ����̂ǂ������厖�k���`�l�Ƃ��A���������L���Ȃ������B �@���̂킯�́A���h���̂��̂̌����A���̓����ꂼ��̌������́A�l�ɂ��A�i�܂��j�S�ɂ܂����āA���ꂼ��ɍl����������̂�����A�������h�ł����X�Ӗ����ς���̂ł���B����䂦�A��X�܂ł̂��߂ɁA�����̋Ƃ������ڂ��Ȃ������̂ł���B �@�����̊T�����A��ɕ��ނ��āA���̒��̐l�X�̍s���Ƃ�����A�����i����j�ɕΌ�������A�Z�����i����j���d��������A�������Ƃ֕Ό����A�r���ׂ����Ƃ������ƁA�i�����́j���ׂĕ������ł��邩��A�����̓����������Ɩ��炩�ɂ��Ȃ��Ƃ��A���ׂĐl�̒m���Ă���͂��̂��Ƃł���B �@�䂪���h�ɂ����ẮA�����ɉ����������Ȃ��A�����ɋ��ɂ͂Ȃ��B�����A�S�������Ă��̓��k�����̌��\�l���킫�܂��邱�ƁA���ꂪ���@�̊̐S�ł���B |
|
�@ �@�@�y���@���z �@�i1�j��ꗬ�ɂ���āA�����ɉ����Ȃ��A���ɋɂ�Ȃ� �@�ȉ��́A���̕��V���̌㏑�ł���B�����ł́A�����͎��g�̔ᔻ�ɂ����鎋��������Ă���B���ꂪ�A �@�@�s�킴�Ɖ����̉��̑厖�Ƃ��������L�����t �Ƃ������Ƃł���B�����h�̂��ꂼ��ɂ��āA�������牜�Ɏ���܂ŁA�肩�ɏ����Ė��炩�ɂ��ׂ����낤���A�킴�Ɖ����̂ǂ������厖�k���`�l�Ƃ��A���̋�̓I�Ȗ��������L���Ȃ��̂ł���B �@����ɂ��āA�����ɉ�����������������Ȃ����Ƃ������āA����Ŗ��w���̔ᔻ�����Ȃ��̂��낤�A�Ƃ��������������邪�A����͊ԈႢ�ł���B�ނ���A�������炷��A���w���̑����ᔻ�Ȃǖ��Ӗ��ł��邩�炾�B �@���̗��R�́A�\�\�ƕ����͉]���\�\���h���̂��̂̌����A���̓����ꂼ��̌������́A�l�ɂ��A�i�܂��j�S�ɂ܂����āA���ꂼ��ɍl����������̂ł��邾����A�������h�ł����X�Ӗ����ς���̂ł���B����䂦�A��X�܂ł̂��߂ɁA�����̋Ƃ������ڂ��Ȃ������̂ł���A�ƁB �@�܂�A�������h�̓����ł����܂��܈ٌ�������A�����Ȃ�ƁA���̗��h�S�̂��������Ɣᔻ���Ă��A����͓����Ă���悤�ł��ē����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B �@����́A���Ƃ��A��X���{�l�ɑ�����҂ł��A���ꂼ��l�������i���قȂ��Ă��āA�܂�ł܂��܂��Ȃ̂����A�u���{�l�͂������v�Ɖ]���Ĕᔻ�����ƁA�ǂ����I�O��Ȋ��������̂Ɠ����b�ł���B�u���{�l�v�Ƃ����J�e�S���[�ɑ�����͔̂F�߂邪�A������Ƃ���́u���{�l�v�Ȃ���̂��A�����̂��Ƃ��Ƃ͎v���Ȃ��̂ł���B���̓���ƈ�ʂ̍��فA���z���A�Ό��̍����ł���B �@�ƂȂ�ƁA�����͂ǂ������ᔻ�̎d���������̂��H�\�\���藬�h��ᔻ����̂ł͂Ȃ��A���܂��܂Ȍ��ׂ��̂��̂�ᔻ����Ƃ���������I�킯�ł���B �@���̌��ׂ́A�����ɂ��㍀�ڂɏW���̂ł���A����͂��ׂĂ̗��h���A���ꂼ��A���̑����͂�������������Ă��錇�ׂł���B �@�����͉]���B�\�\�����̊T�����A��ɕ����ĕ��͂��āA���̒��̐l�X�̍s���Ƃ�����A��������ɕΌ�������A�Z����������d��������A�������Ƃ֕Ό����A�r���ׂ����Ƃ������Ƃ��A���ׂĕ������ł��邩��A�����̓����������Ɩ��炩�ɂ��Ȃ��Ƃ��A���ׂĎ��m�ł���͂����A�]�X�B �@�������āA�����̌��ׂƂ́A�v����ɁA�������A�Ό��ł���B�^�������ȓ�����̈�E�ł���ɂ����Ȃ��B�������ɕ����ĕ��͂��Ă݂�A�����h�����Ƃ̓Ǝ����Ƃ��Ĕ��蕨�ɂ��Ă���������ꂶ�������Ό��ł����Ȃ��B���������āA�����̑����ᔻ�́A�����̃A�C�f���e�B�e�B�����́u���v���������Ă��܂����̂ł���B���̂�����ɂ����āA�O�ꂵ���ᔻ�ł���B �@�����Ă܂��A�����̓����������Ɩ��炩�ɂ��Ȃ��Ƃ��A���ׂĎ��m�ł���͂��A�]���B�Ƃ���A�����ł́A�����������Ƃ������ʂ͏��ł��Ă��܂��̂ł���B�B���Ă��A���m�̂��Ƃł���Ƃ���A�B�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B���V��`�́A�܂��Ɍ����I�ɕs�\�ł���B�\�\���̂�����̃��W�b�N�́A���Ȃ�ʔ����Ƃ���ł���B �@�������Č���ƁA�����ᔻ�ɂ����āA�����̉��̑厖�Ɩ��������āA�r���I�ɔᔻ����Ƃ����������A�������I�Ȃ������̂́A�����̔ᔻ�����ݓI�ł��茴���I�ł��邩�炾�B�����̑����ᔻ�́u�����v�́A�ʂ̓��藬�h�ł͂Ȃ��A���]�̑S�āA����Ε��@�̏S�̂ɑ���ᔻ�A��������̕Ό��Ƃ��ĕ��͂���Ƃ���́A��̓I�œ��ݓI�Ȕᔻ�Ȃ̂ł���B���̃X�^���X�͈�т��Ă���B
�s�������ɂ��A���X�S�̂������̂Ȃ�o�A��X���̂��߂ɁA�����̋Ƃ����̂����t
�@���́u��X���̂��߂Ɂv�Ƃ����Ƃ��낪�A�����̈ӊO�ȗD�����ł���B��X���̂��߂ɁA�Ƃ������Ƃ́A�Ⴂ�����͏����Ȃ��B����͘V���������́A�s�ӂ̑f��̂悤�ȋC������B�l�͕ς肤��Ƃ��������ւ̊��҂ł���B
�s��ꗬ�ɂ���āA�����ɂ��������i�����j�Ȃ��A���ɋɂ�Ȃ��t
�@����͌���Ƃ��Ẵe�[�[�ł���B����ɕ����̕��@�v�z���W��Ă���Ɖ]���Ă悩�낤�B�@�\�\�䂪���h�ɂ����ẮA�����ɉ����������Ȃ��A�����ɂ��ɂ�͂Ȃ��B�����A�S�������Ă��̓��A�܂�A�����̌��\�A���̂����ꂽ�������킫�܂��邱�ƁA���ꂪ���@�̊̐S�ł���B �@�܂��ɁA�ߕs���Ȃ��҂���Ƌɂ܂������ł���B����ɉ����Ƃ��t��������̂́A�֑��Ƃ������̂ł��낤�B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
|
���������{�Q�� �� �@�ٖ{�W�@ �@
*�y�����A��̂������z |
|
�@���čZ�ق̖���������A�����ɂ͎w�E���ׂ����ىӏ�������B���Ȃ킿�A�}�O�n���{�ɂ́A
�s���Ȃ����ɂ����X�S�̂��͂���̂Ȃ�o�A��X���̂��߂ɁA�����̋��Ƃ����̂����B�i�����j���̒����l�̂����Ȃӂ킴���~��o�A�����ɂ������t
�Ƃ����āA�s�����̋t�A�s���̒��̐l�̂����Ȃӂ킴���~��o�t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ł́A���Ȃ莚�傪�قȂ��Ă���B�܂�A���n�ł́A
�s�������ɂ����X�S�̑ւ���̂Ȃ�o�A��X���̂��߂ɁA�Ȃ���������̂����B�����̑��[�A��c�ɂ��Ђ킯�āA���̒������A�l�̒��Ȃ铹�����~���o�A�����ɂ������t
�Ƃ����āA�s�Ȃ���t�A�s���̒��̓��A�l�̒��Ȃ铹�����~���o�t�Ƃ���킯�ł���B����́A���n���{�Ɋ�{�I�ɋ��ʂ���Ƃ���ł��邩��A���n�����ɂ͂���������̂悤�ł���B�@�܂��A���n�́s�Ȃ���t�Ƃ������ł��邪�A����́A�u����v�Ƃ������Ƃł���B�������A�Â��u���v���ƘA�����ēǂ߂A�u����Ƃ������̂����v�ƂȂ��āA�����������ӂ����₵���Ȃ�B�O�ɁA�s�킴�Ɓu�����́v���̑厖�Ƃ����������邳���t�Ƃ��邩��A�����́u�����̋v�Ƃ���̂��Ó��ł���B �@�悤����ɁA����́A�E���ƌ�ʂƂ��d�Ȃ��āA�s�Ȃ���t�ɂȂ����悤�ł���B���Ƃ��A�s�����́t�Ƃ������́u���v�����E�����A�����u�́v�i�\�j���������u��v�i��j�Ɍ�ʂ��āA�u����v�Ɖ����A���Ɂu�Ȃ���v�Ɖ����\�L����悤�ɂȂ����A�ƁB �@�Ƃ�����A����͎ʂ�����ł��邩��A�������V��i�K�̂��̂ł͂Ȃ��B���̌�̌�ʂł���B��������A�}�O�n���{�ɋ��ʂ��Ă��̌��̂��邱�ƁA���̂��Ƃ��炷��A�s�����̋t�Ƃ������͒}�O�n�����ɂ��łɂ��������ł���B �@�܂��A���̖��ӏ��A�s���̒��̓��A�l�̒��Ȃ铹����茩���o�t�Ɣ��n���{�ɂ���̂��A�悭�킩��ʕ����ł���B�����Ă����A�u���̒��̓����A�l�̒��Ȃ铹�����猩����v�Ƃ������Ƃ����A�u�������猩����v�ƂȂ�ƁA���ӂ��ʂ�Ȃ��B�s�����n�t�ł͂Ȃ��A�u���ăn�v�Ȃ�܂������A�Ȃ̂ł��邪�B �@��������A���ꂪ����ɁA�s���̒��̓��A�l�̒��Ȃ铹����茩�ăn�t�������Ƃ��Ă��A�����́A�u�l�́v�Ƃ�����傪���p�ł���B�܂�A�s���̒��̓��A���Ȃ铹����茩�ăn�t�ł悩�낤����ł���B���邢�́A����ɉ]���A�u���v�����s�v�����Ƃ݂Ȃ�����B�Ƃ����̂��A�ܗ֏��̑��̕��Ⴉ�炷��ƁA�s���̒��̒��Ȃ铹����茩�ăn�t�ŁA�����͈Ӗ����\���ʂ��邩��ł���B �@���n�̂����A�x�i�Ɩ{�́A�s���̒��́y���z�l�̒���������茩���o�t�Ƃ��āA�u���v�����Ȃ��B�����ʃ��@�[�W�����Ƃ݂�A�����炭���n�����ɂ́A���̌��͂܂��Œ肵�Ă��Ȃ������Ǝv����B �@���������āA���n���{�Ɂs���̒��̓��A�l�̒��Ȃ铹����茩���o�t�Ƃ��邱���́A��_�������A���̂܂܂ł������͂��͂Ȃ��B�����炭�A���炩�̌�ʂ̂��������ʐ��������Ǝv����B���̌��^�͏C���s�\�����A���n�����ɁA�s���̒��̒��Ȃ铹����茩�ăn�t�ɗގ��������������炵�����Ƃ������ł���݂̂ł���B �@���悤�Ȃ��Ƃł��邩��A��X�̃e�N�X�g�ł́A���n���{�̎���͍̂炸�A�s���̒��̐l�̂����Ȃӂ킴���݂�t�Ƃ����}�O�n���{�̌��ɏ]���B������̕������ӂ���Ȃ��ʂ�̂ł���B �@���邢�͂܂��A�ʂ̍Z�قł́A�}�O�n���{�ɁA
�s�����ɂ������A�~�������𗘂ɂ��A�������������A���炫�A���܂��Ȃ�Ɖ]���A�~�Ȃւ�Ȃ铹�Ȃ�o�t
�Ƃ��āA�s�����Ɓt�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s�悫��͂��Ɓt�Ƃ��āA�u�悫�v�����ł͂Ȃ��u��͂��v�i�カ�j�Ƃ�����������Ă���B�@������ɁA�������n�ł��A�x�i�Ɩ{�ł́A������s�����ƕЕt�t�Ƃ��āA�u�カ�v�Ƃ�����������Ȃ��B�����炭�A���n�����ɂ́A���̎���͑��݂��Ȃ������̂ł���B���������āA����͌�ɔ���������L�ł���B �@���Ƃ�肱���́A�u�������v�u�ւ�k�l�Ȃ铹�v�Ƃ����Ό��̘b�ł���B�����呾���A�Z���������A���݂̑����Ȃǂɕ邱�Ƃ͂����Ă��A�E�������̐퓬�ɁA�u�カ�v�ɕΌ�����҂�����킯���Ȃ��B���������āA����͂܂��ɗ]�v�Ȏ���ł���B �@�����炭�́A���̌�Ɂs���炫�A���܂��Ȃ�Ɖ]���t�Ƃ���̂Ɉ�������ꂽ��Ȃ̂ł��낤�B�r���Ƃ����̂́A���݂̑����̎��ł���B���܂����Ƃ����̂́A�ڕt�̎���A���������������Ɋ֘A����b�ł��낤�B�������A���@�̂��Ƃł���A�܂����A�u�カ�v�ɕ�҂�����͂����Ȃ��B����䂦�A�����A�カ�Ƃ�����́A������͂��肦�Ȃ��B�����͕Ό��̘b�Ȃ̂ŁA�s�悫�Ƃ������t�ŁA�ߕs���͂Ȃ��̂ł���B �@�ȏ�̂��̂�����A�����̌�߁E���������炤���Ƃ͖��p�ł���B����炪���n�א�Ɩ{�Ɉˋ����Ă���ȏ�A��{���̂��̂Ɍ��ׂ�����B������A�������ߋ`�A�����Ă͂��邪�A���������e�N�X�g���Ԉ���Ă���ȏ�A�_����ɒl���Ȃ��̂ł���B �@�����������Ԃ��~�ς���ɂ́A���{���r���Č����Ȏj���ᔻ�����s����K�v�����邪�A���������t�@���_�����^���ȍ�Ƃ́A����܂ōs��ꂽ���Ƃ��Ȃ������̂ł���B���̌��ʁA�א�Ɩ{�Ƃ����㔭�I��L�̑�����{���A�قږ������ԂŐ��̒��ɉ��s���Ă����̂ł���B �@�܂��A�����ĕʂ̍Z�قɂ킽��A�}�O�n���{�ɁA�s���炫�A���܂��Ȃ�Ɖ]���t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�ɂ́A�s�]���t�Ɂu���v����t���āA�s�]�����t�Ƃ�����̂�����B �@��������n���{�̂����ɂ́A�����h���n���̎q������x�i�Ɩ{�ɂ́A���́u���v����t���Ȃ��B���������āA���n�����ɂ́A�s�]�����t�ƋL�����̂ł͂Ȃ������A�����Ă��̌�A�u���v�������韥����L�����������̂ł���B �@����́A�{���A�}�O�n���{�Ɂs���A�S�����āA�������킫�܂��A�����@�̊̐S��t�Ƃ���Ƃ���A���n���{�Ɂs�������킫�܂�����t�Ƃ��āu���v����t���邱�Ƃ����O�ł����āA��͂�x�i�Ɩ{�ɂ́A���́u���v����t���Ȃ��B �@���������āA���n�����ɂ́A�s�킫�܂��t�ƋL���āA�u���v����t�����̂ł͂Ȃ������A�����Ă��̌�A�u���v�������韥����L�����������B�������������I�Ȏ���ٕ̈ςȂ̂����A���ꂪ�`���h�����āA�������{�̏��L�ɔ��f����Ă���B �@�����̍Z�ق̂��������ʒu�Â��́A�]�����n���{��������Ă����ܗ֏������ł́A�v�������Ȃ��������Ƃł���B�Ƃ����̂��A���n���{�̑��������������L�����Ƃ���A�x�i�Ɩ{�̏�����͗�O�������͌�L�Ƃ݂Ȃ���Ă����̂ł���B�������A���n���{�܂ōL��������L���A�����Ɍ����ƍ�����Ȃ�A�����͂��̋t�������ƒm���̂ł���B �@������ɁA�����������x���̋c�_�͏]���̌ܗ֏������ɂ͑��݂��Ȃ��B����A���n�ܗ֏��ɕΌ����鈫���A���́u�������v�u�ւ�k�l�Ȃ铹�v�A�Ƃ�킯�א�Ɩ{�𗝗R���Ȃ��M����֖��A�������A���܂��ɋ������[�ւ���K�v������A�Ƃ����̂��ܗ֏������̌���Ȃ̂ł���B �@ Go Back |
*�y�g�c�Ɩ{�z  �g�c�Ɩ{�@�Z�ىӏ�
*�y�g�c�Ɩ{�z  �א�Ɩ{�@�Z�ىӏ�
*�y�g�c�Ɩ{�z |
�@PageTop�@�@ �@Back�@ �@Next�@
