 |
�����̌ܗ֏���ǂ� �ܗ֏�������Ńe�N�X�g�S�� ������ƒ����E�]�� |
|
�@���@��@ �@�ځ@���@�@�@�@ ���@�@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@�@ �@�ٖ{�W�@
| �ܗ֏��@�n�V���@1 | �@Back�@�@�@Next�@ |
|
�ܗ֏��S�̂̒n�Ȃ炵������n�V���B���@���w��Ƃ���҂ւ̃K�C�_���X�A�������g���{���̈ē��������Ȃ��B���e�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B
1�@���@�@���@�@�ܗ֏��S�̂̏����ɂ��������
2�@�n�V�����@�@�n�V���̑O�� 3�@���@�̓��Ƃ��@�i���@�̓��Ɖ]���j 4�@���@�̓����H�ɚg�����@�i���@�̓���H�ɂ��Ƃւ��鎖�j 5�@�m��������@�i���@�̓��m������ҁj 6�@�n���Ε���܊��̊T���@�i�����@�̏��ܙɂɎd���鎖�j 7�@�ꗬ�Ƃ������@�@�i���ꗬ�Ɩ��t�鎖�j 8�@�����̓��@�@�i���@�̗���m�鎖�j 9�@������g���������@�i���@�ɕ���̗���m��Ɖ]���j 10�@���q�Ƃ��������@�i���@�̔��q�̎��j 11�@�n�V���㏑ |
�@
�@�@�@1�@���@��
|
�@�y���@���z �@���������ԍ����N���b�N����Ίe���ڒ����ֈړ� �@ ���@�̓��A��V�ꗬ�ƍ����A(1) ���N�b���̎��A�n�ď����Ɍ�����Ǝv�A(2) ���A���i��\�N�\����{�̔�A ��B���̒n��ˎR�ɏ��A �V��`���A�V����炵�A�őO�Ɍ��B(3) �����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A �N����ĘZ�\�B(4) ����N�̐̂��A���@�̓��ɐS�������A �\�O�ɂ��Ďn�ď��������B(5)�@ �����ЂāA�V�c���L�n�앺�q�Ɖ]���@��(6) �ɂ������A�\�Z�ɂ��āA �A�n���H�R�Ɖ]���͂̕��@�҂ɑł����A(7) ��\��ɂ��āA�s�ւ̂ڂ�A �V���̕��@�҂Ɉ��A���x�̏����������� ���ւǂ��A��������Ɖ]���Ȃ��B(8) ����A���X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A �Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A ��x�������������Ȃ͂��B �����A�N�\�O����\���㖘�̎���B(9) ���O�\���z�āA�Ղ������Ѓ~��ɁA ���@���ɂ��Ă��Ƀn���炸�B ���̂Â��瓹�̊�p����āA�V�����͂Ȃꂴ��̂��A ���n�A�����̕��@�s���Ȃ鏊�ɂ�B(10) ����A�P���[��������ƁA ���b�[�B���Č���o�A���̂Â��� ���@�̓��Ɉ����A��\�̔��B ������Ș҂́A �q���ׂ����Ȃ����Č��A�𑗂�B(11) ���@�̗��ɔC�āA���Y���\�̓��ƂȂ��o�A �����ɂ���āA���Ɏt���Ȃ��B(12) �����������Ƃ��ւǂ��A �Ŗ@�̌Ì�������炸�A �R�L�R�@�̂ӂ邫�������p�Ђ��B ���ꗬ�̃~���āA���̐S���������A �V�����V���������Ƃ��āA(13) �\���\���̖�A�Ђ̈�V�� �M���ƂāA���n����̖�B(14) |
�@�y������z �@���@�̓����V�ꗬ�Ɩ��Â��āA���N�C�s���Ă������Ƃ��A���߂ď����ɋL�q���悤�Ǝv���A���Ɋ��i��\�N�i1643�j�\����{�̍��A��B���̒n�ɂ����ˎR�k����Ƃ̂�܁l�ɓo���āA�V��`���A�ω����q���A���O�Ɍ������B �@�����d���̕��m�A�V�ƕ����瓡�����M�A�N��͐ςݏd�Ȃ��Ă����Z�\�i�ɂȂ��Ă��܂����j�B���͎�N�̐̂�蕺�@�̓���S�����A�\�O�ɂ��ď��߂Č�������������悤�ɂȂ����B���̑���A�V�����L�n�앺�q�Ƃ������@�҂ɑŏ����A�\�Z�ɂ��ĒA�n���̏H�R�Ƃ������͂ȕ��@�҂ɑŏ������B��\��ɂ��ēs�֏��A�V���i�L���j�̕��@�҂ɏo��A���x�������������s�Ȃ������A��������Ƃ��������Ȃ������B �@���̌�A�����e�n�֍s���āA���܂��܂ȗ��h�̕��@�҂Ƒ������A�Z�\����܂ŏ������s�Ȃ�������ǂ��A��x�����̗��k�����l���������Ƃ��Ȃ������k���������Ƃ��Ȃ������l�B����͏\�O����\����܂ł̂��Ƃł������B �@���͎O�\���z���ĉ䂪�ߋ���U��Ԃ��Ă݂�ƁA����͕��@���ɂ܂��Ă����̂ŏ������A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ������B���R�ƕ��@�̓��̓���*�������āA�V�̌����𗣂�Ȃ����������ł��낤���B���邢�́A����̑����̕��@�Ɍ��ׂ����������炾�낤���B �@���̌�A�Ȃ����[�������悤�Ƃ��āA���ɗ[�ɒb�����Ă������A���ǁA���@�̓��ɂ���ƓK���悤�ɂȂ����̂́A�����\�̍��ł������B������ȗ��́A�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ��āA�Ό��𑗂��Ă����B �@���@�̗��k�����l�ɂ܂����ď��X�̌|�\�k���|�l�̓��Ƃ��Ă����̂ŁA�����ɂ����Ď��ɂ͎t���Ƃ������̂��Ȃ������B �@���ꂩ��A���̏����������Ă����̂����A���@��̌Â����t���肽��A�R�L�R�@�̌Â������p������͂��Ȃ��B���̗��h�̌����āi�l���j��^���̐S�𖾂炩�ɂ��邱�ƁA�V��*�Ɗϐ��������Ƃ��āA�\���\���̖�A�Ђ̍��̈�V*�i�ߑO�l���O�j�ɕM�������ď����n�߂��̂ł���B |
|
�@ �@�y���@���z �@�i1�j���@�̓��A��V�ꗬ�ƍ����@�ܗ֏���ꊪ�A�n�V���B�n�E���E�E���E��Ƃ������]�ɏy���Ė��Â����܊��̍ŏ��̊��ł���B���̖`���ɁA�����͎��g�̗�������U��Ԃ��āA�����ȒP�ȕ��@���`���L���B �@�ȉ��̂��̎����������܊��S�̂̑O�ɒu���ҏW�����邪�A�u�����v�Ƃ��ēƗ��������͑��݂����A�n�V���`���Ɋ܂܂�Ă��镶�ł��邱�Ƃ���A�����ł́A����ɏ�����z�u�Ƃ���B �@�����Łs���@�t�Ƃ���̂��A�u�Ђ傤�ق��v�Ɠǂ�ł���҂����邪�A����͑Ó��ł͂Ȃ��B�ߐ������̕����̎���A����͂܂��u�ւ��ق��v�Ɠǂ����ł���B��o�̏��ɁA�s�Ȃ܂ւ��ق����r�̂��Ɓt�Ƃ���B�����@���r�̂��ƁA�ł���B�����Łs���@�t�Ƃ���̂��A�u�Ђ傤�ق��v�Ɠǂނ̂��A���́u�Ȃ܂ւ��ق��v�̗ނł���B �@�s���@�t�Ƃ����̂́A�����ł́A����̌ꊴ�ɂ���R���I�헪�������͐�p�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ɒ��ӁB�����́s���@�t�̈Ӗ��́A�퓬�p�̈Ӗ��ł���B �@���������p�ƁA�����ƌ���̂́A�㐢�̕Ό����������ł���B���̌ܗ֏���ʂ��Č����邱�Ƃ����A�㐢�̈Ӗ��ł̌��p�E�����Ƃ����T�O�͂܂��������Ă��Ȃ��\�\���̂��Ƃ��m�F���ꂽ���B �@�Ƃ��Ɂu���@�ҁv�Ƃ����ꍇ�A�d�����Ă����ʂ̕��m�ƈ���āA���|�ҁA�퓬�p�̐��Ƃ̈Ӗ��ł���B�������A����͕����̂悤�Ȑ퓬�p�́u���_�Ɓv���w�����̂ł͂Ȃ��A�����܂ł����|�ҁA�����̐퓬�҂Ƃ����Ӗ��������B �@���āA�s���@�̓��A��V�ꗬ�ƍ����t�Ƃ������Ƃ����A���̓�V�ꗬ�́u��V�v�Ƃ͉����A�ɂ��āA���������j��ʗ�����ɐ������������������Ƃ��Ȃ��B���ꂾ���ł��A���������̏]���̃��x�����m���̂ł���B �@��X�̏����ł́A�u��V�v�Ƃ͑��z�ƌ��Ƃ�����̓V�̂��w���A�A�z�̂��Ƃł���B���������āu��V��v�Ƃ́A�u��v�ɂ��āu��v�A�܂肱�̉A�z�Η��̎~�g�Ƃ��āu��v�A�Ƃ����قǂ̈Ӗ��ł���B �@������A���E����Ɍ��������̖��ɂ��Ă���킯�ł���B����䂦�A���̖��ɐ[���Ӗ��̂��邱�Ƃł͂Ȃ��A�F�������Ƃ��ẲA�z�̑��ɂƂ����A�����̊T�O�Ƃ��Ă͎��Ɉ�ʓI�Ȃ��̂ł���B�����A�_�����Ƃ��V�A���A�O�����邢�̓^�C�̗����X�Ƃ����������̗��h���Ɣ�r����A���������u�N�w�I�v�ȍD�݂��o�����ł͂���B �@�{���ܗ֏��ɂ́u�ꗬ�v�Ƃ��������o�Ă��邩��A�u�ꗬ�v�Ƃ��������炵���B�����͂��̌ܗ֏��̂Ȃ��ł͗����̖��p���Ă���B���@�̂������p�Ɍ����āu�ꗬ�v�̖�����p�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���邪�A�����ɂƂ��āA�Ƃ��ɋ�ʂ͂Ȃ������悤�ł���B �@�ߐ������̎�q�w�ҁE�ї��R�̐V�ƌ��M���^�ɁA
�s���q�V�ƌ��M�A��薈�Ɉ꓁�������A�H���ꗬ�t
�Ƃ���B����ɂ��A�����̗����́u�ꗬ�v�ł���A�ܗ֏��ɂ���u�ꗬ�v�̗p����A����ŖT��B�܂�A�ܗ֏��ɂ���u�ꗬ�v�́u��V�ꗬ�v�̌�L�ł͂Ȃ��B�������g���u�ꗬ�v�Ə����Ă����̂ł���B�@�u��V�ꗬ�v���u�ꗬ�v���A�Ƃ��Ɍ�������̎g�p���̂ł��邩�A�Ƃ����Ƃ���͊m���Ȃ��B�ܗ֏��́A���@���V�ꗬ�Ə̂��āA���N�C�s���Ă����A�Ƃ���B���h���̂ɂ���قǂ���������C�z���Ȃ��B �@�����嗬�̒��ɂ́A�d��������Ɂu�~�����v�A�O�͂Ɂu�������v���̂�����̂��������B�~�����́u�~���v�Ƃ́A�ǂ�Ŏ��̔@���A�����̓�V�A�~����ł���B�}�O�̕��������ł́u��V���v�Ƃ����B����́A�����̓�V���炷��ƁA�~�����̃V�m�j���ł���B�܂����́u�~�����v���A�K�����������ŗL�̗��h���̂łȂ������悤�ŁA����ŁA�u��V�ꗬ�v�u�ꗬ�v���������Ƃ��������̂��낤�B������A�u��v�ɂ��āu��v�A�A�z�Η��̎~�g�Ƃ��āu��v�A�Ƃ������ƂŁA�u��V�v�Ɓu�v�ɂ��قǂ̈Ӌ`���Ⴊ����킯�ł͂Ȃ��B �@���m�̍��E�C�l���ՂƂ����`������i�����邪�A����͌`��u�C�l���Ձv�ƌĂ�ł��邪�A�{���̃f�U�C���́A�u��V�ꗬ�v�u�ꗬ�v�̃V���{���C���[�W�ł���B �@�����������́A���Ƃ��u�~�����v��p���āu��V�ꗬ�v�ɉ��������̂ł͂Ȃ��B�������s�N���Ɂu�~�����v���̂����Ƃ������͂Ȃ��B�ނ���A��N���̖嗬�̈ꕔ�Ɂu�~�����v���̂�����̂��o���Ƃ����A�t�̃v���Z�X���l������B�u��V�ꗬ�v�����ł��p������ł��A�L�c�i�p�̏��������̂��݂�ƁA��ʂɂ́u�������v�Ə̂��Ă����i�L�c����c���j�B �@���������āA�u��V�ꗬ�v�������ĕ����̌��@�Ƃ��Ĕr���I�ɍl����̂͌���Ă���B���邢�́A�u��V�ꗬ�v�������̊����I���@�ŁA����ȑO�̉~�������X�́A�������̂��̂��A�Ƃ����F�����A���炩�Ȍ�F�Ɖ]���ׂ��ł���B���ӓI�ȉ��߂ł���B �@����䂦�A����������F�����s����Ă��鍡���ł́A�����̈�Y�͌����ɂ͑��݂����A���݂���͖̂��݂̂̎��Ĕ�Ȃ���̂ł���A����䂦����Ӗ��ł́A������̈�Y�́A���������ܗ֏��Ƃ����e�N�X�g�̓����ɂ������݂��Ȃ��̂�������Ȃ��B �@ Go Back �@ �@�i2�j�n�ď����Ɍ����� �@���@�̓����V�ꗬ�Ɩ��Â��āA���N�b���C�s���Ă����̂����A���̕��@�̓��̂��Ƃ��A�����ł͂��߂āA�����ɏ�������킻���Ǝv���A�ƕ����͋L���B�����Œ��ӂ��ׂ��́A���ꂪ�A�����Ƃ��Ă̍ŏ��̕��@�_���Ƃ������Ƃł���B�����悤�Ȃ��Ƃ́A��ɂ��ĎO�q�ׂĂ���B �@�悤����ɁA�����͂��̂Ƃ��ɂȂ��āA�͂��߂ĕ��@�_���������B�����āA�{�������グ�Ȃ��O�Ɏ��S�����̂�����A�{���͈�e�ł�����B�܂�A���̍ŏ��̒���͓����ɍŌ�̒���Ȃ̂ł���B�ܗ֏��́A�����̍ŏ��ɂ��čŌ�̕��@���ł���B �@���̋L�q�́A�ЂƂ̋}���ł��邩��A�悭���ɓ���Ă����Ă������������B�����ɂ͖{���A�ܗ֏��ȑO�ɂ́A�����Ƃ��Ă̕��@�����q�͂Ȃ������̂ł���B �@�������A���́s�n�ď����Ɍ�����t�Ƃ������傪�A�܂Ƃ��ɓǂ܂ꂽ�Ⴊ�Ȃ��B���Ƃ��A�O�\��i�O�\�܁j�ӏ@���A��X�̉]���u��㕺�@���v�����삾�ƐM���ċ^��Ȃ������A���Ȃ��x�z�I�ł���B�܂��Ă�A�����������@�O�\�܉ӏ����ܗ֏��Ƃ����i���_�I�}�����f���āA�u�߂���Ɛ����A�̂�����₽�ʁB����Ɏ����ẮA���j�����̃C���n�����S���ʎ҂�̃^�����ł���B �@��������A���̂悤�Ɍܗ֏��ɖ��L���Ă��邱�Ƃ�ǂ߂Ȃ��Ƃ́A���ӂƌ����ׂ��B�������Ȃ���A�ߔN�Ɏ����ẮA�ܗ֏��ɂ��́s�n�ď����Ɍ�����t�Ƃ�������̂��邱�Ƃ����m�炸�ɁA�ܗ֏��_�������Ƃ����k�y�܂ł���B���邢�́A��L�̐i���_�I�}���ɌŎ����邽�߂ɁA���̌����̈ӂɖ�������҂������B�܂��ɓ|���ƌ����ׂ��B �@���̂悤�ȍ����̏����炱���A���N�b���C�s���Ă������@�̓��̂��Ƃ��A�����ł͂��߂āA�����ɏ�������킻���Ǝv���A�ƕ������L�����̉ӏ����A���߂Ċm�F���Ă������Ƃ����N�ɂ����߂�B �@���Ƃ��A���������̔N�ɂȂ�܂ŁA���@�_����،��Ȃ������̂ł͂Ȃ��B���@�u�`�ɂ����āA�����ł̋������������B����Ȃ��v�z�Ƃ́A�u�@���䕷�v�u�q�H���v�̓��m�I�`���̒��ɑ����B�����炭�������A���̌ܗ֏��������˂A�u�t�H���v�Ƃ��������������c������������Ȃ��B �@�܂��A���̌܊��̕����i�ܗ֏��j�ɋL�q����Ă���悤�Ȃ��Ƃ́A�����ݐ����ɐ��Ԃɒm���Ă������B����͖{���㏑�ɁA�s�����ꕪ�̕��@�Ƃ��āA���əB�鏊�t�Ƃ���ʂ�ł���B �@���Ƃ��A�����ɂ��ẮA���̓ꗬ�̂ق��ɂ��A���́u�����ꕪ�̕��@�v�u�啪�ꕪ�̕��@�v�Ƃ������@�_�ł����A��Ɍ��y�����ї��R�^�̔w�i�ɂ����Č��y����Ă��邩��A�������ǂ��������@���_�������̂��A���Ԏ��m�̂��Ƃł������悤���B �@������A�Ȃ������́A�����ŁA�͂��߂āA�����ɏ�������킻���Ǝv�����̂��B �@���̂��Ƃ́A����Ӗ��ł́A�{�����Ō�܂Œʓǂ��Ă͂��߂Ă킩�邱�Ƃ�����A�����ł́A�����ē������B���Ă������Ƃɂ���B�ǎ҂ɁA�����̋L�q�ƁA�����Ɍ��������Ă���������������ł���B �@ Go Back |
���������{�Q�� �� �@�ٖ{�W�@ �Έ�Ɩ{�@�n�V������
*�y���R���W�z  ��V�ꗬ�V���{���C���[�W  ���E�C�l���Ձ@�`�{�{������ �F�{�s�@���c���p�ّ�  �Έ�Ɩ{�@�u�n�ď����Ɍ�����v
*�y�n�V���㏑�z
�s�E�A�ꗬ�̕��@�̓��A�i�����j�����ꕪ�̕��@�Ƃ��āA���əB�鏊�A�n�ď��������A�n���Ε���A���܊���t |
|
�@ �@�i3�j���i��\�N�\����{�̔� �@�ȏオ���̈�i�̖��A�O�u���ɑ������镔���ł���B �@���i��\�N�i1943�j�\���́A�����̎��̈�N���O�ł���B�\����{�Ƃ������t�́A���̐߂̖����ɁA�\���\���Ƃ���̂ɑΉ�����B�����ł��邩��A���t�������Ă���̂ł���B �@��B���̊�ˎR�Ƃ����̂́A��a�R�Ƃ������B��ˎR�Ƃ͑S���ǂ��ɂł����閼�����A�����Ă��͓��A�������āA�u��ˁv�̖��͂���ɗR������B�����Ɂu��ˊω��v�ƌĂ��ω���ꂪ�����āA����Ε����I�Ȑ��n�ł���B���݂͉_�ޑT���Ƃ����i���E�F�{�s�������j�B �@��ˎR�̖��̒ʂ�A�����ɂ���ޓ��Ƃ����A�������āA�����ŕ����͂��̌ܗ֏����������Ƃ����`��������B����͖������̕����`�L�i�{�{������Ռ�����ҁw�{�{�����x�����l�\��N�j���E�����n���`���ł���B���̏����ˋ������w��V�L�x�ɂ͂���ɊY������L�����Ȃ��B������ɁA�w�����`�x�ɂ́A
�s���i��\�N�mᡖ��n�\���\���A���p�ܗ֏��A���ޖ�j���e�n�e�ҔV�B���n���c�R�����t�R�a���m�������n�j��������t�t
�Ƃ����āA�u���ޖ�v�Ƃ��邩��A����͊�ˎR�̗�ޓ��̂��Ƃł���B����ƁA��������S�N���o���Ȃ������ɁA��������ޓ��Ōܗ֏����������^�����n�߂��A�Ƃ����`�����ł��������Ă����̂ł���B�@�������A�w�����`�x�ɂ��Ă��㐢�̓`�����E�������̂ł���B��L�ɂ���A���c�R�����t�R�a���Ƃ����̂����ł���A���̋L������������`�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ�����A�����́A�{���������n�߂�O�ɁA��ˎR�ɓo�����B�V��`���ω���炵�Ƃ���Ƃ��납��A�u�V�v�Ɓu�ω��v�Ƃ�����̏@���I�Ώۂ������ɂ��邱�Ƃ��m���B �@���̏ꍇ�A�V�͎I���݂ł���A�ω��͕����I���݂ł���Ƃ͈ꉞ�����邪�A���������悭�l���Č���K�v�����낤�B�����ɂ�����@���Ƃ������́A�����ł͐G��Ȃ����A��X�̂����{�{�����ɂ�����u�������v�̖����l����Ƃ������ł��Ȃ��|�C���g�ł���B �@�Ƃ���ŁA��ˎR�ɓo��c�Ƃ��邪�A��ɂ��q�ׂ�悤�ɁA��ˎR�Ŗ{���������n�߂��Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�\����{�̂�����A��ˎR�ɓo�����A�V��`���ω����q�����O�Ɍ������A�Ƃ������Ƃ����ł���B���������Ă��̕��͂ł́A��ޓ����ܗ֏����M�̏ꏊ�Ƃ���ޗ��͂Ȃ��B �@��X�̏����ł́A���̓���ˎR�ɓo�����̂́A���������U�͂��߂ĕ��@�������M����ɂ������āA���̒��q���A���F�肷�邽�߂ł���B���������āA��ޓ����Ă��Ď��M�����Ƃ����b�ł͂Ȃ��B �@ Go Back |
 ��ˎR�ƌF�{�s��  ��ˊω��@��ޓ� �F�{�s�������@�_�ޑT�� |
|
�@ �@�i4�j�����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\ �@�����͉��s�����ł��邪�A��X�͂����ʼn��s�����Ă݂��B�}�O�n�ܗ֏��ł́A������u���Ёv�Ƃ����ɁA�u���v�Ƃ��Ă���̂��q���g�ł������B �@���̌ܗ֏����{���݂�ƁA�u����ĘZ�\�v�̌�ɉ��s������Ⴊ�قƂ�ǂł���B�������A���̈ꕶ�͗����̊J�n���ł��邩��A�㕶�ƈ�ł���B�܂��A�s�V��`���V�����X���őO�Ɍ��t�܂ł��O���ɑ�������B�����ŁA���͂̌ċz���ς��Ă���B�䂦�ɉ��s������Ƃ���A���������Ȃ��B �@�����������s�[�u�͏]���Ȃ��������Ƃł���B���������ǂ݂́A��X�̃e�N�X�g�̓��e���͂���Ă͂��߂ĉ\�ɂȂ����̂ł���B �@���̈�߁\�\�s�����d���̕��m�A�V�ƕ����瓡�����M�A�N����ĘZ�\�t�\�\�́A���̃T�C�g�ł͌J��Ԃ����p����镶�ł���B����Ƃ����̂��A���̂킸���ȍs���ɁA�����Ƃ����l���Ɋւ����Z�k����Ă��邩��ł���B �@�܂��A�u�����d���v�B�\�\�����̎Y�n��d���Ƃ��錈��I�ȍ����͂��̕����ɂ���B����قǃ_�C���N�g�ɏ�����Ă��Ȃ���A����܂ő����̌����҂⏬���Ƃ��A�����۔F���A�����Ĕ���o�������̂��ė����Ƃ����o�܂�����B������ɂƂ��ẮA�����炭�A����قǎ�킵���ꕶ�͑��݂��Ȃ��ł��낤�B�����A���ꂱ���A�܂��ɓ|���I�Ȏ��ԂȂ̂ł������B �@�Ȃ��A�����Œ��ӂ��ЂƂ��Ă����A�ܗ֏��ʖ{�Ɂu�d���v�̕������u�����v��u�����v�ƋL���P�[�X������B��������āA�ܗ֏��Z���҂�����͌뎚���Ɗ��Ⴂ���āA���邢�́u�d���v�ƒ����ɋy�Ԃ��Ƃ�����B����������͗]�v�Ȃ��ƂȂ̂ł���B �@�ߐ��ł́A�w���c�ƕ��x�ɂ��u�����v�ƋL���B����͔d�B�o�g�̍��c�����q��c�Ƃ��鍕�c�Ƃ̂��Ƃ��炷��ƁA���ҊL���v���̌뎚�ł���Ƃ݂���B�w���c�ƕ��x�Ɂu�����v�ƋL������A�}�O�ł́u�d���v�ł͂Ȃ��u�����v�ƋL���Ⴊ���X����B �@�u�d�v�́u���v�Ɖ��������ŁA�×��u���v����p�����͏��Ȃ��Ȃ��B�܂��d���́u���v�������悤�Ɂu���v����p���邱�Ƃ��Ⴊ�����B�u�͂�܁v�́u�d���v�ƋL���Ɍ��܂������Ƃł͂Ȃ��B�Ñ�ł́u�j�ԁv�Ƃ����������B�d�������͂��������ŏ����父���Ȃ̂ł���B�ܗ֏��ʖ{���u�����v��u�����v�ƋL���Ȃ�A����͂���悢�ł̂ł���B�������A�n���d���ł́A��͂��ʂɁu�d���v�Ə����Ă������Ƃ͒m���Ă����ׂ��ł���B �@���ɁA�u�V�ƕ����瓡�����M�v�B�\�\���ꂪ�����́u���@�ҁv�Ƃ��Ă̐����Ȗ��̂�ł���B�ܗ֏��͕��@���Ȃ̂ŁA���������t�H�[�}���Ȗ��̂���L���B����ɑ��A�u�{�{�����v�͒ʏ́A���̂Ƃ����ׂ����ł���B �@���̖��̂�Ɋւ��āA����������Ă����A�܂��u�V�Ɓv�Ƃ��������k�����ȁl������B����́u����߂�v�ƓǂށB�w�{�����|���`�x�ȂǁA�����m�炸�Ɂu�ɂ��݁v�ƃ��r��U��Ⴊ���邪�A����͌��ł���B �@�V�Ǝ��́A�퍑����A���썑�g��S�̒|�R��ɋ��������Ƃł���B�x�z�̈�O��Ȃ����ܐ�Ă��ǂ̍��l�ł���A�d���A���O�A�����O���Ɉ͂܂�āA����珔���͂ɖ|�M���ꂽ���̎�ł������B���̉ƌn�̌��c���A���厛���F�Ƃ���B�䂦�ɐV�Ǝ��͓������ł���B �@�ނ��A����͋M�헬��杂̈��ł����āA���厛���F�����ۂɔ��썑�֗����ꂽ�Ƃ��������͂Ȃ����A�܂��ē��n�Ɏq���₵���킯�ł��Ȃ��B�������A���������j���W�Ƃ͕ʂɁA�V�Ǝ��́A���̌��c���k�ƁE���厛���F�Ƃ���`����L���A�������𖼂̂��Ă����Ƃ����u�����v�͂���B�����́u�V�ƕ����瓡�����M�v�Ƃ������̂�ɁA�����u�����v�ƋL���̂́A����䂦�ł���B �@�������V�Ǝ��𖼂̂�̂́A���@�ҐV�Ɩ���̉Ƃ��k��������ł���B���V�Ǝ��𖼂̂�ȏ�A�����炭���썑�g��S�̐V�Ǝ��ɘA�Ȃ铯���ł��낤�B�Ƃ��낪�A��̓I�ɂ��ꂪ�ǂ������W�ɂ���̂��A�s���ł���B �@�����A�|�R���E�V�Ə@�т́A�d���������S�̒����R���E�F�쎁����{�q�ɓ������l�ŁA�V�Ǝ��͉F�쎁�̐��͉��ɂ������炵���B�܂������A�퍑���A�������āA���삩��אڂ���d�������֗���Ă����ƁX�������������B�����������o�������������Ƃ��炷��A�V�Ɩ���̉Ƃ��A���������u�d���֗���Ă����Ɓv�̈�ł�������������Ȃ��B �@����ɑ��A�������Ƃ́A���q�蕶���L���悤�ɐԏ����t�A�悤����ɔd���ɑ�������ԏ��n�̉Ƃ̈�ł���B�ԏ����t�Ȃ瑺�㌹���ł���B�������A���ꂪ��̓I�ɂǂ̉Ƃł��������A�������ł��������s���ł���B�����A�{�{�����́u�{�{�v�Ƃ����̂́A�����̑ォ�疼�̂�o���������ŁA���������̃P�[�X�̂悤�ɁA���g�̏o�g�n��ʏ̂ɂ����ɂ����Ȃ��B �@�����āA�u�V�ƕ�����v�B����́A�����̑�ɖ��̂�o�����Ƃ��������A���@�ƂƂ��Ă̐V�Ɩ���̉Ɩ��ł��낤�B�V�Ɩ���̎���A���������̕��@�Ƃ��ċ������Ƃ��A���̉Ɩ��u�V�ƕ�����v���p�������̂Ƃ݂���B �@�Ƃ���ŁA�������u������v�𖼂̂邱�Ƃ������ł��Ȃ��炵���A�����͕s���ɂ�����̍���G�̂����Ƃ�ł��Ȃ��z���A�Ƃ����_����̐̂��������A�ߔN�ł�������_���̂��Ƃ���������҂�����B���邢�́A���̔��ɁA������i�삷�邽�߂ɁA�����́u������v�𖼂̂����̂ł͂Ȃ��A����������ȕs痂�����킯���Ȃ��A�����̖�l���邢�͂��̗������A��t�h���āu������v�ɂ��Ă��܂����̂��A�Ƃ�������������B�Ύ~�ƌ����ׂ��B�����͓����̎����m��ʁA���m�����炵�Ă���ɂ����Ȃ��B �@�悤����ɁA�����̓����A���Ƃɂ́u������v�𖼂̂�҂͖����ɂ������B�����炭�u������v�𖼂̂�҂��S���ł͑������������낤�B���Ƃ��A�V�Ǝ��̃P�[�X�ł́A�x�z�̈�O�`�ܐ�ɂ����Ȃ��|�R��傪�V�ƈɉ��A�������A���̓����ƘV�ł����炭�m�s���S�Ă��ǂ̎҂܂ł��A�V�Ɣ����A�V�Ɣ��O����̂��Ă����B �@�ނ��A����͒���̂��n�t���̂���E���ł͂Ȃ��B�Љ�I���K�Ƃ��Ă̎��̂ł���B�܂����ƂɌ��炸�A�_�E�Ⓛ�H�ȂǐE�l�ɂ��u������v�𖼂̂�҂����������̂ł���B�����������Ƃ́A�{�T�C�g�ł͂��߂Ē��ӂ����N����܂ł́A������������L�̂悤�Ȉ����Ȃ��Ƃ������Ă������̂ł���B �@���@�҂����̐E�l�ł���B�V�Ɩ���̏ꍇ�A���́u����v�Ƃ����̂́u���o�v�Ɠ��`�̍��ł��邪�A���@�ƂƂ��ẲƖ��́u�V�ƕ�����v�𖼂̂����悤�ł���B�������āA�����͐V�Ɩ���̉Ɩ����k���ŁA���̃u�����h���u�V�ƕ�����v�𖼂̂����B����ȏ�ł��A����ȉ��ł��Ȃ��B �@�ȏ�̏��_�ɂ��ẮA�{�T�C�g�̏��_���ɏڂ����̂ŁA������Q�Ƃ̂��ƁB �@�Ō�ɁA�u���M�v�Ƃ���̂́A�����恁i���݂ȁj�ł���B恂̂����́u����v�Ɖ��ǂ݂ɂ͂��Ȃ��B�������A����恂̓ǂ݂͕s���ł���B �@�w�����`�x�̓c���G�V�ʖ{�ɂ́A�u�n���m�u�v�ƃ��r���ӂ邪�A����͕��������`���ɂ͈ٗ�̂��ƂŁA���������̍����͖��炩�ł͂Ȃ��B�w�����`�x�́A�g�����@�́u���@�v��恂ƌ�����āA�u�J�l�m���v�ƃ��r���ӂ�B����́u���@�v�u���[�v�Ƃ��L����āA���Ƃ��ƍ�������u�P���{�E�v�ł���B���邢�͂܂��A�w�����`�x�͑������R�E�`���Ɂu���V�e���v�ȂǂƂ����ǂ݂�����B�u���V�e���v�Ȃ�`�����O�ɏ\�O�㏫�R�E�`�P�Ƃ����l�����邩��A����͖��炩�Ɍ�F�ł���B����ȋ�ŁA�w�����`�x�̃��r�́A��T���܂߂����ӓI�Ȃ��̂ł���B����āA�w�����`�x�ʖ{�Ɂu�n���m�u�v�Ƃ��邩��Ƃ����āA����������Ƃ���킯�ɂ͂����Ȃ��B �@�����A�u���v���́u���Ɓv�ƓǂޗႪ����̂ŁA恁u���M�v�́u���Ƃ̂ԁv�������\��������B���Â�ɂ��Ă��A�܂��L�͂ȖT�Ȃ��̂ŁA��l������Ɍ��߂�킯�ɂ����Ȃ��B���������āA�u���M�v�Ƃ���恂̓ǂ݂͖��m��A�Ƃ��Ă����ׂ��ł���B �@�w�{�����|���`�x�ɕ�����恂��u�����v�Ƃ��A�s��������J�R�_���{�{���U�������ƍ����t�Ə����Ă��邪�A������T���s���ł���B�u�����J�R�_���{�{���U�������v�ȂƋX�����������㐢�̈�h���A���̂悤�Ɍ����o�����̂�������Ȃ��B �@�ȏ�̂悤�ɁA���@�҂Ƃ��Ă̕����̃t�H�[�}���Ȗ��̂�́u�V�ƕ����瓡�����M�v�ł���B�܂�A���́u�V�Ɓv�A�E���́u������v�A���́u�����v�A恂́u���M�v�ł���B �@���ꂪ�A���@�҂Ƃ��Ă̕����̖��̂�ł��邩��A���������`���Ɂu�{�{������v�ȂǂƋL���̂́A�㐢�����̗��h�ł��邱�Ƃ̈�ł���B�u�{�{�����v�����ԂŗL���ɂȂ�����A�{���́u�V�Ɓv�Ƃ����������Y�p���ꂽ���ʁA�����������h�`�������������B �@�{�{�ɐD�i���_�Г��D�j�ɂ��A�����́A�_�Ɓi�V�Ɓj�̈�Ƃ��p���������A���g�̑�ɂȂ��āu�{�{�v���𖼂̂�悤�ɂȂ����B�����炭�A�����́A�P�H�ŎO�ؔV����{�q�ɂ��Ĉ�Ƃ�n�݂����Ƃ��A������{�{���Ƃ����̂ł���B������́A���@�Ƃł͂Ȃ��A�����I�ȉƖ��Ƃ��ċ�ʂ����Ƃ������Ƃł���B |
 �g�c�Ɩ{�@�n�V�� �`��  ��Ɩ{�@�n�V�� �`�� �u���������v�̕���  ���厛���F���� ���R������s����  �퍑�����d������n�}  �V�ƕ��U�瓡�����M 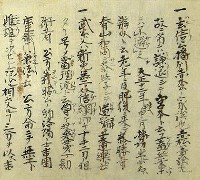 �����`�@���Y�ӏ�
*�y�{�����|���`�z
�s�{�{���U�����Ҕd�B�l�A�ԏ������A�V�Ɓk�ɂ��݁E�U�����l����B���j�V�Ɩ���ցA�B�\�蓁�p�B�i�����j�}���\�O���A�������ׂ����ƘZ�\�]�x�A��������J�R�_���{�{���U�������ƍ����t *�y���_�Г��D�z �s�L��B�V�����_�ƎҁB�V���V�ԁA���k�������}�O�H����B��⏳�ƞH���U�����M�A������{�{�B�����q���ȗ]�`�q�B�̗]���i�����t |
|
�@���āA�s�����d���̕��m�A�V�ƕ����瓡�����M�A�N����ĘZ�\�t�Ƃ����ꕶ�������̂́A�������d���Y���Ƃ������Ƃł���B�����āA���ɂ����ЂƂd�v�Ȃ��Ƃ́A����ɂ���ĕ����̐��N���m�肷�邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A���i��\�N�ɘZ�\���Ƃ������Ƃ���t�Z���āA���N�͓V���\��N�i1584�j�Ɠ���ł���킯�ł���B �@���������q�{�{�ƌn���ł́A�����̐��N��V���\�N�Ƃ���B��N�����킯���B���ꂪ���ɋ��������͕s�������A�����������A�����ɋ߂��O���O�N�i1846�j�ƒx���j���ł��邱�Ƃ��炷��A������I���W�i�������ƌ��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���q�{�{�ƕ����͂��̌n�}�Ɍ�����@���A���x�����ӏ����Ԉ���Ă����肵�āA���Ȃ�e���Ȏ҂��쐻���������ł���B�����炭���L�҂Ɍ�F���������̂ł���B �@�{�T�C�g�̑��_�l�ɖ��炩�ɂ���Ă���悤�ɁA�{�{�Ɠ`���͐��삪�V���������ł͂Ȃ��A���̓��e����`�����Ȃ��Ȃ��B���Ƃ��A���������S�N�����ď����ꂽ�����ƁA�������g�̌ܗ֏��̋L����ɂ��������͂��Ȃ��B���������ĉ�X�́A���̌㐢�쐬�̋L������L�Ƃ��ċp�����A�������N��V���\��N�Ɠ��肷��킯�ł���B �@�Ȃ��A���́u�Z�\�v�Ƃ��������Ɋւ��āA����͏C���I�T���ł����Đ��m�ɃW���X�g�Z�\�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A������V���\�N����Ƃ����{�{�Ɠ`����˂����Ȃ��Ƃ�������������B����ǂ��A�N��ɂ����ĘZ�\�Ƃ��������́A���ʂȈӖ���L����B�l�\�A�\�ȂǂƂ��������͔�r�ɂȂ�Ȃ��B���Ȃ킿�Z�\�́A��N�z�T�C�N���i12�~5��60�N�j�̔N�ł��邩�炾�B �@���ꂪ�����A�Z�\��ł���A���̎����ɒʗL�̂��̏�����������B���Ȃ킿�\�\�u�Z�\��v�A�������́u�Z�\�L��v�ł���B���̎����ł́A�ȉ��ɁA�\�O�A�\�Z�A��\��Ƃ����������L���悤�ɁA�T���ł͂Ȃ����m�ȔN����L���Ă���B����ɑ��A�s�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��t�s�N�\�O����\���㖘�̎���t�Ƃ���悤�ɁA�T���́u�Z�\�P�x�v�u��\����v�ƋL���B���̗p�Ⴉ�炷��A�����͘Z�\������A���̂܂܁u�N����ĘZ�\�v�Ə������ɂ����Ȃ��B�C���I�T���ł͂Ȃ��̂ł���B�v����ɁA �@�@�@�@�s�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�t �@�@�@�@�s�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��t �@���̓���ΏƂ����邾���ł��A�u�Z�\�v�Ɓu�Z�\�P�v�̏��������͖��炩�ł���B���̓_�Łu�N����ĘZ�\�v�ɂ͉��̖����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ꕔ�ɁA���́u�Z�\�v���u�Z�\��v���Ƌ��ق����������B����́A���܂��ܓ�_�̑����{�{�ƕ�����M���ċ^��Ȃ��֖��Ȑ��ł���B�㐢�����ɂ��ẮA���̎j���ᔻ��������Ƃ�����ŕ��������ׂ��ł���B �@���ẮA��������o�������A�u�����d���v�Ƃ����L���ɑ����l�̋��ق����Ă������オ���������A�ߔN�ł͂������ɂ���Ȗ֖��͌�ނ����B�Ƃ��낪�ŋ߂ł́A�u�N����ĘZ�\�v�ɑ��A�����ȋ��ٖϐ������҂��o�Ă����̂ł���B�������Đ�O�������A�ܗ֏��̋L���́A�����ʂ�ɓǂ�ł��炦�Ȃ��̂ł���B �@�ӂ��A�l�͐�������x�Ŋo���邩��A�����̔N����ԈႦ��킯���Ȃ��B�N���܂��Đ���������A���N�ʼn��ɂȂ����Ɗm�F������̂ł���B�����͂��̔N�Z�\�ɂȂ��āA���~�Ɏ���җ���ԋ߂ɍT�����̂��@���ɁA�{�����M���J�n�������ŁA��ˎR�ɓo���ċF�肵���̂ł��낤�B �@�������āA���̈�߂́A�����������ɂ����āA��ނȂ��d�v����L���Ă���B���Ȃ킿�A����ɂ���ĉ�X�́A�����̐����Ɛ��N����肵����̂ł���B�܂��ɂ��̌ܗ֏��ɋ��邩����A �@�@�s�����͓V���\��N�i1584�j�A�d�����̂ǂ����Ő��܂ꂽ�t �̂ł���B�����`�L�����ɂ����āA����ȏ�̂��̂͂��肦�Ȃ��v���C�}���[�Ȏj���ł���B�����ے肷��j���́A����܂ŏo�����Ƃ͂Ȃ��������A������o�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B �@���̏o���n���ɂ��ẮA�{�T�C�g�����́s�����̏o�g�n�͂ǂ����t�Ƒ肷�錤���v���W�F�N�g�̐��ʂ��Q�Ƃ��ꂽ���B �@ Go Back |
 �{�{�����N�� �V���\�N����Ƃ���  �u�����d���v�u�N����ĘZ�\�v �Έ�Ɩ{ |
|
�@ �@�i5�j�\�O�ɂ��Ă͂��߂ď������� �@�������g���L���Ƃ���̂��̍ŏ��̌����́A�����ŏ\�O�A���ŏ\��ł���B���݂Ō����A���w��N�����B��������ɂ́A���߂���ƌ�����������邪�A�K�����������ł͂���܂��B �@�������g�́A�����Ƃ��Ă͋ɂ߂ċ���ȑ̋�̎���ł������ƌ��Ȃ�����B�����̓��{�l�̐��l�j�q�̕��ϐg���͈�Z�Zcm�ɖ����Ȃ��A�\�\�����������̂������炵���B�����͏\�O�̍��ɂ͂��łɕ��̑�l�����傫�ȓ��̂������Ă�����������Ȃ��Ƃ��������͐��藧�B�\��̏��N�����̑�l�����}�̂��傫���Ƃ�����́A�����ł��悭���邱�Ƃł���B �@�܂��A�퍑�����Ƃ͂����փ����ȑO�̓����̖\�͓I�����Ă���A�r�Ԃ镺�@�҂Ƃ��āA���̏��N���A����Γ��ٓ_�isingular point�j�Ƃ��ďo�������Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B �@���m�̂��Ƃ��A�����\�O�̐܂̏ё���Ƃ������̂��A�������c����Ă���B���̂����̊o���̂���u���c�{�{���V���ё��v������ɁA�r�c�b���i���{�E�r�c���x���j�g���̐��ԑg���E�q���o�l�Y�i���ΐ�����n��Z�j���������āA���������Ƃ��Ȃ������̂��A�r�c�b��炪�ނ����o���Ďʂ��������̂炵���B�������̑��́A�s�����V�_���A�_�����c��w�����t�Ƃ����āA���c�Ĉ����ʂɏ������Ă����悤�ł���B�]�˂ł͂��̂悤�ɂ��āA���́u�\�O�v�����ё��悪�ĎO�ʂ���Ă����̂ł���B �@���̋{�{���V���ё�������ɁA�㐢���N������z�����ĕ`�����Ƃ��������A���Ƃ��ƕ���������Ȗѐ[�������ɕ`�����G�������āA��������N�������ƍ��o���Ďʂ������̂ł��낤�B���������A��L�ё��̊o���ɂ͌�l���鏑���āA����͏\�O�̐܂̏ё����Ƃ������A�{���͎O�\���̎��̏ё����낤�ƋL���B���������ĎO�\���Ȃ̂��s�������B �@���邢�́A����́u�{�{�����ё��v�i�{�������˕����j�̎^�ɂ́A�\�O�̐܂̏ё����Ƃ����b�͂Ȃ��A��������Ƃ̉ƘV�������A�������Ă�Ŏd�����������܁A�����̏ё�������`�����̂����ꂾ�A�Ƃ����킯�ł���B�������l��������ȉ��`���킯�͂Ȃ����A����͉摜�ɖܑ̂������㐢�̕t�^�ł���B�����Ƃɂ����A���̃P�[�X�ł́A����́u���N�����v�̏ё��ł͂Ȃ��̂ł���B �@�������A���̉�͐l�C���������ƌ����āA���������Ŏʂ��ꂽ�炵���B�Ƃ��ɂ��ꂪ�\�O�̕����̎p���Ƃ������ƂŁA�l�C���o�����̂炵���B�ܗ֏��͒m�炸�Ƃ��A���������߂Č��������̂́A�\�O�̂Ƃ����Ƃ����b���J�ԗ��z���Ă�������ł���B��L��_����̂��̂����A�֒֎R�k������l��Ƃ�����_�i���c���p�ّ��j�����̈��ł��낤�B �@���̈�A�̏ё���ɋ��ʂ���ߓx�Ȉّ��Ԃ�ɂ́A���ݓ`��镐���̏ё��̒��ł��Ƃ��ɋ����[�����̂�����B�����Ȃ�A�����͋����A���N�̍����炱��Ȗтނ������̕������������݂���������Ƃ����Ƃ��납�A�\�㐢�I�̕����C���[�W��`������ł���B �@����ɂ܂��A�\�O�Ƃ����N��ɂ�������Ă݂�A����́A���`���猋���ւ́A����Α�l�̒��ԓ���́A�C�j�V�G�[�V�����̔N��ł���B���������āA�����̍ŏ��̌������A�����l�ފw�I�Ɍ����Έ��̃C�j�V�G�[�V�����V��Ƃ��Ă̈Ӗ���L���邱�Ƃ��l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�����Ȃ�A���̌����͐��l�Љ�ւ̎Q���֖̊�Ƃ��čs�Ȃ����m�I�E�l�iwarrior murder�j�ł������\��������B�Ƃ���A����߂ăA���J�C�b�N�Ȗ����I�Ӌ`�����̌����͂��Ɖ]���悤�B �@���������āA����̏펯�Ƃ͈قȂ�A���̕����́u����v�́A�����̉��炩�̕��Ɗ��s��w�i�ɂ��Ă���Ƒz�肵����̂ł���B �@Go Back |
 ���c�{�{���V���ё� 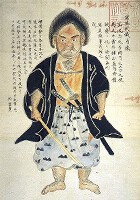 �{�{�����ё� |
|
�@ �@�i6�j�V�c���L�n�앺�q�Ɖ]���@�� �@�L�n�앺�q�Ƃ����l���͕s���ł���B�������ܗ֏��ɂ��̖����L�����̂ŁA�㐢�ɂ��̖����c�����l�ł���B�E�́u���m�S�l���v�ɂ��o�ꂷ��B �@���݁A���̗L�n�u�앺�q�v���u���ւ��v�Ɠǂނ̂���ʓI�����A�u���m�S�l���v�ɂ��U�艼������悤�ɁA����́u���Ђ傤���v�Ɠǂނ̂��������B���ꂪ�c�����̂��ƂȂ�A�Ȃ�����u���ւ��v�ł͂Ȃ��A�u���Ђ傤���v�ł���B �@���m�̐l���ł́u���c�����q�v������B����͔d�B����o���}�O���c�Ƃ̎����I�Ȍ��c�A���c�����q�i�@���j�ł���B�����q�́A�����E���̗P�q�ƂȂ��āA�u�����v�����q�𖼂̂��Ă����B�����̊����̓ǂ݂≹�C�́A�ؗ��x�O�����ŖT�ł���B�����q�̓L���V�^���喼�Ƃ��Ă��L���ŁA�t���C�X�w���{�j�x�iLuis Frois, Historia de Iapam �j�̂悤�Ȑ؎x�O�����ɂ��̖����o�ꂷ��B����ɂ��A�����q�́u�R�f���E�J���r���E�G�v�iCodera Quambioye�j�Ɩ����L����Ă���B�܂�u�����q�v�͓����u����т傤���v�Ɠǂ�ł����̂ł���B �@����Ɠ��l�A�L�n�u�앺�q�v���u���Ђ傤���v�ł���B���������������ǂ݂ŁA���́u�앺�q�v�Ƃ����������������͂��ł���B���������āA�����Ő��Ԍ[�ւ̂��߂ɁA�u���ւ��v�ł͐������Ȃ��A�Ƌ������Ă����K�v������B �@�ܗ֏��̕����ɂ��A�L�n�앺�q�͐V�����̕��@�҂��Ƃ����B�������A�ܗ֏��ł́A�L�n�앺�q�ɂ��āA���ꂵ������Ȃ��B �@�V�����͓����L���̗��h�̈�ł���B���̐V�����ɗL�n�̖��̂��邱�Ƃ��炵�āA����ƍN�ɗL�n�_�������p��������I�B�̗L�n�����̈ꑰ���A�Ƃ�����������炵�����A�ނ�̊m���Ȃ��B���n�����`�L�w��V�L�x�ɁA
�s�~�������V�c���g���N�B�L�ԑ�a��{�V�A�L�ԗ��g�]�t�m��{��L�n�n�B�L��沑O��g���]�t�B���G�A���l�i���B�L�Ԋ앺�q�n���Ƒ��i�����V�B�헤���ю����V�g�]�ҁA�����m�����~�������Z�p����B�V�����B�g���X�B���~�����i���t
�Ƃ��邪�A���Ȃ�̕������Ԉ�����L���ł���B����Ɂu�L�Ԋ앺�q�͑��Ƒ��Ȃ�悵�v�Ƃ���̂́A�u���m�S�l���v�ɂ�����ʂ�A�J�ԓ`����臂��o�Ȃ��B�w��V�L�x�̏\�����I����ɂ́A�`�������ȊO�Ɍ��ޗ����Ȃ��̂��m���ł���B�����̕����]�`���w��V�L�x�̂��̋L�������p���Ă��邪�A����͂��낻���߂�������낵���B�@�Ȃ��܂��A���݁A���̏��߂Ă̌����̒n���A�d�B���p�S�������i���E���Ɍ����p�������j�̉͌��ɔ�肷�镗���x�z�I�ł���B�������A����́A�吳���̒n���̌S�����E�����A�ߑ�̓`���ł���ɂ����Ȃ��B���ꂪ�d�B�̂ǂ����ōs��ꂽ�Ƃ܂ł͌������Ƃ��Ă��A�����Əꏊ����肷��ޗ��͂Ȃ��B �@�]�ˊ��̎����Ȃ�A���ۏ\��N�i1727�j�́w�O����ϕM�L�x�ɁA
�s�\�O�m���A�V�c���m���@�җL�n�앺�q�g�]�ҁA�d�B�j�����A�_�Ӄj�����q�����q�A���~�K�L�m���D�����e�A�����]����v�|���L�X�t
�Ƃ��āA���Ă����悤�ȍu�k�b�ɂȂ�̂����A�����ł͖��g��������͌��ł͂Ȃ��u�l�Ӂv�Ƃ��Ă���B�ꏊ�͊C�l�ł���B�������A
�s�����ӂׂ����肪�����A�Ȃ�l�ӁX�X���������t�i���Ƌ`������j
�̂悤�ɁA�������ŕl�ӂ��͊݁E��[�Ƃ���P�[�X�����邪�A��B�́w�O����ϕM�L�x�ɏ������[���闝�R�͂Ȃ�����A���́u�l�Ӂv�͂�͂�C�̕l�ӂł��낤�B�Ƃ���A���̋L���͔d�B�̂ǂ����C�ݕ����C���[�W���Ă�����̂̂悤�ł���B�@���̓`�����炷��A�����d�B�ł����p�S�����̂悤�ȎR�ԕ��ł͂Ȃ��A�����Â߁A�d����ɖʂ����K���S���l��������i���E�P�H�s�Ԋ���j�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�Ƃ���A�ꏊ�͋{�{���̋ߏ��ł���B �@�������A�w�O����ϕM�L�x�̓`���L���ɗ�������̂��A���قǂɂ��Ă����������悢�B���̋L���ɂ́A���Ƃ��M�ߐ��͂Ȃ��̂ŁA������s�m��Ƃ��Ă����ׂ��ł��낤�B �@ Go Back |
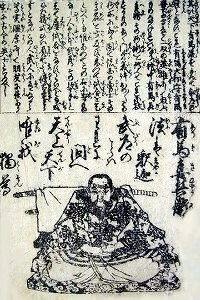 �L�n�앺�q�@���m�S�l��� �u�@�͎߉ށA�����̂��Ƃ́A���� ��ցB�V��V���A�B���Ց��v  �����������̒n�H ���Ɍ����p������  �d�������W�n�} |
|
�@ �@�i7�j�A�n���H�R�Ɖ]���͂̕��@�� �@�L�n�앺�q�Ƃ����l������̍ŏ��̌����ɑ����āA�����\�Z�̂Ƃ��̌����ł���B�������A���ꂪ��������ڂ̏������������A�ƂȂ�ƁA����͊m���ł��Ȃ��B�����͂����͏����Ă��Ȃ�����ł���B �@�A�n���Ƃ����̂́A���݂̕��Ɍ��k���̓��{�C�ɖʂ����n��ł���B�암�̔d���͎R�z���A�A�n�͎R�A���ŁA��������������������قȂ�B����ΐ����d���̏��N�ɂƂ��Ĉٍ��ł������B�܂蕐���́A�\�Z�ňٍ��C�s���J�n���Ă����̂ł���B �@�\�\�Ƃ����̂��A�����̕����`�L�̃X�^���_�[�h�ȕ���ł��邪�A���͌ܗ֏��ɂ͕������A�n�֍s�����Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�u�A�n���H�R�v�Ƃ��邾���ł���B �@�u�A�n���H�R�v�Ƃ́A�A�n���̏Z�l�A�H�R�Ƃ����Ӗ��ł���B�A�n�Ō������s��ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������A���q�̕�����ł́A�����͒A�n�֍s�������ƂɂȂ��Ă���B�ƂȂ�ƁA����͋{�{�ɐD���������畷�����b���낤�B�������A�ǂ����ĒA�n���Ȃ̂��B�����́A���ꂩ�A�n�ɉ��̂��������̂��B �@��������ȉ��́A�]���̕��������ł͏o�����߂��̂Ȃ��b�ɂȂ�B �@���́A�����͓����̒A�n�ɉ��̂��������B����́A�����̏o�g�n���l����A�e�Ղɑz�������B�Ƃ����̂��A�����\�Z�̓����A�A�n�|�c���͐ԏ��L�G�i�����q���L�ʁj�ł���A���̐ԏ��L�G�����A����ԏ����Ō�̏��ł������B�����̐��n�E�d�����K���S�{�{���́A����ԏ����̗̈�ł���A�����̎��������O�A�ԏ��L�G�ɑ��������m�������\��������B �@�A�n�̐ԏ��L�G�̉Ɛb�c�ɂ́A����ȗ��̕���̕��m����������A����䂦�A�������̂̐l�X���������Ƃł��낤�B�d�B����̕������A�A�n�Ɍ��т��̂́A�܂��ɂ��̂悤�Ȋ������ł���B �@�ܘ_�A���N������A�n���킵�߂�A���������l�I�l�b�g���[�N�ɋC�Â��������҂͂��Ȃ��B�T���ɘf�킳�����̂��ƂɋC��D���āA���܂�ɂ��d���̕����ɂ��Ė��m�Șb���肾�����̂ł���B �@���N�����́A�A�n�̒|�c�鉺�ɋ������āA�����ŕ��@�C�s�������ŁA���|���w�Ǝv����B�]���Ȃ�A�����̒m�ƌ|�p�̟��{�̏ꏊ�́A�܂��A���̒A�n�|�c�鉺�ł���B �@�Ƃ����̂��A�ԏ��L�p�́A����ȗ��A�������|�̋����m�F�ł���A�����͒��N��q�w�ҁE�I�����x�����A���{�ɂ�����ŐV�̎�w�����ɐs�͂��Ă����B�L�G�́A�A�n�|�c�ɍE�q�_���������A���{�ł͒����₦�Ă����ך��k�����Ă�l�̋V�������A�ՋV�����s�����B���������V�����m�I�ȃG�l���M�[�ɖ����������A�����̒A�n�ɂ͂������B �@�A�n�́A�����א쎁�̗̍��������O��ɐڂ���B�����ĒA�n�́A�O�g���o�āA���s�֒��������n��ł���B���܁A�a�c�R������̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�̒��ԏ�ɂ́A�P�H�i���o�[�Ƌ��s�i���o�[�̎Ԃ�����ł���B�������A�قƂ�ǂ��̓�����ł���B����͐_�˂�����ł͌������Ȃ����i�ł���B �@���̎����̎��̋L���ɂ́A�������㋞�������Ƃ������Ă���B�Ȃ�قǁA�����ɂƂ��āA�A�n�́A�d���Ƌ��s�����Ԓ��p�_�ł������̂ł���B�d������A�n�ցA�A�n���狞�s�ցB���̃v���Z�X�����A��������Ă���̂��������B �@���������āA�������A�n�֍s�����Ƃ��Ă��A����͒P�ɗ��̓r���A���R�ɗ���������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����͂��炭�A�n�|�c�鉺�ɋ������āA�Ő�[�̒m�ƌ|�p�̌O�����A�������āA���s�L�т�l�������̂Ǝv����B �@���̈Ӗ��ŁA�����ɂƂ��āA�A�n�Ƃ����y�n�̈Ӌ`�͑傫���B�ܗ֏��ɁA�u�A�n���H�R�v�̂��Ƃ������āA������L�O�����̂ł���B�\�Z�̕����͏H�R�Ƃ������G�Ɛ���ď������B�ɐD�̏��q�蕶�́s�F�߁A�X�ɖ��t�ƋL���Ă���B���̊X�k���܂��l�Ƃ́A�A�n�̒|�c�鉺�̂��Ƃł��낤�B �@�Ƃ�����A���̒A�n���̏H�R�͕s���Ȑl���ł���B�ܗ֏��ɕ������L�����Z�\��ȏ�Ƃ��������̂����A��̓I�ȑ���̖����������܂�Ă���̂́A���̏H�R�ƑO�L�̗L�n�A���̓�l�����ł���B���Â�����������N���̌�������ł���A���̖����L���ȏ�A�����ɂƂ��ĈӋ`�[�������������̂ł��낤�B �@������ɁA�����`�L�̒��ŕK�����M�����A�L���ȏ����Y��g�����̖��͏o�ė��Ȃ��B����͂ǂ������킯���낤�ƁA���ꂵ���v���̂ł͂Ȃ����B�������A���������㐢�̊��҂𗠐邠���肪�A�����Ƃ����l���̖ʔ����Ƃ���Ȃ̂ł���B �@�ق�Ƃ��́A�ӔN�̕����ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A���������㐢�L���ɂȂ������������A�L�n��H�R�Ƃ�������Ɛ�����v���o�ł���B�H�R�̖��́A�ނ����G����������A�����͏����c�����̂��낤���A������A�A�n�Ƃ����y�n�̉��������L���Ɍ��т��Ă��邩��ł���B �@ Go Back |
 ���������n�}
*�y���q�蕶�z  �A�n�|�c�隬 ���Ɍ������s�a�c�R���|�c  �ԏ��L�G�W�n�}  �u�V��̏�v�|�c�� |
|
�@ �@�i8�j��\��ɂ��ēs�ւ̂ڂ� �@�����͓�\��̂Ƃ��s�i���s�j�֏��A�V���̕��@�҂ɏo��A���x���������s�Ȃ������A��������Ƃ��������Ȃ������Ƃ����B �@���́u�V���̕��@�ҁv�Ƃ����̂��A�g���ł��낤�ƌ����͂����A�����͂ǂ��܂ł���A�����ߍ���ł�����̂炵���B�Ƃ��낪��������A�{�q�ɐD�����Ă����q�蕶�ł́A���Ȃ�ڍׂȘb�ɂȂ��ďo�Ă���B�����g���̑ΐ�L���Ƃ��Ă͍ŌÂ̂��̂�����A�ꉞ���Ă����K�v�����낤�B�����͊��������A�ȉ������ǂ߂A
�s��A���t�ɓ���B�}�K���̕��p�A�g���Ȃ�җL��A���Y��������Ɛ��ӁB�މƂ̎k���\�Y�A���O�@�i��ɉ��ė��Ղ̈Ђ𑈂ӁB���s��������嫂��A�ؙ��̈ꌂ�ɐG��āA�g���A��O�ɓ|�ꕚ���đ����B���߈ꌂ�̑��L��Ɉ˂�āA�������J���B�ނ̖吶���A�����Ĕ�ɘ����ċ���A�����A�Q���ɂ��ĕ����B���ɕ��p�����āA賔����L��ʁt
�@�b�͂������B���s�֍s���āA�u�}�K���V���p�v�A�܂���{��̋g���Ə̂���g�����̒��k���\�Y�ɏ�����\����A���O�̘@���Ŏ����������B���\�Y�͕����̖ؓ��̈ꌂ�œ|�ꂽ�B���˂āA�����͈ꌂ�����ł���ȏ�͑ł��Ȃ��A�Ǝ�茈�߂Ă������̂ŁA���\�Y�̖������܂ł͂��Ȃ������B����͔ނ��˔ɏ悹�ċ������B���\�Y�͎��Â��ĉ������A�������p���̂Ē䔯���ďo�Ƃ����\�\�B�@���������b�����q�蕶�̏o����܂łɑ��݂��Ă������̂炵���B�Ƃ��낪���̕����g���̋L���͂܂�����������B
�s����A�g���B���Y�A���A���O�ɏo�A���Y�������B�B���A���P�ؙ̖����Ę҂���B���U�A���̋@�ɗՂ�Ŕނؙ̖���D�ЁA�V�����B�n�ɕ����ė����Ɏ����t
�Ƃ����āA���x�͋g���`���Y������B�������A���q�蕶�ɂ́A�`���Y�����\�Y�Ƃǂ�ȊW�ɂ���̂��A�L���͂Ȃ��B�`���Y�𐴏\�Y�̒�Ƃ���̂́A�㐢�̔��n�����`�L�ɂ����Ȃ��A����͔��Ŕ����������[�J���ȓ`���ł���B�@�����ꏊ�͂�������O�ł���B�ꏊ�͕s���ł���B�ڗ]�Ƃ��������E��m�ȏ�A����Ȗؓ�����ɂ����`���Y�����A�����͉��Ƃ��̖ؓ���`���Y����D���āA�ނ�o�E���Ă��܂����B�u���|���v�Ƃ������瑦���ł���B �@�������ĕ����́A�V���̕��@�ҁA�g�����l�Ȃ���|�����B�Ƃ��낪�A���q�蕶�̋L���ɂ͂܂������������āA��̗��O���菼�̌����̘b�������ɏo�Ă���B
�s�g�����吶�A�����܂ݖ��ꂵ�ĉ]���A���p�̖����ȂẮA�G�����ׂ����ɔA�Ԃ���ɉ^�炳��ƁB�����āA�g�������Y�A���p�ɊA���O�A����粂�ɔނ̖吶���S�l������A�����|�����ȂāA�����V���Q����Ɨ~���B���U�A�����A���m��̍ΗL��A��`�̓������@���Aↂ��ɌႪ�吶�Ɉ��Ђĉ]���A�A�T�lਂ�A���₩�ɑނ��B�c�Љ��G�Q�𐬂����𐬂��Ƃ��A��ɉ����ĔV������ɁA���_�̔@���B���̋����V�L���A�ƁB�O�G���U�����A����̖ҏb��ǂӂɎ�����B�Ђ�k�Ђė��z�ɋA��B�l�F�V�����Q���B�E���m�d�A��l���ȂĖ��l�ɓG����ҁA���ɕ��Ƃ̖��@��t
�@�Ƃ����킯�ŁA�g�����\�Y�A�`���Y�ƁA��l�܂œ|���ꂽ�吶��͉���������A�u���p�̋Ƃł͕����ɂ͏��ĂȂ��B������낤�v�Ɗ�B�g�������Y�͕��p�ɂ��Ƃ悹�āA���菼�̕ӂ�ɖ吶���S�l�����W���A���܂��܂ȕ�����g���ĕ������E�Q���悤�Ƃ����B�����͓����������z���˂��������̂ŁA���̕s���ȓ������@�m���āA�����̖��Ɏw�������B�u���O�����͊W�Ȃ��l�Ԃ��B�����ɑދ�����B���Ƃ��G���Q����Ȃ������Ȃ��قǑ����ł��A���̊Ⴉ�猩��A���_�݂����Ȃ��̂��B�ǂ����ċ���邱�Ƃ����낤���v�Ƃ����B���ʂ́A�����ҏb��ǂ��Ɏ��Ă����B�����͏����A�Ђ�k���Ďs���A�����B�l�݂͂Ȃ�������Q�����\�\�Ƃ�������ł���B�@�g����吔�S�l�A����ɕ����͈�l�A���̋L�����̂��p�Y杂̓T�^�݂����Ȃ��̂����A���łɕ�������\����̏����O�N�i1654�j�Ƃ��������i�K�ŁA�����܂ł̐��b���o���オ���Ă����̂ł���B����Ȍコ�܂��ܔ��h�����āA��̕����`���̃n�C���C�g�ƂȂ�g�����Ƃ̑Ό��K���`�������̂ł���B �@���q�蕶�́A�����ɔs�k���ċg�����@�Ƃ��u����v�����Ƃ������B�Ƃ��낪�w�{�����|���`�x�ł́A�g���͖��O�Y�Ƃ����҂�����k���ł��̌���������Ă��邵�A���̖��O�Y���c���\��N�̋֒��\�y���s�̂����n�������̑������N�����A�x��̎҂�ɎE���ꂽ�Ƃ����b������B �@�Ƃ������Ƃ́A�c����N�ɕ����ɔs��āA��������́u����v�����g�����@�Ƃ��A���̖��O�Y��ɂ��ĕ������ꂽ�悤�����A���̋֒��T�S�����ŁA�g�����@�Ƃ͂܂��܂���w�ɕm�����͂��B�Ƃ��낪�A���̌���A�g�����͑��������悤�ł���B �@�勝���N�i1684�j�̕��Z���S�w�g���`�x�ɂ́A���̏����Ƃ͂܂������قȂ�u�{�{�����v���o�ꂵ�ċ����[�����A�����͐������g���̗R�������n�앨��ŁA�@������A�����ɓo�ꂷ��u�{�{�����v�́A�x�c�����Ƌ{�{�����̃n�C�u���b�h�����̂ł����Ȃ��B���̂�����́A�m�����сn�{�{�����`�L�W�̒O�����ϕM�L�lj����Q�Ƃ̂��ƁB �@Go Back |
*�y���q�蕶�z
�s�㓞���t�B�L�}�K���V���p�g���ҁB�������Y�މƔV�k���\�Y�B�����O�@�i��Aॗ��ՔV�ЁB嫌����s�A�G�ؙ��V�ꌂ�A�g���|�瘰��O������B���˗L�ꌂ�V���A��J��������B�ޖ吶�������㋎�A�Z�������Q�����B�������p賔��L�t  �@��쌻���@���s�s�k�掇��
*�y���q�蕶�z
�s����A�g���B���Y���o���O�A�����Y�B�B���������P�ؙ��ҁB���U�Ց��@�A�D�ޖؙ����V�B���n�������t
*�y���q�蕶�z
�s�g���吶�ܛ�����]�B�ȕ��p�V���G���A�^�ԉ����B���g�������Y�����p�A�𘰗��O����粁B�ޖ吶�ɕS�l�A�ȕ����|�����~�Q�V�B���U�����L�m��V�A�@��`�V���Aↈ���吶�]�B��ਖT�l���ށB�s���G���Q�����A���ᎋ�V�@���_�B�����V�L�A�U�O�G��B������ǖҏb�A�k�Ў��A���z�B�l�F���Q�V�B�E���m�d�A�Ȉ�l�G���l�ҁA�����ƔV���@��t  �{�{�g�������V�n�� ���s�s�������掛�ԃm�ؒ� ���������q�蕶�́u���O�����v�� ���̒n�ł���Ƃ��������͂Ȃ� |
|
�@ �@�i9�j�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ� �@���s�œV���̕��@�҂ɏ����Č�A�����͏����e�n������A���܂��܂ȗ��h�̕��@�҂Ƒ������A�Z�\��ȏ�������������s�Ȃ����̂ł��邪�A��x�������Ȃ������B����͏\�O����\���A��܂ł̂��Ƃł������\�\�Ƃ������Ƃł���B �@���̖��s�̋L�^�́A�����̕����]�`�̒��ŕK�����M����鎖�ւł���B���̌ܗ֏��̋L����ǂ߂킩��悤�ɁA���̘Z�\��ȏ�̎d���́A�\�O����\���A��܂ł̂��Ƃ��Ƃ����̂ł���B�܂�A����͕����̏\�ォ���\��܂ł̊Ԃ̂��Ƃł���B �@�Ƃ��낪�A�����Ό�����̂́A��������ʂ܂ł̐��U�ŘZ�\��ȏ�̎����Ɗ��Ⴂ�������ł���B�ӔN�̎����܂ŁA���́u�Z�\�]�x�v�ɉ����Ă��܂��̂ł���B �@���������炩�ɁA�������g�̋L�q�ł́A����͏\�ォ���\��܂ł̊Ԃ̏\�܁A�Z�N�Ԃ̂��Ƃł���B���̌�̎����͐��̂����ɓ����Ă��Ȃ��ƌ���ׂ��ł���B���Ƃ���A���̘Z�\�]�x�̏����ƁA���̌�̎����Ƃ́A�����Ⴄ�̂��B�����͂����炭�A�����Ɠq�������������ƁA�����ł͂Ȃ������Ƃ̑���A�Ƃ������Ƃł���B �@�Ƃ���A�����͎Ⴂ���̏\�܁A�Z�N�ԂɘZ�\��ȏ�����������̂ł���B���ꂾ�ƁA�N���ώl��́\�\�P�Ȃ鎎���ł͂Ȃ��\�\��������������Ă��邱�ƂɂȂ�B�����狭�����C�s�҂��Ƃ��Ă��A����͐q��̂��Ƃł͂Ȃ��B�Ⴋ�����́A����Ӗ��Ŗ����Ȓj�������̂ł���B �@�ӂ��́A�ꐶ���̌����ł��A�����㐢�ɂ̂������Ƃ�����B���Ƃ��A����������̎҂ł́A���i�\��N�ɉ�z�����Ҍ����ŗL���ȍr�ؖ��E�q�傪����ł���B����ɑ������͘Z�\��ȏ�A���������Ӗ��ł́A�����͖{���ɖ����Ŗҗ�ȕ��|�҂������B �@�Ƃ���ŁA���́u�Z�\��ȏ���������ĕ��������Ƃ��Ȃ������v�Ƃ����L�q�ɂ��āA�������炵�����������Ă���̂��A�Ƃ������]�����Ȃ���Ă����B�������A����͊��Ⴂ�Ƃ����������m�Ȃ̂ł���B �@�܂�A�l�͌�������̂�������O�ŁA����Ȏ����b�͕@�����Ȃ�Ȃ��Ƃ���̂́A�ߑ�̓���I�Z���X���炷�铹���I���f�ł����āA����Ȃ��̂͌ܗ֏��̋L�q�Ƃ͖����Ȃ̂ł���B �@���̋L�q���A�ܗ֏��Ƃ��������̎��������Ƃ��ď�����Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł͗�@�Ƃ��āA���g�̖��̂�A���������҂��A�������Ă����̂��A�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�悤����ɁA�t�[�e���̓Ђ��u��O�A�����Ɣ����܂���́c�v�ƌ����āA�m�`���̂Ɠ�����@�Ȃ̂ł���B�������������I�V���Ԃ̒��Ɍܗ֏���������������B �@���������āA�������������̐m�`�̐�l���A�����b�ƌ������͖̂��m�ɓ������̂ł���B�Ƃ��ɕ����̏ꍇ�A�ǂ������̉ƒ��̒N����A�Ƃ������̂������悤�Ȓ��������݂ł͂Ȃ��B����͕��������U�A���O�҂Ƃ��Ă̕��@�҂ł��葱�������ՂƂ݂�ׂ��ł���B �@�b�����ǂ��A�P�Ȃ鎎���ł͂Ȃ��������̌��������́A��L�̂悤�ɓ�\���A��܂ŁB������A���̍�������I��ɂ����炵���B���̔N��炵�āA��ʂɍŌ�̌����Ƃ����̂́A�w�����`�x�w��V�L�x�Ȃǔ��n�`�L�Ɍc���\���N�i1612�j�̂��Ƃ���ޗ����̈ꌏ�ł���B���Ƃ��A������c���\���N�Ƃ���͔̂��n�`�L�݂̂ŁA�}�O�̓`�L�w�O�����ϕM�L�x�ɂ͕����\��̂��ƂƂ���B���������āA�ޗ��������̔N�͕s���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̌��ɂ��ẮA�{�T�C�g�ɕʂɘ_�c����Ă���̂ŁA������Q�Ƃ��ꂽ���B �@�܂��A�ܗ֏��ɂ́A�g���̖����L���Ȃ����A������́A�㐢�̕�����ڗ��ɂ܂łȂ����L���Ȋޗ��������̂��Ƃ��A�����͉��������Ă��Ȃ��B�܂�́A�M���Ŋޗ���ł��E�����������A�Z�\��ȏ���������ĕ��������Ƃ��Ȃ������Ƃ����ނ̐퓬�҂Ƃ��ẴL�����A�̈�ɂ����Ȃ����̂̂悤�ł���B �@�O�Ɉ��������q�蕶�ɂ́A���̛ܗ��Ƃ̌����̋L�������łɂ���A�������ޗ�������杂̒��ł��A�܂��ɂ��ꂪ���o�L���ł���B
�sূɕ��p�̒B�l�L��A���͊◬�B�ނƎ��Y�����������ށB�◬�]���A�������ȂĎ��Y�������𐿂ӂƁB�������ւĉ]���A���͔��n�����Ђđ��̖���s�����A��͖،���č��̔�����͂���ƁB������������ԁB����ƖL�O�̍ہA�C���ɓ��L��B�M���ƈ��ӁB�_�Y�A�����ɑ������B�◬�A�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂���A�����ڂ݂��p��s�����B���U�A�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���A�P�x���B�̂ɑ��A�M�������߂Ċ◬���ƈ��Ӂt
�@�b�͂܂�A�������B�\�\�◬�Ƃ������p�̒B�l�������B���̋L���ł́A�����͕̂����ł���B�◬�̕��͎ė����A�u�^���ŏ��������悤����Ȃ����v�Ƃ����B����ɑ������́u���͐^����U����Ė��Z��s�����B���͖ؓ��Ŕ�p�������悤�v�Ɠ������B������������тƂ��邩��A���̃P�[�X�ł́A�����͌_���K�v�Ƃ������̂炵���B���҂͒���ƖL�O�̊Ԃ̊C���ɂ���M���ŏ������邱�ƂɂȂ����B�◬�͎O�ڂ̔������Ƃ�������A����͒��������ł���B�����͖ؓ��A�������ꌂ�Ŋ◬��ł��E�����B�@�ӂ��͖ؓ��Ɛ^���Ȃ�A���̕����L���Ƃ݂Ȃ����B����͌��̕����E���͂����邩��ł͂Ȃ��B�ؓ��͒f�ʌ`�炵�Đ^�����^�����x�ɂ����ė�邩�炾�B�����������͖ؓ����g���B����͕������O�͂��q��ł͂Ȃ��������Ƃ̏؍��ł���B �@�ނ��A����ł́A�����͐܂ꂽ��Ȃ�������A�ړB���o��ŕ����O�ꂽ��ŁA���͂����Ď��p�ɑς�����̂ł͂Ȃ��B����I���p�I�ȕ����ɂ́A�^���ɑ���v������͂Ȃ��B �@����ɉ����ĕʂ̂��Ƃ�����B���Ȃ킿�A�ؓ����g���̂́A����Ӗ��ōł��v���~�e�B���ȕ���g�p�ł���B�Ƃ����̂��A����͐�Ƃ������A���ӂ��邱�ƁA�K�E�̓�����ł�_�������̂ł���B�o�E�ł���B �@���̖o�E�͎E�l�̌��n�`�Ԃł���A������̓���A�E�����ɁA�����̐퓬�v�z�̍��{���_�Ԍ�����̂ł���B����������A�����ɂ́A�S�@�_�̒ʑ��I�N�w�͂Ȃ����A�B����`�̂����̔��w���Ȃ��B�����Ɩ\�͂̍����ɂ܂ŃA�N�Z�X�����퓬�҂ł������B �@ Go Back |
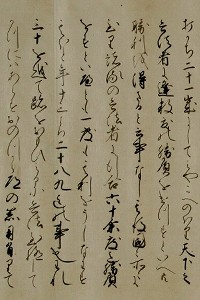 �g�c�Ɩ{�n�V���@���Y�ӏ�
*�y�����`�z
�s�����A�n�s�ҁm�c���\���N�p�q�A��\����n�̒������n�����m��j���e�c�t *�y��V�L�z �s�����c���\���N�l���A���U�s�������q�j�҃��m��\��i���n�B�������n������m��j�����t *�y�O�����ϕM�L�z �s���V���\����A�ܗ��g�m�����m���B�ܗ��n���`�V�̍���B�Óc�����Y�g�]�A���{�m�Җ�g�J���B����A�ٔV���n�Ãm��粃j�A���B笎d�m�y���A���g�J���t *�y���q�蕶�z �sৗL���p�B�l�B���◬�A�^�ދ������Y�B�◬�]�A�������������Y�B�������]�A�����������s�����A���،���������B��������B����^沑O�V�ۊC���L���A���M���B�_�Y���������B�◬��O�ڔ����ҁA�s�ږ��s�p�B���U�Ȗؙ��V�ꌂ�E�V�B�d���P筁B�̑����M���A���◬���t  �ޗ����@�R�������֎s |
|
�@ �@�i10�j���O�\���z�āA�Ղ������Ѓ~��� �@���̂���������Ȃ��Ƃ��͏����Ă���B �@���������𑲋Ƃ��������́A�O�\���z���āA���̂��ߋ���U��Ԃ��Ă݂�B�����Ďv������B�����̕��@�A�퓬�p�����ɂɒB���Ă����̂ŏ������̂ł͂Ȃ������B���R�ƕ��@�̓��̓����������āA�V�̌����𗣂�Ȃ����������ł��낤���B���邢�́A�ΐ푊��̑����̕��@�Ɍ��ׂ����������炾�낤���A�ƁB �@����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă������A�����ŕ������q�ׂĂ���̂́A�����͖��s�ł���ė��ꂽ���A����͎����̗͂̂����ł͂Ȃ��A�ƌ����Ɍ������Č����Ă���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B
�s���̂Â��瓹�̊�p����āA�V�����͂Ȃꂴ���ւ��A���́A�����̕��@�s���Ȃ鏊�ɂ�t
�@�ĊO��������Ă���̂́A���̕����₢�����̋^�╶�ł��邱�Ƃ��B�����₢�Ƃ��āA����䂦�A�Ȍ�̓��̒T���ւƘb���i�ނ̂ł���B�@�Ƃ��낪�A�����Ƃ킯�̔���ʌ���́A�s���̂Â��瓹�̊�p����āt�Ƃ����ӏ��̌�߂ł���B����ɂ��ẮA�u������˔\�������āv�Ɩ��Ⴊ��O���炠��A���������ނ˂���P������߂��嗬�ł���B �@���яG�Y�͂���ɂ��ď�����������������Ă���B�����������A���Ă���ȏ�̓ǂ݂͏o�Ȃ������Ƃ����Ӗ��ŁA�����Ēʂ�ʓlj��Ȃ̂ŁA�E�Ɍf����B �@�悸�ŏ��ɖ��炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂́A���т̌�߂ł́A�u��p�Ƃ́A���_�A��p�s��p�̊�p�v���Ƃ������Ƃ����A���ꂪ�ԈႢ�ł���B���т̗����́A�u��������|�̍˔\�������āv�Ƃ���������ʂ̌�߂�����̂ł͂Ȃ��B�����A���̕��̂悤�ɁA�u��p�v�Ƃ������t�ɓO�ꂵ�čS���Ă݂����Ƃ��낪�A���ѓI�Ȃ̂ł���B �@�u��p�v���l�I�Ȋ�p�s��p�̊�p���w�����Ƃ͓������łɂ��������A�����ŕ����̂����s���̊�p�t�Ƃ́A���̈Ӗ��ł͖��_���肦�Ȃ��B����͓��́u�͂��炫�v�u��p�v�Ƃ����Ӗ��ł̊�p�ł���B �@���т͂�����A�l�I�Ȋ�p���̂��Ƃƌ�߂��āA�u�ړI�𐋍s�������̂́A�����̐S�ł͂Ȃ��B�����̘r�̋����ׂ���p�ł���v���D�u�ƌ��B�����������̕����悭����܂ł��Ȃ��A����͎����̘r�̊�p�ł͂Ȃ��A�u���̊�p�v�Ȃ̂ł���B �@���т́s���̂Â��瓹�̊�p����āA�V�����͂Ȃꂴ��̂��t���A�e���ɂ��悭�ǂ�ł݂Ȃ������炵���B�����ŁA�u��p�v�������̊�p�s��p�̊�p�ƍ��o���A���̂܂ܓ˂������ĉE�̂悤�ȃ��j�[�N�ȓlj���W�J���Ă��܂����̂ł���B �@�u�K�v�Ȃ̂́A���̊�p�Ƃ��ӕ��̂��ꂽ�l�ւ̉�����v�\�\�D�u���镶�͂̓Y�b�������Ƃ��A�ߎS�ł���A�Ƃ������Ⴊ���̕��ł���B �@���т́u��p�v���A�����ȍl���ł͂Ȃ������Ȃ߂Ă����āA�������]�A�D�ꂽ���̂Ƃ��ċ~������A�Ƃ����葱�������B����Ώ��тɂ͏퓅��i�ł��邪�A�����ŏ���Ȏ�������āA�������ĂĎ��n���邾���̂��Ƃł���B�ǎ҂͂��ꂪ�펯�̓]���ł���悤�ȍ��o�ɓ����āA�������o����\�\���������ї��ł���B �@���ǁA�E�̏��т̓lj��ɂ����Ďc������̂́\�\�u���@�́A�V�O�̂����ɂ͂Ȃ��B�L���ȍsਂ̒��ɂ���v�Ƃ����A����Ӗ��ŕ��}�Ȏv�l�����ł���B�c�O�Ȃ��ƂɁA�u�s�ׁv�u���s�v�Ƃ����T�O�ɂ܂Ŏ�������Ȃ���A���т͎�����点�āA���̊T�O�̖L�`�������Ă��Ȃ��B���т̌��E�ł���B �@�Ɠ����ɂ���́A�]���̕����_�̌��E�ł�����B�ō��̕����_�ł���A�]���͂��̂��肳�܁A����䂦�ɂ����A�V�����n���ɗ��r���������_�̊��҂����Ƃ���ł���B �@���߂Č����A�����ŕ����̂����u��p�v�́A���̂�̌l�I��p�ł͂Ȃ��A�u���̊�p�v�Ȃ̂ł���B���̍�p�A���̂͂��炫�ł���B�����܂ł��Ȃ����A�����������̂͂��炫�Ƃ����v�l�͓����V�������̂������B �@����ɂ��Ĉȉ��̂��Ƃ��m�F���Ă��������B���Ȃ킿�A����͏�����_���̉���Ƃ��č��������钆���I�v�l�Ƃ͈�����A�ɂ߂ĐV�����ߐ��I�Ƃ�������ۓI�v�l�̏o���ł���B�C���_�Ƃ��Ă̓��̎v�z�́A�����I�F�ʂɐ��ߏグ���āA�ȑO���炠�����B�������A�����̂����u���v�́A���炩�Ɏ�q�w��ʉ߂����Ȍ�̍�����`�I�Ȏv�l�ł���A���������ۓI�ł���B �@�O�\���߂��āA�����͏���������邱�Ƃ��Ȃ��A�����d�������_�Ƃ���悤�ɂȂ����B�����ŁA�P�H�E����E���̂����炵���̎�A�{���ƂƏ��}���Ƃɐe�߂��A���@�w��̂������A�O�ؔV���A���ňɐD��{�q�ɂ��āA���ꂼ��A�P�H�Ɩ��ɋ{�{�Ƃ�n�݂����B �@�������A�ܗ֏��̋L�q�ɂ��A�����͂܂������ƁA�C�s���d�˂Ă����B����͍ŋ��̕��@�҂ƂȂ�����́A����̏C�s�ł���A����Ε����ɂ�������ʋ��ʂł̏C�s�ł������B �@ Go Back |
*�y���яG�Y�̓lj��z  �d�������W�n�} |
|
�@ �@�i11�j���@�̓��ɂ��ӎ��A��\�̔�� �@���̂�����������������Ă���͔̂����Ȃ��Ƃ��B �@�����͂��̌�A�Ȃ����[��������Ƃ��āA���ɗ[�ɒb�����Ă����B�����������ʁA���������@�̓��ɂ���ƓK���悤�ɂȂ����̂́A�\�̍��ł������B������ȗ��́A�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ��āA�Ό��𑗂��Ă����A�ƁB �@����͂���u����̏C�s�v�ł���B�����́A��\��܂ŘZ�\����̌����ɔs���m�炸�A�����ʂ�V�����o�A�ŋ��̕��@�҂Ƃ��Ă̖������l�����A���������łɌ��������𑲋Ƃ����B�����͕��@�҂Ƃ��Ă̖ړI��B�����Ă��܂����͂����B �@�s�ׂ͂���ړI�̂��߂ɁA������������邽�߂ɍs���A�Ƃ����̂��X�^���_�[�h�ȍs�ח������Ƃ���A���̎���̏C�s�͂��肦�Ȃ����Ƃł���B�ł́A�Ȃ�������������̏C�s���K�v�Ȃ̂��B���́A�����ɂ͍s�ׂƒB���Ƃ̊Ԃ̍��{�I�t��������B �@�����炭���̎���̏C�s�́A�T�ƂȂǂŌ����u�؏�̏C�v�A�܂������ɂ܂��C�s������Ƃ����u�C�؈�@�v�̍l���ɋ߂��B�����C�s�̖ړI�͌�B�ł���B��������B���Ă��܂�����͉������邩�A�Ƃ����A�܂��C�s������̂������B����ɂ͂܂��A���Ɏ�������ȁA����ɑ�����ȂƂ����T�ƈꗬ�̎u�������邪�A�Ƃ���A��肻�ꎩ�̂͑��݂��Ȃ��Ɓu���v�킯�ŁA����́A�g�|���W�J���ȃ��[�v��`���v���Z�X�ł���B �@�ʂ̌�����������A�����͉��ғ��o�R�����Ƃ������Ƃł���B �@�}�l�́A�u�����v�֓��B���悤�ƁA���������w�͂���B�Ƃ��낪�A�����̂悤�Ȃ��̓��̓V�˂ɂ��āA�����͖����o�Ȃ��̂ŁA�C��������A���łɓV�����o����u�����v�ɋ����Ƃ������ʂł���B �@�����́A���s�ŋg������œ|���A���̏�A����������đ�������߂ď��������A���ǁA���������G�ɂȂ��Ă��܂����B�������A�Ȃ��A�����������Ă��܂����̂��A���ꂪ������Ȃ��̂ł���B�����͂��̓V�����o���鎩�g�ɔ[���ł��Ȃ��B�V�˂䂦�̌ǓƂł���B �@�������A�����͑Ë����Ȃ��B�����ɔ[���������܂ŁA���̓��������߂�B����u�Ύ��v�ȋA�蓹�̉����������Ă͂��߂āA�u����v�Ƃ���������B���̓��̓V�˂ɂ��āA���̓��j�A�ȒP���ł͂Ȃ��A���ғȂ̂ł���B �@�����̏ꍇ�A�Ȃ����[��������Ƃ��鎖��̏C�s���ŏI�I�Ɋ�������̂́A���������@�̓��ɂ���Ƒ�������悤�ɂȂ������ł���B�����͂���́A�\�̍��ł������Ƃ����B����Ε����́A��\�N�����̎���̏C�s�Ɏ��Ԃ��₵���̂ł���B �@�����ŋ����[���̂́A���̓��������Ƃ́A�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ��āA�Ό��𑗂��Ă����A�Ƃ���������ł���A�������s�����I�t�ƌ����Ό�����Ƃ���ł���B �@�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ����A�Ƃ����̂́A�܂�͌����Ƃ��Ắu���v�Ɉ�̉������A���ꉻ�����Ƃ����A�_���`�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ނ���A���g�̖ړI�Ƃ��Ă̂��������u���Ɂv���̂��̂��������Ƃ��A�u�����T�����ׂ����͂Ȃ��Ȃ����v�ƌ�肦��̂ł���B �@���̓_�����́A�ɂ߂Ď��R�Ȓn�_�܂ōs�����Ƃ������Ƃł���B�����͎��R�Ƃ������t���g�p���Ă���B����������͏�����X�̗p�@�Ƃ͈قȂ�B �@�܂��X�̗p����u���R�v�Ƃ������t�͖����ȗ��̋ߑ�I�ȊT�O�����A���̌��t���͕̂����ɗR�����Â����炠�����B���������������́u���R�v�Ƃ������t���g���Ƃ��A����͌����Ƃ��Ắu���v�ɑ����Ă͂��߂ē��鎩�R�Ȃ̂ł���B �@�������悤�₭���ɓK���悤�ɂȂ����Ǝv�����̂́A�\�̍��B���Ώ��}���Ƃ̖L�O���q�ڕ��ɂƂ��Ȃ��āA�������d�������B�֍s���̂��A���i��N�i1632�j�A���̂Ƃ��l�\��B������A�����́A�O�\��`�l�\��̂قړ�\�N�ԁA�d�������ʂ��āA����̏C�s�ɔ�₵�Ă����B�������s�N���A�d�������_�Ƃ����������A���̎���̏C�s�̊��ԂƏd�Ȃ�̂ł���B �@ Go Back |
  �����R  |
|
�@ �@�i12�j�����ɂ���Ă��Ɏt���Ȃ� �@�L���Ȉꕶ�ł���B�ܗ֏��̒��ł��w�ɐ�������قǏ]���������e�[�[�ŁA����{���������Ă���Ɏ��g�ށB �@������������A�����́u���M�v�Ƃ��A����Ǝ���d�́u�s���v�Ƃ��A���������ނ̉��߂����ׂ��ł͂Ȃ��B �@�����Έ��p����āA��C�����Ă��܂��Ă��錾�t�����A�u�ƍs���v�́A �@�@�@�s���~�͑����A���~�����̂܂��t ������B���́u�ƍs���v�������̎������Ƃ����̂��A���n�����`�L�w�����`�x�w��V�L�x�ȗ��̓`�������A���ꂪ�����̒��q���Ƃ����m�͂Ȃ��B�������A���̏��X�͕ʂɂ��Ă��A���̌��t�͂����ɂ������̌��������Ȃ��Ƃł���B �@����_�͋M�����������A�����͐_���𗊂�ɂ��Ȃ��Ƃ����̂ł���B���̃|�W�V�����͂���Β�������ߐ��ւ̉ߓn���̎v�z�ł���B���Ȃ��Ƃ��A�_�������Ȃ��c���Ȍ������Ď��A�����̐l�X�̎r�̂��琶�����v�z�ł���ɂ������Ȃ��B �@�ł́A�_���ł͂Ȃ��A���Ɉˋ�����̂��B�܂��ɂ��ꂪ���H�����Ƃ��Ắu���v�ł���B �@���������݂ɋ�g���ĉ^�p�����鎞�A�܂��ɐl�Ԃ͎��R�Ȃ̂ł���B���̌��������Ƃ��Ε����@���Ƃ����Ƃ��A���m�ߑ�Ȋw���a�������B����Ӗ��ŁA�ߐ������͂��������\����L��������ł���B �@�����͎��H�������@������������Ƃ�������̏C�s��ʂ��āsreflexive process�t�̃g�|���W�J���ȓ�������B���ӎ��ɂ���Ă��܂����s�ׂ����߂čl����B����͂��Ԃ�\���E�ł��肦����������Ȃ��T�C�G���X�i�Ȋw�j�Ƃ��Ă̒m�ł������B
�s���@�̗��ɔC�ď��Y���\�̓��ƂȂ��A�����ɂ���Ă��Ɏt���Ȃ��t
�@���@�́u���v�ɂ܂����āA���X�̌|�\�̓��Ƃ��Ă����̂ŁA�����ɂ����Ď��ɂ͎t���Ƃ������̂��Ȃ��A�ƕ����͌����B�����́A�L���Ȉꕶ�ł���̂ɁA�]���܂�������ǂ���Ă����ӏ��ł���B�@����䂦�A�܂��A���́u���v�Ƃ�����ɍS�D���Ă݂�K�v������B���̌ܗ֏��ŕ����͂��́u���v�Ƃ������{���S�тɂ킽���đ��p����B���������ꂼ��̕����ɂ܂����āA���̌�`�͈ꗥ�ł͂Ȃ��B���`�I�Ȍ�ł���B �@�����ł́A���@�́u���v�A�Ƃ͂����Ȃ邱�Ƃ��B�ܗ֏��́u���v�́A�Ȃ��Ȃ�������{��ɂ͂҂����肭���ꂪ�Ȃ��B�p��́smerit�t�̃j���A���X�ɋ߂��B���_�A�����A���l�A�������X�̌�`���܂ށB�����Ă܂��A���v�k��₭�l�ibenefit�j�Ƃ������Ƃł���B�����iutility�j�A���p�ieffect�j�̈Ӗ�������B �@�����������Ƃ�O���ɒu������ŁA���ꂪ�u���@�̗��v���Ƃ������Ƃɒ��ӂ���K�v������B�܂�A�u���v�̂�����̈Ӗ��́A�����iwin�j�Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A���̎����̏��ɂ����āA�O�ɁA
�s����A���X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A��x�������������Ȃ͂��t
�Ƃ������Ƃ���ł���B�܂�A�s��x�������������Ȃ͂��t�́u���v�ł���B�����ł́u���v�Ƃ́A�ق��Ȃ�ʁA�����̂��Ƃł���B����䂦�A���@�̗��ɔC���āA�Ƃ����̂́A���ӂ��ނ�ŖA���@�ɂ����ď�����ɂ܂����āA�Ƃ����Ӗ������ł���B�@�����͎������A���@�̏����ɂ܂����āA���X�̌|�\�i���|�j�̓��Ƃ��Ă����A�Ƃ����킯�ł���B����́A��l�̓V�˂��A���̂Â���̓������ŏ��������Ă��܂������A�N�O�\���߂��āA���̓����t�ɂ��ǂ蒼�����ƂŁA�悤�₭��\�N��ɁA���@�̓��ɓK���A���g�̏����ɔ[���ł���悤�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ̔��ʂł���B �@�����͏������������̐����̂܂܁A���ʂ̕��|���C�����Ă������B����Ύ���̂Ȃ��Ŋw�тƂ����B���̂��Ƃ��]���Ă���̂ł���B���ɂȂ��Ďv���ƁA�t���Ȃ�Ĉ�l�����Ȃ������B�悤����ɁA�����͎��g�����g�̎t���ɂȂ邵���Ȃ������B����䂦�A�����͖��t�Ɗo�̐l�ł���B�u�����ɂ����ĉ�Ɏt���Ȃ��v�Ƃ����̂͂��̂��Ƃł���B �@���̂��Ƃɕ����̌ǓƂȉe������̂́A�ނ��ߑ�̊����Ƃ̐S�ł���B�����ł͂Ȃ��A�����ɓV�˂Ƃ������̐����itrauma�j�����҂̛���������ςނ��ƂȂ̂��B �@�����̏ꍇ�A���@�̗��������炷���̂Ƃ́A�܂�́A���Ɉ����Ƃ���̓Ɗo�ł���B���炩�ɁA��l�̂́A�啶���̑��҂Ƃ��āu���v�����݂���B����䂦�ɁA����Ɉˋ����閳�t�Ɗo�ł���B �@���̂�����ł́u���@�v�u�����v��啶���̑��҂Ƃ���T�ƂƂ����債�����u�͂Ȃ��B�������A�T�Ƃ͎t�������ł���B��͂��t�Ȃ����ē��͗����Ȃ��B�ł���A�����ł̕����́u���t�v�̃|�W�V�����́A���Ȃ��Ƃ����炩�̑T�Ɣᔻ�����܂ނ̂ł���B �@�����������悤�B�\�\���悻�A�t���Ȃ��҂ɂ͒�q�Ȃ��ł���B�����͌ܗ֏����������Ƃɂ���āA�܂��Ɏ��g�̒ʉ߂��������ɂ܂��������@�Ɗw�ւƗU���̂ł���B�t�Ɍ����A���̌ܗ֏��������Ĉ₷���Ƃ����A�u��Ɏt���Ȃ��v�Ƃ������t�̃|�W�V�����̊��߂Ȃ̂ł���B���m�̌ܗ֏��ǎ҂Ƃ̕s�\�ȊW���܂��Ɏ�������킯�ł���B �@�Ȃ��A���́s���Y���\�̓��ƂȂ��t�̕����ɂ��A���͂��́u���Y���\�̓��v�̕��ł���B�Ƃ����̂��A���̌|�\�@�ɂ����炸�A������u�|���̓��v�Ƃ��āA�����̏���͂��ߑ��|�̃A�[�e�B�X�g�̑��ʂ�z�肵�ĉ��߂���҂�����B�܂�A���@�́u�����v���ɂ߂Ă���A���Ƃ͂ǂ�ȓ��ɂł����p�������A����ł��\�y�ł����p�ł���A������ǂ�Ȍ|�\�ł������ɂ͂��Ȃ��t���͂��Ȃ��A�Ƃ����悤�ȋɂ߂ăk�������߂ł���B�ނ��A����͌��ł���B �@���̌��́A�����ł̌ꂪ�u���v�ł͂Ȃ��A�}�O�n�^���n���{���ʂ��āu���v�ł��邱�Ƃ����Ă���_�ł���B�����̌��ł́u���v�́u���v�ƌ݊��������邪�A�����͂����܂ł��u���v�ł���B�u���@�̗��v�ł͂Ȃ��A�u���@�̗��v�Ȃ̂ł���B���̓_�ł́A��g�Œ��L���͂��߁A�]��������������̌�߂͂قڌ��ł���B �@�������đ��ɁA���̌ܗ֏������@���{�ł���A���ꂪ�����u���@�̗��v�ł���ȏ�́A���|���\�́u�|�\�v�́A���|�̂��Ƃł���B����║�x���y�A���|�Ȃnj|�p��ʂ̂��Ƃł͂Ȃ��B �@�����ł̕����́A�u���@�̏����ɂ܂����āA�������̕��|���K�����Ă����̂ŁA�ǂ�ȕ��|��ڂł������ɂ͎t���͂Ȃ������v�Ƃ������Ƃł���B���|�͉��ł����Ȃ����B�������Ɗw�ƏK�Ŏt���͂��Ȃ��Ƃ��邾���ł���B �@���̓_�ŁA����������͂��ׂė���ł���B��O�̐Γc��́A����Β���̕��ނ����A���@�́u���v�Ƃ���̂��A�u�����v�Ƃ���ւ��Ă���B���̐_�q��́A���Y���\���u���܂��܂ȕ��|�v�Ƃ���̂͐��������A��͂�u���v���u�����v�ƍ��낷��_�A�O��Ɠ��l�ł���B�������A���̂��߁u������v�Ƒ}�ނ��A���̕����ł́A���@�́u���v�����܂��܂ȕ��|�̓��Ƃ��Ă���A�Ƃ������ӂ̂悤�ŁA����͌�������E�������ł���B �@���ő�͓���́A�_�q����������蒸�Ղ��ĐV���̂Ȃ����A���������_�q�u���|�v�Ƃ��Ă���̂����Ă���B�܂����c��́A���@�́u���v�ɂ��āA�O��̂悤�Ɂu�����v�Ƃ͂����A���̖�ɍH�v�������Ă���悤�ɂ݂��邪�A�u���@�̓��œ������́v�ƋL���Ƃ���A�u���v�̈Ӗ������Ⴆ�Ă���B���Ƃ��A���Y���\���u�������̌|���̓��v�Ƃ���̂́A���������n���痎���ė��n�����Ƃ����������B�]�T���Ȃ����ȂȂ��Ŋ��s���Ă��܂������̂̂悤�ł���B �@���łɁA���̂�����A�E�̏��яG�Y�̓ǂ݂��݂�ƁA���߂̃��x���ł͑��̒ǐ�����邳�Ȃ����A�܂��܂��I�O��ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B����������ɏ��ʂ̕��|�K���ɂ����Ė��t�ł������Ƃ����̂��A��́u��p�v�Ƃ̃����N�ŁA�����܂ŏ���Șb��W�J���Ă��܂��킯���B�v����ɁA�u�|�v��u�|�\�v�A���邢�́u��p�v�������̈Ӗ��œǂ�ō��o���Ă��܂������I���ł���ɂ�����A���������Ƃ���A�����ĕ����̎v�z�ɒʒB�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B �@ Go Back |
 ���q�� 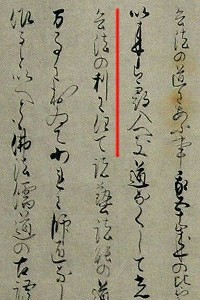 �Έ�Ɩ{�@�u���@�̗��ɔC�āv  �F�{��
*�y������z
�s���@���������p���ď��Y���\�̓�����Ă݂�Ɖ����ł��t���ɂ��Ȃ��ŗ��h�ɏo����t�i�Γc�O�Έ��j �s�����́A���@�������ɂ��������āA��������܂��܂����|�̓��Ƃ��Ă���̂ł��邩��A�����邱�Ƃɂ��Ďt���͂Ȃ��t�i�_�q����j �s���@�������ɂ��������āA�����������|�\�̓��Ƃ��Ă��邩��A�����ɂ킽���Ď����Ɏt���͂Ȃ��t�i��͓�������j �s�����͕��@�����œ��������ɂ��������Ă��������|���̓��Ƃ��Ă���̂ł��邩��A�����邱�Ƃɂ��Ď����ɂ͎t���͂Ȃ��t�i���c�ΗY��j
*�y���яG�Y�z
�s��p�Ƃ����V�O�̝���͖ڂŌ����邪�A�����V�O�̐[���A��X�Ȉَ��̊�p�̒�ɉB�ꂽ萗��́A���Y�ɂ��͂鎖�ɂ�Č��˂Ȃ�ʁB���U�́A�o�҂邾�����Y�ɂ��͂炤�Ɠw�߁A�ނ̌��t��M����Ȃ�u�ݎ��ɉ����āA��Ɏt���Ȃ��v�Ƃ��ә|�܂ōs���B�����k�Ă��ނ��`���A�ނ̂��͂����Y�̈�[��暂��Ă��̂͌��Ӗ����Ȃ����A����͖{�i�̈ꗬ��㉂ł��āA�B�l���P�Z�Ƃ��Ӟ�Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��B�Z�͑f�l�����A�l��������Ă�Ėʔ����Ƃ��Ӟ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ނ́A������㉂̊�p���A�����̙��̊�p�ɋy�ʎ���Q�������A�P�Z�Ƃ��ӕ��l�`�ƓI�ȍl�ւ́A�ނɂ͏������Ȃ����Ǝv�ӁB������A��p�Ƃ��ӂ��̙̂J�l�T�O���A�ނɂ��ẮA�܂�Őq��ƈقĂ���炾�Ǝv�ӂ̂ł��t�i�u���̐l���V�v���a24�N�j |
|
�@ �@�i13�j���ꗬ�̌����A���̐S�������� �@����́A�O�L�́u�����ɂ���āA���Ɏt���Ȃ��v�ƘA������B �@�����̏����������Ƃ͂����A���@��̌Ì���肽�肵�Ȃ����A�R�L�R�@�̌Â���������p���Ȃ��B���̂��̗��V�̌����āA�l���A�^���̐S�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ������A�Ƃ���B�\�\�����͌ܗ֏��L�q�̃|�W�V�������������Ă���Ƃ���Ȃ̂ŁA���ӂ��ēǂ܂ꂽ���B �@�����܂ł��Ȃ��A�R�L�R�@�̌Î���p���Ȃ��A�b��ɂ��Ȃ��Ƃ́A���̌ܗ֏��́A���@���Ƃ��Ă̍��{�I�َ����������B����Ώ펯�I�ȕ��w�A�R�w�̓����ɂ͔[�܂�Ȃ��̂��ܗ֏��ł���B����͑��̕��@����ł�ㆂ��Ă݂�A��R�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B �@�����炭�A���̌R�L�R�@�̌Î��ɂ��ẮA�����ɂ͌��ׂ����Ƃ��R�قǂ��������낤�B�����̕��m�͖��ɂ��A�R�L�R�@�̕]���A����_�c�ɉԂ��炩���Ă����B�������A�����͂����Ă�������Ȃ��ƌ�������B��������Ȃ��̂́u�����āv�ł���B���́u�����āv�̃|�W�V�����������I���ƌ�����B �@������ɁA���܂��Ɉ����Ȃ��Ƃ������҂��Ղ�₽�Ȃ��B�H���A�\�\�����͌��p�Ƃł����āA�R�w�҂ł͂Ȃ��B����ŕ����叫�Ƃ��č�����w���������Ƃ��Ȃ��B����ȕ���������̂��Ƃ��ܗ֏��ɏ����Ă���̂����A�w�`��@�ȂNj�̓I�Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ��A���ۓI�ȋc�_�ɏI�n���Ă���A�]�X�B �@�悤����ɁA�����������Ƃ��V�^����ŏ����҂́A�ܗ֏��ɌR�w�җ��̋��������҂��Ă���悤�����A���̂�̖֖������炵�Ă���̂ɋC�����Ȃ��B����A�ܗ֏��ɉ��������Ă��邩����Ȃ��A�Ǝ����Ő�`���Ă���悤�Ȃ��̂ł���B �@���̓_�A�ʼn߂ł��Ȃ��ϐ����Đ��Y����Ă���̂�����Ȃ̂ŁA�ȉ��Ɏ���ӂ����N���Ă����B �@�ܗ֏��Ɂu�ꕪ�̕��@�v�Ƃ����̂��o�Ă���B����͈ꕪ�k�����Ԃ�l�Ƃ����̂�����A��l�ő���Ɛ키�Ƃ��̂��Ƃł���B���������̐킢�̏ꏊ�͂ǂ����Ƃ����A����͐��Ȃ̂ł���B����̏�ł���B�����͌ܗ֏��ŁA�u�ꕪ�v�̕��@�ɂ��ďq�ׂ�Ƃ��ł��A���ȊO�̏��z�肵�Ă��Ȃ��B �@�ܗ֏��͈�ʌ����̕��@���{������A�u�ꕪ�v�̕��@�Ƃ����Ă��A���@�҂̌���������A�s���̌��܂ł͂Ȃ��̂ł���B�܂��ċ���⓹�ꎎ���ł͂Ȃ��B���m�̓����ǂ���͐��ł���B����̌���𗣂�āu�ꕪ�v�̕��@���Ȃ��B������ɁA����Ȃ��Ƃ������炸�ɁA�ܗ֏�������Ȃ錕�p�w�쏑���ƍ��o���ĉ�������������҂�����B �@�u�ꕪ�v�̕��@�ɑ��A�u�啪�i�����j�v�̕��@�́A�W�c��ł���B�������A����͍���̍Œ��̑��l�����m�̐퓬�ł���B�����������̌ܗ֏��̃��j�[�N�ȂƂ���́A�u�ꕪ�v�̕��@�Ɓu�啪�i�����j�v�̕��@�������ى����ăg�|���W�J���ɘA�ڂ��Ă��邱�Ƃ��B���̊̐t�ȓ����𗝉��ł��Ȃ��҂��A��L�̂悤�Ȃ��Ƃ������̂ł���B �@�������A���Ƃ��ΌR���w�̌ÓT�w���q�x�̂ǂ��ɁA�㐢�̕����R���̂悤�Ȑw�`��@�ȂNj�̓I�ȉ�������邩�B�܂����q���̐l�͂ǂ��ŁA�叫�Ƃ��č�����w�����Ă����Ƃ����̂��B�ނ��A�����łȂ��ɂ�������炸�A�w���q�x�͍������܂��ɐ푈�_�̐����Ȃ̂ł���B��L�̂悤�Ȃ��Ƃ������҂́A����ł��m���Ă���w���q�x�̒��g�����m��Ȃ��̂ł���B �@�叫�Ƃ��č�����w������҂łȂ��Ƃ��A���������̕��m�́A�����邲�ƂɌR�L�R�@�̌Î��ɂ��āA�w�`���ǂ��́A��@���ǂ��̂Ƙ_�]���Ă������̂��B����́A�����̉�X���X�|�[�c�����̌��ʂɂ��āA���ɓ���ׂɓ���]�_��������̂Ɠ��l�ł���B����͂����������k�`�Ƃ������̂ł���B �@�����͂��̎�̍���_�ɂ́A��ւ����A�ł���B�ł́A�ܗ֏��ɂ����鍇��_�̃|�W�V�����͂ǂ��������̂ł��������B�\�\����͂ǂ��݂Ă��A�m���̔w�ォ��єz��U��悤�ȃX�^���X�ł͂Ȃ��B �@���ɂ����镐���̐S���Ƃ��Ă����Ό����Ă����̂́A��������́A�m���ɐ旧���ē����ׂ��ŁA�m���̔w�ォ��єz���ӂ���Ƃ��́A������E���Ƃ͌ĂȂ��B�m���̎҂ǂ��̔w��ɍT���āA�єz��U���Ă���悤�ł́A�����͂Ƃ܂�ʁB��R�̐擪�ɗ����Đ^����ɓG�w�֓ˌ�����̂������Ƃ������̂��B�叫����l�̗E����āA�m���͂悤�₭�������̂Ȃ�A�Ƃ����b������B �@�������ܗ֏��Łu�啪�i�����j�̕��@�v�Ƃ��ċ����Ă���̂́A�m���̔w��ɉB��čєz��U��悤�Ȉ��ՂƂ����b�ł͂Ȃ��B�ނ��뎩�痦�悵�Đ키�A���팻��ł̃��[�_�[�Ƃ��Ă̐S���ł���B�ܗ֏��ɂ����鍇��_�́A�����܂ł����̌���ɑ��������̂ł���B �@�����悤�Ȃ��Ƃ����A�א쒉���i�O�ց@1563�`1646�j���R���̘b�ɂ͂����A�u�������R�@���ւ鎖�Ȃ��v�ƌ����Ă����Ƃ����B�����āA�\�\�R�@�̔��w�̐}�ȂǂƂ����A���A�R�@�҂Ƃ����ē`������̂́A����ٍ͈��̍����ł����āA�{���i���{�j�̐푈�ł͖��ʂȂ��Ƃ��B�����叫�́A�G�̗l�q���l���Ĕ����𗧂āA���̏�̕��ʂ��������ɏd�v�Ȃ̂��B����Ȃǂ́A����̔������{�ɂ��āA����O�i�ƌ��߂āA�G���������͍L�������A�G���߂����͉~�������邾���ŁA���̖���̑Ԑ��œ�����A������̂��B�叫���S�キ���Ă͏����������B�m���Ƃ��ɁA�G�����叫��M�p���Ȃ���A�l���i�R���j���g�����Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƁB �@�悤����ɁA�M���G�g�̎��ォ��A�փ����A���w�܂ŁA���x��������o�������א쒉���ɂ��Ă����ł���B����Ȃǂ́A�n���̈�o���̂悤�Ȑw�`��ŁA������L������ۂ߂��肷�邾�����������A�������ď����c���Ă���B����ɂ�����叫�ɕK�v�Ȃ̂́A�Ջ@���ς̂��̏�̔��f�͂ƁA�����ėE�C���B���ꂪ�m�������B�R�@�̔��w�̐}�ȂǂƂ����āA�������ʂȗ��_���肰�ɔ��荞�ތR�@�җ��́A���̖��ɂ������Ȃ��B����ٍ͈��̂�肩����������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����{�l�̂�邱�Ƃł͂Ȃ��B�א�Ƃ̌����`���ł́A�����͂���Ȃ��Ƃ�������Ƃ����킯�ł���B �@�������J��Ԃ������̂́A���@�́u�q�b�v�u�q�́v�Ƃ������Ƃł���B����́A�u�m���v�̗L���Ƃ͖��W�ł���B����Ύ��H�I�ȗՋ@���ς̑Ή��͂ł��邪�A���ԓI�Ȃ��̏�̏ɑΉ����邾���ł͂Ȃ��A���������ω����̂��̂ݏo�����ƁB����͓����Ɂu�����v�Ȃ���ł��Ȃ��B�܂�́A���������Ӗ��ł́u�q�b�v�u�q�́v�ł���B����������A�����̋����́A�m���Ƃ��Ă̕��w�R�w�ł͂Ȃ��A�����ƍ��{�I�ȁA�퓬�҂̎v�z�Ƃ����ׂ����̂ł���B �@�܂������A���p�����Ȃ炢���m�炸�A�{���A���l���Ő키����Ɂu���Ɓv�ȂǑ��݂��Ȃ��B����́A�����A�����o�ςɐ��Ƃ����݂��Ȃ��̂Ɠ������Ƃł���B������u�]�_�Ɓv�͂��Ă��A���͐��ƂȂǂ��Ȃ��̂ł���B �@�������A�R�L�R�@�̌Â�����Ȃǘb��ɂ��Ȃ��Ƃ����̂́A�m���R���̔w��ɂ��čєz��U��Ă���悤�ȌR�w�җ��̋c�_���������̂ł���B�����܂ł��Ȃ��A�R�w�җ��͗��_�����炵���݂��Ă��邪�A����̋�_�ł���B �@�ނ��땐���̋����́A�u�啪�i�����j�v�̕��@�Ƃ������A�u�啪�i�����j�ꕪ�v�̕��@�Ƃ���Ƃ���ɁA���̓��ِ����������B���A���Ȑ��ɂ����Đ퓬�ҌX�l�������킫�܂��m��ׂ�����������B�����ɂ͕������m�����Ȃ��B�����̋����̂��̏ꏊ�́A�l�Ƃ��Ă̕��m�����ł����ɐ키���A�Ƃ������Ƃł���B���̋�̓I�Ȍiconcrete individual�j�̈ʑ��ɗ��r����Ƃ����X�^���X���ޗ�̂Ȃ����̂ł������B �@������ɁA�����͌��p�͒m���Ă��Ă������m��Ȃ��A��x���叫�Ƃ��č�����w���������Ƃ��Ȃ��A�����畐���͍������鎑�i���Ȃ��A�ȂǂƂ��������ȕ]�_���A���܂��ɔ�������Ă���B����ȂǁA�܂��Ɍ����Ⴂ�̃^�����ɂ����Ȃ��B���m�ƌ����ׂ��B�ї��R�ł����R���_�������Ă���B���R�͕����̒m�F�����A�叫�ǂ��납�A���s�̒��l�o�̎�҂ł������B �@�����A�叫�Ƃ��č�����w�������o��������҂́A�������֗^�������킵���m��Ȃ��B��������܂������c���������ł���B�������A�������Ȃ����Ă����A�������̓I�ɕ��͂��Č�肦���҂͂��Ȃ��B����ȏ���������Ȃ琥��q���������Ƃ��낾���A�ނ��Ȃ��̂͂��̐��ɂ͑��݂��Ȃ��B �@�悤����ɁA���A���Ȑ��ɂ͐��ƂȂǑ��݂��Ȃ��B���͖��x�������V�����A���̌o���Ȃǖ��ɗ����Ȃ��B�ߋ��̌o���ɌŎ�����ΕK�����s����B���ꂪ����̌���ł���B�푈�ɂ��悻���̂Ȃ�����̓��{�Љ�ɐ����鏔�N�ɂ��A���̎����͑������ɂ��炸�A�������������Ƃ��āA�����悻��m������Ƃ���ł��낤�B �@���Ƃ�蕐���͋�݂ȍ����ɂ��炸�A���A���Ȑ��ɂ͐��ƂȂǑ��݂��Ȃ��A���̌o���m�Ȃǒʗp���Ȃ��A���͂˂ɐV�����Ƃ����푈�̖{�����A�\���ɒm��ᶂ��Ă���҂ł���B�����āA���̏�ŁA���ɂ����ČX�l���Œ�������킫�܂��m���Ă����ׂ����A����ɂ������{�I�ȋ������q�ׂĂ���B�ܗ֏��ɏ����Ă��Ȃ����ƂŁA�^���d�v�Ȃ��Ƃ͑��ɉ����Ȃ��̂ł���B �@�Ƃ���ŁA�����ɂ�����A�����Ƃ��Ȃ��L�q������B�����́A���@��̌Ì���ؗp���͂��Ȃ��Ƃ����B �@���������Ȃ�ƁA��������͋ɂ߂ē����Ƃł���B�Ȃ��Ȃ���{��̋��X�ɂ܂ŁA�����̌��t���������Ă������炾�B��������ӂƂ��Đ˂��A�Ì���č\���������w�̔����͂܂���̌㐢�̂��Ƃł���B �@�������A�����������������o�������̂́A�܂��ɕ����̈ꕶ�������Ě���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł���X�́A�����̊_�Ԍ����A�����ł��Ȃ��ł��Ȃ��A�v�z�̉\���E�Ɏv������̂ł���B �@����ɂ��āA���яG�Y�͉E�f�̂悤�Ȍ����������Ă���B�s�B����S���ے肵���āA���h�Ȏv�z���z���o�ҏ��킯�͂Ȃ��B�����A�ނ̐��}�ȓV�˂́A�������s���ė����̂ł���t�Ȃǂ́A��ɂ���ăJ�b�R�悷���鏬�яG�Y�߂ł��邵�A���ɂ����I�O��ȂƂ�������邪�A��{�I�ɓ��ӂ�������e�ł��낤�B�܂��A���̂����肪�A���т̓lj��́A�}�S�̕����_�ƈႤ�Ƃ���ł���B���������Ƃ��Ĉ����Ă݂��킯�ł���B �@����ɂ��Ă��A�����͂�͂�A�u�V�����V���������Ƃ��āv�Ə����̂ł���B�������A����������Ȏ����I���O�ΏۂƂ��Ă݂�ׂ��ł͂Ȃ��B�܂��A�����̌��������́A�V���Ɗω����ۏؐl���Ƃ������Ƃł��Ȃ��B��͂�u���v�Ȃ̂ł���B���g�̓����^�����ǂ����A���̋��̔��ˑ��Ƃ��Ă��Ă̂�����Ƃ������Ƃ��B���̂͂Ȃ��̂ł���B���ꂪ�A
�s��Ƃ��A������ƌ��鏊��t�i��V���j
�Ƃ������Ƃł���B�@�T�Ƃ́A�_�G�ƌd�\�̘�̑Έʖ@���͂��߂Ƃ��āA���Ɛo�̔�g�ő���������Ă����B�Ȃ�A�T�v�z�̕����ł����ǂ߂Ȃ����Ƃ��Ȃ����A����͕����̖{�ӂł͂���܂��B�ނ���A���̋��́u�Ӂv�����Ƃ���A�u�V�ӎ������v�Ƃ����؎x�O�����Ɍ�����e�[�[�ɂ��ʂ��Ă��܂��̂ł���B����������A�u�V�����V���������Ƃ��āv�̈Ӗ��́A�����ʗL�̎v�z���炷��A�v����ɁA�u�����v�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B�Ƃ���A���@�������f����Ӗ������ł��̈�߂͓ǂ܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�A�����]���Ƃ���́A�u�Ŗ@�̌Ì�������炸�v�Ƃ����|�W�V�����ł��낤�B �@�Ȃ�قǁA���́u�V���v�́A�����ŐV�v�z�Ƃ��Ă̎�w�I�ȁu�V�v�̈Ӗ��ł͂Ȃ��A�ނ��떯�Ԃɗ��z�����V���v�z�̂���łł��낤�B�܂�u���e���g�E���܁v�Ƃ�����ɍ��Ȃ��c��Ӗ��́u�V���v�ł���B���������ĎI�Ƃ������������I�ϔO�Ȃ̂ł���B �@�����ЂƂ́u�ϐ����v���܂��A���ԐM�K���̂Ȃ��Ō���ׂ����̂ŁA�������Ă�����ˎR�̊ω��M�ƑΏƂ��Ă݂�ׂ��ł���B�ω��M�͌×������I�ł���A�ߐ��Ƃ��Ɋω����u�[���Ƃ��Đ������}���邱�ƂɂȂ�̂����A�����̌��̃|�W�V�����́A�����I�Ƃ������A�����I���O�I�ł���B �@�悤����ɕ����́A�T�ł����q�w�ł���A��N�̍�����e����ŁA�����ɓO�����f�{�Ƃ��Ă��������A���̔ӔN�Ɏ���A�����ŐV�̎v�z�̌��t�Ō��̂ł͂Ȃ��A�ނ����O�I�Ȗ��ԐM�̕��փV�t�g�����|�W�V�����Ō�낤�Ƃ��Ă���B���ꂪ�A���@��̌Ì���ؗp���邱�Ƃ͂��Ȃ��Ƃ����ނ̌������ł������B �@�Ȃ��A���Ƃ���A�����Ȃ̂��B���̓����͖��炩�ł��낤�B�ܗ֏��͉��`��`�̏��ł͂Ȃ��B�܂��ɖ��l�����̕��@���{�Ȃ̂ł���B���S�҂ɂ��ǂ܂��鋳�{�ł���B���w�҂Ȃ班�N�ł���B���������q���܂œǎ҂ɑz�肵���̂��A���̂悤�ɁA�����ł͂Ȃ��A�킴�Ƙa���ŏ����ꂽ���̕��@���{�Ȃ̂ł���B �@ Go Back |
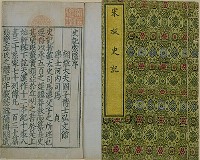 �v�Ŏj�L�i���� 1534�N�j  �d���@�O����  ���o�����@���q
*�y�א쒉���z
�s��������ɌR�̌䕨��ɁA�������R�@���ւ鎖�Ȃ��B�i�����j�R�@�̔��w�̚��ȂǁT�]�A���A�R�@�҂Ɖ]�ęB������́A���n�ٚ��̍����j�āA�{���̝D�j�������B���U�叫�n�A�G���[���l�֔��𗧂āA����̕���ਐ�v�B�䓙�n����̔������{�ɂ��āA����O�i�Ƌɂ߁A�G�������n�A�����ցA�߂��n�������ցA����̊i�j�ē����o�A�������B�叫�S�サ�ăn�������ӕ���B�m�����j�G���叫���v�͂���o�A�l���n���͂�ʕ���A�Ɣ��R�A�V�l��\��t�i��������N���@�L�n�L�j  ���═�o�������� 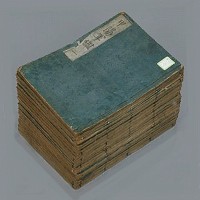 �b�z�R��  ��q��ށ@����@�ї��R��_�Z��
*�y���яG�Y�z
�s���U�́A�����̛��n�S�����瓾���v�z�̐V�����������ɂ��āA���Ȏ��������Ă�ɑ���Ȃ��A�ނ́A������u�Ŗ@�̌Ì�������炸�A�R�L�R�@�̌Â���p�Ђ��v��炤�Ƃ����B����͖��_�A�c���Ƃ��Ăُ͈�Ȏ��������A���A�����Ɍ��ւA�s�\�Ȏ��ł������B�_���Ƃ��u�ܗ֏��v��暖����Ă�܂��B�B����S���ے肵���āA���h�Ȏv�z���z���o�ҏ��킯�͂Ȃ��B�����A�ނ̐��}�ȓV�˂́A�������s���ė����̂ł���B������A�u�ܗ֏��v�́A��҂����Ђ����������A�[���ɉ]�Г������ł��邩�ǂ����^�₾���A���͂��̎v�z�̓��@���̂��̂́A�܂��ƂɓI�m�ȕ\���Ă��B�������ӕ��͂ɂȂĂ���Ɏv�͂��B����ł悢�B���ꂪ���U�Ƃ��Ӑl���ł����A�Ƃ��ӈӖ��ł́A�v�z�̓��@�����ނ̎v�z�ł����A�ƌ��ւ�ł����B����͋ɂ߂��Ցn�I�Ȃ��̂ł��āA���_�A��V�ꗬ�𑊙B�������p�g�ВB�Ƃ͉���萌W���Ȃ����̂ł���܂��t�i�u���̐l���V�v���a��\�l�N�j  ����@���ω����� �������@������ |
|
�@ �@�i14�j�\���\���̖�A�Ђ̈�V�� �@��ɖ`���A�����́A���i��\�N�i1643�j�\����{�̍��A��B���̒n�ɂ����ˎR�ɓo���āA�V��`���A�ω����q���A���O�Ɍ������A�ƋL���Ă����̂ł��� �@�������Z��ł����̂��A�F�{�铌�̐�t�隬�i�����`�j���邢�͋ߍx�̑��i�O�����ϕM�L�j���Ƃ���A�������炱�̊�ˎR�ւ���Ă��āA�S�P�̐����Ȃǂ��āA�V��`���ω����q�����O�Ɍ������A�Ƃ������Ƃł��낤�B �@�������Ȃ���A�\����{�̍��Ƃ������̓��̊�ˎR�́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���q���A�F��̂��߂̓o�R�ł���B�������Čܗ֏��������n�߂��̂́A���ꂩ�琔����A���̉ӏ��ɋL���\���\���ł���B �@�\���\���Ƃ������́A���R���̓��ɂȂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A����͌܌��ܓ��⎵�������Ɠ������\��ߋ��̓��ł���B�����́A�{�����N�e����ɂ������āA�킴�킴�ߋ��̓���I�̂ł���B��������������j�ɂ����ď]�����ӂ���Ă��Ȃ��������Ƃł���B �@�������āA���̋L���ɂ��A�ܗ֏����M�J�n�́A�����܂œ��肵������̂ƂȂ����B�܂�A���i��\�N�i1643�j�\���\����̓Ђ̍��ł���B���M�J�n�����ꂾ�������ɓ���ł���P�[�X�͒������B �@�Ƃ���ŁA���́u�Ђ̈�V�v�Ə��{�ɂ���Ƃ���ł���B���ꂪ�]���̌ܗ֏��ǂ݂ɂ͓ǂ߂Ȃ��������ł���A�Ȃ��Ȃ��̓�ł������B�Ƃ����̂��A����͏C���I�Ɂu��V�v�Ƃ������̂ŁA�����̎��I��@�ɂ��čs�����A�u������ɂ��ꂽ���D�̂��̂���ł������B �@�܂�����ł�������̂́A���́u�Ђ̈�V�v���u�Ђ̈�_�v�Ƃ����������w���Ă���炵�����Ƃł���B�������A���́u��_�v�Ƃ�����́A����̏\��ꉹ�̑��A�����̂��Ƃł�����A�����̎n�܂���Ӗ�����B�܂�A�ܗ֏��̎��M�J�n�ƁA���́u��_�v�Ƃ�����͏C���I�ɏd�Ȃ�B �@�����͂����ŁA���́u��_�v�Ƃ�����̘A�z�Ō���V�Y�����Ă���B�Ƃ����̂��A�u��_�v�Ƃ����ꂪ�������鈢���ɂ́A���Ƃ��Έ����ρA�܂��̑��݂̕s���s�łƂ�����ρA�������瓖���̕��@�ł͂Ƃ��ɁA�����̗����Ƃ������Ƃ������āA�u��_�v�ɂ͂��������A�z�ނƂ��낪����B �@���́u��V�v�́A�܂����̂��Ƃł���A���̏\���\���̖�A�\����k�Ƃ������l�Ƃ����āA���������閯�����������B���邢�͈����ςɂ́A����ɂƂ��Ȃ����֊ςƂ����ϖ@�������āA�����ł��u���v�̘A�z����������B�u�����ь����@���v�Ƃ������������B�����́A���������������̈Ӗ��̑��d����M���āA�u��V�v�Ə������炵���B �@�܂�́A���^���́u��V�v�̂����̈�V�A���ł���B�u��V�v���������������u��V�v�Ə����A���̏����̉��y�Ƃ������̂Ɋ����ł��Ȃ���A�ܗ֏���ǂ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@���āA�����́u�Ђ̈�_�v�ł���B�\�\�����܂ł͓��{�l�̐������Ԃ͕s��s�����A���݂̂悤�Ɉ���������莞�@�ł͂Ȃ��A�G�߂̓��̏o�E���f�̎��Ԃ̈Ⴂ�Ŏ��Ԃ͐L�k�����B����\���Ȃ珉�~�ŁA�邪������������A�����Ђ̍��ł��A�W���̌ߑO�l�A������������ւ����B�u�Ђ̈�_�v���Ƃ���A��_�͈ꍏ�i�ԁj�̎l����́A�ŏ��̈Ӗ��ł���B�܂�A��������Ȃ�A���~�̂��Ƃ䂦�A���Ԃ���ւ���ČߑO�l����肷�����O�A�Ƃ������ƂɂȂ�킯���B �@���̓_�ɂ��A��g�Œ��L�́u�Ђ̈�Ă�@�ߑO�l���O�\���v�ƋL���Ă��邪�A���������Ƃ��Ă��̎��Ԃɓ��肵���̂��s���ł���B �@���́u�Ђ̍��v�Ɋ֘A���Č����A�����͓O�邵�ċN���Ă����悤�ł���B�O�q�̂悤�ɂ��́u�\����v�͂���Ύ��n�Ղ̌����̖�ł���A���̗���œO�邵�ċN���Ă����̂ł��낤�B�u�\����v�̌��̒��ނ���A�N�̍��ł���A�������������l�X�͐Q���ɂ����A�����͐Q���ɂ��̂܂܋N���Ă����B �@�����āA�s�\���\���̖�A�Ђ̈�V�Ɂt�Ƃ���̂́A�閾���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����܂ł��u��v���Ƃ������Ƃɒ��ӂ������B�܂�Â����{�̈���́A�閾���ƂƂ��Ɏn�܂�̂ł����āA���̓Ђ̍��͂܂��u��v�ł���B �@���������ĕ����̎��M�J�n�́A�\���\���̖閾���O�ł͂Ȃ��A�\���\���̖�ł���B����͌��݂̓����ł́A���u�\����v�̌ߑO�l���O�ɂȂ�B�����ɐ���z��ɒu�������Č����A��Z�l�O�N�\�ꌎ��\����̌ߑO�l���O�A���ꂪ���M�J�n�̎��_�ł���B �@���Ȃ݂Ɍ����A�ٖ{�ɂ́A�ۉ��Ɩ{�̂悤�ɂ�����u���v�k�A�V�^�l�ƋL�����̂�����B����͎���̉�₂ł���B�Ђ̍�������ł��ƁA��m�b�ʼn��߂��āA�������Ă��܂����̂ł���B���́u�����v�ŁA�ۉ��Ɩ{�����͏��ʂ��d�˂���̐V�����ʖ{���Ƃ������Ƃ��m���̂ł���B �@�悤����ɁA�����Œ��ӂ��ׂ��|�C���g�́A�u�\���v�̖閾���O���ƌ������ƁA����Ⴄ�A�Ƃ������Ƃ��B�����́u�\���\���̖�v�Ə����Ă���̂ł���B���̓_�A������Ă���ܗ֏�����{������̂ŁA���ӂ��Ă��������B �@���āA�ȏ�̂悤�Ɂu�Ђ̈�V�v���u�Ђ̍��̈�_�v�ƁA�����ĕs�����ɉ������̂����A�ނ��́u��V�v���u��_�v�̌�肾�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�u��_�v���u��V�v�Ƃ��Ď��I�ɕϊ����ĕ\�����Ă���Ƃ������Ƃ��B�Ƃ��ɁA�u�\����v�̌��������A���́u��V�v�ł���B�������A���̋�ɒ���ł��܂����u�\����v�̌��B���̋�k�����l�Ȃ�s�݂̈�V�A�����͂����Ђ̍��ł���B �@�Ђ̈�V�B�\�\���̑��`�I�ŖL���Ȕw�i�̂��镐���̎��I��@�́A����܂œǂݎ��ꂽ���߂����Ȃ��B�ނ���t�ɁA�ǂݑ��Ȃ��҂�������Ƃ����n���ł���B���̒��ɂ́A���ł����`�ʂ�ɂ����ǂ߂Ȃ��d���̋��҂����āA�u��V�v�́u��_�v�̌�肾�Ƃ���̂ł���B �@���̓_�A���{�̂����א�Ɩ{�̂݁A�u�Ђ̈�Ă�v�Ɖ����ŋL���Ă���B������A�u��V�v�Ƃ��������ɕs�R���o�������ʎ҂̏��������ł���B�ۉ��Ɩ{�́u���v�Ǝ����d�V�ŁA���炩�Ɍ�m�b�ɂ����ςł���B���ꂪ���̎ʖ{�ɂ͂Ȃ��A�א�Ɩ{�݂̂ɔ��������\�L�ł���Ƃ��납��A�א�Ɩ{���㔭�I�Ȏʖ{���Ƃ������Ƃ����������̈�[�ł���B �@�����́A����ɂł��ǂ߂�悤�ɁA�����ł͂Ȃ��a��Ōܗ֏������������A�K���������ł������ŏ������킯�ł͂Ȃ��B�}�O�n���܂ޏ��{���ƍ�����Βm��邱�Ƃ����A�����̃I���W�i���́A�u��V�v�Ɗ����ŏ������̂ł���B �@���āA�\���܂ł��Ȃ��A�u�Ђ̍��v�ɂ͏@���I�ɓ��ʂȈӖ�������B�܂�A�����E�����Ȃǐ��ː_��̌����Ђ̍��ɂ��邾���ł͂Ȃ��A�×��ՋV�̊J�n��A�Q�ďC�s���X�̎n�߂͓Ђ̍��Ƃ����K���ł������B���Ȃ��Ƃ��Ђ̍��́A���Ȃ鎞�Ԃł���B�����ŁA�������킴�킴�A�ЂƂ����������L���Ă���̂ł���B �@�܂�A�\���\���Ƃ������ʂȖ�́A�Ђ̍��Ƃ������ʂȎ��Ԃ��L���Ă���Ƃ�����݂�A���ꂪ�����̏@���I�V��ɂ������Ƃ���́A���Ԃ̑I�тł���B����������A�����͐��U�ŏ��̕��@���̎��M�J�n�ɂ�����A���̓��ʂȓ�����I�сA���̐��A�F��̊蕶�Ƃ��āA���̎������������낵���̂ł���B �\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�Ƃ���ŁA���̓`�����L�ۂ݂ɂ���A�ܗ֏����M�̏ꏊ�͗�ޓ��ƂȂ邪�A���̌ܗ֏��̕��������邩����A��ޓ��ŏ����n�߂��Ƃ��A�������Ƃ��L���Ă��Ȃ��B�@�����炭�A���M�̏ꏊ�́A�\�\�v���蕽�}�ȏ�ʂ����\�\�F�{�̋���ł��낤�B���邢�́A�����łȂ���A���N�̔��a���_�̎����m���悤�ɁA�F�{�ߍx�̑��ɂ������ʑ��ł��낤�B�����ȂǂŁA��������ޓ��Ōܗ֏������M���Ă���V�[�������邪�A����͘b��ʔ������邽�߂̃t�B�N�V�����ł���B���̌ܗ֏������ɂ́A��ޓ��ŏ����Əq�ׂĂ��镔���͂ǂ��ɂ��Ȃ��̂ł���B �@���āA���̎��������Ɋւ��āA�ЂƂ����Ă����˂Ȃ�ʂ��Ƃ����肻�����B����́A���̎������{���ƕ��̂��Ⴄ�Ƃ������R�ŁA���̎������������������̂ł͂Ȃ��A�㐢�̉����Ƃ�������A�ꕔ�ɗ��ʂ��Ă��邱�Ƃł���B �@����͉�X�̊ʼn߂����ʕT���̈�ł��邪�A�܂��ɕ��̂����Ȃ���A���͕��͂Ƃ������̂�m��ʎ҂̋Y���ł���B���Ȃ킿�A�����͖{���Ɠ������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������g�̑O��̍���ɋC�Â��Ă��Ȃ��̂ł���B �@���j�I�Ɍ���A�������{���Ɠ������̂ɂȂ����̂́A�����ŋ߂̂��Ƃł���B����܂ł́A�������ł����A�����͖{���ƈႢ�A�����ނˉ��܂����Ȍ��ȕ��̂ŏ��������̂ł���B�Ƃ��ɂ́A�{�����a���Ȃ̂ɏ����͊����A�Ƃ����������B�悤����ɁA�����Ɩ{���̕��̂��قȂ�̂����ʂł����āA�{���ƕ��̂����������Ƃ�������̕����H�Ȃ̂ł���B �@���悻�A�������������I�Ȓm�������Ȃ��_�҂��A���̂̍��ق������Ӗ����肰�Ɏw�E���邪�A�ܗ֏��̂悤�Ȓf�ЏW�ƂȂ�ƁA�{�����ɂ����̂̃u��������Ƃ��������ɂ��ẮA�m��Ȃ��ƂɁA�܂������C�Â��ʂ��̂炵���B �@���̓_�ɂ��A��X�̕��͂��炷�鏊�����q�ׂ�A�ܗ֏��̖{���Ə����ɂ́A�ʐl�̂��̂Ƃ���قǂ̍��{�I�ȕ��̂̑���͂Ȃ��B�������͂�������҂Ȃ�A�قȂ镶�̂ō앶�͉\�ł���B�܂��āA���̃P�[�X�ł́A�̑����ׂ��قǂ̗L�ӂȍ��فisignificant differences�j�͑��݂��Ȃ��B �@�����܂ł��Ȃ��A���̏����̓��e��ǂ߂A���悻�����̖���]�l�ɏ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����͖��炩�ł���B�H���A�s����A�P���[��������ƁA���b�[�B���Č���o�A���̂Â��畺�@�̓��Ɉ����A��\�̔��B������Ș҂́A�q���ׂ����Ȃ����Č��A��������B���@�̗��ɔC�āA���Y���\�̓��ƂȂ��o�A�����ɂ���āA���Ɏt���Ȃ��B�����������Ƃ��ւǂ��A�Ŗ@�̌Ì�������炸�A�R�L�R�@�̂ӂ邫�������p�Ђ��t�]�X�B����Ȃ��Ƃ�������̂́A�����{�l�ȊO�ɂ��낤�͂����Ȃ��B �@���������āA�����ܗ֏��ɂ����āA�{���^�����̕��̂̍��ق�_����͖̂��Ӗ��ȏ��ׂł���B����䂦�A���낤�͂��̂Ȃ����̂̍��ق�_���āA����������������҂�����Ƃ���A����͂��������O��̍��낪����̂�����A�܂������I�O��ł����Ȃ��ƒf���Ă悢�̂ł���B �@����ɕt��������A���̌܊��̏��ɂ��ẮA���̓��e���͂���A�܊����͂��߂��珇�ɏ������낵���Ƃ݂͂��Ȃ��B���e�͐؎��f�Ȃ̂������ŏ�����Ă������Ǝv����B�����͏��������A��肵�āA�ȑO�ɂ͂Ȃ������������̕��@�����쐬���Ă������̂ł���B �@���̊��i��\�N�i1643�j�\��������N����A�����͎��ʁB�������A�������s���̕a�ɓ|���̂́A�������N���o���ʂ����ł���B��������ˎR�ɓo���ċF�肵���̂́A���łɂ��̎��A���̗\��������������ł��낤�B�����͎����̋߂��̂������āA�{�����M�Ɏ�肩�������B �@���������Čܗ֏��Ƃ́A�����Ȍ�̈Ӗ��ŁA�����́u�⏑�v�ł���A�܂��O�q�̂悤�ɁA�܂��������������Ƃ��ăf�U�C�����������Ȃ̂ł���B �@�������A�����͌ܗ֏����u�����v���Ď��̂ł͂Ȃ��B��q�̂悤�ɁA���M�J�n��܂��Ȃ������͕a�ɓ|��A�{���𖢊����̂܂c���Ď��̂ł���B���ꂩ�瑽���̉ӏ��Ŋm�F����悤�ɁA�{���͖����̏��Ƃ݂�ׂ��ł���B����e�Ƃ��Ĉ₳�ꂽ���e���A���̎������V�傪�ҏW���A�����̊��̒ʂ�A�܊��{�ɂ��āA��l�ɂ����`�������̂ł���B �@���̃I���W�i���͑����Ɏ���ꂽ�炵���B���������āA����̉�X�̂��Ƃɂ́A�㐢�`�ʂ��ꂽ�ʖ{�������݂��Ȃ��B���������ꂼ��ɍZ�ق�L����s���S�Ȏʖ{�����Ȃ��B�������������m�̏�ŁA���ꂩ��ܗ֏��̐��E�ɓ����čs�����Ƃɂ���̂ł���B �@ Go Back |
 �F�{�����W�n  ������  ���֊�  �\���}
*�y�g�c�Ɩ{�z  �u�\����v�̌�  ��ޓ�����
*�y��ޓ��Ōܗ֏������������H�z |
�@PageTop�@�@ �@Back�@ �@Next�@
