 |
宮本武蔵 資料篇 関連史料・文献テクストと解題・評注 |
|
Q&A 史実にあらず 出生地論争 美作説に根拠なし 播磨説 1 米田村 播磨説 2 宮本村
| [資 料] | 東 作 誌 解題 | Go back to: 資料篇目次 |
 東作誌  美作国周辺図 西作・東作 |
宮本武蔵の出生地に関して、武蔵自身は『五輪書』に「生国播磨」と書いている。かほどの明確な記述にもかかわらず、武蔵を「生国美作」にしてしまうのが、武蔵産地美作説である。明白に不条理なこの説が発生する根拠を与えた史料は、まさにこの十九世紀の本書、『東作誌』につきると言ってよい。 本書は、武蔵死後百七十年の文献であり、いうまでもなく武蔵関係史料としては成立は遅い。しかも、美作ローカルな一地方資料である。にもかかわらず、まことに法外な地位を与えられてきたのが、本書なのである。それゆえ、ここでの関心は、その肝心の『東作誌』に、何がどこまで書かれているか、それを客観的に検証しておくことである。 ところが、武蔵産地美作説が有名な割には、名のみ聞くばかりで『東作誌』などよく知らないという人が大半であろう。それゆえ、まず書誌学的に簡単な解題をしておきたい。 というのも、美作説を主張する論者でさえ、かんじんのこの『東作誌』について知識がなく、その結果、まともに紹介すらできていない、というのが実状だからである。あるいは『東作誌』の何たるかすら知らずに、孫引き・曾孫引きで論陣を張るのだから、随分なことではないか。 ともかく、そういう現状ゆえに、武蔵産地美作説否定論者である我々播磨武蔵研究会が、『東作誌』の解題をせざるをえないという破目になっている。そんな皮肉な事態も、現在の武蔵研究のありさまの一端を示すものである。 さて、本書は、美作国の「東分」、つまり、現在の岡山県東北隅の部分に相当する作州東部六郡の地誌である。「東作」とは、東部美作の意味である。撰述者は、津山松平家中の正木兵馬輝雄(?〜1823)、彼の廻村調査(フィールドワーク)開始は、文化九年(1812)で、序文に記載あるごとく、いったん書上げたのは文化十二年(1815)のことらしい。ただし、通俗武蔵本などで一般に、この年を『東作誌』成立の年とするが、これには問題がある。 つまり、それで本書が脱稿したのではなく、正木は、文政元年(1818)夏まで廻村を続けていて、追加のフィールドワークをしていた。したがって、本書の完成は、それ以後とみなすべきであろう。しかも、津山侯への本書の提出は、後述のように正木死後のことだから、彼は文政六年(1823)の死の年まで改稿増補を進めていた、とみなすのが妥当であろう。 |
|
いちおう本書成立の経緯を言えば、以下のごとくである。 この地誌が出るまで、美作の地誌には元禄四年(1691)成稿の『作陽誌』があった。ところがこれは作州西六郡のみで、吉野郡を含む作州東部六郡を含んでいなかった。つまり『作陽誌』は、所期の目的からすれば、未完の地誌だったのである。一世紀以上も後の、正木のこの地誌編纂事業はこれを補完しようとする試みであった。 しかし、『作陽誌』の試みは、なぜそんなことになってしまったのか。それには、次のような事情があった。 関ヶ原戦後、慶長七年に小早川家が断絶となって領地は解体、翌年、津山に入部した森忠政(1570〜1634)の当初、津山森領はほぼ美作全域、十八万石の所領であった。忠政以後、森家は代々後嗣に多難で、ついに元禄十年(1697)に改易となるが、話はそれより少し前のことである。 元禄二年、森家家老長尾隼人勝明を中心にして地誌作成の企画がもちあがった。長尾はこの事業の予算人員を確保し、作州西部六郡について江村宗普(春軒)に、東部六郡について川越玄三(玄俊)に担当させた。 かくして東西それぞれ分担してのフィールドワークが開始された。西部担当の江村は順調に仕事を完成させ、上記のように元禄四年に成稿をみた。 ところが、東部担当の川越の仕事の方はなぜか遅々として捗らない。結局挫折した川越は、それまで蓄積した草稿を焼却してしまったともいう。何か複雑な事情があったものと推測される。 編者の長尾は、挫折した川越の仕事を、別人を担当に立てて再開した、ということもなかったようである。そのうち、津山森家は元禄十年、森長成病死、後嗣衆利〔あつとし〕の不都合あって、同年八月除封、つまり森家は取り潰されてしまう。お家断絶である。 これは衆利の乱心が原因だったとされる。この変事で、家老長尾勝明は失職、主人の位牌を抱いて出雲へ去り、松江城主松平家に五百石で仕え、宝永三年(1706)彼地で歿という。 かくして津山領は分割され、新しく転封してきた松平家の知行は十万石に減少した。その後津山領は、享保十一年(1726)に再度減封され、五万石まで縮小した。この結果、作州東部六郡の大半は、天領もしくは他藩所領となった。 ちなみに言えば、正木輝雄がフィールドワークに歩いた文化文政年間、東部六郡三百五十ヶ村のうち、津山藩領はわずか四十五ヶ村にすぎない。吉野郡にいたっては、全域が幕府領であり、但馬生野代官所あるいは丹後久美浜代官所の管轄地となった。 したがって、東部六郡がもはや津山領ではない地域となった以上、未完に畢った『作陽誌』を、新規に現地調査をして完成させようとする正木の仕事は、津山松平家の「公務」ではありえなかった。本書の編纂は、まさに正木の私的な作業として遂行されたのである。この点は、『作陽誌』と本書のスタイルも文体も違うという結果のみならず、記事を書くスタンスの違いともなって現れている。 正木は、文化九年あたりから廻村を始めたようだ。津山松平家の「国元日記」や正木の「勤書」にそれが確認できる。津山侯は、正木の廻村調査に対し、「御内用」として、そのつど津山を離れる許可を与え、また年々調査費を支給していた。 松平家は津山城主となって久しいから、属領は四分の一程だとしても、美作の国主を自認していたふしもある。しかし、対象地が幕府領や他藩所領地である以上、自分領のごとくに振舞うことはできない。津山松平家の御内用だといっても、現地の村役人を直に動かすことはできない。だから、これは正木の個人的な調査だという建前が必要だった。 従来注意を惹いてきたのは、本書の主意并凡例において、正木が「講武のひま/\、潜行のより/\、經廻しことを記したり」と書いて、フィールドワークに歩くのを「潜行」とも称していることだ。ただしこれは、彼が隠密のごとく内意をうけて密かに調査に歩いたということではなく、津山城下から地方(ぢかた)の村々へ下ったという表現である。この「潜行」の意味を取り違えてはいけない。津山侯の内命も資金も得ていたが、表向きは個人的な遊行である。それを「潜行」と称したのである。 ところで、正木は、松平家譜代の家臣ではない。寛政年中に新規に召抱えられた新参である。なぜ、そのような新参者に、こうした廻村調査が許されたのか。そのあたりは疑問が残るところである。 というのも、松平家は、すでに百年以上も美作津山城主としてあり、その家中人士に、土地の地理歴史に詳しい者もあったはずである。にもかかわらず、『作陽誌』の補完という仕事を、正木のような新参者に委ねたというのも、解せないことである。 しかしながら、一つには、この仕事をあえてやろうという好事の士が家中にはいなかったこと。そして第二に、案外、土地に不案内な正木のような者が、ある意味で客観的な調査ができるということもあったかもしれない。 そして第三に、この正木が軍学師役であったことである。軍学師というのは、兵学のみならず、いわば家中の知識人として、主君に進講する役目である。いわば、兵学者として国の地理歴史を知っておくことは、肝心なことである。国情を知らなければ、主君への講義もできない。 その進講の機会に、正木が主君に、この廻村調査について、個人的な仕事として、その内意を取り付けたというのは、ありそうなことである。 |
 東作六郡  津山城下再現CG
文化年間東作六郡所領別村数  東作誌 主意并凡例 当該部分 「講武のひま/\潜行のより/\」 |
 正木輝雄 兵学系図 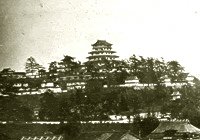 破却以前の津山城 明治五〜六年頃松平国忠撮影 |
では、兵学者・正木兵馬とは何者か。正木の前歴は知れないが、妻子を連れて諸国浪々のあげく、寛政三年(1791)二月、作州津山城主松平越後守康哉〔やすちか〕(1752〜1794)に、擬作四十五俵で召抱えられた。のちに御用は軍学師役である。記憶力抜群で、諸国を渡り歩いた物知り、というあたりが買われたのであろう。 正木はどの兵学流派を学んだのか。この件は、地元美作でも、従来知られていなかったことである。ところが、近年、正木が息子直三郎に伝授した「兵学系図」(文化五年)を発掘したことにより、それが判明するようになった。 同書によれば、正木はまず、天明四年(1784)、英守太為貫から越後流(謙信流)の皆伝をうけた。また、翌天明五年(1785)に、辻花五左衛門適成(三河岡崎本多家儒官)から山鹿流の皆伝をうけたということである。 正木は津山仕官後も、兵学修行に努め、寛政五年(1793)に、上州沼田の山内老鬼通武から、小幡景憲系甲州流の皆伝あり。享和三年(一八〇三)三月に、加賀の脇田伊織直暢から、もうひとつ、山鹿流の重伝があったものらしい。ただし、これらの免許状の類いは残っていない。 正木には妙なエピソードが語られている。正木は仕官当初、松平家臣の諸流の者らと剣術の仕合をしたが、彼は、勝つどころか、だれにも負けてしまった。全敗だというのである。 しかし、これは正確な話ではなく、俗説の類いである。「国元日記」の寛政三年二月十七日条によれば、正木は鎗術と剣術の仕合を御覧に供したとある。勝負は、今枝流の村上彦三郎とは、村上の先勝。同じく今枝流の河瀬登之助とは、河瀬が先勝。進藤流の上田喜内とは、上田の先勝。同じく進藤流の和田茂十郎とは、相打。ただし、四分六で和田の優勢。帰真流の樫野仲四郎とは相打。同じく帰真流の宮地佃とは、宮地の先勝。続いて鎗の心勝流の栗田寛次郎とは、双方入勝で引分、勝負なし。雲平流の上田喜内とは、双方突勝。同じく雲平流の今泉兵弥とは、これも双方入勝である。 正木は軍学講師として仕官したのだから、剣術や鎗術では相手にかなわないはずである。ところが、これみると、おおむね正木は負けが多いが、相打や引分もあり、決して全敗ということではない。だれが言い出したことか、正木全敗説は根拠なき妄説である。 ともあれ、この御覧仕合が済んで、こんどは松之間で、正木が関ヶ原記の講読である。この軍学師役候補は、当日、本来の役も勤めたということである。 また、正木は甲州流師範として軍学師役を勤めていた、という者もある。しかし、津山仕官以前は、正木の免許は越後流と山鹿流のみで、仕官後に、甲州流皆伝と山鹿流重伝をうけている。したがって、正木の兵学は甲州流に限ったことではない。したがって、この点でも、従来の説は訂正されるべきである。 |
|
正木は、文化十二年(1815)正月に、隠居して家督を息子へ譲り、正木勝良(かつら)と名のった。現役の時も隠居後も、まさに、東作各地へ頻繁に出入りして、その地誌を書き続けていたのは、こういう人物だった。本書の宮本武蔵記事にある種のバイアスがかかっているのは、主君師範としての軍学師、兵学者だった正木というこの人物を念頭におくことで、理解しうるのである。 正木は文政六年(1823)に死去したが、生前、この「作陽誌東分」としての本書は、津山侯に提出されなかったようである。「勤書」あるいは「国元日記」の文政八年(1825)三月八日条に、正木の息子・正木兵馬(襲名)が、亡父の調査した「作陽誌東分」を差し出し、銀一枚下されたという記事がある。おそらく、正木死後数年たって、このようにして本書原本は献上されたのである。 つまり、生前、正木はこれを提出しなかった。とすれば、それは何故か。――しかし、この問いには錯覚があるようだ。言い換えれば、本書を公的な文書、「国書」と見誤っているのである。 本書は、漢文ではなく、和文で書かれた。それは、正木が本書序文に記すように、農夫にも読めるようにとの配慮である。要するに、正木はまず本書を、民間で読まれうる文書として編纂したのである。 正木はいう、「あなかしこ、国書と具へむおりもあらば、漢字正文に改め替て」と。もし国書として松平家に所蔵される機会があれば、その時は、国書らしく、漢文に書き改めたいというわけである。言い換えれば、本書は、公的な文書ではなく、あくまでも正木の個人的な著作であり、民間の人士に読ませるものであった。 したがって、正木が書いた段階では、本書はそのような位置づけであった。この点、錯覚があってはならない。 正木の死後、それも数年たって、息子兵馬が父のこの遺作を津山侯へ差出した。これが本書の正本で、津山松平家に収蔵された。その後、この書は死蔵されて、忘れられてしまう。というのも、本書が国書たる公的文書ではなく、正木の個人的著作だったから、その扱いも軽かったのであろう。 ちなみに、正木の死後差し出された本書原本は、現在も行方不明である。我々が確認した範囲では、現在、津山藩にあったという写本があり、また、別の写本もあるが、当地津山にあるのは、東作六郡全体ではなく、その三分の一ほどである。とくに、吉野郡や英田郡は全体が欠本している。とすれば、正木死後、津山侯に提出された「作陽誌東分」は、東作六郡全体とは限らない。その一部だった可能性もなきにしもあらず。 かくして、死蔵されていた本書が「発見」されるのは、正木の死後二十八年経った嘉永四年(1851)のことだった。江戸藩邸で儒官・昌谷〔さかや〕精谿がこれを発見した。しかし欠本散佚あり、この昌谷によって「修復」編集されたのが、「追補作陽誌」。今日我々がいうところの『東作誌』である。昌谷は、正木家はじめ民間にあった写本で、残欠を補ったのであろう。ようするに、昌谷精谿のこの作業によって、はじめて本書の存在が知られるようになったのである。 以上を要するに、本書は、家中新参の軍学師役・正木兵馬によって書かれた地誌である。それも、百数十年前の森家時代に編纂された『作陽誌』が、美作東分を欠くゆえに、それを追補する企画であった。しかるに、本書は、かつての『作陽誌』のような公的な地誌ではなく、あくまでも、編著者正木の個人的な著作である。正木はこれを、農夫にも読ませる意図をもって、漢文ではなく和文で書いた。本書は、そのように民間で読まれるべき著作であった。 正木は、本書を書くために、文化年間、廻村調査を実施した。文化十二年、隠居の年の序文があるから、その段階で一通り仕上がったようだが、その後も、正木は廻村調査を続行しているから、正木は改稿増補を続けていたもようである。したがって、改めていえば、文化十二年段階で本書が完成したとみなすことはできない。 もう一つ、重要なポイントは、正木が生前、本書を提出しなかったことである。本書の差出しは、正木死後数年たって、息子がそれを行ったのである。この点で、昌谷精谿が書いた「追補作陽誌」序文には事実誤認があるとみえる。昌谷は、正木本人が浄写本を献上したものごとく誤解している。しかし、実際は、本書の差出は、正木死後のことである。 正木がその生前、本書を津山侯へ提出しなかったことは、上述の通り、本書は正木の個人的著作であり、民間向けに書かれていたことと相応する。正木の仕事は、津山侯から御内用として調査費も支給されていたが、それは、国書地誌の編纂ということではなかった。そうである以上、正木本人は、これを津山侯へ差出すつもりはなかった。もし提出するとになれば、漢文体に書き改める必要があったのである。 もう一つは、本書が、正木には、まだ完成とは思えなかったかもしれないことである。もし完成していたら、私的な事業とはいえ、調査費の補助までうけていたのだから、当然差出したはずである。おそらく、民間向けに書いたことと、この未完成という両面で、提出の機会がなかったのであろう。 あるいは、息子が差出した父の遺作は、それがどの範囲のものだったか、東作六郡全体だったのか、それとも一部分だったのか、提出原本が行方不明で未見だから、それが知れない。全体を三十一巻にして整備して、「追補作陽誌」としたのは、嘉永年間の昌谷精谿の仕事なのである。それやこれや、本書については、まだ解明すべき諸点が残っている。 また、いうまでなく、文政八年の段階では、本書の呼称は「作陽誌東分」であり、もちろん「東作誌」というタイトルは、まだなかった。正木本人が本書を「東作誌」と呼んだのではない。嘉永四年の昌谷編修の段階でも、「追補作陽誌」という名であった。「東作誌」とは、後世の名づけである。この点も、誤認があってはならない。 さて、その後、写本で本書は伝えられたが、刊本としては明治十七年(1984)に、まず長尾勝明編とした『校正作陽誌』上中下三巻本が刊行され、明治末には作陽古書刊行会が矢吹金一郎正巳に校訂を依嘱して、大正元年に『校訂作陽誌』刊行、ついで大正二年(1913)『東作誌』も出版されたのである。 ここで興味深いのは、『東作誌』の校訂と刊行に深く関わった矢吹金一郎が、明治四十二年(1909)に、従前の自説をまとめて、「宮本武蔵伝」なる小冊子を発行していることである。言い換えれば、『東作誌』の校訂者と、宮本武蔵産地美作説の主唱者とは、まさに同一人物なのである。矢吹金一郎の曰く、
《宮本武蔵ハ美作國英田郡讃甘村大字宮本ノ人(舊吉野郡宮本村)父太郎左衛門同郡名族平尾氏ヨリ出テ同郡竹山城主新免伊賀守宗貫ニ屬シ城下ニ居リ平田無二ト稱ス》(宮本武蔵傳)
さても、このような場面に遭遇するとき、宮本武蔵遺蹟顕彰会本『宮本武蔵』の刊行もまた、明治四十二年四月であることからして、まさに、『東作誌』の刊行と宮本武蔵産地美作説とは、相互に深く関係し合っていたことに、改めて想到するのである。顕彰会本『宮本武蔵』の説は、矢吹金一郎の所説に全面的に依拠するものであった。かくして、明治末、『東作誌』と顕彰会本『宮本武蔵』の両者は互いに相乗効果をもたらし、「美作の宮本武蔵」をめぐって、何ごとか気運が盛り上がってしまったのである。ともあれ、この明治末の気運を通過点にして、正木の東作地誌編述の試みは、現在に到るまで武蔵美作出生説の揺籃として、二世紀の長きにわたって機能し続けたのである。それだけではなく、吉川英治の小説『宮本武蔵』大成功の結果、妄説生産が跡を絶たないというありさまなのである。 したがって、いまや、要するに本書に何が書かれているか、何が書かれていないか、それを検分する時期にきている。当地を調査して、正木は、何をどう書いたのか、それを知っておくべきである。 ここでは、『東作誌』のうち吉野郡の、「宮本村之記」「下庄村之記」中の関係箇所原文と、その現代語訳を掲載し、そして評註を付して、参考資料として供するものである。 |
 勤書 正木兵馬 当該部分
*【勤書】
《同(文政)八乙酉三月八日。父勝良江、作陽誌東分仕立被仰付候處、同人存命中、取調置候旨ニ而、先達而差出候付、銀壱枚被下之候》  追補作陽誌序(部分)昌谷精谿撰 嘉永四年(1851)
*【追補作陽誌序】
《先輩正木翁、獨自發憤、以補此為己任。単身獨行、奔走四方、従事於茲。若干年終、以作為斯編。浄寫一本、以獻之於公府。留稿本於家、以為副本》  東作誌写本の題名  矢吹金一郎「宮本武蔵傳」 明治四十二年四月 |
