 |
�{�{�����@������ �֘A�j���E�����e�N�X�g�Ɖ��E�]�� |
|
�@Q&A�@ �@�j���ɂ��炸�@ �@�o���n�_���@ �@������ɍ����Ȃ��@ �@�d���� 1 �ēc���@ �@�d���� 2 �{�{���@
| �m�� ���n | ����V�l�u�b �w�{�{�����x | Go back to: �@�����іڎ��@ |
 ���s������� |
 �����a�@����32�N���� ���s�s�����搹��@�~�ڔ��� |
|
�@���s����̕����_�{�̐��ׁA�a���ɋ߂���p�ɁA���Ђ��Â�Ƃ��`�e�̂��Ȃ��ӏ��̘a�����z������B�ߑ�̏��Y�Ȃ��疾���̈�ՂƂ��ďd���w����Ă��錚���ł���B����́u�����a�v�Ƃ������A����{������̉�����{�݂Ƃ��āA�����O�\��N�i1899�j�ɏv�H�������̂ł���B �@������������{������́A�����푈�̏����ɐ��������̋C�^�̒��A������\���N�i1895�j�ɔ����������Ԓc�̂ŁA���{�ɓ`���I�ȕ������ċ����A���p����ɂ���Đ��N�̐��_��b�B����Ƃ���A���s�ɋN�����^���ł���B����قlj��Đ��q�ɌX���������̐��_�́A�����푈�������_�@�Ƃ��ăi�V���i���Y���֎u���]����̂����A�܂��ɂ��̒���isymptom�j�̈�����s�̑���{������̔����ł������B �@����{������́A���N�l�ɂ͋��s�{�m���ȉ��A���s�̖��m������A�˂Ă��邪�A���̖��̒ʂ�S���g�D���߂����A���قɏ����{���m�e����Ղ����B�傽�鎖�ƂƂ��ĉ�����i�����a�j�̌��݁A�����ՂƉ������̊J�ÁA���|�u�K�A������W�A���|�j�o�ŁA�@�֎��i�������j���s�Ȃǂ��f���A�L���S���ɉ������A���̉^�c��p�͉��ƗL�u�̊�t�ł܂��Ȃ����̂Ƃ����B�悤����ɖ��Ԃ���u�����������ċ��^���ł���B |
 ��@����  ��T�����I�@ ���s�s�������T�����n��  ���������@��1�� ����43�N1�� |
�@���̑���{������̔��N�l�ɖ���A�ˁA�c�̔�����͖����i��c���j�Ƃ��Đ[���֗^�����҂̈�l�ɁA�퐳�ʁi1844�`1918�j������B�ނ͎O�͂̕ɊC�S�������̐���A�����ˎm�ł������B�����̃e�����Y���̎���ɂ͔��n�̉��������邱�Ƃ��������炵���B�p�˒u���ɂ������˂̐����ɂ������Ď������Ƃ��ē������B���̌�A�O�\�̂Ƃ��i�@�ȂɔC�����āA�Ȍ㔻���E�����Ƃ��Ċe�n�ɓ]���@���E�Ő������l�ł���B����{������̔������ɂ́A���s�n���ٔ����������ł������B�̂����ٔ��������ƂȂ�A�����O�\�O�N�̑ފ����ɂ́i�`�����j��R�@�����̌����ɂȂ��Ă���B �@��͑ފ�����Ɗ��ɂ��o�āA��T�����I�@�i���E���s�s�������T�����n���j�Ɉڂ�Z�݁A����{������{���̊����ɘV��������邱�ƂɂȂ�B���p�����{�����̊ē��Ƃ߂邩�����A�u����m�v�Ƃ������m���J���ču�`������悤�ɂȂ�B���m�́w���m���x�̒��ҁE�V�n�ˈ�́A�ꍂ�Z���ɂȂ�O�A���s��勳���̎���������A���̂������{������̏�c���ɏA�C���Ă���B���������A�����c���Ŋ����ɑ���{������̊��������Ă����B �@�퐳�ʂ͘a���̑��w�w��������A�����ƂƂ��������[�։Ƃƈ����ׂ��A���̊����͍u�`�⎷�M�ɂ������B����{������͖����O�\��N�ȗ��A�@�֎��w�������x�����s���Ă����B��������Ɂu���|�u�b�v�i�̂����肵�āu���p�n���u�b�v�j��A�ڂ����B�w�������x�͂�������p������A�����l�\�O�N����V�����w������x�Ɩ������߂čďo�������B��͂��̋@�֎��̕ҏW�ēɂȂ�A�]�c���ɂ͓����Վ��Y�i�Γ�j�炪����A�˂�w�e�ł���B �@���āA���́w������x�̑�ꍆ������\���܂ŁA��\��ɂ킽���āu�u�b�E�{�{�����v���A�ڂ��ꂽ�B�M�҂́u����V�l�v�A�܂萅��m�̎�A�퐳�ʂł���B �@���̘A�ڍu�b�������ō̂�グ��̂́A���������j�ɂ����Ė������ׂ��炴����W��L���邪�䂦�ł���B���Ȃ킿�A
�i1�j�@�u�]�������`���v�Ƃ����`�Ԃ����A���̏Љ�ɂ��A�f�Џ��Ȃ���A���ݍs���s���̕����̋L�����e�𐄑������邱�ƁB
�@�����܂Ő��Y���ꂽ�����_�܂��͕��������́A���̐���V�l�u�b�Ɉˋ�������̂����Ȃ��Ȃ��B�������A����炪�I�A�O���I�Y���Ȃ̂ŁA���҂��ӎ��������ɐ���V�l�u�b�̏��������肵�Ă���P�[�X�������B���������āA����珔���̕������邱�̍u�b�ɂ܂ők�s���A���̏�������͂��A�����Ɋ܂܂���T���w�E���A���̎j���Ƃ��Ă̕]���m�ɂ��Ă����K�v������B�i2�j�@�O�N�o�����Đ��Ԃ̕����ςɑ傫�ȉe����^����悤�ɂȂ����A�{�{�����������Łw�{�{�����x�i�����l�\��N�j�ɑ���ِ���������ƁB �i3�j�@�����Ƒ���̍u�b�ł���A����̘b�ȂNjZ�p������܂ދ�̓I�Ȏ��_�����邱�ƁA���邢�͎d���ɍ��܂��������Ƃ����C���[�W���͂��߂Ē�N�������ƁB �i4�j�@�����Œ��ꂽ�ϓ_�́A�吳�E���a��ʂ��āA�Ȍ�̕����_���邢�͕��������ɑ���ȉe����^�������ƁB �@�����ł͖{�A�ڍu�b���畐���֘A�`�L�����𒊏o���^���A�����ɕ]���������Ď����Ƃ�����̂ł���B�����͖������̕����ŁA��ɂ���ċ�Ǔ_�����͂قƂ�ǂȂ����A�e�N�X�g�́A�ǎ҂̂��߂ɓK�X��Ǔ_��}�����Ă���B��������f�肵�Ă����B |
|
�@
�u�b �{�{���U�i��j �@�]�̕��p�n���u�b�́A�v���������ɘA�ڂ���ꂽ���A�q�~�\���ȂĖ����@�~�̏��B��L������A��È�ƌe�݂Ɖ]�ә|�����A�������̔p���Ɉ�㔂��Ė{����������ᢍs���邱�ƁT�ȂẮA�ӔC��܂����x�����Ă������ʂ̂�(1)�A�\�ĕ��p�����{�����ōu�������{�{���U�̏��B���Ǝv�����A�n���l�ւ�ƁA���U�̎��Ղ͑��̕��p�Ƃ��͔�r�I�\�����əB�͂ċ���B�A����V�L�̔@���͍Ŗ��m�ł���(2)�B�R��ɒr粋`�یN�́A�F�{�ɍ݂�{�{���U����������̏������āA�{�{���U�Ƒ肷��ꏑ��ҏS�����A�q�N����ᢍs�ƂȂ��B�������{椂���ɁA��V�L�Ɠ�V�L�ٖ̈{�Ƃ��l�I�k���������l���ĕv���o�k���Ă��Ɓl�Ƃ��A�������̏N�W�ɌW��ޗ��Ɠ��N�̉{������ꂽ�����Ƃ��܁k�悱���Ɓl�Ƃ��ĕҏS����ꂽ�҂Ǝv�͂�A���X�����ɍs�͂āA���U�̙B�ɉ��Ėw�Lj⊶�Ȃ��ƌ��Ă悢�B���������ޗ��̑唼�͋�B�n���ɏo���҂ŁA���U������̈��ڂ����{���Ƌy���Ƃ̉Ɛb�ŕ��U�̋������҂̙B���t�́A�P��̘^�����ċ���ʂ₤�Ɍ��]��B笂ğ�C�̈�삪�Ȃ��ɂ������(3)�B�]�͍��c�ƁE���}���ƁE�{���ƁE�L�n�Ɠ��A���U��萌W���鏔�Ƃ̙B���╷�������Č������Ǝv�ӂ��A�M�����Z��ਂߑ�硂��Ȃ��B���ȑO����U�����Ēu���҂�A�B�����m�o�ƐM���ċ���҂��A������(4)�B���ĕ��U�̙B�S�����u�b����d��������A���U�B�i�r粌N�ҏS�ȉ������j�ɏA�āA��]���ׂ��y����҂͔�]����A�ٙB����҂͍l�قƂ���A�S���̝������Ȃ����҂͏E��Ƃ��āA���b���邱�Ƃɒv���܂����B���͗]�������Ɍւ�桂ł͂Ȃ��B���U�̔@���́A���ҏC�s������ਂߑ��Ֆw�ǘZ�\�P�B�ɕՂ��Ɖ]�Ӓ��ł����̂�����A�]���u�b��L�鍠�ɂ͖��X�B��ċ��鎖�Ղ������������Ę҂�ł��炤�Ǝv�͂��(5)�B |
|
�@�@�y�]�@���z �@�i1�j�������̔p���Ɉ�㔂��Ė{����������ᢍs �@��q�̂悤�ɁA����{������̌����@�֎��w�������x�i�����O�\��N�Z���n���j������A�퐳�ʂ͂���Ɂu���|�u�b�v�i�̂����肵�āu���p�n���u�b�v�j��A�ڂ����B�w�������x�͖����l�\��N�\�ł�������p������A�����l�\�O�N�i1910�j�ꌎ����V�����w������x�Ɩ������߂čďo�������B��͂��̋@�֎��̕ҏW�ēɂȂ�A�܂�����V�l�̕M���ŁA�u�b�u�{�{�����v��A�ڂ���̂ł���B�����͘A�ڂɂ�����A���̂�����̂��Ƃ�O���Ƃ��Č���Ă���킯�ł���B �@ Go Back �@ �@�i2�j���p�����{���� �@���p�����{�����́A����{������̋���@�ւł���B���̊J�݂͖����O�\���N�i1905�j�\���ŁA���p�̏p�Ȃƈ�ʋ��{�Ƃ��č���E�����E�n���E���j�E���w�E�p��Ȃǂ̊w�Ȃ������A�C�Ɗ��Ԃ͈�N�Ȃ����O�N�ł���B�����������l�\�l�N�i1911�j�㌎�ɂ͔p�~���ꂽ�B�C�Ɛ��̊�Ԃ���݂�ƁA���̌�̌����E�̎w���҂����̖�������A����Ȃ�̖������ʂ����Ă���B�������܂��A�v���قNJw���͏W�܂炸�A�ړI�ɓK��Ȃ������̂�������Ȃ��B �@�퐳�ʂ́A���p�����{�����Ŏw���ɓ��������B�{�����ē̔ނ��S�������̂́A�w�Ȃ̕��ŁA���p�j���������B���̒��ɂ͕����Ɋւ���u�`���������悤���B �@�Ƃ���ŁA���̗L�������̎��ւ͂قƂ�ǂ�䩔��Ƃ��āA���m�ȓ`�L����Ȃ��B����ɑ��āA�J�ԉp�Y�ɂȂ��Ă��܂��������̓`�L�ƂȂ�ƁA���Ȃ�ڂ������̂����łɒm���Ă���B���Ƃ��A���́w��V�L�x�i���i�ܔN�E1776�j�Ȃǂ�����ł���B �@�������A�{�u�b�̑O�N�A�����l�\��N�ɂ́A�܂������V���������`�L���o�ꂵ�Ă����̂ł���B �@ Go Back �@ �@�i3�j�r粋`�یN�͋{�{���U����������̏������� �@���F�{�̋{�{�����������́A�����O�\��N�i1906�j�����L�u�ɂ���Č�������A���N�ɂ͕����̈�n��i�̓W������J�ÁA����ɖ����l�\�l�N�i1911�j�ɂ͌F�{�ߍx���c���|��̕����˂�����Ȃnj����������s�Ȃ����B�Ȃ��ł������l�\��N�i1909�j�A�{�{�����������ҁw�{�{�����x�����s�������Ƃ͍ő�̈Ӌ`���鎖�Ƃł������B�{���́A�w���쎏�x�i���邢�͂ނ���A������̏����j�Ɉˋ����A���������Y�Ƃ���V���ł��邪�A�����҂̎v�f�����傫�ȉe���𐢊Ԃɗ^�����̂ł���B �@�r�Ӌ`�ہk�悵�����l�i1861�`1923�j�͂��̒��҂ŁA�������s��勳���ł������B�������s�ɖ{����u��������̊��������Ă����퐳�ʂ́A�r�Ӌ`�ۂ��悭�m���Ă����ł��낤�B �@���炩�ɓ퐳�ʂ̂��̍u�b�́A�O�N���s���ꂽ������{�w�{�{�����x�ɑR���ĘA�ڊJ�n���ꂽ�B��̃X�^���X�́A�r�ӂ̕����`�L�̌��т͔F�߂���̂́A��C�̈�삪�Ȃ��ɂ�����ʂƁA���ᔻ�I�ł���B�悤����ɁA������{�w�{�{�����x�̍ޗ��̑唼�́A��B�n���ɏo�����̂Ł\�\�Ƃ������A������I�Ȃ��̂Ł\�\�A�������d���Őe�߂����{���Ƃ�A���ƉƐb�ŕ����̋��������҂̓`���Ȃǂ́A�̘^����Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����A�Ƃ����킯�ł���B �@�ʂ́u�����v���A�퐳�ʂ̓C���[�W���Ă���̂ł���B �@ Go Back �@ �@�i4�j���U��萌W���鏔�Ƃ̙B���╷�� �@�ʂ́u�����v���A�퐳�ʂ̓C���[�W���Ă���B�ł́A���������퐳�ʂ̒m�����͈̔͂ɓ����Ă����`���Ƃ͂����Ȃ���̂��B �@��́A���c�ƁE���}���ƁE�{���ƁE�L�n�Ɠ��A�����ɊW���鏔�Ƃ̓`���╷�������Ă݂����Ǝv���A�Ƃ�������A����珔�Ƃɕ����W���������邱�Ƃ͔c�����Ă���炵���B �@���c�ƂƂ͋�B�}�O�ő�喼�ɂȂ������c�ƂŁA����͎n�c�E�@���͂��ߏd�b�Ɛb�炪�����d�B�o�g�Ƃ������Ƃ������āA���������̕��m�c�ł���B���}���Ƃ́A�����i���^�j�����Ύ���ȗ��A�����ƊW������A�Ƃ��ɉƐb�E�c���原�i�{�{�ɐD�j�������̗{�q�ɂȂ����Ƃ����[����������B�{���Ƃ̕��́A�d�B�P�H�Ɨ���ɏ��Ƃ��ē����������납��A�����Ɖ�������A�܂������̗{�q�E�O�ؔV�����{�������̒��q�E�����Ɏd���A�������S�ɍۂ��}�������A�Ƃ�����������B�L�n�̕��́A�������̐܂̕������Ȃ��������Ă���A�L�n�����ƌ�F�̂��������Ƃ��m��邪�A���̑��Ɏ��������������̂��B���Â�ɂ��Ă��킪���Ă���̂́A����珔�Ƃɕ����W����������Ɣc�����Ă�������ł���A�܂����̈ꕔ�����Ă�������ł���B �@�V���ɓ��肵�����̂ł͂Ȃ����A�ȑO����U�����Ă��������́A�`�����m���Ɣނ��M���Ă�����̂��A�����炩����A�Ƃ����B����ɂ���āA�퐳�ʂ͌�����{�Ƃ͈Ⴄ�\�[�X�������Ă���Ɖ]�����̂ł���B�������Ȃ���A�ނ��{�������������̊̐t�Ȃ��͖̂��炩�ł͂Ȃ��B���̓_�͒ǂ��ċL���ł��낤�B �@ Go Back �@ �@�i5�j��]���ׂ��y����҂͔�]���� �@�u�����`�v�Ƃ�������������̂ł͂Ȃ��B���̍u�b�̒��Łu�����`�v�Ƃ���̂́A�{�{�����������ҁw�{�{�����x�����̕����`�L�̂��Ƃł���B �@�u�{�{�����v�Ƃ����^�C�g����L���鏑���͑����B����Ō�N�A�����́u������{�v�Ɨ��̂���悤�ɂȂ邪�A����V�l�u�b�͓������s�̗��N�̂��Ƃ䂦�A�܂�����ȗ��̂͂Ȃ��A������u�����`�v�Ƃ����̂ł���B��X�͊���ɂ��u������{�v�Ƃ��Ĉ����B �@�퐳�ʂ̂��̍u�b�́A�O�N���s���ꂽ������{�w�{�{�����x�ɑR���ĘA�ڊJ�n���ꂽ�̂ł���B�퐳�ʂ́A�����ɂ��āu��]���ׂ��y����҂͔�]����A�ٙB����҂͍l�قƂ���A�S���̝������Ȃ����҂͏E��Ƃ��Ă��b���邱�Ƃɒv���܂����v�ƌ��B�r�Ӌ`�ۂ炪�m��ʎ������m���Ă���Ƃ̎�������A���������b�ɂȂ�B �@�����������́A�����֘A���������������\�����傢�ɂ������B����ŁA�u�]���u�b��L�鍠�ɂ͖��X�B��ċ��鎖�Ղ������������Ę҂�ł��炤�Ǝv�͂��v�Ƃ����A���m�̎������@�Ɋ��҂��������̂ł���B �@ Go Back |
 ����V�l�u�b�@�{�{���� �A�ڑ�1��`�� ����������1���@����43�N1��  ������{�w�{�{���U�x ���`���@����42�N |
|
�@
�u�b �{�{���U�i��j �@���U�B(1)�ɂ́A���U�̑c�����c���Ă��A���욠�p�c�S�i�p�g��S�j�|�R���V�Ɓk�ɂ��݁l�ɉ��@�тɎd�ցA��䵑��ɏZ�����V�Ǝ����o�ւ�ꂽ�̂ŁA���q���m���V�Ƃ𖼘����A�V�ƉƂ͕��c�̕����ɛ������҂ł���A���m�̖����V�͌�ɓ��S�]�Ñ��厚�{�{�ɏZ�����U�����n�ɐ��ꂽ�҂Ƃ��Ă���(2)�B���l暂͕��c���̌n�����Ɉ˂�Ȗ��ɏo�҂ċ��āA�^��e����P�n�͂Ȃ��₤�ł��邪�A�������V�y���U�����c�ƂƂ�萌W�������邱�ƁA�c�ȑa�Ȃ�̊�������(3)�B �@�]�������B���ɂ�(4)�A�����V�͑��㌹���ԏ��������c���v���̎q��(5)�A���ߋ{�{����V�����i����V�Ǝ���㋂Ŗ����V���i����(6)�A�Z���͔d�����K���S�{�{����(7)�O�̏��ʏ����O�Y�����ɛ����ċ�����(8)�A�\��̖��l�œ����n�߂�(9)�A�ʏ��ƖŖS�̌�ʏ��̘Q�l�͑������c�ƂɎd�ւ��A�����V�̐e���c���Z�V�i�A�V�ƈɉ��A�R��Ε��q���F���c�ƂɎd�ւ�(10)�A�����V�͍��c�����q�F���̒핺�ɏ������̏��]�Ɉ˂莖����Ƃ��͗������o�͂��鎖�ɂȂ��A����薳���V�͍��c�Ƃɏo������(11)�A���d�b�̏M�g�Y���Ƃ͍ō��ӂł�������A��������E�v��l�Y���q�W�A���ɂ̐l�������V�̋������������Ă���(12)�B |
|
�@�@�y�]�@���z �@�i1�j���U�B �@��q�̂悤�ɁA�u�����`�v�Ƃ�������������̂ł͂Ȃ��B���́u�����`�v�Ƃ����̂́A������{�w�{�{�����x�̕����`�L���w���B�@ Go Back �@ �@�i2�j���U�̑c�����c���Ă��c �@���̕����́A������{�̏����̗v��ł���B�����̑c���E���c���Ă����썑�g��S�̒|�R���V�ƈɉ��@�тɎd���āA���S�������ɏZ���A�V�Ǝ���^����ꂽ�̂ŁA���c���Ă̎q�E���m���V�Ƃ𖼂̂������ƁB�V�ƉƂ͕��c�i�F�쑽�j�̟����ɑ��������ƁB���c���m�́i�V�Ɓj����ւł���A��ɓ��S�]�Ñ��{�{�ɏZ���A���������̒n�ɐ��ꂽ�҂Ƃ���]�X�B �@���Ƃ��A�{�T�C�g�m�����сn�̏��_�����Q�Ƃ��Ă��炦�A�������邱�Ƃ����A������{�̕����`�L�͌�T�Ɖ����̏��Y�ł���B �@���̒Z���v�ł����A����I�����r���݂���B���Ƃ��A���c���Ă��|�R���V�ƈɉ��@�тɎd�����Ƃ������A���c���Ă͐V�Ə@�т����܂��O�Ɏ������Ă��邩��A�V�Ə@�т͏��Ă̖S��ȊO�ɏ��������悤���Ȃ��B����ɑ��A���c���Ă͂��̎q�E���c���m�����܂���\�N�ȏ���O�ɟf���Ă���B����ȍ�����������������L���镽�c�ƌn�}�Ɉˋ������̂��A�����Y�n������ł���B �@��X���m�F������̂́A�\�㐢�I���߁A���؋P�Y���g��S����������Ė��ԓ`�������W�����Ƃ��A���������c���m�Ƃ����l���̎q�Ƃ��Ă��̒n�ɐ��܂ꂽ�Ƃ����u�`���v���������A�Ƃ��������ɂ����Ȃ��B�@ Go Back �@ �@�i3�j�����V�y���U�����c�ƂƂ�萌W �@�u�b�̎�E����V�l�́A�����ƌ�����{�w�{�{�����x�̓`�L��ᔻ���Ă���B����͓����̒��҂��A�ނ̒m�l�ł���A���������s��勳���̒r�Ӌ`�ۂł��������Ƃ�����B�����̒�勳���̌��Ђ����A���Ă��܂��قǑ���Ȃ��̂ł������B �@����Ƃ�����A�������ߑ�I�ȕ]�`�̎��ؓI�̍ق��Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B�{�{�����͂��łɍu�k���ڗ��Ƃ�������O�|�\�̂Ȃ��ŗL���������B���������ʑ��������́u�U�𐳂����������͂��ށv�Ƃ��āA���̎������m�����A���\�̕����ł͂Ȃ��j���̕��������悤�Ƃ���A���������g�U�肪�V�������̂������B���̓_�����F�߂��邦�Ȃ��B �@�������ނ́A�r�Ӌ`�ۂ���������������W���������Ă��Ȃ��B���{�́w�{�{�����x��ǂ����ł���B���������āA���̕����Y�n�������ᔻ����ޗ��������Ȃ��B�܂�����n���j�̒m�����Ȃ�����A�u���䕶Ꝃ̍��A���c���ĂƂ��ӂ��̂���v�Ƃ����L���ƁA���c���Ă��V�Ə@�тɎd�����Ƃ����L���́A�I�悵���������ْf���錈��I�Ȏ�i�������Ȃ��B �@�������������̂ŁA�퐳�ʂ́A�u����ւƕ��������c�ƂƊW���������v�Ƃ����������a���ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ����A�Ƃ����]���Ȃ��̂ł���B �@������_���ӂ��Ă悢�̂́A�킪�A��ɂ͖{���Ɗ֘A�����Ɍ��y���A�����ł͍��c�Ɗ֘A�����Ɍ��y���Ă��邱�Ƃł���B�ǂ����A�ނ��c�����Ă���̂́A�{���Ƃƍ��c�Ƃ̎��ӎ����̂悤�ł���B�@ Go Back �@ �i4�j�]�������B���ɂ� �@�����Łu�]�������B���v���o�Ă����B�҂��Ă܂����A�Ƃ����Ƃ���ł���B�Ƃ����̂��A�퐳�ʂ����������Ƃ����`���́A���Ȃ��Ƃ��������ɂ͌������Ă����炵�����A���ݕs���Ŋm�F�ł��Ȃ����������f�Ђł���A����䂦��X�͂����퐳�ʂ���̓`���Ƃ��Ă̂݁A�݂炵�߂邱�Ƃ��ł��邩��ł���B �@�����ł��́u�]�������B���v�ɑ����X�̃X�^���X�́A���̓�_�Ɋւ��B���Ȃ킿�A�i1�j���ꂪ��������Ă��邩�A���̋L�����e�̊m��A�i2�j���̋L�����e�̎j���Ƃ��Ă̕]���A�ł���B���̓�̍�Ƃ�ʂ��āA�퐳�ʂ��ˋ������u�]�������B���v���A���������ɂ����Ĉʒu�Â����邱�Ƃ��ł���B �@�����܂ł��Ȃ����A�吳�E���a��ʂ��ď]���́A���̓퐳�ʂ́u�]�������B���v�Ɣނ̏����ɂ��āA���ᔻ�Ɉ��p����Ⴊ���������B�������Ȃ���A�������u���Ă����A���܂ł����Ă����������̐i�W�ɑ肪����B���������āA�퐳�ʂ��ˋ������u�]�������B���v�ɑ��A�j���Ƃ��Ă̕]����������Ƃ��Ă����K�v������B �@Go Back |
*�y������{�E�{�{�����z |
|
�@
�i5�j�����V�͓c���v���̎q �@�퐳�ʂ̂����u�]�������B���v�ɂ͂ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��������A���̋L�����e�@���\�\�Ƃ����킯�ŁA�ȉ������������Ă������B �@�܂��́A�u�����V�͑��㌹���ԏ��������c���v���̎q�v���Ƃ���B����́A�ŏ�����A�܂����������̓��e�ł���B �@�����Łu�c���v���v�Ƃ���̂́A���_�Г��D��w�d���Ӂx�Ȃǔd���j���ł́A�c���r���q�v���̂��Ƃł���A�{�{�ɐD�̕��ł���B�����Ȃ�ƁA����ւ܂�V�Ɩ���́A�{�{�ɐD�ƌZ��ł���A�����������͖���ւ̎q�炵������A�����͈ɐD�̉��ɂȂ��Ă��܂��B���㏇�����Ԉ���Ă���̂ł���B �@���s��d�B�O�ɂ�����̟f�N�E�N���v�Z����A�c���r���q�v���̐��N�͓V���Z�N�i1578�j�ł���B�悤����ɁA���N���炷��ΐV�Ɩ���̎q�̐���ł����āA���オ�܂������t���܂ł���B �@�u�]�������B���v�̘b�́A�̂�������卬���ł���B�������A������A������B�́A���Ԃ�}�O�̓`���Ƃ���A�v�������Ȃ����Ƃł͂���B�Ƃ����̂��A�����}�O�n�`���ɂ��j���ɁA���ނ̐��㍬�������邩�炾�B �@�܂�A����͒}�O�V�Ǝ��n���̋L���ł���B�{�T�C�g�m�����сn�}�O�V�Ǝ��n���̃y�[�W���Q�Ƃ����Ƃ�낵�����A���̒}�O�V�Ǝ��n���ɂ��A�\�\����i��B�g��S�|�R���E�V�ƈɉ��@�сj�̉Ɛb�E�{�{����V��́A�\�����̑��p�̖��l�A�ԓc����ɂ����āA����V���l�œG���l�Ƒΐ킵�A�\�����̑��ŏ����āA���̌��Ƃɂ�葥�킩��V�Ƃ̐����������ꂽ�Ɖ]���`���Ă���B����V��̑��q�E�V�ƈɐD�́A�א�z���璉�����Ɏd�����B���̎q�E�����͌��p�ŗL���ɂȂ����B����ɂ���ĕ������̌��p�����Ԃɓ`�������\�\�Ƃ����b�ł���B �@������̘b�ł́A�����͈ɐD�̑��q�ŁA���㏇���́A �@�@�@�@�@�{�{����V��@���@�V�ƈɐD�@���@�V�ƕ��� �Ƃ�������ł���B�퐳�ʂ́u�]�������B���v�ł́A���ꂪ�A �@�@�@�@�@�c���v���@���@�{�{����V���@���@�{�{���� �Ƃ��������ł���A�{�{�ɐD�͓c���v���̎q�ł���Ȃ�A�����̗{�q�E�ɐD�͕����̏f�����Ƃ������ƂɂȂ�B��������A�{�{����V��������ւ������`���̖��ŋg�����@�Ƒΐ킵���Ƃ����ẮA����͓c���v���o���i�V���Z�N����j�ȑO�̂��Ƃł���B�܂���������́A���ꖢ���ȑO�̂��Ƃł���B �@�܂��u�]�������B���v�ł́A�����͓c���v���̑��ɂȂ邩��A�V���Z�N����̓c���v�������̂Ƃ��A�܂�V���\��N�i1584�j�ɁA���̑������ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ʂ�A�卬���Ȃ̂ł���B�@ Go Back �@ �@�i6�j���ߋ{�{����V�����i����V�Ǝ� �@���̂����肩��A�u�]�������B���v�̔n�r���I�����Ă���B �@�܂��A�V�Ɩ�����u�{�{����V���v�Ƃ���̂́A�{�{�����̕��e�Ȃ�u�{�{�v�����낤�Ƃ����������琶�������̂ŁA����������̎��q�ł͂Ȃ��A�`�q���Ƃ���������m��Ȃ��B�������A�V�Ɩ�����u�{�{����V���v�Ƃ���̂́A��B���[�J���̓`���̓����ł��邱�Ƃ́A�{�T�C�g�����̏��_���Ŏ�����Ă��邱�Ƃł��邪�A���̂��Ƃ��炷��A�퐳�ʂ́u�]�������B���v�̏��݂͒}�O���c�Ǝ��ӕ������낤�ƁA���������B �@�����͐V�Ɩ���̏\��̉Ƃ𑊑����āA�V�Ǝ��𖼂̂�悤�ɂȂ������A���_�Г��D�ɂ��A�{�{���𖼂̂�悤�ɂȂ����̂́A�����̑ォ��ł���B�V�Ɩ�����{�{���Ƃ�����́A���ꂶ�����I�ȓ`���̎w�W�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���������āA�u�]�������B���v�̐��́A�V�ƂƋ{�{�̏�����|�������T���ł���B����������A �@�@�@�@�{�{����V���@���@�V�Ɩ���� �Ƃ���̂́A�V�Ǝ��Ɋւ���m�����Ȃ��Ƃ��납��A���̂����u�V�Ɓv�̈�������������ʂł���B�V�Ǝ��Ɋւ���m�����Ȃ��Ƃ����_���A��B���[�J���ȓ`���̓����ł���B�`�����̂��̂��ʂ����ό`�v���Z�X�́A �@�@�@�@�V�Ɩ���@���@�{�{����V�� �Ƃ��������ł��邪�A�`���̃|�W�V�������炷��A�ŏ��͋{�{����V���ŁA��ɐV�Ɩ���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���ꂪ�`���̑k�y�I�\���ɂ�����|���̌`�Ԃł���B�@ Go Back �@ �@�i7�j�Z���͔d�����K���S�{�{�� �@����͂܂��A�ӊO�ȂƂ���Łu�K���S�{�{���v���o�Ă���B �@�V�Ɩ���ւ̏Z���́A�Ȃ�Ɣd�B�̗K���S�{�{�����Ƃ����̂ł���B�������A���������b���o�Ă���v���Z�X�́A�����������������͂��ł���B �@�܂�A�q�̐��n�͂����ނ˕��e�̏Z���ł���B�Ƃ���ŁA�����͐����d���A�������K���S�{�{���̎Y�ł���\�\�����������A����ւ̏Z���͔d�����K���S�{�{���ƂȂ������̂ł���B���������āA �@�@�@�@�����̎Y�n�@���@����ւ̏Z�� �Ƃ����ڍs���A�`���ɓ��ݓI�ȃv���Z�X�ł���B����́A�����̐������u�{�{�v�Ȃ�A���E������u�{�{�v����ł���͂����A�Ƃ������f�Ɠ��O�ł���B�������A����͖������̎����ł������ꍇ�̂��ƁA���ۂɂ͖���͎����ł͂Ȃ�����A������{�{���Ƃ��邱�Ƃ��A�܂��A���̏Z�����Y�n�ɓ����Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�ȏ�̂��Ƃ����ɂ߂������ŁA���̓_���m�F���Ă����K�v������B
1�j�@�퐳�ʂ́u�]�������B���v�̔w�i�ɂ���`���́A�����̎Y�n�͔d�����K���S�{�{�����Ƃ�������D�荞��ł��邱�ƁB
�@���āA�ꉞ����珔�_���m�F���Ă����Ƃ��āA�퐳�ʂ́A���́u�]�������B���v�̋L���ɂ��A�V�Ɩ���ւ��������d������Ƃ�������������̂ł���B���ꂪ�A������{�w�{�{�����x�̕����Y�n������Ɛ^��������Η�������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B��ɂƂ��Ēr�ӂ̐��͔[���ł��Ȃ����̂ł���������A���̒����A�ڍu�b���J�n�����̂ł���B�@
Go Back
2�j�@�����̎Y�n�͔d�����K���S�{�{�����Ƃ������́A�d���n���j���ł��镽��f���w�d���Ӂx�ɂ���Ċm�F�����邱�ƁB 3�j�@�������A�퐳�ʂ́u�]�������B���v�̓`���́A���m�ȏ����������A�������d������Ȃ�A����ցi�����ƌ�F�j���d������Ƃ��鉯���̐���œW�J�����炵�����ƁB 4�j�@�������A�V�Ǝ��T�n�͐��d���֗������Ă��邩��A���ۂɂ͐V�Ɩ�����d���Z�l�A���邢�͔d������ł���\���͔ے�ł��Ȃ����ƁB 5�j�@�퐳�ʂ́u�]�������B���v�̓`���́A����ւ��c���v���̎q�ł���Ƃ��āA�{�{�ɐD���ƁE�c�����̏����捞��ł��邪�A���̎捞�݂ɂ����č���������A������B�i�����ł͒}�O���c�ƒ����Ӂj�œW�J�����`���ł���炵�����ƁB �@ �@�i8�j�O�̏��ʏ����O�Y�����ɛ����ċ��� �@���̕ʏ������i1555�`80�j�̎O�ؕʏ����́A�퍑�����A���d���ɑ傫�Ȑ��͂����Ƃł���B�u�d�������S�V���v�i�V���L�j�Ƃ������Ƃ��炷��Γ�\���̐퍑�喼�ł���B�������G�g�̔d�������ɍŌ�܂Œ�R���A�V�����N�i1580�j�O�؏闎��̂����ؕ������B �@�Ƃ���ŁA����ւ��K���S�{�{���Z�̕��m�Ȃ�A�ʏ������ɑ������Ƃ����̂͌��ł���B���̏Z�����炷��A�����̐ԏ��L�G�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B�K���S�͐��d���A�O�͓��d���A�ꏊ���܂������قȂ�B�u�K���S�{�{���v�Ƃ������ɗ]�v�Ȗڔz������邩��A�n�r�������Ă��܂��̂ł���B�������������ɁA�퐳�ʂ́u�]�������B���v�͋C�Â��Ă��Ȃ����A�܂�������Ƃ���قǂ̏����Ȃ��悤�ł���B �@�������A����Ȗ�����`���Ă��܂��̂ɂ��A���R���Ȃ��킯�ł��Ȃ��B�Ƃ����̂��A�퐳�ʂ́u�]�������B���v�́A����ւ�c���v���̎q�Ƃ��邩��ł���B�w�d���Ӂx�ɂ��A�{�{�ɐD�̎����E�c���r���q�v���́u���O�؎��v�ł���B�܂�A�c�����͎O�؏��E�ʏ����̟����ɂ������B�Ƃ���A����ւ�c���v���̎q�Ƃ���u�]�������B���v�̓`�����A����ւ�ʏ������ɑ������Ƃ���̂��A���̂�����ɂ����Ă͋��ʂ��Ă���킯�ł���B�������A���オ�������Ă���̂́A�s�\�����r�ł��邪�B �@�������Ȃ���A�悤����ɁA����͋{�{�ɐD�̎��ƁE�c�����̓`�����������Ĕ���������B�̓`���ł���B���q�{�{�Ɠ`���ł́A�V�Ɩ���̍��Ղ͐Ռ`���Ȃ���������Ă��邪�A�퐳�ʂ́u�]�������B���v��`���ٖ{�ƌ���A��B�ɂ�����`���̕���o�H������������ł��낤�B�@ Go Back |
 ���s�[���̓c���ƕ揊 �[���R���@���s�s������ �ɐD�ƌZ�킪�����������e��i�����j
*�y���掏�E�ɐD�̕���z
*�y�}�O�V�Ǝ��n���z
*�y���_���D�z  �d���� ����f�����M���  �d�������W�n�}
*�y�d���Ӂz |
|
�@
�i9�j�\��̖��l�œ����n�߂� �@��B���q�̕�����i�k��B�s���q�k��ԍ�j�̔蕶�ɂ́A�u���E�V�Ƃ͖���ƍ����A�\��̉Ƃ��Ȃ����B�����͂��̉ƋƂ��A���ȗ[�Ȍ��s���l�����������ʁA�ނ������ɒm�����̂́A�\��̗L�����͈꓁�̂���ɔ{���邱�ƁA������A�͂Ȃ͂��傫�ȍ�������Ƃ������Ƃł���B�������Ƃ͂����A�\��͏�p�̕���ł͂Ȃ��B����ɑ���{�̓��́A�����̏���̓���ł���B�Ƃ���A�������ď\��̐^���Ƃ���Ƃ��Ă��A���̒����Ɉ�w���邱�Ƃ͂Ȃ��B�䂦�ɁA�\��̉Ƃ����߂āA�̉ƂƂ����̂ł���v�Ƃ����L��������B �@���̕�����{���́s���U�A�ƋƂ��A���s�錤�t�Ƃ����L���ɂ��ẮA�d�����S�̔��_�Ёi���Ɍ����Ð�s�ؑ��j�ɂ��铏�D�̋L���Ɗ������āA�����͖���́u�\��̉Ɓv���A����̎���ɑ������p�����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A���@�҂͈��̐E�l������Z�p�͉ƋƂƂ��Ă���A���̖��Ղ��p�������B�����́A�p���҂̂��Ȃ����́u�\��̉Ɓv�̖��Ղ��A���炩�̉��ő��������Ƃ������Ƃł��낤�B �@����ƕ����́u�e�q�v�W�́A�E�l�̐��E�̋[���I�Ȑe�q�W�Ɠ��ނł���B�V�Ɩ���͕����́u���v�ł��邪�A�����܂ł��[���I�Ȑe�q�W�ɂ����镃�ł���B �@�Ƃ�����A����̏\��̉ƂɊւ��ẮA���q�蕶�����o�j���ł���A���������X�̓`�����W�J�����B�������Ȃ���A����ւ��\��̖��l�Ƃ����̂͂܂������A����n�n�����Ƃ����̂́A�ِ��Ƃ݂Ă悢�B���q�蕶�́A����������̏\��p���x�[�X�ɂ��Ȃ�����������Ƃ����݂̂ŁA����̓��ɂ͌��y���Ă��Ȃ��B�������A��̖��ɁA�p���������͎̂����ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�����̕����`�L�u���@��c���B���M���B�ҁv�`���ɁA����̋L��������A�����ɁA �@�@�s����A�\��m���p�����A����j�E�c�V�A��퐔���A���t �Ƃ���B�Ƃ���A����ւ͏\��̖��l�œ����n�߂��A�Ƃ����̂́A�u�]�������B���v�̋L�������ł͂Ȃ��A�퐳�ʂ̌��t�ł���B�Ƃ���A�����ł́u�]�������B���v�́A�}�O���c�ƒ��́w�O�����ϕM�L�x�炵���ƁA���������̂ł���B �@������t��������A�\��p�͐V�Ɩ���̔����ł��Ȃ����A�p�͕����̔����ł��Ȃ��B�\��p���p�����ɑO�Ⴊ����B�������A���������̓p�ɓ���ɂ��ẮA����̏\��p���}��ƂȂ������Ƃ͎����ł���A�����̓p�ɂ�����Ƒn�͂��̃v���Z�X�ɂ������B�@ Go Back �@ �@�i10�j�ʏ��̘Q�l�͑������c�ƂɎd�ւ� �@�퐳�ʂ��Љ��u�]�������B���v�̋L�����e���݂�ƁA�ʏ����ȊO�̏����̖����������A�O�؏�̕ʏ������d�B�S����x�z���Ă����Ƃ̍��o������悤�ł���B �@�ނ��A�ʏ����͓��d�����S���̈�ŁA����═���ɊW�̂��鐼�d���ɂ́A�ԏ����Ƃ�F�쎁�A���邢�͏������ȂǁA�ʏ����Ƃ͈قȂ�̎傪�������Ă����B���̕ӂ�̒m���̌��R������A�u�]�������B���v�̋L�����A�d�����牓����B�A������}�O���[�J���̓`���Ɉˋ��������̂ƒm���B �@�����ŁA�}�O���c�ƒ��Ǝv���������ȉ��ɕ��Ԃ̂ł���B�����������������Ă݂悤�B �@�܂��A�u�c���Z�V�i�v�̖�������B���̐l������ւ̐e�����Ƃ����̂́u�]�������B���v�̋L���Ƃ������A�퐳�ʂ̉��߂ł��낤�B����ւ��c�������i�c���v���̎q�j�Ƃ����̂�����A���̓c���Z�V�i�͖���e�����Ƃ������߂ɂȂ�B�������A�c���Z�V�i���̐l�̎��ւ͕s���B���_�Г��D�̋{�{�ɐD�ɂ��A�c�����̎҂����ܒ}�O�ɂ���Ƃ̂��Ƃł���A�c���Z�V�i���A���̂��ƂƂ����炭�֘A����B�{�{�ɐD�̕��E�c���v���̔�����]�Z�킪�A���c�ƒ��ɓ������̂ł��낤�B �@���ɁA�u�V�ƈɉ��v�B����́A��B�g��S�̒|�R��傾�����V�ƈɉ��@�т̂��Ƃł���B�{�T�C�g���_���ł��Ȃ��݂̐l��������A�����ł͐�����v���Ȃ����A�V�Ə@�т͔d�B�����S�����R��̉F�쐭���̎O�j�ŁA��B�g��S�̐V�Ǝ��֗{�q�ɓ������B���O�̉F�쑽���ɑ����A�c���ܔN�̊փ������A�̒n��ޓ]�A���̗��N�A�}�O�ō��c�����Ɏd����悤�ɂȂ����B�m�s�͒}�O�����S�ɓ��ł���B �@���̎��Ɂu�R��Ε��q�v�Ƃ�����������B����͂����炭�R��ΉE�q��̂��ƂŁA�������Ƃ���A�V�Ə@�т̎��Z�E�F��S���i�V�����N�ɐ펀�j�̑��q�ł���B�V�Ə@�тɂƂ��Ă͎��Ƃ̌Z�̎q�A�܂艙�ɂ�����B�R�萩�́A�����S�F�쎁�̖{���n�i���E���Ɍ������s�R�蒬�j�̒n���ł���B �@�����ŁA���ӂ��Ă��������̂́A���֕s���̓c���Z�V�i�͕ʂɂ��āA�V�ƈɉ����R��Ε��q���u�ʏ��̘Q�l�v�ł͂Ȃ����Ƃł���B������́A���d�������S�̉F�쎁�ł���A�Ƃ��ɐV�ƈɉ��@�т́A�F�쎁����V�Ǝ��֗{�q�ɏo�āA����g��S�̒|�R���ł���B�ʏ��Q�l�Ƃ͂܂��������Ⴄ�l�X�ł���B�@ Go Back �@ �@�i11�j���c�����q�F���̒핺�ɏ����� �@����ւ́A���c�����q�̒�E���ɏ������i1554�`96�j�̗^�͂ƂȂ����\�\���̋L���̏o���͓���ł���B��q�̔@���A�w�O�����ϕM�L�x�����̕����`�L�u���@��c���B���M���B�ҁv�`���ɁA����̋L��������A�����ɂ́A �@�@�s�M�N�@�����m���A���c���ɓa�m�^�͖�t �Ƃ����L��������B���������āA�O�ɏo���u����ւ͏\��̖��l�œ����n�߂��v�Ƃ����b�ƁA���́A�u���c�����q�F���̒핺�ɏ������̏��]�Ɉ˂莖����Ƃ��͗������o�͂��鎖�ɂȂ��v�Ƃ����b�́A�ǂ�����w�O�����ϕM�L�x���l�^���ł���A�퐳�ʂ̂����u�]�������B���v�́A���̕����Ɋւ��邩����A�w�O�����ϕM�L�x���Ɠ��肵����B �@�������A�w�O�����ϕM�L�x���A����Ɂu�M�N�@�����m���A���c���ɓa�m�^�͖�v�Ƃ���Ƃ�����A�u���c�����q�F���̒핺�ɏ������̏��]�Ɉ˂�A������Ƃ��͗������o�͂��鎖�ɂȂ��v�Ƃ����b�ɂ��Ă��܂����̂́A�퐳�ʂ̊g����߂ł���B�퐳�ʂ̂����u�]�������B���v�̋L���ƁA�ނ̑z���Ƃ̑���́A���X�ɂ��Ă���Ȃ��̂ł���B �@���������āA���̎��Ⴉ�炷��A�퐳�ʂ��u�]�������B���v�̋L�����Ƃ������̕����́A�K���������m�Ȉ��p�ł͂Ȃ��A�ނ̗v��Ɖ��߂������肱��ł���B���̕����͓T�����s���ł��邾���ɁA�ނ́u�]�������B���v�̏Љ�L���ɂ͈��̗��ۂ��K�v���A�Ƃ�����X�̌��������������ł��낤�B�@ Go Back �@ �@�i12�j���ɂ̐l�������V�̋����� �@���̋L���́A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ͂Ȃ��A�퐳�ʂ́u�]�������B���v�͕ʂ̎����ł���B �@�����A�u���d�b�̏M�g�Y���Ƃ͍ō��ӂł����v�Ƃ���u�M�g�Y���v�́A�D�g�ۍ��q��ߐ��̑��q�E�Ύ��ł���炵���B�ۍ��q��́A�V�Ə@�т��{�q�ɓ���Ƃ��A�d�B�����R��̉F�쐭������@�тɕt�����čs�������߂̈�l�ł���B���̌�V�ƉƂ𗣂�A�F�쐭���̌��֖߂������A������������āA�G�������i���c�j�����q�̟����ɓ������B�D�g�Y���͖ۍ��q��̓�j�ŁA�ܕS�B���̌n�������B�ɑD�g���𑶑�����悤�ɂȂ����B����A�ۍ��q��̒��j�͍��q�叮�M�Ƃ����A�d�B�Ɏc���Ďq���͑D�g�{���̑���J�i���E���Ɍ����p�S�O�������j�ɑ������Ƃ����B �@�D�g�Y�������c�ƒ��d�b�������Ƃ͉]���Ȃ��ɂ��Ă��A���̑D�g�Y���͕ʂ̏��ɂ������o���Ă���B����͒}�O�V�Ǝ��n�����̋L���ł���B �@����ɂ��A�V�Ə@�т͉F���q�E�����q�Ƃ�����l�̑��q����B�֓������č��c�ƂɎd���������悤�����A���@�т̎���A�Z�̉F���q�͔�����A��̎����q�͒}�O�Ɏc�������̂́A�������i���فj�ƂȂ�B�d�b���c���삪�ނ��E�������A�������Ă����̂��A���c�ƒ��̏��ѐr�g�ƑD�g�Y���������q�ɕ}���Č܌��𑗂��Đ������������A���ѐr�g�ƑD�g�Y���͐V�Ƌ��b�ł���A�Ƃ����b�ł���B �@���c�����q�͔d�B�ŁA�G�g����K���S�Ǝ����S�Ɍv�l����^����ꂽ�̂����A���̂Ƃ��A�F�싌�b�����c���ɑg�D���ꂽ�B�퐳�ʂ̂����u����ցv�ׂ͂ɂ��āA���ۂ̐V�Ɩ���́A���̑D�g�Y���Ɠ������F�쎁���ӂɂ��������A���c���ɗ^�͂���悤�ɂȂ������̂̂悤�ł���B �@�܂������́u��������v�́A���c��\�l�R�̖�������i1559�`1643�j�ł��낤�B�o�g�͉��ÌS������i���E���Ɍ����Ð�s�j�ŁA�}�O������͎O��A�S�l�g��a����B�q�̔��E�q��̑�ɂȂ�ƌܕS�ɂȂ��������c�ƒ��ɂ������B�u�v��l�Y���q�v�́A�v��l���q�i1545�`1592�j�̂��Ƃ炵���A�Ƃ����������c��\�l�R�̈�l�B�v�쎁�͔d���������S���ޕr��k���E���Ɍ�����s�l�ɑ�X�������ƁA�l���q�̕��E�d���k�������ˁl�����c�����q�́u���v�E���k���Ƃ����l�Ɏd�����Ƃ�������A�ÎQ�̉Ɛb�ł���B�l���q�͊����q�ɏ��N�����珬���Ƃ��Ďd�����B�L�O������ܐ��^����ꂽ���A���\�̖��Œ��N�Ŏ��S�B���q�̏d�`�͐Ί_���̐�Ő펀�A��̏d�����Ɠ��p���A�}�O������͘Z��A�Ȍ�v��Ƃ͍��c�ƒ��V�Ƃ��đ��������B �@����́A�w�O�����ϕM�L�x�ɕ��ɏ��^�͂Ƃ���悤�ɁA���c�Ǝ��ӂɂ����炵�����A����͔d�B����̂��Ƃł���B���c������B�L�O�ֈڏZ���āA�������B�֍s�������A����̋�B����͒����͂Ȃ��B���_�Г��D�ɂ��A�V���N���ɒ}�O�H����Ŏ��Ƃ��邩��ł���B�v��l���q�͕��\�̖��Ő펀�����l������A�ނ�����������V���N���Ɏ��Ƃ����͎̂����͓K���B�v����ɁA����ƍ��c�Ƃ̉��͎�Ƃ��Ĕd�B����̂��ƂŁA��B����͒����Ă����N�ł��낤�B �@�Ƃ��낪�A���c�Ƃ̋L�^�ł́A�c�����̕������ɐV�Ɩ���̖����L�ڂ��Ă���B�ƂȂ�Ɩ���͌c���N�Ԃ܂Ő����Ă����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���������c�ƕ������͌㐢�̋L�������邩��A�����̋L�����̂܂܂ł͂Ȃ��A����Ɋւ���L�^�̐M�ߐ��͒Ⴂ�B���������Ė���𒆒Èȗ��̌Õ���Ƃ��镪�����̋L�������₵���B�����́u���v����́A���c�ƒ��ł͓`���̗L���l�������̂ŁA���c�ƂƂ̊W����������`����������������������̂Ƃ݂���B�@ Go Back |
 �{�{�������������� �k��B�s���q�k��
*�y���q�蕶�z  �d���Ï�}  �����R�隬 ���Ɍ������s�R�蒬 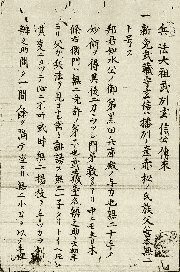 �O�����ϕM�L ���@��c���B���M���B��
*�y�}�O�V�Ǝ��n���z  �P�H���Ӎ��c��\�l�R�o���n |
|
�@
�u�b �{�{���U�i���j �@�]�������B���ɂ́A�����V���Ȃċv���̎q�Ƃ����̂�����(1)�B�N�㑴���̍l暂�肵�āA���̘_�Ђ���䗝�R����Ǝv�͂�邪�A�c���⏬���̍l暂͌Ɓk����l���q�k���l���A�]�������B���ɂ́A��҂̏����{�{�n�����c�����āA�������v���m���Ǝv����҂�����(2)�B���ܘY�̈ɐD�́A�d�B�����S�ēc���̋��m���{�r���q�̓�j��(3)�A��̐����͏��ĂȂ����ʏ������̉Ɛb�̖��ŁA���U�̏]�����c��҂ł���B�O�ؗ���̌�A���̕����ēc���ɏZ�����̂ŁA�r���q�ɉł����B���U�́A�r���q�̍ȁE�����ܘY�̕�Ƃ̉��̂͂���A�r���q���܂����Y���D�ނ��̂ŁA�x�X�r���q��K�ӂđ��Ƃɑؗ������B�����A���ܘY���c����荜�i��痁k�����܂��l���˟�������̂����āA���ɒ��������B���ܘY�����\�����U�ɉ��k�Ȃl�����|����A���U�͏I�ɔ��ܘY�����]���ė{�q�ɂ���(4)�B �@���ܘY�������������A���}���Ƃ�蕐�U�����������Ƃ̑��k�������B���U�͎d���̖]�Ȃ��ƂČ����Ђ����A�ĎO�Ďl�̍��]�ɕ��U���������Ɋ����A�u�����͍ŏ����䓚�����ʂ�d���̖]�͌����܂��ʂ��A���̗{�q�ɔ��ܘY�Ɛ\���҂����āA�v�͂܂���N�ł͂���A�Y�p�����n�ł��Ԃɂ͍��Ђ܂��܂����A�Ⴕ���\�ɂĂ����҂��䏢��������T�Ȃ�A���͌㌩�Ƃ��Ď��X�҂艽�Ȃ�Ƃ���p������܂����v�Ɠ��ւ��̂ŁA���}���Ƃɉ��Ă͕v�ɂĖ������Ɖ]�ӂ��ƂŁA���ܘY��V�n�O�S�ŕ��ւ�ꂽ�B���|�ŕ��U���̒ʎ��X���}���Ƃɍs���A�a�̂������������ƒ��̐l�X�ɓ��p�̎w������������A���㔪�ܘY�͒ǁX���g���āA�����ɐD�Ɖ��߁A�I�ɉƘV�E��螁k�̂ځl��A�\�l������͂�Ɏ���(5)�B���b�́A�{���Ƃ̉Ɛb�ŕ��U�̗�������ސl���A���U�̎��ւ�����ƂāA���\�\�O�N�ɑԁX�ēc���ɏo�����A���{�r���q�̎q���Ɉ��Ē��悽�|�������҂��Ƃ���B�������{�Ƃ͓y�n�̑可�����߂ċ������A���͏��q�̋{�{�Ƃ͈ɐD���O��ڂōK���q����i���P�l��Ղ��ċ���B���������̂őa���ɂ͂Ȃ邪�A�����̌�����W�݂͌ɒv���ċ���Ƃ̎������Y���Ă���(6)�B �@���̒��揑�̑�ӂ́A�j���ƔF�ނׂ��J�l�����邩�Ǝv�͂��A笂đO�ɂ��b�����ʁB���c�ƁE�{���ƁE���}���ƁA���͕ēc���ɏA�āA���U��萂��鎖�ւ������Ȃ�A���U�̙B�͈�w���m�Ɏ���ł��炤�Ǝv�͂��(7)�B |
|
�@�@�y�]�@���z �@�i1�j�����V���Ȃċv���̎q�Ƃ����̂����� �@����͑O�o�́u�]�������B���v�̘b�ŁA����ւ܂�V�Ɩ���́A�c���r���q�v���̎q���Ƃ����`���̂��Ƃł���B�������r���q�́A�{�{�ɐD�̎����ł���B�����Ȃ�ƁA�V�Ɩ���́A�{�{�ɐD�ƌZ��ł���A�����������͖���ւ̎q���Ƃ�������A�����͈ɐD�̉��ɂȂ��Ă��܂��B���̍��c�ƒ��ŏo���炵���`���̐��ł́A�W�l���̐��㏇�����������Ă���̂ł���B�@ Go Back �@ �@�i2�j�]�������B�� �@���̘b�̑O�i�ŁA�u�����`�v���Ȃ킿������{�w�{�{�����x�̕����`�L���A�w��V�L�x�̓D�ӈɐD�i�{�u�b�ł́u�D�ӕ����v�j�`�����̑�������A�܂�����Ɋ֘A���āA���q�{�{�ƌn�}�Ɍ��y���Ă�����p�������i�����p���Ă���B �@�u�N�㑴���̍l暂�肵�āA���̘_�Ђ���䗝�R����Ǝv�͂�邪�A�c���⏬���̍l暂͌Ɓk����l���q�k���l���v�]�X�Ƃ���̂́A�u�����`�v�����y���p�������q�{�{�ƌn�}�̋L�����e�ɂ�����邪�A�퐳�ʂ͏��q�{�{�ƌn�}�����Ă��Ȃ�����A�_�]������Ă���B�i���̏��q�{�{�ƌn�}�ɂ��ẮA�{�T�C�g�e���̕ʘ_�����Q�Ƃ��ꂽ���j�B �@���̏�ŁA�퐳�ʂ́A���q�{�{�ƌn�}�ɗގ���������������Ƃ��āA�ȉ��A���̏Љ�Ɏ��|����B�퐳�ʂ��Љ�邱�́u�]�������B���v�́A�O�o�̂��̂ƕʂ́A�{���ƒ��ŏo���`���ł���B�@�@ Go Back �@ �@�i3�j�ɐD�́A�d�B�����S�ēc���̋��m���{�r���q�̓�j �@�u���ܘY�v�́A�{�{�ɐD�̗c���������͏����Ƃ���āA���㑽���̕����]�`�═�������ɓo�ꂷ�閼�ł���B����͂��̓퐳�ʂ̘_������o�����̂ł���B�����A����ɍ���������킯�ł͂Ȃ��B�㐢�̓`���ł���B�����ɂ͈ɐD�̖����u�c���原�v�ł������Ƃ��������Ȃ��B �@���āA���́A�ɐD���u�d�B�����S�ēc���̋��m���{�r���q�̓�j�v�Ƃ����A���̉��{���ł���B����͑��Ɍ��Ȃ�����ł���B �@���Ƃ��A�ɐD����l�̂ŏo�����L�������_�Г��D�i���Ɍ����Ð�s�j�ɂ́A���{���̋L���͈�Ƃ��ĂȂ��B���������āA�c���r���q���u���{�v���Ƃ��邱�̓`���L���́A���炩�Ɍ㐢�̓`���ɂ����̂ł���B����䂦�܂��A�ȉ��̋L�����e���^�킵���B�@ Go Back �@ �@�i4�j���U�̏]�� �@�L�������ɒǂ��Ă݂悤�B�\�\�ɐD�̕�̐����͏�������ĂȂ����A�ʏ������̉Ɛb�̖��ŁA�����̏]���ɂ�����҂ł���A�O�ؗ���̌�A���̕����ēc���ɏZ�����̂ŁA�r���q�ɉł����\�\�Ƃ����b�ł���B �@�����̏����������c���Ă��Ȃ��̂͊��K�ɂ����Ȃ����A����͈ɐD�̕�̐�����m��Ȃ��`���ł���B�ɐD�̕ꂪ�匴�i�����j�����Ƃ����L���͂����ɂ͂Ȃ��B���������āA���́u�]�������B���v�ɂ�����ɐD�Ɋւ�����́A���łɂ��Ȃ�������Ȃ����i�K�̂��̂ł���B �@�ɐD�̕ꂪ�匴�����Ƃ������Ƃ́A�\�����I���̒n���j���w�d���Ӂx���F�����Ă�����ł���B���������āA���́u�]�������B���v�̐��������́A����������Ȃ�x���ł��낤�ƁA�ڐ������邱�Ƃ��ł���B �@�ɐD�̕�́A�w�d���Ӂx�ɂ��A�O�؏�ɋ߂������S���䑑�̋{�e���̐l�ł���B�ɐD���v�������̑��ɋ����Ƃ������Ƃł���B�ɐD�̎Y�n�͈��S�ēc�������A�ɐD�̒�E�����ɂ��āA�w�d���Ӂx�́A������u�����S���䏯�r�K���m�Y�v�Ƃ���B��̎Y�n�͉����S���䏯�ł���B������A�ɐD�Z��́A������������āA���S�ēc���ł͂Ȃ��A��̎��Ƃ̂�������S���䏯�̑��ň炿�A���邢�͐��܂ꂽ�̂ł���B �@�ɐD�̕�̎��Ƃ́A���Ƃ��Ɛے×L�n�S�̑匴�������A�r�ؑ��d�ɖłڂ���đޓ]���A���쎁�����ɓ������悤�ł���B�d�B�O�̕ʏ������ŖS���A���̌㒆�쎁���O�؏�ɓ���B���̂Ƃ��A�匴�����O�֗����炵���B���_�Г��D�ɂ��A���N�̖��œ��傪�펀���A�j�q�Ȃ��A���ƂƂ��Ă̑匴���͒f�₵�����A�ɐD�̕�͂�����ċ����邽�߁A���q�̈�l�ɉƖ����k�����ނ���t�ɂ��ė��g�������B���ꂪ�ɐD�̒�E�匴�����ł���B �@���������āA���́u�]�������B���v���A�ޏ���ʏ������̉Ɛb�̖����Ƃ���̂́A�`���̍���������B�������A���̈ɐD�̕ꂪ�A�����̏]�����Ƃ����B�ޏ��́A�O�؏��E�ʏ������̉Ɛb�̖����Ƃ�������A��������ƁA���̏]�Z�������̕����m���Z��Ȃ�A�����̏o���́A�ɐD�̕�̎��ƁE�匴���Ȃ̂��B�����͎O�؎��̎q�ŁA���̏o�g�n�͎O�ł������̂��B���̂�����܂ŗ���ƁA���͂�A�قƂ�ǒ����̕��ނł���B �@�Ƃ��낪�퐳�ʂ́A�V�Ǝ����ʏ����̟����ɂ������Ƃ����T����M���Ă���l�q�ŁA�O�o�́u�]�������B���v�ƁA�����ň����Ă���u�]�������B���v�Ƃ̋L�����e���A�O�؏��E�ʏ����ԂƂ��Ċ֘A�t������̂ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂��Ă���悤�ł���B �@���Ď��̘b�ɂȂ邪�A�����͈ɐD��{�q�ɂ����B����͎����ł���B�Ƃ��낪�A���́u�]�������B���v�ł́A�������\�\�����́A�r���q�̍ȁi�ɐD�̕�j�Ƃ̉��̂�����i�܂�]�Z�j�A�r���q���܂����|���D�̂ŁA�x�X�r���q��K���Ă��̉Ƃɑ؍݂����B�����͈ɐD�i���ܘY�j�������̊�ʂ�F�߂āA�{�q�ɂ����A�]�X�B �@����͓��̉��{�Ƃ̕����`���Ƃ����ׂ����̂ŁA���^�́A�u�������ɐD��{�q�ɂ����v�Ƃ��������ł���B���ꂪ�A�ł́A�u�ǂ��������ŕ����͈ɐD��{�q�ɂ������v�Ƃ������R�̐�������A����͈ɐD���e�����������낤����A�Ƃ������b�I�W�J�ɂȂ�B�܂�A�`���̓`���ߒ��ł́A�����͂��̂܂܂ł͕��u����Ȃ��B�������ɐD��{�q�ɂ����Ƃ����������A�e���W�ɂ���ĉ��߂����B���͂��łɉ��߂ɂ���ĐN�H����Ă���̂ł���B����ɂ�������A�����͈ɐD�̐e�����Ƃ������b��̔��]�iinversion�j�������A����ɖނ��炵�����Ђꂪ�t���A�Ƃ����Ȃ�䂫�ł���B���Ȃ킿�A���̔��]�́A �@�@�i1�j�ɐD�́u�����̐e���v�ł��� �@�@�i2�j�����́u�ɐD�̐e���v�ł��� �Ƃ��������ł���B���̊�{�`���ł���ƁA�����̏o�����̂��̂��A�ɐD�̎��ƁE�c�������ӂɈ�������B���́u�]�������B���v�̂悤�ɕ������ɐD�̕�̏]�Z�ɂȂ�����A���邢�́A���q�{�{�ƌn�}�̂��Ƃ��A�������r���q�̒�A�ɐD�̏f���ɂȂ��Ă��܂��킯�ł���B�����������b��̍\���y�ѓW�J�́A�\�����I������\�㐢�I�ɂ����Đ�������Ă��������̂Ǝv����B�Ƃ����̂��A���Ȃ��Ƃ��\�����I���́w�d���Ӂx�����̈ɐD���ɂ́A����Șb�͂܂�����Ă��Ȃ�����ł���B �@Go Back |
*�y������{�E�{�{�����z  �d�������W�n�}  �ɐD�̕�̎��� �d�B�����S���䏯
*�y�d���Ӂz |
|
�@
�i5�j���}���Ƃ�蕐�U�����������Ƃ̑��k������ �@�ȉ��́A�ɐD�����}���ƂɎd������b�ł���B�܂��A���}���Ƃ�蕐���������������Ƃ̑��k���������B�����͎d���������͂Ȃ��ƌ����f��������A�ĎO�Ďl�̍��]�ɁA�����͑���ɁA�{�q�̈ɐD���������Ă��炢�����Ɨv�]���āA�ɐD����������ꂽ�A�Ƃ������Ƃł���B �@����́A�ɐD�{�q���悩�A�d�����悩�A�Ƃ�����̖��Ɨ��ށB�܂�A�ɐD�͕����̗{�q�ɂȂ��Ă��āA���̌�A���}�������ɏ�������ꂽ�̂��A����Ƃ��A�ɐD�͂��łɖ��̏��}���Ƃɏ��������Ă���A���������}���Ƃ̋q���ɂȂ����Ƃ��A���̉��ŁA�ɐD�͕����̗{�q�ɂȂ����̂��A�Ƃ������ł���B �@��҂ɂ��ẮA�w�d���Ӂx�ɂ��̗Ⴊ����B�\�\���������ɂ���ė��āA���}���E�ߏ��Č�ɉy�������B���̎��A�ɐD��{�q�Ƃ��A���̌�A���}���L�O���q�ɓ]�������Ƃ��A���������B���邢�́A�ɐD�\�Z�̎��A�Ԑk���l�̌��召�}���E�ߌA�{�{�����Ƃ����V�����o�̕��p�҂����������q���ɂ��Ă������A���̈ɐD�����̉Ɓk���}���Ɓl�ɏ������Ă����Ƃ���A�ɐD���������ʂ����ꂽ�����ł��邽�߁A�������{�q�ɂ����B�̂��A�L�O���q�֍��ւ̂��߁A�ɐD�������ɂ��ĉ������A�]�X�B �@�悤����ɁA�w�d���Ӂx�̂悤�Ȓn���j���ł́A�ɐD�������̐e���ŁA������͗{�q�ɂ����A�Ƃ����b�͈ꌾ���Ȃ����A�t�ɁA���������̏��}�������̋q���ɂȂ����Ƃ��A���܂��܂����ɈɐD���Ɛb�Ƃ��ċ���A�����͂����{�q�ɂ����A�Ƃ����킯�ł���B �@���̂悤�ɁA�ɐD�͕����̐e���ł͂Ȃ��A���}������������ĕ����̗{�q�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ̕����A�����Ƃ��炵���̂����A�㐢�̓`���ł́A�����͋t�ɂȂ�X��������B�@ Go Back �@ �@�i6�j�{���Ƃ̉Ɛb�ŕ��U�̗�������ސl���c �@���āA���́u�]�������B���v�̏o���ł���B�`���̃^�C�g�����������炩�ł͂Ȃ����A�퐳�ʂɂ��A����́A�{���Ƃ̉Ɛb�ŁA�����̗�������ސl���A�����̎��ւ����邽�߁A�ēc���ɏo�����A���{�r���q�̎q���Ɉ����Ē���������b���Ƃ����B���́u�{���Ƃ̉Ɛb�ŁA�����̗�������ސl�v�����҂Ȃ̂��A���̍u�b�͈̔͂ł͕s���ł���B �@����ɑ��A���̒������_�����L����Ă��āA���\�\�O�N�i1700�j�ł���Ƃ����B���b���ŗL���ȁA�����������]�ˏ��a���̘L���ŋg�Ǐ������������̑O�N�ł���B�����ߗׂ̖{���ƂƂ����A�P�H���E�{��������㒉���ł���B �@������ɁA�{�������Ɏd�����u�����̗�������ސl�v�Ƃ��������ŊY������̂́A�܂��́A�{���ƒ��̕��������`�҂ł��낤�B�������́A�������ΐ��Ł���c����������Y�E�q��^�P��������Y�E�q��^���c�Ǝ��悷����̂ŁA���\�\�O�N�Ƃ����ƁA���̍�����Y�E�q�啃�q�A�^�P���邢�͐^���̐���ł��낤�B �@���̌��\�\�O�N�ȑO�ɁA�ĔC�O���q����邪�{�������ɏ��o����d���Ă�������������B���̂Ƃ��A�u�×��v�Ƃ��āA�ΐ��ňȗ��̕��������{���ƒ��ɑ������킯�ł���B �@�퐳�ʂɂ��A����͖{���ƒ��̎����炵������A�P�H�Ȍ�A���]������ɁA�O�͉���ɍ����������{���Ƃ̉ƒ��̓`���ł��낤�B�{���ƒ��ɂ́A��L�̂悤�ɁA�������ΐ��Ł���c���c�Ƃ����������������āA�������Ə̂��A�����܂ŎO�͂Ŗ嗬���c�����B������������́A�`�����e�����邩����A���Ȃ�ό`��ւ����������ł���B����䂦�A�����ƈɐD�̂��Ƃ��A�{���Ɨ��]�ߒ��ł��Ȃ�`���̕ό`���������悤�ł���B �@����Ƃ͕ʂɁA�����[���̂́A�ɐD�̏��q�{�{�Ƃ̎q���̋L�����݂��邱�ƂŁA���q�̋{�{�Ƃ͈ɐD���O��ڂōK���q��Ə̂��A�Ȃ��l��Ղ��ċ���A�Ƃ���B �@�{�{�ƌn�}�ɂ��A���̍K���q��́A�ɐD�原�����E�q��ݒ偨�K���q�����Ə�������n���̎O��ڂł���B�ɐD�̒��j�E�����q���M�͓�\�Z�Ŏ��S�A���̂��߈ɐD�́A�Z��R�ΉE�q��g�V�̑��q��{�q�ɂ����B���ꂪ���ڂ̖��E�q��ݒ�ł���B�O��ڂ̍K���q�����́A�������������q���M�̎q�ŁA�ɐD�̑��ɂ�����B�K���q��ʼnƓn�ɖ߂����̂ł���B���\�\�O�N�����́A���̍K���q��̑�ł���B�@ Go Back �@ �@�i7�j�j���ƔF�ނׂ��J�l�����邩�� �@���́u�]�������B���v�͎j���Ƃ��ĔF�߂�ׂ����l������ƁA�퐳�ʂ͂����B�������Ȃ���A����Ȃ킯�ɂ͂����Ȃ��B�O�L�̔@���A�L�^�ɂ͌��\�\�O�N�Ƃ����A���J�[���ł��Ă���悤�����A�ȏ㏇�����������悤�ȓ��e���炷��A�����炭�\�㐢�I�̍�ł��낤�Ǝv����B �@�������A�ɐD�̕�̏]�Z�Ƃ���̂́A���q�{�{�ƌn�}�قNjɒ[�ł͂Ȃ����A����ł��A�ɐD��{�q�Ƃ���ɂ͕����̐e���ł��낤�Ƃ������߂��A�`���̒��ł��̂܂ɂ��{���ւ���ւ�������̂ł���B�퐳�ʂ��������́u�]�������B���v�̍����U����̓}�V�ƌ����邪�A����ł��A�ɐD�̕�̐�����m�炸�A�ɐD�������u���{�v�r���q�Ƃ���ȂǁA�n���Ńt�B�[���h���[�N�����Ƃ��v���ʓ��e�ł���B �@���_�������A�j���Ƃ��ĔF�߂�ׂ����l�͂Ȃ��B�������A����͖{�u�b�̓��e�ɂ�邩����łł����āA�퐳�ʂ́u�]�������B���v�������ł���A��������������e�N�X�g���͂��ł��邩������Ȃ��B�@ Go Back |
*�y�d���Ӂz  ���Ώ隬  �P�H��V��t  ���q�{�{�ƕ揊 �k��B�s���q�k��ԍ� |
|
************************************************************* �@�y�@�v�@���@�z �@�{�u�b�ŁA�퐳�ʂ������u�]�������B���v�͓��ނ����āA��́A�}�O�̍��c�ƒ��ŏo���炵�����́A������͔d�B�̕P�H���◴������Ƃ߂����Ƃ̂���{���Ƃ́A�㐢�O�͂���������̓`���ŁA��������`�������{���ƒ�����o���炵�����̂ł���B �@���́u�]�������B���v�̋L�����e�́A�ǂ��ł��������B�ēx�f�Ă݂悤�B
�i1�j�@����ւ́A���㌹���ԏ�����̖���E�c���v���̎q�B
�@�ȏ�ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA���́u�]�������B���v�̋L�����e�́A����ցi�V�Ɩ���j�̏��ł���B������ɁA����ւ̏Z���͔d�����K���S�{�{���Ƃ���Ƃ���́A�s�����͗K���S�{�{���Y�t�Ƃ���n���d���̏��ɋ��������̂ł��낤���A����ւ�c���v���̎q���Ƃ���A���̓��e���炷��ƁA���q�{�{�ƌn�}�Ɠ��������邢�͏�����̐V�����앨�ŁA�`�����ό`����āA���̂悤�Șb�ɂȂ������̂ł��낤�B�i2�j�@�͂��ߋ{�{����V���Ə̂��A��ɐV�Ǝ����k���Ŗ���ւƏ̂����B �i3�j�@����ւ̏Z���́A�d�����K���S�{�{���B �i4�j�@����ւ́A�O�̏��E�ʏ����O�Y�����ɑ����Ă����B �i5�j�@����ւ́A�\��̖��l�œ����n�߂��B �i6�j�@�ʏ��ƖŖS�̌�A�ʏ��̘Q�l�͑������c�ƂɎd�����B����ւ̐e���c���Z�V�i�A�V�ƈɉ��A�R��Ε��q���A�݂ȍ��c�ƂɎd�����B �i7�j�@����ւ́A���c�����q�̒�E���ɏ������̏��]�ɂ��A������Ƃ��͗����ɗ^�͂��邱�ƂɂȂ�A�����薳��ւ͍��c�Ƃɏo�������B �i8�j�@����ւ͍��c�Əd�b�̏M�g�Y���Ƃ͍ł����ӂł������B �i9�j�@��������E�v��l�Y���q�i��l�Ƃ����c��\�l�R�̕����j�ȂǁA���c�ƒ��̑����̐l������ւ̋��������B �@�܂��A����ւ͎O�؏��E�ʏ������ɑ����Ă����Ƃ����̂́A�c�������u�O�؎��v�ł������Ƃ��������肩��o�Ă�����̂ł��낤�B�����떳��ւ�c���v���̎q���Ƃ���̂�����A�����������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�������Ȃ���A����ɂ܂��A����̐V�Ǝ����O�ؕʏ����ɑ������Ƃ������o������悤�Ȃ̂ŁA��d�̌�`���������ďo���b�ł���B �@�V�Ɩ���ƍ��c�Ƃ̉��́A�����炭�����i���c�j�����q���K���S�⎳���S�Ȃǐ��d���ɗ̒n���̂��_�@�ł����āA���d���̕ʏ�����}��邱�Ƃ͎����゠�肦�Ȃ����Ƃł���B���̓_�ł��A���̑��́u�]�������B���v�̓��e�́A�d����m��ʖ����̒n�Ŗ������`�������`���Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�����c���ɏ������̗^�͂ɂȂ����ƋL��������A����͂���ň��̐M�ߐ������邪�A��������A�v��l�Y���q�A����ɏM�g�Y���Ƃ̊W�ɂ��ẮA���̓`���ȊO�ɂ͒m��Ȃ����A���c�ƒ��̌ʏ��ƕ��ɂ���ȋL�����������̂�������Ȃ��B �@�ȏ�̂��Ƃ���A���̑��́u�]�������B���v�̖���֏��̂����A���Ȃ��Ƃ��O���̏����ڂ͂܂������M�ߐ����������̂ŁA�ˋ�����ɂ�����Ȃ��B��B�}�O�̍��c�ƒ��Ő��܂ꂽ�`���ł���A�`�������́A�����炭�\�㐢�I����k�邱�Ƃ͂���܂��B �@���ɁA���́u�]�������B���v�͂ǂ����B �@������́A�����{�q�̋{�{�ɐD��}��ɂ������ł���B������A�������Ă݂�A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�i1�j�@�ɐD�́A�d�B���S�ēc���̋��m�E�u���{�v�r���q�̓�j�B
�@���łɊe���ڂ͌ʂɌ������A�����Ő���������A�r���q�́u���{�v���A����͖��炩�ȊԈႢ�ł��낤�B�ɐD�o���Ɋւ��Ă͔��_�Г��D���ꎟ�j���Ȃ̂����A������������A�r���q�͓c�����ł���A���{���ł͂��肦�Ȃ��B���������āA���\�\�O�N�ɒ��撲���������Ƃ������A���łɂ��̎��_�ŁA�b�͂��₵���̂ł���B�i2�j�@�ɐD�̕�̐����̋L�ڂ͂Ȃ����A�ʏ������̉Ɛb�̖��B �i3�j�@�ɐD�̕�́A�����̏]���ł���B �i4�j�@�O�ؗ���̌�A�ޏ��̕����ēc���ɏZ�������ŁA�u���{�v�r���q�ɉł����B �i5�j�@�����́A�e�ʂƂ������Ƃ������āA���{�Ƃɂ����Α؍݂����B �i6�j�@�����́A�]���̑��q�ł���ɐD��{�q�ɂ����B �i7�j�@�����ɏ��}���Ƃ�菢���������Ƃ̘b�����������A�����͂����f���A����ɗ{�q�̈ɐD���d���������B �i8�j�@�ȏ�̘b�́A�{���Ƃ̉Ɛb�ŕ����̗�������ސl���A�����̎��ւ����邽�߁A���\�\�O�N�ɕēc���֏o�����A�u���{�v�r���q�̎q���Ɉ����Ē�������b�ł���ƁA�`���ɋL���Ă���B �i9�j�@�����҂��������u���{�v�r���q�̎q���́A�可�����Ƃ߂Ă���A���q�̋{�{�ƎO��ڂ̍K���q��ƁA�����̏���̂����Ă��ǂ̕t�������͂��Ă���B �@�w�d���Ӂx�ɂ́A�ɐD�̌W�ݎq���������ēc���ɂ܂�����Ƃ��邩��A���\�\�O�N������ɕēc�̓c�����͑������Ă����B���������āA�可���̉��{�ƂȂ���̂��c�������}�Ȃ̂�������Ȃ����A�ɐD�̕�̏o����m��Ȃ��Ƃ����ẮA�����҂͂���ʑΏۂɘb���Ă��܂����Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B��N�́w�d���Ӂx�̕�����قǏ��͐��m�ł���B���������āA���邢�͏����͋t�ŁA���̒��撲�����̂��̂����͂����ƌ㐢�̓`���ŁA�b�̒��Ō��\�\�O�N�Ƃ������_�ɉ������ꂽ���̂�������Ȃ��B �@���ɁA���̑��́u�]�������B���v�̍ł��ˏo�����|�C���g�A���Ȃ킿�A�s�ɐD�̕�͕����̏]���t�Ƃ�����_�B����ɂ��ẮA���������`�������\�\�O�N���_�ő��݂����A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ����A�w�d���Ӂx�͂�������^���Ă��Ȃ��B�����A���悤�ȓ`��������A�ēc�ב��Z�l�E����f���̂��Ƃ�����A�ނ���ϋɓI�Ɏ��^�����ł��낤�B����䂦�A�ɐD�̕�͕����̏]���Ƃ����`�������݂������Ƃ́A�n���d���ł͊m�F�ł��Ȃ��̂ł���B �@���̋L�^�҂́A�{���Ƃ̉Ɛb�ŕ����̗�������ސl�ł���Ƃ����B���̑��́u�]�������B���v�́A�{���ƒ�����o�����̂̂悤�����A���̐l���́A�{�u�b�ɂ�邩����A�s�ڂł���B���\�\�O�N���_�Ƃ����ƁA�P�H���E�{�������̉Ɛb�Ƃ܂ł͓���ł���B�������A�{���Ƃ́A�����ƕP�H���ł������̂ł͂Ȃ��B�����e�n��]�X���āA���̎������܂��ܕP�H���ł������ɂ����Ȃ��B���������āA���ˊ���т��ċ�B�}�O�ɂ��������c�ƂƂ͎���Ⴄ�B�{���ƊW�̔d�B�����͎c��ɂ����̂ł���B����͕P�H�˂ɂ��Ă������邱�ƂŁA�\�����I���̍]�ˎ���O���܂ł́A��傪�p�ɂɌ�サ�Ă���B���]�����͂Ȃ͂������B���������āA�ː��L�^�͂��ߎj�����c��ɂ����Ƃ����������B �@����䂦�A���̒��撲�������\�\�O�N���_�̂��̂��A�Ƃ����_�͒��d�������̂����A�s�ɐD�̕�͕����̏]���t�Ƃ�����_���܂߂āA�����`���Ƃ����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B���������̓`�����A�]�����ƂɊe�n�����{���ƒ��̓`����}��ɂ��Ă���ƂȂ�ƁA�����̂��₤���j�����ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B �@�s�ɐD�̕�͕����̏]���t�Ƃ����`�����܂߂āA�������ɐD�̐e�����Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ��\�����I���́w�d���Ӂx�ɂ͂Ȃ����̂ŁA����͂����炭�\�㐢�I�̓`�������ł��낤�B����Ɍ��\�\�O�N�Ƃ����A���J�[���ł��Ă���Ƃ��Ă��A�����Ε����L�����N�f�[�^����������̂͒ʗ�ŁA���̃P�[�X�ł��A���\�\�O�N�����Ƃ����L�����̂��̂��`���ł���\��������B �@�{���Ƃ͕P�H�Ȍ�A�z�㑺��A�O�͊��J�A�����É́A�Ό��l�c�A�e�n��]�X���āA���a�Z�N�i1769�j�ɎO�͉���ɋ������B�����ȗ��̕��@�́A�������Ƃ��Ė{���ƒ��œ`�����ꂽ�B�����炭�A���̑��́u�]�������B���v�́A���̎O�͕������̓`���ł��낤�B�������A��L�̂悤�ɁA����͂��Ȃ�`���ό`��ւ�����̓��e�ł���B���������āA�f�Ђɂ���炵�����b�f�����邪�A�S�̂Ƃ��čr�����m�ȓ`���ƂȂ��Ă���B �@�������Ȃ���A���Ƃ��ǂ�Ȃ��̂ł��A����ꂽ�����͎������������̂ł���B��X�͓퐳�ʂ̍u�b��ʂ��Ă����A��́u�]�������B���v�̓��e��ˌ��ł��Ȃ��̂����A��������炪�Ĕ��������Ȃ�A�܂��ʂ̓ǂݕ����\�ł���B���̉\���͕��������̊J�����Ƃ��Ďc���Ă��������ƍl����B |
�@PageTop�@ �@�����іڎ��@ �@Back�@ �@Next�@
