 |
���k�E�{�{���� �d�������������ݒ����k�� |
|
| ূɕ��p�̒B�l�L��A���͊◬�B�ނƎ��Y�����������ށB�◬�]���A�������ȂĎ��Y�������𐿂ӂƁB�������ւĉ]���A���͔��n�����Ђđ��̖���s�����A��͖،���č��̔�����͂���ƁB������������ԁB����ƖL�O�̍ہA�C���ɓ��L��A�M���ƈ��ӁB�_�Y�����ɑ������B�◬�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂��薽���ڂ݂��p��s�����B���U�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���P�x���B�̂ɑ��M�������߂Ċ◬���ƈ��ӁB�i���q�蕶�j |
| 07 | �`���Ƃ��Ă̊ޗ������� �@�i��сj | �@Back�@ �@Next�@ |
Go Back to�F
�@�ڎ��@
|
�@�i���@�@�O�j �\�\�������������܂��B���͒x���܂ł��肪�Ƃ��������܂����B�ޗ��������`���ɂ��āA���łɂ��Ȃ�̓��e�̂��b�ɂȂ��Ă���܂��B�����A���������˂����������Ǝv���܂��B �`�\�\����͂ǂ��܂ŁA�b���s�����̂ł������ȁB �b�\�\�}�O�n�`���ł́A��������ɓ������ď����Y��҂����B���n�`���ł́A�������x�����ď����Y�͑҂����ꂽ�A�Ƃ���������܂ł������B �a�\�\�����͔ڋ��ɂ��������Ēx�������A�Ƃ����ߑ�̋����j��I�����́A�悤����ɁA��c�Ԃ肵�������̂��ƂŁA�����V�������Ԃ͂Ȃ��B����͍�錾�����ʂ肾�ȁB �b�\�\�Ƃ���ŁA�܂��ʂ̍\���I�Ώ̐����������B����͑O�ɏo���A�������̋G�����ȁB����́A�ߑ��̋L�q�����邩��A����Őݒ�̔���͂ł���B �a�\�\�܂肾�A�w���ϕM�L�x�́u�\���v�Ƃ���̂ɑ��A���n�̓`�L�ł́A�w�����`�x�͉����Ƃ����L�����������A�w��V�L�x�ɂ��A������u�l���v�A������\�O���Ɠ��肳���B�悤����ɁA�w���ϕM�L�x�Ɓw��V�L�x�ł͋G�߂͋t�ŁA�w���ϕM�L�x�́A�\���܂菉�~�̂��ƂƂ���̂ɑ��A�w��V�L�x�ɂ����ꂪ���Ă̂��Ƃł���B �`�\�\������Ώ̐��ɋɂ߂Ē����ȑΗ��ł����āA���b�_�I�ɂ݂���Ȃ苻���[���Ƃ��낾�B �@�@�@�@�@�@���@�~�@�~�@���@�� �b�\�\�����A�O�̂��ߒ��ӂ��Ă����A�������̂͂ǂ��炩�A�ȂǂƂ����ڒ����Ȗ₢�͋p������i�j�B���������A���������́A�w�]�C�������x���\���ŁA�w���ϕM�L�x�������\��A����ɑ����n�`�L�ł͕�����\��ƁA�\�N�̍��ق�����B�������ւ̃i�C�[���Ȋ͂��̐�ΓI���قɖ|�M����邾�����낤�ȁB �a�\�\���Ă����ŁA�����̈ߑ��̘b�ɂȂ�B�ߑ��Ȃǂǂ��ł���������Ȃ����A�Ƃ����̂�����l�̊��o�Ȃ�A���̓����̐l�Ԃ͈ߑ����C���[�W�ł��Ȃ��ƃ��A���e�B�Ɍ�����Ƃ��낪�������炵���B �`�\�\�w�]�C�������x�ł́A�������̓��̑����́A�Ƃ����b�ŁA�u㌎q�̂��͂�����͂������ɂ��Ē��Ă����v�Ƃ���B �a�\�\�u���͂�v�Ƃ����̂��@�ق��ȁB���m�̂悤�ɁA����͉����E���������A���Ƃ̓|���g�K����igibao�j���炫�Ă���B������u���͂��i����E�ށj�����v�ɂ��Ē��Ă���Ƃ����B����Ⴀ�A������ؕ��̍Ő�[�t�@�b�V���������i�j�B �`�\�\�w�]�C�������x�ł͕����͏\��������A�c���Z�N�i1601�j�Ŋփ������̗��N�ł��ȁB�|���g�K�����l�͑�ʂɕ�������������ł������A�؎x�O���ȑO������A�鋳�t�������Ɋ������Ă����B��������������A�����̓�t�@�b�V�����͓��R���肤��B �b�\�\��ؖf�Ղ͗������傫������A���喼�͋����ă|���g�K���l���l��鋳�t�Ɛe�߂��悤�Ƃ��Ă������B�c�������̕��m�͔h��ȓ�t�@�b�V�������D�݂������i�j�B�Ƃ���ŁA�w���ϕM�L�x�ł́A�����̈ߑ��́A�\�����~�̔������G�߂̂��ƂƂāA���ɂ͏����𒅂���Ɉ��𒅂āA�Ƃ������D�ł���B�����͔����E�����ŁA�����㒅�Ƃ������ƂɂȂ�B �`�\�\���̒��߂��ȓ��ł��������ǂ����́A���̋L���ł͂킩��Ȃ����A�̂��₦��G�߂����A�C��n�邩�爿���d�˒����Ă���B �a�\�\�w���ϕM�L�x�́A���ɂ͏����A��Ɉ��𒅂āA�Ƃ������x�����A�}�O�n��p�́w���@��t�`�L�x�͂������B��ނ��̉����ɁA��ɍ��H��d�̈ߏւɔ�̃J���T���𒅂��A���j�q�̓����߂ɏ�т��āA�Ƃ����t�@�b�V�����i�j�B �b�\�\�����͎�������ȁA����ȃh�h��ō����Ȉߑ��ɂȂ�i�j�B����A�����Y�̕��ɂ͉��̋L�q���Ȃ��B �a�\�\�������Ē������ꂪ�o�Ă���B�u�J���T���v���ȁB�n��ɂ���ẮA�����ł��܂����̌ꂪ�c���Ă����āu�J���T���v�Œʂ���B����Ɏ����Z�тŁA��ǒ��ł���B�Ƃ��낪����́A���Ƃ̓|���g�K����ŁA�u�y�́v�Ƃ������Ď������Ă���B��n�Y�{���Ɏ������̂��ȁB��؛����ɂ��̃J���T���p�̃|���g�K���l�Ȃǂ��`����Ă���̂�����킩��B���ꂪ��������āA�ߐ������ȗ��A�������ƒ��Ƃ��čL���p������悤�ɂȂ����Ƃ����킯���B �b�\�\������A��t�@�b�V�����Ƃ݂Ă悩�낤�B��߂͏����Ɉ��Ƙa�������A�Z�т̃J���T���Ƃ̑g�ݍ������t�@�b�V���i�u���Ȃi�j�B �a�\�\���łɌ����ƁA�w�]�C�������x�ł́A���͗��t�k�������l�ƂȂ��Ă���ȁB����́A�����闧���сB����R�ŕG���ł�������āA�������r�J�Ƃ����g�ݍ��킹�ɂ������̂ŁA������т̈��ł���B�u�J���T���v�Ƌ�ʂȂ��Ɏg���邱�Ƃ�����B���̋L�q�̗����́A�w���ϕM�L�x�̃J���T���Ɠ����Ƃ݂Ă悩�낤�B �b�\�\�����������Ƃ��ˁB�w�]�C�������x�ł́A���������t�@�b�V�����ŃL���Ă���킯���i�j�B���Ȃ݂ɁA�J���T�����~�̍�ƒ��Ƃ��Ďc�����悤�ɁA�����̋G��͓~�ł���B���������āA�G�߂̈ߑ������Ƃ��ẮA���n�`�L�̏��Ă��́A�w���ϕM�L�x�̂������~�̕����Ó��ł���B �`�\�\����ƁA���n�`���̏��ĂƂ����G�߂́A�����ł͋G�ꂪ����Ȃ��i�j�B �b�\�\�������āA�}�O�n�w���ϕM�L�x�̓`���ł́A�����̈ߑ��͏����Ɉ��̏d�˒��A���̓J���T���ł���B���Ԃ��Y�������B����ɑ����n�`�L�ł́A�F�┫���Ƃ����w���ϕM�L�x�ɂȂ��������o�ꂷ�邪�A����������ڂ����̂́A�w�����`�x�̊����ɁA�u��������̗����𒅂��Ƃ����̂͊ԈႢ���B������]���A����l�͔���̌т𒅂��Ƃ����A�◬�i�Ƃ̎d���j�̎��ɔ�̌т��ꂽ�Ƃ����v�Ƃ����āA��q�b�ł��̗������J���T�����p����ے肵�Ă��邱�Ƃ��ȁB���̑���ɏo�Ă���ꂪ�u�ցv�Ƃ����a��B �a�\�\���̏ւ́A�т��͂��Ă����Ƃ����̂��낤�B�������ւ́A���Ɋ�������X�J�[�g��̂��̂ŁA�т̗ނƂ͌����������̂����A����������p�����Ƃ����킯���B����ŁA�퓬�ɋy�ԂƂ��A�u�ւ������������v�Ƃ����ÓT�I�ȕ\���ɂȂ�B���̏ւƂ�����͉��ł��邪�A�܂��㐢�̌т̃C���[�W�ŏ����Ă���ˁB�������A�ǂ����Ă������Ƃ����~�̈ߑ����g�������Ȃ��悤�Ȃ̂��ȁi�j�B �`�\�\�G�߂�����Ȃ�����˂��i�j�B �a�\�\�悤����ɁA���n�ł��ŏ��́A��������̗���������Ă����Ƃ����b���������̂��낤�B�Ƃ��낪�A���ꂾ�ƋG�߂�����Ȃ��ƂȂ��āA�����ɋy�B����ł������Y�ɂ͔�̗�������������܂܂�����A�G�߂̖�����I�悵�Ă���B �b�\�\����Ƃ��A�����̓J���T���i��̗����j�ł͂Ȃ��ւ��Ƃ����A���n�`���`���̎����ł́A������t�@�b�V�����̎������Ȃ��āA�a���t�@�b�V�����ɉ�₂��ꂽ�Ƃ�������������ˁB�i�j�B �`�\�\�F�ɔ������Ƃ��A�������B �a�\�\���n�`���̃t�@�b�V�����́A�ǂ����A�c�����̃t�@�b�V�����ł͂Ȃ��B�㐢�̂��̂��B �b�\�\��������B������A���n�̓`���Œ��ڂ����̂́A�w�����`�x�ɂ��A�������M�œn�C�̂Ƃ��ȉ��k�킽�Ԃ��܁l�Őg���A�����Ă����Ƃ����L�����ȁB �a�\�\����͖��A�܂���c���j���������Č����u�ؖȈȌ�̎��v�ŁA����͖ȓ����A�������͑~���݂����Ȃ��̂������낤�B�Ƃ���A���炩���~�̃t�@�b�V�����̓`���������ȁB���Ƃ��Ɖ��ւ�����ł́A�\�����~���ޗ��������̋G�߂ŁA�����͖ȓ��������Ԃ��čs�������ƂɂȂ��Ă����̂��A�����������Ɏc�������Ƃ������ƁB �`�\�\����͓��R���肤��ȁB�`�����ψق��Ă��A�G�߂����āA���b�v�f�̈�[���p��ς��Ďc������B �b�\�\�����A�܂��ɂ��ꂪ��_�B�w�����`�x�̖��A�w��V�L�x�ł͂����́u�ȓ��v�ɂ��Ă��܂��āA�Ӗ����ɂȂ��Ă��邪�A�w�����`�x�̖��\�\�܂�̏��~�̈ߑ��̍��Ղ͎c���Ă���B �`�\�\�w��V�L�x�ł͎l���Ƃ������珉�āB�Ȃ̂ɁA�ȓ��Ƃ������~�̃t�@�b�V�����B����͂ǂ����ĂȂƁB �a�\�\�����I�ɕύX�������A����Ő��b�v�f�Ԃɖ������������Ă���B�ނ��A�l���Ȃ�ȓ��łȂ��āA�Ȃʂ��łȂ��Ă͘b�͍���Ȃ��i�j�B����́A�w��V�L�x�i�K�ŏ���ɋG�߂��l���ɂ������A�ȓ��Ƃ������~�̐��b�v�f�́A���̂܂c���Ă��܂����Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\�w�����`�x�ł́A�ȓ��ǂ��납�A��������ˁB�������A����Ƃ��������B���́A����ɐg�̂��₳�ʃE�C���h�u���[�J�[�ɂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A����ΐ_�b�I���삾�ˁB�܂�A�����n���A�V���~�Ղ̍ۂ̐^���P�i�}�h�R�I�t�X�}�j�̌̎��Ƃ͌���ʂ��A����ȃ~�\���W�J���i�_�b�w�I�j�ȃV�[���������ɔ������Ă���B �a�\�\�܌��i�M�v�j�̐��ł́A�ւ��^���P�������Ƃ�������A��������ƁA�w��V�L�x�ɂȂ�ƁA�w�����`�x�̖����A�ȓ��Əւɕ��������A�Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\�悤����ɁA���̃V�[���ł́A�^���P�ɂ���܂ꂽ�����́A���������c���Ƃ��č~�Ղ���_�̔@���A�n�C���Ă���ِl�ł���i�j�B �a�\�\���̂悤�Ȑ_�b��p�́A�������A�A���J�C�b�N�ȌÂ����b�f���B�܂�A���n�`���́A�Ӗ��������炸�A���̖�����Ƃ����V�[�����c�������߂��B�n�C�̍ۂ̃E�C���h�u���[�J�[�Ȃ�A�Ƃ��ɕs�s���͂Ȃ��ƁA�L�҂̌��{�}�����܂ʂ��ꂽ���̂��낤�B�����ŋ��R�A���������_�b�I�v�f���c���Ă��܂����B �b�\�\���낤�ˁB���̏�ʂ��ł���Ƃ������Ƃ́A���b�_�I�ɂ����A�`���̒�^�֓��B���Ă��܂����Ƃ������Ƃ��B�V�����āA�ό`�̒��������n�`���ɂ��A�Â����Ւf�Ђ͎c���Ă���Ƃ������Ƃł�����B �\�\�����ƁA���b�̊ԂɁA�����t�@�b�V���������Ă݂܂����B����������B �`�\�\�����Ȃ���A��̂悢���Ƃł��ȁi�j�B |
 �C���̌i�@�V�[�{���g�w���{�x
*�y�]�C�������z
�s���U�����̑����n�A㌎q�̂��͂����A���͂������ɂ��Ē��A�ڂ̖_�ɋؓS��łĎ��V�A�@����肳���ɓ��ɂ킽��āA��ɂ��������ď@�����܂t �s�����A�@�������̂������A���U�����t�̑O�����͂�ЂāA�͂��܂̂܂֕������G�ɉ�����t *�y�O�����ϕM�L�z �s���V���n�����Y�����T�L�j�n�C�Z���B�R���n�\���m���j�e�A���j�n���������V�A��j�����L�e�A�J���T�������V�A�M�m�D�����l�ڃj���A�n�m���j�B���A�L�}�i�N�ō��A���m���j�m�R���������e���m���A�؏��E�q�吻�g�]�B�t�n�B�������j�n�A��탊��S���m���A�����m���n�烒�R�V�탊�e���e���B�M���m�_�Ӄm��j���|�A���������q�U�m��j���^�w�A�M�m�D�n�E�m���j�A���j�̃e�R���A�T�V�E�c���L�e�����Y���ҋ������t  ��؛����̃|���g�K���l���m
*�y���@��t�`�L�z
�s�����j�����o�A��t�E�m���J�^�N�탊�m�P�A�E�m�n���ȃe�ؓ��m�n�g�V�A���m���������L�l�j�탊�i�V�A�������A�n��ڌܐ��j�n�w�A��m�ؓ��m�����������j���A�����n�A�ꃀ�N�m�����j��j���H��d�m�ߏփj��m�J���T�������V�A�ꏃ�q�m�����߃j��уV�e�召���w�A���M�j�惊�e���j�n�����t 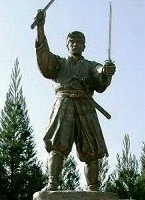 �{�{�������̗��t��
*�y�����`�z
�s������e�ǒ����ɏ\���A�����уj�}�����m��Ѓ��ȃe��d�m�����j�V�A���������m������m���������g�]�n��i���J�B����]�A���l����m�������g�]�A�◬�K���j��m�n�J�}���g�]�X�n�A�M���j�e��������e�F�g�V�A����j�ȉ����P�e�M���j���X�B�i�����j�P���m�ȉ����E�A�Z�������A�փ����N褰�e�������k���l�V�A�ؓ�����Q��f�ǒ��҃��t *�y��V�L�z �s���U�n���m�������e�A��@���уj�n�T�~�A���m��j�ȓ������e�A���D�j��e�o���B�i�����j�D���j�e�������V�e�F���J�P�A�E�m�ȓ������e���X�B�i�����j���m�F��j�D�����e�A���q�^���|�m�ȓ����E�M�A���n�D�j�u�L�Z�������e�փ����N�J�R�Q�A�ޖؓ�����P�A�f���j�e�D���������A�ǒ��R�g���\���A�s�X�уj�n�T����@�j�e��d�m�����X�t  �~�@���@�吳����ˋ{�쑺
*�y�܌��M�v�z
�s�V���~�Ղ̎��A�^���P���ė���ꂽ�Ƃ��邪�A�另�{�����A���`��������ׂ̂��̂ł���Ǝv�ӁB���ł��A�ɐ���_�{�Ɏc�Ă�邩���m��Ȃ����A�ɐ��̑��_�y�ɁA�V�W�̂���̂́A���Ӗ��ł���B�����_���ȍ����A�V�c�Ɋ��S�ɒ����܂ł́A�����ɂ��A�O�C�ɂ��G�ꂳ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�O�C�ɐG���ƁA�_���������ӂƍl�ւĂ�B�̂ɐ^���P�ŁA��g�����݂����̂ł���B�����ĂĂ����ԂɁA��������ꂽ�t �s�^���P�ɕ�܂�ĕ�������ꂽ���́A�V�c�̌�n���ɂ����A���L�^������B�����ŕ��������ɂȂ炸�ɁA�����݂��Ȃ��ꂽ�B���̏K�����Ȃ��ȂČ�A�t�ɂɁT���̖����A�^���P�ɕ�܂āA�����ɍ~��A���n�ŕ����Ȃ��ꂽ�̂��ƍl�ւė����B��X�́A�{��ŁA�^���P��x�X���g�ЂɂȂ�̂ŁA�V�ォ�玝�č~��ꂽ���̂Ǝv�ӂ��A���́A�t�ɍl�֒��������A�������̂ł���t �s���Ƃ��ӌ�́A���������́A�������̏��[�����̗p��ւƎv�͂�Ă�邪�A�ق�Ƃ��͕R�̂Ȃ��A���C�~�̗l�ȁA�傫�ȕz�ŁA�^���P�Ə̂������̂��̂ł���B�����Ă�Ƃ��ӂ��Ƃ́A�ɔ����鎖�ŁA���Ԃ̂��̂��݂́A���ɍL���A�����d�ɍs�͂ꂽ���̂ŁA���̂����Ђƌ����Ă��B��ɂ́A������z����A���r�̈Ӗ��ɍl�ւė����t�i�Ñ�l�̎v�l�̊�b�j |
| �@ | �]�C������ | ���ϕM�L | ���@��t�`�L | �����` | ��V�L |
| �G�@�� | �i�L�ڂȂ��j | �\���@���~ | �i�L�ڂȂ��j | �i�L�ڂȂ��j | �l���@���� |
| ��� |
���ꂪ�� ㌎q�̃W�o�� | ���ɏ����A��Ɉ� |
��ނ��̉��� ���H��d�̈ߏ� ���j�q�̓����� | ���@�� | ���̈� |
| �с^�� | ���@�t | �J���T�� | ��̃J���T�� | �� | �� |
| ���@�� | �\�\ | �\�\ | �\�\ | �F�Ɣ��� | �F�Ɣ��� |
| �P�@�� | �\�\ | �\�\ | �\�\ | �ȁ@�� | �ȁ@�� |
| �����Y�ߑ� |
�����i�����j�̉��� ���ۂ̋�i�Z�j | �J���T�� | �i�L�q�Ȃ��j |
�́X�ꑳ���H�D ���@�� ���@�� |
�́X�ꑳ���H�D ���v���� �����W |
|
�b�\�\�ł́A�����̈ߑ��ɂ��Ă͂��ꂭ�炢�ɂ��āA�����ΐ푊��̃t�@�b�V�����ւ��������B �a�\�\�}�O�n�̓`���ł́A�����̑���̃t�@�b�V�����́A�w�]�C�������x���Ɓu�����̉��ɓ��ۂ̋�v�ƁA���炭�ÓT�I���ȁi�j�B�u�����v�k�͂��Ƃ��l�Ƃ����͓̂����ŁA������X������H�D�Ɏ������́B�u�\���v�Ƃ����̂����邪�A����͖��m�ł͂Ȃ��B����͖@�������҂̑m�̗̂����ŁA�ނ����t�⒃�l���Ƃ������B �b�\�\����́A�w�]�C�������x�ł́A���O���u��c�@���v���Ƃ����̂ƌĉ����Ă���ȁB �`�\�\�w�]�C�������x�ɂ́w����^�x�̗��Ԏ��R������ł��邵�A�܂�����b��ɏo���悤�ɏ�c�@�ӂ̘b�����邩�猾���̂ł͂Ȃ����A���O���u�@���v�ŁA�����𒅂Ă���ƂȂ�ƁA�����̑���͒��l�ł͂Ȃ����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ȁi�j�B �b�\�\����A����͂��Ȃ����قȘb�ł͂Ȃ��A�ޗ��́A�u�@���v�Ƃ������������A�|�p�I���w�̐[������҂ł��������������B��X���u�@���v�Ƃ������ɒ��ڂ���䂦�B �`�\�\���̂�����́A�]���̕��������ł́A���ɂ��ꂽ���Ƃ���Ȃ������i�j�B �b�\�\����䂦�A��X�̌����ɂ���āA�ʂ́A�I���^�i�e�B���Ȋޗ������\�ɂȂ����B���̐��ŁA����Ɏj�����o��悢���ˁB�Ƃɂ����w�]�C�������x�̓`�����A�u�@���v�Ƃ��������Ɣ����Ƃ����ߑ����A�����̑���ɒ����Ă��邱�Ƃ́A����̕����`�������ɂ����Ė����ł��Ȃ��|�C���g���낤�B �a�\�\���̃T�C�g�ł́A�m�������p�сn�Łu�A�[�e�B�X�g�����v�Ƃ����^�C�g�������Ă���̂����i�j�A�����ЂƂA�u�A�[�e�B�X�g�ޗ��v�Ƃ����̍����K�v���������ȁB�Ƃ���ŁA�ߑ��̘b�̑��������A�����̉��ɒ��p���Ă����k�������l�́A�悤����ɊZ���B�u���ۂ̋�v�Ƃ�������ɂ́A����͒��Ԃ̂Ȃ��ۓ����ˁB����͐퓬�p�̕������B���͕����Ɠ����A���t���낤���B �`�\�\�����̉��ɊZ���݂���Ƃ����̂��A�Ȃ��Ȃ������̑���A�C���[�W�͑N���ł��ȁB �a�\�\�����̕��͓�t�@�b�V�����A�@���͏a���a���t�@�b�V�����i�j�B���̑ΏƐ��́A�������\���̎�N�A�����ď@�������ԂN�Ƃ����N��ݒ�̑��Ⴞ�ȁB �b�\�\���낤�ȁB�u�����͎�N�A�ޗ������N�v�Ƃ����ΏƓI�ȍ\�}���ˁB�����āA���ꂪ�ޗ����������̃t�@�b�V�����́A�ł������̋L�q���e���Ƃ����Ƃ�����ʼn߂��Ă͂�����B �a�\�\�����ŁA�F�ՕM�̊ޗ��������̊G�i�{�{���O�l���X�؊ݖ��d���V���j�ł����Ă������B��Ѝ։̐�F�Ղ͖������疾���ɂ����Ẳ�Ƃ�����A�ߑ㏉���̊ޗ������������m���B |
*�y�]�C�������z
�s�@���n�A�����̉��ɓ��ۂ̋�𒅁A�O�ڈꐡ�̐]�̓��������A�ؓ�����Ɏ��A���M�ɏ�A�����킽��t  ���x���m��  �{�{���O�l���X�؊ݖ��d���V�� ��Ѝ։̐�F�ՕM |
 �{�{���O�l |
 ���X�؊ݖ� |
|
�a�\�\���҂̈ߑ��ɒ��ڂ���A����������������C���[�W����Ă��邩��A�ނ��c�����̃t�@�b�V�����ł͂Ȃ����A���O�l�E�ݖ��Ƃ��ɂȂ��Ȃ��Â����ӏ��̈ߑ����ȁB �b�\�\�����Ƃ�����q�𒅍���ŁA�����ɉH�D�B�H�D�����ʂ��ɂ��č��ɂ܂Ƃ킷�B���O�l�͗������ȁA���X�؊ݖ��͌т��ˁB�������{�{���O�l�͎Ⴍ�ăn���T���A���ʂ̔��j�A����ɍ��X�؊ݖ��͒��N�̂��������������i�j�B �a�\�\���ꂪ�w�]�C�������x�́A�����̏��ꂪ����㌎q�̃W�o���Ƃ��A�@���̔����̉��ɓ��ۂ̋�Ƃ������̂Ƃ͈Ⴄ�̂͌����܂ł��Ȃ��B�����A�w�]�C�������x�̃t�@�b�V�����̕�����قǖʔ����B �`�\�\�����̑�����������N�j�ɂ��āA����ȏa���t�@�b�V�����𒅗p�������A�ޗ��������̉f������������̂����i�j�B��������A�\���̕����ɓ�t�@�b�V������h��ɒ����āA�ޗ��ɓ��ۂ̋�ɔ����Ƃ����ߑ��𒅂��������A���ꂩ�ޗ����Ƀu�b���Ă��i�j�B �a�\�\�łȂ��ƁA���B���̓`�����������i�j�B���������A�ޗ����̂��钷�B���ւ̘A�����A��B���n�̂��₵���`���Ɉˋ��������������Y�������Ă��Ƃ����̂��A�ԈႢ�����B �b�\�\�������A���ꂪ�����I�O�̐̂̂��Ƃł͂Ȃ��A���ŋ߂̂��Ƃ��i�j�B�Ƃ���ŁA�w���ϕM�L�x�ł́A�����Y�ɂ̓J���T���ȊO�ɋL�q�͂Ȃ����A�Ƃ��ɕʂ̋L�q���Ȃ��Ƃ�����݂�A����͕����Ɠ����悤�ɁA�����Ɉ��̏d�˒��A���̓J���T���Ƃ����t�@�b�V�������낤�ˁB �a�\�\�����̈ߑ��ɂ��ẮA�}�O�n�Ɣ��n�̓`�L�̍��ق͑ΏƓI���������A�����Y�̈ߑ��ƂȂ�ƁA���̑ΏƂԂ�͂����Ƌɒ[���ȁB�w���ϕM�L�x�́A�����Y�̈ߑ��ɂ��ăJ���T�����p�����L���Ȃ����A�w���@��t�`�L�x�ɂȂ�ƁA�����Y�̈ߑ��Ȃǖ������ĉ��������Ȃ��i�j�B�Ƃ��낪�A���n�`�L�ł́A�����Y�̈ߑ��́A�́X�ꑳ���H�D�A�i����j�����A���܂Ƃ����āA�L�q�͋�̉�����B �`�\�\�������A���n�`�L���ƁA�����̃t�@�b�V�����͒n���ŁA�����Y���h��ł��ȁB �a�\�\���Ƃ��Ɗ��ݒ肪���Ȃ肿��������ˁB�����Y�̈ߑ��́A�a�l�̌���D�ŗ����Ƃ����ݒ�ɍ��킹�āA�����S�[�W���X�ɂ����̂�������Ȃ��B�����Y�̑����H�D�Ƃ����̂́A�}�O�n�`���ɂ͂Ȃ��L�������A�����H�D�Ƃ͂���ɑ����Ȃ��H�D�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��w�ŋ�̏�ɒ��p���������ŁA���ł̃t�@�b�V�����B��H�D�Ƃ��������A�����ނˑ������������̂ő����H�D�Ƃ����킯���B �`�\�\�}�O�n�́w�]�C�������x�̂��������ɑΉ�����̂��A���̑����H�D�ł��ȁB���n�`���ł́A����p�̋L���͂Ȃ����A�r���ŏ������̂��������i�j�B �b�\�\�����̓�t�@�b�V�������������悤�ɂˁB���������b�ɏo���悤�ɁA�����}�O�n�ł��A��́w���@��t�`�L�x���ƁA�����̈ߑ�����ނ��̉����A��ɍ��H��d�̈ߏցA���j�q�̓����߂ɏ�т��āA�Ƃ����A��F�Â��߂̃h�h��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��ȁi�j�B�������Șb�́w���ϕM�L�x�̒i�K�ɂ͂Ȃ��B �`�\�\�w���@��t�`�L�x�͔��n�`���̉e�����Ă���B�����Y���́X��̉H�D�ɑR���āA����Ȕh��ȃt�@�b�V�����ɂ����̂��ȁB �b�\�\��������肻�������A�t�ɌÌ^�Ƃ������Ƃ����肤��ˁB�������A���n�w�����`�x�̋L�q�Ŗ��Ȃ̂́A�����Y�̂����́X��̉H�D���A�s���]�A���F�������q�̖�g�t�Ƃ������L�������Ă��邱�Ƃ��ˁB �a�\�\����͑�����B���̍א엧�F�i1615�`1645�j�́A�O�ւ��\���߂��Đ������q�ŁA�Ƃ��Ɉ��������q�������B�������A���n�`���̌�邲�Ƃ��ޗ����������A����Ɍc���\���N�i1612�j�̏o�����������Ƃ��Ă��A�ނ͂܂����܂ꂿ�Ⴈ���i�j�B���܂�Ă��Ȃ��҂���A�ǂ����ĉH�D��q�̂���B �b�\�\������`���ł��A�b�̓��`�����i�j�B��́w��V�L�x�͂�������{���āA�������Ă���B�ƁA�v������A����k�ɂ͂�͂�A�u�������A�������A�א쒆����㗧�F�����A�◬�������������܂��v�Əo�Ă���B�w��V�L�x�̌��{�͕s�\���Ȃi�j�B����������́A���n�`���������ɐ������Ă������Ƃ������؋����ȁB �`�\�\���̑����H�D�̐F���A�́X���k���傤���傤�Ёl�ł���Ƃ����̂́A�����Ԃ�h��Ȃ悤�����B �b�\�\�́X��͐F�̖������A�́X��̐w�H�D�ƂȂ�ƁA����͂�������Ń|�s�����[�Ȃ��̂��B�́X��̐w�H�D�Ƃ����Ƒf�ނ܂Ŋ܈ӂ���Ă���B�܂�A�嗅�т̔�F�̐w�H�D���ˁB�f�ނ͗��т��낤�ˁB �`�\�\���̗��т͖ѐD���ŁA������|���g�K����iraxa�j�ł��ȁB �a�\�\�������A�����́X��ɂ͔\�u�́X�v�ւ̎Q�Ƃ�����A�����ł��́X�͐Ԃ����߂̑����ł��邪�A�́X�̊�͎��ɐ����ĐԂ��Ƃ����܈ӂ�����A����ɁA�́X��߂炦�Ă��̌�������Đ��߂��F���́X��ƌĂԂƂ̓`���̔���������B������A�����œo�ꂷ���́X��Ƃ����F�ɂ́A�P�ɔh�肾�Ƃ����ȏ�ɁA�����܂����s�g�ȉ���������B����Ώ����Y�̈ߑ��́A�����̑O�ɂ��łɌ��̐F���i�j�B �b�\�\����Ƃ�����́A����ɐԂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�Њd�I�ȐF���ˁB���܂������Ő^���Ԃɐ��߂Ă��A�Ƃ����F���ˁB����ɁA���b�_�I�L���Ƃ��ẮA�a�l�א�O�ւ��o�b�N�ɂ��������Y�̗D�ʗD������������F���B �`�\�\����ƁA�����Y����N������h��ȃt�@�b�V�����A�Ƃ����킯�ł��Ȃ��B �b�\�\�́X��Ƃ����F���̂��̂ɂ́A��N�Ƃ����R�m�e�[�V�����͂Ȃ��B�w�����`�x���́X��̑����H�D���o�Ă����`���i�K�ł����A�܂������Y�͎�N�ł͂Ȃ��B �a�\�\�悤����ɁA�ޗ����ɗ����Ă��鏬���Y���i��Z�Z��N�ݒu�j�́A�{���̓`���̎p�ł͂Ȃ��B���a�ɂȂ��ė��z�����u�g�앐���v����́u���㏬���Y�v�ŝs�����ꂽ�C���[�W���B�������A�����Y�\���ΐ��́w��V�L�x�ɏ����Ă���ȂǂƂ����Ԉ�����b������B����͖{���ɂ͂Ȃ��L���ŁA�킸���ɒ��L�ɋL�����ꂽ�ِ����Ƃ������Ƃ���Y����Ă���B �b�\�\�������A�M���Ŏ����N�̃I�b�T�������E�ޗ����A�܂�������������Ȕ����N�ɂȂ�Ƃ��A���ɂ��v��Ȃ��������낤��i�j�B �`�\�\���ܑ��݂��鏬���Y���́A�ǂ��������O���̏��N�p�B���ꂾ�������Ă���ƁA��������グ���i�j�B |
 �ޗ����̕��������Y�� 2002�`03�N�@�ݒu
*�y�O�����ϕM�L�z
�s�����Y�n���M�j���A�Ɨ���l�A�����l�j�e���n���B�R�����J���T�������V�A�d�����m�ؓ�����j�c�L�e���e���t *�y�����`�z �s�����Y�n�́X��m�����H�D�m���]�A���F�������q�̖�g�n�j���������A���������t *�y��V�L�z �s�����Y�n�́X��m���i�V�H�D�j�A���v�m���������V�A�����W�����~�t *�y���@��t�`�L�z �s�����j�����o�A��t�E�m���J�^�N�탊�m�P�A�E�m�n���ȃe�ؓ��m�n�g�V�A���m���������L�l�j�탊�i�V�A�������A�n��ڌܐ��j�n�w�A��m�ؓ��m�����������j���A�����n�A�ꃀ�N�m�����j��j���H��d�m�ߏփj��m�J���T�������V�A�ꏃ�q�m�����߃j��уV�e�召���w�A���M�j�惊�e���j�n�����t *�y��V�L�z �s�������m���A��䏬�q�j����������j���V�X�ӃV�����i���j�A�����d�D�X���R�g�m���J�i�����A��e�������A�������A�א쒆����㗧�F�����A�◬�����N���V���t�A�������O�i�N���o�L���x�J���Y�B�Ǝm�m���j�����L�e�A���~���܃~�w�g���x�V�g�A�������L�e���e�s�߁t �� �́X��  �\�@�́X |
 �ޗ��� �R�������֎s |
 �g������ �R�����⍑�s |
 ���J�����Y�̗� ���䌧����s |
 ���P�������Y���� ���䌧�z�O�s |
|
*�y���q�蕶�z
�sূɕ��p�̒B�l�L��A���͊◬�B�ނƎ��Y�����������ށB�◬�]���A�������ȂĎ��Y�������𐿂ӂƁB�������ւĉ]���A���͔��n�����Ђđ��̖���s�����A��͖،���č��̔�����͂����ƁB������������ԁB����ƖL�O�̍ہA�C���ɓ��L��B�M���ƈ��ӁB�_�Y�A�����ɑ������B�◬�A�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂���A�����ڂ݂��p��s�����B���U�A�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���A�P�x���B�̂ɑ��A�M�������߂Ċ◬���ƈ��Ӂt *�y�]�C�������z �s���U�����̑����n�A㌎q�̂��͂���A���͂������ɂ��Ē��A�ڂ̖_�ɋؓS��łĎ��V�A�@����肳���ɓ��ɂ킽��āA��ɂ��������ď@�����܂t *�y�O�����ϕM�L�z �s���V���n�����Y�����T�L�j�n�C�Z���B�R���n�\���m���j�e�A���j�n���������V�A��j�����L�e�A�J���T�������V�A�M�m�D�����l�ڃj���A�n�m���j�B���A�L�}�i�N�ō��A���m���j�m�R���������e���m���A�؏��E�q�吻�g�]�B�t�n�B�������j�n�A��탊��S���m���A���m���n�烒�R�V�탊�e���e���B�M���m�_�Ӄm��j���|�A���������q�U�m��j���^�w�A�M�m�D�n�E�m���j�A���j�̃e�R���A�T�V�E�c���L�e�����Y���ҋ������t *�y�����`�z �s�d�c�_�V���n�O�������ܐl�}����\�ܐΎ����A�ߎ�m�t�i���B���k���l����Ō��e���x��j���i�����A����j�i���x�V�g�e�����P���h���A�_�V������ؓ��ŏo���J�i���Y�B�ߎ胂�A�������V�^���E��ԃ������j�A���������^���o�����m���^���x�V�g�A���P���o�A�_�V����j�{�e�ƃ��i�Z�h���A��ԃ������j�ꐡ�������i���Y�B�_�V���A���r���̃V�e�A�����m���g�i�����B�ߎ胂���i���V�̃j�A�����m��q�j�����k�K�l�n�Z�����V�g��B�������n�m�j�������q�m���A�D�a���A��A�������q�n���i���́A���n�������������V�g��B��V�ꗬ�j�ߎ�_�i�h�݃g�]�n�A�d�c�_�V���K�P���i���t *�y���@��t�`�L�z �s�����j�����o�A��t�E�m���J�^�N�탊�m�P�A�E�m�n���ȃe�ؓ��m�n�g�V�A���m���������L�l�j�탊�i�V�A�������A�n��ڌܐ��j�n�w�A��m�ؓ��m�����������j���t *�y�����`�z �s�����Q�N�N�e���у���A���Y���q��j��e�A����ȃe�ؓ����탊�o�t *�y��V�L�z �s����j���e�A�D���ȃe�ؓ�����L�j�탋�t
*�y�{�����Y���B�z
�s���l�̐��ɁA�����ޗ��Ǝd����ďM���ɕ������A���������̂����D�l�Ɍ�Ђ��A�e�w���Ď��ׂ������ق��߁A�D��肠����Đ����Ȃď������Ȃ��B�ޗ����������قƖ��t�����O�ڗ]�̑品���Ȃď�����������Ɓt *�y��������L�z �s�ݗ��g�]���p�ҁA���փj�҃e�A���U�j�V�A�q���Z���g�]���X�B���U�S���k�g�e�A���Y�j�D�����e�A��c�j�����A��{����e���L����ڌܐ��A�Z����ڔ����j�V�e�A�M�����ナ�A�ݗ��g�����t�B�ݗ��K���n�O���P���i���t  ��F�D�f�ޖ͑��،��@�S��4��2�� ���F�����n�͑������@�S��3��5��  䂂ő���  �D�ő��� |
�b�\�\�ł́A���ł�����A����̕������Ă��������B�ޗ��������Ŏg��ꂽ����̘b���B �`�\�\�����L���ɂȂ��Ă���Ƃ���ł́A�����͂��̌����̂Ƃ��A�M�̟D����������̂�ؓ��ɂ��Đ�����Ƃ����b�ł��ȁB���ꂪ�ޗ����e�`���ł͎��ۂɂ͂ǂ�Șb�ɂȂ��Ă��邩�B �a�\�\�������ˁA�܂��ł��������q�蕶�̋L���ɂ��A�◬���u�^���Ŏ��Y�������悤�ł͂Ȃ����v�Ɖ]���B����ɑ������́A�u���͔��n�i�^���j���g���Ă���A����͖،��i�ؓ��j���g������v�Ɠ������B���l�͌��������̌_������B�����ďM���ŗ��Y����A�◬�͎O�ڂ̔����A�����ڂ݂��p��s�������B�����������͖،��̈ꌂ�Ŕނ��E�����B���̑������ƁA�d���������x���قǂł������B�\�\�Ƃ����b�݂̂��B�����ɂ́A�����͖،����g�����Ƃ������L����Ă��邾���B �`�\�\�܂�A�M�̟D��䂂Ŗؓ���������Ƃ������b�f�́A���q�蕶�ł͂܂��o�����Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă������B �a�\�\���ɁA�}�O�n�̓`�����L���w�]�C�������x�̋L�����ʔ����B����ɂ��A�ڂ̖_�ɋ؋���łāA�Ƃ����L��������B����͙��̕�����S�ŕ⋭�������́A�Ƃ��������A�K�l�Ƃ�������S�ŕ⋭�����_�ŁA�S�B�_�k���Ȃ����ڂ��l�̘��킾�낤�B �b�\�\�S�ɓS�_���i�j�B����ƁA����͖_�p�̕���ŁA�ނ���Ƃ͈Ⴄ���ؓ��Ƃ��Ⴄ�B���q�蕶�̂����u�،��v���ǂ��������̂��w���Ă��邩�A�悭�l����K�v������B �`�\�\���q�蕶�́u�،��v�Ƃ��������ɒ��ڂ��čl�@������́A�]����������Ȃ����A����͒P�ɖؓ��ł͂Ȃ��A�_��p�̂悤�ɒ�������Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł��ȁB�������ږ_�ƂȂ�ƁA�܂����������̃C���[�W�Ƃ͈Ⴄ���i�j�B �b�\�\�����͌��p�݂̂ɂ��炸�i�j�B�u���v�ƂȂ�ƁA����͒������퓹��Ƃ����C���[�W���B�����͖_����g������������Ȃ��B�}�O�̓�V���ł́A�����p��̓㓁�Ƃ������̂��`������炵�����A���������w���ϕM�L�x�ŁA���������p����̂́A�ؓ��ł͂Ȃ��ڏ��i�j�B����������������g�p���Ȃ������Ƃ͉]���܂��B �`�\�\�����̒�q�ɁA�������_�ߎ�p�̉��c���ցi�l�V���j�Ƃ����҂�����B�����̗��V�ɖ_�p�����������Ƃ͔��n�`�L�̉]���ʂ�B �a�\�\�����Ǝd�����ĕ����Ē�q�ɂȂ����Ƃ������c���ւ́A�������A�c�����N�Ɏ��\�]�şf�Ƃ�������A�������������͔N���B�Ƃ���ƁA����͂܂��ɍ���ғ��m�̘V�l�ΐ킾�ȁi�j�B���c�����ł͂��߂ĕ����̒�q�ɂȂ����悤�ɔ��n�`�L�͏����Ă��邪�A�}�O�n�́w���ϕM�L�x�̏������Ղ�ł́A���c�u�l�V��v�͔��ȑO����̒�q�̂悤���B���̂�����A�`���͕������Ă���B �b�\�\���������n�`�L�́A���̖_�p�����c�l�V���ɋA���Ă��邪�A����͖_��p����������Ȃ����Ƃ��������Ă��邾�����B�Ƃ��낪�A�w�ܗ֏��x�̋L�q�ɂ���ʂ�A�����͗B����`����Ȃ�����A�ނ���_�p�E��p�̂悤�ɒ��߂̓�����p�������Ƃ͑z�肵�Ă悢�B �`�\�\�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�������ڏ���g�����b���ĎO�o�Ă��܂��ȁB �a�\�\������A�w�]�C�������x�̂����S�،ږ_�����Ȃ����ے�ł��Ȃ��킯���B���ꂩ��A�����}�O�n�́w���ϕM�L�x�́A���Ȃ��̓I�ɕ����̓�����L���Ă���B�܂�A�M�̟D���l�ڂɐ��č�������̂ŁA���ꂾ���ł͂Ȃ��A�n�̕��ɓB�����ԂȂ���������ł����݁A����̏��Ɂi���藯�߂Ɂj���ڂ���ꂽ���̂��Ƃ�������A����͋��\�ȓ�����i�j�B������́A�������ŁA����͔�̂����܂܂̎育��̖́A����̏������������������̂ł���B�܂�A�w���ϕM�L�x�ł́A�����͑召��̓����p�ӂ����Ƃ����b���ȁB �`�\�\����́w���@��t�`�L�x�ł��قړ����ł����ȁB�������A�B�����ԂȂ��т�����ł����Ƃ����b�͂Ȃ����i�j�B �b�\�\���n�`�L�ł́A�����̓���͖ؓ����Ƃ��邪�A������M��䂂܂��͟D�ō�����Ƃ���_�������B�����͂ǂ���A���q�蕶�̋L�����甭�W��������ނ��B �a�\�\�ǂ���A�������^�����g�����Ƃ����b�͂Ȃ�����A����͏��q�蕶�̊�{���͓��P����Ă���Ƃ������Ƃ��B���q�蕶�ł́A�u�◬�͐^���^�����͖،��v�Ƃ����ΏƐ�����������Ă��邾���B����ƁA�����͂����g�����ꂽ�،����g�����\�����傫�����A�ǂ̂����肩��A�M�̟D���ޗ��ɂ���Ƃ����b�ɂȂ������B����́A�w�]�C�������x�Ɓw���ϕM�L�x�̒��Ԃ��B �b�\�\������Ƒ҂����i�j�B���̂�����������������͂��Ă݂����B�w���ϕM�L�x�ɂ͂������Ɂs�M�m�D�����l�ڃj���t�Ƃ��邪�A����ɓB�����ԂȂ���������ł�����œS�B�_�݂����ɂ������̂�����A����ɟD�����o�������̂ł͂Ȃ��B����ɁA�������Ɏ育��Ȕ�t���̖�p�����Ƃ��邩��A������́A�D�ł͂Ȃ��B�������A�����Ɂs���A�؏��E�q�吻�g�]�B�t�t�Ƃ��L���B �a�\�\�ӂށB��q�̐؏��E�q�吻��Ȃ�A����͊ޗ��������̂Ƃ��ɍ�����Ƃ��������A�O�X���畐�������������Ă����،����A�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�ȁB �`�\�\�w���ϕM�L�x�ł́A�S�B�_�݂����Ȃ��̂�����A�ޗ��̏M�̟D�Ƃ������Ƃɂ܂��d�_�͂�����Ă��Ȃ��Ƃ������ƁB �b�\�\�������ˁB����Ɓw���Y���B�x���ȁA��̓I�ɂ��ꂪ�o��̂́B �a�\�\�قړ������́w��������L�x�ɂ����l�̋L�������邪�A�w���Y���B�x�ł́A�u����l�̐��v�Ƃ��āA�M���ɏM�œn�鎞�A�����͞��̐܂��D�l����Ⴂ�āA�e�����Ď��ׂ���������čׂ߁A������g���Đ�����Ƃ����B����ƁA�����ɗ�́A�u�ޗ��́A�����ƂƖ��t�����O�ڗ]�̑品��p���āA�����������v�Ƃ����b���o�Ă���B �`�\�\��������ƁA���n�`�L�w�����`�x�w��V�L�x�́A���ɂ��w���Y���B�x���Q�Ƃ��Ă��邩��A���̂�����́w���Y���B�x����d���b�Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��ȁB �a�\�\���̉\���͍����B�w�����`�x�́A�u���Y���q��Ɍ�āA䂂��Ȃ��Ėؓ������o���v�ƁA��������ւ̖≮�E���ё��Y���q��̉Ƃł̘b�Ƃ��Ă���B��������邩����ł́A������S�N�A�����c���Ĕ���ɂ���Ă��������̏M�l�A���q�̏��l�E���������Y���畷�����悤�Șb�ɂȂ��Ă��邪�B �b�\�\��㔪��֓`���������炵�����������Y�Ƃ����}�́A���f�B�A�̃|�W�V�����͂��Ƃ��Ɯ~�����̂���i�j�B���Y���q��ɏM�̟D���邢��䂂�������Ėؓ���������Ƃ����̂́A�����ɂ����֎Y�̂悤�����A���͔��Ő����������b�f���낤�B���̃\�[�X�́w���Y���B�x���낤�B �a�\�\�w��V�L�x�́w�����`�x�����낢���₂��Ă��邪�A�����ł��A�w�����`�x�Ɂu䂁v�Ƃ���̂��A�u�D�v�ɕς��Ă���B �`�\�\䂂ƟD�Ƃł͑�Ⴂ�i�j�B�����A�w���Y���B�x�̂����u���v�Ƃ����̂́H �a�\�\����́A�����Ƃ݂����Ȓ|�̊Ƃł͂Ȃ��A�D�̂��Ƃ��B�Ƃ�����A��������䂂ƟD�Ƃł͑�Ⴂ���B �b�\�\���̂悤�ɒ��ڗv�f�Ƃ��Ă̓�����킪�����Ƃ����̂́A�܂������r��ɂ���V�����`�����Ƃ������Ƃ��ˁB���Y���q�傩��Ⴂ���Ƃ����b�́A���͔��Y�̓`�����낤�Ƃ����̂́A����ȂƂ��납����m���B �a�\�\�������A�w���Y���B�x�̂����u����l�v�́A�M�̞���̑f�ނɂ��Ă��邪�A����͂ǂ��ɗR������B���̂����A�M�����n�C���M�����A�Ƃ����悤�ɃA�\�V�G�[�V�����i�A�z�j�͐i�ށB�u�M�����v�́u�M��䂁v�ł����������u�M���D�v�ł��悢�B��������͜��ӓI���ȁB �b�\�\�������A���������̍ŏ��ɁA���q�蕶�́u�،��v���u�؞��v�Ɠǂ݈Ⴆ�Ă��܂����\��������B���������P���ȉߌ낪�`���̔��[�ɂȂ������������B���ꂪ�A���_�B������́A���������u���v�̃C���[�W���ێ�����M�̉B�g�n��̑��݂��ˁB����͏M�ɊW������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���V����V�j�t�B�A���̌q���_�B�����ŁA�������ޗ���|�����ؓ����A�D���邢��䂂ō�������̂��Ƃ������b�f�̗R���́A�܂��ɂ��̓`���̏ꏊ�A�܂��C�ݕ��Ƃ����n�搫�f���Ă���悤���B �a�\�\����Ɋ֘A���Č����A�D���퓬�̕���Ƃ��Ďg�p���ꂽ�Ƃ����`��������i�j�B����k�����l�W�c�̐퓬�ɂ́A�ނ炪������ɂ��Ă���D������ɂȂ�B����́A���������Ȃǐ��Y�p��_���̕���ƂȂ����Ƃ��������Ɠ������Ƃ��ˁB �`�\�\����L�ł͖��������A�|���Ƃ����������ȁi�j�B�����ޗ����łȂ��āA�R����������A�܂��ʂ̑f�ނɂȂ������낤�B �b�\�\�������ޗ���|�����،����A���b�_�I���x���ŗ��ʂ���ɂ́A���ꂪ���_�������Ƃ����������s�����ȁB�����A�����ɂ͒n�搶���Ɖ��̐[������Ƃ̊֘A�����D�荞�܂��B���̂悤�ɕ��_�����ꂽ�،����A����ɖؐ��ł͂Ȃ��A���̑f�ނ��n��ɉ��̐[�����i�ł���˂Ȃ�ʂ̂́A���b�_�I���x���ł̍�p���B |
|
�`�\�\�ޗ����́u�M���v�B���݂͂����Ԃ�p���ς��Ă��܂��Ă��邪�A���Ƃ͏M�݂����Ȍ`�̓��������̂��ˁB�����Ȍ�A���Ȃ薄�����ĕό`���Ă��܂����B �a�\�\�������ɂ͓��̖ʐς́A�ܐ���炢�B���͂ǂ����ˁA�O���͂��邾�낤�B��؏��X���M�����āA�����̌������擾���āA���D��������Ƃ��A���ꂱ��M����������A���Ǒ�p��s�œ|�Y���i�j�B���Ƃ͎O�H����������B���{���{��`�u�����̏����Ȃ�A���܂̊ޗ����́B �b�\�\�M�݂����Ȍ`�̓��ŁA�M���B�b�����ǂ��A�����}�O�n�ł��w�]�C�������x�Ɓw�O�����ϕM�L�x�̓���L���ɂ͏d�v�ȍ��ق������āA����́A�O�҂̓���܂������C�ݕ��Ƃ����n�搫�f���Ă��Ȃ����Ƃ��B�w�]�C�������x�́u�C�H�L�v�ł�����B�Ƃ��ɊC�Ɋւ�镶���ł���B�C�ɉ��̐[���w�]�C�������x�̋L���ɂ����āA�����̓���M�̘A�z�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�d�v�ȃ|�C���g���ȁB �`�\�\�Ƃ���A���̓_���ǂ��݂邩�ł��ȁB �a�\�\�����͖�������i�j�B�����̓���́A���Ƃ��ƏM�̞���䂂�D���ޗ��ɂ������̂ł͂Ȃ������B����́A��������p���Ă����،��������B����������́A�B��ł����ĕ���Ƃ��ĕ⋭���ꂽ�B�_�̂悤�Ȃ��̂������B�����̓���́A�w���Y���B�x���邢�͔��n�`���̂����悤�ȁA����̓���A�D�܂���䂂Ƃ͉��̊W���Ȃ������B����́A��ɓ`���W�J�̉ߒ��Ŕ����������b�f�ł���B���_�������A�����������Ƃ��ˁB �`�\�\䂂ƟD�Ƃǂ��炪���������A�ȂǂƂ����c�_���Ȃ��ꂽ���Ƃ����邪�A����ȋc�_�͑O����Ă��邩�疳���ł���i�j�B �b�\�\������������M�̟D�i䂁j�Ŗؓ���������Ƃ������b�f�́A�`���Ƃ��Ă͂������낢�B�����B���X�g���[�X���ɂ����A�u���R���[�W���̐_�b���ȁB�w�]�C�������x�̋L���ɂ͂Ȃ�����A�����炭�\�����I�O���ɊC�ݕ����ԓ`���Ƃ��ďo���������̂ŁA������`�L����荞�悤���B �a�\�\�w���ϕM�L�x�����ւ�����̓`�����E�����Ƃ��A������������M�̟D�Ŗؓ���������Ƃ�������Șb�͂����o���Ă����B�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x�̓u���R���[�W���_�b�̈Ӗ��������ӎ����Ă��Ȃ��B��������A����̋�̓I�L�q�ɋC���s���Ă���B �`�\�\�����悤�ɟD��f�ނɂ��č�����Ə����Ȃ���A������̔c���̎d�����Ⴄ�ˁB �b�\�\�w�]�C�������x���ƁA�����̓���́s�ڂ̖_�ɋ؋������āt�A�܂�S�ؕ⋭�̌ڂ̖_�B����ɁA�w���ϕM�L�x�̘b���Ă݂�ƁA�����̓���́A��͂肽���̖ؓ��ł͂Ȃ��A�n�̕��ɓB�����ԂȂ��ł������̂Ƃ�������A����͂��Ȃ若�\�ȕ��킾�ȁB�B�����ԂȂ����ɑł����߂�ƂȂ�ƁA���̖،��͂��Ȃ葾�����̂��B �a�\�\���߂ĉ]���A�܂�A����͂�����S�B�_�̈��B�����ɂ悭����������B������A�܂�A��E���E�F��E�ƁE���E���B�_�E��̎���̕���̓��Ɋ܂܂��B���Ȃ�d�����O�͂̂���҂Ȃ�g���铹��ˁB����ƁA������A�����͏��������p�ӂ��Ă����Ƃ����_�����Ƃ͈قȂ�B���̒}�O�n�́w���ϕM�L�x�ł́A�����͖ؓ��ł����A�召���̓���Ă��ȁB �`�\�\�����A���̔�t���������ɂ͎}�������Ă����肷�邩�����ꂵ�Ȃ��i�j�B�����Ȃ�Ƃ��ꂪ�\��ł���B �b�\�\�ޗ��������̂Ƃ��Ɏg�����̂Ɠ����`�̖ؓ��Ƃ����̂��A�ǂ����Ɂi����E���䕶�Ɂj�`����Ă��邪�A����͂����̖ؓ����i�j�B����A�}�O�n�`���ɂ���B�_�̃A���J�C�b�N�Ȗ��͎͂����Ă���B �a�\�\����ŁA�w���ϕM�L�x�ɂ��A�����͏����Y�̓�����҂��Ă���B�l�ӂ̊�ɍ��|���A��������G�̏�ɒu���A�M�̟D�i�呾���j�͉E�̕��A���Ɂu�̂Ăāv�����Ă���B���́u�̂Ă�v�Ƃ����̂́A�肩�痣���̂ł͂Ȃ��A���ɓ����o�������D�Ŏ�Ɏ����Ă���Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\�������ĕ����́A���̊��D�ł����Ƃ��ނ��đ҂��Ă���B���̂�����́A�C���[�W���N�͂������āA����̃f�B�e�[�����悭�o���Ă���B �@�@�@�@�u�����͂��ނ��āA�����Y��҂��Ă���v �@�������ނ��A���n�`�L�ł͘b���t�ŁA�����Y���҂������قǁA�����͒x���̂ł���i�j�B |
 �M���i�ޗ����j�̌��`  �V����������݂�ޗ���
*�y�����L�z
�s���l�ɐl�X���Q�����鑴���ɁA�ˈɉ���l�́A���̈��̖،˖��c���J�āA����l�������肯��B�~�l�ɏo��b�ƌ�����͖��āA��������ɁA�L�`�ł���b�̏����k�߁A�l�ڎO���L���鑾���ɁA���ڗ]��̋��B�_�e�ɑ}�āA�剹�g�Đ\����́t�i��22�@��ٍ��n���������t�˗E�͎��j  ������������V�Ɍ��サ�� �Ƃ����`���̖ؓ��@���l�ړ�
*�y�O�����ϕM�L�z
�s���V���n�����Y�����T�L�j�n�C�Z���B�i�����j�M���m�_�Ӄm��j���|�A���������q�U�m��j���^�w�A�M�m�D�n�E�m���j�A���j�̃e�R���A�T�V�E�c���L�e�����Y���ҋ������t *�y�����`�z �s�����Y���i���j�}�`�c�J���A���V�L�V�X���j�y�t *�y��V�L�z �s�i�����Y�́j�r�^�҃c�J���t |
| �@ | �]�C������ | �O�����ϕM�L | ���@��t�`�L | �����` | ��V�L |
| �����̓��� | �S�ؕ⋭�̌ږ_ |
�D�̖ؓ��l�� �B�ŕt �ؔ�t�������� |
�E�̖ؓ� �������n��ڌܐ� ��̖ؓ������� | 䂂̖ؓ� | �D�̖ؓ� |
| ����̓��� |
�O�ڈꐡ�̐] �@�� |
��ڎ����̐] �d�����ؓ� | �O�ڂ̐] | �O�ڂ̑��n |
�O�ڗ]�̑��� �i���O�����̗R�j |
|
�\�\�ł́A���������Y�̓����̘b�ł����A�����قǁw���Y���B�x�̂��b�ɂ��o�܂����悤�ɁA�����ƂƂ�������Ȍ��A�Ƃ����̂������ʂ葊��Ȃ̂ł����B���̂�����͂������ł��傤�B �`�\�\�܂��A���q�蕶���ˁB�����ɂ́u�O�ڂ̔��n�v�Ƃ���B����͂킴�킴�u�O�ځv�ƋL���Ă���ȏ�A����Ȍ����Ƃ����`�����������炠�������Ƃ��킩��B���ꂪ�ޗ�������̋N�_�ł��ȁB �a�\�\�w�]�C�������x���L����c�@���̓���́A�O�ڈꐡ�̐]�̓��A����ɂ�����ؓ�����ɒĂ���B�܂�A�@���̓���͓���ȁB�w���ϕM�L�x�̋L�������l�����A�]�͓�ڎ����A�����Y�̖ؓ��Ɋւ��Ă͏����ڂ����āA���ԂɐU���p�̘b������A���ꂪ����̋��ꂽ�Ƃ����d�������ȁB �`�\�\�u�]�̓��v�Ɓu�ؓ��v�̓��Ƃ����_�ł́A�w�]�C�������x�Ɓw���ϕM�L�x�͋��ʂ��Ă���B���ꂪ�}�O�n�`���̘b�B �b�\�\�Ⴂ�������A�w�]�C�������x�ł́A�����̓���ږ_�݂̂ł���̂ɑ��A�@���̓���͐]�̑����Ɩؓ��̓�ł���B�w���ϕM�L�x�́A�����͑召��{�̖ؓ��A�����Y�͐]�̑����Ǝd�����̖ؓ��̓�B�w�]�C�������x�ł́A�@��������p�̂����߂����R���ŁA��������p�ӂ�����̂ɑ��A�����̕��͏��ꂪ����㌎q���@�قƂ����ƃ����ȑ����Łi�j�A������_��{�Ƃ����g�y���A�Ƃ����ΏƓI�\�}�B �a�\�\���̐]�̓��Ɋւ��Č����A�O�ڈꐡ�͒��傾���A��ڎ����͂�Ⓑ�߂Ƃ������x���ȁB���������āA�������ڂ̖_�ŏ@�����O�ڈꐡ�̐]�Ƃ���w�]�C�������x�́A�o���Ƃ��ɒ���������������Ă���̂ɑ��A�w���ϕM�L�x�́A�������l�ڂ̖ؓ��ŏ����Y����ڎ����̐]�Ƃ��邩��A�u��������v�Ƃ����_�́A�ނ����ނ��Ă���i�j�B �b�\�\���������āA�t�@���b�N�ȈЗ͂͌�ނ��Ă���i�j�B�w���@��t�`�L�x���ƁA�O�ڂ̐]�B �`�\�\�}�O�n�`���̂����@���������Y�̓���ł���]�̓��B�]�͐\���܂ł��Ȃ��A�������ȗ��̗L���ȓ����Y�n�ł��ȁB �a�\�\���������O�ł͂Ȃ������A���݂Ȃ牪�R���q�~�s���ł���B���q���ɂ͒原�A�P���A���Ƃ��y�o�����B�����A�@���������Y�̐]�͓`���Ȃ̂ŁA�������g�p�����Ƃ����ȏ�̈Ӗ��͂Ȃ����낤�B |
*�y���q�蕶�z
�s�◬�A�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂���A�����ڂ݂��p��s�����B���U�A�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���A�P�x���B�̂ɑ��A�M�������߂Ċ◬���ƈ��Ӂt *�y�]�C�������z �s�@���n�A�����̉��ɓ��ۂ̋�𒅁A�O�ڈꐡ�̐]�̓��������A�ؓ�����Ɏ��A���M�ɏ�A�����킽��B���U����ɂ킽�肽������āA���Ƃ������Ђ���A���̐]�̓����ʂ��A���̂�����ɐĊC�ɂ��āA�ؓ������C�ɂȂ����A�M��肠����A���ɗ����Đ�Ӂt *�y�O�����ϕM�L�z �s�����Y�n���M�j���A�Ɨ���l�A�����l�j�e���n���B�R�����J���T�������V�A�d�����m�ؓ�����j�c�L�e���e���t �s�����Y�A�g�c�e�ԃV�A��ڎ����m�]�m�������E�j�J�P�A���ԃj�ŐU���A�ʃ��t���Y�J�R���B�ܗ��K��B�m�����j�A���ԃj�U�������g�X�B�d���������ԃj�U�e�A�G�ԃA�^���x�j�A���e�����t���o�A�藡���m�@�N��o�V�A�������e�ؓ��j�e�Ńc�N�����g�C�w���t *�y���@��t�`�L�z �s�Óc�����Y�n�ヌ�e���M�j��҃��V�j�A���j�吨�m�����A��j�����K���^�������e�A��t�m�������X���l�g���v�P���A���߃N�i���g�A�]�m�O�ڃi�������U�e�A�⃒�����e�C�j�n���t |
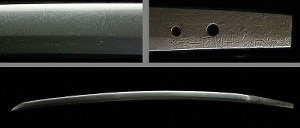 �]���� ���原�i��k�����j�@���@�F2��3��4�� |
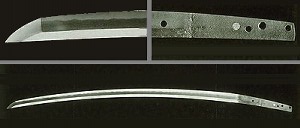 �����@�������i���q���j�@���@�F2��4��7�� |
|
*�y�����`�z
�s�����Y�n�A�́X��m�����H�D�m���]�A���F�������q�̖�g�n�j���������A���������A�O�ڃm���n���U�e�A�⃒�����j���Q�A���ۃj���e�����K�߃N���}�t�t *�y��V�L�z �s�����Y�n�́X��m���i�V�H�D�j�A���v�m���������V�A�����W�����~�A�O���P�m�������уX�m���O�����m�R�n�t
*�y�{�����Y���B�z
�s���l�̐��ɁA�����ޗ��Ǝd����ďM���ɕ������A���������̂�����D�l�Ɍ�ЂāA�e�w���Ď��ׂ������ق��߁A�D��肠����Đ����Ȃď������Ȃ��B�ޗ����������قƖ��t�����O�ڗ]�̑品���Ȃď�����������Ɓt |
�b�\�\����ɑ��A���n�`�L�ɂ́u�]�v�Ƃ����L���͂Ȃ��B���̑���Ɂw��V�L�x�ł́A�s�O���P�m�������уX�m���O�����m�R�n�t�ƁA�����ɂ킴�킴�u���O�����v�̖����o���B �a�\�\�����͊��q���̐l�A���O���D�̓��H���ȁB�����͑����������Ă��āA����E�d�������Ȃ��Ȃ��B�������ȗ��喼���ɂȂ��Ă��āA����͐]�ɗ��ʗL���Ȗ����̖����o���Ă���Ƃ������Ƃ��ȁB�������A�����Ȃ�����O�������א�Ƃɓ`���������A���̔��n�`���̃l�^�́A�����������̂����肩������Ȃ��B�������A������͓�ڎl���ŁA�u�O���P�m�����v�ł͂Ȃ��B�`���͗v�f�����I���ȁB �`�\�\�����̒�������ɂ���A�w���ϕM�L�x�ł́A���̐]����ڎ����k81cm�l�Ƃ������@�ł��ȁB�������������Ƃ��Ώ��q�蕶�̂悤�Ɂu�O�ڂ̔��n�v�Ƃ����悤�ɊT���������āA����ȓ��̃C���[�W������̂ɑ��A����͂����ɂ��������悤�ȋL���ł���B �b�\�\�ǂ������킯���A�w���ϕM�L�x�́A���̓������q�̋{�{�ɐD�̉Ƃɓ`����Ă���Ƃ����L�����L���i�j�B�Ƃ���Ώ��q�{�{�ƂɁu���̂Ƃ��̓��v�����ꂾ�Ƃ��ē`����āA���ɂ��������̂��A��ڎ����������̂�������Ȃ��B �`�\�\����͂ǂ��֏������̂��i�j�B �b�\�\�����ˁA���q�{�{�Ƃ̎q���́u���̂Ƃ��̓��v���ǂ������낤�A�u���Ă݂�i�j�B�Ƃɂ����A���ւ̓`���ł͂����������Ƃ������B�Ƃ���ŁA�����}�O�n�́w�]�C�������x�ł́A�]�͐]�����A���@�͎O�ڈꐡ�k94cm�l�ƒ����B�܂�A������́u�O�ڂ̔��n�v�̘H�������A�w��V�L�x�́u�O�ڗ]�v�Ƃ����L���ƌĉ�����Ƃ��낪����B���������āA�����Y�̒���Ȍ��Ƃ������b�f�́A�}�O�n�`���ɂ��������Ƃ������ƂɂȂ�B �a�\�\�����Łw���ϕM�L�x��������ڎ����Ƃ������@�̂��Ƃ����ˁA����ł͑債�Ē����Ȃ�����A�n�n�肪���̐��@���Ƃ������������낤���A�w�]�C�������x���O�ڈꐡ�Ə����Ă���ȏ�A���ꂾ�����n�n�萡�@�Ƃ����킯�ɂ������܂��B �b�\�\�w���ϕM�L�x�́u��ڎ����v�Ƃ����ِ��͂��邪�A���͂��������O�ڂƂ��������ł��邩��A����͏��q�蕶�ɔ�����u�O�ڂ̔��n�v�Ƃ����`�������z�����Ƃ݂Ă悢�B �`�\�\�w���Y���B�x�͏��q�蕶�������Ă��āA�u�������قƖ��t�����O�ڗ]�̑品�v�Ƃ����`�����E���Ă���B���́u�����Ɓv�͂ǂ����炫���̂��B �b�\�\����͒��B�̓`���łȂ��Ƃ��A�����ł��o����͂Ȃ����B �a�\�\����ł͔w���Ɏl�ڂقǂ̑�����w�����������Y�̃X�^�C�������z���Ă��邪�A�u�O�ڂ̔��n�v�͂���قǂ̂��̂ł͂Ȃ��B �b�\�\�������ˁB�w�]�C�������x�ɂ́s�O�ڈꐡ�̐]�̓��������t�Ƃ����āA����͍��ɍ����ŁA�w�ɕ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����A�O�ڂ̑品�����ɍ����A�����U��Ƃ�������ɂ́A���Ȃ�̑�j�ő�͂̍����Ƃ����C���[�W�͂���ˁB |
|
�`�\�\�o���̓���̘b���ςƂ���ŁA�ł́A������������̘b�ֈڂ�܂����ȁB �a�\�\�}�O�n�ł́w�]�C�������x�ɂ͌����������悤�Ȃ̂����A��̓I�ȋL�q�͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x�ɂ��A���̏M���Ō���������Ƃ����̂ŁA�C�����������M�͒�����낵�A�M�ƂȂ��G�ƂȂ��������Q�W�����A�Ƃ���B �b�\�\���ւŌ�������̂�f��ꂽ�̂ŁA�M���ł�邱�ƂɂȂ������A�Ă̒�A�������Q�W���Ă��������ȑ����ɂȂ��Ă���A�Ƃ����Ƃ��낾�낤�ˁB �a�\�\����ŁA��i��剽�^�̘b�͌�܂킵�ɂ��āA���́w���ϕM�L�x�̋L���ɑ��A���n�̓`�L�ł͂܂�Řb���Ⴄ�B���������A���n�̓`�L�ł́A�א�Ƃ̌������Ǘ������̉��ŁA�������s�Ȃ�ꂽ���ƂɂȂ��Ă���A���̓�l�ւ��ۛ��܂���S���A�V���܂茩�����A���ւ����Ƃ���B �`�\�\��������n�̓`�L�ł́A�M���́u���q�̐Ⓡ�v�A�䂪�Ƃ̒�戵��������ˁi�j�B �b�\�\�������A���q�ŋ֎~�߂��o���Ă��A���B���ւ��猩���ɉ����邾�낤�A�Ƃ������b�ł͂Ȃ��B�����̊��ݒ肪�͂��߂������Ă���B�w���ϕM�L�x�ł́A����͉��ւł����āA���q���א�̓a�l�����̌����ɉ��̊W���Ȃ��B�}�O�n�Ɣ��n�̓`���́A���̂悤�ɘb���Ⴄ�B �a�\�\�Ƃ���ŁA�w���ϕM�L�x�ł́u�L�B��i�̏�剽�^�v�������œo�ꂷ��ˁB��i��͌Â���ŁA�֖�C���̓��[�ɂ����āA�C����N����d�v�Ȉʒu�ɂ���B�L�O���א�̂ɂȂ��Ė�i��͉ƘV���c���̗a����ƂȂ����B�w���ϕM�L�x�͂��̏�傪�A�א�z����a�Ɛb�����A���������O�����Ə����Ă��邪�A�����L�O�͍א�́A���̖�i���́A������w���c�ƋL�x�ɏo�Ă�����c�����i1572�`1624�j���낤�ȁB �`�\�\���̖�i���͕ٔV���i�����j�Ɲ፧�̎҂��Ƃ����B���ꂪ�Ɨ���吨���A��ďM���ւ���Ă��Ă���B��g�̑����������A�i���g�́j�����ɍ��������A�l�ӂɋ��Č�������A�Ƃ����b�ł��ȁB �a�\�\��g�̑��Ƃ́A�����������䂪������ڈȏ�̂��̂������B��ڂ��邢�͎O�ڂƂ��������ɕC�G������̂��������B����Ȃɕ䂪�����Ȃ�Əd���Ĉ����ɂ����̂����A���͂̎҂͕��C�ő����ӂ�����Ƃ����B������A����ȑ�g�̑����������ԂƁA���ꂾ���ňЈ��I���B �b�\�\�w���ϕM�L�x�̂����̋L�q�́A��i��剽�^���u�Ɨ��吨���A���A��g�m�������Z�v�ł���A���̘A���͂���Ɍ����ł͂Ȃ��A�R�����o�����Ă��Ă���Ƃ����b���B��i��剽�^�����������Ă��鋲���́A���ߗސg�̉��̕��Ȃǂ����ĉ^�Ԕ��ŁA�_��ʂ��ď]�҂ɒS������B�����������̋L�q�͕���̒�^���B���Ƃ��s���E���������߂����t�Ƃ����u���w�R�v�̈�߂��������������ˁi�j�B �`�\�\���āA��i��剽�^�̈�c�́A�����̉����c�ŁA�����������W�c�ł���B�����Ȃ�ƁA�����[���̂́A��͂���n�`���Ƃ̑���ł��ȁB �a�\�\���n�`�L�ł́A�����͂�������l�ŏ��M�ɏ���ĉ��ւ������Ă���B����ɑ��A�����Y�̕��͓a�l�̌���D�ł���Ă��邵�A�����ꏊ�͍א�Ƃ����d�ɊǗ����Ă���B�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x�ł́A�����̕�����i��̕����W�c�������c�ɂ��Ă���̂����A�����Y�́A�A��̉Ɨ���l�����B �b�\�\�b�͌����ɐ����i�j�B�����ŁA�}�O�n�`���Ɣ��n�`���ł́A�ǂ����A�����̊W���t�ɂȂ��Ă���炵���A�ƌ��������B�܂�A�}�O�n�`���ł́A��i���ȉ������̖������������A�����Y�͒P�ƍs���B���n�`���ł́A�����͒P�ƍs�������A�����Y�͓a�l�̑D�ŗ��邵�A���g�x�ł̎҂����ɂ���B �a�\�\����ɁA�}�O�n�́w���ϕM�L�x����i�����o���Ă���̂́A���n�������������W�҂ɐ�����̂ƑΔ䂵����B �b�\�\�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x���E�������B���ւ̓`���̃|�C���g�́A��i��傻�̂��̂ł͂Ȃ��A�����Y���Ǘ������Ȃ̂ɑ��A�����ɂ͖L�O���̉����c�������Ƃ����ΏƓI�ȍ\�}�ȂB �`�\�\�悤����ɁA�����Y�ɐS��I�ɉ��S���镨��̍��Ղ�����B���B�����炷��A��i��͂��Ƃ��Ɩї��̏邾�����B���ꂪ�A�L�O�ɍא삪�������čא�̂��̂ɂȂ��āA�ڏ��ȑΊ݂̏�ɂȂ��Ă��܂����B���������`���̐S��I�Ȕw�i�������āA��i��剽�^���o������킯���B �b�\�\���̒ʂ肾�B����ƖL�O�̑Η��I�Ίݐ�����{�I�ȍ\�}�B���B��������ƁA�n���̏����Y���Ǘ������Ȃ̂ɑ��A�X�g�����W���[�̕����ɂ͌������̉����c������Ƃ����A�s���Ȋ���������������킯���ˁB �a�\�\����͑O�ɘb���o���A�w���Y���B�x���L���Ă���s������a�H�A�ޗ��A�{�{���U�Ǝd���̎��A�̓��V���̕�����́t�̘b�A�u�����͓n�C����l���������ǁA����������������v�Ɗޗ����D���ɖ₤�Ƃ�����̈�b�����A�����ŁA�u�{�{�i�����j�̗^�}�������������邩��A���͏�����܂��B�����Ȃ����v�ƑD�����ޗ��Ɍ����ˁB����͂��̒��B�̓`���̓`���炵���B �`�\�\����͓V���Ɖ����邪�A�Ï����Ð�C�́w���V�G�L�x�ɂ����l�̘b������B �a�\�\�n���̓`���ł͂������A�Ƃ����������Ղ肾�ȁA����́B����ƁA����͎������Ă��Ȃ����A�◬�i���p���h�j�̓`���ɁA����Șb�����邻�����B�\�\�J�c�E�ɓ����߂̒�q���A���c�P�E�q�傾�ˁB���̑��c�P�E�q��̒�E���c�s�Y�����ւ̂�����ŁA�����Ǝ������ď������܂����i�j�B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����������́A���ɂȂ����i�j�B �`�\�\�Ƃ�ł��Ȃ��W�J���Ȃ��B �a�\�\�������A�����̔ڋ��Ȗd�v�ɂ���āA�̂��ɑ��c�s�Y�͕����ɎE���ꂽ�B�◬�̓`���ł́A�����͂܂������̓G���Ȃȁi�j�B �b�\�\����A���[�J���ȓ`���ł͕����͓G�������A�◬�̓`���ł͂����Ƌɒ[���ˁB�����A���������`���́A�ޗ��������Ȍ゠�������Ŕ��������Ƃ������Ƃ��B�������āA�����ɏ����ĕ����ɎE���ꂽ�Ƃ������̑��c�s�Y���A�Óc�����Y���ƁB �a�\�\�u�����v�i���c�j���u���v�i�Óc�j�ɂȂ����Ƃ����A���������]�a�R�[�X�����肤��ȁB �`�\�\�w���ϕM�L�x�ȑO�ɁA�^�_�E�C�`���[�i���c�s�Y�j�́A���łɃc�_�E�R�W���[�i�Óc�����Y�j�Ȃ��Ă����B �b�\�\�����ɏ��������A�����ɎE���ꂽ�Ƃ������c�s�Y�̂��̓`���Ȃǂ́A�ɒ[��������Ȃ����A�����Y�ɐS��I�ɉ��S���镨��́A���̎�̂��̂��ˁB�������A�w���ϕM�L�x�̋L���ɂ���̂́A���낤���Ďc��������̍��ՂȂB�`�����̂܂܂ł͂Ȃ��B �`�\�\����ƁA�w���ϕM�L�x�̋L���͍��Ղ����ł��c���Ă��邪�A�����A���n�`���ƂȂ�ƁA�����Ə����Y�̗��ꂪ�t�ɂȂ��Ă���B����́A�đg�D���ꂽ�V�����p�^�[�����Ƃ������ƁB �a�\�\���낤�ˁB���n�`�����ƁA�Ǘ������Ȃ͕̂����̕��ŁA�����Y�Ɨ�����������Ă���i�j�B �b�\�\���b�_�I�������ȁB����̏ꏊ���ɗ^���Ă��邩��A�����Ȃ����B |
*�y�O�����ϕM�L�z
�s���҃m�M�A�R���V�A�M�g�i�N�G�g�i�N�A�����Q�W�X�B�L�B��i�m��剽�^�m�א�z����a�Ɛb�������n�A���V�������m�҃��w�A�Ɨ��吨���A���A��g�m�������Z�A�����j�����J�P�A�_�Ӄj���e�����X�t *�y�����`�z �s�O���{���j�߃g�V�e�ۛ��y�r�V�σ��֎~�X�B���j�ߍŃ����d�i���t *�y��V�L�z �s�O���{���j�\�L�e�A���x�o�������m�ۛ��y�V�����֎~�A���B�i�����j���j�n���g�x�Ńm�҃����V�n�T���B���m�j�ߚ��d�i���t  �ޗ��������i���]��  ��g�̑� �E�F���M�� �����B�Z�����F�d ���F���M�� �����V�Z�����M�F �Ƃ��ɒ�2�ځi60cm�j
*�y�{�����Y���B�z
�s������a�H�A�ޗ��A�{�{���U�Ǝd���̎��A�̓��V���̕�����́A���ɑ��̊����ɋy�āA�M�ˌ����̂��ߏM���ɓn�C���鎖�삵�B�ޗ����D��Ɏ���ď�D���B�ޗ��A�n��ɍ��ĞH�A�u�����̓n�C�r���B�����Ȃ鎖���݂�v�B�n��H�A�u�N�s�m��B�����͊ޗ��Ɖ]���@���A�{�{���U�ƏM���ɂĎd������B���̂Ɍ�������ƂāA�������n�C�Ђ������炸�v�Ɖ]�B�ޗ����H�A�u�ᑴ�̊ޗ���v�B�n����i���j���T��ЂĞH�A�u�N�ޗ�������D�𑼕��ɂ��ׂ��B�������B�ɋ��苋�ӂׂ��B�N�̏p�~�̂��Ƃ��Ƃ��Ӌ��A�{�{���}�r�������B�����Ė���ہi�j���Ƃ����͂��v�B�ޗ��H�A�u�����]���Ƃ��A�����̎d���A�ᐶ�Ƃ�~�����B�R�Ƃ����A�����d���̎���A�c�i�Ёj�����Ƃ���������ӂ鎖�͗E�m�̂�����|��B��K�i���j�D���Ɏ����ׂ��B���킪�����ՂĐ������T���ׂ��B�˕v�Ƃ��ւǂ����u�������v�ƂāA�������@���܂���o���ēn����o�ӁB�n��܂𗬂��đ����E�������t *�y���V�G�L�z �s�◴���U�̉�Ɩ���Ȃ��A�ɍ��菬�M���������ĂӂȂ��܂֓n���Ƃ������A�Y�̂��̂Ƃ��◴���ƁT�߁A�u�����̏���l�𐔑������B�ēn���B�吨�Ɏ�Ȃ��Ƃ��ӎ��L���l�ɂĊ��ӂ܂��A�����͂Ђ�Ɍ䖳�p�Ȃ�v�Ƃ��ӁB�◴���H�A�u�m�͌����͂܂��A���������Ȃ�A�����n�炳��͎m���Ղ�Ƃ����A�Ⴕ�傹���ɂĉ���ՐJ�͂���ɂ�����ׂ���v�Ƃ��ӂāA�����ē��ɓn��t
*�y�◬���n���}�z
���ɓ����ߗS���\�� ���\�\�\�\�\�\�\�� �����c�O���q�吳���\��㍶�q��ѐ��d �� ����㍶���q �� �����c�P�E�q��L�Մ����c�s�Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͐M�Z�d�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����c�Z�Y���q�� |
|
*�y�]�C�������z
�s�@���n�A�����k�����l�̉��ɓ��ۂ̋�𒅁A�O�ڈꐡ�̐]�̓��������A�ؓ�����Ɏ��A���M�ɏ�A�����킽��B���U����ɂ킽�肽������āA���Ƃ������Ђ���A���̐]�̓����ʂ��A���̂�����ɐĊC�ɂ��āA�ؓ������C�ɂȂ����A�M��肠����A���ɗ����Đ�Ӂt *�y�O�����ϕM�L�z �s�����Y�n���M�j���A�Ɨ���l�A�����l�j�e���n���B�R�����J���T�������V�A�d�����m�ؓ�����j�c�L�e���e���B�M�������|�A�V���w���ڃe�Ɨ��j�����J�\���Z�A�ރm�d�������撼�V�A�l�c�܃c�ŐU�e�C��j�e�`�A�����⋤�j���o�V�A�X���^�_�g�k�L���`�A�T�����ؐ܃e�C���e���A�������L�\�o���e�M�m�c�N���҃c�B���n�A�^�g�q���V���j�ŏ��^���g���A��g�m�������^�Z�^���m�A�����j�e�n�كX�ԕ~�g�S�j�J�R���V�j���t *�y���@��t�`�L�z �s�������A���q�m���א�z���璉����m�Ɛb�����ѓ��A��������A�t�X���g�e�A���m�e�����t�Z�V�j�A���j�吨�l�W�^���́A�����]�g��j�A�V�J�^�_�m�R�i���o�A�M����e�����Z���g���j�ナ�A�����j���J�P�������T�Z�e�����^���V���j�A�Óc�����Y�n�ヌ�e���M�j��҃��V�j�A���j�吨�m�����A��j�����K���^�������e�A��t�m�������X���l�g���v�P���A���߃N�i���g�A�]�m�O�ڃi�������U�e�A�⃒�����e�C�j�n���t
*�y�����`�z
�s�i�����Y�́j�O�ڃm���n���U�e�A�⃒�����j���Q�A���ۃj���e�����K�߃N���}�t�B�����A���������j�����e�e�H�A�u�����Y���^���B���o���]���⃒�̃��v�g�t *�y��V�L�z �s�����Y�����U�e�A�⃒�����j���W�A���ۃj���e���U�K�߃d�N���}�t�B���j���U�����j�����}���A�j�c�R�g�e�]�N�A�u�����Y���^���B���o���]���⃒�̃��v�t  �ޗ��� ���X�؊ޗ��V�� �����l�O�N�i1910�j���� �������`���ɂ����ł͂Ȃ� |
�`�\�\���̎��_���炷��A��̗L���ȁA�����Y�������̏���̂Ă��Ƃ����V�[�����A�ĉ��߂��\�ł��ȁB �a�\�\����́A���Ƃ��Ƙb���Ⴄ�킯��B�w�]�C�������x�ł́A�@���́A�O�ڈꐡ�̐]�̓��������A������A�ؓ�����ɒĂ���B�����ĕ�������ɒ����Ă���̂����āA�u���Ƃ��v�Ђ���v�A���̐]�̓����A���̏���ɐ��ĊC�Ɏ̂āA�ؓ����C�ɓ������ꂽ�B �`�\�\�@�����̂Ă��̂́A���̏₾���ł͂Ȃ��B�ؓ����̂Ă��B�������A���̏���ɐ��Ď̂Ă��A�Ƃ����킯�B �a�\�\���ꂩ��A�w���ϕM�L�x�̕��͂�����ڂ����b�B�����Y�͏��M�ɏ���Ă���Ă���B�A��͉Ɨ���l�����ŁA���ɂ͐���k������l��l�����邾�����B�����Y�͏M�ŁA�d�����̖ؓ�����ɂ��ė����Ă����B�d�����̋L���͈ȑO�ɂ������B������Ďd����������Ƃ����A���̎d�������ȁB�M����������ƁA�\�\�Ɖ]�����A�M���͉��ւ̖ڂ̑O�ɂ���A������������Ȃ����Ȃ��̂����i�j�\�\�A�Ƃɂ����A�M���̊ԋ߂ɗ���ƁA���U��Ԃ��ĉƗ��ɉ������������������B����Ə����Y�́A�ނ̎d�������撼���āA�l�A�܉�ŐU���āA������C��֝e�蓊�����B����͍ŋ��̕���ł���͂��Ȃ̂����A�ӊO�ɂ������Y�͂�����C�֓����̂Ă��Ƃ������Ƃ��ȁB�����l���������Ă̂��Ƃ��낤�B�������A����ǂ́A��������ƂƂ��ɒ����o���A���邷��Ɠ������B�����āA����܂��ĊC�֝e��̂Ă��̂��ȁB�������ď����Y�́A�����g�̓���e�Ɉ����āA�l�֒����̂�҂��Ă���A�Ƃ�������B �`�\�\�����āA���ڂ��ׂ��͈ȉ��̒��߂̌��B���Ȃ킿�A����́A���Ƃ������Y�������ɑł��������Ƃ��Ă��A��g�̑��������������̕��m�����́A���̂܂܂ɂ��Ă�������͂����Ȃ��A�����Ă������Ă����͂Ȃ��A�����v��������ł��낤���c�B �b�\�\�܂�A����ł��܂��A������߂���͂��͂�K�v�Ȃ��B����́A����Ƃ꓾�Ȃ��Ɗo�債�������Y�́A�ߌ��I�Ȑg�U���ł���A�Ƃ����킯���ˁB����́A��p�́w���@��t�`�L�x�ł���{�I�ɓ����B�����̖����Ǝv����u�����ѓ��v���A���𗧂����āA�����ɂ���Ƃ���������ˁB �a�\�\��قǂ́w���Y���B�x�̘b�ɂ��A�D�����ޗ��Ɍ����A�u���Ȃ����ޗ��Ȃ�A���̏M���悻�֒�����B���������֍s���Ă��܂��Ȃ����B���Ȃ��̏p���_�̔@���ł����Ă��A�{�{�̒��Ԃ��������������邩��A�����Ė��͂Ȃ��v�ƁB�܂�A�M���֍s���͎̂��E�I�s�ׂ��A�~�߂��ق��������Ƃ����������B�ޗ��������ɂ́A�u���܂��̌����悤�ɁA�����̎����A����͐����c�肽���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���������̌_��������̂��B���Ƃ����������ʂƂ��Ă��A�_��Ɉᔽ���邱�Ƃ͗E�m�̂��Ȃ����Ƃ��B����͕K���M���Ŏ��ʂ��낤�B���܂��A����̍����Ղ��Đ��𒍂��ł���B�G�v�Ƃ͂����A���܂��̎u�Ɋ������v�ƁA��������@���܂����o���ēn��i�D���j�ɗ^�����B�D���͂��̍��E�Ɋ������܂𗬂����\�\�Ƃ����悤�Șb���ˁB �b�\�\�]�k�Ŏ֑��ɂȂ�悤�����A�����ł����u�@���܁v���A���z���Ɗ��Ⴂ���Ȃ��悤�Ɂi�j�B�ޗ����������āA�������z���Ƃ���Ă�����A�Ƃ������Ƃ���Ȃ��B �a�\�\�@���܂́A��Ɏ�����Ƃ����č��z�Ɠ����ɂȂ������A���Ƃ͋�̓��ɒ�����|�V�F�b�g�ł���B��⏬���Ȃǂ���ꂽ�B������|���g�K���l�̂����炵���A�������̎Y���ł���B�g�ɒ����ė����Ȃ��@���܂𑼐l�ɂ���Ă��Ƃ����s�ׂ́A���̏���̂Ă�̂Ɠ����Ӗ��������B����͎��ʂƌ��܂����A�Ƃ������Ƃ��ȁB �`�\�\�ޗ��͎��E�I�s�ׂ��Ɖ����Ă��āA�M���֓n��B�܂��ɔߌ��̃q�[���[�ȂB �b�\�\�����ďd�v�ȃ|�C���g�́A�`���̓����̈Ӗ��Â��ł́A�����̑���E�ޗ��A���邢�͏@���������Y���A���̏����Ď̂āA�d�����̖ؓ����C�֎̂Ă�Ƃ����U�����́A�ߌ��I�g�U�肾�����A�Ƃ������Ƃ��B �`�\�\�����܂Řb������A���n�`�L���A�ǂ�قǓ`���̈Ӗ����e����₂������A���ꂪ��������B �b�\�\���n�`�L�ł��������A�����Y�͑����̏���̂Ă�B���̗��R����������L���͂Ȃ����A�������������Č������t�A�u�����Y��������B�����Ή������̏���̂Ă��v�Ƃ����L���ȉȔ������镔���́A�I���b�f�ŁA�V���߂̏��Y����B����ł́A�����Y�͉��̍l�����Ȃ��ɏ���̂Ă���������i�j�B �`�\�\���ۂ��l����A�����Ȃ炻�̏�́A�키������܂ɂȂ�B���厖�Ɏ�Ɏ������܂ܐ키�����͂��Ȃ��B �a�\�\������A�u�����Y�A���Ȃ��̕������B������Ȃ�A�ǂ����ď���̂Ă��v�Ƃ������̉Ȕ������A����Ȃ�A�����Y�͂�����Ԃ��悢�A�\�\�u�����������A�o�J�߁B���̏�́A���܂����u�b�E���Ă���E�����v�i�j�B �`�\�\�u����ȂɁA���̒�������܂ȏ������Ɏ������Ă��������̂��v�i�j�B �b�\�\�킢�̑O�̌�����ŁA����������Ԃ����\�Ȃ悤�ɁA�悤����ɁA�L���Ȃ��̏�ʂ̉Ȕ��͍l��������Ȃ��B�ǂ����āA����Ȓ��r���[�ȉ��V�ɂȂ������Ƃ����ƁA����́A���n�`�L���`�����^��Y�����Ă��܂��Ă��邩�炾�B �`�\�\�܂�A���֎��ӂ̓`�����^�ł́A�����Y�́A����ɏ���̂Ă��̂ł͂Ȃ��āA����܂����A�����Ď̂Ă��B���͂⎀���o�債�Ă̂��Ƃ��B �a�\�\���n�`�L�́A���́u����܂��āv�Ƃ����̐t�ȏ�����̂ĂĂ��܂��Ă���B�u��܂��āv�Ƃ���������������Ă���ƁA�u�����Y�A���Ȃ��̕������B������Ȃ�A�ǂ����ď���̂Ă�v�Ƃ����Ȕ����������悤���Ȃ��B �b�\�\����܂��Ď̂Ă��̂́A���Ƃ́A���Ƃ������ɏ����Ă������̖��͂Ȃ��A�Ə����Y���o�債�āA�d���ɗՂƂ����ߌ��I��ʂ����^���B���n�`�L�ł́A�����Y�̏���̈Ӗ�����₂��āA�t�ɊԔ����Ȃ��̂ɔ��]���Ă��܂����B �`�\�\���Ƃ������ɏ����Ă������̖��͂Ȃ��A�Ə����Y���o�債�āA�Ƃ����͖̂��炩�ɁA��Ɂw���Y���B�x��w���V�G�L�x�̎��^�����`���̂悤�ɁA�ޗ��ɓ���I�Ȑ��b�������Ƃ������Ƃł��ȁB �a�\�\����������A�M�����u�����v���ł͂Ȃ��u�ޗ��v���ƌĂԂ悤�ɂȂ����A���ւ�����̐���ł���`���ȂB����ɁA�����̏���܂��Ď̂Ă�Ƃ����ߌ��I�g�U�肪�w�]�C�������x�ɂ݂���Ƃ���A�����ۛ��Ƃ������A�s�҂ւ̐S��I���S�͑����Ɍ`������Ă������̂炵���B �b�\�\�{���͂ˁA�u�����Y��������B�����A�������̏���̂Ă�v�Ȃ�Ă��Ƃ́A�����Ɍ�����܂ł��Ȃ����Ƃ��i�j�B�u�����A�������̏���̂Ă�v�́A�������A�����Ă������Ȃ����E�I�s�ׂ��o�債�������Y�́A�ߌ��I�g�U����̂��錾�t�ł������͂����B�Ƃ��낪�A���n�`���͈Ӗ����܂������ϊ����āA�ߌ��I�Ȑg�U������m�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����B �`�\�\����ɂ��Ă��A���̑����̏���̂Ă�Ƃ����g�U��ɂ��āA�قƂ�NJԔ����ȋc�_������܂ő��������ł��Ȃ��i�j�B �a�\�\�������̌�����{�w�{�{�����x��ʂ��āA�w��V�L�x�̋L�����e���L���ɂȂ��āA���n�`�L�́u�����Y��������B�����A�������̏���̂Ă�v�Ƃ����Ӗ��Â��������ʂ��Ă��܂�������ˁB�u�����������Y�����āA���h�������v�Ƃ��������߂������ɐ��Y����Ă����B�������A������w�ܗ֏��x�̋L�q�Ɗ֘A�Â����肷��B�܂������Ђǂ����Ԃ������Ă����i�j�B �b�\�\�����邱�Ƃ͂ˁA�u�����Y��������B�����A�������̏���̂Ă�v�Ȃ�ĉȔ��́A�����͌����ēf���Ȃ��������낤�i�j�A�Ƃ������Ƃ��B�������A�����Y�������̏���܂�����͂��Ȃ��������낤�B����͔s�҂̂��߂̓`���̒��Ő������A�V���{���b�N�Ȑg�U��ȂB |
|
�a�\�\�����ŁA�戵�����ӂȂ̂́A�����Y�͌Q�W����}���ꂽ�Ƃ����w���ϕM�L�x�̋L�����ˁB �`�\�\�����Y�͏M���牺��鎞�A��щ��葹�˂ď�ꂽ�A�Ƃ�����̏�ʂł��ȁB �b�\�\�w�]�C�������x���ƁA�@���͏M���瑾���̏�Ɩؓ����C�֎̂Ă��Ƃ����b�̌�A�M����オ���Ă������d���J�n�ƂȂ邪�A�w���ϕM�L�x�ł́A�����J�n�O�Ɏ�G�s�\�[�h���E���Ă���B�Q�W����}����鏬���Y�Ƃ����̂����ꂾ�ˁB �a�\�\�邪�߂��Ȃ�ƁA�����Y�́i���ԂD�悭�j�M�̌���Ŕ�B��������ё��˂ė��G�������B���̂Ԃ��܂ɁA�����̌Q�W�͈ꓯ�ɏ����\�\�B�ǂ����w���ϕM�L�x�ł́A�����Y�͓O�ꂵ�ċ�M�����҂炵���B �b�\�\�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��A��̖�i��剽�^�ɂ��l�|�����B �a�\�\�����Y�͓���e�Ɉ����i�Ƃ����̂́A���łɔ������ď���̂Ă�����A�����g�ł��邽�߁j�A��i��剽�^�̑O�ɍs���A�u���Ȃ��͂ǂ������l�ł����āA�����ɋ�����̂��v�ƙ�߂��B����͓��R���낤�B���̒j�������镐���W�c�͖��炩�ɕ����̗^�}�A�����c���B���^���]���A�u����͕ٔV���Ɛe�����҂ł���B�������̕��Ƃ̏����������̂��ߓn�C�����B���̕��ɂ͂܂������S�̂Ȃ��҂��B���ɐ������̂��A���낽���ҁv�ƁA�U�X�ɔl�����B �b�\�\�܂�A�����Y�͕����̉����c�ɍR�c�����B����ƁA��i���́A����͂���Ɍ����ɗ����B�s�]�e�����j���i�L�҃i���t�A���܂����ǂ������������͑S���Ȃ��B���܂��ɍR�c�����o���͂Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��낾�ȁB����������Y�ɑ�����b��̋�M����B �`�\�\�u���ɐ������̂��A���낽���ҁv�Ƃ����̂́A�Ȕ��������Ă���B�w���@��t�`�L�x�̕��́A��i��剽�^�ł͂Ȃ��A�u�����ѓ��v�Ƃ����������ǁB �a�\�\�����ѓ��͒��V������A���Ƃ��Ǝ��オ����Ȃ����i�j�A�����Y�̍R�c�ΏۂƂ����_�ł́A�����|�W�V�����̖������ȁB �b�\�\�����Y�͌����̌Q�W�ɏ����̂ɂ���A�����̉����c���ɔl�|�����B�������A�}����l�|������Ȃ������Y�A�Ƃ������̏�ʂ́A�����܂ł��Ȃ����b�_�I���]���o�����̂��B�܂菇���Ƃ��ẮA�����Y�ۛ��̔ߌ��Ƃ��Ă̐��b���^�������āA���ꂪ�A����������M��ʂ֔��]���ꂽ�Ƃ������Ƃ��ˁB �a�\�\������M�ւ̔��]�́A����ɐi�߂A�₪�ēG���u���X�؊ޗ��v�Ƃ���������ǖ{�̓G���ޗ��������A�����邱�ƂɂȂ�B�����ł͊ޗ��͓G���̑ΏۂƂȂ�A���������ׂ����݂ɂȂ�B���́u���X�؊ޗ��v�̏o���́A�����̔ߌ��̉p�Y�����炷��A�܂������ɂ̃C���[�W�Ȃ̂����A���b�_�I�W�J�ł͂��������Ώۂ̉��l���]�͗e�Ղɐ�����B �`�\�\�s�H��A���ɂ������炸�R�ɂ������炸�A�����l����̊Ԃɂ���B�l��قǓ��ĂɂȂ�Ȃ����̂͂Ȃ��i�j�B����͉�X�̍����̎Љ�ł�����I�Ɍ����錻�ۂł��ȁB�q�[���[�Ƃ��Ă��Ă͂₳�ꂽ�l���������Ƃ����ԂɈ����ɂȂ�B �a�\�\�����������ƁB�b�����ǂ��A�}����l�|������Ȃ������Y�Ƃ����V�[���̐��b���^�́A�����c��w�i�ɂ��āA���łɏ����ւ����������҂Ƃ���֏����Y���ːi����A�Ƃ����sself-destructive�t�i���œI�����E�I�j�ȍs�ׂ��B�����܂ł��Ȃ��A����͏����Y��ߌ��̎�l���ɂ��镨��Ȃ���ˁB �b�\�\���̔ߌ��I�p�Y�ƁA�����̂ɂ���邱�̏�Ȃ����S�߂ȏ����Y�A�Ƃ����ɓI�ȍ\�}��}�����͉̂����B�����́A�]���̎R�r�A�X�P�[�v�S�[�g�̘_�����@�\���Ă���B�O�ɂ������悤�ɁA�����Y�̘A��͉Ɨ���l�����ŁA���ɂ͐����l�����邾���B���������Ǘ������Ȃ��������Ō���ɓo�ꂾ�B�����ɂ͌����̌Q�W���K�v�ŁA����ΑS����G�ɂ��ăX�P�[�v�S�[�g�ɂȂ�B���ꂪ�F�ɚ}����l�|������Ȃ������Y�̖{�����ȁB �a�\�\�X�P�[�v�S�[�g�̘_���́A������ɂ��Ă����`�I���B�����Y�͔ߌ��̎�l�������M����鑶�݂֔��]����B�������A����ȋ�M�̃G�s�\�[�h�͔��n�̓`�L�ɂ͂Ȃ��B�ނ��뗧��͋t�ɂȂ��Ă���B�x��Ă����͕̂����ł���A�܂��l�|����̂͏����Y�̕����B �`�\�\�u����͐�ɗ��Ă������B���܂��͂ǂ����Ēx��Ă����̂��B���₨��A���܂��A���Ă͋C�����ꂵ�����v�ƁB�����͕������Ȃ��ӂ�����ē����Ȃ��B���̌�ŁA�����Y������̂ĂāA�]�X�Ƃ����b�ɂȂ�B �a�\�\�w���ϕM�L�x�̓`���́u��������ɓ��������v�Ƃ��邪�A�����Y�������ɏ���Ƃ����G�s�\�[�h�����荞�܂ꂽ�����A�s�U�X�j�����X�t�A�܂�u�����Y��l�|����v���́A��i��剽�^�̖�����B����ɑ����n�̓`���ł́A�u�����Y����ɓ��������v�u�����Y���l�|����v�Ƃ����ݒ�ŁA�ǂ������ꂪ�����Y�֓]�����Ă���B���̑���ɁA�����͔l�|����̂ł͂Ȃ��A�u�����Y��������v�ƒ������ď����Y��{�点��Ƃ�������B �b�\�\�����Œ��ӂ��ׂ��́A�����Ə����Y�A�ǂ��炪��ɓ������đ����҂��Ă������A�Ƃ������Ƃ��ˁB �@�@�@�@�u��������ɓ������āA�����Y��҂v �@�@�@�@�u�����Y����ɓ������āA������҂v ���Ƃ��A�Ì^�͑O�҂����A��ɓ������đ����҂ق����A�����c�����ėL���ȏ����ɂ���B�ߌ��I�Ȍ��^�ł́A��ΓI�s�������m�ŏ����Y�������֓˓�����Ƃ������E�I�s�ׁB�w���ϕM�L�x�̋L���ł́A���̍\�}�͂��̂܂܂ɂ��Ă����āA�ߌ��I��̂�}����銊�m�Ȏ�̂ւƕϊ����Ă���B����A���n�`�L�́A�\�}���܂��������]���āA�i�����c��w�i�ɂ��āA���łɏ����ւ����������҂Ƃ���ցA�����Y���ːi����Ƃ����j���œI�����E�I�ȍs�ׂ��A�����̕��U���Ă��܂��B���ꂪ�A�u�����Y����ɓ������āA������҂v�Ƃ����\�}���ˁB �a�\�\���Ƃ��Ə����Y�̂��̂ł��������E�I�|�W�V�������A�����̕��֓]�����邱�Ƃɂ���āA�s�ׂ̈Ӗ��������D�ق��āA�����̎��œI�s���̔ߌ��������S�ɖ��������Ƃ����킯���B �`�\�\�����͏����Y���C���Ƃ����قǑ҂�����A�Ƃ����ݒ�͔��n�݂̂ɂ���B������A�u�����Y����ɓ������āA������҂v�Ƃ����\�}����̔��W�ł��ȁB �a�\�\���n�`�����A�`���Ì^�̈Ӗ����܂��������]���āA�V��������ɂ��Ă��܂����̂́A���́A�u�����͏����Y�����Ƃ����قǑ҂�����v�Ƃ������b�f�ł��킩��B �b�\�\�������A�w���ϕM�L�x�̓`�����e�́A���n�`�L�̋L�������Ì^�����A����ɂ��Ă����ꉻ�͂��Ȃ�i��ł���B�܂�A�����Y�Ɉ�ʂ�Ԕ����Ȃ��Ƃ������āA���ꂩ����ɕ����o��Ƃ������Ƃɂ���B �a�\�\����܂ŁA��ɍ������A���ނ��Ă������A���̖ⓚ�̊Ԃɗ����A�D�Ŕ������O�E�֑ł������A�u�ǂ������A�����Y�B�ٔV���͂����ɂ��邼�v�ƌ��t���������B��ʊO�ɂ����������ˑR�o�ꂵ�Ă���B �b�\�\�O�ɏo���A���������ނ��đ҂��Ă���Ƃ����p�ƂƂ��ɁA���̏�ʓW�J�͂悭�ł��Ă���B���b�Ƃ��ăR�i��Ă���A�Ɖ]���ׂ�����B���ꂾ���ɁA���̊ޗ����`���́A���n�Ƃ͈قȂ���Ő����������ꂾ�ƌ���ׂ����ȁB |
*�y�]�C�������z
�s�@���n�A�����k�����l�̉��ɓ��ۂ̋�𒅁A�O�ڈꐡ�̐]�̓��������A�ؓ�����Ɏ��A���M�ɏ�A�����킽��B���U����ɂ킽�肽������āA���Ƃ������Ђ���A���̐]�̓����ʂ��A���̂�����ɐĊC�ɂ��āA�ؓ������C�ɂȂ����A�M��肠����A���ɗ����Đ���t *�y�O�����ϕM�L�z �s���j�E�߃N�i���g�A�i�����Y�́j�����D�e��r�g���B��r���W�e���G���c�N�B�����m�Q�W�ꓯ�j�t�B�����Y�A�������L�\�o���A��剽�^�K�O�j�s�L�A�u�C�J�i���l�i���o�����j�n�������R�]�v�g�R�K���B���^�K�]�A�u�䓙�n���V���g�e�L�Җ�B���������g�m�����������m�דn�C�X�B�]�e�����j���i�L�҃i���B���j���^���J�A�T���ҁv�g�A�U�X�j�����X�B�v�}�f�����V���n�A��j���J�P�A�T�V�E�c���L�e�������V�K�A�ⓚ�m���j���A�K���A�D���ȃe��������c�O�c���E���ŝc�q�A�u�@���A�����Y�B���V���n���j�A���]�v�g���t���J�P�����t *�y���@��t�`�L�z �s���߃N�i���g�A�]�m�O�ڃi�������U�e�A�⃒�����e�C�j�n���A�M�c�N�g�A�A���~���J�P�e�g���g�L�A�c�}�d�L�e�|���P���o�A���l���c�g�t�B�����Y�ԖʃV�e�A���j�ѓ��K�O�w�s�A�u������m�����j�A�������n���p��v�g�A�����J�j�]�B�ѓ��ŏe�A�u�䓙�n�����ѓ��g�]�ҁA���y���A�����B�������t�m�ܕ��A�e�����A�������L�A�����j�ナ�^���B�v�j�J�}�q�i�L�Җ�B�ٔV���n�A���j���^���v�g�]�w�o�A�����Y�����ŐU�^�_�A��t�m���w���t�t  �ޗ�������  �ޗ����������� 2003�N����
*�y�����`�z
�s�����Y���}�`�c�J���A���V�L�V�X���j�y�A�����҃e�y�j���A���R�g�V�i�f���ۃj���e�]�A�u��n�z�j��B�e�҃����B�����]筃c�J���R���B�A�R���ヌ�^���v�g�B�����ّR�g�V�s���A�s���K�@�V�B�P���m�ȉ����E�A�Z�������A�փ����N褰�e�������V�A�ؓ�����Q��f�ǒ��҃��B�����Y�n�A�́X��m�����H�D�m���]�A���F�������q�̖�g�n�j���������A���������A�O�ڃm���n���U�e�A�⃒�����j���Q�A���ۃj���e�����K�߃N���}�t�B�����A���������j�����e�e�H�A�u�����Y���^���B���o���]���⃒�̃��v�g�B�����Y�{�{�e�A�����߃d�N�gꎃN�A�摴���ԃ��Łt *�y��V�L�z �s�r�^�҃c�J���A���U�K�҃����n���J�j���A���R�g�V�e�i�e���ۃj���`�]�A�u��n�z�j��B�e�҃����B�����]筁X�X�����B�ܓ��ヌ�^���J�v�B���U�ґR�g�V�e�s���A���J�U���K�@�V�B�����Y�����U�e�A�⃒�����j���W�A���ۃj���e���U�K�߃d�N���}�t�B���j���U�����j�����}���A�j�c�R�g�e�]�N�A�u�����Y���^���B���o���]���⃒�̃��v�B�����Y�u���e�A���U�K���߃d�N�gꎃN�A�������b�j�U��A���U�K���ԃ��Ńc�t |
|
*�y�]�C�������z
�s���U����ɂ킽�肽������āA���Ƃ������Ђ���A���̐]�̓����ʂ��A���̂�����ɐĊC�ɂ��āA�ؓ������C�ɂȂ����A�M��肠����A���ɗ����Đ�ӁB�@���A�ނ������������͂�ӁA���U�̂т�����āA�_�ɂď@����������łɑœ|���B�����A�@�������̂������A���U�����t�̑O�����͂�ЂāA�͂��܂̂܂֕������G�ɉ�����B���U���������������A�@�������������Ƃ�����A�����W������łāA�����ɑŎE���t *�y�O�����ϕM�L�z �s�v�}�f�����V���n�A��j���J�P�A�T�V�E�c���L�e�������V�K�A�ⓚ�m���j���A�K���A�D���ȃe��������c�O�c���E���ŝc�q�A�u�@���A�����Y�B���V���n���j�A���]�v�g�A���t���������B�����Y�A�g�c�e�ԃV�A��ڎ����m�]�m�������E�j�J�P�A���ԃj�ŐU���A�ʃ��t���Y�J�R���B�ܗ��K��B�m�����j�A���ԃj�U�������g�X�B�d���������ԃj�U�e�A�G�ԃA�^���x�j�A���c�e�����t���o�A�藡���m�@�N��o�V�A�������e�ؓ��j�e�Ńc�N�����g�C�w���B���V�����M�m�D���E�e�m�ʃj�����A���J�R���j�J�R���A�o���A�^���x�j�A���V���A�D���������U��e�ō��~�A�����Y���������ԃ������j�؍��A�݃j�A�^���B�T���������Y�K���A��m���}�n���e�A�����ȃe���V���K���m���E�c�B���V���K�ؓ��n�A�����Y�K���j�A�^���A�^�W�^�_�g��O�ԃV�T���e�A�K���j�h�E�g��X�B���V���A��m�ڃ��Ń��g�����������A�����Y�t�c�g�N�A�K���A���G���c�L�i�K���A���j�c�t�B���V���K�R���T���m�O���n�����g�ؕ��e�A�J���T���O�j�����B���V���A��m�ڃ����V�^�R�J�j�Ńc�B��̓m�R���M�m�D�m�V�^�R�J�i�����ȃe�A���W�c�{����c���Ń^���́A���N�_�P�e�q����Z���t *�y���@��t�`�L�z �s������t�n��j���J�P�A�t���^�_�g�����������V���A�����m�������A�u�ٔV���A�����Y�K�҃��^���]�v�g�߃��|���o�A��t�N���c�g�ڃ��J�L�A��j���J�P�i�K���A�ؓ����ȃe�_�����O�x���E�w�ŝc�q�A�X�c�g���e�A�ؓ����E�e�j��Q�m���\�m�܃c���m�ʃg�]�n�A�X���^�_�g�|�����B�����Y�n�ޗ��m���ԃg�J���]�����j�e�A���m�n�^�j�e�N�����^�_�g�}���V�A�|���n���j���g�A�����Y�ō��g���w�V�K�A��t�n�ؓ����U��Q�e�����Y�K���ԃ��V�^���J�j�Ń��V�j�A�E�m�n���^�����ȃe�Ń��V�́A���j�Ŋ������e�^�a�^�_�g�V�T�������A���ؓ����A�Q�e���W���Ń��V�J�o�A�����Y�A���m�P�j�|���B��t�g�S�����Ń��g�������V���A�����Y�|���i�K���؝c�q�V�K�A�ؐ�j�e��t�m�J���T���m�O���ؗ��V�P�����A�g�j�n�c���Y�A���E�w�k�P�^�������A�D���e�����Ŋ��t *�y�����`�z �s�����Y�{�{�e�A�����߃d�N�gꎃN�A�摴���ԃ����B�����K�����m���ڐ��e�����c�B���i���j�������Ńm�ؓ��A�����Y�K���j�����e�A�����j�K�e�A�����ؓ�����e�b�N���A���U��e�Ń^���g�X�B�����Y��i�K���ŕ��t�B�����K褰�^�����߃m���m�G�m��j���^�������A�Ґ����������X�B���i���j�����K�ؓ��A�����ǃK�e���m�������Ő܃e�A���`����X�t *�y��V�L�z �s�����Y�u���e�A���U�K���߃d�N�gꎃN�A�������b�j�U��A���U�K���ԃ��Ńc�B���U���N���|�m�ؓ��A�����Y�K���j���������j�����B���������Y�K�ŃV�����m�ؐ�A���U�K�����m���ڃj�A�^���e���A��@�������c�B���U�ؓ���Q�e���N���`�A���U��e���^���g�X�B�����Y���i�K�����j���t�B���U�K���m�G�m��j�����^�����A�O�������T�L�k�B���U�K���|�m�ؓ��A�����Y�K�e�����������܃e�A���`����X�B���@�����������o�d�t *�y���q�蕶�z �s�}���\�O����N�����p�̏����Z�\�]��A��Ƃ��ď������閳���B����ĉ]���A�G�̔������̊Ԃ�ł����Ώ�����炸�ƁB���k�ˁl�ɑ��̓I����͂��t |
�b�\�\���Ƃ��w�]�C�������x�ɂȂ��v�f���A�w���ϕM�L�x�ł͑����o�����Ă���B�����L�����w�]�C�������x�͋ɂ߂ĊȌ��Ȃ��̂����A�w���ϕM�L�x�ł͂��Ȃ�̑��₪�݂���B �a�\�\�w���ϕM�L�x�ł́A����܂ŏ����Y��҂��Ă��ނ��Ă����������u�����Y�A����͂����ɂ��邼�v�Ɛ��������A����Ŏ����J�n���B�������A�ޗ��̔�`�̑����ɁA���ԂɐU�鎖����Ƃ���B�d���������ԂɐU���āA�G��������x�ɁA����������U��o���A�藡���̔@������A�������Ă͖ؓ��őł����鎖�Ɖ]���A�\�\�ȂǂƂ������������B �`�\�\�w�]�C�������x�ł́A�@�����D����݂ɏオ��ƁA�����ɏ������͂��܂�B �b�\�\�������ˁB�w�]�C�������x�ł́A�܂��s�@���A���U�������Ȃ��蕥�Ђ���t�Ƃ���B�u�Ȃ���v�͉���ł͂Ȃ��ギ��ŁA���ɕ����Đ邱�ƁB�@�����r��_���ĉ��ɕ����������A�����͔�яオ���Ă��킵�A��ꌂ�ŏ@���̓���ł��ē|���B���̂Ƃ��@���̌��������̗��t�̑O�����B�����̑�́A�N�オ��@���̓���������x�łB����ŏ@���͐▽�B�������{�I�ɂ́w���ϕM�L�x�����l�����A���e�͑傫���c���ł���B �a�\�\�����ǂނƁA�����Y�����Ă�����ƕ������M�̟D���E�e�̈ʂɝ����A�������U���������o��������x�ɁA�����͟D��������U��グ�đō��݁A�����Y�����𐅎Ԃ���܂������ɐ؍��ށB�ƁA�݂ɓ��������B����ǂ������Y�̓��͎�̗�����]���āA���i�n�̑��ʁj�ŕ����̍��̕���i�ʁj��łB�����̖ؓ��́A�����Y�̓����ɓ�����A�����Y�͂��������Ɠ�O�ԁk�l�`�܂��l��ނ��āA�K����ǂ��Ɠ|�ꂽ�B���������ł���Ɨ����Ƃ�����A�����Y�A�ӂ��ƋN��������A���G�������܂ܓ������ɕ����B�����̃J���T���̑O�����n�����Ɛ�����āA�J���T�����O���ꂽ�B�����̑�͋��ŁB��͂ŁA�������M�̟D�̋��łȂ��̂ŁA�����c�{���x���ł����̂ŁA�����Y�̓��͍ӂ��āA�Ђ�炷�悤�ɑO�̂߂�ɓ|�ꂽ�\�\�Ƃ������悾�ȁB �b�\�\���̂悤�ɁA���e�̑���͂��Ȃ�傫���B�����Ȃ�A�w�]�C�������x�Ɓw���ϕM�L�x�̊Ԃ̐��\�N�̂������ɐ��b�����i�̂����A�ǂ����ǂ��c����͈�ڗđR���낤�B �`�\�\������x������t�H���[����A�����������������̂ŁA�����Y�͕����̕��֎���ĕԂ��B���悢��ΐ�ŁA�����Y���肩����B��قǂ̘b�̌J�Ԃ��ɂȂ邪�A�����Ő��b�̎菇�Ƃ��āA�����Y�̐�@���������ˁB �b�\�\�����Y�̋Z�́u���ԁv�ł���Ƃ����B�C���[�W�Ƃ��ẮA�呾�����А��悭�u���u����]������悤�����A�K�����������������̂ł͂Ȃ��B�w���@��t�`�L�x�̌��悤�ɁA���̘e�ł���肭���Ƃ����̂ł��Ȃ��i�j�B �a�\�\�����̃P�[�X�����������A���Ԃ͕Ԃ��Z�ɈӖ�������B�܂葾����O�������U��Ԃ��B���̂Ƃ���������⓷���B���������ς�ؒf����̂��Ԑ�B����́w�����L�x�ɂ���B�Ƃ�����A���Ԃ͐�Ԃ��Z������A�����Ă��̊ޗ����̋L���́A�����̉����g�̒��߂���ꂽ���ƂɂȂ��Ă���B �`�\�\���ɂ��������Y�́u���Ԃ��v�ɂ������͂���킯���i�j�B�w���ϕM�L�x�ł͂���ɂƂǂ܂炸�A�d���������ԂɐU���āA�G��������x�ɁA����������U��o���A�藡���̔@������A�������Ă͖ؓ��őł�����\�\�Ƃ����L��������B �a�\�\�����ŁA�����ꂽ�Ƃ�����̎d�������o�Ă���B����ŁA�d�������ǂ��g���邩�A�킩��B�܂�A�d�����͌�����яo���d�|��������A�ԍ����������Ă��A���ꂪ�U��o�����ōU���ł���B����͎藠���̂悤�ɔ�яo���B�ԍ������l�܂�ƁA�d�����͖ؓ��Ƃ��ċ@�\����B �`�\�\���ߗ��p�̕���Ȃ̂ł���i�j�B �a�\�\���̎d�����̐U��o���̂Ƃ��A���Ԃ̋Z���g���B�d�����͕s�ӂɔ�яo��������ʂ�����̂ł����āA�u���u���U����̂ł͂Ȃ��B����Ȕn�������C���[�W�ɂȂ��Ă��܂��̂́A���ԂƂ����Z��������邩��ł���i�j�B �b�\�\������A���n�`�L�ł́A�����Y�̑�ꌂ�͕����̔��Ԃ��P���B���ꂪ�����̔����̌��іڂ�ؒf�����B����͏�i�����C�ɑ�����U�艺�낷���̂ł��낤���A��������ԉ]�X�̘b���炷��ƁA�����ς���Ȃ����ȁB���Ԃ̔�Z���J��o���O�ɁA�����|���̑O�Z���q�b�g���Ă��܂����Ƃ������ƂɂȂ邪�i�j�B�ǂ����ˁB �a�\�\����Ƃ��A���n�ł͐��ԉ]�X�̘b�͂܂������o�Ȃ�����A�ʌn���̌��@�ł���̂��B �b�\�\���Ƃ���A�}�O�n�`���Ɣ��n�`���ł́A�����Y�̌��@���ꎩ�̂��Ⴄ�Ƃ������Ƃ́A�O���ɂ����Ă����ق����悢�i�j�B �a�\�\���Ԃ�łƂ����̂́A�s�G�̔������̊Ԃ�ł����Ώ�����炸�t�Ƃ������q�蕶�̋L�����炷��A����͕����̐�@�B���n�`���͓��e�ɖR���������ł͂Ȃ��A�퓬��ʂ��ĊO���₵���B |
|
�`�\�\�����Y���d�����āA���������킷��B�ޗ����`���̋L�q�͂ǂ���A�����ɂ��ςĂ����悤�Șb�ł��邪�A�����͈�ʂ�ǂ�ł����܂����ȁB �b�\�\�܂����q�蕶�́A�ŏ����̕����`�L�ŁA����͋L���������Ƃ��V���v�����B�㐢�̂��̂̂悤�ȍu�k��ɂȂ��Ă��Ȃ��B���ɔ�r�I�Ȍ��Ȃ̂́A�w�]�C�������x�Ɓw��������L�x�����A���̓̓����́A�������яオ�点�Ă������Ƃł���i�j�B �a�\�\�������A�w�]�C�������x�͈ٖ̂{���ˁB��X�̎Q�Ɩ{���ƁA�u�Ƃт�����v�ł͂Ȃ��A�u�̂т�����v���B�u�̂т�����v���u�Ƃт�����v�Ɣh��ɂȂ����B �b�\�\��̂��̂قǔh��ɂȂ�i�j�B�Ƃ�����A�����͑��肪���ɕ������������킵�āA��яオ�������ƂɂȂ�B����������́A�����̗��t���邢�͔�т���ꂽ�Ƃ������b�f�Ɏh������Ă̔��W�`���낤�ȁB�W�����v����Ζ��h���ɂȂ邩��A��т����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B����́A���łœ|���ꂽ�����Y���A�G�������܂ܑ��������ɕ������Ƃ����w���ϕM�L�x�̕����ނ��炵���B �`�\�\����Ō���Ɩ��炩�Ȃ悤�ɁA�w�]�C�������x�ł͏����Y�̑ł��́A����Ȃ��B �a�\�\�����ɒ��ڂ��ׂ����ȁB�w���ϕM�L�x�ł́A�����̑ł������ł���̂́A���Ɠ����B�Ƃ�����A�w�]�C�������x�Ɓw��������L�x���w���ϕM�L�x�̋L���Ƌ��ʂ���̂́A�@���������͊ݗ��̓����ւ̒v���I�Ō��A�����ĉ��ɕ����������ŕ����̗��t���邢�͔�т���ꂽ���Ƃ��B���̓�͊�{�I�Ȑ��b�f�ł������炵���B �b�\�\�������A���҂ɔ䂷��A�w���ϕM�L�x�̓��e�͂��Ȃ芮������u�[���v���Ă��܂��Ă���i�j�B�܂��J�Ԃ��ɂȂ邪�A������x�ǂ�ł������ˁB �a�\�\��낵���i�j�B�������M�̟D���E�e�̈ʂɝ����A�������U���������A�o��������x�ɁA�����͟D��������U��グ�đō��݁A�����Y�����𐅎Ԃ���܂������ɐ؍��ށ\�\�Ƃ����̂��U���̉��V�B���Ă��̏�ʂŁA�E�e�̈ʂɍ\���āA�Ƃ������Ƃ́A����͂ǂ����A�Q�ƌ����w�ܗ֏��x���V���ɂ����u�E�e�̍\���v�̂悤���ȁB�E�̘e�ɉ��ɍ\���āA���肪�ł�������̂ɉ����āA�䂪�������E���̉���������ɏ�i�ɐU�グ�A�����ďォ��h�J�b�Ƒł킯���B �`�\�\�����Y�����𐅎Ԃ���܂������ɐ؍��ށB����ƁA�݂ɑ���ɓ��������B�Ƃ��낪�A�ǂ��������̂��A�����Y�̓��́A��̗�����]���Ă��܂��āA�n�ł͂Ȃ����i�Ђ�E�n�̑��ʁj�ŁA�����̍��̕���i�ʁj��łB����ɑ��A�����̖ؓ��͏����Y�̓����ɓ��������B�����Y�́A�^�W�^�W�Ɠ�O�Ԍ�ނ��āA�K����ǂ��Ɠ|�ꂽ�\�\�B �a�\�\�����Ƃ����Ԃ̏o�����ŕ��͂��Ă���ɂ���������܂����i�j�A�����܂łŏ����������Ƃ����Ƃ��낾�ȁB�����Y�̌��͕����̎����������͂����������A�܂��Ɏ茳�������ĕ��ł����Ă��܂����B����Ɠ����ɏ�i����u�`�������̖ؓ����A�����Y�̓����q�b�g�����B �`�\�\�Ō��͓��������A�����̍U�ߏ����ł���B �a�\�\�����Y���K���������ē|�ꂽ�̂ŁA�������ܕ�������̖ځi��j��łƂ��Ƌߊ��u�ԁA�����Y�͂ӂ��ƋN��������A���G�������܂ܓ������ɕ����B�����������Y���ԍ������킸���ɔc���ł��Ȃ������炵���A�����͕����̓���ؒf�����A���������̃J���T���i�Z�сj�̑O�̕������n�����Ɛ�����āA�J���T�����O���ꂽ�B �`�\�\�����̓�̖ځi��j�͋��ŁB���������Ⴂ�ʒu�ɂ��鏬���Y�̓����A�����̑�͂ŁA�������M�̟D�ō�������łȖؓ��i�B���т�����ō���ł���j�ŁA�����c�{���x�܂őł����̂ŁA���͍ӂ��āA�����Y�͂Ђ�炷�悤�ɑO�̂߂�ɓ|�ꂽ�c�B �b�\�\�����݂�ƁA���Ȃ��̓I�ȏł���B���Ԃ�w���ϕM�L�x�̓`����������ڂ������낤�B���������e����̓I�������قǁA���̓`���Ƙb������Ă���̂��A���̂��̍������番�����b�����炾�낤�B |
*�y���q�蕶�z
�s�◬�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂���A�����ڂ݂��p��s�����B���U�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���P�x���t *�y�]�C�������z �s�@���A�ނ������������͂�ӁA���U�̂т�������A�_�ɂď@����������łɑœ|���B�����A�@�������̂������A���U�����t�̑O�����͂�ЂāA�͂��܂̂܂֕������G�ɉ�����B���U���������������A�@�������������Ƃ�����A�����W������łāA�����ɑŎE���t �i�ٖ{�j�s�@���A���U�������Ȃ��蕥�Ђ���A���U��т�������A�ޖ_�ɂď@��������łđœ|���t *�y��������L�z �s���U���g�e�J�R���o�A�ݗ��q�Ńj�a�����A�E�P�n�d�V�e���m�����Ńj�A�ݗ��g���t���e���m���j�����B���m���j�t�~���e�A���j���t�B���U�����k�e��A�K���o�A��уm���O���o�J���e���^���B���U�S�̓��o�V�e�ŔV�j�A�����o�j�Ӄe�A�����j���X�B�ݗ��K�惒�z�e���j���ՃA���t *�y�O�����ϕM�L�z �s�����Y�A�g�c�e�ԃV�A��ڎ����m�]�m�������E�j�J�P�A���ԃj�ŐU���A�ʃ��t���Y�J�R���B�ܗ��K��B�m�����j�A���ԃj�U�������g�X�B�d���������ԃj�U�e�A�G�ԃA�^���x�j�A���c�e�����t���o�A�藡���m�@�N��o�V�A�������e�ؓ��j�e�Ńc�N�����g�C�w���B���V�����M�V�D���E�e�m���j�����A���J�R���j�J�R���A�o���A�^���x�j�A���V���A�D���������U��e�ō��~�A�����Y���������ԃ������j�؍��A�݃j�A�^���B�T���������Y�K���A��m���}�n���e�A�����ȃe���V���K���m�������E�c�B���V���K�ؓ��n�A�����Y�K���j�A�^���A�^�W�^�_�g��O�ԃV�T���e�A�K���j�h�E�g��X�B���V���A��m�ڃ��Ń��g�����������A�����Y�t�c�g�N�A�K���A���G���c�L�i�K���A���j�c�t�B���V���K�R���T���m�O���n�����g�ؕ��e�A�J���T���O�j�����B���V���A��m�ڃ����V�^�R�J�j�Ńc�B��̓m�R���M�m�D�m�V�^�R�J�i�����ȃe�A���W�c�{����c���Ń^���́A���N�_�P�e�q����Z���t |
| �@ | ���ϕM�L | �]�C������ | ��������L | �����`�E��V�L |
| �����Y��ꌂ | �����̎�@���ł� | �����̐��� | �q�ݑł��Ɏa�� | �����̔��ԁ@�����͂�� |
| ������ꌂ | �����Ō� | �����Ō� | �����@���킳��Č� | �����Y�̓��� |
| �����Y��� |
�G�������܂� ���ɕ��� | �\�\ | ������ʼn��ɕ��� | �|�ꂽ�܂܉��ɕ��� |
| ������� | �\�\ |
��т����� �i��ꌂ�j |
����� �i��j | �\�\ |
| ���ߐ؏����� |
�J���T���̑O�� �i��j |
���t�̑O�� �i��1���j |
��т̐��O�� ����i��j |
���������������̐� �O������i��j |
| ������� | �����Y�������� |
�����Ō� �����ɑŎE�� |
�������� �����Ɏ��� |
�e�������� ���C�� |
|
*�y�����`�z
�s�����Y�{�{�e�A�����߃d�N�gꎃN�A�摴���ԃ��ŁB�����K�����m���ڐ��e�����c�B���i���j�������Ńm�ؓ��A�����Y�K���j�����e�A�����j�K�e�A�����ؓ�����e�b�N���A���U��e�Ń^���g�X�B�����Y��i�K���ŕ��t�B�����K褰�^�����߃m���m�G�m��j���^�������A�Ґ����������X�B���i���j�����K�ؓ��A�����ǃK�e���m�������Ő܃e�A���`����X�t *�y��V�L�z �s�����Y�u���e�A���U�K���߃d�N�gꎃN�A�������b�j�U��A���U�K���ԃ��Ńc�B���U���N���|�m�ؓ��A�����Y�K���j���������j�����B���������Y�K�ŃV�����m�ؐ�A���U�K�����m�����j�A�^���e���A��@�������c�B���U�ؓ���Q�e���N���`�A���U��e���^���g�X�B�����Y���i�K�����j���t�B���U�K���m�G�m��j�����^�����A�O�������T�L�k�B���U�K���|�m�ؓ��A�����Y�K�e�����������܃e�A���`����X�B���@�����������o�d�t |
�`�\�\���Ɂw�����`�x�w��V�L�x�̔��n�̓`�����݂�ƁA�ŏ��������Ă���B �a�\�\�܂��A�����Y�̑��ł͕����̔��Ԃ�łB����ƁA�����̔������n�����Ɛ�ė�����\�\�B�܂������u�k���ɂȂ��Ă��邪�A����͖��炩�ɁA�����̃J���T���i���t�j�����đO�ɐ��ꂽ�Ƃ������b�f��ό`���Ĕ������Ă���B�ނ��A���n�`���ȊO�ɂ͌�������Ȃ��L�����ȁB �`�\�\���������A�������O���т̔��������Ă���̂��A���������̂���i�j�B �b�\�\���̂Ƃ��A�����̑�ꌂ�͏����Y�̓���łB�����������Y�������ɑ���̓����U���������ƂɂȂ�B����Ō�����|�ꂽ�����Y�����ɕ����A�����̈��̐����O������藎�Ƃ��\�\�B����́w���ϕM�L�x�Ƌ��ʂ�����b�f�����A��ꂽ�̂̓J���T���ł͂Ȃ��A���̐��ł���B �a�\�\�Ƃ����̂��A�����������n�`���ł́A�����̓J���T���◧�t�ȂǒZ�т̗ނ͒����Ă��Ȃ������B���̐��������������Ă���Ƃ������D���B���t�i���v�����j������Ă���̂͏����Y�̕��ȂȁB �b�\�\��O�_�B�w���ϕM�L�x�Ȃǒ}�O�n�`���ł́A�����Y�ɂƂ��Ēv���I�ȁA�����̑�́A�����ւ̍ēx�̑Ō��B����ɑ����n�̓`���ł́A�e���̉�����Ő܂�Ō����B����ŏ����Y�͋C�₷�邪�A���炭���āA�����������Y�̌��@�Ɏ�āA�������m�F�����Ƃ����B �a�\�\�������A���̃f�B�e�[���͈Ӑ}�I�ȞB�����ŁA�����Y���▽�������ۂ��͕s�����ȁB�܂��A���n�`���ł́A���ӂ����ȂǂƂ����I���ȕ\����������ꂽ�����łȂ��A�e���̉�����Ő܂��₳�����Ƃ�����֕ό`���ꂽ�A�Ƃ������Ƃ��B �b�\�\�܂��A�ꌩ���Ė��炩�Ȃ悤�ɁA���^�ƂȂ������b�f�̂������͕ό`����Ȃ���ۑS����Ă���B�����𒊏o���āA�ޗ��������`���̑c�`���č\�����Ă݂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����͕ʂ̌�����Ƃɂ����Ď��{�����B �`�\�\�����ʼn��߂Ċm�F���Ă����ׂ����Ƃ́A�w���ϕM�L�x�Ɣ��n�`�L�������̂́A�o���Ƃ����Ȃ萬�������`���ŁA�������傫���Ⴄ���e�����Ɏ����Ă��邱�Ƃł��ȁB �b�\�\�����������܂ł��Ȃ����Ƃ����A�w���ϕM�L�x�Ɣ��n�`�L�̂ǂ��炪�j���ɋ߂����A�ȂǂƂ������́A���̐ݒ莩�̂ɍ��낪����B����������łɎj���𑈂��悤�Ȓi�K�̋L���ł͂Ȃ��B��X�͕����`���̔����Ɛ������m�F�����邾���ȂB �`�\�\�����������q�蕶�ɂ́A�s���U�A�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���A�P�x���t�Ƃ����L�������Ȃ��̂��A�����܂Řb�����B��̉������Ƃ������Ƃ��i�j�B |
|
�b�\�\�������āA�܂��b������i�j�B�����Y��|������A�����͂ǂ��������B�w���ϕM�L�x�ɂ��A�������ޗ�����b�Ƃ������ׂ����e���������ˁB �`�\�\�����͂܂��A�����Ă����J���T���i�Z�сj��E���̂Ă��Ƃ����B���ꂪ�ʔ����b�ł��ȁB �a�\�\�����́w���ϕM�L�x�̓ƒd��B�Ƃ����̂��A�܂��́u�{�^���v�Ƃ����ꂪ�����ɏo�Ă���B�u�J���T���v���|���g�K����Ȃ�A���́u�{�^���v���|���g�K����B�����ł��{�^���́A�ߗނɂ��Ă���A���ł���B�u�J���T���̃{�^���v�͊O���ꂻ�̂܂܂̗p��@���ˁB�J���T����E���ɂ̓{�^�����O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���E���{�^���Ɋւ��Ƃ́A��͂�J���T���͗����тƂ͈���Ă����킯���B �b�\�\�J���T����E���Ƃ́A�Y�{����E���悤�Ȃ��̂ŁA�\�\���������́u�Y�{���v�̓t�����X��Ƃ��Ă��邩��A�b����₱�����Ȃ�B�܂��A����ł��A�����Y��|�����������A��Ԃɂ�������Ƃ̓J���T����E�����Ƃ������A�Ƃ����̂��ʔ����B �`�\�\�ł́A�Ȃ��A�����͉����g�ɐ����Ă����J���T����E�����̂��B�ǂ����āA����ȁA����̎������炷��\�\��ȍs���������̂��B �b�\�\����ɂ͗��R������킯���ˁB�ЂƂ́A�J���T�������đO�ɐ���Ă��܂����B���ꂪ����܂Ȃ̂ŒE���̂Ă��B�����ЂƂ́A���̑ΐ�ŁA�����Y�������ɗ^���������������A��������邱�ƁB�����Y�̑����͕����������Ă����J���T��������B�������A���ꂾ���������ƁB �a�\�\�悤����ɁA�����Y�̓J���T��������������ƁB�����̒��ڂ́A�����Y�̑�����������������ǂ��������A���ꌩ��A����̉����g�ɂ͉��̕������Ȃ����A�ƁB������A���̐K���܂�Ő����܂����āA�����ɖ��������i�j�B �`�\�\�����g�O����I�o���āA�ł��ȁi�j�B�����ŁA�w���ϕM�L�x���q�ׂ�͔̂�b�B�܂�A�����Ō����̂́A����͂͂�������u�̏�ʂ̂��Ƃ������̂ŁA��������̏�ł�������͂���Ȃǂł��Ȃ������B�Ƃ��낪���́A�����Y�̑����͕��ł��Ȃ���A�o������قǕ����̎��ł��Ă����B�����͉����݂̋��o���ď����B�����A�Ƃ����閧�̘b�ȂB �b�\�\����䂦�A�����͂��̂܂܉B���ł���i�j�B�w���@��t�`�L�x������P���Ă��邪�A�����͎��g�̎�̏o���������Ȃ��悤�A�����܂����ďO�l�̎����������g�̕��ֈ�点���B�Ƃ���A�����g�̕����Ȃ��������ɖ������������̍s�ׂ́A�B���Ƃ��ċ@�\����B �`�\�\�Ȃ�قǁA���̂�����A�}�O�n�́w���ϕM�L�x��w���@��t�`�L�x�����L���́A�Ȃ��Ȃ��悭����Ă���܂��ȁB �a�\�\���������u������m��Ȃ��͂��̔�b�v�Ƃ́A���͌��R�̔閧�ł����āA�m��ʎ҂��Ȃ��Ƃ�����ނ̔�b�i�j�B���ꂪ�`���̌��̒��ŁA�l�̎������Η���������ʂނƂ����̂́A���ꂱ���A��蕨�̓`���̒��ŗp������퓅��i���ȁB �b�\�\����������A�w���ϕM�L�x�̓`���͏\���ɐ��b�����i��ł���B��������A���Ȃ��珬���̂悤�ȏ�ʂ����Ă���̂����R�ŁA��q�́A�����͏����Y�̓�����҂������A�����Ƃ��ނ��Ă���Ƃ����V�[�������̗Ⴞ���A�����ł��A �@�@�s�����m�݃��o�V�A�r���B�T���^���g�J���t �Ƃ��悤�Ȑ▭�̌ċz�������Ă���ˁB���������Ƃ��납�炷��A�����͂��낤���ď������A�Ɠ`���͋����������Ƃ��낾�B�����ŁA���̔�b�̃|�W�V�����́A�ޗ����̋ߕӂŌ��`����ꂽ�`���A�܂菬���Y�ɐS��I�ɉ��S����`����c�`�ɂ��Ă���͖̂��炩���ˁB �a�\�\�܂肾�A�����Y�͕����ɔs�ꂽ���A����ł������̕����ł����B���������茳�������������ŁA���������̂Ƃ���ŕ����̎�ԂƂ��낾�����B�\�\�������āA�����Y�͂قƂ�Ǖ����ɂЂ����Ƃ�ʒB�l�Ƃ��āA�܂��Ɂu�L���v�Ɏc����u�L�O�v����邱�ƂɂȂ�B �`�\�\����������b�́A�����ɑ���`���̃N���e�B�V�Y���A��]���B�܂�A�����Y�������ɕ������Ƃ��������ɑ���A���̃v���e�X�g�ł��ȁB �b�\�\���邢�͂܂��A�u����������ǁA�����ĕ����Ȃ������v�Ƃ����۔F�̐g�U�肾�ˁB�c�`�ƂȂ����`���ł́A�����Y�͒���̍��l�A�n���̐l�ԁB���ꂪ�ِl�E�{�{�����ɑ��P�킵�����Ƃ́A�ǂ����Ă��������ׂ��v�_�ȂB �`�\�\����ɑ��w���ϕM�L�x�́A���������n���̓`�����E���Ă����Ȃ���A�w���̕���x�ӂ��́s�Ƃ���t�Ƃ��������Ȍ����ŁA�����ό`���Ă���Ƃ��낪����B �b�\�\�Ƃ��낪�����A���łɌ����悤�Ɂw�����`�x�w��V�L�x�Ƃ������n�`�L�ł́A����ȕ����̎�o�����Ă����Ƃ����f�B�e�[���͂Ȃ��B���̑���ɁA�����̓�����ł��������Y�̑����́A�����̔�����藎�Ƃ����A�Ƃ����ό`�������B������A����ł̂Ƃ���ŕ����͊�Ȃ������Ƃ����킯�����A�����������������B �a�\�\�܂�A�����Y�͋��������A�����������͂���ȏ�ɋ��������A�Ƃ����b�Ȃ̂ŁA����͏����Y�ł͂Ȃ��������̗g������ɏd�S������B�悤����ɁA�w���ϕM�L�x���n�������Y�`���̍��Ղ�Z���Ɏc���Ă���̂ɑ��A���n�`�L�ł́A�����������Ղ͈�|����Ă���킯���B |
 ��؛����̃J���T�� �{�^�������Ă���
*�y�O�����ϕM�L�z
�s���V���A��m�ڃ����V�^�R�J�j�Ńc�B��̓m�R���M�m�D�m�V�^�R�J�i�����ȃe�A���W�c�{����c���Ń^���́A���N�_�P�e�q����Z���B���V���n�J���T���m�{�^�����O�V�A�J���T�����J�i�O���̃e�A�K���c�~�}�q�e���N�J�R�Q�A�����Y�K�������惊�A�M�m���j�Ń}�^�K���e���߃��B�n�W���J���T�������Z�^�����n�A���l���y���w�A���N�J�R�Q�A����j�A�^���^���n�A�n�Q�V�L�ꃆ�w���̓P�^���҃i�V�B�����K���Ńi�K���A�V�^�R�J�j�Ń^���j�����A�������n���V���A�����m�݃��o�V�A�r���B�T���^���g�J���t *�y���@��t�`�L�z �s��j�����Y�K�Ń^�������A��t�m���j�ō��A�l�ܕ����P�����A��t���Ӄ��ȃe�A�����Y�K�ʃ��T�V�e�ؓ����g�����V�́A�����Y�K�g�ネ�w�m���e�ŃV�́A�؎��i�V�B���V�m���i�K���������P�����A�ꃀ�N�m�����m�G���j�e�B�T���V�́A�����l�����m���U���P���g�]�B�J���T���m�O�ؗ��V�^���n�A�l�m���^�����i���o�A�Ў�j�����A�Q�A�M�j�m���A�����P���t  �ɔ\��}�@�M���L�ڂ��� |
|
�`�\�\���̕����̕����Ƃ������ł́A���n�`�L�ɁA�������Șb������B��ɕ��������F�{�ɏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ��A����N�̐����O���̔ӁA��w���߂̎��̂��ƁA�������u�������������ɕ�������ꂽ�Ƃ����b�ł��ȁB �a�\�\����́A�����Ƃ��D��ň��������ɏo����b���ȁB�d�b�u�����˂������ɁA���s�ŋg�����\�Y�Ƃ̑ΐ�̂Ƃ��A�g������ɕ�����ł����ƕ��������A����͂ǂ��ȂA�Ɛq�˂��B����ƕ����́A�����������A�Y���Ɨ����ĐC�������ŁA�u�����˂̑O�ɍ����Č����A�u���͗c���̎��A�����mᝁi�͂��j���ł��āA�������ƌ��ꂵ������A�y���ɂ��Ă����B���\�Y�Ƃ̎d���̎��A�ނ͐^���Ŏ����͖ؓ��������B���\�Y����ɑł����Ƃ����Ȃ�A�������͐^���ł���A���R�A�r�����c���Ă���͂��B���������邩�A�悤�����Ȃ���v�Ƃ����āA����ɐC��������A�E��Ŏ����̔��������킯�āA�����˂̊�ɓ˂������B���˂́A�����ɋC������āA�̂������āA�u�r���͌�������Ȃ��v�B�u�������育���Ȃ����v�ƕ����B���˂��u�Ȃ�قǁA�Ƃ��ƌ��͂����v�Ƃ����ƁA�����͒��ɗ����A�C������̂Ƃ���֖߂��A���������̍��ɂ��āA���������ȂłāA����Ƃ��Ă���B����̏��m�́A��Ɋ��������đ����l�߁A��l���@��������҂��Ȃ������B�u���˓a�ꐶ�̕s�o�Ȃ�v�ƁA���̂���ᔻ���������Ƃ������Ƃ��\�\�Ƃ����b���A�w�����`�x���L���Ă���B�Ƃ��낪�A�w��V�L�x�ł́A�b�͂܂����������ŁA���̑ΐ푊�肾��������āA�g�����\�Y���◬�ɂȂ��Ă��܂��Ă���i�j�B |
 ��Ԕ��i�א쒉���̋��فj�����͌^ |
|
�y�����`�z ���N�����ғ��A��w���m�ӁA������O�����g�V�e�����O����������j�e�A���������ȃj�A���B��鎮���n�j���J�g�Řb�m���A�u�����˓a�m��������i���n������\��n�A�u��N�g�����\�Y�g�d���m���A�g���惒�Ń^���R�v������K�A�@���j�e��Ɓv�g�A���B�����A�e�p���ԓ��A�Y���h���e�C�i���c�e�A���˓a�m�G���j�c�J�g���V�A�u���c���m���A���j�n�X�k�mᝁl�o�҃e�A���ヒ�䃊�o����V�N��j���A�y���j�e����B���\�ǎd���m���A�ރn���������n�ؓ��j�e��B�����j�e�惒�Ń���n�S�r���݃x�V�B���l�k�Ƃ��Ɓl�䗗��v�g�A���m��j�C�i���c���A�E�m��j���J�L���e�A���˓a�m��j�c�L�������B���˓a�A�m�c�P�j�\���e�A�u�r�����w�s�\�v�g�A���B�i���U�j�u�V�J�g�䗗��Ɓv�g�A���B�i���ˁj�u�i���z�h���x�k�Ƃ��Ɓl���͌�v�g�]�g�L�A�i���U�j���j���`�ナ�A�C�i�����V�A���g�m���j�c�L�A���J�L�i�f�e����^���B����m���m�A��j���������A��l���@�����X���҃i�V�B���˓a�ꐶ�m�s�o��g�A����ᔻ�݃V�g��B�_�������m���i���B |
�y��V�L�z ���N�����O���m�ӁA��Ԕ��j���e��w���m���A�e����j�e���U���L���B�K�����n�A���J�j�ߗL���B�R���j�A�u�����˓a�m������g���i���n�A����������U�j�H�N�A�u�M����N�◬�g�����A���V���A�◬��j�Ń^���R�A�����@�ށB���ʃ��m�l�q�j�e�L���V���v�g�q�����B���U�g�J�N�m���i�N�A���e�C�i���惊�A���˓a�m�G�{�j�c�J�g���V�A�u��c���m���A�@���g�]��v�V�A�����L�e�����A�y���i���B�◬�g�����m���n�A���n�����A��n�ؓ��i���B�����j�e�惒�Ń��V�i���o�A�r�ՃA���x�V�B�\�N�䗗�L�v�g�A���m��j�e�C�i���惊�A�E�m��j�e�����~���P�e�A������j�˃J�R���B���˓a�A�ネ�j�����e�A�u�r���G�s�b�v�g�i���B�i���U�j�u�܁k�����l�ƌ䗗�L�׃V�v�g�]�B�i���ˁj�u�������x�����P�\�V�^���v�g�B�i���U�j���m���j���e�A�C�i�����V�A�{�m���j�c�L�A���~���e����g�V�e�݃��B���i�j�j����m���m�A��j���������A�@���X���҃��i�N���G�^���B�����ˈꐶ�m�e����g�A�����ᔻ�L�V�g��B |
|
�b�\�\������㎞��̂��Ƃ�����ˁA���n�`�L���ł��M�ߐ��������Ă�����ׂ��Ȃ��A����������`���������ɐ������Ă��邱�Ƃ̒������ȁB��b�̃t�H�[���Ƃ��ẮA�u�����˂�����肱�߂��Ƃ������b�f���������B�Ƃ��낪�A�ΐ푊�肪�g������◬�֒u������Ă���B���b���e�ł͂Ȃ��A��̂̕������ӓI�ȂB����́A�\�����I����ɂȂ�ƁA�ޗ������������ԂŗL���ɂȂ��āA����ɏ���������Ƃ������Ƃ���Ȃ��̂��i�j�B�`���͐��Ԃ̉e�����Ă������������̂�����B �`�\�\�������A�u�����˂Ƃ����낤�҂��A����Ȃ��Ƃ����邩���ȁB �a�\�\���܂�N�������Ȃ����Ƃ����ǁA���̎u�����ˁi1573�`1649�j�́A�������o�����܁k���Ƃ����l�̖��Łw���ә��x��w�p�Y�S��x�i���p�Y�S�l���j�ɂ��o�ꂷ��A���E�Œm��ꂽ�l������B�e���̎u�����ː��v�͔����哪���߂ĘZ���H�d�b�����A���j���o�����܂����i��\�N����c����N�Ɏ��ʂ܂ŁA�����哪�B�O�֖v��͔�����a���������Ƃ�����B�����Ɖ��ՂŘQ�l�ɂȂ����A�����א�Ƃɏ���������悤�z���������B�Ȃ��Ȃ��̐l���Ȃ�B�u�����˂͕������\�Έȏ�N�����B�������Ȃ��Ƃ����\�ɂȂ��Ă���B�V�����p�Y���B����Ȕނ��A���������ċt�ɂ�肱�߂�ꂽ�Ƃ����̂́A�ǂ����A�^���ɂ�����b���ȁi�j�B �b�\�\�������o�������u�����˂��B����ȉp�Y����肱�߂������A�L���ȓ������o����肷���������A�Ƃ���������́A���̓�V�ꗬ���ӂŔ��������ɉ��`�����낤�B �a�\�\���������A����ȂƂ��낾�B�������o�J�ȏ����Ƃ�{���N���ǂ����A���̔��n�`���ɂƂт��āA�����́u���X�Ȑ��i�v�������D�Ⴞ�Ƃ���B����Ȃ��킲�Ƃ������O�ɁA�����������̐��b�ɐM�ߐ������邩�A������l����Ƃ����i�j�B �b�\�\�܂���������B�܂��A���̐��b�͔������ȁB�������A�w�����`�x�̋g�����\�Y���A�w��V�L�x�Ŋ◬�ɂȂ��Ă��܂��̂ɂ��A���܂������̂��i�j�B���n�`���͂ǂ������b�_�I�u���������ӂ炵���B |
 �������o�����܁i�u�����ˁj ���p�Y�S�l��� |
|
*�y�O�����ϕM�L�z
�s���V���A��m�ڃ����V�^�R�J�j�Ńc�B��̓m�R���M�m�D�m�V�^�R�J�i�����ȃe�A���W�c�{����c���Ń^���́A���N�_�P�e�q����Z���B���V���n�J���T���m�{�^�����O�V�A�J���T�����J�i�O���̃e�A�K���c�~�}�q�e�A���N�J�R�Q�A�����Y�K�������惊�A�M�m���j�Ń}�^�K���e���߃��B�n�W���J���T�������Z�^�����n�A���l���y���w�A���N�J�R�Q�A����j�A�^���^���n�A�P�n�V�L�ꃆ�w���̓P�^���҃i�V�B�����K���Ńi�K���A�V�^�R�J�j�Ń^���j�����A�������n���V���A�����m�݃��o�V�A�r���B�T���^���g�J���t  �|���̈�{�����̂���ٍ��D  �����𗧂Ă��������M |
�b�\�\�b��߂����B�����ł�����A�w���ϕM�L�x�̂��܂̕����̋L���ɂ��Ė��ɂȂ�̂́A�s�����Y�K�������惊�A�M�m���j�Ń`�}�^�K���e���߃��t�Ƃ���Ƃ��낾�낤�ˁB �`�\�\���̕����͂�����Ɠ���ł��ȁB�ǂ��ǂ݉������B �b�\�\�M�̒��Ƃ����͔̂����B��������������A�����̏M�͔��D�������̂��A����ǔ����Ɂu�����ׂ�v�Ƃ͉��Ƃ��悭�킩��Ȃ��C���[�W���A�����͊ԈႢ�Ȃ̂ł͂Ȃ����A���邢�͌�`��ʂł͂Ȃ��낤���A�ȂǂƂ��������z���o���������A�v����ɂ���͊̐S�ȓ_��m��Ȃ����炾�B �a�\�\����m��Ȃ����A�Ɖ]���A�����̏M�͔�����|�����Ƃ��ł����A�Ƃ����|�C���g���ȁB �b�\�\�����ȂB��������Δ����𗧂āA�����Ȃ��Ƃ��͔�����|���đ����B���ꂪ���{�̔������M�B���M�̌�������{�I�ɂ͏M�͑����œ������Ƃ������Ƃɂ���B���͕⏕�I�Ȃ��̂��B�����Ȃ甿�z�͂Ȃ�䭂����ł���B���̓`���̃C���[�W�ł́A���D�����������̑D�Ƃ����킯���B �a�\�\�����������ł�����_�A�������ɔ����͓|���邵�A����Ɍׂ邱�Ƃ��ł��邪�A�ǂ����Ă��������f�B�e�[�����o�Ă���̂��A�Ƃ����Ƃ��낾�ȁB �`�\�\����͒P���ɁA�������ŁA���邢�͋t���������̂ŁA����|���đ����ōs���Ƃ������Ƃł͂���܂���ȁB �b�\�\�����͐��b�_�I�ϓ_���番�͂ł���B���b�̖��ӎ��I����Ƃ��Ă����Ɍ��o���Ă���̂́A�܂��ɉB�g�Ƃ��ẴV�[���ł����āA����͗v����ɁA�����Ƃ͒j���̉B�g���Ƃ����킯���i�j�B �`�\�\���Ƃ�蕐���́A���łɃJ���T����E���ŁA�����g�������ɂ��Ă���̂ł����ȁi�j�B �b�\�\�����g�ɐ����Ă������́i�J���T���j��E���Ƃ����s�ׂɂ��Ă��A�ꌩ�ȃf�B�e�[���̂悤�ɂ݂��邪�A���͐��b�_�I��ѐ��́A���̔����Ɍׂ�Ƃ������i�ɋ�������Ă���B �a�\�\���Ȃ킿�A�J���T����E���������̌ҍ��ɂ��邻�̒j���ƁA������̉B�g�Ƃ��Ă̒j���i�|���ꂽ�����j�̎C�荇�킹�������A�����ɍs�Ȃ��Ă���s�ׂ̖{���ł����āA���̓�{�̒j���̉^�����������j�F�̂���ł��邱�Ƃ͖��炩���ƁB �b�\�\�����������Ƃ��B�������āA������̃f�B�e�[���A���Ȃ킿�u�����������Y�̑���������čs�����v�Ƃ������b�f���A�ɂ킩�Ɋʼn߂��ׂ��炴��v�_�ƂȂ�B�����܂ł��Ȃ����Ƃ����A���҂��s�҂��瑾�����l������Ƃ́A�X�T�m�������}�^�m�����`�_�b�Ɍ��炸�A���Ȃ蕁�ՓI�Ȑ_�b�f�Ȃ̂����A���̏�ʂŔ�������Ă���̂��A��͂肻�̐_�b�I�s�ׂȂ̂��ˁB �a�\�\�������A�����������Y�̑���������čs�����Ƃ����͎̂����ł͂���܂��B�������A���̓`���̏�ʂł́A���ꂪ�_�b�I���x���܂ŒB���邪�䂦�ɁA�����������Y�̑���������čs�����Ƃ������b�f�Ƃ��Č���Ă���B�����Č����܂ł��Ȃ��A�����l���_�b�̃t�@���b�N�ȃV�[���́A�����ł͋ɂ߂ĔZ���Ȓj�F�W�̉B�g�ɂ���ĐF�Â�����Ă���_�����ڂ����̂ł���i�j�B �b�\�\���̂悤�ɁA���b�_�I��ѐ���L���Ă���Ƃ������Ƃ̈Ӗ��́A�w���ϕM�L�x���̎悵���ޗ����`�����A����Αc�`�ɋ߂��Ƃ������Ƃ������B�����Ɏ����ꂽ�u�����Y�̑�����������v�u�M�̒��Ɍׂ�v�Ƃ����V�[�������Ƃ߂��Ȃ����������A���b�̖{���ł������킯�ŁA���̕����`�L����������Ă��܂��̂́A���̓`���c�`���炷�łɉ��������Ă���؋����ȁB |
|
�`�\�\�Ƃ���ŁA�w�]�C�������x�ɂ��A�����|���������͏��q�A��B�����͏��q�ɏZ��ł�������ł��ȁB�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x�ɂ͂���ȋL���͂Ȃ��B������͕������ےÂ��璷��֗����ِl�E���l�ł���B�������w���ϕM�L�x�ł́A�����͂��̂Ƃ����q�Ƃ͉��̊W���Ȃ��B �b�\�\�������ˁB�������āA�������낢�̂́A�����O���u�@���A�ǂ������B�ٔV���i�����j�͂����A���Ă��܂����v�Ɛ����������ʁB���̕����́A�w���ϕM�L�x����{�I�ɓ����B�}�O�n�̓`���ɓ����I�Ȑ��b�f���ȁB�Ƃ��Ɂw�]�C�������x�́u������@���A�����������v�Ƃ�����ۓI�ȋL�q���܂�ł��āA����sliving dead�t����������Ă���B �a�\�\�w���ϕM�L�x�̕����Q�Ƃ���A�b�͂������B�\�\�����O�������Y�̎��[�ɋ߂Â��Č���ƁA���͂⏬���Y�͑����₦�����ł���B�����̒�����A�u�ٔV���͂����ދ��������B�����Y��A���͂₱��܂ł��v�ƌ��t��������ƁA�����Y�͗���������ƌ��J���A�ӂ��Ɨ����A�u������t�����B���������̂��v�ƈꐺ����ŁA�O�ւ����ςƓ]��ő����₦���\�\�Ƃ�������B �b�\�\���̈�i�̓�������w�]�C�������x�́u������@���A����������v�̌��I�ȁsliving dead�t�̎p�́A��ނ��Ă���B���A����ł���ʂ�͕ۑ�����Ă���悤���B�����������͌���������������B�����O��͏����Y�̎��[�ɋ߂Â��āA�l�q���M���B�������ǂ��������Ƃ��A�����Y�́u���[�v�ɂ́A�܂������������B �`�\�\�������A���[�ɑ�������͕̂ς��A�ƕςȃc�b�R�~�����Ȃ����Ƃ��i�j�B �a�\�\�����Y�́A����������ƌ��J���A�ӂ��Ɨ����A�u������t�����B�i�ٔV�����j���������̂��v�ƁA�ꐺ����őO�ւ����ςƓ]��ŁA�▽�����Ƃ����B����������Y�̏����ւ̎��O�Ɠǂނ̂́A���㕗�̓ǂ݂ł����Ȃ��B�����͂�͂�A�����Y�̎��[���sliving dead�t�Ƃ��ē������A���������A�Ƃ����s�v�c�����̂܂��ꂽ�����A�`���̓ǂݕ��Ƃ��Ă͐������B �b�\�\�f��I��@�ɂ͂悭�����������A���͂⎀�Ǝv��ꂽ�Ώۂ��A�܂��Ɂsobjet abjet�t�Ƃ��ē˔@�Ƃ��ė����オ��B����ɂ܂Ŕ������������I�ȁsobjet�t�̉^���ł���B���̈�i�̏����Y�̎��[�̓����Ƃ́A�����͂��̓�x�ڂ̎������Ȃ˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����킯���B �a�\�\����䂦�A�����Y�́u���[�v�Ƃ��������͖������Ă͂Ȃ�Ȃ��킯���B�����Y�͓�x�����B��x�ڂ͐g�̓I�ȃt�B�W�J���Ȏ��Ƃ��āA��x�ڂ́A�C���^�[�T�u�W�F�N�e�B���i�Ԏ�̓I�j�ȎЉ�I�Ȏ��Ƃ��āB �`�\�\���������ď����Y�́A�����̌Q�W�̊�O�Ŏ���ł݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������킯���B �b�\�\���������ꂪ�A�����̌Q�W�ɚ������Ă��āA�܂��ɂ��̎r�́A�sliving dead�t���N���オ��Ƃ����_�ł́A�O�ɘb��ɂ����Ƃ���́u�l�|����鏬���Y�v�Ƃ̎����ѐ���L����킯�ŁA���������R�~�J���ȃu���b�N����[���A�̗ނ��ɂȂ��Ă���B �`�\�\�܂�A�u�l�|����鏬���Y�v�͎��[�ƂȂ��Ă��N���オ��A����������ł��A��͂�|��āA����ǂ͖{���Ɏ���ł��܂��B �a�\�\����������ʂ����w�]�C�������x�͌Ì^���������A������w���@��t�`�L�x�����̃p�^�[���P���Ă���B����́A�w��t�`�L�x�ɂ́w���ϕM�L�x�����Ì^�̐��b���܂ނƂ����Ⴞ�ȁB |
*�y�]�C�������z
�s�����n�A���M�ɏ�āA���q�̒n�]�A��B���U�M���o����Ƃ��鎞�A�����̒����A�u�@�������ɁA�ٔV���m���������U������ٔV���Ɖ]�Ȃ�n�������̂����v�Ɖ]�Ђ���A������@���A�����������A�C����~�āA�u�ٔV�����Â��֍s���v�ƁA���߂�o�T��č������t *�y�O�����ϕM�L�z �s�T�e�A�����m�M�ˁA�����Y�K���[�j�߃d�L�����j�A�n��������X�i���B�����m�������A�u���V���n�R�����`�m�N�K�A�����Y���n�������J�v�g�A�����J�P�V�j�A���გ�N�n�c�g���q���L�A�t�c�g���g���A�u����c�N�����A�������f�n�i�L�v�g�A�ꐺ�T�P���f�O�w�J�c�p�g�z���e�A����^���B�Í��m�p�Y�g���c�x�V�B�ɉ��t *�y���@��t�`�L�z �s�����m�������A�����Y���ۛ��m�҃j�e���L�P���A�߃���e�A�u�����Y�A�ٔV���n�A���K�A�ő��i�L�J�v�g�ăn���V�J�o�A���^�������Y�X�c�N�g���A�u�����N�����A�����}�C�j�v�g�]�i�K���A�œ|�j�|�^���B���j�E�҃m�҃i���g�A�l�X�Ƀ~�P���g�]�t |
|
*�y�����`�z
�s���U�K�ؓ��A�����ǃK�e���m�������Ő܃e�A���`����X�B�����k���炭���āl�����ؓ����́A�胒�ȃe�����Y�K���@���W�e�A�������M�t�R�g�����k������l�A�R��A�y�j���g�m���j���e���X�V�A�N�e�ؓ����c�A�M�j�m���]�A�����n���|�Ȏ˃g�A���B��������j�A�r�_�m�ヒ��A�M�������B�R�����s���g���n�A���䞨���e�A���X�B�@�k�̂��l�������q�j�ҁA������m��j���e�A��������t�B����ƘV����j�e�A���\�m�����s�B�g�V�e�A��萃j�d��A���e��A������j������Z�������n�A�c�������v�ꃋ�m�����v�c�N�m���m�R�g��g�]�n�t *�y��V�L�z �s���U�K���|�m�ؓ��A�����Y�K�e�����������܃e�A���`����X�B���@�����������o�d�B�b�N�L�e���U�ؓ����̃e�A�胒�����Y�K���@�j���q�A�烒���Z�e�������M�t���c�b��B���V�e�@�Aꡃj���g�j���e���X�V�A�N�e�ؓ����c���A�{�m�D�j�s�A���A�������g���j���T�V�e�s�����J��B���m萃j�d���A������j������V�e�X�ӃX�B���m�㏬�q�j�����A������j�A�������m�m���^�g�������i�T���R�g����t�B�V����c�V�A���m����s�B�V�e�A�����m萃j�d�k�g�i���t  �ޗ������Ӓn�}
*�y���c�ƋL�z
�s��A�����l��i�ɔ퐬����A���N�{�{���U���M�L�O�֔�z�A���@�̎t���d��B���䏬���Y�Ɛ\�ҁA�◬�̕��@���d�A�����t���d��B�o���̒�q�ǂ����@�̏����\���A���U�����Y���@�V�d���d��ɑ����A�L�O�ƒ���V�ԂЂ����m��Ɋޗ����Ɖ]�Ӂn�ɏo���A�o�����ɒ�q��l���s�Ҕ��ɑ���A�������d�A�����Y��ŎE��B�����Y�͔@����q��l���s�Q��B���U��q���Q��B�ꋏ�\��B����ɏ����Y�h���v���A�ޒ�q���Q���A��ɂđŎE�\���B���i���q�֑����ցA�����Y��q�ǂ��v�ꖡ�A�u����Ƃ����U��ʼnʁv�ƁA�吨�ޓ��֎Q�\��B�˔V���U��ٖ�i�ɓٗ��A�����l��ɕ���ɕt�A�䐿���퐬�A���钆�֔폢�u��ɕt�A���U�����^���J�\��B���㕐�U��L��֔푗����B�Έ�O�V��Ɛ\�n��ɁA�S�C�V���ǂ��䕍�퐬�A����v�x��A���ʏ�L��֑��́A���U�i���j����ւƐ\�҂ɑ��n�\��R�Ɍ����t |
�b�\�\���ꂪ�`���̑c�`�ɋ߂����̂�ۑ��������̂ł��낤�Ƃ́A����܂����n�`�L�Ƃ����킹�Ă݂�킩��B�܂�w�����`�x�Ƃ���P�����w��V�L�x���L���̂́A�����Y��|�����������ؓ����̂āA��ŏ����Y�̌��@���A���̐₦���̂��m�F����Ƃ�������B���ꂪ�}�f�Ȏ�������͕킵�����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�Ȃ̂����A����ŁA�`���̑c�`���牓���`�Ԃɓ]�����Ă��܂��Ă���B �`�\�\�ނ��w���ϕM�L�x�̂悤�ɁA��������������ɂ������āA�����Y�̌�������čs�����Ƃ��A�J���T����E�����҂���Ŕ����Ɍׂ����Ƃ����̐S�̃f�B�e�[�������Ă���B �a�\�\�j�F�I�B�g�ł͂Ȃ��A���̑���ɕ����͌��g�Ɍ������Ĉ������ċ���Ƃ����A����Η�V�������������B���������̃V�[�����A�}�f�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��Ă���i�j�B �b�\�\�������A�w�����`�x�͋C�ɂȂ�b���L�ڂ��Ă���B�܂蕐�����M�ɔ�я��Ƃ��A���̊����ɁA�s���]�A�����n���|�Ȏ˃g�A���B��������j�A�r�_�m�ヒ��A�M�������B�R�����s���g��t�ƋL���ˁB �`�\�\����͕������������ꂩ��ދ����悤�Ƃ���Ƃ��A�����𑙂œ˂�����A���邢�͔��|���ˊ|����U�����������A�Ƃ������Ƃł��ȁB�����͍r�_�\�\������������E�����_�\�\���щz���ē��������瓖����Ȃ������Ƃ����̂����A�w�����`�x�̂��̋L���́A���Ȃ̂��B �a�\�\�v����ɁA����́w�����`�x�̏�ʂ̔w�i��z�N����킩��B���n�`�L�ł́A�����Y�͍א�O�ւ��C�ɓ���ŁA�a�l�̌���M�Ō����n�ւ���Ă���قǂ̃G�X�^�u���b�V�������g�B�����═���͉ƘV�E���������̃R�l�ŏ����Y�ɒ��킳���Ă�������ِl�ł���B�Ƃ������Ƃ́A�a�l�����ڂ̕��@�҂ŁA���������̎t���ł��鏬���Y���E���������ɑ���A�א�Ǝm�̍U�����Ƃ������ƂɂȂ�B����͍א�ƒ��ɏ����Y�̒�q�����������Ƃ��������̌��o���ȁB �`�\�\�א�ƒ��ɏ����Y�̒�q���������āA�ނ炪�������P�������Ƃ���A�������������������ꂩ��}���œ��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯���B �a�\�\���̂悤�ɁA�s���]�t�Ƃ�������ɂ��A����ɋ}���œ����������łȂ��A�����͍U�������Ƃ����b���ˁB���̕z�u�́A�������n�`���ł��A�F�{�n�ɑ��锪��n�̗v�f���ȁB�w�����`�x�ɂ��������̔���n�̓`���ɑ��ẮA�������Ɂw��V�L�x�͌��{�����ė}�����A�������Ă���B����͉��₩�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��낾�낤�i�j�B �b�\�\����ŁA���̕����ɑ���U�����������Ƃ������b�f���������߁A�w��V�L�x�ł͂���ɑ����b���Ӗ��s���ɂȂ��Ă���B�܂�A�Ȃ��A��ɕ��������q�֗��āA�������������ƁA���������ɗ����A�s���ɂȂ��Ă��܂����i�j�B���̘b�͉ƘV���c�̏㋖���łȂ������̂ŁA�����͉��ւɖ߂����Ƃ����b�����A��ɕ��������q�֗������̗��R����������Ă���킯���ˁB �`�\�\�w�����`�x�̕��́A�����Ɏd�|����ꂽ�U�����L�^���邱�ƂŁA���̕����̈Ӗ���ۑ����Ă���B���̂悤�ɁA�w��V�L�x�́w�����`�x�ɑ������ł͂Ȃ��B���{�ҏW�ɂ���ĈӖ��s���̕����ݏo���Ă��܂��B �b�\�\�����ŁA���́u������������U�������v�Ƃ������n�`�����A�����Œ肹���鎞�_�ł̕���ł��������Ƃ��m���B���n�`���̂�����̈ٓ`�́w���c�ƋL�x���ˁB�����͂����ł́A��i���̏��c�����̂��Ƃ֓�������Ŕ삳�ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���i�j�B �a�\�\�܂�A���̘b���͂��߂���]���ƁA�����̌_��ł́A�����E�����Y�o���Ƃ��A��q�͈�l���A��Ă��Ȃ��������B�Ƃ��낪�������ɂ͒�q���������Ă���A�����������Y��|������A�����Y�͑h���������A�����̒�q����������Ă������ď����Y��ł��E�����A�Ƃ����b�ȂȁB �b�\�\�����ŁA���̂��Ƃ����q�֓`����āA�����Y�̒�q�������ꖡ���S���āA����Ƃ��������ʂ������ƁA�吨���ďM���։������B���̂��ߕ����͖�i�֔��āA���c�����̖�i����ɔ삳�ꂽ�̂ŁA�������������B���̌�A�����͕�����L��쑗���āA�u����ցv�Ƃ����҂g����n���������ȁ\�\�ƁA�w���c�ƋL�x�̕��͂��������`�����e���B �`�\�\���́w���c�ƋL�x�̋L���́A�������n�`���ł��w�����`�x�Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�B�w�����`�x������n�ł���̂ɑ��A������͌F�{�n�ł��ȁB �a�\�\�w���c�ƋL�x�ł́A�w�����`�x�̒��������̘b�͂܂������o�Ȃ��B���̑���ɕ����̔�҂Ƃ��āA���c�Ɛ�c�̉���������킯����B���������ē`�����ꂼ��̉�c�����Ԃ�ɂ́A�����Ƃ���ł���i�j�B �`�\�\����ɉ����āA�w���c�ƋL�x�ł́A�d����A�܂������Ă��������Y���A�����̒�q�������ł��E���A�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��邪�A�w�����`�x�ł́A������P�������͕̂����̕����B���̓_�ł��A���҂̓`���͑ΏƓI�ł��ȁB �a�\�\�������A�w���c�ƋL�x�ł��A�s���䏬���Y�Ɛ\�ҁA�◬�̕��@���d�A�����t���d��t�Ƃ���A�܂������Y�̒�q�����͏��q�ɂ����Ƃ����킯���B���������_�ł́A���҂ɂ͋��ʂ����Ƃ��������B�ǂ���������Y�̋��_��L�O���q�Ƃ���Ƃ���͓����ŁA���ꂪ���n�`���̓������ȁB �`�\�\����͂��łɂ݂��悤�ɁA�}�O�n�̓`���Ƃ͈قȂ�B�w���ϕM�L�x�ł́A�����Y�卑�l�Œ��{�Z�l�Ƃ��邵�A�����܂ł�����͉��ւȂ̂ł��i�j�B �b�\�\�Ƃ��낪�A�w���ϕM�L�x���w���c�ƋL�x�Ƌ��L������b�f���ЂƂ����āA���ꂪ��i���i���j�̑��݂��ȁB�w���ϕM�L�x�͂��̖��͎��O�����ƋL�����A����͏��c�����̂��ƁB����ƁA�����̔�҂́A�w�����`�x�̌����悤�Ȓ��������ł͂Ȃ��A���c�������������A�ƌ��_�Â��邱�Ƃ��ł��邩�B�������b�͂����͒P���ɑ������Ō��߂�����̂ł͂Ȃ��i�j�B �\�\�����Řb�����邽�߂ɁA�\��p�ӂ��܂����B����������B |
| �@ | ���ϕM�L | ���c�ƋL | �� �� �` |
| �����Y�̏ꏊ | ���咷�{ | �L�O���q | �L�O���q |
| �����̏ꏊ | �ف@�l | �L�O���q | ���剺�� |
| �����W�� | ��i��剽�^ | ���c���� | �������� |
| ������ | �����L���E�����Y�s�� | �����L���E�����Y�s�� | �����s���E�����Y�L�� |
| �� �� �� |
�����M�G�������Y�� ���������� |
�����̒�q�������Y�� �ł��E�� |
�������i�����Y��q�Ɂj ���E���|�ōU������� |
| �� �� �k |
�����Y�̓��͏��q�� �{�{�ɐD�Ƃɂ��� |
��i��ɔ삳�ꂽ������ �L��쑗����� |
���q�֗��������� ������\������邪�p�� |
|
�b�\�\����ɂ���Č���A�w���c�ƋL�x�̒��ԓI�ʑ��A�܂�w���ϕM�L�x�Ɓw�����`�x��}���|�W�V�������߂�̂��悭�킩��B���Ȃ킿�A�w���c�ƋL�x�̋L�����w���ϕM�L�x�Ƌ��L���镔���́A�`���c�`�ɔ�r�I�߂��B���̓`���c�`�͏�q�̂悤�ɁA�s�ҏ����Y�ɐS��I�ɉ��S������e�ł����āA�w���c�ƋL�x�̓`���ł͂��ꂪ���Ȃ�ۑS����Ă���悤�����A����ɂƂǂ܂�Ȃ��B �a�\�\�����Y�ɉ��S���钷��̒n���`���ł́A�����܂ł��Ȃ��u�����Y�͕��������A�����Ȃ������v�Ƃ����۔F�̃|�W�V����������B���������۔F���w���c�ƋL�x�̓`���ł͑傫���c���ŁA�����̑Ō��͏����Y���E���Ɏ���Ȃ������A�����̒�q�������Y��ł��E�����̂��A�Ƃ������b���e�������炵�Ă���B �`�\�\���̐��b�f���C������̂��A���������Y���Ҍ_��ł͒�q�͈�l���A��čs���Ȃ����ƂɂȂ��Ă������A�������͂����j���āA�����̒�q�ǂ�������ɉB��Ă����A�Ƃ�����ʐݒ�ł��ȁB �a�\�\����́A��ɌÐ�Ï������w���V�G�L�x�ɋL���ԊԊւ̓`���A�܂蕐������l��A��Đ�ɓn���Ă����Ƃ��A���̖�l���l�l������ď����Y���ʂ������A�Ƃ������b�ɂ��ĉ�����Ƃ��낾�ȁB �b�\�\���������āA�w���c�ƋL�x�̓��e�́A�n���̓`���c�`�̕��������̂܂ܓW�J�������̂����A��������i��ɔ삳��A����ɂ͖L��܂Ō쑗���ꂽ�Ƃ����b�̓W�J�́A�`�������ߒ��Ő��܂�āA���Ȃ葝�B���i���̂��B �`�\�\���̂����A�����̐g�����u����ցv�Ƃ����҂ɓn�����������A�Ə����B����͂܂��������h���������b�Ƃ��������悤���Ȃ��i�j�B �a�\�\�����镃�A����̖S��́A�����ł�����Ă���i�j�B�Ƃ���ŁA�w���ϕM�L�x���w���c�ƋL�x�Ƌ��L������b�f�A�܂蕐���̉����c�Ƃ��Ă̖�i���̑��݂�����B��i���Ƃ��̕����W�c�́A��������ւ̃v���[���X�Ƃ����_�́A���������u�L���ȕ����^�s���ȏ����Y�v�Ƃ����Η��\�}�B������w���ϕM�L�x�Ɓw���c�ƋL�x�����L����̂ɑ��A�w�����`�x�̓`���ł́A����]���āu�����s���^�����Y�L���v�Ƃ����悤�ɕϊ����Ă��܂��Ă���B �b�\�\����������A���b��̕����ւ̖��炩�ȉ��S�́A��㔪��n�̓`���݂̂̓����B����͓`���Ƃ��Ă͐V�����l�����������̂��ˁB�w���c�ƋL�x�̓��e�́A�`���c�`�̕�����ۑS���Ă��邾���ł͂Ȃ��A���̉�����ɓW�J���ꂽ���̂��B�w���c�ƋL�x�̋L�^�͌��\�N�ԁA���ꂾ���ꕔ�`�������̌`�Ԃ��c���Ă���B����ɑ��w���ϕM�L�x�̓`���ł́A���������������u�L���ȕ����^�s���ȏ����Y�v�Ƃ����Η��\�}�ɂ�����̂́A�����ł͂��łɏ����Y�͚}����l�|�����Ώۂł���B�u�s���ȏ����Y�v�̈Ӗ����A�S��I���S���炷��ݒ肩��V�t�g���āA���̈Ӗ������֓]�����Ă���B �a�\�\�Ƃ��낪���A�w���c�ƋL�x�̓��e�����̂܂܌Â����ƌ����A�����ł͂Ȃ��B���Ƃ��ƒ���̒n���`���ɁA�����Y�͕s���ɂ�������炸�P�킵���Ƃ��������I�X�^���X���������B��������Ί݂̖L�O���ɁA��������i��ɁA�����̋��͂ȉ����҂������Ƃ����W�J�ɂȂ����B �b�\�\�w���c�ƋL�x����荞�̂͂��������Ίݐ��̑Η��`���ł����āA�{���̊ޗ����`���ł́A��i���͑�����A�G���Ȃ��i�j�B�������炸���Ԃ���h�����Ĕ��W�����`�����w���c�ƋL�x�̓��e����B�O�̂��ߌ����Ă����A�w���c�ƋL�x�̋L�����A�M�ߐ��̂��鎖���ƍ��o����X�����ߔN�����Ă��邪�A����͓|���I�T���ł���B �a�\�\�����������ȁA�ޗ�����F���i�Ђ����j�ƍ�������悤�ȋL��������̂��A�w���c�ƋL�x�Ȃi�j�B�L�O����Ɍ��e������A����Ȍ�F�͐����Ȃ��B�㐢���ŏ����ꂽ�`����������A����́B �`�\�\����������A�ޗ������M���ɂ��ẮA�}�O�n�́w���@��t�`�L�x�̕�����قǐ��m�ł��ȁB �a�\�\�M���͐ԊԊցi���ցj�Ɠ����i�嗢�j�̊Ԃ̓����Ɛ��m�����A�u�^�����q���v�Ƃ������̂��Ƃ܂ŏ����Ă��邩��ˁB����ɔ�ׂ�ƁA�w���c�ƋL�x�̋L���́A�܂������A�z�Ȃ��Ƃ������Ă���i�j�B �`�\�\�ނ��w���c�ƋL�x�̋L���́A�㐢�ł����ޗ����`���̈�ŁA���Ȃ�ό`����Ă���B���������ɓ���ēǂޕK�v������B�Ƃ��낪�A�����������肪�ł��Ȃ��҂������̂́A���������̂��i�j�B �a�\�\�w�]�C�������x�̋L���́A���������Ӗ��ł͕ʂ̑c�`���Ղ��c���Ă���B�@���͂��̎����ɂ͕���������ǁA�����A�����̎҂ł����āA���p�����ł������������B��q�������n���ɑ����B��q�����͕����Ƃ��Ƌ@����M���Ă������A�v���悤�ɂ͂����Ȃ������A�Ƃ����b���ȁB �`�\�\�@���̒�q�����͕����Ƃ��Ƌ@����M���Ă����A�Ƃ����̂��|�C���g�ł��ȁB���n�́w���c�ƋL�x�ɂ́A�����Y�̒�q�����������Ƃ��ƏP�����Ă���b������B�������A������͏��q����̏P���ŁA��q�����̋��_���Ⴄ�B �b�\�\�w�]�C�������x�Ɓw���c�ƋL�x���c�f����ގ��̓`���������������Ƃ������Ƃ��ˁB�����Œ��ӂ����_�́A�w�]�C�������x���A�@���ɂ́u�����v�ɒ�q�������Ƃ��邱�Ƃ��B���̓`�L�̂悤�ɁA�����Y�̒�q���L�O���q�ɑ��������Ƃ���̂ł͂Ȃ��B�w�]�C�������x�ł͂����܂ł��A�����͏��q�Z�A�@���͒���Z�A���������đΊݐ��̑Η��\�������m���B����䂦�A�@���ɂ́u�����v�ɒ�q�������Ƃ���A���́u�����v�Ƃ͒���𒆐S�ɂ����n����w���̂��낤���A�����ł͎R�z�H�̓��͔��O�܂ʼn��X�����Ƃ�������ʔ����낤�B �`�\�\�@���̒�q�����͕����Ƃ��Ƌ@����M���Ă����A�Ƃ����w�]�C�������x�̋L���́w���ϕM�L�x�ł͏����Ă���B �a�\�\�w���ϕM�L�x�́A�����Y�͌Í��̉p�Y�Ɖ]���ׂ��ł���A�u�ɂނׂ��A���ނׂ��v�ƋL���B�������肵�����̂��i�j�B����������́A�w���ϕM�L�x�̒n�̕��ł͂Ȃ��B�܂��`���̈��p�����ł���B����́A���ɁA���̘b�͉��֕ӂ�Ō��`����A�Əq�ׂ�L�q������Ă���̂��݂�킩��B �b�\�\�������ˁB�ȏ�́A���ւ�����Ō��`����Ƃ���ł���B���̂��Ƃ���A�M�����ޗ����ƌĂԁB�\�\��������w���ϕM�L�x�̒n�̕����B�������A��������̊ԁA�����Y�̓��́A���Ȃ��{�{�ɐD�̉Ƃɂ���Ƃ��A�Ƃ������`�̉\�b�������t���Ă��̒i�͏I��B�`���ɂ����̏؋��̕i�A���A���Ȃ��̂̏��ЁB �`�\�\�Ƃ���A���̃��A���Ȃ��̂̏��ЁA�܂蕐���������Y�������������A���q�̋{�{�Ƃɂ���̂��A�L�ҕ��ς��m�F�������Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B �a�\�\����͂����܂ł��`���̓`�����ȁB����������A���̊ޗ����`���ɂ��Ă��A���ԕ��ς��i�C�[���ɐM���Ă����Ƃ��������A�`���͓`���̂܂܂ɓ`����Ƃ������ƁB���ꂪ�u���M���`���v�̈Ӌ`�Ȃ̂ł���i�j�B �`�\�\�������A�w���@��t�`�L�x���A�{�{��n�̉ƂɁA���߂������̓��ƁA�����̖ؓ���J���T��������Ƃ����̂́A�C�ɂȂ�|�C���g�ł��ȁB �a�\�\�╨�������Ă���i�j�B�������A�w��t�`�L�x�̒O�H�M�p�́A���q�̋{�{�Ƃ�m���Ă��邩��A����́w���ϕM�L�x�Ƃ͕ʃ��[�g�̓`���L�^��������Ȃ��B �b�\�\������������Ȃ��B�Ƃ�����A���ԕ��ςɂ��Ă��A�����ƍ]�˂Ƃ̉��҂̐܁A���̏����̑������x���ʂ����B�������̍��܂łɂ́A�ޗ����`���́A�n�����ֈȊO�ɂ����������Ő������Ă����B�������Ă��̏������A�����Ƃ��L���ȕ����L�O�n�ւƏ��i���Ă����̂����A���Ȃ��Ƃ����̓����u�������v�ł͂Ȃ��u�ޗ����v�ƌĂ��ȏ�A�n���ł͘b�͈���Ă����B�����W�j���ɂ݂���ޗ����`���̍��Ղ��݂�A�n���̐S����S�����̂́A�����ł͂Ȃ��ޗ��̕��������̂��ˁB |
*�y���V�G�L�z
�s�Ԋԃ��ւɂēy�l�̉]�ЙB�ւ��ɔ{�ɋL�����Ƃ͑�ɈقȂ�B�◴�A�����̉�Ɩ���Ȃ��A�ɍ��菬�M���������ĂӂȂ��܂֓n���Ƃ������A�Y�̂��̂ǂ��◴���ƁU�߁A�u�����̏��A��l�𐔑������B�ēn����B�吨�Ɏ�Ȃ��Ƃ��ӎ��L��A��l�ɂĊ��ӂ܂��B�����͂Ђ�Ɍ䖳�p�Ȃ�v�Ƃ��ӁB�◴���H�A�u�m�͌����͂܂��B���������Ȃ�A�����n�炳��́A�m���Ղ�Ƃ����B�Ⴕ�傺���ɂĉ�A�ՐJ�͂���ɂ�����ׂ���v�Ƃ��ӂāA�����ē��ɓn��B�͂�������l�̎m�l�l�o�͂����A�I�Ɋ◴����B���i�߁j�~�߂��Y�l�A�◴���`�S�ɂ������z�����A�������i���邱�ƁT�Ȃ��B�����͒m�炴��ǂ��A�y�l�̕���̂܁T���L���Č�̍l�ւƂ��B���l�܂��A�{�{�̎q�����q�̉ƒ��ɍ݂�A�����̉�������āA�◴���ɑ�������A�Ɖ]�t  �֖�勴�ƌÏ�R�i��i�隬�j
*�y���@��t�`�L�z
�s������n���������n�����e�A�\���m�m���_�������J���P���o�A����̎僂�j�����i�h�v�����փ[�����V�J�o�A��t�g�����Y�m�������A�n�c�S�L�m���j�e�n�������A���V�j���A���嚠�Ԋԃ�萃g沑O���嗠�g�m�ԃj�l�ƃ����L�����A���B�M�m�`�i���́A�M���g���X�B�m���}�G�g���}���m���A�t���^�^�����q�g�]�ҁA�t���摹�W���j���Q�M��J���P���o�A�G�g���{�e�A�^�����q�������m��w�Ǐ�A���Z�����V�B���j�^�������q�K�n�J�����m��j�A���V�́A�������^�����q���g�]�B�M���n�^�����q���m����j�׃����n�B��t�A�����Y�A�����j�n�e�����Z���g��Z�����t *�y�]�C�������z �s�@�������d���Ƀn������ǂ��A���������̎҂ɂāA���@�����ɂĂ��肯��Ƃ���B�@������q�ǂ������ɑ����A���U��������Ƃ˂�ւǂ��A�S�ɂ܂������B���U�n�������ɂ����ނ��A���ɂɓ�N���܂苏�Z���B�v��薾�Ώ��}���E�ߏ��ẲƂɗL���ďZ���B�א�z����A���@���]�̂��Ɛ[�ؖY�������A�ѐ����ɉ���B�����A�z�����㚠��̂��ʂӔ��Ɏ���ݏZ�A���@�̎w��\����B������ˎR�Ɖ]�R���ɂĎ��X�B���U��㕺�@�b�B�s���ՁA���l�̂ق܂�L����B�ޗ����̎d���n�A���܂��\���̎��ɂ��A���@�����n�A�ЂƂւɌ����̏���A�S�ɕs�����ǂ��Ȃ�ƁA���U��N�ɐ\����Ƃ���t *�y�O�����ϕM�L�z �s�R���A���m萕Ӄj�e��B������B�v�����V�e�A�M�����ܗ����g�ău�B�����Y�K�уX�����m���A�����A�{�{�ɐD�K�ƃj�L���g�J���t *�y���@��t�`�L�z �s�����Y�K���A��t�m�ؓ��A��m�J���T���A���j���L�O���q���}����m�b�A�{�{��n�K�ƃj�B�҃Z���t  �ޗ����Ɗ֖�C�� |
 �ޗ������ӌ����n�}
*�y�ܗ֏��z
�s�����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�B���N�̐̂��A���@�̓��ɐS�������A�\�O�ɂ��Ďn�ď��������B�����ЂāA�V�c���L�n�앺�q�Ɖ]���@�҂ɑŏ��A�\�Z�ɂ��āA�A�n���H�R�Ɖ]���͂̕��@�҂ɑł����A��\��ɂ��āA�s�ւ̂ڂ�A�V���̕��@�҂Ɉ��A���x�̏����������Ƃ��ւǂ��A��������Ɖ]���Ȃ��B����A���X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A��x�������������Ȃ͂��B�����A�N�\�O����\���㖘�̎���t�i�n�V���`���j *�y���q�蕶�z �sূɕ��p�̒B�l�L���A���͊◬�B�ނƎ��Y�����������ށB�◬�]���A�������ȂĎ��Y�������𐿂ӂƁB�������ւĉ]���A���͔��n�����Ђđ��̖���s�����A��͖،���č��̔�����͂���ƁB������������ԁB����ƖL�O�̍ہk���́l�A�C���ɓ��L��B�M���ƈ��ӁB�_�Y�A�����ɑ������B�◬�A�O�ڂ̔�������ɂ��Ę҂���A�����ڂ݂��p��s�����B���U�A�ؙ��̈ꌂ���ȂĔV���E���B�d���A�P�x���B�̂ɑ��A�M�������߂Ċ◬���ƈ��Ӂt   ����R����ޗ���������]������ ���݂͉��֎s�X
*�y�O�����ϕM�L�z
�s�\�Z�m���A�A�n���H�R�g�]���͔V���@�҃j�ŏ��ʃt���A�n�m���j�ڃ����R�g�C�w�h���A���m���A�ꃊ�B�w���s���B�y�e�Z�\�P�x�m�����A����j�����^�����ɁB�Q�N�S�j�V�e��ꃊ�B�t�t  �{�{����������@����R���� �k��B�s���q�k��ԍ�  ���X�؏����Y��@����R���� ���a26�N ���㌳�O�� �v�F���z�ƒJ���g�Y
*�y���㌳�O�z
�s�����Y������Ă邱�Ƃɂ��ẮA���q�s�̂ق������C�ŁA����R�̒���A�ቺ�Ɋ֖�C���������낵�A�͂邩�Ɋޗ����i�D���j�߂��D�̏ꏊ���A�~�n�ɑ݂��Ă���邱�ƂɂȂ����B����R���s�̌����ɂ���̂ŁA�����Y��𒆐S�ɂ��Đv���A���������q�s�̖����̈�ɂ������A�Ƃ����s�̈ӌ��ł����t�i�w���M���X�؏����Y�x���a�N�j |
�`�\�\�������āA�֖�C����]�ގ���R�̏�ɁA�{�{�ɐD������ȕ����L�O������Ă����A���̔蕶���A���̊ޗ����̂��Ƃ��L���Ȃ�������A���̘b�͏����Ă��܂��Ă�����������Ȃ��B �b�\�\�������낤�ˁB���q�蕶���ޗ��������̂��Ƃ��L�����̂́A�܂��ɂ��ꂪ���̊C���̏����ōs�Ȃ�ꂽ���炾�B���ւ̉Y�l�����́A���̏������u�ޗ����v�ƌĂԂ悤�ɂȂ��Ă����B���q�蕶�͂��̎��ւ��L�ڂ����B���̏��q�蕶�̑��݂͑傫���B����A�����`�L�́A���������̔蕶���Q�Ƃ��Ȃ��甭�W�����B �a�\�\�ޗ��������́A���[�J���ȓ`���Ƃ��Ă��łɂ������B�������A���̎d���������܂œ`������قǗL���ɂȂ����̂́A��͂����̉̕���E��ڗ��Ȃlj����ŏ㉉���ꂽ���炾�ˁB���ꂪ�Ȃ�������A���[�J���ȓ`���Ƃ��Ė��v���Ă��܂�����������Ȃ��B �b�\�\���ǂ̂Ƃ���A���q�蕶�Ɖ�����i���ˁB�{���Ȃ�A���̓`���Ɠ����悤�ɁA���[�J���ȓ`���Ƃ��Ė��v���Ă��܂����͂��̂��̂��A�����đ����������肩�A�\�����I�ɂǂ�ǂ������B������A�ޗ��������͗�O�I�Ȏ��ւ��ƌ�����B �`�\�\�����́w�ܗ֏��x�`���ŁA���g�̗�����U��Ԃ��Ă��邪�A�����ɂ͊ޗ����̋L���͂Ȃ��B�ޗ��������́A�����ɂƂ������L���ׂ��L�O��I���ւł��Ȃ������悤���B �b�\�\�����炭�A�ޗ��������̑���A�◬�́A�������|��������̂Ȃ��́sone of them�t�ɉ߂��Ȃ������̂��낤�B�ɂ�������炸�A���q�蕶�̋L�������́u�◬�v���A�������傫�ȑ��݂ɂȂ����̂́A�\�����I��ʂ��Đ��������ޗ����`���ɂ����̂��B �a�\�\����Ƃ�����A�ޗ������������������A�����̑ΐ�L�����A�̑����I�o�����̂��Ƃ��݂Ȃ��̂́A���炩�ȊԈႢ���ȁB���������A���̌����̎������s�����B�}�O�n�`���������\��̎��ւƂ���̂��A���Ȃ����ے�͂ł��܂��B �`�\�\���q�蕶�́A���s�ł̋g�����Ƃ̑ΐ�̌�ɁA�ޗ����̎d�����L���Ă���B���̋L�q�������A�N��I�����Ƃ݂Ȃ��āA�ޗ��������s�̋g���̌�A�܂蕐���̌c������������̎��ւƂ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�������A����́A���q�蕶�̋L�q������N��I�����Ƃ݂Ȃ��Ƃ�����������̉��ł́A����Ή����̈�ɂ����Ȃ��B �a�\�\����������t���ɂ��Ă����ׂ����Ƃ����̂́A�ȑO�ǂ����ŏq�ׂ���������Ȃ����A���q�蕶�ɂ���ޗ����̋L���́u�����ɕ��p�̒B�l�����v�Ƃ��������o�����ˁB����́A���炩�ɔN���ǂ��ďo�����ł͂Ȃ��B���������̂Ƃ��Ƃ����̂ł��Ȃ����A���O�ɂ́A�V�Ɩ���̎��ւɑk�����L��������B���̂����肩��L�q�̏����͔N�㏇�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�ƌ��邱�Ƃ��ł���B �`�\�\�����ɕ��p�̒B�l����A�Ƃ����̂́A�u���������A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�����ɕ��p�̒B�l����v�Ƃ��������ł��ȁi�j�B�����L�O������Ă�R����A������ƒ[�������邠�̓��ōs�Ȃ�ꂽ�d���̂��Ƃ��O���킯�ɂ͂����Ȃ��B����͏����Ă�����A�Ƃ����g�U�肪����������B �a�\�\���ꂪ���̔蕶�̃��[�J���e�B�A�n������ȂB�������������ŁA���̔肪�����Ɍ��Ƃ�����A�ʂ̌������ւ��L���ꂽ���낤�A�Ƃ������Ƃ��B�������A���q�蕶�̐�q�҂ɂ��A�ޗ��������̔N�͖��炩�ł͂Ȃ��������A�����Ƃ�������Ȃ��B�Ƃ����̂��A���ꂪ�߂����āi�j�A���蓖���A�n���̐l�ԂȂ炾��ł��m���Ă������Ƃ�������Ȃ��B���������C�����ɖ����������ł́A����Ȏ��m�̎����͋L�ڂ��Ȃ��B����ŁA�n���̎��ւ����A�����ɕ��p�̒B�l����ƁA�ΐ�L�����A�̍Ō�ɒlj��I�ɋL�q���ꂽ�B�����Ȃ�ƁA�ޗ����������g�����Ƃ̑ΐ�����ゾ�Ƃ͌����Ȃ��B �`�\�\�ނ���A���B���̑����`�����E�����w�]�C�������x�̋L�����ƁA�ޗ��������̂Ƃ��͕����\��������ˁB �b�\�\���ꂪ�A�ޗ��������͂��s�Ȃ�ꂽ���A�Ƃ������Ɋւ����X�̗��ۂ̗v�����ˁB�����������ۏ������̘b���Ƃ������Ƃ��A��X�̕����N�����Q�Ƃ���҂͔O���ɒu���Ă��炢�����B�����̑ΐ�L�����A�̂����A�L�n�앺�q��A�n���H�R�Ƃ����ŏ����̑���͂Ƃ������Ƃ��āA��͂���ʂȑ���́A��\��̂Ƃ��d�����������s�̋g����傾�낤�B����ŁA�����͂��̖����m�������B�������A�ޗ��������̔N��I�ʒu�Â��͖��炩�ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ́A�����ʼn��߂ċ������Ă��������B �a�\�\����ɂ��Ă��A�\�Z�̎��̒A�n���H�R�Ƃ̑ΐ�Ɍ��y���āA�w�O�����ϕM�L�x���L���̂́A�H�R�ɏ��������Ƃ́w�ܗ֏��x�n�V���ɍڂ����Ă��邯��ǂ��A�����������łǂ�ȓ������������A���̋�̓I�ȓ��e�ɂ��Ă͌��`�����Ȃ��B���v�Z�\�]�x�̎����A����炪����ɉk��Ă���̂͐ɂ��ނׂ����Ƃł���B�S�̂�������ƈ����������`�����Ȃ��A�Ƃ����b���ȁB�\�����I�O���ɂ����Ă��炻���������B �b�\�\�w�O�����ϕM�L�x�����������ԕ��ς́A���̎��L�ɂ��A�����\��N�i1671�j�̐���ɂȂ邩��A�����v���\�Z�N�ɂ��Đ��܂ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B�������ނ́A�d�B���ɋ��Z���Ă����ĔC���邩��A���ڎw�����Ă���B�ĔC�͎�N�̍��A�F�{�ŕ����{�l�ɐڂ����\���̂���l���B�ĔC���炢�낢��b�����͂��̗��ԕ��ςł���A�����Z�\����̎d���ɂ��ẮA����A�����`�����قƂ�ǂȂ��A�ƒQ���Ă���킯���B �a�\�\�����͖��s�̕��@�҂Ƃ��ėL�����������A�������g�͎��g�̃L�����A�ɂ��āA�قƂ�lj������Ȃ��ĉ�Ȑl���������悤���ȁB �`�\�\����ł��A���Ԃ�A���ꂼ��̓y�n�Ƀ��[�J���ȓ`���Ƃ��Ă������B�����A�قƂ�ǂ����j�̒��ɖ��v���Ă��܂����Ƃ������Ƃł��傤�ȁB����́A���̕��@�҂̎�������Ă��킩��B�����قǂłȂ��Ă����������d���������͂��̎҂ł����A�قƂ�ǘb�͎c���Ă��Ȃ��B����́A�����������h�����Ȃ��ƁA���Ƃ��Ǝc��Ȃ����̂ł��B �b�\�\���������āA�ޗ��������̎��ւ��c�����̂́A�������U�̃L�����A�̒��ł���O�I�Ȃ��̂����A���@�҂Ƃ������ۑ��̂̒��ł��܂������H�L�ȃP�[�X���낤�B�������A���̊ޗ����`�����c�����Ƃ����̂́A���q�蕶�ɋL�����ƂƂ��ɁA�����E�ɂ����Đl�C�̂����i���a���������炾�B����͂܂��������R�̂��Ƃ��ˁB �a�\�\�ޗ��������L���̂��鏬�q�蕶���c�����̂��A���R���낤�B�M�B����d�B���֓]�����A�܂�������L�O���q�ֈڕ����Ă������}���Ƃ́A�����܂ŏ��q�ɋ����āA�]���͂Ȃ������B�{�{�ɐD�Ƃ����q�ɑ������A�ԍ�R�i����R�j�����R�Ƃ��ď��L���Ă����B���ꂪ�A�������}���Ƃ����q���瑼���Ɉڂ��Ă�����A���̕���������͎c��Ȃ�������������Ȃ��B����Ȃ��̂���A�喼�ƒ��̎���́B������A���q�蕶���c�����̂��A����Ӗ��ł͋��R�̎������B �b�\�\�i���}���j�����̉��E�����́A�����ɔd�B���삩��L�O���Âֈڂ������A���̒��Ï��}���ƂȂ́A�O��ڂɂ͗̒n�v��������˂��B���̌�A�킪�k���������m�̎l���B���������̌�ɂ́A�d�B�̈��u�i�����S�j�ֈڂ���Ă��낤���Ĉꖜ�B���q�̏��}������������Ȃ������̂́A����͍K�^�Ƃ��������悤���Ȃ��B �a�\�\���}�������E�{�{�ɐD�̌N�b�J�b�v���́A�L�O���}���Ƒ����̂��߂̓y���z�����ƂƂ��ɁA�������֓`���̊�b���z���Ă��ꂽ�B�������A�ނ�Ȍ�ɏ��}���Ƃ��L�O���q�ɑ����������Ƃ́A�܂��������R���B����R�̔蕶������l�́A���ꂪ�c���Ă���Ƃ������̊���ɋ����K�v������B �`�\�\������A������̂������R�ŋ��������̂́A������㌳�O�̍��X�؏����Y�����B�u�����Y�̔������������߁v�i�j�B�����i�w���X�؏����Y�x�j������Ėׂ�����Ƃ́A����Ȏ��I�Ŝ��ӓI�Ȃ��̂��A�s�̌����ɋ�����Ă悢�̂��i�j�B �a�\�\����́A�n������v���������Đݒu���ꂽ���̂���Ȃ��B���q�ɏ����Y������Ă����ƌ����o�����̂́A���㌳�O���g�ȂB �`�\�\�������̂Ƃ��A���傤�Ǐ��q�̎s���I�ŁA�����Y��ݒu�Ő��b�ɂȂ����s���̂��߂ɁA���̍�Ƃ͉��������Ɏs���𑖂������B�������͂Ȃ͂������i�j�B �b�\�\����Ȃ��Ƃ����Ă��������A�܂��A�����炩�Ȏ��ゾ�����̂���i�j�B �a�\�\���̂Ƃ��A������̕��͂܂����ݒn�ɖ߂��Ă��Ȃ������B�������ɂ������B������A����R�ł��A�҂��Ă����̂͏����Y�̕��������B����ǂ́A�\�N�ȏ���҂����ꂽ���ȁi�j�B �b�\�\���܂��n���ł́u���������Y�܂�v�Ƃ����̂�����Ă��邻�������A�ŏ��́A�u�����Y�܂�v�����������B���������s�c�����ɂȂ����Ƃ��A�ŏ��ɐ苒�����̂́A�u���X�؏����Y�v�Ȃ�B���ꂶ�Ⴀ�A�{�{�ɐD���A���̎R�̘[�̕揊�A���̑��t�̈��œ{���Ă��邾�낤�i�j�B �a�\�\�����̎s���͂������A���B�l�������B���q�s���͒��B�l�Ƃ��Ē����Ă������A���q�̗��j���A���B�l�����W���ꂽ�Ƃ������Ƃ����B �b�\�\���B�̋t�P���i�j�B�ޗ����ŕ����������Y�͒��B�Z�l�������ȁB �`�\�\�������A���̏����Y��̉��ɁA���㌳�O����̎��쏬���{�������B �a�\�\����Ⴀ�A��قǐ}�X�����U��������i�j�B�g��p�������āA��B�{�{���ɔ�����Ă����A�����܂Œp�m�炸�Ȃ��Ƃ͂��Ă��Ȃ��B �`�\�\�Ƃɂ����A���̏����Y��́A�j�����炷��A����R�ɂ͗]�v�Ȃ��̂��B�����ǁA�������������N�̏����Y�̓����������Ă��Ȃ������A����R�ɂ͂܂��~��������Ƃ������̂��B �b�\�\�u�g�앐���v�͂����m�炸�A���㌳�O�́w���X�؏����Y�x�Ȃ�āA�����Ⴞ����ǂ܂Ȃ���������B���㌳�O�����̏����Y��́A���̒J���g�Y�f�U�C�������A���̕��������ۂ��L�O����ߑ��ՂƂ��āA�ۑ����Ă����悢�i�j�B �`�\�\�Ƃ���ŁA���̎���R�̕�����A���̏��q�蕶�⑶�̗L��A����͌����܂ł��Ȃ����A�������Ō����A�w�O�����ϕM�L�x�����������ԕ��ςɂ��A�����Z�\����̎d���ɂ��Č��肪�قƂ�ǂȂ��A�Ƃ������Ƃ�����A������������ς�A�ޗ������������v�����\��������B���邢�́A�ʂ́A��X���܂������m��Ȃ������̑ΐ푊�肪�A�u���X�؊ޗ��v�̃|�W�V�������߂���������Ȃ��B �a�\�\�܂��A�Ƃɂ����A�ޗ����`���͎c�����B���̏����ł̌������G�����ɋr�F����āA���ꂪ�������S���I�ɗL���ɂȂ�ɂ��������āA�ޗ��́u���X�v�ɂȂ�A�܂��n�����B�ł��A���̎��m�̕����E�ޗ��̑ΐ���b���炽�����h�����A�ޗ��������ɂ��ē`�������������������B����������ł́A�������`�L�ɓ������`���ɂ��Ă��A���܂��܊����ȓ`�������̐Ղ��m�F�ł���B��X�͂��̍��Ղ����ǂ��āA�ޗ����`����ǂ݉������Ƃ��ł���Ƃ����킯���B �b�\�\������A�`���̈قȂ郔�@�[�W�����������āA���b�f���ƍ����\�����͂ł��邩�炾�ˁB����̍��k��ŁA�ޗ����`�������̐V�����̖���J�����Ƃ��ł������A����͕��������݂̂ɂƂǂ܂炸�A�ߐ��Љ�ɂ�����`������̌����Ƃ����_�ł��A���Ȃ萬�ʂ������肻�����B |
|
�`�\�\���āA�b�͏I�肻���ɂȂ����A���̂ւ�ŁA���낻�������낵�����ȁi�j�B �\�\���肪�Ƃ��������܂����B�ޗ����`���ɂ��āA���W���̍����ȁi�j�������W�J����܂����B�ǂ���n���ɖ������b���������āA�����ł͗v�邱�Ƃ��s�\�Ȃقǂł��B�܂��A�]���̊ޗ����_�̐�����y���ɔ����������F���ł̂��b���A�����A���čs���̂ɓ�V���܂����i�j�B�{�T�C�g�̌����v���W�F�N�g�ɂ�����ޗ����_�������A�ǂ݂����Ƃ����v�]���A�ȑO���炩�Ȃ肠�����̂ł����A����ŁA�悤�₭���̔C���ʂ������Ƃ��ł��܂����B���̍��k��́A�����U��Ԃ��Ă݂�A���������ɂ�����ޗ����_�Ɋւ��āA�L�O��I�ȏꏊ�ƂȂ�܂��傤�B����͋^������܂���B �a�\�\����܂ł̊ޗ����_�́A�܂��A��T�̓t�B�N�V�����A�����Ƒ卷�Ȃ��i�j�B�w���Ɖ]����悤�Ȃ��̂���Ȃ��B���������킯�ŁA�b�𔒎��ɖ߂��āA�[�������蒼���A�Ƃ������Ƃ��B����܂ł̏�����S���A�����Ҍ����āA�T�����猩�����Ă�낤�Ƃ������ƂȁB���ꂪ����̂悤�ȑ傫�Ȍ��ʂɂȂ����B �b�\�\����͉��X���������A����Łu�ޗ����`���̌����v�Ƃ����_������{�A����������ł������������ȁi�j�B �`�\�\���̃^�C�g���͊m�ۂ��Ă����܂��傤�B��ɂ���āA�{�T�C�g�̏������p�N�����o�邾�낤���A�������A�p�N���Ă���Ă��������B�����ǁA�Q�Əo�����炢�͖��炩�ɂ����i�j�B �a�\�\���`���ւ���������Ȃ��A�p�N���Ėj���ނ肷�鈢������������ȁi�j�B����́A����Ԃɂ킽��A���Ԗ�������{�����i�j�Ƃ������Ƃ������̂ŁA�����܂Řb���y�B�v���������A�������Ă��܂����B���I�邩�Ǝv���Ȃ���b���Ă������i�j�A�b���܂������r��Ȃ������B �`�\�\����ŁA�������A���̂��т͔�ꂽ�i�j�B �b�\�\�܂��A�����x�ɂ�����̂�����B����͂Ȃ��Ȃ��ʔ����b���ł����B�܂��e�[�}���i�����̂ŁA�˂����݂����Ȃ�ł����ˁB������܂��A�ޗ����`���͂�邱�Ƃɂ��悤�B �\�\�����ԁA�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B�܂��̋@������҂������܂��B �i2005�N11���g���j
|
