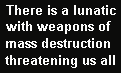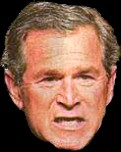|
���k�E�{�{���� �d�������������ݒ����k�� |
|
| �����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�B���N�̐̂�蕺�@�̓��ɐS�������A�\�O�ɂ��Ďn�ď��������B�����ЂĐV�c���L�n�앺�q�Ɖ]���@�҂ɑŏ��A�\�Z�ɂ��ĒA�n���H�R�Ɖ]���͂̕��@�҂ɑł����A��\��ɂ��ēs�ւ̂ڂ�A�V���̕��@�҂Ɉ��A���x�̏����������Ƃ��ւǂ��A��������Ɖ]���Ȃ��B���㚠�X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A��x�������������Ȃ͂��B�����A�N�\�O����\���㖘�̎���B�@�i�ܗ֏��E�n�V���j |
| 03 | �N���푈�E���Ɨ��D | �@Back�@ �@Next�@ |
|
�`�\�\����ǂ��납�A�܂���Ղ��C�O�h���������Ƃ̂Ȃ����q�����A���̋@��ɃC���N�֏o�����Ƃ����o�J������B����ȃo�J�ɐ��������点�Ă���A�����ƃo�J�ȍ�������X���i�j�B���ꂾ����`�����������푈�Ȃ̂ɁA���������ɐK����U���ăA�����J�ɒǐ����悤�Ƃ��Ă���B���ƂƂ��āA�Ȃ��Ă��Ȃ��ˁB �b�\�\�R�����Ȃ��ƁA���ƂƂ��đ̂��Ȃ��Ȃ��Ƃ����_���������ˁB�������A�h�q��Ƃ������̌R����̋��z���ړx�ɂ���A���q���͎����㗧�h�ȌR�����A����Ŗ��ɗ����ǂ����͕ʂɂ��Ă����B�������A���ꂪ���@���炷��Δ@�̑g�D���Ƃ��Ă���B���@�����_�́A�悤����ɁA���q���Ƃ����@�g�D�����@�����悤�Ƃ������Ƃ��B�C���N�֎��q�����o�����Ƃ�����}�́A�C�O�h���̑O�������Ă��܂����Ƃ��������ł͂Ȃ��B���q�������@������`�����X�ƌ��Ă���B �a�\�\����́A�܂�A�h���������q�����Ɏ��҂��o�邱�Ƃ��ˁB�]���҂��o��ƁA�͂��߂Đ��_���ς�B���E�̎��̌��l���̑O�ɂ́A���������������Ȃ����炾�B�����Ȃ�ƁA�C���N�֎��q�����o�������Ƃ������������B����ǂ��납�A���q���̍������l���㏸���āA���A�҂̐g����E���āA���̓���ꏊ�ɏo�邱�Ƃ��ł���B�����čŌ�ɂ́A���@�ɂ����č��@������邱�ƁA���ꂪ���҂���Ă���B �`�\�\�s���Ď���A�ꉭ�~�܂łȂ�o�����Ƃ����b�����łɂ��邻�����B���l���l���o�邩�m��Ȃ����A��l�ꉭ�Ȃ�������������A�Ƃ����킯�ł��ȁB�S�l����ł��S���A�Ƃ����v�Z���B �b�\�\�����������˂��A�s���Ď���ꉭ�~�A�Ȃ�Ă̂́A�����ɂ�����Șb���B���q�����̐��������Ŕ������Ƃ����ɓ������B���̐��{�͂Ȃ�Ƃ����ڂ����S�̎���Ȃi�j�B�Ƃ��������A��`�������Ȃ�����A���̘b�ɂȂ�B �a�\�\�����Ƃ��A����́A��`�����������āA�����̐������^�_�ŏ���ł���܂łɂ́A�܂��s���Ă��Ȃ����炾��i�j�B�R���Ƃ����̂́A�ŏ��͋��Ōق��b�����B�^�_�Ŏg���邽�߂ɂ́A��������`�����Ƃ����R�ɂ̂��Ă��܂����Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B������A�s���Ď���P���~�A�Ƃ����̂́A���i�K�ł́A���q�����A���R�Ƃ������b�������̒i�K���Ƃ������Ƃ��ˁi�j�B �b�\�\�����ŁA�痢�̓����������i�j�B�܂��������A�C���N�֎��q���𑗂荞��ŁA���ꂩ�ɋ]���ɂȂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����S���A�҂��邱�Ƃ��F��A�Ƃ����̂́A�\�����̌����ȑ������B���́A���ꂩ����ł�����A��������ȂȂ�������A����̃~�b�V�����͎��s�����A�Ƃ������Ƃ��ˁB �`�\�\����Ȃ���ȂŁA���O�������̉����̂ƃE���E�����Ă�����A�O��������l�A��ɎE���Ă��܂����B �b�\�\��l�Ƃ��܂��Ⴂ�̂ɁA�C�̓łȂ��Ƃ������ȁB �a�\�\�܂������A�Ȃ��B �`�\�\���̏T�����ł��������A�w�T������x���B�����2�l�̈�̎ʐ^���ڂ����Ƃ������ƂŁA���������ł����ˁB�O���̃��f�B�A�͂�����u�v�������A�������A���{�̃}�X�R�~�͂�����u�v���Ȃ������B�}�X�R�~�͐^����`����̂������Ȃ̂ɁA����͂ǂ��������Ƃ��A�Ƃ����킯�ł��ȁB �b�\�\��̎ʐ^�́A���҂ւ̖`�����Ƃ����B�����������ł͂Ȃ��ˁB����́A������������A�Ƃ����Љ�̃^�u�[�ɒ�G���邩�炾�B���̂Ƃ������A���Ȃ��̂��A���܂��Ƃ���B���͉̂B������˂Ȃ�Ȃ��B�������������X�i���K�j������B������A�u�͂����v�Ƃ��������Y�����J���邱�Ƃ����肦���킯���B��������ƁA���̂̌��J�́A���Y�ɓ������Ƃ������ƂɂȂ�B�����ŁA���҂ւ̖`�����Ƃ������ƂɂȂ�B �a�\�\���������Љ�̋�C�ɏ悶�āA��̎ʐ^���J�����@�x�ɂȂ�B�}�X�R�~������K�����āA��̎ʐ^���f�ڂ��Ȃ��B���̎���K���̘_���́A�����}��̈����Ɠ����Ȃ��i�j�B �b�\�\�����炾��A���{�̃}�X���f�B�A�̌���́A���{�l���E�̎��̂Ƃ������A���Ȃ������ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������̓����ɉ���ł��Ȃ�����A�������ߏo���A�r������B������̕������҂ւ̖`���ł͂Ȃ��̂��B�����}��̈����Ɠ�������K���̘_�����Ⴀ�ȁB �`�\�\��������A�푈�f���͂��ׂĂ��@�x�ɂȂ�B�O������l�̈�̎ʐ^�ł͂Ȃ��A��̉f���̃��B�f�I�^�������B����͈ꎞ�l�b�g��ŒN�ł����邱�Ƃ��ł����B����������ŏo���Ă������B�����ǁA����͂�肷�����ȁB �b�\�\�������ȁB���܂�Ӗ��͂���܂��B�C�O�Ȃ�j���[�X�ԑg�ŗ��ꂽ���肫����̉f�����B�������A���{�l�O����������Ƒ_���ĎE���ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���炩�Ɍx�����ȁB �a�\�\����͓��{���{�ɑ���x�����B�A�����J���{�ɓ������ČR���𑗂荞�����Ƃ��鑊��ɑ��āA�댯������~�߂����������Ƃ������b�Z�[�W���B�Ƃ��낪�A����ɑ��āA���{���{�̔����́A����ȋ����ɍ�����悤�ł͒j���p�i�����j��Ƃ������Ƃ��ˁB �b�\�\���낻��A�Ԑ��͐퓬���[�h�Ȃ�i�j�B�������A�ǂ����ŁA�悭����Ă��ꂽ�A�Ƃ���������������ˁB����́A�e�����X�g�炪�悭����Ă��ꂽ�A�Ƃ����t�̈Ӗ����i�j�B �`�\�\����ł���ƁA�퓬���[�h�ɓ����A�Ƃ������Ƃł��ȁB���q�����o�����ɁA�]���҂��o���Ƃ������Ƃ́A�\�z�O�̐��ʂ��B�܂������A���̘b���o�āA��疜�~�o���Ƃ����B�������̈ꉭ�Ƃ��A���̋�疜�~�Ƃ��A�����Ă��邪�ˁA�}�������x�@������h�m�ɂ���Ȃɏo���Ă��Ȃ������͂����B �a�\�\������A����́u����v�Ȃ�i�j�B�}�������x�@������h�m�ɂ͌����͂��Ȃ��Ă��A�C���N�Ŏ��˂Ζ@�O�ȋ����o�����Ƃ����A����͎��q�����@�������Ă̓����ȂB�����Ǝv���A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͂��Ȃ�悢�A�Ƃ����Z�i���ˁB |





|




*�y�����z�Ӗ��s���� |
�b�\�\�Ƃɂ����A����͂��ׂė��̃n�i�V���B�C���N�֏o�čs���ɂ́A��`�������R�ł��~�����Ƃ��낾���A���ꂪ�Ȃ��B�u�䍑�̂��߂Ɏ���ł܂���܂��v�Ƃ͌����Ȃ��B�͂����肢���u�A�����J�哝�̂̂��߂Ɏ���ł܂���܂��v�Ƃ������Ƃł����Ȃ��i�j�B����ȃo�J�Șb�͂���܂��B����܂����A�Ƃ��낪������͂����������ƂȂB����Ȃ��ƂŁA���q���̎�҂��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B �a�\�\�����Ɩ��m�Ɍ����A�u�A�����J�哝�̂̂��߂Ɏ���ł܂���܂��v�Ƃ��������Ȃ��h���B����͔����z�̂��邱�Ƃ��i�j�B �b�\�\���₨��A�����Ԃ��I�Ȃ����t���ˁi�j�B �a�\�\�ނ��A�����I�Ƃ��������A�A�����J�鍑��`�̗��s�s�Ȑ푈�̂��߂ɁA���{�̎�҂����̐������]���ɕ�����Ƃ́A�����Ƃ��A�Ƃ������Ƃ��B �b�\�\���₢��A��₩���Č������̂ł͂Ȃ��B�^�̗J���҂Ȃ�A�������A�����������Ƃ͌���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����͉E���̐ꔄ�����ł͂Ȃ����B�����܂Łu�O���[�o���Y���v�Ƃ������̕Ē�ꉡ�x�z���ɂ܂������܁A�����̃i�V���i���Ș_���͂ނ���K�v�Ȃ̂��B�������낤�H�@���{�̌o�ϐ���ɂ��Ă��A���O�ɂȂ�����Ƃ₻�̎��Y���A�A�����J���{�̎�ɖ@�O�Ɉ�������n���Ă��邶��Ȃ����B���ꂪ���݂̓��{�ł͍���Ƃ��ĕ��C�ōs���Ă��邱�Ƃ��B������̂��āA�����ʂ�A�����I�s�ׂƌ����̂��B�������������I�s�ׂ����C�łȂ���Ă���ȏ�A�A�����J�鍑��`�̗��s�s�Ȑ푈�̂��߂ɁA���{�̎�҂����̐������]���ɕ�����̂ɂ��A���̒�R���Ȃ��킯���B�E���͂���ɑ��A�{���̂��ˁB �`�\�\�C���N�֎��q�����o���Ƃ������Ƃ́A�͂�����ƕĒ鑤�ɗ��Ƃ������Ƃł��ȁB�������A�O���R���ɂ���̂ɑ����R�^���A���W�X�^���X���e�����X�g�ƌ��߂��āB�����������A�W�A�I�ȍs�����Ƃ����ȏ�A���n�̃��W�X�^���X����͓G�ΐ��͂Ƃ݂Ȃ���A�U������B �b�\�\�l���Ă݂�A����Ȃ��Ƃ��B���ăA�����J�R�ɐ�̂��ꂽ���{���A����ǂ͐�̌R�ɉ���낤�Ƃ��Ă��Ă���B�������A�����J�R�ɉ��S���āB�u�A�W�A�v�Ƃ����|�W�V�����͂ǂ��Ȃ����B �a�\�\������A�����Ȃ�A�哌�����h���̈�u�͂ǂ��Ȃ����i�j�B���{�l�͂����Y��Ă��܂����̂����B���܃C���N��A�t�K�j�X�^���Ŏ��s����Ă���A�R����̂ɂ͉��̑�`���Ȃ��B�ނ���A��`�ȂǁA���͂�K�v�͂Ȃ��A�Ƃ�����ݕs���Ȓ鍑��`���B���̑�`�̂Ȃ��R����̂����A�L���X�g��������`��w�i�ɂ����鍑��`�I�s���ł���B �b�\�\�����Ē[�I�Ɍ����A����̌R����̖̂ړI�́A���炩�ɐΖ��������B�T�_���E�t�Z�C����r�������̂́A�v����ɍ��ېΖ����{�̂��߂ɁA�C���N���ĐA���n������A���������sre-colonization�t������̌R����̂����B�t�Z�C�������ӂ��邾���Ȃ�A���ꂪ���������ȏ�A�������ƈ����g��������B�����͂����ɁA���ڂȂ��R����̂𑱂��Ă���̂́A�A���n��Ԃɂ��Ă���Ƃ������Ƃ��B �`�\�\�����܂ŘI���Ȓ鍑��`�I�s���ł���ɂ�������炸�A���{�̃}�X�R�~�͂܂��u�e�����Y���v�Ƃ����A�����J�̘_�����_���̂悤�ɔ�䍂��Ă��܂��ȁB�_���͉����l�����Ɍ��t�����邪�A���{�̃}�X�R�~�����͋���ۂȂB����łȂ�������A���܂ʼnp�Ē鍑��`�ɐA���n������Ă���킯�i�j�B �b�\�\������ˁA���{���{���A�C���N���R����̂��邱�Ƃ́A���ېΖ����{�̂��߂��A�Ɩ��m�Ɍ��������B�T�_���E�t�Z�C���ɔC���Ă�������A���ېΖ����{�ɃC���N�̐Ζ������R�ɂ����������A�u���v�v�ɂȂ�ƂˁB���̍��v�̂��߂ɁA�R����̂ɎQ������̂����āB �a�\�\�C���N�����x���Ȃǂƌ����Ă��邪�A����͌R����̂��������邽�߂̌������B�ĉp���C���N��A���n�����悤�Ƃ��Ă���B���̃o�X�ɏ�肨�����ȁB��肨�����ƍ��v�ɂȂ�Ȃ��ƁA������������B�Εē����Ȃ�Čӗ��Șb���o������A�b���ʂ��Ȃ��B�p�Ă��C���N��A���n������R����̂ɁA���{���Q�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ��ƁA���{�����͐Ζ����������킳��邱�ƂɂȂ邼�i�j�A�Ƃ��ˁB �b�\�\�������������́A�u�b�V�������⍑�ېΖ����{������ۂɂ��邾�낤�B���������A����Ȃ炻��ŁA���̂��߂Ɏ��q�����o���A�C���N�̐Ζ������̂��߂Ɏ��q�����o���A�ƌ����悢�B���q�������S�l���̂��ƁA���������ɕK�v�ȃG�l���M�[�m�ۂ̂��߂Ȃ�d�����Ȃ�����Ȃ����i�j�A�Ƃ����L�����y�[����悢�B �a�\�\�����܂��ɂȂ��Ă���̂́A���̃|�C���g���B�������A���������ɕK�v�ȃG�l���M�[�m�ۂ̂��߂Ȃ�A���q�������S�l���̂��ƈ������Ƃ����_���́A�����ɁA���{�����ɕK�v�ȃG�l���M�[�m�ۂ̂��߂Ȃ�A�R����̂ɒ�R���鐨�͂͟r�ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�C���N�l�����l���̂��ƒm�������Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ����_���ł�����ˁB���ꂪ�{���̂Ƃ��낾���A�Ȃ�Ƃ��c�����A���i�j�B �`�\�\�����ŁA����ȉ��ꂽ�G�l���M�[�ȂǗ~�����Ȃ��A�����ƃN���[���ȃG�l���M�[���~�����A�ƂȂ�A���̍������㓙�ł����ˁi�j�B �b�\�\�����Ȃ�ƁA���������q���h�����A�Ƃ����I���������o���Ă��邼�i�j�B����ƁA�㓙�łȂ������́A�����̓C�����A���q���h���̕��������A�Ƃ����I�������������ȁi�j�B �`�\�\�悤����ɁA���v�Ƃ����_���Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł���B���v�Ƃ����_���������o���A���������낤�ƁA���������낤�ƁA�]���҂��o�Ă�������܂�Ȃ��Ȃ�B�����������A�C�̓ł����d�����Ȃ��A��ނ����Ȃ��A�Ƃ����b�ɂȂ�B �a�\�\���́u��ނ����Ȃ��v�̘_���ɁA��������������Ă��܂��B��������肾�ˁB�A�����J�̌R����́A����ɂ͑�`�����͉����Ȃ��A�������u��ނ����Ȃ��v�Ƃ����킯���B�A�����J�哝�̂ɐK����U����{���̏�Ȃ��p�́A���Ă͂���Ȃ����A�������u��ނ����Ȃ��v�i�j�B �`�\�\�Ȃɂ��Ƃ������ł����A�u��ނ����Ȃ��v�Ƃ����Ă��邠�����ɁA���Ԃ͂ǂ�ǂ�����B�A�����J�̈ꌳ�x�z���ǂ�ǂ�ѓO�����B���͂⍑�A�Ȃǖ����ł���܂łɂȂ����B��肽�����肾�B�A�����J���e�F���Ȃ������͒n����ɑ��݂ł��Ȃ��Ȃ�B�S���A��Ƃ����ׂ����i�j�B |
|
�a�\�\���������A�����ׂ��ɂȂ����a�l��߂܂����B�T�_���E�t�Z�C���́A�悭�����Ă����ȁB�Ă�����A����ł������Ǝv���Ă������B �`�\�\�ł��A�����Ă����ɂ��Ă��A�ނ͂������͂������̂ł��傤�ȁB�_�Ƃ̒��̒n���Ɍ@���������Ȍ�����ɉB��Ă���Ƃ����߂܂����B��̕ČR�͑�͂��Ⴌ�A�\�N�́u�߂܂����Ƃ��A�l�̂悤�������v�Ɗ��������ɔ��\���Ă����i�j�B �a�\�\�u�E�C�A�K�b�f���iWe got him�j�v�i�j�B �b�\�\����������Ȃ�A�u�K�b�f�[���iGod damned�j�v�Ƃ����ׂ����낤�i�j�B �a�\�\���̉��l�ɂȂ��ĕ߂܂����t�Z�C���͈�l�ŁA���̑哝�̐e�q���ȂǁA�e���`���Ȃ������B�ƍَ҂͖{���I�ɌǓƂȂ��i�j�B��̌�́A�ނ������ĂĂ������ĂȂ��Ă������������B�����U�����܂ށA�ΐ�̌R��R�����ɂ͊W�Ȃ����낤�B���ꂪ�t�Z�C���̎w���ɂ����̂��Ƃ́A������v��Ȃ��B��̕ČR�͑�͂��Ⴌ�����A��������A�t�Z�C����N���܂ł����ƕ߂܂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������A�Ƃ��������͂ǂ��ȂB�A�����J���{�́A����Ń|�C���g���҂������肾�낤���A���Ƃ��Ɣނ������Ă��Ă������ĂȂ��Ă��A����Ƃ͖��W�ɑΐ�̌R�����͓W�J����Ă����B �`�\�\���{�̃}�X���f�B�A�ɂ��Ă��A���̃j���[�X�ɕ�����Ă����B���ς�炸�A�o�J���˂��i�j�B��̎x�z���ǂ́A�t�Z�C����ŞN�O��Ԃɂ��ĎB�����f���𗬂����B���ǂ����������̂��B �a�\�\�t�Z�C�������炵���ɂ��Ă������ȁB���̋L�҉�́A�鍑��`�̈�煂���I���Ɍ��������̂��ˁB���̖��C�Ȏ����́A��m�炸���ӎ��ɏo�Ă��܂����A���̖{�����낤�B �b�\�\�A�����J���{�́A�t�Z�C����߂܂��āA������ǂ��������邩�A�����ɐ��Ԃ̎������W�߂����Ă����āA���̌��ɂ�肽�����Ƃ������肾�낤�B�C���N��̂̕s�������A�t�Z�C�������Ƃ����]���Ō떂�������肾�ˁB �a�\�\�t�Z�C���ߑ��́A�C���N��̃L�����y�[���̓�������B�A�����J���{�̓C���N��̂ŃO�b�h�j���[�X�������Ȃ������B�����œP�ދC�^���������Ă���Ƃ���ŁA���̕������B�������A����́u�������Ǝ咣����v�L�����y�[���ˁB���ꂩ��A�t�Z�C���̈��t��\�����ĂāA��������B�t�Z�C��������H�킹���邼�i�j�B �b�\�\���������ˁA���̖\�N���x�����̂́A�A�����J����������Ȃ����B�t�Z�C���̐�����Ă����{�̓A�����J���{�������B �`�\�\�����ł��ȁB���ăt�Z�C���������x���Ă��������̓A�����J�������B�t�Z�C���������g���āA�C�X����������`�̃C����������ׂ����悤�Ƃ����ˁB�A�����J�ɂƂ��ēƍِ����قǁA�s���̂悢���̂͂Ȃ������B�ւ��ɖ��剻����ƁA��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A������A�ƍِ����̕����x����B����̓C���N�Ɍ���Ȃ������B�ƍَ҂Ƙb������A�ȒP�e�Ղɗ��������B�t�Z�C������������قǔȂ��Ƃ��ł����̂́A�A�����J���e�F���Ă������炾�B���������Ŕ�����ȏ�A���ł���点�Ă����B�������ċ��Ŕ����邠�����͂悩�������A���̓ƍِ����Ɣ��ڂ������āA���ŗ������Ȃ��Ȃ�ƁA����ǂ͂��̓ƍِ��������ׂ��ɂ�����B �b�\�\���ꂪ����܂ł̃A�����J�̎���������B���̓_�ł͈�т��Ă���i�j�B�������A�u�b�V�������͖����Ȃ��Ƃ����Ă��邵�A���Ȃ�A���������Ƃ�����Ă��邼�B���̐����́A�X�L�����_���ʼn�ŁA�Ƃ������Ƃ����肤��ˁB�����͂Ȃ����낤�B �a�\�\�����Ō����A�O�ɘb���o�����A���ˑ̐��ˁB�ƍN�̎���܂ł́A�܂��A�������̕��͋C���������B�փ��������ď��喼�ɏ������Ă�������B���̉��`���������B����Ƃ͍ő�̑喼�ɂȂ������A����ł����喼�̈�Ƃ����F�����������B���������ꂪ�ƌ��̎���ɂȂ�ƁA�����W���I�ɂȂ��Ă��܂��B����܂łɁA�����Ƃ����ׂ��A���喼�̏���������Ă���B��ւ�肵�Ă邤���ɁA����Ɏ��������喼�͋��Ȃ��Ȃ�B �b�\�\���܂�A�����J�哝�̂́A�����ʂ����E�̐��Α叫�R�i�j�B�����ł͂Ȃ����ˁA���̐��́u�v�Ƃ́A�C�X����������`���ˁB��X�̍��́A���̐��Α叫�R�ɑg�D����āA�C���N�R����̂̂��߂ɓ������������Ă���B����ɗB�X���X�Ƃ��ĉ����邱�Ƃ́A�u��ނ����Ȃ��v���Ƃ��낤���ˁi�j�B �`�\�\�C���N���ЂÂ��A����ǂ̓C�������A�V���A���A���������V�i���I�͂ł��Ă���B���E���̏��喼�́A���̐��Α叫�R�ɒ�R�ł��Ȃ��Ȃ����B�����āA�����͖k���N�B���ꂪ�Еt���A�n����̒�R���͈͂�|�ł������ƂɂȂ�B�V���ו��A�i���̕��a���K��邼�i�j�B �a�\�\�k���N�ɂ͐Ζ��͂Ȃ�����A�N���̃R�X�g�Ɍ����������b�g�͂Ȃ����ˁB�L���X�g���k�̐��m�l�̂��Ƃ�����A���{�l�̌R�����g���Ă�点����肩�ˁi�j�B �b�\�\�����Ȃ�Ɗ�ԘA��������ȁB�ǂ�ȑ̐��ł���������A���a��������B�A�����J�����Α叫�R�̈ꌳ�x�z�A�ƍق̐��̒��ɂȂ��āA�n���ɕ��a������Ă���B�������A���̂����A�V�c�É����ł͂Ȃ��āA�A�����J�哝�̖����O�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ˁi�j�B �a�\�\�����ɂ́A���������Ȃ��Ă���B���̕��a�Ɩ����`�A���̋A�����܂��ɂ��ꂾ�B���{�l�̓A�����J�ɐ�̂���Ĉȗ��A���̐��܂ŃA�����J������A�A���n�����ꂽ�B���{�قǕĒ�x�z���ѓO���ꂽ���͂ǂ��ɂ��Ȃ��B �b�\�\���{�͌R����̂���āA�]���܂ŐA���n������Ă��܂����B����܂ł̓t�@�i�e�B�b�N�ȍ������ƐM�����Ă������A�ӊO�Ȃ��ƂɁA�L�̂悤�ɑ�l�����Ȃ����܂����B�C���N�̌R����̂ł��̑O������҂����Ƃ���A����͍��{�I�Ȍ��ł���i�j�B �`�\�\���ꂪ�؋��ɁA��̌R����̎����U���B���̎����U���̘A���ŁA�J�~�J�[���U�U���͊��S�ɂ�����D���܂����ȁi�j�B �b�\�\����Ȃ����͕ԏサ�������i�j�A�J�~�J�[�U���������ǂ������Ă������A���ꂪ�������悭�킩��B���ݓ��{�l�̓C���N��R���͂̃Q�����I�����U�����A���̒ɂ݂��Ȃ����Ă���̂ł͂Ȃ����B�ނ���A�ɂ݂̋���������Ƃ���A�����U���ŎE������鑤�ɑ��Ă̂��ƂŁA�����Ď������鑤�̒ɂ݂ւ̋����ł͂Ȃ��B�������A���Ă̐_�����U�����A�ߌ��Ƃ��ċL�����A���̒ɂ݂ւ̋����͎���Ȃ������͂����B�Ƃ��낪�A�C���N�̎����҂̒ɂ݂ɋ�������ǂ��납�A����Ȃ閳�m�֖��ȋ��M�I�ӓ��Ƃ��Ă������Ȃ��B����ł́A��X�̕��c�̐���́A���ăJ�~�J�[�U�������s���Ď���������҂����͕�����܂��B �a�\�\���̐��܂ŃA�����J������A�A���n�����ꂽ�A�Ƃ������_�ŁA��X�͂������łɁA�펞������������҂����𗠐��Ă���킯��B����͌R����`�̋��M�I�ȍs���������Ƒ����������_�ŁA��X�������A�����U�����鑤�ɉ�邱�Ƃ͗\�肳��Ă����̂��B���q�����o���Ƃ������Ƃ́A�R����̂̈�[��S�����ƂŁA�����U�����鑤�ɗ��Ƃ������Ƃ��B���j�͉��A���˂��B �b�\�\�R���j�A���Y�����B�g�Ɏg���āA�|�X�g�E�R���j�A���Y���Ȃ�āA�̂Ȃ��Ƃ������Ă��邠�����ɁA�{���̃R���j�A���Y���ɊѓO����Ă��܂����A���B �`�\�\�ŋ߁A��w�n�̂ǂ����̊w��ŁA���\�͂�����^�����܂ŁA�p��ł�낤�Ƃ������ƂɂȂ����炵���B����ȂǁA�܂��ɔ]�ɂ܂ŋy�R���j�A���Y�����ˁB�p��鍑��`�ɑ��郌�W�X�^���X�Ȃ�Ĉӎ��͂ǂ��ɂ��Ȃ��B �b�\�\���̂����A�p��ŕ\���ł��Ȃ��T�O�͂��@�x�ɂȂ邼�i�j�B�Ђǂ�����ɂȂ����ȁB �a�\�\����A�܂������B�������Ȃǂ������Ȃ��i�j�B �b�\�\�������A�L���X�g���鍑��`�́A��������̂��̂ł͂Ȃ��A�`��������ˁi�j�B�L���X�g���鋳�ƐA���n��`�́A���ł�16���I�ɓ��A�W�A�ɐi�o���Ă������B �`�\�\��Ă�C���h�ŐA���n���ɐ������āA�n���Ō�̃G���A�A�ɓ��ɉ���Ă����B |


 Drag makes him "Disoriented" 


 

|
|
�\�\���āA�A���n���̘b���o���Ƃ���ŁA�L���X�g���鋳�t��땺�Ƃ���A���n�����ƁA���邢�͏G�g�̒��N�N���͂ǂ��������Ƃ������̂ł����B����Ɋ֘A���āA�퍑�Љ�̎����A���邢�͏\�Z���I�̐퍑���ƁA���̎Љ�̍��فA�Ƃ������Ƃł́A�������ł��傤���B�������ʉ߂�������̓]�ςł����B �`�\�\�܂��A����Ƃ����l�����������Ƃ������Ƃ�����ˁB���_�����ł��ȁB�������A����͕��_���������番���ցA�Ƃ����P���Șb�ł͂Ȃ��B �a�\�\���Ȃ��Ƃ��퍑���Љ�Ƃ����̂́A����ł���������������Ȃ������Љ�ˁB���_�̋�ʂ͂Ȃ��B�������������Ă����̂́A�ƒP�ʂł͂Ȃ��A���Ƃ����������̒P�ʂ��ˁB�̎�̒����ɉ�����̂��A���P�ʂʼn��l�o���A�Ƃ����b�ɂȂ�B�̎�̕����A����Ǐo���Ă��ꂽ��A�N�v�͂��ꂾ���Ə��Ƃ������āA�������o���B���邢�́A����͓�\�������A�������H�Ƃ͒��邼�A������p�ӂ��Ă��邼�A�Ƃ��ˁB�����Ă݂�A�������̒����ŁA�b���݂����ɂ��Ē�������B �b�\�\���������_�ł́A���ˊ��̂悤�ɕ��_�����͂Ȃ������B�������A�ނ��A�̎�͕��m�Ƃ��������W�c������Ă����킯���B���m�͒m�s���Ă��邩��A��}�E���ԂƂ������z���������A��Ă̂��Ƃ����A���m�͉ƒP�ʂœ����ɉ�����B�o�w�̂����͂�����ق��ˁB���������_�ł́A���_�����͐퍑���ɂ��������B�ނ������I�ɂ͕��_�����ŁA��펞�ɂ͑��P�ʂŒ�������ˁB �a�\�\������A����I�ɂ͕��_���������A�퓬�Ƀv�����A�}���Ȃ��Ƃ�����Ԃ��B�ނ�m�Ƃ����E�l�̐��Ƃ͂������A����͗v����ɖ\�͒c���ˁB����ł����ƁA���X�g�Ƃ����g�D���ˁA������C���[�W��������B �b�\�\���m�Ƃ����ƁA�g���I�ɏ�ʂƂ������o�����邪�A����͋ߐ��̒����Љ�ł̂��ƁA�퍑���͂����ł͂Ȃ��ȁB |
|
�a�\�\�ʔ����b������ˁB���ꂽ���͐��ɏo�Ă��܂��āA�邪����ۂɂȂ邩��A���܂���A��ɓ����Ă���A�Ɨ̎傪�e���֎w������B���ꂾ�ƁA���֏o��̂͗̎�ȉ��̕��m�����A������̂́A�S�������Ƃ����\�}���B�����܂łɂȂ�ƁA���_�A�т͂��Ȃ�̂��̂��B����������A��ʖ��O�͖T�ώ҂̗���ł͂Ȃ��A�ނ���푈�ɉ��S���Ă���B�푈�Ɋ������܂�Ă���Ƃ������ɓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �`�\�\���������ꍇ�łȂ��Ƃ��A�n��̑��⒬�̏Z�l����ɓ���P�[�X�͑����ł��ȁB����́A�ǂ��������Ƃ��ȁB �a�\�\�������A�푈�ɂȂ�ƁA���⒬�̑���k�������l�A�܂菗�q���V�l�́A���Ƃ��A�R�֔��Đ퓬���I��̂�҂B�Ƃ����̂́A�N�����Ă������̗��D�����������炾�B������A���܂���A���D�����肵�Ă��Ȃ��ŁA�����Ɛ^�ʖڂɏ�U�߂����i�j�A�Ȃ�ď���������������B���������A��U�߂͂قǂقǂɂ��āA���D���Ĉ����g�����Ƃ����`�Ԃ̐N���푈�����Ȃ��Ȃ��B �b�\�\���D���푈�̖ړI�������Ǝv����ӂ�������ˁB�퍑���́A�N��������N�����ꂽ�肵�āA���D�������Ă���B�N�����Ă��A���������ƈ����g����B���̍s�����A�����̎��s�E�s���ƌ��ẮA�ԈႢ���B����͐푈�̓��@���̓y�I��S�Ƃ������A�험�i�ړ��Ă̐킳���Ƃ������Ƃ��ˁB���̓_�A����̈�ʓI�����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�B �a�\�\�����������˂��A��O�����Ƃ������A�낭�ł��Ȃ������o��������菑���Ă�������ˁi�j�B�o���������Ƃ����j�����̗~�]������āA�A���͉҂��ł����B�������������������p�Y�Ƃ��ď̗g����̂́A���̉ƒ��q���̋L�^���������A����̒ʑ���Ƃ����̏���������Ƃ����ĕς��ˁB �`�\�\�ǎ҂͏�����ǂ�ŁA�p�Y�Ɠ��ꉻ���邪�A�����łȂ��Ă��A�����͉p�Y�̎q���Ƃ������C���ɂȂ�B�I���W�D�݂̃q�[���[������A���ꂪ�n���Ɉ����i�j�B |


|
 

*�y���@���L�z 
*�y�����n�z |
�`�\�\�퍑���̗��D�Ƃ����ƁA���ڂ̕��𗪒D����ق��ɁA�u���c�v�Ƃ����ēc��ڂ̈�������Ď�������A���q���������čs���Ă��܂��l�̗��D���������B���i�A���c�A����Ɛl�ԁA���̎O�����D�̃^�[�Q�b�g�ł��ˁB �a�\�\�����������Ƃ��ˁB�ŋߕs���̂������A�_�앨�̐ޓ����������Ă���B���ēD�_�͂悭���������A�����䂪�Ƃł����ꂽ���Ƃ����������A���ꂪ���ɂȂ��ċN����Ƃ́i�j�B���N�܂ł͑q�ɂ���̓D�_���������A�Ƃ��Ƃ����N�́A�܂��ɂ��̊��c���������ˁB���N���Ă݂�ƁA�c��ڂ̈�������Ă��܂��Ă���i�j�B �b�\�\�͂����܂ł������i�j�B���̂����A�l������邩�ˁB�Ƃ�����퍑���̗��D�A�l�Ԃ̗��D�Ƃ͌����Ă��A���q�������ł͂Ȃ��B�j���߂�ɂ��āA�A�s����B����͂�����ߗ��ł͂Ȃ��B���i�Ɠ����悤�ɁA�l�Ԃ����i�ɂȂ����炾�B�l�g�����̏��i�Ƃ������Ƃ��ˁB�푈���I��ƁA���������s�����B����͗��D�i�̎s�A�Ȃ��ł��l�g�����̎s���B�푈���I��ƁA���i�Ƃ��Ă̐l�Ԃ���ʂɏo���B�傫�ȍ���̌�ł́A����A�����Ƃ����A���i�Ƃ��Ă̐l�Ԃ���������B���v�����W����A�Ђƈ�l���Ȃ�����@��������B�O�����i�j�B �`�\�\���{�֕z���ɂ����鋳�t�̕����ɂ�����ȕ�����܂��ȁB �a�\�\���[���b�p�l�͓����A���E�����r�炵�܂����āA�O���[�o���ȓz��s����`�����Ă����B����A�W�A�ɓ��{�l�͂��Ȃ�o�Ă����B�P�g�E�i�ѓ��j�ɔ����āA�}�J�I�A�C���h�̃S�A�A�ʂĂ̓��[���b�p�܂ŁA�����ٍ��֘A��čs���ꂽ�A���������������낤�B����ɂ͐؎x�O�鋳�t����݂��Ă����i�j�B���������A�|���g�K����X�y�C���̐鋳�t�̕z�������́A�f�Ղ̗��v����o�Ă����B�L���X�g���鋳�̃R���j�A���Y���́A���Տ����ƕs�����ˁB���̂Ƃ��l�ԂƂ����̂͏d�v�ȏ��i���ˁB �`�\�\����ƁA�퍑���̗��D�Ɛl�g�����̃m�E�n�E�́A�鋳�t���狳����ꂽ�Ƃ������Ƃł����ȁi�j�B �a�\�\�K���������������킯����Ȃ��B���V�A������ȑO����A���{�ɂ��l�g�����͂������B�����߂�ɂ��ꂽ�A�����A�e�ʂ������߂��B��������l�������B���l�͖{���A�ǂ���ɂ������Ȃ������܂��͗����I���݂�����A����╺��E���i�����肷�邵�A����Ȑl�����߂��̒��������B���ɂ͕K�����������l�������l���t���ĉ�����B�������A���l�������W�c�ŁA�艺���g���đg�D�I�Ɂu�l����v�����āA���v��������B�������A���ꂪ�A�s�����قǁA�g�D�I�ɑ�ʂɂȂ����̂́A�\�Z���I�㔼�B�܂�A�L���X�g���鋳�������ĈȌ�̂��Ƃ��ˁB�l�Ԃ̏��i���́A�������ăL���X�g���̋����̈���낤���i�j�B �`�\�\�퍑���̐푈���`���F�[�V�����ɂ��āA�]���́A�̓y�I��S�Ƃ������͜~�����ˁB�푈�����퉻����̂́A�l�ƕ��Ƃ����험�i�ʼn҂��Ő����Ă����A���������u�푈�o�ρv���������Ƃ������Ƃł��ȁB �a�\�\�������A�푈�ő���c�����r�p���ĐH���Ȃ��Ȃ�������A�푈�ŐH���Ƃ�������ɂȂ�B�푈�ł����҂��Ȃ��ƂȂ�ƁA�푈�͂�߂��Ȃ��B���ꂪ�퍑���̂����������ɂ킽�������R���B �b�\�\���c�M���̌R���ȂǁA���ꂱ���g�D�I�ɐ����߂������Ă���ȁB����͔����߂����邽�߂����A�����͂ǂ��̐��ł����������L�l�������B �`�\�\�푈�̓��@�͐험�i�ړ��āB����������V���Ȃ���A����������ɂ͉����Ȃ��i�j�B�l�Ԃ��߂�ɂ���A���ɂȂ�B���������V�X�e�����o���オ��ƁA�푈�͐l�Ԏ��̎�i�ɂȂ�B�푈�͎E�����������ł͂Ȃ��A�����߂荇��ɂȂ�i�j�B �a�\�\����Ŏv���̂����A���q�蕶�ȂǂɐV�Ɩ���́u�\��v�̉ƂƂ���ˁA���̏\��p�͌㐢�̂悤�Ȍx�@�����̕ߔ��p�ł͂Ȃ��A�����������Ől�Ԃ��߂�ɂ���A�l�Ԏ��̋Z�p�������̂ł͂Ȃ����B �`�\�\�����A����͕������N���_�ɂ�����V���ł��ȁi�j�B �b�\�\���͕����Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��B�g���̋N���͏\��i����j�p�ŁA���ꂪ�l�Ԏ��̋Z�p�������A�Ƃ����̂͂��肤�邱�Ƃ��ˁB �a�\�\�����߂�ɂ��Ă��A����ł����ߗ��Ȃ�A�H�킹�Ē����ĂƂ����o������邾�����B�����߂�ɂ���̂́A���邽�߂��ˁB����������ʕ����́A�����A�����߂艽�l�Ƃ����`�����ˁB�����ł́A�E�������̉��{�������߂�ɂ��Ă���B�����Ȃ�ƁA�t�ɐN������鑤�́A�R�֓����������ł́A���̍Г��������Ȃ��A�ƂȂ�ƁA�Z������֓������Ă�킯���B�퍑���A�R��ł��ӊO�ɖʐς��L���̂́A�Z���̔���\�肵�Ă̂��Ƃ��낤�B �b�\�\���������킯���B���������āA�̎�͏Z����ی삷��`�����Ă����킯���B���܂����ی삵�Ă�邩��A�ӂ��炨������ɂ�����ƍv���ł����A�Ƃ����_�B���m�͖{���I�ɖ\�͒c�Łi�j�A�������������ŔN�v�����B�������A�̎�̕����Z����A�s����Ă��܂��ƁA�o�ς����藧���Ȃ�����A�ی삵�Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��B�̎�ɂƂ��ĉ����_���[�W���Ƃ����ƁA���Y�҂����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B �`�\�\���̔��ʁA���U���������B�Z���������Ă��܂��B���邢�́A�u�S���͑��̂Ȃт��₤�Ȃ�v������A�ǂ̐��͂��낤�Ƌ������ւȂт��B�̎�ɂƂ��ẮA���Ƃ��ƏZ���͂��ĂɂȂ�Ȃ����̂��i�j�B �b�\�\���邢�́A�o�w���ċ���ۂɂȂ鍪����Z���ɔC����Ƃ����b�����A�z��̏㐙�i���̌P���ɁA������R��������Ȃ�����Ƃ͂����A�n���l�i�����j��ɏ��C����̂͊댯���A��Ȃ��Ȃ�Ɠ����o����āA���Ǐ�͓G�̑��ɂ���Ă��܂����A�Ƃ���B�����Đl����M�p����ȁA�Ƃ����킯���ȁi�j�B |
|
�b�\�\���_�����̘b�ɂ��ǂ�A���_�����Ƃ����̂́A��ʂɂ͏G�g�̓���ȗ����Ǝv���Ă���B�������A�G�g���͂��߂Ă����������킯����Ȃ��B����ȑO����A�y���K�͂Ŏx�z���m�����āA�����喼�ɂȂ����̎�́A�����Ă����������Ă����ˁB����Ꝅ�őy���x�z�����������z�O�ł����A������~�A��������������Ă����B �a�\�\�V���N�Ԃ̏ؔ@�̋���֗߁i1537�N�j���ˁB�����֎~�̌`�Ԃ����A����͕��͂��ꌳ�x�z���邽�߂̂��̂��B����Ӗ��ł́A����O�̑y���x�z�́A�G�g�̓����`�Ԃ̐�삯���ˁB�����ďG�g�̓Ƒn�ł͂Ȃ��A�ꍑ�K�͂ł́A�O��͂�����ł����邾�낤�B �`�\�\���̂����A����ƌ��n�̓Z�b�g�ɂȂ��Ă���B�_���Ƃ��ē�����������A���Y�҂Ƃ��ċ������������Ƃ����̂��A���ƌo�c�̊�ڂɂȂ�B�����������ɁA���n�͓y�����̎�̊������v��N�Q����s�ׂ��ˁB���n�ʼnB�c��E�����Ă��܂��B �a�\�\�]�\�̗]�n���Ȃ��Ȃ邩��y�����̎�̗����͎�����A�Ƃ��������A���Y�͂�喼���ڍׂɔc�����邱�Ƃ�ʂ��Ď������D����Ƃ������Ƃ��ˁB�������A���n�͑��}���n�Ȍ�A�������͂Ȃ��B�ߐ���ʂ��āA�v���_�N�e�B���B�e�B�i���Y�́j�͉��{�ɂ��Ȃ������A�����ɂ͗̒n�����Ƃ������͈ȑO���̂܂܂̐����B���z�͕����ʂ�]�\�ɂȂ����B �b�\�\���̘b�Ō����A�]�ˎ���A�܌��ܖ��Ƃ������ďd�ł��Ƃ����Ă邪�A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ˁB�����̌��n�����������A�܌��ܖ��ł������A���ۂɂ͂܂���������ǂ܂肾�낤�B �a�\�\���܉�X�́A��������ŋ��ƕی������݂Ŏl�A�܊��͒�������Ă���ȁB���Ă݂�ƁA��X�͎l���Z���̌��d���ہB���ꂪ���̂����Z���ɂȂ邾�낤�B�ƂȂ�ƁA�Z���l���B �`�\�\���ꂶ�Ⴀ�A���㍑�Ƃ̐l���́A�̖̂��S�����������Ɖ՝��n�����Ă��܂����i�j�B �b�\�\�Q�[�ł��Ȃ���Ⴀ�A�̂̕��������Ƃ�����炵���B�Ƃ���ŁA�퍑�喼���܂�����������̂́A��ʏZ�����������邽�߂Ƃ��������A�y�����̎�������I�ɕ����������邽�߂������B���X�ɑ��钼�ڎx�z���m�����邽�߂ɁA�y�����̎�̊������𐧌����r�����ɂ�����킯���B �a�\�\���Ď����I���͂������y�����̎�́A�������т邽�߂ɁA�g�D����đ喼�̎x�z���ɓ���B�w�b�z�R�Ӂx�Ɂu�^�͂͂��Ƃ��Ƃ��튯�ɂȂ�v�Ƃ����A���ꂾ�ˁB �b�\�\����ǁA���ꂪ���܂��s�����n�������A���̌�����X���̐������ł����A���ˊ���ʂ��đ喼�x�z���ѓO�ł��Ȃ������n�������B���������n���ł́A�����ȗ��̉Ƌ��c���Ă���B�����̎Љ�g�D�������܂ő���������������B������A��T�ɂ͌����Ȃ����A���_�����ƌ��n���ѓO�����Ƃ����̂́A�����I�Ȃ��̂���ߐ��I�Ȃ��̂֎Љ�g�D���ω�����w�W���낤�ˁB |

�G�g����߁@����V��t����
*�y����֗߁z
*�y�b�z�R�Ӂz |

*�y���N���X�L�z
*�y���@���j���[�m���ȁz 


*�y�J�u�������ȁz |
�`�\�\���N�o���̍ہA���{�̖��O�́A����������Ƃ��đ傢�ɋ������Ă������A�喼�͌R���������B�Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă���B�������A���̃h�T�N�T�ɁA�喼�̗̍��x�z�͂��Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă���ˁB �a�\�\����́A���N���������Ȃ�ɒ[�Ȃ��̂��������炾�B��͂��o�����Ă��܂��ẮA�̍��x�z�͎蔖�ɂȂ��Ă��܂��B���̌��ɁA�ݍ��ł͂����Ȏv�f�����������ď���s���ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�N���푈������ցA�Ƃ����e�[�[���ѓO����Ȃ������̂́A���N�o�������m�����ł͂Ȃ��A�̍��Z�����ʂɓ���������̂��������炾�B���X�̎�҂�������������ˁB �b�\�\�A���́A�o�҂��̂��肾�����낤�i�j�B������ނ���A�푈�͕��m����������Ă����Ǝv���Ă��܂��̂́A���������ԈႢ���ˁB�������瑫�y�N���X�܂Ŋ܂߂����m�W�c�̑��ɁA����Ɠ������x���m�W�c�A�S���E���l����������Ă����̂����Ԃ��B���m����l������A����ȊO�ɐ�l�A�m�W�c�������B���̔m�W�c�������_���̏W�c���ˁB���N�N���ł��������m�W�c���A�S�����炻�ꂱ�����\���ƏW�߂�ꂽ�B�������A�ނ���ł����̂́A�ނ��험�i�̗U�f���ˁB �a�\�\���N�N���́A����܂ł̐퍑���̓���Ɠ����p�^�[���ŁA�E�C�Ɨ��D��O�ꂵ�Ă���Ă���B��ʂ̈�́A���l�E�������A�Ƃ������Ƃ�����A����������������A�����ŁA�������ƑD�ɐς�ő����Ă���B���܂萔���������āA�Ɛ����������đD�ŗA���ł��Ȃ��ƂȂ�ƁA�킢���@���������Ă���B���ꂪ���l�E�������Ƃ��������ˁB�������Ă܂��A�험�i�́A�������ł͂Ȃ��A�������l�Ԃ��험�i���B�����̏Z�����ʂɐ����߂�ɂ��āA���{�֑����Ă���ˁB �`�\�\����ƁA�������̒���@�ւ͂����₩�ȗ��j�I�������Ƃ����̂��ȁi�j�B����@�̏]�R�m�̓��L�i�c�O�E���N���X�L�j������܂��ˁA���R������́A���{�������Ă����l�������l���Q��ēz��s����`�����Ă����炵���B����ɁA�N���R�ɐl���������]���āA�ǂ�ǂ�����Ă����悤�ł��ȁB �b�\�\�l�Ԃ�험�i�Ƃ��ē��{�֑���B���̗��D�_�����A�����[�����ƂɁA��\���I�̘_���Ɠ����Ȃ��B�w��c���^�x�Ƃ��������̐��j�����邪�A�����ߗ��ɂȂ������{�l���m�̋��q������B���������ƁA���N�l����{�֘A�s���Ă��āA�J���҂Ƃ��ē�������B���{�̔_���͂���Ƒ���ĕ��Ƃ��Ē��N�ɑ����āA�u�㍑�v�܂薾�ւ̐N���R�Ɏd���Ă�B���Ȃ킿�A���{�l�͏o�����Ă��܂�����A�������Y�͐����߂�ɂ��Ă������N�l�ɂ�点�悤�A�Ƃ����킯���B �`�\�\���������Ӗ��ł́A�N���푈�̑g�D�_�́A�G�g�̎��ォ��ς��Ă��Ȃ������B�������A�G�g�͂ǂ����āA���N�o���A�喾���x�z�ȂǂƂ����A�r�����Ȃ����𗧂Ă��̂ł����ˁB �a�\�\�������́A�֑�ϑz�ł����ł��Ȃ��B���[���b�p�l�̃L���X�g���鋳�����́A�A�W�A�A���n���\�z�ƃV���N���i�C�Y�i�����j�������̂��ˁB�G�g���֑�ϑz�Ȃ�A���[���b�p�l�֑͌�ϑz�������Ɏ������Ă��܂����A�������i�j�B �b�\�\�C�G�Y�X��̓��C���h���@�t�A���b�T���h���E���@���j���[�m�̏��ȂȂnj���A���{�͐A���n���͖��������A�x�߂Ȃ�\���\��������A���̂Ƃ����{�l�̌R���͂��x�ߐ����ɗ��p�ł���Ƃ̕��ȁA���ꂪ�i�j�B �`�\�\�X�y�C���l�̓A�����J�嗤���o�āA�\�Z���I���ɂ͑����m�����f���ăt�B���s���ɓ��B���Ă܂����ȁB�������A�W�A�A���n�����Ƃ̋��_�ɂ��āA�ɓ��n��Ŗf�Ղƕz���̉����Ȋ������s���Ă����B �a�\�\�鋳�t�����́A�����Ɏx�ߐ����̌�������Ă���B�M���ɉ���Ă����t�����V�X�R�E�J�u�����i����Z�N��C�G�Y�X��̓��{�z�����j�ɂ��A�x�ߐ����ɂ͘Z�̃����b�g������ƌ����ˁB���������ƁA�b�͂܂������鍑��`�̘_�����B�J�u�����́A�`�m�i�x�ߐl�j�͉x�y�ɒ^�M�����a�ł���A�����琪���͗e�Ղł���ƌ����ˁB �b�\�\���̗���A�ꂢ�̃}�J�I�̈ꌏ���ˁB���{�l�\�O�l���}�J�I�ɓn���������A����l�̎x�ߌR�ɕ�͂��ꂽ���A�x�߂̑D��D���ĒE�o���������B���̍ۂɑ����̎x�ߐl���E���ꂽ���A���{�l�͐���l��ɂ��Ĉ�l�����l���łȂ������A���{�l�͐푈�ɋ������Ƃ����b�����A�������Ӓn��ł̓��{�l�̃C���[�W�͊C���A�悤����ɗ��D����\�͒c���ˁi�j�B �a�\�\�\�Z���I��ʂ��ăW���p�j�[�Y�E�p�C���[�c�͓��V�i�C���r�炵�܂����Ă����B�����ŁA�A���̓`�����嗤�֗��o���Ēm���Ă����肷�邱�Ƃ����肤��킯���B���������狭�����Ƃ������ƂŁA���p�ƌ����A�C��n���ė��P������{�l�i�j�B �b�\�\���R�Ƃ������A�C�����ˁB�A���̗��c�E���F�ڍ��ւ̈��F���Ȃ�Ă̂��ɐ��ɍ����������C���ŁA�F�쐅�R�ɑg�D���ꂽ��}���낤���B�\�܁`�Z���I�͐퍑����Ƃ������ƂŁA�����ɂ������j�̖ڂ������Ȃ����A���͕��m�͗��D�ƌ��Ղ̏�𓌃A�W�A���ݑS��ɓW�J���Ă���B�����C���^�[�i�V���i���ȃV�i�C�Ƃ�����ʐ��E�́A�퍑�Ƃ����h���X�e�B�b�N�ȃP�`�Șb����Ȃ��B�S�C�Ȃ�ĕ�����ŏ��A�}�J�I�̐��Y�n���璼�ڎd���ꂽ�̂��낤�B �`�\�\����ƁA�S�C�̓`������q���o�R�Ƃ����̂́H �a�\�\�ނ��A�|���g�K���l����q���ɂ���Ă��āA�Ƃ����͎̂������낤�B�������A���̃|���g�K���l�����͘`���̑D�ɏ���Ă���ė�����i�j�B �b�\�\��q���ȑO����A�`���̓|���g�K���l�ƕt�������Ă������A�ނ��S�C���m���Ă����B���{�l�͂���ȑO����V�i�C���݂𛄂��Ă����̂�����A�X�y�C���l��|���g�K���l�̐�y�������͂����ˁB�|���g�K���l���}�J�I�ɋ����̂𖾒��ɋ����ꂽ�̂́A�`����ǂ����������炾�B �a�\�\��q���̈ꌏ��ɂȂ邪�A�}�J�I�ɐ헪���_���J�݂����ƁA�V�i�C�͈̏�ς���B�ŏ��ɓS�C����ő�ʂɎg������ؑ��s�̎G��O�͐��R��w�i�ɂ��Ă���B���̘A���́A���Ŏg���O�ɊC�œS�C���g���Ă����B�G��O�ȊO�ɂ�����̏W�c���������낤�B�ނ�͕����W�c�ł���Ɠ����ɁA�n�C���ՏW�c�ł�����A���������퐶�Y�̃e�N�m�W�c�ł�����ˁB �b�\�\�C���^�[�i�V���i���Ȑ��R���o�b�N�ɂ��Ă����Ƃ����̂ł́A�����Ƒ��������̗Ⴊ����ˁB���Ƃ��A�Ëg�̕ρi1441�j�Őԏ����S�����R�`�����E���āA�d�B�֓�������Ő�������s�k���A�ԏ��������͉�ł���B���̂Ƃ��A�Ëg�̕ς̎�d�҂̈�l�A�ԏ����n�����ɂ́A�����̖؎R�邩��E�o�A�Ȃ�ƒ��N�֓������B����ŁA���N�̎g�߂�����ė��ăN���[���������A�ԏ����ɂ��ꍑ���̂��Ė��f���Ă���A���Ƃ�����ƁB�ό㔪�N���ĕ����N�ԁA�@���݂Đԏ����ɂ͋A�����ĖI�N���邪�A���ǔs�k���ĉ͓��̑��q�Ŏ��ʁB���ꂪ�j�����ǂ���������A�ԏ������~�S�ȗ����R��~���Ă����̂͊m�������A�\�ܐ��I���̍��ɂ́A���R�����N�Ő�̂܂ł��Ă����Ƃ͂Ȃ��ɂ������炸�B �a�\�\�����ˁA�\�ܐ��I���ɂ́A���łɂ���������Ԃ���B�C�ɂ͋��E�͂Ȃ��B �`�\�\�ƂȂ�ƁA�ʐ����j�ςƈ���āA�����̓��{�l�͐퍑����ŁA�����̐푈�ɂ��肩�܂��Ă����킯����Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ��A�X�y�C���l��|���g�K���l�����A�W�A�ɐZ�����Ă����悤�ɁA���{�l���嗤���ݕ��ɂ��Ȃ���绂��Ă����Ƃ������Ƃł��ȁB �a�\�\���������킯�ŁA�C�G�Y�X��̃J�u�����͍����ɁA���{�l���g���Ďx�߂𐪕�����Ƃ����Ă��o���Ă���B�E���ȕ��m�����͈�����V�Ŋ��X�Ƃ��ĕÉ��ɕ�d����ł��낤�ƂˁB�����Ԃ�i�����b�����i�j�A���{�ŕz������ړI�́A���{�l���L���X�g���k�ɂ��āA�x�ߐ������ƂɊ�^�����邱�Ƃɂ����A�Ƃ����킯���B���ƖړI�͖��m���i�j�B �b�\�\�����s���ȂǁA���N�֏o�w�����喼�ɐ؎x�O�����邪�A�܂��ɂ��̃o�e�����̖d���i�j�̃��f�����낤�ȁB���ہA�؎x�O���m�͏��Ȃ��Ȃ������B��̓����̗��̎��_�ł����A��B�̐؎x�O�������͂͂��Ȃ�̗͗ʁB���̋C�ɂȂ�A����ǂ��납���������āu�؎x�O�N���R�v��g�D�ł����������B �a�\�\�C�G�Y�X��̃J�u�����̓X�y�C�������Ɏx�ߐ��������Ă��邪�A�����ɁA�G�g�ɂ����Ă������낤�B���̒��N�N���̍����ɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ��B |
|
�`�\�\���{�l�L���X�g���k���g���ăV�i�𐪕�����A�C�G�Y�X��̃A�W�A�헪�͂������Ƃ��āA�G�g�̕��͂ǂ����������v��ł������ȁB �a�\�\�V�c�𖾂̍c��ɐ����āA�G�����֔��Ƃ���B ���N�����͉H�ďG���������͉F�쑽�G�ƂɎx�z������B�G�g���g�͖k���ɓ�������A�]��̔J�g�ɏ���\���A��������C�H�C���h�x�z��ڎw�����肾�����Ƃ��A�܂������鍑��`�I�Ȋ�悾�B����́A���{�l���哱����哌�����h���A���ȁi�j�B���Ƃ��ƈ���������������A���{�R������R�ƍ��o�������N�l�������炵������ˁB �b�\�\���̐N���v���W�F�N�g�́A�C���h�̐A���n���͕ʂɂ��āA�ŏI�I�ɂ͓��{�V�c�𖾂̍c��ɐ����āA�Ƃ����鍑���̂Ȃ�i�j�B�����嗤�́A�����Ɩk���ٖ����x�z���ˁB�����S���l�̌��͌����ɋy���A�����������Ėk���Ӌ����甭�����̂ŁA���ꂪ�������̉������Ƃ���̂́A������Ɖ������B�����h�̊��������A�������������������x�z����Ƃ����p�^�[���A������G�g���_�����̂��낤�B �`�\�\�鍑���̂̎��s�́A���{�R���k���R�n�����ł͂Ȃ��������Ƃ��i�j�B �a�\�\�G�g����}�������Ƃ��A�킸���l�\�N��A�����������ٔ��ٖ̈����i����j���������Ă��܂����ˁB���{�l�̐N���푈�̎��s�́A���N�����o�R�ő喾�����l�낤�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����ˁB���N�����͊C�ݕ������ɂ��āA�����N�U�����A���ځA�]�삠���肩������āA��C�Ɏ�s���U�����������A�헪�I�ɂ̓x�^�[��������������Ȃ��B �`�\�\������A�����āA��R�̑傫�����N��������A�Ƃ�����i�K�헪�ōs���Ă��܂��Ď��s�����B�]�삩��N�U�Ƃ����̂́A�`���Ɠ����ŕi���Ȃ��i�j�ƁA�݂��̂��ȁB �a�\�\�����������Ƃł�����܂����A���m�l�قǃ`�m�i�x�ߐl�j���i���Ă͂��Ȃ������B���w�̏\�����I�ƈ���āA�����܂����{�l�͓��l�h���Ă����̂�i�j�B�����됹�l�E�Ђ̖{���A�u��v�����A���E�̒��S�ȂB�����玖���`�I�ɍ\���đ�R��g�D���āA�܂����N������D���đ嗤�N���̋����Ƃɂ���Ƃ������Ƃ������ˁB �`�\�\�喾���ɍU�ߓ��邩��A����ʂ��A�W�Q������O����ɂ�����邼�A�Ƃ����̂��A���N�N���̘_���������B �b�\�\��͂����Ƃ��Ă݂�A�����̓��{�̌R���͂��炷��A����͖��d�Ȋ�ĂƂ݂͂��Ȃ������͂����ˁB������A�G�g�̓����A���[���b�p���܂߂��n����ŁA�R���I�ɍł����傾�����͓̂��{�������̂�����B����قǂ̌R���͂������Ă��Ă��������Ȃ������̂́A�������A��R���������������A���w�b�i�C�E�X���V���j�̊C�R�ɕ������Ƃ������Ƃ����A����͌��ʂł����āA�����͂�͂�⋋��⋂Ƃ������ȏ��ʂ�̖��i�j�B�N���푈�̌����͌��n�����Ȃ̂����A�\�����Ƃ����N���R���ێ����邽�߂ɂ́A��͂�{������̕⋋�V�X�e�����K�v���ˁB�G�g�̂��Ƃ����炻�̂�����͒N�����n�m���Ă����낤���A�⋋�V�X�e�������܂��@�\���Ȃ������B �a�\�\���\�̏���ŁA���X�ɐ��C���������āA���R�|�Δn�̐������m�ۂł��Ȃ��Ȃ����B��C���物�C���݂�`���Ėk�シ��⋋���Ȃ�āA�܂��ɊG�ɉ悢���݂������B���̘`��������{�̐��R�͒��q�̌Ղ������i�j�B �b�\�\������N�ł́A���{�l�͘`���̃C���[�W����������ˁA�`�z�͉��݂����r�炵�ē����܂ł͐N�U���Ă��Ȃ��͂��A�Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�푈���n�܂�ƁA���Ԃ͂܂������t�ŁA�`�z�͂����Ƃ����ԂɊ���╽��܂Ŋׂꂽ���A���̐��R�͎キ�āA�����ɕ⋋����ؒf�ł����B�@������ɕq�ȏG�g�͑��X�ɒ����l���Ă���ȁB �`�\�\���̌�́A���{�R�͌��n���B�ŗ��D�����肾�������A���̌R�����o�Ă���ƁA�琨�ɓ]���đ喾���N�U�ǂ��낶��Ȃ��Ȃ����B���ƌ��ɓ��������̂́A�����s���c�B �b�\�\���̑��̗��Ҍh�Ƃ����l�������Ȃ�ʔ������A������̌����͏����s�����ˁB����͐e������̏��l������ŁA�C���ɏڂ������A���N�N���̑O�q���Ƃ߂��B �a�\�\����ɁA�����܂ł��Ȃ����A�����s���͐؎x�O�喼���ˁB�s���͐푈�̓r���ŏG�g�ɁA���N���ł���������A���܂��ɂ���Ă��A�ƌ����Ă������B�����s�����N���푈�ɂ���قǔM�S�������̂́A���N�ɐ؎x�O�̉������݂������炾��B �b�\�\�����s���́A��N�����ł��l�낤�Ƃ����B����ŁA���\�O�N�ɁA��̍~���g�߂��d���Ăē����@���⌺�h�a�����k���֔h���������A����͍~���Ȃ���A�`�R�̒��N����̊��S�P���������������B���ꂶ�Ⴀ�A�s���̊�}�����j�Z���i�j�B |




|
 
*�y���c�钺�@�z
�s���Ɍ܌R�c�E�����E���R�s�{���s�@���E�k���������͂��Đ��g�ƂȂ��A�_�@�O�c�V�����R�E���Ҍh�g�ƂȂ��Đ߂������A�t�������炵�A�G�g���ē��{�����ƂȂ��B���ӂɋ�������Ă��A���ӂ�Ɋ��������Ă��B���b�ȉ��܂����ꂼ��ʂ�Ċ��E�������p�ĉ��͂𔖂��B��ďق��ē��̍��l�ɍ����Ȃ�B���̍��߂�Ĉ�z������炵�߂�B���X���̓y�ɋ���Đ��X���̖��ׂ�B�������䂪���c���c��A������̍��Ɏ��ӁB���ɖ���čĂѕ����B�D���̐��T�ƈ��ӂׂ��B�����Ă��Ȍ�A������O��A�i����S�����ЁA���������ēV���ɕA�M�`�������ď����Ɩr���݁A���߂̈ΏO�͖��߂ċ�戢�����ցA�������C�ɐ�����Ȃ��炵�߂�B�Z�\�Z���̖��A�v�������������ƂƂ��A�{�Ƃ𗣊����B�܂��ɉ��ӂ��ĕ��V���A���̕���Ȏq�����đ����ڂ�����ނׂ��B����A���̋��Œ����ӂ�̂��A��A�V�S�ɓ��ӂ鏊�Ȃ̂��̂Ȃ�t *�y�G�g��ӕ\���z �s�����\�l�N�㌎���ܓ��A���{�����b�L�b�G�g�A���������A�m��m��B���C�̏��b�A���ɒ��̐��T�ɋ��ӁB�N���E����E��y�E�ߊ��A�݂ȉ�����恲���B�b��ꏅ�����A���Ղ̎���Ȃ�B������тĕK����������ցA��d�ɐ\�ӂ��A�c��ŒO�y��s������B�肭�͋��@�����Ƃ��B�V�g��ɉ��B�ނ�ŕ\�����ĕ����t  ���d���i1879�`1910�j�@�؍��؎�  �ɓ������i1841�`1909�j�@���{���� |
�`�\�\�������A���N�o�����A�G�g�̖��d�A���㖝���邢�͋��C�Ƃ݂�̂́A���j�Ƃ̏�ŁA���ꂪ���j�w�̌��E�ł��傤�ȁB �a�\�\���N�o���\�z�͐M���̍����炠�����B�鋳�t�⏤�l�̘b�ɂ̂��Ă����̂���B���N�N���ɂ��Ă��A�鋳�t��A��čs���Ă���ˁB�����͐鋳�t��O�����l������Ă��������ł͂Ȃ��A���{�l�C�����l�̎��n�̏펯�Ƃ��āA���A�W�A�̐�������A���Ȃ�ڂ����m���Ă����B �`�\�\�������A�n���͊ۂ��Ƃ������Ƃ�m���Ă����B�R�y���j�N�X�I�]��͒ʉ߂��Ă����i�j�B �b�\�\�����������E�j�I�ȈӖ����A���{�j�̐��Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��悤���ȁB �a�\�\�����̓��A�W�A�̏���炷��A���邢�͓��{�̕��͂��炷��A�鍑���̂́A�R���㖳�d�Ȑ헪�Ƃ͉]���Ȃ��B�R���I�ɂ͎����Ȑ푈���B�������s�͌����ɋy���A�����k�[�܂ň�C�ɐN�����Ă���B�Ƃ��낪�A��x�N�����āA�Ƃ��ɓP�ނ����B �b�\�\����́A�ǂ����Ă������̂��B��́A�⋋�V�X�e�������܂��@�\���Ȃ��������Ƃ����A����́A�����������ߏd���S�Ŗ{�����敾�����Ƃ����A���j�w�̏펯�͉R���ˁB���ݎc���Ă��镶���́A�������ߏd���S���Ƃ����i�����������ˁA�����^�Ɏ����j�Ƃǂ����A�������ߏd���S�ŐN�������܂����Ƃ����X�g�[���[���ł����������B�ނ���A�C��⋋�V�X�e���͑��X�ɍ��܂��Ă��邩��A�����悤�ɂ�����Ȃ����A�܂�����ŁA�������ߏd���S���A�s�\���Ƃ����i���́A��������s���̏؋��Ȃ�B�����������T�{�^�[�W���ɑ����Đ������Ȃ������Ɖ]���������悢�B �`�\�\�܂�A�G�g�̓V���͂܂������W���I�i�K�łȂ��A���喼������Ꝅ�I�`�Ԃ������B�������A�܂��̍��o�c����܂�Ȃ����喼�ɂ́A�\���Ȓ����\�͂��������Ƃ͎v���Ȃ��B�喼���������������悤�ɂ��A�x�z���ѓO���Ă��Ȃ��ȏ�A�����l���������Ȃ��B�����������Ƃł��ȁB �b�\�\���������G�ŁA���j�����̓���B���N�o���́A���̓����ƒ�����ʂ��������W���̐��\�z��_���������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B������A���喼�́A�\�͈ȏ�̓����ƒ����Ƃ�������������ꂽ�B����͒����W�����̃e�X�g���ˁB�����ȓ��Ƃ������G���B �a�\�\���̐N���푈�́A�����W���̐��̏\���ȍ\�z���O���A�����ɁA�����W���̐��\�z��_�������̂Ƃ����A���̂�����̓���q�ɂȂ����\���́A������ƔF�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����W���̐��\�z���G�g�̎v�f�����A��x�̏o���ŁA����͐��������Ɖ]���邾�낤�ˁB���������Ӗ��ł́A���̎��s�͐����������i�j�B �`�\�\������A�鍑���̂Ƃ����s��ȃv���W�F�N�g�́A�ǂ��܂Ŗ{�C���킩��Ȃ��B������G�g�̕s�𗝂ȗ~�]���邢�̓��K���}�j�A�b�N�ȋ��C�Ƃ݂���j�Ƃ́A���́A�ǂ��܂Ŗ{�C���킩��Ȃ��A�Ƃ��������疌���킩��Ȃ��i�j�B �b�\�\�o�w�������喼�����āA�G�g���ǂ��܂Ŗ{�C���킩��Ȃ��B���ꂪ�A�v����ɁA�G�g�̒����W���̐��\�z�v���W�F�N�g�������Ƃ���ˁA���N�Ŕs�k�����̂́A�G�g�ł͂Ȃ��A���喼�����B�G�g�́A�ƍN�̂悤�ɐ��Α叫�R�ł͂Ȃ��A�֔��Ƃ����|�W�V��������������A����͂��Ƃ��ƁA�V�c������ɂ��������W���̐����u�����Ă̂��Ƃ��B �a�\�\�Ȃ�قǁB����ƁA���N�N���́A���D�푈�Ƃ����ÓT�I�ȑ��ʂ��₵�Ă����ˁB���Ɛl���v�����ܗ��D���Ă���B����́A���喼�̌R���ɗ��D�̌������������Ƃ������Ƃ��ˁB�험�i�l���́A�N���̕�V�����ł͂Ȃ��A���̖ړI���̂��̂������͂����B �b�\�\���낤�ˁB�����A���N�N���̐�㓝����{�C�ōl���Ă����Ƃ���A����قǂ܂ł̔j��Ɨ��D�͂��܂��B������A�R�X�g�ƃC���J���̎��x�o�����X���炷��A�N���E���D�E�P�ނƂ����ÓT�I�p�^�[������������悢�A�Ƃ����b�ɂȂ�B������A�Z���N���s���ŁA������ڎw�������헪�ł͂Ȃ������B����ɁA���喼���A�����@�����o�Ȃ��قǂ܂ō������A���g���ł�������˂��B �a�\�\����͏G�g�̑Ë��Ԃ�����Ă��킩��B�ŏ��́A���N�𐧈����đ喾�����e�v���W�F�N�g���������A���ɔ����씼�������ł悢�Ƃ������ƂɂȂ�A�Ō�́A���c�邩��̍����Ɩf�Ղ̋��̓�_�����B �`�\�\�悤����ɁA���{�����ɕ����Ă��炤���ƂƁA�����f�ՂőΖ��f�ՓƐ��]�ނ����B �b�\�\�Ƃ��낪�A���͍����͂��Ă���Ă��悢���A���O��݂����Ȗ\�͓I��ؐl�ɂ͊����f�Ղ͋����Ȃ��Ƃ����Ԏ��B���\�ܔN�i1596�j���̎g�߂�����܂ŗ������A����͒��u�a�g�߂Ƃ��������A�����g�Ȃ�B�����E�G�g�͂��߁A�ƍN�ȉ��̏��喼�����̊��ʂ����^����A�����̈ߊ��𒅂��āA�k���̕��p�Ɍ������Čܔq�O�@������A�Ƃ������C�x���g�������B���ꂪ�A���j�Ƃ̂����Ƃ���́u�u�a�v�̓����i�j�B �a�\�\�G�g�͖��g�̖���ɓ{���Ēǂ��Ԃ����Ƃ������A��������Ȃ��B�̐S�̖f�Ջ����Ȃ��������炾�B���ꂶ��A�G�g�ɂ͉��̃����b�g���Ȃ��i�j�B����ŁA�ēx�o�����Ē��N�암���m�ۂ��āA���Ƃ̌���L���ɂ��悤�Ƃ������A�����̕�����Ɏ���ł��܂����B �b�\�\�܂��A�G�g�̑Ë��Ə����Ԃ���݂�A���ǂ́A���̐N���푈�̓��@�́A���ɞB���ȂB����ƍN��O�c���ƂƂ������L�͑喼�����̐푈����r�������̂́A�ނ炩�����̃`�����X��D�����߂����A�푈�̗�����Ɛ肷�邽�߂��ˁB�푈��ʂ��Č��͂��m�������A���ꂾ���͏I�n��т��Ă���B �`�\�\����ƁA�����W���̐��\�z�v���W�F�N�g�������Ƃ������Ƃ����邩��A���N�N���́A�G�g�ɂƂ��āA�����ĕs�𗝂ȃT�C�R�e�B�b�N�ȍs���ł͂Ȃ��A�����I�ȍs�����Ƃ������ƂɂȂ�܂���ȁB�����̏Z���ɂƂ��Ă͖��f���ɂȗ��j�I�Г����ǁB �b�\�\�܂������A�n�^���f�Ȃ��Ƃ��i�j�B�`�z�������N���������N�����̂��̃g���E�}�e�B�b�N�ȍЖ�́A��\���I�ɂ��������ꂽ�ˁB �`�\�\���B�̃n���s���w�ňɓ��������ÎE����܂����ȁB����͒�R�����̈�[�����A�����̓��{�l���炷��A�e���s�ׂ��ˁB����ȋ�ɁA���܃C���N�l�̒�R�������u�����e���v���Ə������{�̃}�X�R�~�\��������ƁA���j���牽���w���A���Ȃ����Ă��Ȃ��ˁB���Ȃ��Ƃ����[���b�p�̃}�X���f�B�A�́A��������W�X�^���X�Ə����Ă���B �a�\�\���鍑��`��R�����́A�鍑��`�̑����炷��A�����e�����X�g�W�c�̔ƍ߂Ƒ��ꂪ���܂��Ă���i�j�B�C���N�ɏo�����Ă���؍����{�́A�`�m�E���d���k�A���W�����O���l�̂��Ƃ�z�N���ׂ����B���N�̊O�����D���ی썑�ɂ��āA�ی쌠���s�g���邽�߂Ɋ���i�\�E���j�ɓ��ĕ{�������āA���̏��㓝�Ă��ɓ������B�����t�c���肪���Z��N�����A�ɓ������ˎE�����̏\�����ˁB���V�A���������d�����S�����āA���{���Ɉ����n�����B���N����Z�N�A���d���Ɏ��Y�����A�����i���������j�Ŏ��Y���s�A�����āA�������N�����Ƃ������悾�����B���I�푈���_�@�ɓ��{�͂���Œ��N���蒆�ɂ����B �`�\�\���d���͎O�\�����肾�������A�ɓ����E���āA���Y���ꂽ�B����ȑO�A�ނ͍b�ߔ_���푈�i1894�N�j�ł͐��{���A�_�������R�̒����ɂ�����`���Ƃ��Đ���Ă���B���̌�J�g���b�N�̐�����Ă��܂��ȁB����ɏo�����ƈ����[����̂��߂Ɋw�Z��ݗ�������A��R�^���ɎQ������ˁB�����������s�����߂̋`����g�D���āA�������烍�V�A�̃E���W�I�X�g�b�N�֓n�����肵�āA�����ɓ����Ă����B �a�\�\���d���͈ɓ���_�����Đ����������A����ŁA�ɓ����E���āA���R�����́u���߂��v�Ɗ�Ƃ����b������B����ŁA�O��e�����ł���ƂˁB �b�\�\����̓e�����ƍ߂Ƃ����}���ŁA��R�^����e���ł��邩��ˁB���N�������ꉞ�A���N�����ʁA�������Ƃ����@�I�Ȍ`���葱�����̂��������A���ۂɂ́A�����Ƃ������̎匠���D�A�A���n���́A���{�̈��|�I�ȌR���͂�w�i�ɂ������̂������B���̖\�͓I�A���n�x�z�ɑ��A���N�l�ɂ̓e���ƌĂ���R���������Ȃ������B����ŁA�ɓ��ÎE�����A�x�z���鑤�́u���߂��v�Ɗ�B����ŁA�O��e�����ł���ƁB�e���̘_���́A���W�X�^���X��ƍߍs�ׂƒ�`������̂��B |
|
�\�\�G�g�̒��N�N���푈�́A�G�g�{�l�̎��ɂ���ďI������킯�ł����A����ɂ���āA���{�l�͐M���ȗ��̑嗤������������Ƃ�����]���̂Ă��ƁB �b�\�\���Ȃ��Ƃ��Ȍ�O���I�قǂ͂ˁi�j�B�G�u������ŁA���͍R�����n�܂�B�C�O�N���ǂ���ł͂Ȃ��B�������A�푈�ł͂Ȃ��A�C�O�f�Ղ̗��v�Ƃ������܂��b�͑����B���喼�͋����ă��[���b�p�����Ƃ̃`�����l�����m�ۂ��悤�Ƃ����B �`�\�\�ɒB���@�́u���k���v�Ƃ��āA�g�߂����[���b�p�ɔh�����Ă���ˁB�������c�������g���B���ꂪ�A�c���\���N�i1613�j�̏o���A�����炻�̂���́A�܂�����ɖL�b�G���������B���ƍ]�˂̓�d���͏�Ԃł��ȁB �a�\�\�ƍN�͂���ȑO�ɁA�t�����`�F�X�R��̐_����ʂ��āA�X�y�C�������Ăɐe���𑗂��Ă����ȁB�������A�ɒB���@���ƍN�̗��������t���āA�g�߂�h�������B���{�̑D��s�E���䏫�Ĉ�s�����̎g�߂ɓ��s�����B�����A�����͂܂����쐭���́A�փ����̎肪����������A�O�l�喼�͓Ɨ��������͂ŁA���Ȃ莩�R�ɍs�����Ă����B �b�\�\�ɒB���@�̓T���E�t�@���E�o�E�e�B�X�^���Ƃ����ܕS�g���̑�D�������������B�{���̑�m�n�q�D���ˁB���̑D�������m��n���āA���ł������L�V�R�܂ōs�����B��������͍̂]�˂̑D��H���Ƃ����B���{�l�̑D��H�́A���łɋߐ������ɁA�����m�����f�ł���D�����Ă��܂��Ă������̂��ˁB���̑D�͌��ǁA�����m������邱�ƂɂȂ�B���̌�A������X�y�C������������āA�I�����_��̌R�͂Ɏg���B �`�\�\����́A���܂�m���Ă��Ȃ����A�d�v�Ȏ����ł���ȁB���Ԃł͑����m�����f�Ƃ����ƁA�����̙��Պۂ������ɂȂ�����ˁB�������A���Ȃ��Ƃ��ߐ������̓��{�l�̋Z�p�����́A�����Ȃ��̂ŁA�����m�����f�ł���D�C�ő��ꂽ�B �b�\�\���������A���������Ɋ�q�g�ߒc�����F�l�c�B�A�ŁA���̋ߐ������̎g�߂̋L�^���������A���̈Ӗ����킩��Ȃ������Ƃ����ˁB�c���N�ԂɃ��[���b�p�ɓ��{�l�g�߂����B���Ă������Ƃ́A�z�������Ȃ����Ƃ������B���肦�Ȃ��Ǝv�������낤�B �a�\�\�D�����T���E�t�@���E�o�E�e�B�X�^�iSant Juan Bautista�j�Ƃ����̂́A�����n�l�A�������u����̃��n�l�v�̕����ˁB�����Ƃ��A����̓V�哰�����̖��Ղ��Ă���B �`�\�\�����D�̎ʐ^���݂�ƁA�D�̃}�[�N����j�䂾�B �b�\�\�ɒB���{���̉Ɩ�́A�O������B���������ɂ��A�e��A�˖�A�ᔖ��ƁA�����ȉƖ���g���Ă���B���̌����g�߂̂����̐e���ł́A���@�̃t�H�[�}���Ȗ��̂�͏��������炾�B �`�\�\�������A��j��Ƃ����͍̂א�Ƃ̉Ɩ�ł��傤���B �b�\�\�������ʔ����Ƃ��낾�ˁB���@�͂����ȉƖ���g�����悤�����A�א삩�����B���Ă���i�j�B���̍א�ɏ��]���ē�����j������̑D�Ɏg�����B �`�\�\�����ʂ�A�u�悻�s���v�̖�i�j�A�����O���������炷��ƁA���̑D�͂܂�ōא�O�ւ��d���Ă��D�݂����Ɍ�����B �b�\�\�܂��A�ǂ����Đ��@�����̋�j����g�����̂��A�������Ă݂�Ɩʔ������낤���B �a�\�\�ŁA�u���k���v����������E�ɒB���@�̎g�ߒc�́A�c�����x�q�Z�E�q��풷�A���{�l�͑S���e�n�̏��l���܂߂đ����S���\���B�ނ�͂��̑D�ő����m�����f���āA�O������m���@�G�X�p�j�A�i���E���L�V�R�j�֓��B����B�����͒��p�n���ȁB��������A����ɑ吼�m�����f���āA�X�y�C���֓��B����B��Z��l�N�\���̂��Ƃ��B���{���o�Ă����N�ゾ�B �b�\�\���̂Ƃ��g�ߒc��s���}�����̂��A�V�I�h�A���B���̐l���́A�X�y�C�����G�͑��̒�A��ܔ����N�A�C��ŃC�M���X�ɔs�k�������̒�Ƃ����̂ŁA���j�ɖ����c�����l�����ˁB�ނ����̒��������{�l�g�ߒc���A���[���b�p�ōŏ��ɏo�}�����B �`�\�\����͖ʔ��������ł��ȁB�X�y�C�����G�͑��͂��������Ă����i�j�B �a�\�\����ŁA��s�̓Z�r���A�֓���B�����͈ē����A���C�X��\�e���_���̌̋��ŁA�X�y�C���l�̊C�O�Y��̍����n�������B���ꂩ��A�R���h�o�A�g���h���o�R���āA��s�}�h���b�h�֓���B�����œ������E�̑唼�����L����Ƃ��ꂽ�X�y�C�����ɉ�B�����Ĕ��P�������ɑ؍݂��邪�A���̊ԁA�x�q�́A�X�y�C������ÂŐ���Ȑ��玮������Ă��炤�B�x�q�Z�E�q��̐��疼�́A�u�t�F���y�E�t�����V�X�R�E�t�@�Z�N���v�B�t�����V�X�R�͐��l�t�����`�F�X�R�̖������A�t�F���y�͂��̃X�y�C�����E�t�F���y�̖��Ղ����B����͑�ςȊ��}�U�肾�˂��B �b�\�\�������A�v���̂����A�����C�G�Y�X��ƃt�����`�F�X�R��̑Η����������ˁB�C�G�Y�X��́A���Ȃ�ȑO������{�H������ŁA�z�����Ă������A�V�����N�����g�߂̐�������B�ʔ������ƂɁA�C�G�Y�X��͎x�q�g�ߒc���A���[�}�܂ōs���̂�j�~���悤�Ƃ���ˁB�ɓ����牓�H���������g�߂ɑ��A�Z�N�g�Ԃ̑Η��Ƃ͉����P�`�Șb�����A�L�^�ɂ��Ύ��ۂ����������Ƃ炵���B �a�\�\�ŁA���ǁA�X�y�C��������p�S���Ă���āA�}�h���b�h�𗧂��āA�o���Z���i�A�T���g���y�A�W�F�m���@���o�R���āA���[�}�֓���B�L���X�g���̑�{�R�A�T���s�G�g���吹���̑O�̍L��ŁA����I�ڂ̃p���[�h�������B���[�}�@���p�E���ܐ��q�y����Z��ܔN�\�ꌎ�A�x�q�͈ɒB���@�̏��Ȃ���n���A�������{��ŏq�ׂ��B���͂��̔N�́A���Ă̐w�A�܌��ɖL�b�����ŖS���Ă����ˁB �`�\�\���̕������ʔ����ȁB���̐w�̔N�ɁA���[�}�Ŗ@���ɉ���Ă������{�l�������Ƃ����̂́B �b�\�\���̃T���s�G�g�����@�́A�W�����E�������c�H�E�x���j�[�j�v�̗��L�͂܂��o�����Ă��Ȃ����A�~�P�����W�F���v�̐����̃N�[�|���͂��łɂ������B�x�q�̓��[�}�Łu�h���E�t�B���b�|�E�t�����V�X�R�v�ƌĂ��B���{����̎g�ߒc�̑�g���ˁB���[�}�̃{���Q�[�[�{�ɂ́A�N���[�h�E�h���G��Ƃ����x�q�풷�̗��h�ȏё��悪�c���Ă���ˁB����ɁA�L���i�[���{�ɂ��A���̓��{�l�g�ߒc�̊G���lj�ɕ`����Ă���B���[�}�؍ݎ��̂��̂��낤�ˁB �a�\�\�g�ߒc�͗��N�i��Z��Z�N�j�ꌎ�܂Ń��[�}�ɂ����B�A�H�ɂ����A�@���͈ɒB���@�ւ̒����͂��ߋL�O�̑��^���ƋA�r������^�����B�}�h���[�h�Œ����؍݂������ƁA���[���b�p�𗣂��͈̂�Z�ꎵ�N�����B�d�v�Ȃ��Ƃ́A�O�N�̈���Z�N�A�ƍN�����ɁA�����ē��N�����A�X�y�C�����̏��Ȃ������ĉY��ɗ��q�����A���g�T���^�E�J�e���[�i���ǂ��Ԃ��ꂽ���Ƃ��B �`�\�\����͏G�����͂�����ƁA�X�y�C���ł͂Ȃ��A�C�M���X�E�I�����_�̐V�������̂��Ă����Ƃ������Ƃł��ȁB����ƁA�����G�����A�����J�g���b�N�r���̑I���������Ƃ������Ƃ��B �b�\�\�����������ƂɂȂ�ˁB�ƍN�̐e���̕Ԏ����������X�y�C�����̎g�߂���������̂��x�������ˁB���ꂪ�����Ⴄ�ƁA�����̗��͋N���Ȃ�������������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A���j�͋��R���̐D��������A�킸�����ꗂ���ɑ傫�ȑ���ƂȂ��Č��ʂ���B �a�\�\���ǁA�ɒB���@�̌����g�߂́A�吼�m�����f���ăm���@�G�X�p�j�A�ɒB���A�������瑾���m���̍`���A�J�v���R�ŁA�}���ɗ��Ă����T���E�t�@���E�o�E�e�B�X�^���ɏ�D���āA�����m��n��B��Z�ꔪ�N�Z���A�����������̂́A���{�ł͂Ȃ��t�B���s���̃}�j���ȂB�ǂ����Ă��B����́A���łɓ�N�O�ɃX�y�C�����̓��g�̑D���ǂ��Ԃ���Ă������炾�B �b�\�\�X�y�C���̗���͈����Ȃ��Ă����B�����ŁA�܂��\�e���́A�f�B�G�S�E�_�E�T���t�����V�X�R�Ƃ����鋳�t�𖧍q����������B�f�B�G�S�͑O�N����������Ă����t�����V�X�R�E�f�E�K�����F�X�Ǝ���悭��āA���@���̃\�e�����Ȃ��̑�������B�������ăK�����F�X�͐��֍s���āA����Ő��@�ɉ���āA�������n�����B�����A�x�q�͈�Z��Z�N�܂Ń}�j���ɂ���ˁB �a�\�\�}�j���ɂ͓������{�l������l�͂����ˁB��Z���N�ɂ̓}�j�����߂����āA�X�y�C���ƃI�����_�̊ԂŐ푈���������B�����ŃX�y�C����������B�ɒB���@�������������T���E�t�@���E�o�E�e�B�X�^���͂��̂Ƃ��}�j���ɂ��邪�A���Ԃ�X�y�C���R�ɒ�������āA�������ĊC��Œ��炵���B���̌�A�C�̓I�����_�D�������Ă��邩��A�����e�Ղ����{�ւ͋A��Ȃ��B�����Œ���o�R�Ő��A�ꂽ�̂́A���a�Z�N�i1620�j�Ƃ����킯���B �`�\�\����ƁA�܂�܂鎵�N������́A�܂��A�����ւ�ȗ��s�������킯���B���ɋA������A��N�قǂŎx�q�Z�E�q��͎��ɂ܂��ȁB���̔N���A��̒����}���A�鋳�t���\�O�l���ΌY����q�����܂ސM�k��\��l���a��B�c�����N�i1597�j������ꏊ�ŁA�G�g�̖��߂œ�\�Z�l�����Y�ɏ�����ꂽ�B���얋�{���؎x�O�֗߂�z�������A�ɒB���@�͗D�_�s�f�ɂ���������B�����A�l�����������悤�ł��ȁB �a�\�\���{�̓I�����_�ƃC�M���X�̐V�������x������悤�ɂȂ����ɑ��āA�X�y�C���E�|���g�K���n�̐鋳�t�Ɛ؎x�O�͓O��I�ɒe������悤�ɂȂ����B������A���̓_�ł́A�]���̐؎x�O�e���̌����͕ύX��v����B�܂�A�؎x�O�e���Ƃ́A�����L���X�g���k�̐V�����v���e�X�^���g�h�̋����ɂ���āA���{���������J�g���b�N�h��e�������Ƃ����\�}���ȁB�ɒB���@���؎x�O���Y�𖽂��Ă��邪�A���g�͋������Ƃ����I�v�V�����������Ă����B �b�\�\�u���k���v�Ƃ��ăX�y�C�����ցA�ʏ��̐\�����o�����Ƃ��A�t�����`�F�X�R��鋳�t�̐G�ꍞ�݂́A���@�͎������R���Ƃ������Ƃ��ˁB���@�́A���w�ȑO�A�܂��ƍN�v��̎���������_���Ă������낤���A�܂������_���闧��ɂ������B�͂Ȃ������I�������Ƃ������Ƃ��ˁB �a�\�\�o�`�J���̋L�^�ł́A��Z��Z�N�̒i�K�ŁA��\�l�̐؎x�O�����{�ɂ����Ƃ�������������B���@�̓X�y�C�����Ƃ̌��b��ʂ��Ēʏ������l�����A���̖f�Ղ̕x�������āA���k�ɌN�Ղ���B����������}�́A�ƍN���܂��e�F����Ƃ��낾�����B �b�\�\�ƍN�̑ΊO����́A�C�M���X�E�I�����_�Ƃ����V���������ł͂Ȃ��A�������Ƃ̃`�����l�����c���Ă����A������ɒB���@�ɂ�点���Ƃ����Ƃ��낾�ˁB |

�ɒB���@�� 
�����T���E�t�@���E�o�E�e�B�X�^�� �{�錧�Ί��s�n�g 500���̖{�i�I�ȑ�m�n�q�D �D�̃}�[�N����j�� 
�A�}�e�B�Ғ��w�ɒB���@���g�^�x �C�^���A��ł�1615�N���[�}�ŏo�� 
�T���s�G�g���吹�� 
�p�E��5���� 
�~�P�����W�F���u�s�G�^�v1499�N 
�x�q�풷���@�{���Q�[�[�{�� 
�x�q�풷���@���s�����ّ� 
�����}���} |

��؛���
*�y��z
�s���x���X�Ƃ��ċy�ď��A�ᚠ�Ƃ����]�~��������w�\�l�j��v����b�A�֔V��B���肵����̏@�|�A�n�O�X�@�䑶�m�A�ʏ@�j�됬�s�����j�������B嫑R�n�V���l�����x��@�x��t�A�x�X���f�d��B�A���㐶�V�厖��ّ����҃n�A�˕s�Տ@�|�F�X�������f�~�A���l�ԔV��@�A�����p�J���ɊQ���A�I�j�қ��V���ӎE��L�B���O�u�������̂��A�ɐF�g����ӌ�́A��g�ܐ��x笌�Ӊ��@���B�R�|�j���x��s�v�c�V�V����v�A�y�l�@���R����B���Ƃ��Ě��ƔV�]���V�A���V�~�V�������B�@�O�X�닏��A�E�V��@�x�j�s���ցA��X�l�X�V������������A���I��V�F�g�j�e��փo��Ĕw���ʔV�V��A�ɍ���㘔V�I���A���x�V�厖��~��|�A�ߒQ�g�j�P���̔@���V�d����B�ֈȔ�טH��B�R�ΊC��j���t���Ҍ�B���ȏ����V�V�����|�A���y�}�f���ÌA�钆�V���X�̃j���{�V�O���s�R��B���������V�捹���s�y�����B�����V���w���a�◗��t�i�ꌎ�\�O���j 
�L�n��U�}�@����
*�y�N�[�P�o�b�P���̓��L�z
�s��\�l���i�ꌎ�\����j���B���쐼�̏����A���Ȃ苭���B���H�̍��������A�ߌ�A�L�n�̂̔����R�̗v�ǂ���l���̈�}�C���̏��ŁA��Ƌt���̂��ߐ��[���q�̂悢���n�ɒ┑�����B�i�����j����a�͌������A�u���͂���ɂ��ẴI�����_�l�̗v�������]�˂Ō��B�v���B�{��A������A����ɂ��āA�ō��̊t�V�Ƙb���A�I�����_�l�̗��v�ƂȂ�l�A�w�͂��悤�B�܂��v���Ƌ��Ɂw�}�j����S�ł����邽�߁A���ǂ̑D���c��̗p�ɋ��������x�Ɛ\���o���͔̂��ɂ悢���Ƃł���B�����A���炭�̊Ԃ��ꂪ�s���Ȃ��Ă��A�M���ɂƂ��Ĕ��ȗ��v�ƂȂ낤�v�A�ނ͂܂��������A�u�}�j���̓I�����_�l�̕��͂ŏ\����̂ł���̂ł͂Ȃ����v�B�ʎ��͓������A�u��������s���A���̐�̂��m���ɂ��邽�߂ɂ́A���{�l�́A���Ȃ�傫�Ȑ����̕��͂��K�v�ł���v�B����a�͐q�˂��A�u���{���K�v�Ƃ�����̏��i����Ђ������炵�A���{�ɕ�d���邱�Ƃ��o���邩�ǂ����v�B�ʎ��͓������A�u�|���g�K���l�����Ȃ��Ȃ�A���S�ɍs������ł���B���{���v�����邾���̃V�i���i�������ė��邱�Ƃ͕ۏ���B�����ăV�i���ς�Ղ����߂ɁA�I�����_�l�̓V�i�l�Ǝ����N������͂Ȃ��v�t�i���˃I�����_���ق̓��L�E���ϗm�q��j 
�V�������Ꝅ�W�n�} 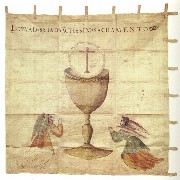
�V���Ꝅ�w���� �}���͐��t��}�B�㕔������ ����Łu���Ƃ�������ւ͎]������v 
���̏\���ˁ@���隬���@���� |
�`�\�\�ŁA���i�N�Ԃ��V�������̗��̘b�ɔ�Ԃ��A�ƍN�̎���́A�悤����ɁA�؎x�O�e���͏��喼�ɂƂ��Ă̓��G�������Ƃ������Ƃł��ȁB �b�\�\�X�y�C���E�|���g�K���Ƃ����������Ƃ̒ʏ����Ղ����喼�͑_���Ă������A�鋳�t�Ǖ���؎x�O�e���Ƃ������G�܂��邱�Ƃɂ���āA���ڌ��Ղ̋@���D�����ˁB���̈���ŁA���{�̓I�����_�E�C�M���X�Ƃ����V�����ƌ������āA�C�O���Ղ�Ɛ肵���Ƃ����i�D���ˁB���̂Ƃ��A�����̗��́A�����{�A�Ƃ��ɋ�B�̏��喼�����邱�ƂŁA����I�ɐ؎x�O���������Ɛ≏�������Ƃ����킯���B �a�\�\�����������Ƃ��ˁB���ہA�V�������̐؎x�O�Ꝅ�́A�ߐ��ł͑��ɗ�̂Ȃ���K�͂Ȕ����������B�������A����œ��{�͐؎x�O�֗߂ƍ����ցA�Ƃ����̂����ȏ��I�ȗ��j���ꂾ���A�����́A������Ƒ҂āA�ƌ��������B����ȕ��ɗv�Ă��܂��Ă͂����Ȃ��B �`�\�\�V�������̗��ł́A�L���X�g���Ƃ����ً��ɑ���킢�������A�ً��@��ɑ�����{�̕����h�q�������A�Ƃ������A���̓_�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��B �b�\�\�悤����ɁA����́A���[���b�p�̑����猩��ƁA�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�A�L���X�g���̋����E�V���̍R���́A�㗝�푈�������B���ꂪ�؋��ɁA�I�����_�͑D���A��������đ�C���Ԃ�����ł���i�j�B �`�\�\�������˂ɂ������I�����_���قْ̊��j�R���X�E�N�[�P�o�b�P���ɁA���{���o�w�v�������āA�I�����_�D����C�����ďo���A���i�\�ܔN�̈ꌎ���{���甼���A�C�ォ��S��\�����A�ΉΖ�䂩���S��\�����A�C�������Ƃ����A����ȋ�̓I�ȖC���̋L�^�܂ł���i�j�B �a�\�\�؎x�O�Ꝅ�O����̖������ˁB����́A��X���ď�̖ړI�́A���Ƃ�ӒD�����荑��ɔw��������A�������������I�s���ł͂Ȃ��A�؎x�O�̏@�|�ɗ����Ԃ��ĐM����邽�߂ł���B������ɁA�C��ɓ��D�������邪�A����́u���{�V�O���v�ɂ������̂ł͂Ȃ����ƁA��͌R�̍s����}����B���N��́A�I�����_�l�̗͂���āA�p���������Ȃ��̂����i�j�A�Ƃ������Ƃ��ˁB �b�\�\���̖���d�v�Ȃ̂́A�����z�͂ǂ����ȂA�Ɲ������Ă���B���X������̂��i�j�B�i�V���i���Y���ɏƂ炵�āA�������������̂͂��܂���̕����낤�A�ƁB����́A�L���X�g���̋����E�V���̑Η��R�����،�����d�v�����Ƃ�������ł͂Ȃ��A�u���{�V�O���v�Ƃ������t�����A���{�i�V���i���Y�����̂��̂𑊑Ή������ő����̎j���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă悢�B �a�\�\�א쒉�����A�ނ́A�I�����_�l�̉����������ď�𗎂Ƃ��Ă��A�O���������p�J���̏�Ȃ�����A�ƕ��S���āA���叫���開�{�̏�g�A�����ɓ���M�j���l�����Ƃ����b������ˁB����������悤�Ș_�����B�����M�j�́A������ď�̘A�����\�����ȂA�Ƃ����B�A���͓���片�R������ƐM���Ă���B����œ�ؑD�����ď�Ɍ����ĖC��������A�ӋC�������Ē�R����߂�͂����ƁB�q�����܂�����i�j�B �b�\�\�����M�j���u�q�b�ɓ��v�Ƃ������Ď����グ��A�������₽�Ȃ��̂����A��̓��X����}�Ԃ���݂�A�Ꝅ��������Ȃ��ƂňӋC�������Ē�R����߂�͂����Ȃ����A�V���k���G���Ƃ������Ƃ͔ނ�ɂ͏��m�̂��Ƃ��B����́w�ȍl�S�^�x�̋L��������b�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ǂ����ɂ��Ă��A���{���I�����_�l�̗͂��肽�Ƃ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�I�����_�l���ď�̃L���X�g���k�ɑ����Ȃ获�X�ȖC���������킯���B �`�\�\�sDer fliegende Holländer�t�i���܂悦��I�����_�l�j�ł͂Ȃ��āA�C������I�����_�l�˂��i�j�B�������A���炩�ɃL���X�g���M�҂ł���l�X�������l���Ă��ɁA�I�����_�l�͑�C�ŖC�������B����͏@���j��Ƃ��������A�L���X�g���j��̔ƍߍs�ׂł��ȁB�L���X�g���k�̂��邱�Ƃ́A�̂������A����s�\���i�j�B �a�\�\�\�Z���I�ȗ��A���[���b�p�l�͓����A���E�����r�炵�܂����Ă������A���ۂɂ͉h�͐������������B���傤�ǂ��̍��́A�X�y�C����|���g�K���̋������E�����͂��������āA�I�����_��C�M���X�Ƃ����V�����E�V���͂�������������B�I�����_�l��C�M���X�l�́A�㔭�g���������A���쐭���ɁA�J�g���b�N���k�͓�Ăł���Ȏc���Ȃ��Ƃ�������A�����ł͂���Ȕ�������A���������Ċ댯�ȘA�����Ɛ������킯���B�����̗��́A���ڂ̂��������͋��~�ȑ㊯�̉՝��n���ɂ����Ȃ����A���̐����s���Ɋւ��ẮA�I�����_�̏��l����݂��Ă����B �b�\�\�I�����_�͓Ɨ��푈������āA�X�y�C������Ɨ����������Ő��\�N�B�����̗��̓����A�C���h�̃S�A���ŁA�܂��I�����_�ƃ|���g�K���͊C�������Ă���B�����͐푈��Ԃ��ȁB �a�\�\������A�]�˖��{�́A���̐푈��Ԃ̗����ԍR���Ɋ������܂�Ă���B��X�I�����_�l�́A�r�W�l�X�����̂��t�������ł悢����ǁA�|���g�K���l�́A�؎x�O��k���g���āA���{�����������ł����A�Ȃ�Ă��Ƃ𐁂����ށi�j�B �`�\�\���ꂾ������Ȃ��āA�}�j����̂Ȃ�ČR���v���W�F�N�g�������o���Ă����悤���B �a�\�\����́A�͖C�ˌ��Ō���U���ɋ��͂����I�����_���ق̃N�[�P�o�b�P�����L�^�����A���{��g�̌˓c����Ƃ̉�b���ȁB�}�j����S�ł����邽�߂ɁA�͑D��������A�ƃI�����_���l�͖��{�ɐ\�o�Ă����炵���B �`�\�\�Ƃ������Ƃ́A�����̗������A�I�����_�l�́A���{�l�Ɂu�}�j�����U���Ȃ���̂Ȃ�A�x�����܂����v�ƍ����Ă����Ƃ������Ɓi�j�B �b�\�\������O�̊��i���N�i1630�j�A�������E���q�d�����A���\�������̂��߂̒�@����h���������A���q�d���{�l���}�������̂ō����~�݂ɂȂ����Ƃ��A����Șb�����邩��A���̐؎x�O�Ꝅ���N����O�ɁA�}�j���U���̌v��͂��낢��o�Ă����̂��낤�B �`�\�\�}�j���ɂ͓��{�l���������āA�}�J�I�ƂƂ��ɐ؎x�O�̃Z���^�[�������ɂ��Ă��A���̉����͂��傢�Ƙb���킩��B �b�\�\����A�N�[�P�o�b�P���̓��^�ł́A�˓c���삪�A�u���{����o�����Ȃ��Ă��A�I�����_�l�����̕��͂Ń}�j���͐�̂ł���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����ƁA�u����A�}�j����̂��m���Ɏ��s���邽�߂ɂ́A���{�l�̐��R���R�̑����傫�ȕ��͂��K�v���v�Ɠ������B�v����ɁA�I�����_�l�́A���܂�����Ɠ��{�l�����̋C�ɂȂ��āA�}�j�����̂ł��邩������Ȃ��ƍl���Ă����悤���B���ꂪ���s�ł��Ȃ��Ƃ��A�|���g�K���E�X�y�C���̌R���������ˁA������_�V�ɂ��āA�f�Ղ̃r�W�l�X������Ɛ�ł���Ƃ��������B �a�\�\�I�����_�l�͓����f�ՂƂ���������_���ēo�ꂵ���B���̂��߂ɂ́A�X�y�C���l��|���g�K���l��r�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A���얋�{�́A��B�Ɏc�������J�g���b�N���͂���|���邱�ƂŁA�V�����̍��ۓI�A�d�̕Ж_�������ł��܂����Ƃ����킯���i�j�B �`�\�\����ƁA�V�������̈ꗐ�܂ł́A���݂��Ă����ɂ���A�؎x�O�͋�B�ɂ��Ȃ肢���Ƃ������Ƃł����ȁB �a�\�\�������낤�ȁB�u�����Ԃ�v�̐؎x�O�Ƃ����ˁB���������u�����Ԃ�v���A�؎x�O�M��e�F����ƁA��ŗv�����Ă���B���邾���ł������l���}���҂��o���̂����A�����؎x�O�M�҂͋�B�S�̂ł͏\���͂������낤���A�S���ŎO�\���Ƃ������v���́A����قǔ��I�Ƃ��v��Ȃ��B�L���X�g���͂��Ȃ�������Ă����B �b�\�\�O��ډƌ��̂Ƃ��ɓV�������̗��ŁA�����ł͂Ȃ��V�������A���������������������A�ƍN�̑�܂ł͂��������I���͂Ȃ������ȁB �`�\�\���̓V�������̗��ɂ��ẮA���j�w�̕��ł͖��Ȃ��ƂɂȂ��Ă���܂��ȁB �b�\�\��O�L�n�ł͂��Ƃ��Ɨ̎叼�q�̉՝��n���������Ȃ��A���A�S���Ꝅ�_�́u���͑Ζ��O�v�Ƃ����ÓT�����I�}�������y���āA�؎x�O�M�Ƃ����ǖʂ������Ȃ����B����͖��O�Ꝅ�����A���͑��͎��؎x�O�𗝗R�ɑS�����s�E�����Ǝ咣����҂܂ŏo�āA�؎x�O�M�͕����I�Ȍ_�@�ɂ��Ă��܂��B�ÓT�����I�}������ނ����ߔN�ł��A����͈Ꝅ�ȂA�؎x�O�ł͂Ȃ��A��������ɂ����A�Ȃ�Ă��Ƃ������o���B �`�\�\��؎x�O�����邩��A�K�������؎x�O�Ꝅ�ł͂Ȃ��A����͒n�拤���̂̈Ꝅ���ƁB �a�\�\�؎x�O�ł͂Ȃ��S�����A�u�ꖡ���Ȃ���ΎE�����v�Ƌ�������Ė������Q���������A����ɘA�ꍞ�܂�Ă���B�Ꝅ�Ƃ�������ɂ́A�n�拤���̂̑S�ʓI�^���ŁA�l�̎��R�Q���̍s���ł͂Ȃ��i�j�B�Ꝅ�Ƃ����̂͂����������̂ȂB �b�\�\�����l�K�͂̈Ꝅ�ł͎G���Ȑl�Ԃ����āA���R�����̏W�c�ł͂Ȃ��B�y���̔_��������A�����s���Ɛb�������Ƃ̘A����L�n�Ƃ̋��b�Q�l�����邵�A���q������������B�������A�Ꝅ�ď邵���{�̂́A��͂�u�؎x�O�̕S���ǂ��v�ȂB�ނ炪�؎x�O�Ɂu����������v�u�����オ��v���āA�Ꝅ���Č�����Ă����B�̎�̉՝��n���ɍR�c���������ł͂Ȃ��A���̐؎x�O�M��e�F���Ă���Ƃ����̂��A���̗v������B �a�\�\�ނ�͏����낤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���ʋC������ȁB������A���Ŏ��ʋC���B����͈ȑO�̓y�Ꝅ�Ƃ��㐢�̕S���Ꝅ�Ƃ��Ⴄ�A���{�I�Ȉَ������B�p�[�h���i�i�Ձj�����Ȃ��Ă��A�}���̃|�W�V�����͑N������B �`�\�\�}���͓V���̖傾�ˁB�������{�̗��j�w�͂܂��������Ă��Ȃ��B������A���܂��ɁA����́A�؎x�O�̈Ꝅ���A����Ƃ��S���Ꝅ���A�ȂǂƂ��������ȓΗ��}���ł������z���Ȃ��B �b�\�\���{�̗��j�w������ȗL�l������A���@�`�J�������l�ɗ�̂����߂���Ă���i�j�B�L���X�g���k�Ȃ�A����Ȗ\�͓I�Ȕ����͋N�����Ȃ��Ƃ��ˁB�Ƃ��낪�A�ď�̐؎x�O�́A��X�͍������������͖ѓ��Ȃ��A�U�����Ă��邩��h���ł��邾�����ƌ����Ă���B �a�\�\�L���X�g���k�łȂ��Ȃ�A���隬����A�ǂ����Ă��ꂾ���A���̏e�e���璒�������\���˂���ʂɏo��i�j�B �`�\�\���@�`�J���́A���܂��ɂ����ď�҂�̏}���s���𗝉����Ă��Ȃ��B���������Ӗ��ł́A�L���X�g����j��A�H�L�Ȏ����ł��Ȃ��i�j�B |
|
�b�\�\�Ƃɂ����A�����ď�̈Ꝅ�O�́A���ǂ��܂ł������������A�N���X���z�ɂ��āA���������āA�Δ��I�i�Ԃāj���J�̍~��悤�ɓ������̂ŁA�U�������́A�Ђ��őދp�����Ƃ����A��؏d���̕�������ˁB���隬�ŋߔN���@���ꂽ�\���˂Əƍ�����ƁA���́u�N���X���z�ɂ��āA���������āv�Ƃ����V�[���������[���B �`�\�\����́A�ꂢ�̋t�\���˂̂��Ƃł����ȁB �b�\�\�����ȂB�\���˂́A�ӂ��\���̏c�_�̏オ�Z���ĉ��������B�Ƃ��낪�A���隬����o���\���˂͎O�Z���`����̏����Ȃ��̂����A���̒����ق��Ƀ��U���I�̒ʂ���������B�Ƃ���ƁA�������ɉ�����ƁA�\���˂��t���܂ɂȂ邩���������B �a�\�\����́A�{�����O�ɎO�x�C�G�X��ۂy�e�����ȁB�u����͂���Ȑl�͒m���v�ƌ����Ă��܂��āA�{�������B�C�G�X�͐U��Ԃ��āA�y�e�������߂�B�y�e���͊O�֏o�āA�Ђǂ��������B�i���J������22�́j �b�\�\�C�G�X�Ƌ��ɂ������Ƃ�ے肵�����̃y�g���́A����ɂ����Ă����؎x�O�Ꝅ�O�ɏd�Ȃ�B�����͐؎x�O�ł��邱�Ƃ�ے肵���ߋ������B�e���ɂ���ē]�����@�����u�]�сv�؎x�O���B���ꂪ�؎x�O�ɗ����Ԃ������A�w���̍�����B �`�\�\���̃y�g���̓��[�}�ŏ}������B���̂Ƃ����ɂȂ������A�����̓C�G�X�Ɠ����悤�ɏ\���˂Ɍ������鎑�i�͂Ȃ��ƁA�㉺�t���܂����Y��]��ŏ��Y���ꂽ�Ƃ��B �a�\�\�T���s�G�g���吹���́A�y�g���̏��Y�n���Ƃ����ꏊ�Ɍ����Ă���B�L��̃I�x���X�N�����̕W�����B�y�g���́A���[�}�E�J�g���b�N����̑n�n�҂ł��邵�A�V���̖�̌������ے��I�l���ł�����B �b�\�\�悤����ɁA�t�\���˂́A�C�G�X�̒�q�ł��邱�Ƃ�۔F�����y�g���̃V���{�����ȁB����̈Ꝅ�O�͂��̋t�\���˂����Ɍ����Ă����B�����܂ł́A�܂����肤��b���B �`�\�\���̑��ɉ�������Ƃ���ƁH �b�\�\���ꂪ�A��؏d���̂����A�u�N���X���z�ɂ��āA���������āv�Ƃ����p�Ɋւ�邱�Ƃ��B�܂�A�Ꝅ�O�́A���̃y�g���̋t�\���˂����ɉ����Ă��āA�퓬�̎��ɂȂ�ƁA������z�ɂ��ĂĔ����������B �`�\�\�Ȃ�قǁA��������ƁA�������̋t�\���˂�����ǂ͏�����ɂȂ�B�w�������҂��u�����Ԃ�v�Ƃ����킯���B �a�\�\�������ɁA�Ꝅ�O�́A���������V���{���b�N�ȑ�����������������ȁB�t�\���˂��t�ɂ��āA�����Ԃ����^�����Ȑ؎x�O�Ƃ��Đ�����Ƃ����킯���B �b�\�\���隬����o���t�\���˂́A���������ӂ��Ɍ���ׂ��ł͂Ȃ����B�t�\���˂ŏ��Y���ꂽ�y�g���̎p�ɏI�炸�A����̐؎x�O�Ꝅ�O�́A����Ӗ��Ńy�g���̌����܂ōs�����ƁB �`�\�\���ꂪ�A���隬����o���t�\���˂̉��ߊw�I�Ӗ��ł��ȁB 
|
*�y���ԏO����؏d������z
�s�c����y�ӉȔV�R�A���ւ���n��B�K�V���V�O���ӊ\��|�A��V���j�͏钆���Ȃ������ی��Ȃ��o���A���Ƃ��[�����\�A�邠�����S�{��ŗ��A������ւ�����̂́A�����܂ł������������A���邷���Ђ����j���āA�͂��܂����������A�Δ��I���J�̂ӂ���Ő\��t���A�悹�O����݈��\��t�i���������t�j *�y���J�������z �s���ɐl�X�C�G�X��߂ւđ�Վi�̉Ƃ։g���s���B�y�e����������Ĝn�ӁB�l�X����̓��ɉ��āA�����ɍ�������A�y�e���������ɍ����B���X�A�y�g���̌����č�����������A���ɖڂ𒍂��Č��ӁB�u���l���ނƋ��ɂ��v�B�y�e���m�͂����Č��ӁA�u����A��͔ނ�m�炸�v�B�b�����āA���̎҃y�g�������Č��ӁA�u�����ނ��}�o�Ȃ�v�B�y�e�����ӁA�u�l��A�R�炸�v�B�ꎞ���肵�āA�����̒j��������Č��ӁA�u�܂��������l���ނƋ��ɂ��肫�B���K�������l�Ȃ�v�B�y�e�����ӁA�u�l��A����̌��ӎ���m�炸�v�B�P���ЏI�ʂɁA�₪���P���ʁB��A�U�Ԃ�ăy�e���ɖڂ𗯂߂��܂ӁBূɃy�e���A�u�����ɂ́A�P���O�ɁA���O�x���ۂ܂�v�ƌ��Ћ��Ђ��䌾�����Џo�����A�O�ɏo�łāA�r�i�����j��������t�i22�� 54-62�j  
���隬�o�y�\���� |
|
�\�\�Ƃ���ŁA�V�������̗��ňꝄ�O�������Ă��ċʍӂ�������U�h��̂��Ƃł����A���̂Ƃ��A���ŕ������L�n�����ɏo�������̂����Ă��܂��B�L�n�����͕��̐��M�̑ォ��̗L�͂Ȑ؎x�O�喼�ł����ˁB �a�\�\���̗L�n�����̕��e�A���M�̂��Ƃ����ˁA���M�͐؎x�O�喼�A������Ƃ������A���ǂ��Ȃ�啝�Ȑ؎x�O�x���ɉ���āA�L�n�x�z�̗̖����ׂăL���X�g���k�ɂ������B�����ɕ��m��e�������@��j���B���M�͌c���\���N�i1612�j�ɉ��{�唪�����Ŏ��r�A�������ꂽ���A���̏��͎̂q�̒��������������B �b�\�\�����͗c����������l�ŁA�͂��߃L���X�g���k���������A�ƍN�̑[�u�Ŋ������āA�{�������̖��i���P�j���Ȃɂ����B����́A�喼�̎q���l���Ɏ���č]�˂ɏZ�܂킹��Ƃ�������̌��ʂ��ˁB�����͕��S�����Ƃ��ɂ͂��łɐ؎x�O�����A�̍��L�n����藣����ċ��邤���ɕʂ̎v�z��m���Ă��܂����킯���B �`�\�\�]�˂ɋ��邤���ɋt���]���ꂽ�Ƃ������i�j�B�{�������͔d���̕P�H���ɂȂ������A���̖{���������ۂƂ���������ŁA�L�n�����ƕ����Ƃ̉����ł���B �a�\�\�������������́A�Ɠ������Č�A�̓��̐؎x�O���Y�A����j��A�鋳�t�Ǖ��ƁA�e�����鑤�ɉ�����B�����͎��g�ٕ̈��A�d�b�Ƃ��̉Ƒ��܂ŏ��Y�����ˁB �b�\�\�債���]���Ԃ肾���A����������͓����͏��Ȃ��Ȃ��B�����ˁA�L�n�����͂��̌�����ɓ]���ɂȂ����B���̌�ɓ������Ă������q�d���́A�����Ꝅ�̌����ƂȂ锗�Q���s�����Ƃ������A�������Ă��炭�͐鋳�t��ی삵�Ă����B�悤����ɁA�؎x�O�e���͏@���I�C�f�I���M�[�Η��̖��ł͂Ȃ��B����͕ʂ̖�肾�ˁB���{�l�̓V�r�A�ȃC�f�I���M�[�Η��͂��Ȃ����A�ł��Ȃ��i�j�B �a�\�\�����ǁA�����V���̃��[�J���ȈꝄ�ɑ��A�������喼�ɓ����������ď\�����l�̌R���ŕ�͂��ğr�ł����̂́A���̃X�P�[���E�A�E�g�����i�j�B�q�d������g�ɂ����ŏ��̓����́A������瓇�ƁA�v���ď��L�n�ƁA�����嗧�ԉƁA��͌R�Ƃ��ẮA���ꂾ���̐l���ł����\���Ȃ͂��ȂB �`�\�\�ď�̈Ꝅ���́A����e��H�Ƃ��ʂɌ�����Ɏ���������ď邵�����A�Ȃɂ����q�����܂߂Đ����l������B���ӁA�H�Ƃ͐s���邩��A�����҂Ă悩�낤�ɁA��R�ōU�ߒׂ��Ƃ������������ɂ����B �b�\�\���ہA�ɂȂ��Ă����~�҂͂܂����Ȃ������B�������ɂ��Ē�R�����E�������Ȃ�A���Ɛ������A��͂��Ă���悩�����B�������o�w����K�v�͂Ȃ��������A���ʼn�������邱�Ƃ��Ȃ������i�j�B �`�\�\��B�ƍ]�˂ł͋����������B���]�˂֒B����̂ɔ����A�w�߂�����̂ɔ����B�����ꃖ���B�]�˂ł́A���ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�c�����Ă��Ȃ��B �a�\�\�����M�j����g�Ƃ��Ĕh�������̂́A�͂��ߐ�㏈���̂��߂������B�����Ꝅ��������������낤�Ǝv���āA�����M�j��h�������B�Ƃ��낪�A�r�����Ŏ��ł́A�܂������ł��Ă��Ȃ��B�ŁA��������Ă���̂��A�Ƃ������ƂɂȂ����B �b�\�\�L�n�̓������V���̕x������Ꝅ���ɍU������āA���낤���Ď����������Ă����Ƃ����L�l�����A���{�������́A�y�������̈Ꝅ�Ƃ������ƂŁA�y�����Ă����ӂ�������ˁB�������A�Ꝅ�O�͂��̐킢�̏o���͂��̐��ɂ͂Ȃ��A�}�������Ȃ��ƒm���Ă����B����ŁA����ɂ����Ă����B �`�\�\�����_�̍��ւ̓�����ɂ����B �a�\�\��g�̔q�d���ȉ���͌R�̏��喼���肱�����Ă���̂�m���āA���̍א�Ƃ��͂��ߋ�B�̏��喼�́A�������ƁA�����͐�ւ̎Q����u�肷��B�����Ƃ��Ă͂Ȃ炶�A�Ƃ����Ƃ��낾�ȁB �b�\�\�����Ƃ��Ă͂Ȃ炶�A�Ƃ����A���̂����肪���ƎЉ�i�j�B����ŁA���{�͏\�����Ƃ����X�P�[���E�A�E�g�ȌR����g�D���邱�ƂɂȂ����B �`�\�\����͎��̂Ȃ�䂫��������A���w�ȗ���\���N�Ԃ�̐푈�̐��B����������́A���A���Ȃ��̂���Ȃ��āA�V���{���b�N�ȓ����ł��傤�ȁB �a�\�\���̂Ƃ����ӂ�v����̂́A�����̗��̑O�N�����A�嗤��ł́A������u���v�Ə̂��A���N�����������Ƃ��ˁB�����嗤�ł́A�ٖ����̐������ɂ��x�z����������B���������Ȃ��ŁA���̗ł́A���̊�@�����������Ƃ݂Ă悢�B��B�ɂ��ꂾ���̓������������̂́A���̉��K���낤�B �b�\�\�嗤�ł́A���`����ʂ��āA�C�G�Y�X����͂ɐH������ł����ˁB�C�G�Y�X��鋳�t�����́A�t�����`�F�X�R������v���O�}�e�B�b�N�ŁA�����𒆍����ɉ��߁A�������������A�z���ɂ������Ă͒����l�̊��K�E�`���I�V���d���邵�A�E�q���q���c���J�Ȃǂ̋V����F�߂��B���̑Ë��I�Ȃ����́A��ɃJ�g���b�N�h�����Ŕᔻ����邪�A������ɂ��Ă��A�A�_���E�V���[���iAdam Schall�A����]�j�̂悤�ɁA�V���w���Z�Ƃ������Ȋw����ł͂Ȃ��A��C�̒����܂ŋ������̂��A�C�G�Y�X��B �`�\�\�V���[���́u������v�͐���Ɂu������v�Ƃ��Ē����S�y�Ŏg��ꂽ�B�����N�ɃO���S���I��ɉ��߂�܂ŁA���ꂪ�g���Ă����B���܂ł����̋���͖��ԂŎg���Ă���ˁB �a�\�\���̐��������ł́A���m�ΖC�̌������w�U�l�v�x�i�����\�Z�N�E1643�j������ˁB����͐��m�ΖC�A�Ζ�A����Ɋe��Ί�̐����Ǝg�p�@�̂��Ȃ�ڂ������������Ă���B �b�\�\���ꂾ���ł͂Ȃ��A��������A�@�B����A���w�E�����w�E���w�̊�b�Ȋw�܂ł���B���������̂�����ƁA���m�̉Ȋw��H�w�́A�����̌R���e�N�m���W�[�����{�I�ɕϗl�������B�D�v���ǂ����ŏ����Ă����悤�ɁA���������������ł͂Ȃ��ٖ�������������A���ꂪ���R�ɂł����Ƃ����b������B �a�\�\�Ƃ�����A�嗤�ł͖�h��m�A�C�G�Y�X��m�̉e���͑傫���B���������āA���鍑�̐����Ƃ���������̂Ȃ��A�嗤�ŃC�G�Y�X��n����z���Ă���̂ɑ��A���쐭�������{�̃C�G�Y�X��̉e���͂Ȃ����c�}�ɑ��A�����O��I�ɔr�������Ƃ����̂́A���R�̂����Ă̂��Ƃ��낤�B �b�\�\�Ƃ��ɃV���[���̎���͐M�k���}�������B��Z�ꎵ�N�ɂ͂킸���ꖜ�]�������̂��A��Z�܁Z�N�ɂ͏\�ܖ��A�Z�Z�N�㔼�ɂ͓�\�ܖ��l�Ƃ����������B������A�����̗��Ȍ�A�嗤�ł͋t�ɖ�h��M�k�͑����Ă���B���̓_���炷��A�����̓��{���{�́A����Ӗ��œ��قȑI���������킯���B������b�̔h���v���͒f�������A�������ɑ��Ă͍ŏ��G�ΓI�ɍ\���Ă����B �`�\�\������܂��A�I�����_�l�E�C�M���X�l�̐V���h�̐����I�ȓ���m�b��������Ȃ����i�j�B�悤����ɁA�]���̑P�ʁE���ʘ_�ł́A�����ē����̗��̗��j�I�ʒu�Â����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ǂ������킯���A���ꂪ�����_�ƃ����N���āA�P�ʁE���ʘ_�ł��̈Ꝅ������Ă��܂��B �a�\�\����ł͉�����������Ƃɂ͂Ȃ��ˁB�������܂œO�ꂵ�����E�����s����̂́A�����ɂ̓C�M���X�E�I�����_�Ƃ����V�����̓������������������낤�B�Ꝅ���������ɂ��Ă��܂����̂́A�����L���X�g���k�ȂB���悻�����̗��܂ł́A�L�������̐؎x�O�֗߂ŁA�L���X�g���k�͂��Ȃ葽���c�����Ă����B�喼�ɂ��A�؎x�O�ٔF�Ƃ����̍��͑����������A�ł���Ȃ�C�O�ւ̊J�������m�ۂ������Ƃ����C���͂������B �b�\�\���̑�\�Ⴊ�A�c�������g�߂��o�����ɒB���@���A�Ƃ������ƁB�����̗��܂œ�\�N�A������A���̓�\�N�ł����Ԃ���ς����킯���B������L�n�����̂悤�Ȑ���́A���ǂ��������ω���̌����Ă���̂��ˁB |

�����̏\���ˁ@���隬���@����  ������w�}  ����U���喼�z�w�} 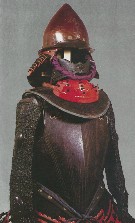
��ؓ�� 
Johann Adam Schall von Bell �i1591�`1669�j 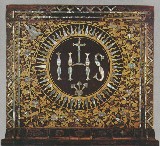
�C�G�Y�X���� IHS�̓C�G�X�L���X�g ���c��Ιησους�̓��O���� |
|
*�y�t���C�X�@���{�j�z
�s���Nj撷�i�R�G�����j�t�́A���˂ɓ�������ƁA�����������Ȓ��ӂ������āA��̗F�l�ł��鏔�m���ɏ�����A�i�����j���Ƃ����Ė\�N�i�G�g�j�Ɏ������āA�i�Ղ����̒Ǖ��߂̓P����肦�ʂ��̂��A�����s���Ăق����ƍ��������B�����̏��M�̉^�і����Ƃ߂��؎x�O�́A���Ɂi���c�j�����q�a�̋��ɍs���āi���j�B�ނ́A�����̐킳����A�����ɂ����\�N�̐w�ցA�����O�ɖ߂��Ă��Ă����B�ނ͎Q�킵�����̎҂̂����������������̂ŁA���̈̑�Ȍ��тƏo��ɑ��ĕ��邽�߂ɂ���ė����̂������B�ނɂ͂��łɖL�O�̍�������Ă����B�i�Ƃ��낪�G�g�͂͂��߁j�ނ����Ă�����Ƃ͂����A�܂��u���܂��͂���ɉ������Ȃ��B���߂�\�͂��Ȃ��B���܂��͐؎x�O�ɂȂ��������͖��������A�����̑喼�⑼�̋M�l�����ɁA������ɐ����āA�؎x�O�̋������Đ�����A����܂ł̐_�X�ւ̐M���̂Ă�悤�ɐ����������Ă����B����Ȃ��܂��ɍ���^����킯�ɂ͂�����v�ƌ����A����Ɋ����̔l�i�G����ނɂ��т����B �@�����q�͎v������l���������̂ŁA���Â��悻�����āA�������Ԃ��D�]����̂��������B�ނ́i�R�G�����j�t����̏���ƁA�t�������ً̈��k�̕�����Ɉ��Ă������ǂނƁA�����������̎茳�ɂƂǂ߂āA�i�Ղւ̕ԏ��ɏq�ׂ��B�u���͂��̂��т̈����I�ȕϓ��ɂ͋ɂ߂ėJ�����Ă��܂��B���������̎�i�f�E�X�j�����̂悤�ɋ�����������ɂ́A�����ɂ͂���߂Đ����ȗ��R������͂��ł��B�����̏����ܖ��ɗ����ǂ����킩��܂���̂ŁA����Ɏ�n���͎̂��������ƍl���A���̎茳�ɂƂǂ߂Ă����܂��B�����i�R�G�����t�̒�Ă̂悤�ɁA�G�g�ɑ���j�����ɂ���Ď������܂������悤�Ȃ�A���͂�낱��ŁA���L���邷�ׂĂ̕��\�ƉƎY�����o���A�Ȃ����̂����A���ɑтт鑾���������Y���č��o���܂��傤�B�������Ȃ���A�f�E�X�́A���̂悤�ȋɈ��l�i�G�g�j��㭂����ɂ�����Ȃ��ł��傤�B�i�G�g�́j���������͐������Ȃ��Ǝv���܂��B���́A�{���Ȍ�A�V�i�̒�q�D���o��܂łɁA�������Ԃ��ς��̂����҂��Ă��܂��v�Ɓt�i��18�́@�\�N������E�i�Ղ����A����ѐ؎x�O�@��ɑ��Ė��������Ƃɂ��āj  �@���L���V�^���� �����ɃN���X�i�\���ˁj�A���͂� Iosui Simeon�i�W���X�C�E�V���I���j  �V�ƉƗݑ㓃����@�Ɩ� ���⎛�@���������q�s�O�ޖ� |
�`�\�\�����ł����A�����ƒ����A���̗��l�͂��̐��ォ�炷��ƁA�Ƃ����؎x�O�M������o�Ă���ƌ����܂��ȁB �a�\�\�L�n�����́A���̐��M���Ă��؎x�O�喼�ŁA�����́A�c������g������A���S�����Ƃ��ɂ́A���łɐ؎x�O�������B�̂��Ɋ������邪�A�q���̍�����؎x�O�M���ň���Ă���B�������A�����̕��͂ǂ����ȁB �b�\�\�����̕��́A�L�n�����قǂł͂Ȃ����A����ł���͂�A�؎x�O�M���Ƃ������̂�O��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A���c�����q�i�@���j�̂��Ƃ�����ˁB�����o�������̋{�{�����ӂ́A���c�����q�̗̒n�B���c�����q���͂��߂ĖL�b�喼�ɂȂ����̂́A�G�g����K���S���Ɉꖜ��^�����Ă̂��Ƃ��B���̗̎�E���c�����q�́A�M�S�Ȑ؎x�O�喼�������B �`�\�\���R�E���̋������āA���c�����q�́A�����s���ƂƂ��ɐ؎x�O�@�k�ɂȂ����̂ł����ȁB �b�\�\���c�����q�͎��ʂ܂ň�т��Đ؎x�O�B��̒��V���A���q�̒������A�M�҂ɂȂ����B�����q�̑��V�̓L���X�g���k���ŁA�����̋���ɑ���ꂽ�B�L���v���́w���c�ƕ��x�ł́A���̂�����̂��Ƃ́A�܂�Ō����ɖ�������Ă��邪�i�j�B �`�\�\���k�邷�ׂ��A�邷�ׂ��l���B�������A�����q�E�������q�̐؎x�O�M�́A�Ӑ}�I�ɖ��E�����Ƃ��Ă��A�d���A�E��������A�w���c�ƕ��x�̍��c�ƑO�j�́A�S���̃t�B�N�V�����ł��ȁB �b�\�\�L���v���́A�d������̍��c�ƑO�j�ɂ��ĂقƂ�lj����m�炸�Ɂw���c�ƕ��x�������Ă���i�j�B �a�\�\���Ώ��ɂȂ��Ă������R�E�߂��A�G�g����M���Ƃ邩�A�喼����߂邩�A�̓�ґ���𔗂��āA���ǐM���Ƃ������Ƃ͗L���Șb�����A���̂Ƃ��A���c�����q�͐؎x�O�M�҂ł��邱�Ƃ��̂ĂĂ��Ȃ��B����́A�G�g�������܂ŗv���ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B �b�\�\����ɂ��ẮA���낢�뉯�������邪�A��B�����푈�ɂ����鍕�c�����q�̐�����炷��A�L�O�Z�S�\�ܖ��͏��Ȃ�����B����͓����̃p�[�h���i�i�Ձj��̉��߂����A�G�g�́A���c�����q���������Ȃ��̂ŁA����ȏ��Ȃ��̒n�����^���Ȃ������Ƃ����B�G�g�͊����q�̔\�͂�ɂ���ŁA�ނ̐M�����Ԃ��ԗe�F�����Ƃ����킯���B �`�\�\�����A�G�g�̋��߂́A�܂������̋֎~�ł͂Ȃ��A�o�e�����Ǖ��߂ł��ȁB�؎x�O�M�҂̑喼�́A�͏o������悢�Ƃ����Ă��ǁB���喼�̐؎x�O�M���֎~�����킯����Ȃ��B �b�\�\�������ȁB�������A�u�_�����{�v���咣�����G�g�̈ӂ�����ŁA���������A�������Ȃ��Ȃ��B���̂Ƃ��A�������Ȃ��������c�����q�ɂ��ẮA�t���C�X�i���{�j�j�Ȃǂ́A�G�����ق߂Ă����B �a�\�\�t���C�X���m���Ă���R�f���E�J���r���E�G�iCodera Quambioye�j�A�܂菬�������q�A���M�̐l���ȁB�����s���͈ꎞ�M����������B����ɑ��A�����q�ɂ͊����̋C�z���Ȃ��B �`�\�\�t���C�X�́w���{�j�x�ɂ��A�V���\�ܔN�̏G�g�̃o�e�����Ǖ��߂ɃA����H�����R�G�������A���c�����q��ʂ��ď���ɓ��������悤�Ƃ������A�ނ͂�����Ȃ��߂ĉ������߂�ˁB�������Č����ɂ́A�u�f�E�X�́A���̂悤�ȋɈ��l�i�G�g�j��㭂����ɂ�����Ȃ����낤�v�i�j�B�ނ͂��������͐������Ȃ��Ǝv���܂���A�Ƃ����킯���B �b�\�\���Ȃ��ÂȒj���B�t���C�X�́w���{�j�x�����p���Ă���o�e�����Ǖ��ߕ����͐��m�Ȃ��̂��B�����́A�R�G�����֑����������q�̕ԏ������ď����Ă���B�����q�́A�f�E�X�̓{��ɂӂ�ďG�g�̖��͂��������͂Ȃ����낤�ƌ����B�����q�́A�G�g�ɂ͂قƂقƎ���Ă��Ĉ��z���s���Ă��邪�A�����⋃�����Ă���p�[�h���̃P�A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�j�B �a�\�\�G�g���C�ɓ���Ȃ������̂́A���c�����q���؎x�O�@��ɋA�˂������Ƃł͂Ȃ��A���̏��喼�ɂ�������ɓ��������āA�M�҂ɂ��悤�Ƃ��Ă����A���̕z���s���̂��Ƃ��B �b�\�\�����q�́A���Ȃ�ϋɓI�ȐM�҂������B�L�O���Âɍs���Ă����������A�փ������A�}�O�ő�喼�ɂȂ��Č���������낤�B���������̐؎x�O������}�O�ֈ�������Ă���B�F��c�ƘV�̖��ΑS�o���؎x�O�����A�փ������A���ΑS�o�͒}�O���c�̓��ɏꏊ��B �`�\�\���c���V�̏H���ł����ȁA����́B�}�O���c�ƂƂ����A�V�Ə@���A��B�g��S�̒|�R��̍Ō�̏�傾���A���̐l�͂�͂�փ������A���c�@���ɏE���āA���c�Ɛb�ƂȂ��Ē}�O�����S�ɒm�s���B���̐V�Ə@�тɂ��A�؎x�O�̘b������܂����ȁB �b�\�\����͂ˁA���Ƃ��Ƌ�B�}�O�֍s�����V�ƉƂ̉Ɩ䂩��o���b�ȂB �a�\�\�Ƃ����ƁA��̏\�����A�N���X��̂��Ƃ��B �b�\�\�V�Ǝ��̉Ɩ�́A���m�̂��Ƃ��{���O�b�Ȃ��A�i���q�s�j�O�ޖ̐��⎛�ɂ���V�ƉƗݑ㓃�A�܂�V�ƉƂ̕��̖�́A�O�b�ł͂Ȃ��A�ǂ������킯���A�\���̃N���X��ȂB�������A�}�O�V�Ǝ��n���ł��A�V�Ə@�т̖����n�͕s���A�Ƃ��낪���`���ɂ́u�ɉ�l�v�Ƃ����J���Ă���B����͐q��ł͂Ȃ��B�����ŁA�V�Ə@�с��؎x�O�����o�Ă����B �`�\�\�����V�Ə@�т��؎x�O�ł���A��ɖv�N���揊���s���ɂȂ邱�Ƃ́A�傢�ɂ��肤�邱�Ƃ��ƁB�ߏ��ɋ��Z���Ă������ΑS�o�̂��Ƃ����邵�B����ɁA�@�т̑��q�E�����q�����w�̂Ƃ��A����ɓ����Ă��܂����B����͂��ԂΑS�o�̉����낤�B �b�\�\���Ƃ��Ɖ��R�̉F��c�ƒ��ɂ́A�؎x�O�M�҂����������B���̂��Ƃ��O���Ă��A�V�Ə@�ю��ӂɂ́A���ꂱ��؎x�O�M�̍��Ղ�����B �a�\�\���������A�փ�����̑O��A�V�Ə@�т̓������悭�킩���ȁB���Ԃł́A�F��c�G�Ƃɏ]���Ċփ����Q��A�ȂǂƂ���������{�w�{�{�����x�̐������܂��ɔ������Ă���҂����邪�A���ہA�V�Ə@�т͊փ����ւ͏o�Ă��Ȃ��ˁB�V�Ə@�т͉F��c���Q�ł͂Ȃ��A�ː�g�����A���̌ː�眈��͊փ����̑O�N�A������F��c�����ŗ������ĉƍN�̟����ɓ������B �b�\�\�ː�眈��͊փ������A�����됣�ɓܐ��^�����đ喼�ɂȂ�B�V�Ə@�т����c�ƂɎ��������̂��ː�眈��B�V�Ə@�т������F��c�ɏ]���Ċփ����ɎQ�킵�Ă�����A���ꂱ�������ł͍ς܂Ȃ��B�U�ߒׂ��ꂽ���낤�B���ǁA�O��̏��画�f���āA�V�Ə@�т͊փ����푈�̎��A�����Ȃ������B����ŁA�V�Ə@�т͗̒n�͎��������̂́A�����ł����i�j�B �`�\�\�����ǁA���̍s���l���́A�D�_�s�f�Ƃ��������A��͂�؎x�O�M�̏L��������B�����ł��Ȃ�������A���c�@�����E���āA�m�s���Ƃ́A�@�O�Ȃ��ƂɂȂ�B �b�\�\���c�����q�͔d������A�G�g��������𐿂��āA�V�Ə@�т̎����E�F�쐭���̋��́A�����S�ɎO���̗̒n���B�ނ��ȉ������邪�A��������A�؎x�O�M�҂Ƃ������C�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��ˁB�����A����������A�̂��Ƃ́A�܂������ł����Ȃ����ˁB |
|
�`�\�\�V�Ə@�т̘b�ɂȂ��ĒE�����Ă��܂������i�j�A�����̂��Ƃɘb��߂��A�������c���̍��A�̎�͐؎x�O�喼�E���c�����q�A����ɔd�B�{�{���ɋ߂����m���̈ꌏ������܂����ȁB �b�\�\�����A���Â̗̎�́A�����s���B�V���\���N�i1590�j�A�A���b�T���h���E���@���j���[�m�iAlessandro Valignano�j���A���[�}�@���ɉy�����ċA���Ă����u�V�����N�g�߁v�������A��āA�G�g�y���̂��ߏ㗌�̓r���A���Âő؍݂���B���̎��͉z�N���āA�\�ꌎ���{������قǎ��Âɂ����B�����s���⍕�c�������F�g����؎x�O�W�҂����@���j���[�m�ɉ�ɗ����B �a�\�\����ɁA���Âł́A�N��㗌�̏��┑�������A���N�g�߂����͐��m���y�����t���Ē��������Ƃ����ˁB���Â̖��ɁA�o���b�N���y�̒��ׂ���n�����Ƃ����킯���B �`�\�\�y��̓��B�I���ł��ȁB�O���S���I���̂��̂������Ƃł��傤�ȁB���̃J���`���[�V���b�N�ɁA���Â̎��ӂ���吨�����ɂ���Ă������낤�B �b�\�\���̍��A�����͎��B�d���ɋ����Ƃ���A�{�{������߂��A�����s���̗̒n�E���Â֍s���āA�ɓ��}���V���͂��ߏ��N�g�߂炪���t���鋳��y���A���@���j���[�m�̐������A���������������Ȃ��A�Ƃ����̂��A���肤�邩���A�Ƃ����\���̘b�i�j�B�����A���c�����q�⏬���s���̊W�n�Ƃ������Ƃł́A�������q���̍��A�؎x�O�M�Ƃ��̕����́A�g�߂ɂ������Ƃ������Ƃ��B �a�\�\���̂�����́A����܂ŕ����������ʼn߂��Ă��������Ƃ��B�Ƃ��ɁA�����s���̐��R�݂̂Ȃ炸�A���Â���͒��N���瓌�V�i�C�ƁA�C���^�[�i�V���i���ɐ��E���g�����Ă���B �`�\�\�w�ܗ֏��x�̕����ɂ́A�C�Ɋւ����g��b�肪����܂��ȁB���Ƃ��A�u�˂��z���v�Ƃ��B �b�\�\�����ɁA�R�ł͂Ȃ��C�̘b���o��̂́A�C�̂��ň�������炾�B�������A���Â̂悤�ȗL���ȍ`���ߏ��ɂ���������ˁB �a�\�\����ɂ��Ă��A�q���̍��A�؎x�O�����̐�������Ƃ���A���̌�̕����̎v�z�����Ȃ�Ȑ܂��������Ƃ������Ƃ��ȁB �`�\�\���������ۂɗc����������Ƃ������Ƃ́H�i�j �b�\�\�����܂ł͂���������Ȃ����낤�i�j�B�������A���c�����q�𒆐S�Ƃ��镐�������̊��������炷��A����Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B�����̐���̑����́A���̐e�̐��オ�؎x�O�����̐�����Ă���B�e�̐��オ�A���������C���^�[�i�V���i���Ȍ�ʐ��E���o�����Ă���B �`�\�\�푈���܂����́sVerkehr�t�i��ʁj���Ƃ���A�G�g�̒��N�N���̓C���^�[�i�V���i���Ȍ�ʂ̈��ł����ȁi�j�B �b�\�\����ɂ͖��f�Ȍ�ʂ����ˁi�j�B���\�̖��̎��A�����͋���B���ꂩ��A�G�g������œ��{�R�����S�P�ނ���̂́A�����\�܍̎��B������A�����������\�܍܂ł̑����ȏ��N���i�j�A���{�l�̌R�����C�O�o�����Ē��N�Ő푈���Ă������ƂɂȂ�B �`�\�\�h���X�e�B�b�N�Ȑ퍑����Ƃ͂������펞�����Ƃ������Ƃł��ȁB �b�\�\�����̐���́A���N���ɁA�C�O�N���푈�̋�C���z���Ĉ���Ă���B����������A���̃C���^�[�i�V���i���Ȍ�ʂ̎Y���̓i�V���i���Y���̍��g�B�����ăC���^�[�i�V���i���Ȋg���̌��ǂ́A�S�ʓP�ށB�G�g������ł��܂��ƁA���̐N���v���W�F�N�g�͈ꋓ�ɈӖ��������B �a�\�\���喼�́A�G�g���ǂ��܂Ŗ{�C���A�킩��Ȃ��������A������G�g�ɑւ��Ė{�C�ł��̐N���푈�̐ӔC��̂ɂȂ낤�Ƃ����҂͂��Ȃ������B �`�\�\�ŁA��������P�ނ��Ă��܂��̂����A���̊C�O�N�������{�l�Ƀg���E�}�e�B�b�N�ȉЍ����c�������Ƃ����Ɓc �b�\�\�܂����������ł͂Ȃ������B�v�����ܗ��D���Ă�������ˁi�j�B�����A�C�O�N���͔�p�Ό��ʂ������Ƃ����̂��A���ȓ_�����A�w�K������ꂽ���Ƃ��ȁi�j�B���̃C���^�[�i�V���i���Ȋg���u���͋}���Ɉނ��A�C�O�N���ō��g�����i�V���i���Y���͎c�����B �a�\�\�����̐���́A�e�̐���̃C���^�[�i�V���i���Y�����A�i�V���i���ɕ��čs���������B�������A�́u�V���v�������́u�ω��v���A�������̂܂܂ł͂Ȃ��A�D�L���̐؎x�O�M����������ʉ߂�����̂��̂ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �`�\�\����́A�_�Е��t���ċp���A�V����ʂɎE�����M���ȗ��̕����v���ł��������킯���B�؎x�O�喼���܂��̓��̐_�Е��t��j�p������A�m����Ǖ�������E�����肵�Ă���B �b�\�\�܂肾�A�퍑�̋���A���������̖��Ӗ��E�����l���I�悵���B�M�������@���ē����ɂ��m�����E�����̂��A���̗��R�͕����̓����I�����ˁB����ɑ��A�ɂ߂ėϗ��I�Ȑ؎x�O�M�̐��E�ρA�l���ς́A�����푈�ɖ�����ꂽ���m�̂���ɁA���Ȃ�e����^���Ă���B����Ƀt�@�b�V�����Ƃ��Ă̊O���������������̂��A���{�l�̐��_��g�ݑւ��Ă���B������ǂ��n�������邩�́A�����̐���̎d���������B |
 ���m�ÂƋ{�{��
*�y�t���C�X�@���{�j�z
�s�i���@���j���[�m�j�t�����i�ނ�j�ɑ؍݂��āA�������̂悤�Ɍo�߂��Ă��邤���ɁA����������Ă��āA���̎��̍`��ʉ߂��鏔��̉��������������p�ɂɂȂ����B���́i���@���j���[�m�t��s�̑؍݂Ƃ����j���Ȓ֎��ɖ�����ꂽ�ނ�́A�l�l�̓��{�l���q�i�ɓ��}���V���猭���g�߁j��A�|���g�K���l�ɑ������āA����Ɋ�B�ނ�̂قƂ�ǂ́A���@�g�i���@���j���[�m�j�̋��ւ����K�����B�����Ă��̂Ƃ��A�ނ�͓��{�l���q��Ƒ傢�ɐS������荇�������A����͐[�����h�̑̂ŁA�ނ����������ĂȂ����B����珔��́A��X�̂��Ƃɂ��Ęb���̂�Ɋ�B�i���{�l���q��́j�g���Ă����n�}��C�}�A�Ƃ�킯�V�i�ŕ`���ꂽ�傫���}���̂���߂Ē������C�^���A�̐}������Ɍ����A��s�����ǂ����o�H�⏔���A�ނ炪�����������s�s�A�Ƃ��Ƀ��[�}�\�\����͊i�ʂ悭�`����Ă����\�\���������B����͂�����������A���ɃC�^���A��������炳�ꂽ�S�~�V�i�A�X�g�����r���j�A�n���V�A���v�A�����Ĕ��ɒ��������Ђɐڂ��A�Ƃ�킯�i���q�炪�j���Ă������c����̑����ł���ߕ������Ȃ��Ƃɋ����^�Q�����B�܂��A�i���q�炪�j�D��ɂ����čI�݂Ȏ���Łi�y����j���t����l�q���݂āA�܂��܂����S���A�ނ炩�炻�̉��t�̎d�����K�����ƁA�D��S�ɋ�藧�Ă��A���t�𑱂��Ăق����Ƃ�����ɍ��肵���t�i��24�́@�t�̎��ɂ�����x�Ƒ؍݂��琶�������ʂƗ��v�ɂ��āj  Ludoico Teisera�G IAPONIAE INSVLAE DESCRIPTIO Cum Imperatorio, Regio, et Brabantia privilegio decennali. 1595 |
 �ԏ��L�G�W�n�}  �|�c�隬�@���Ɍ������s�|�c  �������|���@�O�؎s�א쒬����  ���B�I���搶�e��>
*�y���L�t
�s�\�̓����ɗ��Ă��O�N�A�ʕv����{�̉����ɓ��āA�V�ƗV�Ԃ��Ɛ����A�n�đ��l�����m��āA���{������B���ɑ��{����āA�u���l�����M���B���l�����A�B���������A���B�����߂��B�l�����ׂ�������ׂ��炸�A����ׂ����m��ׂ��炴���B�\�Z蛍J�A�V�ə|�ėT�@����B�`�̕s�Ƃ��鏊�́A���i�ݐ���嫂��A�����Ƃ����鏊�L��B�������ނ��ƕ��̔@���A�P�����邱�Ƌ��������Ƃ��B���̍����鏊�́A������l��嫂��ڂ��鏊�L��B���{�����A�t�B�ɗR�炸�A�����ɋǂ����A�ŘV�̛{�Ɏn�܂�A�ӂ̏��X�n������A���S瑂̔w�y������ȂāA�I�Ɋ�������ਂ߂��B�����Đ�ڂ̈��S�Ɉ���A��ڂ̐⏏��㈂ˁA�[���Ռw�A�ӑ{���ЁA��㊂̑ւ鏊�A���n�̍ڂ��鏊�A�_Ꝃ̕��ӏ��A�E���̐Ђ鏊���A�Q����閩�̐����̏����ɖ���܂Ŋѐ��y�t�������r���B���O�Ő́A��A�V���ߕ��S�����߁A�{��̍��{��ਂ��t *�y�ŗr�^�t �s���{�̏����́A�������ꓐ���B�����L�ʂ̂ݐ���l�S����B���{���Ƒr��Ȃ��B�L�ʓƂ�O�N�̑r���s���A�Ă������y�ђ��N�̗���D�݁A�ߕ����H�̖��Ɏ���܂ŕK�����E���N�ɕ�͂�Ɨ~���B���{�ɋ����嫂��A���{�l�ɔ�Ȃ�t  �ї��R�^�@�{�{�����M ���Ώf�} |
�`�\�\�����̐���́A������A�Ƃ��ɑv��̐�����邱�ƂŒʉ߂��Ă���B�܂�A�_�������ł��̉F����������Ă��܂����_�ł��ȁB �b�\�\�����͕��@���`���������Ă��Ȃ�����A���̎v�z�I�w�i�́A����_�őz�肷��ق�����܂����A���ǁA�����̐���̓����́A�؎x�O�M����v��ւƂ����v�z�I�V�t�g���ȁB�؎x�O�͒��z�I��ΐ_�������A����Ȓ��z�I��ΐ_�����Ŏv�z�̌n���\���Ƃ����ǖʂ��B �a�\�\�����A�����l�ł����A���̎v�z�I�������������|���ȁB��̓I�ɂ́A�ԏ��L�G���瓡�����|�Ƃ����l�����낤�B �`�\�\�����͏\�Z�̂Ƃ��A�A�n���H�R�Ƃ������@�҂Ƒΐ킵�āA�����|���Ă���B���̒A�n�̏����Ƃ����ƁA�����|�c��傾�����ԏ��L�G�ł��ȁB �b�\�\�ԏ��L�G�͍Ō�̐ԏ��喼�Ȃ��A���Ƃ͗�����B�������K���S�{�{���Y�ŁA�ԏ����t���Ƃ���A����͗���̐ԏ����ɑ��������Ƃ��A�����̎��Ƃ��낤�B �a�\�\�ԏ��L�G�́A�V���ܔN�i1577�j�G�g�̔d���N�U�̂����J�邵�č~�����āA�Ȍ�A�G�g�R�ɑ������B�I�{�Ꟁ���œ��������A�l�������푈�̌�A�V���\�O�N�i1585�j�A�n�̒|�c���ɂȂ��āA�喼�ɕԂ�炢���B����͎R���@�S�ȗ��̎R�邾�������A������K�͂ɉ��C���ċ���ɂ����̂��ԏ��L�G�B �b�\�\����ԏ����̉Ɛb�c�͒A�n�Ɉڂ�A�����炭���������̎҂�����������B�\�Z�̕������A�n�֍s���āA�H�R�Ƃ������@�҂Ə��������Ƃ���A����͐ԏ��L�G�̃��C����z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �`�\�\�������������Ă݂�ƁA�����ɂ��ẮA��قǂ̗̎�E���c�����q�̃��C���A��B�L�O�֍s�������c���̓����Ƃ̊֘A������܂����A������A���̗���̐ԏ����A�A�n�֍s�����ԏ��L�G���Ƃ̊֘A������킯�ł��ȁB���c�����q�̃��C���ł́A�؎x�O�M�A�ԏ��L�G�̃��C���ł́A��q�w�B���������v�z�I�w�i���z��ł���ƁB �b�\�\�ԏ��L�G�́A�������|�Ƃ͗���ȗ��̗F�l���ˁB���|�͔d���O�،S�א쏯�̐��ꂾ���A���͂��̓�����Ƃ̎q�����ȁB���͗����B�ǂ����āA�d���א쏯�Ȃɒ�Ƃ̎q�����������Ƃ����ƁA�퍑�̐��ŋ��͍r�p���āA���Ƃ͉����M��������A�ƂĂ����s�ł͕�点�Ȃ��B���|�̑\�c���E�זL�̂���ɂ́A���s���痣��ĂقƂ�Ǎݏ�����悤�ɂȂ����B�퍑�����畐�������ݏ����Ƃ��ȁB���̗����̍��ɂ́A�y�����Ƃƕς�ʗl�ԁi�j�B �a�\�\�V���Z�N�i1578�j�A�M�����痣�������O�؏�̕ʏ����������֎���ܕS�R�̕��m�����W�����Ƃ��A�����͂���ɉ������A�M�����ɗ^�����B�ʏ����͍א�ق��U�ߗ��Ƃ��A���E�����q�͐펀�����B���|�͒��j�łȂ���������o�Ƃ̓��A���N�̍��A����ߍ݂̑T�@�E�i�_���ɂ����̂ŁA���͏��������B �b�\�\�i�_���͑T�������A���|�͂����Ŏ������w�B���̌�A�f���̎��f�̉��ŋ��s�������֓��R����B�������T�����ɂ������炸�A���NJґ����āA��҂̓�����B �a�\�\��w�҂Ƃ��Đ�����Ƃ����̂́A���̓������|���ŏ����ȁB�ߐ����{�ɂ����āA��҂͑����y�o�������A���̂��������͂��̜��|���B �b�\�\�������|�́A�`���I�ȑT�@�̎�w����o�Ă����l�����A�؎x�O�������悭���Ă���B�����瓖���̎v�z���E�͈�ʂ艡�f���Ă���B �`�\�\�������|�͑嗤�ɓn�낤�Ƃ��āA���s���܂��ȁB �a�\�\�Ƃɂ����A�����̎�w�͌ÏL���āA�����_�����Ǝv�����炵���i�j�B�ŐV�̎�w���A���ɓn���Ē��ڊw�ڂ��Ƃ����B�嗤�ɓn��͎̂��s�������A��Ɏv�������Ȃ��@�����������B �b�\�\�G�g�̒��N�N���̂���̗��D�����͂��낢�날�邪�A�����ⓩ�H�Ƃ��������g�̐l�Ԃ����D���Ă����i�j�B�����Ē��N��q�w�̊w�ҁA������f�v���Ă����B���̈�l���I���k���傤�����A�J���n���l���ˁB�c���̖��A�쌴��̐킢�œ������Ր��ɕ߂炦���āA�ɗ\��F�֝f�v����A���ŋ��s�����Ɉڂ���ĕߎ��Ƃ��ē�ւ���Ă����B���̂Ƃ��A���|�͛I���ƒm�荇���āA�ŐV�̒��N��w�Ƀ��A���^�C���Őڂ��邱�ƂɂȂ�B �`�\�\���N�ɂƂ��Ă��A�I���l�ɂƂ��Ă��A���ɖ��f�Ȃ��Ƃ��������i�j�A�G�g�̒��N�N���ɂ���Ă������������𗬂����������B �b�\�\�𗬂Ƃ����ɂ́A����I�ȗD���ˁi�j�B�܁A�Ƃɂ����A�������N�ɂ͌�����`�I�ȃ��f�B�J���Ȏ�q�w���`������Ă����B�������|�ɂ���A�I���̊w���́A���{�̎�w�Ƃ̓��x��������Ă����B�����ŁA�F�l�ԏ��L�G�ɑ��k���āA�ނ�͐V�����̏o�Ŏ��Ƃ��v�悵���B�I����ߗ��̑N��Ɏl���܌o�̕M�ʂ��Ϗ����A����ɜ��|�̌P�_�����ďo�ł���B�땶�͛I���B�N��E�I���̎w���̂��Ƃɐ��i���ꂽ���̈�啶�����Ƃ́A�ԏ��L�G�̎��ɂ���ēڍ��������A�����̊w�␅�����͂邩�ɔ������̂������B �a�\�\�ԏ��L�G�͜��|�̖�l�ŁA�Ȃ��Ȃ������̂킩�����l�������炵���B�������|�i��I���j�ɂ��A�ԏ����i�L�G�j���A�u���{���Ƃ̎�����ӎҁA�Â�荡�Ɏ���܂ŁA�B����̊w��`�ւĖ����v��̗���m�炸�B�l�S�N���A���p�K�̕������ނ邱�Ɣ\�͂��B����Ƃ��A�v����Ƃ��B���ɜ����ׂ��v�ƌ�����Ƃ����B�ԏ��L�G�̏F���͂���ŁA�V������w�i�v��j����{�Ɍ������悤�Ƃ����B�̒n�A�n�̒|�c�鉺�ŁA�E�q�a�����݂��A�̎ߚ����������B���������_�ł́A�������{�̎�w�̍Ő�[�́A���̓������|�E�ԏ��L�G�̃��C���ɂ������B �b�\�\�w�ŗr�^�x�ɛI�����킭�A�u���{�̏����́A���Ƃ��Ƃ����ꓐ���i�j�B�����L�ʁi�ԏ��L�G�j�̂݁A�����Ԃ�l�S����B���{���Ƒr��Ȃ��v�B��ؐl�̍����Ƃ������Ƃȁi�j�B�u�L�ʓƂ�O�N�̑r���s���A�Ă������y�ђ��N�̗���D�݁A�ߕ����H�̖��Ɏ���܂ŁA�K�����E���N�ɂȂ���Ɨ~���v�B �a�\�\���{�ɋ����嫂��A���{�l�ɔ�Ȃ��i�j�B���������킯�ŁA�������x�z�����ؐl�̍��ɂ����āA������m��A���������H���Ă���H�L�Ȑl���B�悤����ɁA�����̓��{�l�̂�����������ɐ[�����ꍞ�A�����{�l�I�ȓ��{�l���ԏ��L�G�ȂB���̍L�G���A�A�n�̗̒n�ŁA�E�q�a���������A�ߚ����c��ł����B �b�\�\�A�n���c�ɂ��Ǝv���Ă���Ƒ傫�ȊԈႢ�i�j�B�ԏ��L�G�̏鉺�ɂ́A���s���i���f�B�J���ȑv��̃Z���^�[���������B�������A�n�֍s���đ��������̂́A�܂��A���{�̂ǂ��ɂ��Ȃ�����Ȓm�I�^���������B �`�\�\�w�ܗ֏��x�ɏo�Ă���A�n���H�R�Ƃ������A���́u�A�n���v�ɂ́A���������w�i������Ƃ������Ƃł��ȁB������܂��A�]���̕����������܂������ʼn߂��Ă������Ƃ��i�j�B �b�\�\�b�����ǂ��A�������A�n�ɂ����Ƃ���A�\��̍��A���łɑv��Ƃ����v�z�I�����������B���̓������|�E�ԏ��L�G�Ƃ������C���������āA���ꂪ�A�n���狞�s�ւƂ����R�[�X���ȁB �a�\�\���������s�֏o��̂́A��\��B���̋��ł́A�������|�̕����T�����������āA�����̒m�I�����I�l���́A�����ŊJ�������B�ї��R�͕�������N�ゾ���A���R�͜��|�ɓ��債���Ă��ȁB�Ⴂ���҂̑��������肦���Ƃ���A����͓������|�̃T�����ł̂��Ƃ��낤�B�����̍��ɂ��Ă��A����͂��Ȃ�|�p�I�f�{������Ƃ݂���B�����͋��s�ŊG�𑊓��ςĂ���ȁB �b�\�\�����͋��s�ŁA�g�����͂��߁u�V���̕��@�ҁv�ƕ��@����������킯�����A���̂������Łi�j�A�����������s�̕����I�|�p�I���ɐg���������Ƃ������Ƃ��B �`�\�\��������̗ї��R�́A��Ƃ��Ď�q�w�ɌX�����A�����̕��͂����ł��Ȃ��悤���B�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���|�̃G���A�ł��ȁB �b�\�\���Ԃ����낤�B�����͗��R�̂悤�Ɏ�q�w�ɏ�������������ł͂Ȃ��B�闤�Ƃ��ɁA�Ƃ��������肾�낤���A�k�v�̎��Q�k�i�Ώf�j�A���ɐ���ӂ��߂��G��I�Ȃ��̂����A���z�������邾�낤�B�������A�a���̐_����A�؎x�O�̐�ΐ_�f�E�X�������ŁA�F���Ƒ��݂�������Ă��܂��v��̗��_�A�������z�_�I���R�w�������w�itranscendental physics�j���ˁA���ꂪ�����̎v�z�̐Ґ����낤�B �`�\�\�ܗ֏��̋L�q�ɒʒꂵ�Ă���̂��A���̕����w�ł��ȁB���ď��яG�Y�́A�����̍�����`���Ŕj�������A�����܂ł͌��Ă��Ȃ��B �a�\�\����ɁA�P���̔ފ݂Ƃ��������̕����v�z�̍��{�́A������܂����Ă��Ȃ��B�����̌|�p�A���@�ł͂Ȃ����̃A�[�g�̕����́A���I�Ƃ������ϗ��I���ȁB���̗ϗ����́A�������ȑT�v�z�ł͂Ȃ��A�ނ����w�̃X�g���N�g�Ș_�����炭����̂��B �b�\�\���ꂪ����Ȃ�����A������������̐S�p�_�œǂ�ł��܂��B�����������m�Œʑ��I�ȕ����_������܂ő���������i�j�B |
|
�\�\���āA���낻��A���Ԃ��s�����Ă��܂��B����������������̂��Ƃ́A�܂��܂��b���s���܂��A����́A�����̎��㐢��̎����ɂ��āA�]�����������ł͒m���Ă��Ȃ��������Ƃ������Ō��ꂽ�Ǝv���܂��B�����̎v�z��|�p�̔w�i�ɂ��ẮA��������߂Ă��b���f�������Ǝv���܂����A�ȏ�̂悤�Ȓm�I����m���Ă������Ƃ͕K�v�ł��ˁB �`�\�\���������f���������I�Ȃ��̂Ƌߐ��I�Ȃ��́A�����ƒ����A�푈�Ƙ�A���������Δ�́A������_��������̕K�{���������A������h���X�e�B�b�N�Ȏ��_�ł͂Ȃ��A���A�W�A�̌�ʐ��E�ł̊֘A���q�ׂȂ���ˁB �a�\�\�v�z�̎����ł́A�؎x�O��V�����v�w�Ƃ̊֘A���ȁB�u�����Ƃ��̎���v�Ȃ�Č��o���ŁA�낭�Ȃ��Ƃ��������Ă��Ȃ��z����������B�Ђǂ��̂ɂȂ�ƁA�����̌�����{�w�{�{�����x�̋L���������ʂ��āA�u����Ȃ������ł������v�Ƃ���Ă���B �b�\�\����ȓڒ����Ȍܗ֏�����{�������B�悤����ɁA�c���Ɗ��i�A�����̐N���ƔӔN�ł́A�Љ�̗l�����v�z���h���X�e�B�b�N�ɕϗe���āA�����ɕ��m�̐������E�l�����������Ԃ����Ă��܂����B���̕ω��̃v���Z�X���������Ȃ��ƁA�ܗ֏��ɏ�����Ă��邱�ƁA�Ƃ��ɂ��̃N���e�B�J���ȃX�^���X���A�܂����������ł��Ȃ����낤��B |
|
�\�\�����ł����A�ܗ֏��lj��v���W�F�N�g�́A���̃T�C�g�Ŏ��{����āA���̐��ʂ����łɌ��\����Ă��܂��B�n�E���E�E���Ɛi��ŁA�Ō�̋�̊��܂ŏI��܂����B�ܗ֏��lj��́A�����������������ƌ��Ă悢�̂ł����B �b�\�\��̊��܂ł�������s�������A��������Ƃ͂܂������͂��Ă��Ȃ��B�܂��r���̒i�K�ŁA���ꂩ�猩�����Ď肪����Ƃ��낾�ȁB �a�\�\�������A���̒i�K�ł������A���������ʂ��ˁB�Ƃ��ɁA����������̊ԈႢ���A��ʂɎw�E����Ă���B����ŁA�ǂꂾ���A����������Ȍ������z���Ă��邩�A�悭�킩��ˁB �b�\�\�܂������A����������Ȗ|���Ȃ��i�j�B �`�\�\����ɁA�ܗ֏�������Ńe�N�X�g�ł��ȁB�u�����v�Ƃ܂ł͌���Ȃ�����ǁA���̃e�N�X�g�E�N���e�B�[�N�ŁA�I���W�i���̓��e�ɂ��Ȃ�߂Â����̂ł͂Ȃ����ȁB �b�\�\���������A��ʂɂ͍א�Ɩ{�����m��Ȃ�����ˁB����͂��Ȃ�E�����������A��l�̊�������ɖ{���ɕ��ꍞ�t�V�̂���Ƃ��������B���̍א�Ɩ{�Ɉˋ����Ă������A���͔������Ȃ��B���݂܂ł̂Ƃ���A�e�N�X�g�̕s���S�ƁA�|��҂̓lj�\�͂̌��@�A���ꂪ���悵�āA�Ђǂ�������ɂȂ��Ă��܂��Ă���B �a�\�\�א�Ɩ{���x�z�I�e�N�X�g�ɂȂ����̂́A��g�Ōܗ֏�����{�Ɏg���Ă��炩�B �`�\�\���ꂾ���ł͂Ȃ��A���a�����܂ŁA���̍א�Ɩ{���A���ƕ����^�M�{�ƌ��Ȃ���Ă����Ƃ������Ƃ�����܂��ȁB���������Ӓ�Ƃ����̂́A�������ӓI�ŁA����������Ȃ��̂Łi�j�A����͍������ς�Ȃ��B �a�\�\�������ȁB�Ô��p�̊Ӓ�ɂ��Ă��A�܂�Ői�����Ă��Ȃ��B����Ȋw�Z�p�������Ӓ�@�͊J������Ă��Ȃ��B�Ȃɂ��땶�w���̐l�Ԃ��Ӓ肵�Ă���B�܂�������Ȋw�I�ŁA�T�C�G���X�E�e�N�m���W�[�̃Z���X���Ȃ��B����ȏ�Ԃ��ƁA�������܂łɑ�ʐ��Y���ꂽ��삪�A���܂��^���Ƃ��āu�V�����v����邩�m��Ȃ��ˁi�j�B �a�\�\�א�Ɩ{�ܗ֏����x�z�I�e�N�X�g�A�Ƃ����́A���ꂩ�畢���K�v������B���Ƃ����āA�����ʖ{�͂ǂ��������s���S�ŁA���ׂ���������B �`�\�\��Ɩ{�̕��͂ǂ����B�������̕����א�Ɩ{���D��Ă���Ƃ����������邪�B �b�\�\������A����������Șb���B�א�Ɩ{�Ɠ�Ɩ{�A����͂ǂ�������ׂ������āA�\���S�����ˁB�����قǂ̍��ق͂Ȃ��B����́A����̈ٓ������ł͂Ȃ��A�e�N�X�g���e���\���ǂݍ��߂킩��B������A���Ƃ���A��Ɩ{�̕����D��Ă���ƌ������Ă�̂́A�܂��������m�ȏ؋����B �a�\�\���������A��앶�ɖ{���܂߂Ĕ��n�ܗ֏������m��Ȃ�����ȁB�ڃN�\�@�N�\�̗ނ��̘_�c����i�j�B �`�\�\�������ɁA���n�ܗ֏������m��Ȃ��Ƃ��������҂���ł��ȁB�悤����ɁA�A���̘_��������ƁA���܂��ɒ}�O�n�ܗ֏����悭���Ă����Ȃ��B���̒��ɂ́A�א�Ɩ{���͂��߂Ƃ�����n�ܗ֏��������݂��Ȃ��A�Ǝv������ł���i�j�B �a�\�\�}�O�n�ܗ֏��́A�܂��������Ȃ��B�ȑO����m���Ă����̂́A���R���ɖ{�����A����͏\�㐢�I�̎ʖ{���ȁB �b�\�\���R���ɖ{�́A�}�O��V���̑���n�̌ܗ֏����ȁB���a�\�N��ɂ��̑��݂��m�����g�c�Ɩ{�����邪�A����͒��R���ɖ{���Â��ʖ{�B�����}�O�n�Ƃ������ƂŁA�_�{�̓��e�͗ގ����Ă���B�ނ��A���̓�{�����ł͐S���Ȃ��B����A�}�O�n�ܗ֏��̔��@��i�߂�K�v������B �\�\�g�c�Ɩ{�́A��V���̑��`�ؕ�������ƁA�}�O��V���̗��Ԍn�ł͂Ȃ��ł����B �a�\�\�����ǁA���̑��`�ؕ��͊����N�Ԃɗ��ԑ������p�����������̂ŁA��V���̎ĔC���邪�g�c���A�ɗ^�������`�ؕ��܂łƁA�M�Ղ��Ⴄ�B����ɉ����āA�g�c�Ɩ{�̋�V���ƁA����ȊO�̎l���Ƃ́A�M�Ղ��Ⴄ�Ƃ������Ƃ�����B �b�\�\���̂�����͍���̌����ۑ�B�g�c�Ɩ{�̎j���]���́A���m�ɗ��Ԍn���ƒm���ܗ֏��@���Ă���łȂ��ƁA���Ƃ��]���Ȃ��B �`�\�\���n�ܗ֏��ɂ́A�}�O�n�̂悤�ȑ��`�ؕ����Ȃ��B���t�̏����E�N�����E�����ȂǁA�`�������܂��܁B �a�\�\�悤����ɁA���`�����Ƃ��đ̍ق��Ȃ��Ă��Ȃ��B����������n�ܗ֏��͂��ׂāA�������V��̖剺�����O�ɗ��o�����ʖ{����h�������㐢�̎ʖ{���ȁB �b�\�\�����̔��n�ܗ֏��́A�ǂ���݂ȁA�p�C���[�c�E�G�f�B�V�����i�C���Łj�Ȃ�i�j�B �a�\�\����Ȋ�{�I�Ȃ��Ƃ��m�炸�A�ܗ֏������͋���ׂ���x���Ő��ڂ��Ă����B����䂦�ɁA�ܗ֏�������Ńe�N�X�g���\�z�����K�v���������Ƃ����킯����B �b�\�\�����A�܂��ɃR���X�g���N�V�������ˁA�t���C�g���̌�̈Ӗ��Ō��������B���������e�N�X�g���Y�����Ȃ���A���������e�N�X�g���ǂ߂����ɂȂ��A�Ƃ�����ȃW�����}�ɁA��X�͓r���ŋC�Â����ꂽ�B������A���ɂ�����悤�ɁA�e�N�X�g���Y�����ǂނƂ����A�p���h�N�V�J���ȍ�������s���ꂽ�킯���B �`�\�\������A�lj����Ă̓e�N�X�g���Y���A���Y���Ă̓e�N�X�g�lj������Ƃ������t�B�[�h�o�b�N�B���������s���߂���Ȃ���A�e�N�X�g���Y���ł��Ȃ��B �b�\�\���������킯���B���̌ܗ֏��lj��v���W�F�N�g�́A�܂��������Ă��Ȃ����A�Ƃ肠�����̂Ƃ���͏o����Ƃ����i�K���B�������A�I���Ȃ����͂Ƃ������Ƃ����_���͂ɂ���悤�ɁA���̓lj����I���Ȃ��lj���������Ȃ����ˁB |
 �א�Ɩ{  ��Ɩ{ 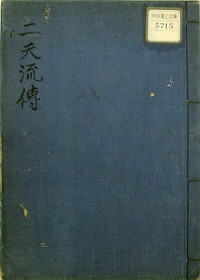 ���R���ɖ{  �g�c�Ɩ{ |
|
�\�\���������ɂ����Čܗ֏��lj��͕s���̍�Ƃł��B���̈Ӗ��ŁA����Ȃ錻����ł͂Ȃ��A����߂ďڍׂȘ_�����W�J����Ă���A���̌ܗ֏������ɔ䌨��������̂́A����܂ŏo�����Ă��Ȃ������B����͑傢�ɐ�`���Ă悢���Ƃł��傤�B�Ƃ���ŁA�ǂ���炨���Ԃ��܂���܂����B����́A�\�ɕ��k����đ傢�ɒE�����܂������i�j�A����́A�O��ɑ����āA�����{�̘_�]�����肢�������Ǝv���܂��B����ŁA�������ł��傤���A���N�͑�̓h���}�������ċ{�{�����̓�����N�Ƃ������ƂŁA��ɂ���ĕ����{�������o�ł���܂����̂ŁA�������ʂ�_�]����Ƃ������Ƃł́B �`�\�\���H�@����̕����{�u�[���ŏo�����̂ɂ́A���N�Ȃ��̂��Ȃ���B�֏�{�ȊO�ɁA�_�]�ɒl����{�����������ˁB �\�\�������A����͏��m�̏�B�ł�����A�O���]���Ă��������܂��B�����Ƀ��X�g��p�ӂ��Ă��܂�����A�Ƃɂ����ǂ�ł��������āA����������\�肵�Ă��܂�����A�W�܂��č��]���Ă������������̂ł��B �b�\�\�����A�Ђǂ����ƂɂȂ����Ȃ��i�j�B �i2003�N12���g���j
|