 |
坐談・宮本武蔵 播磨武蔵研究会萬珍放談会 |
|
| 生國播磨の武士、新免武藏守藤原玄信、年つもりて六十。我若年の昔より兵法の道に心をかけ、十三歳にして始て勝負をす。其あひて新當流有馬喜兵衛と云兵法者に打勝、十六歳にして但馬國秋山と云強力の兵法者に打かち、二十一歳にして都へのぼり、天下の兵法者に逢、数度の勝負を決すといへども、勝利を得ざると云事なし。其後國々所々に至り、諸流の兵法者に行合、六十餘度迄勝負をすといへども、一度も其利をうしなはず。其程、年十三より二十八九迄の事也。 (五輪書・地之巻) |
| 06 | 武士道以前・武士道以後 | Back Next |
Go Back to:
目次
|
――今年(二〇〇四年)ももう師走で、押し詰まってきました。早いもので、もう年末です。我々の武蔵サイトも発足以来二十二ケ月で延べアクセス数が十万を超えました。内容が他の武蔵関係サイトとは水準が違う、という評価もありまして、異例のアクセス頻度になっているようです。さて今回で、この坐談武蔵は六回目になりますね。いろいろ話題は多いのですが、どんなお話をお願いしましょうか。 A――もうイラク戦争の話はやめよう(笑)。日本人青年が斬首されたようだが、それを話し出すと切りがない。 C――今年は台風が変で天候異常だった。地震でも来るのじゃないかと、言っておったら、先月新潟で地震があった。これから寒くなって、気の毒なことだ。 D――地震といえば、阪神大震災からもう十年か。早いものだ。 B――あの時いろいろあったなあ。六千人以上も亡くなったし、けがをした人も膨大な数だった。それでも、皆さんちゃんとやって来られた。神戸には震災の跡形もない。 C――それがいいのだか、悪いのか。あのとき一瞬開いた秩序のクレバス、それをのぞきこんでしまった人もたくさんある。忘れちゃいかんことも、たくさんある。 B――忘れちゃいかんことは忘れたいものだ。しかし、忘れたいけれど、忘れちゃいかんのだね。 ――そういうことです。忘れていたことも不意に思い出したりします。で、今回の「坐談武蔵」の話に入りたいのですが。 B――毎年のことだが師走になると、TVは忠臣蔵をやっているね。「12.8」の真珠湾奇襲=日米戦争開戦は忘れても、忠臣蔵は忘れない(笑)。 C――忠臣蔵は近世人気の定番になった。明治以後も人気のドラマだが、まだそれが続いている。これは興味深いことだね。しかし、忠義というテーマに惚れているのではなく、一種のカタルシスだね。 B――とくに師走、年末だから。こういうカタルシスのドラマは、年末の恒例行事になりうる。カタルシスというのは、つまり清算だから。清算というのは、借りを返す、貸しを返してもらうことだ。 A――清算、決算。要するに、オトシマエをつけることですな(笑)。 B――借りを返すということでは、自分たちの負債感情があった。貸しを返してもらうということでは、これは吉良の首を取るという行動だね。だから、貸しを返してもらうことではじめて借りを返せるということだね。 D――しかし、その貸しというのは、本来は公儀への貸しだね。喧嘩両成敗が暗黙の大法なら、喧嘩の両方ともに切腹である。それを、浅野だけを切腹させたのは、片手落ちだ、不公平だというのが、当時世論の一般的見解だね。 B――その喧嘩両成敗の「喧嘩」だが、これは口論だけでは喧嘩ではない。同じ暴力沙汰でも、取っ組み合いするだけでは喧嘩ではない。刃傷という殺傷行為に関わる。 D――もちろん喧嘩というのは、私闘だがね。そういう私闘を抑制するために、是非裁判するよりも、喧嘩すれば両方とも死罪だぞ、というわけだ。だから喧嘩両成敗のルールは、なぜ浅野(内匠頭長矩)が刃傷に及んだのか、そういう理由を問うようなことはしない。 A――となると、喧嘩両成敗というのは裁判権の放棄ですか。 C――裁判権の放棄というよりも、本来はもっと武断的だね。要するに、暴力は敵に対して行使しろ、内輪で喧嘩するな、そんなことをすると、裁判以前に両方とも切腹だぞ、という私闘抑圧だね。こういうのは戦国の掟だ。 B――そうなると、吉良(上野介義央)が手向いしなかったから、これは喧嘩ではない、という理屈だな。 D――喧嘩というのは、双方が暴力を行使してはじめて喧嘩だ。片方が、じっとこらえて堪忍した場合、喧嘩両成敗の原則は、堪忍した方は罪には問わないことになっている。ゆえに、吉良はお咎めなしという当初の裁きだ。 A――どういう経緯でこうなったか知らないが、とにかく吉良は仕懸けられた喧嘩を回避した。とすると、これは喧嘩両成敗以前というわけかね。 C――これは喧嘩ではない。となると、喧嘩両成敗のルールは適用されず、浅野が一方的に悪い、という結論だね。そうなると、周囲が黙っていない。そもそも、これは喧嘩なんだ、とすれば、喧嘩両成敗のルールを適用しないのはおかしい、納得できないという意見が出てくる。 B――喧嘩か、そうでないか、その前提のところで食い違っている。 C――結局、浅野だけを切腹にした処罰が片手落ちだ、というのは世論だね。しかし、それは口舌の批判でしかない。浪士たちが本所の吉良邸へ討ち入って吉良の首を取った、その行動こそが批判だった。 B――というか、むしろ、それが期待されてしまっていたのだね。期待したのは世論だし、まだやらないのか、いつまでクズクズしているのか、早くしないか、というほどだった。 A――そうなると、応援どころか、プレッシャーだね。やらないわけにはいかない(笑)。 D――そこで、重要なのは、喧嘩にならなかった不発の喧嘩を喧嘩にして、喧嘩両成敗に持ち込むことなんだ。浅野は梶川(与惣兵衛)に組み敷かれて無様にも喧嘩にできなかったが、浅野遺臣らが吉良を殺してはじめて、喧嘩になった。主君の遺恨を晴らすというのは、理解しやすい話だが、これは不発の喧嘩を、喧嘩に昇格させたということなんだ。 C――たしかにね。討入りというアクティング・アウトがあって、公儀の裁きは、ようやく吉良家断絶へ動いた。浅野・吉良両人が死に、浅野家も吉良家も御家断絶、という結果だね。これで喧嘩両成敗となる。 |
  仮名手本忠臣蔵 三段目
*【丁末日記】
《拙者儀、今日伝奏衆へ 御台様よりの御使を相勤候間諸事宜様頼入由申、内匠殿、「心得候」とて本座へ被帰候。其後御白書院の方を見候ヘハ、吉良殿御白書院の方より来り被申候故、又坊主ニ呼ニ遣し、吉良殿へ其段申候ヘハ、承知の由にて此方へ被参候間、拙者大広間の方へ出候て、角柱より六七間もあるへき所にて双方より出合、互に立居候て、今日御使の刻限早く相成候義を一言二言申候処、誰哉らん、吉良殿の後より、「此間の遺恨覚たるか」と声を懸、切付申候。其太刀音ハ強く聞候得共、後に承候へは、存の外切れ不申、浅手にて有之候。我等も驚き見候へは、御馳走人の内匠頭殿也。上野介殿、「是ハ」とて、後の方江ふりむき被申候処を、又切付られ候故、我等方前へむきて逃んとせられし所を、又二太刀程切られ申候。上野介殿、其儘うつむきに倒れ被申候。吉良殿倒れ候と大方とたんにて、其間合ハ二足か三足程の事にて組付候様に覚申候。右の節、我等片手ハ、内匠殿小刀の鍔にあたり候故、夫共に押付すくめ申候》 《内匠殿をハ、大広間の後の方へ、何も大勢にて取かこみ参り申候。其節内匠殿被申候は、「上野介事、此間中意趣有之候故、殿中と申今日の事旁万恐入候得共、不及申是非打果候」由の事を、大広間より柳の間溜御廊下杉戸の外迄の内に、幾度も繰返被申候。其節の事にてせき被申候故、殊の外大音にて有之候。高家衆はしめ取かこみ参候中、「最早事済候間、たまり被申候へ、余り高声にていかゝ」と被申候へハ、其後は不被申候》 《時計の間の御次へ参り候ヘハ、豊後殿相模殿、佐渡殿、丹波殿、大和殿、対馬殿、伯耆殿、其外大目付衆も御列座にて、先刻の一件御尋有之候付、初中終之趣逐一に申上候。其後相模殿御申ニハ、「上野介手疵の義ハ如何程の事に候哉」と御尋故、二三ケ所にて可有之、尤深手にてハ有之間敷旨申上候。豊後殿御申ニハ、「上野介事、其節刀に手をかけ或ハ抜合せなと致し候哉」と被仰候。拙者見及候へ共、帯刀に手ハ懸不申候段申上候》 |
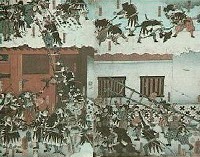
*【多門伝八郎覚書】
《四ツ半時頃 殿中大騒動いたし、御目付部屋江追々為知来ル。只今松之御廊下ニ而喧嘩有之、及刃傷候趣、相手は不相知候へ共、高家吉良上野介殿手疵を被負候由、申来候間、早束〔速〕同役衆不残松之御廊下江罷越候処、上野介ハ、同役品川豊前守伊氏被抱、桜之間方近き御板縁にて、前後不弁高声ニ而、「御医師相頼度」と言舌ふるへ候而被申聞候。松之御廊下角より桜之間之方江逃被参候趣故、御畳一面血こほれ居候。又かたハらにハ、面色血はしり浅野内匠頭、無刀ニ而、梶川与三兵衛〔頼照〕ニ組留られ、神妙体ニ而、「私義、乱心ハ不仕候。御組留之義は御尤ニは御坐候へ共、最早御差免可被下候。ケ様打損し候上は、御仕置奉願候。中々此上無体之刃傷不仕候間、手を御放し、鳥帽子を御着せ大紋之衣紋を御直し、武家之御法度通被 仰付度」旨、被申候得とも、与三兵衛、不差免候故、内匠頭、「拙者義も五万石の城主ニ而御座候、乍去御場所柄不憚之段は重々恐入奉候へ共、官服を着候者、無体之御組留ニ而は官服を乱し候。上江対し奉何之御恨も無之候間、御手向は不仕候。打損し候義残念ニ而ケ様ニ相成候上は致方無之」と能々事を分ケ被申候へ共、与三兵衛、畳江組伏セねぢ付ケ居候ニ付…》 《「其方義、御場所柄不弁、上野介江及刃傷候義、如何之心得候哉」と最初伝八郎申渡候処、内匠頭一言之申披無之、「上江奉対聊之御恨無之候へ共、私之遺恨有之、一己之宿意ヲ以、前後忘却仕可打果と存候ニ付、及刃傷候。此上如何之御各被 仰付候とも御返答可申上筋無之候。乍去上野介を打損し候義いかにも残念ニ奉存候。浅疵ニ御座候ニ付上野介ハいかゝ相成候哉」と内匠頭〔相尋候ニ付伝八郎〕返答いたし候、「浅疵ニ而有之候得共、老年之事、殊ニ面体之疵所ニ付、養生も無心元」と返答いたし候処、内匠頭、顔色歓之体ニ相見江申候而、「外ニ可申上筋無之奉恐入候、御定法通御仕置被 仰付可被下候」と斗ニ相答候》  吉良邸跡 |
A――それは公儀が、浅野だけを切腹させたことの過失を認めたというじゃない。 B――そうなんだ。当時の当事者の意識ではなく全体のプロセスをみれば、それはまるで、大文字の〈他者〉である公儀が、討入り実行を待っていたかのような成り行きだね。 A――Che voui? 汝なにを欲するや(笑)。 B――当初の裁きは、最終的な裁きではなかったというよりも、むしろまだ喧嘩は終ってないだろ、という一種の挑発だな。 C――そして、なすべきことは、わかっているだろうな、ということだな。問題は、このなすべきことをせよという命令を、だれが受け止めたか、ということだね。それは浅野の弟・大学ではなく、家臣たちだった。 B――問題はそこなんだ。もしこれが仇討ちだとすれば、当然弟の大学長広がすべき行動なんだ。兄の仇を討つのは弟なんだ。しかし弟はしなかった。これは閉門されてできなかったのではない。もともと、仇討ちという論理はなかったからなんだ。 A――たぶんね。仇討ちなら、浅野を死なせたのは公儀だから、公儀に対し復讐しなければならない(笑)。 B――太宰春台あたりは、浅野を殺したのは公儀だ、異議があるなら赤穂城に立籠もって切腹でもすべきものを、事件被害者の吉良を襲うとは、筋違いだというわけだ。 D――だから、仇討ちという論理からすれば、吉良を殺すのは筋違いなんだ。吉良を殺すのは、不発に終った喧嘩を実現することだね。もし浅野に遺志というものがあったとしたら、それなんだ。 C――たしかに、浅野は吉良の傷がどうかと、気にしてしきりに問うね。やってしまった以上、殺さねばならない。もしそうでなかったら、これは死んでも死に切れない。ただし、恨みが晴らせなかったということではない。相手を死なせる、それが喧嘩の作法だから。 D――喧嘩というのは、相手を殺すことだね。止めをささなければいけない。喧嘩して、相手を傷つけただけで、その場を去るのはいけない。不始末である。たとえば、喧嘩して逃げる。そしてどこかに第三者の屋敷に駆け込む。喧嘩なら駆け込んできた者を助けてやる。ただし、そのとき聞くのは、相手を確かに殺したか、止めをさしてきたか、ということなんだ。たしかに止めをさして死なせたという言質を得てはじめて、駆け込みを認める。そうなると、追っ手が来ても追い返す。その後きちんと逃がしてやる。そういう保護慣行があった。 C――だから、仕損じた浅野がしきりに吉良のダメージを気にしたのは、これが喧嘩になるかならぬか、その瀬戸際だったからだ。彼が一番恐れたのは、吉良を殺せず、この喧嘩が未遂という不始末に終ることなんだ。 B――たぶん浅野を怒らせアクティング・アウトさせるような諍いが吉良との間にあったのだろうが。大名だって、一人の武士なんだ(笑)。家臣の生活や何やら後先を考えず、ただ武士の一分を立てようとするわけだ。吉良の傷はどうだ、おれは吉良に致命傷を負わせることができたのか、それが最大の関心事なんだ。 D――浅野が梶川に組み敷かれて言ったのは、「おれも五万石の大名だ、この期に及んでジタバタすることはない。おいおい、そんなにすると官服が乱れるじゃないか、離せよ」(笑)。浅野は冷静だよ。 A――アホな精神科医が、内匠頭は心神喪失だの分裂症だったのと書いておるが、それこそ馬鹿だな(笑)。 B――精神科医の言説には厳しくすべきだよ。連中は何もわかっちゃいない。 C――そういう意味では、浅野は古典的な武士を演じている。 B――古い言葉では「男道」、つまりいわゆる武士道が立つかどうか、という問題だね。同じく大石(内蔵助良雄)ら旧家臣の行動にしても、御家再興が叶うならよいが、もしそれができなければ、こちらも黙ってはいない、ということだったろうね。 D――結局これは、主従関係は公儀との関係に優先する、ということだね。幕府が何と言おうと、自分の主人の命令がなければ動かない。逆に、主人の命令なら、公儀と対立することもある。公法が私的関係に優先する普遍的な力をもつことはなかった。 A――そうして連中は実際に吉良の首を取った。それができたのは、幕府の方にも本気でそれを阻止する気がなかったようですな。 B――たしかに、そんなフシがあるな。だいたい、大石が江戸へやって来るのも阻止しない。大石は単独潜入ではなく、十数人ほどの団体旅行だぜ、名を偽ってはいるが、見て見ぬふりをしたことはまちがいない。 C――討入り当時、吉良の屋敷は本所だが、その前は呉服橋だな。この呉服橋のとき、隣人が屋敷替えを願い出ている。要するに、いつ赤穂浪人どもが襲撃してくるか分からない。物騒なので吉良の隣は御免蒙りたい(笑)。 A――吉良は、かわいそうに、村八分状態(笑)。吉良が隠居して引っ越した本所松坂町の屋敷の隣人たちも、迷惑だと思っていただろう。 C――連中も、いつか襲撃があるだろうと予測している。襲撃があった後でも、「火事があったみたいに騒いでいたようだが、そのうち静かになった」としか言わない。他家の屋敷内のことは不介入だが、これじゃあ、あんまり吉良に同情がなさすぎる(笑)。 D――もし駆け込んできたら、保護しなければならない。その用意はあったと思うが。だから、「火事があったみたいに騒いでいたようだが、そのうち静かになった」とは白々しい(笑)。しかし公式の証言としては、それでいいんだ。 B――要するに、赤穂事件の討入りに関しては、見て見ぬふりという環境条件があった。でなければ、準備段階で簡単に事前摘発されただろう。期待されたことを連中は実行した。まさしくそれが、劇場的事件たるゆえんだね。 |
|
――赤穂事件の話が出ましたので、今回は武士の生き方というか、武士道にテーマを絞らせてもらうのはいかがでしょうか。武蔵も「武士の道」という表現を使っていることですし。 B――どうだろうね。武蔵のいう「武士の道」は、後世のいわゆる武士道とは違う。荻生徂徠あたりの世代になると、そういう古い武士の行動を否定する。武士道なんてのは戦国の風俗だという――《武士道と云は大形は戦国の風俗也》(太平策)。ところが戦国時代には「武士道」という言葉はない。となると、武士道というのは、後世の人間が戦国武士に投影した一種の幻想だということになる。 C――結論を言えば、そういうことだろう。武士道に何か実体があるわけではない。それに、今日の我々が使う武士道という言葉は、どうも新渡戸稲造が捏造した武士道イメージに汚染されている(笑)。 A――新渡戸稲造の『武士道』(BUSHIDO: The Soul of Japan )は、明治三十二年(1899)病気療養のために渡米中、執筆してアメリカで出版したものだが、有名になりすぎた(笑)。大統領のルーズヴェルトまで読んで、知人に読めといって配ったらしい。 C――という話は、本書の解説本ならどれでも書いているが、実はそれは「ある信頼すべき筋からの報知」(第十版序)でね、それが事実かどうかわからんよ。だが、もっと重大なのは、これが近代の武士道イデオロギーの典拠となったところだ。 D――しかしだね、新渡戸が言うようなこと、つまり、――過去の日本は武士の賜である。彼らは国民の花たるのみでなく、その根であり、善き賜物は彼らを通して流れでた。自己の模範によってこれを指導したとか、武士は民族全体の善き理想となった。いかなる思想の道も、武士道より刺激を受けざるはなかった。知的ならびに道徳的日本は直接間接に武士道の所産であった、――とかいうのは、事実ではない。 B――むろん、すでに明治三十四年に、その新渡戸の武士道に対し、津田左右吉は、歴史的事実とは言えないとしている。もちろん、それは当っているが。 A――津田左右吉が読んだのは英文の方だろう。最初の日本語訳(桜井鴎村訳・明治四十一年)はまだ出ていない時期だ。原著はフィラデルフィアで出たが、その翌年――つまり明治三十三年――日本でも英文『武士道』(裳華房版)が出版されているから。 D――津田は、新渡戸の武士道概念は根拠薄弱と見ている。一番の問題は、武士道をまるで日本人全体の思想みたいに言うが、武士というのはある特定階級の人間たちのことであって、そういう特殊な階級の思想である武士道を、「ソウル・オブ・ジャパン」だというのは間違っている、というわけだね。 A――そのBUSHIDOの冒頭、《Chivarly is a flower no less than indigeneous to the soil of Japan than its emblem, the cherry blossom.》とある。そもそも、Chivarly(騎士道)がなんで武士道と姉妹関係なんだ、という反発があろうさ(笑)。津田が目くじらを立てたと思われる箇処は、
《武士道はその最初発生したる社会階級より多様の道を通りて流下し、大衆の間に酵母として作用し、全人民に対する道徳的標準を供給した。武士道は最初は選良の栄光として始まったが、時をふるにしたがい国民全般の渇仰および霊感となった。しかして平民は武士の道徳的高さにまでは達しえなかったけれども、「大和魂」は遂に島帝国の民族精神を表現するに至った。もし宗教なるものは、マシュー・アーノルドの定義したるごとく「情緒によって感動されたる道徳」に過ぎずとせば、武士道に勝りて宗教の列に加わるべき資格ある倫理体系は稀である。本居宣長が
D――ようするに津田が言うのは、武士道を大和魂と混同するな、特殊な階級的思想を日本の魂だと一般化するな、ということ。しかし、この点は、明治のナショナリズム勃興期では「武士道」という言葉がまだ定着していない、そういう状態を証言しているな。敷島の大和心を人問はば 朝日に匂ふ山桜花 と詠じた時、彼は我が国民の無言の言をば表現したのである。 しかり、桜は古来我が国民の愛花であり、我が国民性の表章であった。特に歌人が用いたる「朝日に匂ふ山桜花」という語に注意せよ。 大和魂は柔弱なる培養植物ではなくして、自然的という意味において野性の産である。それは我が国の土地に固有である。その偶然的なる性質については他の国土の花とこれを等しくするかも知れぬが、その本質においてはあくまで我が風土に固有なる自発的発生である。しかしながら桜はその国産たることが、吾人の愛好を要求する唯一の理由ではない。その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない》(矢内原忠雄訳) B――後年になって、新渡戸自身は、「武士道」というのは自分が造った言葉だ、と言っている。「武士道」という言葉が、少なくとも近世初期に登場し、それ以後一部で用いられてきたという事実を知らずに使ったと言うね。 D――近いところでは、幕末・明治初期に武士道という語の用例はある。若くして渡米した新渡戸だが、それを知らなかったわけはあるまい。武士道という語は自分の造語であるというのは、どうも後年の韜晦だね。新渡戸稲造の『武士道』の内容には、はじめから批判がかなりあったし、本人もそれを承知だから、自分の造語だというのが、批判を挫くにはよい戦術だ。 A――クリスチャン・ブシドーだという評言もある(笑)。 B――そのクリスチャン・ブシドーは、内村鑑三がそうだ。自分は武士の家に生まれた、それゆえ私は戦うために生まれた、というのが、『余はいかにしてキリスト教徒になりしか』の冒頭だ。 C――「私は戦うために生まれた」というのは、なかなかのキャッチコピーだ。これこそ武士道のテーゼじゃないかね(笑)。 B――クリスチャン・ブシドーというのは、キリスト教というよりプロテスタントの倫理だね、このプロテスタントの倫理で武士道を理解する路線だ。内村鑑三の『余はいかにしてキリスト教徒になりしか』も新渡戸の『武士道』も英文で書かれて、欧米のキリスト教徒に読ませる本だよ。そもそも日本人向けの本じゃない。 A――だから、新渡戸の『武士道』を日本人が批判するというのは、どうも筋が違う。これは、日本人なんて訳の分からない民族を理解する啓蒙的入門書、というか一種の人類学的資料だね(笑)。異国人が無知と偏見をもってトンチンカンな解説をするよりもマシだ、という程度のことだ。 B――なかでも切腹などという、西洋の眼から見れば人類学的奇習としか言いようのない行為を説明しなければならなかった。相手に理解させるには、相手の土俵で説明する必要がある。というわけで、騎士道という観念を援用するし、そしてプロテスタントの倫理だね。新渡戸武士道が武士の倫理的側面を強調するわけだ。 D――ところが、日本人そのものが、こんどはクリスチャン・ブシドーの論理で武士道を理解するようになった。これは一種の逆立だね。 A――逆立も逆立、まったくの逆立だな。かくして武士道という近代的観念が生まれた。だから、その武士道なる観念の母体はプロテスタンティズムだよ。とてもじゃないが、国産とは言いがたい(笑)。国粋主義からすれば異教が自分のど真ん中に居座っている形だ。 C――エイリアンみたいにね(笑)。禅仏教をカリフォルニア経由で逆輸入するのと似ている。戦後においても新渡戸の『武士道』がロングセラーになっておるというのも、このモダンな武士道が更新されているということだろう。 |
 新渡戸稲造(1862~1933)
*【新渡戸稲造】
《過去の日本は武士の賜である。彼らは国民の花たるのみでなく、またその根であった。あらゆる天の善き賜物は彼らを通して流れでた。彼らは社会的に民衆より超然として構えたけれども、これに対して道義の標準を立て、自己の模範によってこれを指導した》 《武士は全民族の善き理想となった。「花は桜木、人は武士」と、俚謡に歌われる。武士階級は商業に従事することを禁ぜられたから、直接には商業を助けなかった。しかしながらいかなる人間活動の路も、いかなる思想の道も、或る程度において武士道より刺激を受けざるはなかった。知的ならびに道徳的日本は直接間接に武士道の所産であった》(『武士道』矢内原忠雄訳)  津田左右吉(1873~1961)
*【津田左右吉】
《先づ攷究せざるべからざるは「武士道」といへる語の意義なり。著者〔新渡戸〕は通篇毫も歴史曲観察を下さゞれば、其の歴史上の起源と變遷とに開して何様の見を持するかを知らずと雖も、余はこの小冊子の表紙に描寫するところを見て、早く既に著者の誤見を抱けることを發見せり。Soul of Japanとは幾様にも解釋せらるぺけれど、「朝日に匂ふ山櫻花」の光景を畫きて之に配したるを見れば、こは極めて「大和魂」の義たること明かなり。大和魂の語、また其の定義を知ること易からずして、平安時代の昔に用ゐられしより、宣長のこの有名なる詠歌に至るまで、必ずしも常に同一の義に使用せられざりきと雖も、この語はもと武士の間より生出せしものにあらずして、また戦國時代にありては聞くこと甚だ稀なるが如く、國民の統一せられて外國と封立せるに至り、始めて其の精神に自覺せられ來りしもの、其の國民的思想の表徴にして、多く對外的意味を含蓄せるは、むかし漢才に對して和魂と稱し、宣長が常に「からだましい」に對して之を用ゐ、或は維新前の壮士が「蒙古の使斬りし時宗」と喝破せしを見ても知るべきに似たり。之に反して武士道は一の階級的思想なり。また毫も其の間に對外的意味あるを認めず。兩者の混同はまづ武士道の意義に於いて第一着の謬見に陥りしものにあらざるか》(「武士道の淵源に就いて」明治34年)  内村鑑三(1861~1930)
*【内村鑑三】
《私の家は武士階級に属した。それゆえ私は戦うために生まれたのであり、揺籠のうちから生くるは戦うなりだった》(『余はいかにしてキリスト教徒になりしか』 ) |
|
*【新渡戸稲造】
《封建時代の末期には泰平が長く続いたため武士階級の生活に余暇を生じ、これと共にあらゆる種類の娯楽と技芸の嗜みを生じた。しかしかかる時代においてさえ、「義士」なる語は学問もしくは芸術の堪能を意味するいかなる名称よりも勝れるものと考えられた。我が国民の大衆教育上しばしば引用せられる四十七人の忠臣は、俗に四十七義士として知られているのである。 ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて、この真率正直なる男らしき徳は最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞讃したるところである》 《嫉む神を信じたるユダヤ教、もしくはネメシスをもつギリシヤ神話において、復仇はこれを超人間的の力に委ねることをえたであろう。しかしながら常識は武士道に対し倫理的衡平裁判所の一種として敵討の制度を与え、普通法に従っては裁判せられざるごとき事件をここに出訴するをえしめた。四十七士の主君は死罪に定められた。彼は控訴すべき上級裁判所をもたなかった。彼の忠義なる家来たちは、当時存在したる唯一の最高裁判所たる敵討に訴えた。しかして彼らは普通法によって罪に定められた、――併し民衆の本能は別個の判決を下した、これがため彼らの名は泉岳寺なる彼らの墓と共に今日に至るまで色みどりにまた香ばしく保存されている》(『武士道』)
*【軍人勅諭】
《我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある。昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ、中〔つ〕國のまつろはぬものともを討ち平け給ひ、高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより、二千五百有餘年を経ぬ。此間世の樣の移り換るに随ひて、兵制の沿革も亦屡なりき。古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて、時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと、大凡兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき。中〔つ〕世に至りて、文武の制度皆唐國風に傚はせ給ひ、六衛府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは、兵制は整ひたれとも、打續ける昌平に狃れて朝廷の政務も漸〔く〕文弱に流れけれは、兵農おのつから二に分れ、古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士となり、兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し、世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち、凡七百年の間武家の政治とはなりぬ。世の樣の移り換りて、斯なれるは人力もて挽囘すへきにあらすとはいひなから、且は我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り、淺間しき次第なりき。降りて弘化嘉永の頃より、徳川の幕府其政衰へ、剩〔へ〕外國の事とも起りて、其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは、朕か皇祖仁孝天皇・皇考孝明天皇、いたく宸襟を惱し給ひしこそ、忝くも又惶けれ。然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初、征夷大将軍其政權を返上し、大名小名其版籍を奉還し、年を經すして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。是文武の忠臣良弼ありて、朕を輔翼せる功績なり。歴世祖宗の專〔ら〕蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも、併〔ら〕我臣民の其心に順逆の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれ。されは此時に於て兵制を更め、我國の光を耀さんと思ひ、此十五年か程に陸海軍の制をは今の樣に建定めぬ。夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは、其司々をこそ臣下には任すなれ。其の大綱は朕親〔ら〕之を攬り、肯て臣下に委ぬへきものにあらす。子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ、天子は文武の大權を掌握するの義を存して、再〔ひ〕中世以降の如き失體なからんことを望むなり。朕は汝等軍人の大元帥なるそ。されは朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰きてそ、其親〔み〕は特に深かるへき。朕か國家を保護して上天の惠に應し、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも、汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし。我國の稜威振はさることあらは、汝等能く朕と其憂を共にせよ。我武維揚りて其榮を燿さは、朕汝等と其譽を偕にすへし。汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の保護に盡さは、我國の蒼生は永く太平の福を受け、我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし》(明治15年陸軍省 達乙第二号 1月4日) |
B――ところが(昭和の)戦争中となると、武士道は鼓吹されたが、半面では、否定された。というのも、武士道なんて封建道徳だ、自分の殿様だけに対する忠義だ、天皇・皇室に対する忠誠じゃない、というわけで、蹴っ飛ばす(笑)。 A――大義ではなく「小義」だというわけだ。赤穂義士なんて人気のあるテーマだって、その線で否定した。山本周五郎の話だが、戦争中の昭和十八年、連載中の『赤穂浪士伝』を途中で中止させられたということだ。 C――それがファシズムだね。とくに大政翼賛会や国民精神(文化)研究所あたりでのさばっていた学者連が、武士道や赤穂義士を否定してかかった。武士道とファシズムは相容れない。そのことに注意する必要がある。 B――ファシズムは、近代の超克という形態のモダニズム運動。武士道など封建思想だとして否定するのは当然だ。そうして戦後、武士道はサバイバルした。しかしモダニズムの運動という点は一貫している。新渡戸の『武士道』は岩波文庫やその他数種の文庫本でいまだにロングセラーだよ。 A――赤穂事件のことは、この本にも書いてあったな。《この真率正直なる男らしき徳は最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞讃したるところである》と、これは手放しの賞賛ぶりですな(笑)。 D――しかし、《封建時代の末期には泰平が長く続いたため武士階級の生活に余暇を生じ、これと共にあらゆる種類の娯楽と技芸の嗜みを生じた。しかしかかる時代においてさえ》というから、この「封建時代の末期」というのは、元禄時代のことだろう。だけど、元禄時代が封建時代の末期とは言えない。むしろ中期というべきだろう。 B――それにだ、《ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて》というのは、かなり変だな。前から続く文脈からすると、この時代は元禄時代を指すように読める。だとすれば、「ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代」ではありえない。それは戦国時代のことだ。 A――あれこれ言い出すとキリがない。そういう本だ(笑)。 C――ここでいう「復仇」という日本語に、新渡戸は《redress》という英語を使う。復仇が敵討、つまり復讐だとすれば、《revenge》だな。あるいは《vengeance》か。しかし、《redress》は復讐とは少し意味がズレる。語義としては、矯正する、損害を取り返す、回復する、一掃する、苦痛や欠乏を軽減する、和らげる、救済する…まあ、こんなニュアンスを含む。 D――だとすれば、ストレートな「リベンジ」よりはよい。意味内容は正確ではないか。損害を取り返す、回復する、というのは正しいし、救済するというのも、敵討の意味としてはありうる。 A――いい意味での超訳ですな(笑)。 B――だろうね。新渡戸の『武士道』は世紀末から新世紀への変り目に出たが、これが日本のナショナリズムがどっと出た時期だった。清国に勝って、こんどはロシアだというので、盛り上がっていた。で、軍人精神はいかに武士道と絡むか。 C――近代天皇制と武士道という問題では、軍人勅諭があるね。これは明治十五年(1882)正月の発布だが、そこで天皇の統帥権を歴史的に位置づけている。それによれば、武家政権の時代は、「兵馬の権は、一向にその武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱と共に政治の大権もまたその手に落ち、およそ七百年の間武家の政治とはなった。世の様が移り換って、こうなってしまったのは人の力で挽回できることではないとはいえ、我が国体にもとり我が祖宗の御制に背く、これは浅間しき次第なりき」といって、まさに非道の時代だったとする。 A――再び中世以降の如き「失体」、国体喪失という失態なからんことを望む、と言うね。《朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、その親しみは特に深かるべき》、宜しく頼むぞ、というわけだ。 D――中世・近世の将軍は武家の棟梁だった。近代のいま、天皇は軍人たちの「頭首」だと宣言した。統帥権云々の制度的問題はあるが、天皇はカシラなんだよ。実に明解じゃないか(笑)。 A――そこで、天皇制は武士をどう総括したか。 B――近世の歴史認識では、天皇制は南朝が正統で、北朝系統になって終った、ということだね。それ以後は、政権が武家にわたった。歴史的には武家が正統なんだ。どうしてそうなったか、熊沢蕃山(1619~1691)に言わせれば、《謙徳を失ひ玉ひし故に天下の権威を失ひ給へるなり》ということだね。 C――徳川幕府が武臣のポジションにあるとしても、実質的には、王権の簒奪だよ。王者が武臣に威を奪われた、それは武家の棟梁に徳があったからだ。要するに、朝廷に徳がない、それが悪いんだと。 A――それが、軍人勅諭の歴史総括では、王権の簒奪というあさましき事態をひっくり返して、天皇政権を回復した、という筋書きになる。王政復古ですな。そうなると、武士も武士道も政治的に否定されるわけだ。 C――だから、戦争中、武士道と軍人精神というテーマの本がたくさん出たし、戦後の反省も、武士道は軍国主義の精神だと信じていたが、それは間違っているわけよ。実は、天皇制原理主義からすると、武士道と軍人精神という、そんな結合はけしからん、ということになる。 B――それは結局、近代天皇制が、封建制を打倒した政治権力だったからさ。天皇制原理主義とは、復古に名を借りたモダニズム以外のものではない。 A――したがって、福沢諭吉や新渡戸稲造の武士道論は、この軍人勅諭に代表しうる天皇制反武士論と対立するわけだ。 B――最近、「明治武士道」だのと新渡戸武士道論をあげつらう連中が出てきたが、こういうのは軍人勅諭との対立という思想的シーンを看過しておるにすぎない。武士道は近代天皇制と対立する契機を内在しているのだよ。 |
|
C――新渡戸以前の世代では、たとえば、福沢諭吉(1834~1901)などは、武士道を「独立」した個人という文脈で言うね。真実の武士は、自ら武士として独り自から武士道を守るのみ。ゆえに今の独立の士人も、その独立の法を昔年の武士のごとくにして大なる過なかるべし、と。 D――無礼打ちに関して、そう云っていた。まあ、無礼打ちなんてのは、無礼だから抜刀して斬るのであって、むやみに切り捨て御免というわけにゃいかない。 A――福沢諭吉といえば、「痩我慢の説」(明治二十四年)ですな。そこでは、武士道モデルは三河武士のようですな。武士道的行動の性格は「痩我慢」、日本が諸外国に伍して独立を維持していくためには、国民一人ひとりの「私」が痩我慢の士風を重んぜねばならぬと。 B――その話のついでに、勝海舟や榎本武揚という連中を揶揄する。旧幕臣なのに明治政府の高位高官についたのが気に入らんというわけだ。 D――諭吉はどういうわけか、三河武士を称揚しているね。「日本魂」とはまさに《Soul of Japan》なのだが、新渡戸はまだ『武士道』を書いていない時期だ。諭吉は、日本魂とはむしろ三河魂と称していいんだ、という。そう言うのは、日本魂の歴史性だね、そんなものは、ここ300年来のことだ、要するに三河武士が出てきて以来のことだ、という。 C――とすれば、封建社会に対する批判者として啓蒙家であった福沢諭吉にしては、ある種の転向だね。明治維新は、すでに遠い。むしろ封建社会の美風として、この「士風」、つまり武士の行動倫理としての武士道だね、これを称揚してしまうわけだ。つまり、このようにして福沢諭吉も、近代武士道イデオロギーを唱和する。 B――ナショナリズムと結合する武士道だね。日本人の固有精神、日本魂は、西洋のものとは違う。そういう日本人の特殊性・特別性を不用意に云い出すと、戦争の原因にしても、西洋は単に掠奪のために侵略を企てた例が多いが、日本ではそうじゃないとする。例えば「元亀天正」時代、つまり信長から秀吉に至る時期だね、その実態を見ると、戦争は、弱者を保護したり助けるために、他の強者と戦ったものが多いと云い出す。そんなバカな、これじゃ贔屓の引き倒しだ(笑)。 D――それと似たことだが、封建政治は、武士の専権であって、平民に対しては「切捨御免」など生殺自由の特権までも有しながら、実際はいかにも優しくて無理無体の挙動はなかったという。そんな生殺自由の特権を武士がもっておったわけがない。このあたり、もう認識がズレている。 C――諭吉は武士道を、弱きを助け強きを挫く侠客風にしたいのさ。福沢諭吉の武士道論は、それこそ混乱したものだが、これは新渡戸武士道以前ということで、ある程度理解はできる。武士道をしっかりと倫理的に基礎づけるという視点が、まだ生まれていない。 A――そうしてみると、新渡戸の『武士道』が、日本でもあれほどウケた理由もわかる。これが武士道というローカルな文化が西洋との関係で位置づけられ、新渡戸ほど明解に整理した武士道論は、それまでなかったからだ。 B――というか、新渡戸武士道論とともに、ある明確なイメージをもった武士道なるものが発生したということだよ。つまりだね、一つは、新渡戸は武士道を発見した、もっと言えば武士道を発明した。もう一つは、新渡戸は失われしものとして武士道を語った。この喪失のポジションが重要なんだ。 C――そうなんだ。ロスト・オブジェクト(lost object 喪失対象)としての武士道。喪失を通じてのみ生産される対象だね、武士道というのは。喪失の前には何もない、喪失の後にはじめて存在する。 B――かつて一度もあったことのない対象が、あったことになる。喪失が存在を生む。ということでは、喪失と回復の物語は、まさに反転しているわけだね。回復以前には喪失もない。諭吉のいう三河魂としての武士道なんてのも、あきらかにその種の対象だね。 D――諭吉がそう言うのは『三河物語』でも読んだからだろう。《徳川の初代より扶植せられて三百年間、封建制度の下に練りに練り上げたる三河武士風の活溌にして浮薄ならざる精神こそ、之を名づけて封建の武士道と云ふ可きものなり》と云ってしまう。どうもよくわからんのは、「三河武士風の活溌にして浮薄ならざる精神」が、三百年にわたって練りに練り上げられた、というあたりだ。ほとんど事実を無視しておる(笑)。 A――福沢諭吉は、何でもそうだが、調子がよすぎる(笑)。 B――話が講談なんだよ(笑)。じゃ、《譜代の衆は御家の犬》という大久保彦左衛門の至言(三河物語)はどうなんだ。 C――そうさ。ただ、先ほどの話だが、その喪失対象としての武士道、その回復というストーリーは諭吉にすでにある。新渡戸も同じ文脈で武士道という宝を語る。ところがだ、新渡戸の『武士道』を読む者がたいてい見過ごしているのは、新渡戸が、武士道の葬送の準備をすべきだ、と語っている側面だね。 A――武士道を発見して、ただちに葬式の準備をする。つまり、葬式のために遺体を発掘する(笑)。 C――文字通り、武士道は遺体として発掘された。この点は重要だよ。武士道は終った。「神の国」の種子が花開いた、その花が武士道だった。《悲しむべし、その十分の成熟を待たずして、今や武士道の日は暮れつつある》、しかしこの「神の国」という言葉が、曲者だな。 B――武士道を葬送する、しかし、ここで暗黙の定理としてあるのは、つまりは、キリスト教という普遍性を通じての、武士道の止揚だな。ナショナルな特殊性を止揚する普遍性としてのキリスト教。 A――その点では、植村正久(1857~1925)の批評が、もっとも的を射ている。武士道を葬って、それを相続するのは、キリスト教だ。武士道の精神はキリスト教によって保全されるだろう、と。 C――それは、内村鑑三でも同様で、武士道は否定的媒介として発見される。そして内村の、たとえば日朝併合から朝鮮布教へ展開する問題で、日朝両民族のナショナルな相違を超克するものとして、キリスト教の普遍性が持ち出される。 A――どうも、帝国主義=植民地支配となると、キリスト教徒が活躍する。 B――新渡戸に対する近年の批判は、国際連盟がらみで、とくに信託統治の植民地支配にからむ話だね。この一件では柳田國男批判も同じ線だ。柳田が日本代表でジュネーヴへ行ったのも、新渡戸の引きだったからね。 C――ようするに、武士道はプロテスタントの倫理と親和性をもつものとして発掘された。そして、その発掘は葬るためだった。キリスト教式に葬式をする。こういう新渡戸のポジションを看過して、新渡戸が単純に武士道を賛美したとするのは間違っている。 A――新渡戸『武士道』は、それが出た最初から誤読された。それは今日も変らない。 |
*【福沢諭吉】
《一片の濁立は生命より重し、之を妨げんとするものあれば、満天下の人も敵に取る可し、親友の交も絶つ可し、骨肉の情も去る可し、断じて躊躇せざる所なれども、扨実際に於ては決して斯る劇しき場合はなきものなり。譬へば封建の時代に武士が雙刀を帯したるは、天下の人を敵にして無禮者は誰れ彼れの容捨なく切て棄てんとの覺悟なりしかども、苟も仁義を重んじて武士道を守る限りは柄に手を掛るの必要なくして、何十萬の武士が何百年の日月を無事に経過したるが如し。当時の天下に鄙劣なる者も多く臆病なる者も多しと雖も、その者が武士に向て無禮せざる間は之を許し、相互に往来して曾て自由の交際を妨げず、唯真実の武士は自から武士として独り自から武士道を守るのみ。ゆえに今の独立の士人もその独立の法を昔年の武士のごとくにして大なる過なかるべし》(『福翁百話』「独立はわれにありて存す」 明治29年) 《或は此日本魂なるものは古来我國人に特有の資質なりと思ふ者もあらん。自から由来久しと雖も、其資質の特に発達したるは三百年来のことにして、我輩の所見を以てすれば、日本魂とは寧ろ三河魂と称して穏なるが如し。徳川の初代より扶植せられて三百年間、封建制度の下に練りに練り上げたる三河武士風の活溌にして浮薄ならざる精神こそ、之を名づけて封建の武士道と云ふ可きものなり。抑も我國の封建制度は一種特別の仕組にして世界古今に其例を求む可らず。(中略)而して其封建制度三百年の間に練り上げたる日本魂とは如何なるものなるやと云ふに、平たく云へば弱いものいじめせぬ気象にして、強を挫き弱きを扶くるこそ其本色と認めざるを得ず。例へば封建政治は武士の専権にして、平民に対しては切捨御免など生殺自由の特権までも有しながら、其これに接する実際を見れば如何にも優しくして更らに無理の挙動を見ず。又戦争の原因にしても、西洋古代には単に他の財宝を目的として侵略を企て又は遠征を試みるなどの例に乏しからざれども、我國に於いては然らず。例へば元亀天正時代の有様を見るに、其戦争は弱者を保護し又は之を助くるが為めに他の強者と戦ひたるもの多し。畢竟日本の武士道は此辺の精神より発し、封建制度の下に練り上げたるものにして、一言これを評すれば侠客風の気象に外ならず》(「時事新報」 明治31年) 

*【新渡戸稲造】
《社会の状態が変化して武士道に反対なるのみでなく敵対的とさえなりたる今日は、その名誉ある葬送の準備をなすべき時である。(中略)我が国においては一八七〇年〔明治三年〕廃藩置県の詔勅が武士道の弔鐘を報ずる信号であった。その五年後公布せられし廃刀令は、「代価なくして得る人生の恩寵、低廉なる国防、男らしき情操と英雄的なる事業の保姻」たりし旧時代を鳴り送りて、「誰弁家、経済家、計算家」の新時代を鳴り迎えた》 《日本人の心によって証せられかつ領解せられたるものとしての神の国の種子は、その花を武士道に咲かせた。悲しむべしその十分の成熟を待たずして、今や武士道の日は暮れつつある。しかして吾人はあらゆる方向に向って美と光明、力と慰謝の他の源泉を求めているが、いまだこれに代るべきものを見いださないのである。功利主義者および唯物主義者の損得哲学は、魂の半分しかない屍理屈屋の好むところとなった》(『武士道』) *【植村正久】 《英文武士道が余りに弁護士的の態度に出たことは余輩の聊か遺憾ととするところなり。然れども余輩は新渡戸氏に於て熱心にして雄弁なる弁護士を得たることを喜ぶ。若しラフカデオ・ヘルン氏をして外国の援軍たらしめば、新渡戸氏の如きは精鋭なる日本の新兵、以って大敵を砕くに足るベし。是れ余輩が『武士道』に於て多とする一言なり》 《然れども新渡戸稲造氏は漫に武士道に心酔するものにあらず。氏は其の将来に維持す可らざるを熟知せり。彼は丁寧に武士道を葬るべきの時到れりと明言せり。武士道を葬りて其の相続を為すべきものは誰ぞや。新渡戸氏は基督教即ち是れなると言はる。是れ甚だ適当なる結論なり。余輩は武士道の精神は基督教に依りて保全せらるべきを疑わず。稿を改めて之を論ずべし》(「福音新報」 明治34年) |
|
D――近年、新渡戸の本(『武士道』)に対する批判が出てきた。それはだいたい、武士道の説明内容はどうであれ、それをキレイ事にしすぎている、ということだな。 A――さっき話に出た植村正久が、新渡戸にこう言ったという話もある。――日本人の所に客に行くと床の間以外に客に来られると困る。それと同様に、新渡戸君の武士道は、床の間付きの部屋を外国人に紹介したものだ、と。 B――そうして植村は、日本の台所を書いてはどうかい、という。武士道の裏側を書けというわけだ。 D――以前から、武士の淵源をならず者、ゴロツキとするような論はいくらでもあった。だから、最近の新渡戸武士道論批判が、武士をキレイ事にしていると言っても、何を今さら、という感があるが。 A――切り取り強盗は武士の習い、というしね(笑)。 B――となると、武士道というのはいったい何だね(笑)。 D――さあね(笑)。というか、武士道という言葉は近世初期の『甲陽軍鑑』あたりで出現したようだが、この語が世間一般に用いられるのは、やはり明治以後だね。それまでは、武士道という言葉はさして一般的ではない。 C――武蔵は「武士道」とは言わなかったね。「武士の道」あるいは「武道」だね。それよりも「兵法の道」。これは芸能あるいは芸道としての戦闘術だ。 D――すこし言葉の詮索をしてみようか。有名な源致雄〔むねお〕の歌があるね。《命をばかろきになして、もののふの道よりおもき道あらめやは》(風雅和歌集)。この命知らずの「もののふの道」が武士の行動規範ということになる。「もののふ」というのは和語としての擬古語の用法だが、これは武士の行動倫理だ。 C――「もののふ」のモノは、物の怪のモノに同じ。武威に呪術的威力、マナを見たのだね。 B――荻生徂徠は物部氏の末裔を称しているが、このモノノベのモノもそれだろう。 D――「もののふの道」は、「弓箭の道」だね。弓矢の道。武士の兵器は、弓矢という飛道具で象徴される。後世のように剣ではない。これは合戦の場面を想定すればよい。 B――紀記(日本書紀・古事記)では、草薙の剣のように、武威というマナを象徴するのは剣である。三種の神器の一つも剣だ。クハシホコチタル(細戈千足)国という戈よりも剣だ。それが、弓矢という飛道具を武威の象徴とするようになるのは、戦法が変ったということか。 D――『今昔物語』に、平将門が新皇を称するとき、《我弓箭の道に足れり。今の世には討ち勝つを以て君とす。何を憚らんや》(巻二十五)といったという話があるが、この「弓箭の道」がそれだね。平将門の武力優勢は、本当は、軍馬の術だろうに、やはり弓矢なんだ。 C――「弓箭の道」が行動倫理として現れるのは、『平家物語』だね。平家都落のとき、平宗盛に郎等たちが忠誠を誓う言葉に、《弓箭の道に携はる習、二心を存ずるを以て長生の恥とす》(巻七)とある。「弓箭の道」の習いとして忠誠が語られる。 D――『太平記』はそれがもっと前面に出てくる。「弓矢の道」だね。《弓矢の道、死を軽んじて名を重んずるを以て義とせり》(巻十)、《弓矢の道、ふたごころあるを以て恥とす》(巻三十一)、《今更弱きを見て捨つるは、弓矢の道にあらず》(巻三十四)。そういう倫理的な行動規範としての武士の道は、『太平記』のころには出ている。 |
*【五輪書】
《武士に於ては道樣々の兵具を拵え、一々兵具の徳を辨へたらんこそ、武士の道なるべけれ。兵具をも嗜まず、其具々々の利をも覺ざる事、武家のたしなみの淺きもの歟》 《二刀と云出す處、武士は將卒ともに直に二刀を腰に付る役なり。 昔は太刀・刀と云ひ、今は刀・脇差と云ふ。武士たるものゝ此兩刀を持つ事、こまかに書顯すに及ばず。我朝に於て、知るもしらぬも、腰に帯る事、武士の道なり。此二つの利を知らしめんために、二刀一流と云ふなり》(地之巻) *【太平記】 《舎弟脇屋次郎義助暫〔く〕思案して、進出て被申けるは、「弓矢の道、死を軽じて名を重ずるを以て義とせり。就中相摸守天下を執て百六十余年、于今至まで武威盛に振て、其命を重ぜずと云処なし。(中略)指たる事も仕出さぬ物故に、此彼へ落行て、新田の某こそ、相摸守の使を切たりし咎に依て、他国へ逃て被討たりしかなんど、天下の人口に入らん事こそ口惜けれ。とても討死をせんずる命を謀反人と謂れて、朝家の為に捨たらんは、無らん跡までも、勇は子孫の面を令悦名は路径の尸を可清む。先立て綸旨を被下ぬるは何の用にか可当。各宣旨を額に当て、運命を天に任て、只一騎也共国中へ打出て、義兵を挙たらんに勢付ば軈て鎌倉を可責落。勢不付ば只鎌倉を枕にして、討死するより外の事やあるべき」と、義を先とし勇を宗として宣〔ひ〕しかば、当座の一族三十余人、皆此義にぞ同じける》(巻十 新田義貞謀叛の事) 《是を見て、「さらば御謀叛の宮に可奉著様なし」とて、吉野十八郷の者共皆散々に落失ける程に、宮の御勢僅に五十余騎に成てげり。され共、赤松弾正少弼氏範は、「今更弱きを見て捨るは弓矢の道にあらず。無力処也。討死するより外の事有まじ」とて、主従二十六騎は、四方に馳向て散々に戦ける程に、寄手無左右近付得ず、三日三夜相戦て、氏範数箇所の疵を被てければ、「今は叶はじ」とて、宮は南都の方へ落させ給へば、氏範は降人に成て、又本国播州へ立返る。不思議なりし御謀反也》(巻三四 銀嵩軍〔かねがたけのいくさ〕の事) |
 芳虎 摂州兵庫求女塚合戦 太平記巻十六「小山田太郎高家青麦事」 |
*【太平記】
《抑〔も〕官軍の中に知義軽命者雖多、事の急なるに臨で、大将の替命とする兵無りけるに、遥〔に〕隔たる小山田一人馬を引返して義貞を奉乗、剰〔へ〕我身跡に下て打死しける其志を尋れば、僅の情に憑て百年の身を捨ける也。(中略)義貞大に恥たる気色にて、「高家が犯法事は、戦の為に罪を忘たるべし。何様士卒先じて疲たるは大将の恥也。勇士をば不可失、法をば勿乱事」とて、田の主には小袖二重与〔へ〕て、高家には兵粮十石相副て色代してぞ帰されける。高家此情を感じて忠義弥染心ければ、此時大将の替命、忽に打死をばしたる也。自昔至今迄、流石に侍たる程の者は、利をも不思、威にも不恐、只依其大将捨身替命者也。今武将たる人、是を慎で不思之乎》(巻十六 小山田太郎高家青麦事) |
|
B――「弓矢の道」が「義」の観念と結合するのは、もちろん、中世当時の宋儒の思想輸入を背景としている。武士の道が中国儒教と結節するのは、近世に限ったことではない。この点、最近の武士道論は、どうも変なバイアスがかかっているな。 C――それは、「弓矢の道」であれ「兵の道」であれ、それは単なる戦闘能力を指すのであって、中世武士に倫理的なものを見ない、という傾向だね。それで、近世武士道と差別化したつもりなんだ。 D――それでは、『太平記』で、どうしてあんなにたくさん忠誠・忠義の逸話が出てくるんだ、ということだね。中世武士が倫理的なものと無縁であったはずがない。 A――『太平記』では、忠義の逸話があって、それが称揚の文脈で語られたのは明らかだ。それで、なぜ、称揚されたかというと、忠節の武士があまりにも少なかったから(笑)。 D――それは言える。以後の戦国時代を通じて、裏切りや寝返り、下克上がむしろ常態だった。だからこそ、忠義・忠誠が称揚された。こういう逆説は押さえておく必要がある。中世の武士の道は戦闘能力、近世の武士道は道徳規範というように、単純に振り分けることはできない。 A――忠節は、希少価値として称揚された。だれもかれも実践しているのなら、ことさら語る値打ちがない(笑)。 B――しかし、どうして近世武士道はあんなに観念化したのか、という問題がある。 C――それは、君臣関係が双務的でなくなったからだね。それは、家臣が一方的に忠義臣従をする、ということじゃない。このあたり錯覚がある。戦乱が偃んで天下泰平、家臣の戦功なしに、君主が一方的に給与するという片務関係になったからだ。 B――つまり、家臣は何の働きもせずに、給料をタダ取りしている、ということだね。これでは、家臣の負債感情が大きくなるばかり。この負債感情、負い目が、忠義道徳の根本源泉なんだ。 D――大名だって、同じだ。現に戦功がないのだから、代替わりごとに、領知を安堵してもらうというシステム。先祖がもらった領地でも、いつ剥奪されるかもしれない。そうなると、基本的に忠義でお返しするほかない。 C――とすれば、中世あるいは戦国期の武士と、近世の武士は、そもそもポジションが根本的に違う。もう少し精しく言えば、近世初期、元和偃武以前以後の境目が大きいね。大坂の陣までと、元和寛永以後だね。 D――「武士道」という言葉は、『甲陽軍鑑』あたりから出てくる。これが元和年間成立というが、それはどうかな。『甲陽軍鑑』は原本はないし、写本もない。残っているのは刊本だけ、しかもその刊本はかなり遅い。 A――そこでいう「武士道」という語の用法を見ると、どちらかというと、「町人」に対する「武士」なんだ。しかし中世的な「凡下」ではなく、「町人」という概念はかなり新しい。 D――もちろん『甲陽軍鑑』は武田信玄の事蹟を中心にした伝承記録を編集した文書であるが、きちんとした資料批判が必要だ。信玄・勝頼二代に仕えた高坂弾正虎綱から聞いたことを能役者(大蔵彦十郎)が筆記したというのを、また弾正の甥(春日惣次郎)が書き継いで、結局、小幡勘兵衛(景憲)が編集したという筋書きだね。しかし、少なくともその編纂は甲州流兵学の成立と平行している。現在のかたちの成立は、元和年間というよりも、元禄前後じゃないか。 C――武士という存在が、その存在理由を危うくするようになって、武士道という語が確立する。武士道という歴史的な思想的実体があるとの錯覚がある。整理をしておく必要があるね。一つは、武士道以前。次に、武士道以後。この境目は、十七世紀半ばあたり。すると、武蔵は武士道以前ということになる。 B――武蔵は『五輪書』の中で《今此書を作ると云へ共、佛法儒道の古語をもからず、軍記軍法の古きことをも用ひず》と書いているが、武蔵は軍記軍法の古事を用いて語るところから距離を措いている。彼のスタンスには独特なものがある。 A――『五輪書』は剣術の指南書で、合戦の指南書ではない、という妄説が後を絶たないが、そんなことを言う連中に限って当時の兵法書をろくに読んでいない。『五輪書』著述の背景には当時の軍記軍法の存在がある。 C――しかも武蔵は、当時の軍記軍法による軍談に対して、「それは違う」というスタンスだな。評論家と実践家の違いだよ。実戦を踏まえた実践家という意味だが。 D――その「軍記軍法」のことだがね、太平記評論集というべき『理尽鈔』(太平記評判秘伝理尽鈔)とか、あるいは一方で『甲陽軍鑑』や小笠原昨雲『軍法侍用集』といった秘書扱いの一時代前の軍記が刊行されて、逆に戦国時代というのものが反省対象になる。しかし、もうその頃になると、戦国からすでに遠い。 C――そのノスタルジックな距離が、近世軍学・兵学だけではなく、武士道という観念を発生させる。 |
*《中世の他の道と同様、「兵ノ道」にことさら精神的・倫理的なものを求めようとすることは適当ではない。「兵ノ道」は〔中略〕勇敢・敏捷で、腕力と判断力にすぐれた、バランス良い戦闘能力の保持に重点を置いており、それであってはじめて中世的な「道」たりうるのである》(高橋昌明『武士の成立 武士像の創出』1999年)
  津軽越中守宛家綱領地朱印状 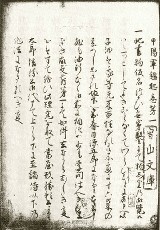 甲陽軍鑑 |
|
*【甲陽軍鑑】
《計略いたすは、昔が今に至るまで、敵・味方のならひなり。武略をつかまつりすますは、武士の一ほまれといふぞ。さてまた計略し倒さるゝは、女人に相似たる侍が、二心を持ちてのことなり》(巻二) 《侍の武略つかまつる時は、虚言をもつぱら用ふるものなり。それを嘘と申すは不案内なる武士にて、女人に相似たる人ならん》(巻二) 《虚言・過言、かりそめにも無用の事。但し、武略の時は苦しからざるは、右過言・虚言の二ヶ条、曲がりたる事なれども、腕の内へ曲がりたるごとし。直ぐにては役に立たず》(末書上巻) 《国持ち給ふ大将たちの、人の国をとりなさるゝ、是は、よその国にさのみとがはなけれども、おしやぶり、手柄次第にとるといへども、昔が今に至るまで、切り取り、強盗、盗人とは申しがたし。それにつきての虚言を計略と申して、苦しからずといふは道理。道理なればこそ、唐・日本までも、計略よくする人をば、謀臣といふてほめたる侍》(巻二) 
*【北条氏綱書置】
《大将によらず諸侍までも義を専に守るべし。義に違ひてはたとひ一国二国切り取るとも後代の恥辱如何に候。天運尽き果て滅亡を致すとも義理違ふまじと心得なば、末世に後指をさゝるる恥辱はあるまじく候。昔より天下をしろしめす上とても一度は滅亡の期あり。人の命はわずかの間なれば、むさき心底ゆめゆめ有るべからず。古き物語を聞きても、義を守りての滅亡と義を捨てての栄花とは天地格別にて候。大将の心底たしかにかくのごときにおいては諸将も義理を思はむ。その上無道の働きにて利を得たるもの天罰つひに遁れがたし》 *【軍法侍用集】 《第三十二、不審すべき事 一、内々聞き及びたるより、敵の人数少なき事 一、まけまじき所にて、敵まけぶりをする事 一、すゝむべき所へすゝまざる敵、或ひは城中物音なき事 一、引くにもあらず、かゝるにもなき敵の事 一、味方をもはなれ、敵にもそむきたる備への事 一、戦ひの時を延ぶる敵の事 一、馬験〔むましるし〕を敵近く、備へたる時の事 一、あつかふまじき敵、あつかひを入る事 一、つよかるべき敵、弱く見ゆる事 一、長陣〔ながぢん〕に退屈の敵、俄につよみの仕方付きたり、大なるたくみをする事 一、聞えある敵、うたれたると沙汰ありて、所もしれず、うちてもなき事 一、味方になるまじきもの、味方になる事。[付けたり]敵になるまじきもの、敵になりたりといふも不審 一、進むべき味方、すゝまざる事 一、勝ち戦に弱みの異見、まけいくさに強みを異見する事 右のごとく、不審あるべきなり。併しながら、なま心得にてふしんある事なかれ。たゞ理非をわきまへ給ふ事第一なり。『功者の書』にもいふごとく、軍の行〔てだて〕などは、負けんと定めて、其上にての勝ちを勝ちと沙汰あるべき事、利をわきまへるなるべし。武学などは、さのみ文字をあらため異国の遠き沙汰せられずとも、近き我朝の取合ひ、舞謡の本などにも、心をよせて思案あらば、勝負はわきまへ給ふべし。軍法のをしへは、水中の月のごとし。されば予聞き及びし軍の沙汰あつめて、『諸家評定』と名付け書き集めたる書あり》(巻二) *【朝倉宗滴話記】 《山城にても、平城にても、むたひに責むべき事、大将の不覚なり。その故は、然るべき兵ども、目の前にて見殺すものにて候。是また分別の第一也》 *【甲陽軍鑑】 《参禅なされ候とても、それをば未来の事と思しめせ。武士は、愚にかへり、現在の名利が本にて候。出家は、現世をば捨てに仕る。これさへ名を取りたがるもの也。ましてや俗家と申せども、侍は中にもほまれを本になさるゝが家にてあり。愚にかへり、軍配をもつばら御もちい候へ》(巻一) |
B――そのばあい、戦国武士というのが、近世武士道にとっては、すでにネガティヴなものではないか。だれもが引用してすでに手垢がついた文言だが、『朝倉宗滴話記』の《武者は、犬ともいへ畜生ともいへ、勝つ事が本にて候》。 D――朝倉宗滴(教景)(1477~1555)は越前の人、彼の父・孝景は下克上の最中に生きた。越前の守護・斯波氏にとって替わった守護代が甲斐氏。その甲斐氏を下克上したのが朝倉孝景で、越前守護代になった。朝倉氏が戦国大名として抬頭してくるのは、この孝景の代だ。宗滴はその孝景の末子だね。 C――いまの《犬ともいへ畜生ともいへ、勝つ事が本にて候》に代表されるように、戦国軍記では、どんな手段を使ってでも、要するに勝てばいい、という世界で、騙し討ちは常態だ。そこで泰平の世になると、例の「詭計は肯定されるか」という問題構成が出現してくるが、これはそれ以前の世界。 A――犬畜生と呼ばれても、勝てばよい。勝ってこそ名がある。勝たなければ名もない。とすれば、目的は手段を正当化する。どんな汚い手であろうと、避けてはいけない、となる。これも武士道なんだ(笑)。 B――そういう武士道を否定することから、いわゆる「武士道」が登場する。 A――そういう「いわゆる武士道」が通例理解されている武士道。となると、ややこしい話になるね(笑)。 D――『甲陽軍鑑』にしても、《勝ちがなくては、名は取られぬものにて候》(巻一)という。詭計の話はあれこれ出てくる。たとえば松平元康(徳川家康)に帰せられる言説に、計略をするのは、昔から今に至るまで、敵も味方もやっていることだ。武略を実行するのは、武士の第一の誉れとされておる、計略によって倒される方が悪いんだ、というような話がある。また、武田信玄麾下の馬場美濃守に帰せられる台詞には、侍が武略を行なう時は、虚言をもっぱら用いるものだ、それを嘘だといって反対するのは、《不案内なる武士にて、女人に相似たる人ならん》という。 C――戦場では武士は、計略を用い虚言を用いる。虚言と嘘は区別されている。それを嘘だといって批判するのは、何もわかっていない。女のような武士である、意地の汚き武士である、というわけだ。 D――こういう批判の部分は、従来文字通り読まれてきたが、「女人に相似たる侍」「不案内なる武士にて、女人に相似たる人」というのは、実は『甲陽軍鑑』が批判しているのは、同時代の道徳的思考だね。中途半端な儒者の言説が槍玉にあがっているのだよ。こういうあたりからしても、『甲陽軍鑑』は十七世紀後半だね。 A――騙されるのは女みたいな武士。どうも軍書は女性蔑視が極端だね。(フロイトではないが)軍隊組織は本質的にホモセクシャルだから。 C――曲がったことは嫌い、というのでは武士はつとまらない。腕が真っ直ぐでは役に立たない、曲がるから役に立つ。戦場では曲がったことをすることは必要だと。 A――《曲がりたる事なれども、腕の内へ曲がりたるごとし。直ぐにては役に立たず》という(笑)。腕もそうだが、真っ直ぐじゃ役に立たないというわけ。 D――これとは逆に、北条氏綱の家訓(氏綱書置)とされるものは、義に反する行動を禁ずる条項を第一条に措く。《義に違ひては、たとひ一国二国切り取るとも後代の恥辱如何に候。天運尽き果て滅亡を致すとも義理違ふまじと心得なば、末世に後指をさゝるる恥辱はあるまじく候》なんてことをいう。もちろん虚言は常の時には許されない。《常には虚言・過言、禁制々々》というわけだ。ただし、武略の時は別だ、虚言もさしつかえない。日常と戦場とでは行動規範が違って当然という考えだね。 B――謀臣というね。計略よくする人を謀臣といって、これは見上げた侍。謀略という語も、決して悪い意味ではない。《虚言を計略と申して、苦しからずといふは道理。道理なればこそ、唐・日本までも、計略よくする人をば、謀臣といふてほめたる侍》という。 D――戦国大名は他国を侵略し略奪したが、それを「昔が今に至るまで、切り取り、強盗、盗人とは申しがたし」というのも、同じ事情だね。《切り取り強盗は武士の習い》という俚諺がここに反映されている。 C――戦場では、騙される方が悪い。こういう計略に満ちた世界だから、詭計を見破る智力が必要だ、となる。 D――計略を知ることに関連してのことだが、『軍法侍用集』に不審すべきことの条々があるね(巻二)。「第三十三、うちがたき敵の事」に、《一、不審の敵を、みだりにうつ事なかれ。一、味方に不審あらば、敵を追ふ事なかれ》とある。その前項に、「第三十二、不審すべき事」とあって、疑ってかかれという話で、用心すべき敵の計略がどんなものか、だいたいわかる。 A――その中でも、《まけまじき所にて、敵まけぶりをする事》、敵が負けるはずがないところで負けたふりをすること、《つよかるべき敵、弱く見ゆる事》、強いはずの敵が弱くみえるケース。こういう罠を仕懸けることがあったわけだ。 C――それから、《味方になるまじきもの、味方になる事》、味方になるはずのない連中が味方につく。これも疑ってかかるのは当然だが、《敵になるまじきもの、敵になりたりといふも不審》というのは、かなり高度な謀略だな。 B――《進むべき味方、すゝまざる事》というのは、ミエミエの内部の敵だし、《勝ち戦に弱みの異見》というのも怪しいのは分かるが、《まけいくさに強みを異見する事》ということになると、勇気と冒険主義の違いというよりも、内部の敵が強硬論を出すケースだね。 C――こういう内部の敵ということになると、内ゲバもけっこうあったはずだね。内部の権力抗争で、あいつは敵のスパイだとして粛清する。暴力組織には内ゲバ・粛清は不可分だが。 D――そこで、《併しながら、なま心得にてふしんある事なかれ。たゞ理非をわきまへ給ふ事第一なり》と警告するわけだ。謀略という頭になると、すべてが疑わしくなるからね。 B――理非をわきまへ給ふ事第一なり、か。同じようにして、蛮勇は誉めたものじゃない。分別第一ということもある。『朝倉宗滴話記』に、無理無体に城を攻めるのは、大将の不覚だとある。その理由は合理的で、立派な働き手である兵どもを見殺しにすることになるからだという。これは無分別に兵隊を浪費するな、ということ。 D――分別第一というのは、一種の合理主義だ。不合理なことは決してするなと。だから参禅して精神修養すれば立派な大将になれるなどと思うな、ということだね。分別は、あくまでも、世俗的合理主義なんだ。『甲陽軍鑑』に《武士は、愚にかへり、現在の名利が本にて候》というね。 A――《愚にかへり、軍配をもつばら御もちい候へ》と。この「愚」が分別なんだ。 C――分別というのは武蔵語彙でもある。ようするに、たとえば宮本武蔵を、禅の悟りという文脈を読むという通弊が今でもあるね。しかし、それは決して武蔵的ではない。武蔵は、武士の道は「勝つ」ことにある、とする世代だが、これは戦国の感覚だね。後世の武士道とは違っている。 |
|
B――勝たなければ話にならないということは、これは覇権主義の世界だ。江戸初期に徳川幕府が創設されたとき、まだそれでも正統性の根拠は存在しなかった。徳川氏も諸大名の一つでしかない。それで、豊臣氏を滅ぼし、その後も有力大名を改易し壊滅させていく。その結果、戦国の世を知らない世代によって正統性の幻想が形成される。 C――新井白石なんぞは、信長・秀吉までは覇権だが、家康になってやっと王道だというストーリーを造りだす(読史余論)。ところが、林羅山あたりだと、まだ家康の覇権をうまく正当化できない。正当化できなくて当然なんだ。 D――藤原惺窩だと、そんな問いには答えられない、といって、答えそれ自体を拒む。 B――つまり、ある政治理念があって、それが覇道を王道として正当化・合理化するというわけではない。徳川の覇権がどのようにして達成されたか、それ知っている世代がまだ生き残っているうちは、家康を神君とする政治装置は「作為」としてしか機能しない。だから、徳川の支配が完成するには、依然として強権を発動して敵を潰すという行動が必要だった。 A――秩序が「自然」になる前に、まず「作為」ありき、ですな。 C――そういうこと。で、関ヶ原役のことだがね、それは東軍の勝利だったが、これは豊臣勢と徳川勢の対決ではない。むしろ、豊臣家臣間の抗争だった。それが証拠に、この合戦を勝利に導いたのは、福島正則、加藤清正、池田輝政、黒田長政、細川忠興、といった連中だよ。徳川譜代の連中はろくに働いていないし、息子の秀忠にいたっては戦場に遅参しておる。家康は大きな借りをつくったわけだ。 D――それは戦後の論功行賞に現れている。まず、西軍に属した諸大名の領地が没収、あるいは減封・転封されたね。改易没収は、近江佐和山の石田三成(十九万石)をはじめ、備前の宇喜多秀家(五十七万石)・肥後の小西行長(二十万石)・土佐の長曾我部盛親(二十二万石)ら八十八の大名、その領地(四百十六万石)が没収。それから、改易は蒙らなかったが、減封というのが、毛利輝元(百二十万石)・上杉景勝(百二十万石)・常陸の佐竹義宣(五十四万石)ら五大名からの没収分(二百十六万石余)がある。そうして、合計没収高(約六百三十万石)は当時の全国総石高(千八百万石余)の三分の一以上である。つまり、天下分け目の決戦だというが、要するにその勝敗の影響は、数量的に言えば、全体の三分の一を超える程度。 A――それが小さいか大きいか、これは何とも言えないですな。 D――それで、勝った家康がこの没収分の大半を取った…のではなかった。逆に、この没収石高(六百三十万石)の八割(五百二十石余)が、豊臣方諸大名に配分されたのだよ。徳川勢は、二割しか稼げなかった。 |
*【林羅山】
《幕府(家康)又曰く、「湯武の征伐は権か」と。春(羅山)対へて曰く、「君、薬を好む。請ふ、薬を以て瞼へん。温を以て寒を治め寒を以て熱を治めて、其の疾已〔い〕ゆるは是れ常なり。熱を以て熱を治し寒を以て寒を治む。これを反治と謂ふ。これを要するに、人を活するのみ。是れ常に非ず。此れ先儒、権の譬なり。湯武の挙、天下に私せず。唯だ民を救ふに在るのみ」と。幕府曰く、「良医に非ずんば、反治を如何。只恐らくは人を殺さんのみ」と。春対へて曰く、「然り。上、桀紂ならず、下、湯武ならずんば、則ち、弑逆の大罪、天地容るゝこと能はず」と》(羅山文集) *【藤原惺窩御暇】 《〔家康が〕武王ノ紂王ヲ討シ事ノ義理ヲ御尋ナリ。妙寿院(惺窩)承テ、「コレハ即事御得心アルベキ理ニアラズ。大切ノ義ナリ。御工夫ツマセラレズバ如何」ト答ヘラレテ、翌日上京ノ御暇申上ラル》(松浦鎮信『武功雑記』) 《或時、湯武の事を聞きたい、と再三御望み有りたれば、合点の行かぬことぢゃ、大坂でも討つ思案かとて、其れから御前へ出られなんだ》(若林強斎『貫川記聞』) [文字化け注記]unicode文字使用のため文中「?」と表示される場合あり。当該Web表示制約文字は「糸へん+寸」(チュウ) |
 関ヶ原布陣図 |
|
(外 様) 10万石以上加増大名 蒲生秀行 下野宇都宮18万→陸奥会津60万 (+42万石) 池田輝政 三河吉田15万→播磨姫路52万 (+37万石) 前田利長 加賀金沢83万→(同地)119万 (+36万石) 黒田長政 豊前中津12万→筑前福岡52万 (+40万石) 最上義光 出羽山形24万→(同地)57万 (+33万石) 福島正則 尾張清洲20万→安芸広島50万 (+30万石) 加藤清正 肥後熊本20万→(同地)52万 (+32万石) 田中吉政 三河岡崎10万→筑後柳川32万 (+22万石) 細川忠興 丹後宮津18万→豊前小倉40万 (+22万石) 浅野幸長 甲斐府中16万→紀伊和歌山38万 (+22万石) 小早川秀秋 筑前名島36万→備前岡山51万 (+15万石) 山内一豊 遠江掛川7万→土佐高知20万 (+13万石) 藤堂高虎 伊予板島8万→伊予今治20万 (+12万石) 生駒一正 讃岐高松6万→(同地)17万 (+10万石) 加藤嘉明 伊予松前10万→伊予松山20万 (+10万石) |
(一 門) 結城秀康 下総結城10万→越前福井67万 (+57万石) 松平忠吉 武蔵忍10万→尾張清洲52万 (+42万石) (譜 代) 奥平家昌 (なし) →下野宇都宮10万 (+10万石) 奥平信昌 美濃加納3万→同 左10万 (+7万石) 井伊直政 上野箕輪12万→近江彦根18万 (+6万石) 鳥居忠政 下総矢作4万→陸奥磐城平10万 (+6万石) 本多忠朝 (なし) →上総大多喜5万 (+5万石) 本多康重 上野白井2万→三河岡崎5万 (+3万石) 平岩親吉 上野厩橋3万→甲斐府中6万 (+3万石) 松平忠政 上総久留里3万→遠江横須賀6万 (+3万石) 石川康通 上総鳴戸2万→美濃大垣5万 (+3万石) 松平忠頼 武蔵松山2.5万→遠江浜松5万 (+2.5万石) 小笠原秀政 下総古河3万→信濃飯田5万 (+2万石) |
|
C――この表をみると、松平忠吉(四十二万石増)、結城秀康(五十七万石増)という徳川一門の加増はお手盛りにすぎないが、譜代の連中への加増は十万石を超えるものがない。それに対し、それ以外の(将来の徳川政権にとって外様になる)大名連中には、十万石を超えるかなり大幅な加増がある。彼らが家康に勝利をプレンゼントしたのだから、8割方を外様に廻さねばならなかったとしても、これは当然だろう。 B――そもそもだね、豊臣方諸大名が積極的に味方してくれなくては、勝てなかった戦さだよ。当然、戦利のほとんどを彼らに配分しなくてはならない。だから、関ヶ原でだれが勝ったのか、というと、それは家康だというのは単純すぎる話だな。 A――なぜ、豊臣方諸大名は東軍についたか。あまりにもキツい中央集権システムを嫌った。むしろ自分たちの自治権が確保できる分権制じゃないと承知できなかった。だから、三成よりは家康の方がまだマシだ、というので味方についた。 D――豊臣家じたいは大坂を中心として六十五万石ほどの領地しか残らなかったね。それだけを見れば、一大名にすぎなくなったとみえる。しかし関ヶ原の結果をみると、少なくとも豊臣体制を潰せるものではない。西国を中心に、諸大名があたらしい本拠をもつようになった。この東西分布は、諸大名も納得できるものだったろう。イザとなると、徳川と対決できる布置なんだと。 B――十七世紀初頭、慶長期の政治状況では、いわゆる二重権力状態だが、それでも、いずれは秀頼を頭にして、豊臣体制を整える。諸大名はそういう将来図である。家康も歳だし、徳川の勢力も暫定的なものだと。 A――家康がいなくなれば、豊臣の天下だと思っている。だから、家康が江戸に幕府を開いても、そう根本的な構造変化ではないと考える。天皇制としての関白支配の方がリアリティがあったわけです。 D――家康が得た征夷大将軍、武家の棟梁という称号は、秀頼の関白と矛盾しないという理屈だね。それはそうなんだが、では先の室町幕府からの継承手続きはどうなんだ、正統性があるのか、というと、それはない。 A――だから、慶長八年(1603)か、征夷大将軍になるとき、足利ではなく同じ源氏の新田の筋目だという系図をデッチあげた。しかし三河の松平は源氏ではない。先祖はどこかから流れついた聖だ。しかし、こいつを新田氏の筋から出たということにして、それで、尊卑分脈も書き換えてしまう。一丁あがり(笑)。 D――公卿どもに「新田殿」と呼ばせる。系譜捏造のさい、足利一族の吉良から系図を出させた。吉良は家康の家譜捏造に加担した恩賞で、高家となった(笑)。とにかく、系譜捏造は徳川家だけじゃないにしても、かなり露骨なことをやったものだ。 C――けれど、足利将軍家の血脈が絶滅したわけではない。足利道鑑(1565~1643)は、十三代将軍義輝の子だったが、人生あれこれあって最後に、寛永十三年細川忠利が拾って、結局熊本で死ぬ。この人は晩年の宮本武蔵と肥後でいっしょだね。 A――忠利の客分で、《道鑑様、宮本武蔵、山鹿へ召寄らすべく候》とあるように、湯治ができる山鹿の別荘へ武蔵とともに呼ばれて行ったこともあるようだ。 B――室町幕府の末裔を差し置いて、幕府を江戸に開いたのは、覇権行為だね。ただ、それをやりおおせたのは、暫定措置だとみんなが油断していたからさ。足利幕府の末期をみれば、幕府という政治装置はそうたいして大きな権力はふるえないと見られていた。将軍職など、だれもが役に立たない中古品だと思っている。それを家康が上手にリサイクルして、リフォームした。 |
 徳川家康像  大坂夏の陣  慶長8年征夷大将軍任官宣旨
*【細川藩奉書】
《道鑑様、宮本武蔵、山鹿へ可被召寄候。然者、人馬・味噌・塩・すミ・薪ニ至まて念を入御賄可被申付之旨、御意ニ候、以上 十月廿三日 朝山斎助 在判 御奉行所》 (寛永17年10月23日) |
|
D――それから大坂陣までの十五年の間に、諸大名を動員するなかで、将軍権力を次第に大きくして行った。この動員は軍事動員の形式だが、実際は江戸や駿府の城や城下町を建設する土木工事への動員だった。 C――普請(土木工事)も軍事的技術の一部だったからね。諸大名は建設業者として奉仕させられた。この普請サービスで、将軍権力は実体化してくる。この時期、諸国の土木建築事業のパワーはものすごいものだ。とにかく浪人があふれていたからね、戦後の失業対策事業だったわけだ。おかげで、近世初期の城郭と城下町は、いまでも残っているし、日本の諸都市の基本を造ってしまった。 D――そういう建設への意志、これが戦国の気分を後退させたのは確かだ。あちこちで新しい町ができる、新しい城ができる。それは新しい大名権力の可視化であるとともに、新しい世界の可視化だった。 B――そのとき重要なのは、これが新しい物を造りだすという、人為的な力の結集だったということだね。けっして、丸山真男が言うような「自然」ではない。むしろ「作事」の時代、だから「作為」の時代なんだ。 C――それは後で問題にしたいが、近世初期は自然法的世界ではない。逆だね。それは秀吉の時代から続いていたことだろうが、ここで、慶長期の暫定的な二重権力状態のなかで――ということはつまりは、絶対的権力が存在しない状態で――諸大名がおのおの好き勝手にいろんなことができた幸福な時代だったと言える。 D――それは、やはり関ヶ原役の産物だろうね。秀吉の中央政権が否定した、地域権力の自律、アウトノミーが、諸大名の領域で実現したわけだから。家康に同盟して徳川を生き残らせた大名連中は、やがて到来する中央政権確立以前の束の間を楽しんだということだね。 A――そのときですら、まだ関白秀頼を頭目にした中央集権的再編という近未来のイメージだね。それが、とにかく、ひっくりかえった。 D――大坂陣は、秀頼の下に浪人が大量に集まって、秩序を転覆しようとしている、これは不届きなことである、という論理だね。もちろん秀頼は主人だから、秀頼を攻めるということにはならない。これを正義の戦争にするためには、秀頼の周辺に悪人がいる、それを排除するという論理だ。 A――秀頼を抹殺したいのだが、それができなかった。しかし、浪人たちが秩序を転覆しようとしている、それを制圧しようという論理で、条件が整った。 B――大坂の役で福島正則や黒田長政を江戸に据え置いて参戦させなかった。これは危ないからね。細川忠興にしても、息子が豊臣方について大坂城に入ってしまった。 C――大坂陣という軍事的決着は、家康の覇権を完成させた。それで、武家諸法度の制定は、それ以前ではなく、ようやくこの勝利の後なんだな。 |
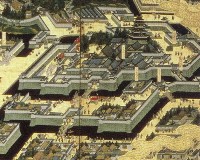 江戸図屏風 部分  豊臣秀頼像 |

慶長二十年 武家諸法度
*【福島正則改易申渡】
《今度広島普請之事、被背御法度之段、曲事ニ被思召候処、彼地可有破却之旨、依御訴訟、構置本丸、其外悉可被破却之由、被仰出候。然所ニ、上石計取除、其上以無人、送数日之義、重畳不届之仕合思召候。此上は両国被召上、両国為替地、津軽可被下之由、被仰出之候也。謹言》(元和五年六月二日、安藤重信・板倉勝重・土井利勝・本多正純・酒井忠世署名、宛名・福島左衛門大夫殿)(『東武実録』) *【細川忠興書状】 《一、加肥後当地著之様子、飛脚三人上せ申進之候つる、今廿四、〔伊達〕政宗・北国之肥前殿〔前田利常〕・嶋大隅殿〔島津家久〕・上杉弾正殿〔定勝〕・佐竹殿〔義宣〕被為召、加肥後無届と 御直被仰聞、此中ニ取沙汰仕候書物ニツ、右之衆へ御見せ被成、 御代始之御法度ニ候間、急度可被仰付と 御諚之由候。その時伊掃部殿〔忠孝〕、加様之儀は急度被仰付候ハて不叶儀と被申由候。如此ニ候間、今朝之内、可為切腹と存候事》(五月二四日付) 《其後永井信濃殿〔尚政〕・稲葉丹後殿〔正勝〕被遣候。其様子ハわきの者不承候。肥後御返事ハ、ゑんより下へおり、「せかれ無調法を仕出候。御検使次第いか様ニも可申付」由被申候。又豊後ハ、「私むさと仕たる儀ヲいたし候条、御諚次第ニ覚悟仕」と、ゑんの上より被申たる由候。此儀は、伝説なから慥成儀候》(同月二八日付)  徳川家光像 |
D――秀忠が将軍職に就くのは、慶長十年(1605)だから、代替りしてもう十年たつ。元和偃武となって以後、どんどん大名を潰しにかかるね。関が原の戦功で尾張清洲から芸備二国五十万石で広島に栄転した福島正則が、元和五年(1619)、改易され配流。理由はおよそ単純で、幕府に無断で広島城を増改築したということだ。 B――これは、正則が幕府にハメられたという説もあるが、そうでもない。幕府は穏便に済まそうとして、工事部分の破却で事を納める、正則も非を認めて取り壊しを約束した。ところが、人手が足りないとか言って実行しない。そうして、この約束不履行に対しての処罰が改易なんだ。 D――このあたりの齟齬は、福島正則などは領国のことは自治権があると思っているし、広島城の修築にしても台風被害があったからということだね。ただし、幕府の謀略という説は別にしても、やはり、中央統制を強化しようとする幕府と、それに抵抗する諸大名という図式はあるね。これは取り潰される前に、対徳川戦争を本気で考えておかなくては、という気分があったろう。 A――幕府の謀略という点では、二代目将軍秀忠死後の、肥後加藤家改易(寛永九年・1632)はどうなんだろう。これは将軍家光暗殺の密書が露見した、ということがきっかけのようですがな。 D――それはどうだったか、真実は不明だ。密書の内容はさまざま説があるが、――家光は土井大炊利勝を謀殺しようとしている、それなら土井は先手をとって家光を打倒すべきである。その節には、かねての申合わせの通り、間違いなく自分もこれを助ける――という起請文だったらしい。この密書を携えていた者が、加藤忠広(1601~1653)の息子・光広の名を出したので、大騒ぎになった。 B――細川三斎(忠興)は息子の忠利と頻繁に書状をやりとりしているが、この件でもそうだね。家光が五大名に証拠の密書を示して改易の事情を説明したとか、加藤父子がそれぞれどういう反応ぶりであったか、風聞を書き送っている。隣国のことだからね、落ち着いてはいられない。 C――しかし、証拠があるようでないようで、よくわからん話だ。結局、この一件の処分は加藤家改易。理由は、当主加藤忠広の不品行、それに本来江戸に置くべき人質を国元に置くという公儀無視、理由はそれだけで、謀叛の件は理由にはなっていない。忠広・光広父子は罪を認めてひたすら不調法を侘び、結局、切腹どころか、出羽と飛騨に配流。忠広は堪忍分として一万石を支給されている。 A――英雄・加藤清正の子孫だからね、そういう処分がせいぜい。 D――これは、弟の秀長改易とともに、家光が最初に行なった粛清だろう。徳川忠長(1606~1633)は秀忠三男で、三代将軍徳川家光の弟。寛永元年(1624)、駿・遠及び甲斐五十五万石を領知して駿府城に拠ったが、寛永八年甲府蟄居、翌九年改易。さらに寛永十年、預かり先の上野国高崎で自害。この弟はご乱行が改易理由だな。 B――ま、粛清というのは、大して理由がないのに実行されるものだ。大御所秀忠が死んでやっと自分の天下になった家光の強権発動だという説があるが、そうではない。権力が確立できているから粛清が可能なのではなく、逆に、粛清を実行することを通じて権力が確立される。 C――権力とは権力関係である(笑)。 A――権力は行使されてはじめて権力である。権力が確立されたら、もう行使するぞという構えだけでよくなる。家光時代はその過渡期ですな。 B――家光は将軍になった早々、加藤清正の子孫を粛清したわけだが、これで威力を獲得したと言える。それは、諸大名に対する威力というよりも、むしろ幕府内部での権力抗争に勝ち抜く一歩だった。将軍の権力はまだまだ脆弱で、とても専制君主とまでは行かない。 C――おおよそ何でもそうだが、三代目には潰れる。徳川幕府も当然そういう運命をたどっただろう。徳川氏も諸大名の一つでしかないという一揆的な軍事同盟、連合政権、これを主従関係に変えたのは、この三代目の家光だよ。家康の頃までは思いも寄らなかった体制だね。 |
|
D――ただ、それでも、自治権のある諸大名の同盟関係という本義は崩せなかった。それは、幕藩体制というマクロ政治のレベルだけではなく、各藩諸家の内部でも主従関係は、自律した武士という存在を前提にしていたからだ。つまり、各藩諸家内部のミクロ政治のレベルでも、譜代もあれば外様もある、そういう本来の同盟関係の意識は残存していた。 B――だから、近世の政治構造をたんなる主従関係で割り切ることはできない。末端の武士に至るまで、まずは武器軍装は自前の自律した存在で、イザとなるとおのおの役目に応じて軍事動員に応じる、というのが根本の構造だね。 D――各藩諸家は軍隊組織だから、階級の上下がある。しかし身分の「分」というのは、道徳的なバイアスを除けば、軍隊組織における持分、役目という機能的概念だ。しかも、それぞれの武士の「分」は自律的なものだ。それが侵すのは名分が立たないし、そもそも「一分」が立たない、という名誉毀損行為となる。 C――その持分、家臣たちの「自分」は、主君は勝手にできない。組織は主君の思いのままにならない。武士たちは組織埋没的ではない自律的分子だからだね。 A――そういう連中の寄合い所帯だから、殿様は一人で、家臣団の組織的ストレスがある(笑)。 C――ただし、それは、家臣団が団結して一揆するゆえのことではない。 B――そう、家臣は「分子」なんだ。組合が団体交渉するわけじゃない。しかし家老たちは、権力関係を貫通する倫理的な次元で、家臣団の権力量を背景にして主君に対応できるわけだ。主君専制独裁は形式で、権力関係の実際はまったく逆だということだね。 D――お家騒動は、もちろん主君の権力が不足してのことだが、家中が二つに割れても、権力関係からすれば、原理的にどうすることもできないわけだ。 B――その抵抗勢力、それは「家」という特殊日本的システム。福沢諭吉がね、《各幾千万個の箱の中に閉され、又幾千万個の墻壁に隔てらるゝが如くにして》と書いている。もちろんこれは近代統一国家、国民国家の立場から、ネガティヴな意味合いで書いておるわけだが、そのように家というブロックの集積体のイメージがある。 C――家というブロックは、一元的に統一された社会とは背反するし、抵抗するものだ。渡辺崋山も、箱や仕切りのイメージで書いていたな。 D――家業だ家督だといって、既得権を主張する。それは梃子でも動かないブロックなんだ。武士の自立的分子性というのは、まさにそういうブロックとしての家システムに拠るものだ。 A――そういう自律的分子という武士のありようは、個人という近代社会の概念とは違う。ある意味で、かなりおもしろい存在だ。 C――もともとが軍隊組織なんだ。しかし、軍事政権だから行政にも軍隊組織のままで当たる。自分、持分は譲らない。 B――そう。土着の国持大名なんてほとんどいない。大半が根無し草、大名に取り立てられた成り上がりで、自分の本貫の地とは無関係な土地に配属されてくる。だから、近世大名は占領軍にすぎない。 D――大名が入部のとき、あるいは代替わりのとき、制札を出すね。これは占領軍としての形式だね。そういう占領統治の形態が存続する。行政といっても軍隊がやる。戦争体制は維持されている。 |

*【福沢諭吉】
《徳川の治世を見るに(中略)日本国中幾千万の人類は、各幾千万個の箱の中に閉され、又幾千万個の墻壁に隔てらるゝが如くにして》(『文明論之概略』) *【渡辺崋山】 《天下と申〔す〕大なる箱、諸侯と申〔す〕小なる箱、士と申〔す〕内のしきり、活物世界を死物にて治め候世の中》(「退役願書之稿」) |
|
*【武家諸法度】
《養子者同姓相応之者を選び、若無之においては、由緒を正し、存生之内可致言上》(天和3年) *【諸士法度】 《同姓之弟同甥同従弟同また甥并従弟、此内を以て相応之者を撰べし。若同姓於無之は、入聾娘方之孫姉妹之子種替之弟、此等は其父之人がらにより可立之。自然右之内にても、可致養子者於無之は、達奉行所、可請差図也》(寛文3年) *【武家諸法度奥書】 《女子は知行を取公義をつとむる事なければ、男子のなき家はそのもの死て後、家人みな道路にたゝむとす。此ゆへに武家の業を勤、またわが家業を相継、家人をも養ふべき器量あるものを見立、わが家の客となし、娘を以て飲食衣服の妾となしつかへしむべし。男子も人の余男にて継べき家もなきものは、上は主君に仕へ下は人の家をたすくる事なれば、女家に客となる事、道理にたがふべからず》(寛文4年 久世広之) 

*【細川家記】
《忰両人有之候へ共、幼年ニ而いまた御奉公相勤可申躰無御座候。私果候已後、領国之儀ハ差上可申候。子供之事ハ、成長仕候上御奉公可相勤者ニ無御座候ヘハ、可仕様無御座候》 *【寛政重修諸家譜】 《慶安三年四月十八日遺領を継、このとき重臣等を営にめされ、肥後国は西国の藩屏なれば、幼小の六丸に任ぜられがたしといへども、三斎以来の忠節、ことには光尚終りにのぞみて請申所も神妙に思召るゝにより、遺領の地相違なく六丸に賜ふ所なり》(巻一〇五 細川綱利条) |
A――そうなると、家督の世襲相続という問題も、よくよく考えるべきことですな。 C――家業や家督という観念は中国にはないし、養子を取って家を継承するという習慣もない。他姓の人間を家に入れて家が存続するという観念は、中国人からすれば異様な蛮習だろうね。 B――そもそも「家」と同じ文字を書いても、中国と日本では内実はかなり違う。あっちは千年以上も続く家譜をもつが、それは言わば「気」の連続した流れだね。他姓の養子を入れたりすると、その流れが断絶する。それに、他姓の人間が自分の父祖でない先祖の祭りをやること自体、道に外れておる(笑)。 C――日本の家は、中国・朝鮮のシステムに比較すれば、かなり異常なものだ。日本の家をアジア的社会システムということで、一つに括るのは実態に反する。家の内容が違うのに、儒教でまとめようとするのが、そもそもできない相談だった。 B――だから日本には本来の儒教は存在しなかった。ラディカルな儒者にさえ、自身養子が少なからず、先祖の祭りは仏教式でやる。本来の儒教からすれば、原則というものを知らない、ということになる(笑)。 D――日本の家のばあい、家業だからそれに「不器用」の者は長子でも嫡子になれない。商家でも養子を取ったのは家業資質の問題だ。大名の場合だと、近世初期には特にそれが問題になった。嫡子があっても相続時それが幼少だと、これは問題。つまり、第一には、幼少の者では役が務まらない。第二に、その子がどの程度の資質があるか、幼少では見分けがつかない。だから、幼少者を相続人とするには、御家断絶という可能性があった。 C――それをかわすには、二通りの方法があったはずだ。一つは転封だね。つまり重要拠点なら、幼年君主では任に耐えないという理由で転封される。播州姫路の池田光政(1609~1682)が鳥取に転封になるのは、その例だね。もう一つは近親者から相続人を選任する。これも播州姫路の例では、武蔵に縁がある本多家のケースだがね、本多忠政の二男政朝が姫路城主となって七年、寛永十五年に死んだ。政朝の男子たちは幼少ゆえ、政朝の従弟・政勝(1606~1671)を城主に据えた。だが翌寛永十六年(1639)本多家は大和郡山へ転封となる。相続はなかなか一筋縄ではないかない。 D――そうだね。これも武蔵所縁の細川家のばあいだが、武蔵死後四年ほどした慶安二年(1649)のこと、細川光尚(1619~1649)の病篤く余命いくばくもない。『細川家記』によれば、見舞いの上使・酒井忠勝に光尚が、突然領知返上を申し出た。理由は、自分の男子二人(当時、六丸(綱利)七歳、七之助(利重)四歳)は幼少で相続人とはなし難いとのことである。これは、ずいぶん大バクチだったね。 C――その場に、小倉の小笠原忠政(忠真 1596~1667)もいたらしい。細川と小笠原両家には姻戚関係がある。忠政の妹(千代姫)をいったん徳川秀忠の養女にして、細川忠利に嫁した。彼女は光尚の母だから、小笠原忠政は光尚にとっては叔父という関係だね。甥がそんなことを言い出したので、忠興・忠利が受けた領知返上とは「沙汰の限り」、これは病苦のせいだ、とその場をとりなそうとした。ところが、光尚は「いやいや決してそうじゃない」といって、幼少の息子二人、国柱になり奉公できる者になるかどうかはっきり見分けがつかない。そこで、公方様(将軍)に判断してもらえないか、という申し出をする。 B――結局、翌年、六丸(綱利)への相続が認められた。この領知返上の自滅的な申し出は、もちろん光尚末期の大バクチ。よくまあ、切り抜けられたものだと思うが、ここはやはり、小笠原忠真が座視するわけにはいかないと動いた形跡があるな。 C――それと、小笠原家家老の宮本伊織だろうね。小笠原忠真ができない根回しをやったようだ。ともかく、光尚はここで、筋を通した。能力なき者、あるいは将来それを期待し難い者、これを相続人にはできないという主張なんだ。これも家業・家職の考えからすることだね。 D――光尚には養子という線は頭からないね。だから、これはだれが仕組んだか知らないが、一発逆転を目論んだ大きな賭けだった。幕府が、「そうかい、それなら」といって、細川家を廃絶する恐れは十分あったからね。忠真が「沙汰の限り」というわけだ(笑)。 C――細川家は丹後で大名に取り立てられた。その後九州豊前小倉、そして肥後熊本。幽斎からたかだか四代だよ。決して土着大名ではない。領地相続は更新制で、一回ごとに賭けをするわけだ。こういう意味では、大名家もキツい条件だった。 |
|
A――世襲制、とくに養子でもかまわないという日本に特徴的な世襲制は、家業・家職、それと持分の意識ですな、先祖が戦功をあげて主君の御家創業に貢献した、それが根拠ですな。となると、主家も恩義があるわけだから、その恩賞を途中で廃止できない。 D――相続を認めないのは、相続者を擁立できない場合か、それともよほどの不品行・失策があった場合だね。しかし、それ以外は勝手に相続を放棄させられない。家臣団が黙っていない。 B――それが組織の運営にとって、抵抗力になってしまう。世襲組織は決して効率のよい組織ではない。それが近代的なものの見方。世襲は非効率な組織システムではない。 D――もともと世襲は、親が戦死しても、子が親の戦功を報いられるというシステムだ。戦死したら、あとはパアというのでは、だれも命がけで参戦しない。戦死しても、子どもたちに戦功が報いられる、それが世襲の原点だ。 B――ところが、家職である「持分」「自分」の世襲ということは、今日の会社企業で言えば、総務部長の息子が総務部長になる、工事課長の息子が工事課長になる(笑)というのを約束されているというのと同じだな。そうすると、現代人の感覚なら納得できない、不条理なシステムだというわけだ。 C――そこには、「死」というモメントは入っていない。死は本来不条理なものだ。現代社会は死を排除しているし、死者は現存しないことになっている。これに対し前近代社会は、死者が支える社会だね。 D――上から下まで世襲が基本、というシステムは、そういうことだ。私的権利の根拠は先祖にある。ところが、武家でもせいぜい祖父や曽祖父までしか身元がはっきりしない。そこで系譜が捏造されるし、大いに需要があった。こんなことは中国や朝鮮ではありえないわけよ(笑)。 B――荻生徂徠あたりは、そういう世襲制を批判していたな。そんなのじゃ、まともな軍隊にはならないと。 C――徂徠の『鈐〔けん〕録』にあったな。秀吉時代の朝鮮侵略でなぜ負けたか、という分析をしているが、そのなかで、明の軍隊は志願兵で、実力主義だ、それに対しこっちは世襲だ、これでは勝てないという話か。しかし、それは徂徠の頃のことで、当時からすれば百年以上前の話だね。 B――荻生徂徠は、日本軍が掠奪集団だった、戦国の気運のそままのヤクザな軍隊だったのを知らない。(朝鮮)半島から撤兵したが、十分掠奪してきておる。だから負けたという意識が日本側にはない(笑)。 D――第二次朝鮮侵略(慶長役)で藤堂高虎の捕虜になって、伏見までつれて来られて、藤原惺窩や赤松広秀とつきあった、姜沆〔カンハン〕という儒者がいるね。彼は元役人(前刑曹左郎)だが、荻生徂徠とはまったく逆の見解を示している。 A――壬申倭乱(文禄役)で、なぜ我々は緒戦であれまで簡単に日本軍にやられてしまったか、という話でしたな。 C――それは朝鮮の文官統制が強くて武班の立場が弱かったからではない。なぜ倭賊が強かったか、姜沆のレポート(看羊録・賊中封疏)はそれを、まさに日本の社会政治システム、封建制と世襲制に理由を求めておる(笑)。諸侯は領地を与えられるし、しかも世襲だ。日本の諸侯は家臣団、つまり私兵をもっている。朝鮮では私兵なんぞもてない、あたえりまえだが(笑)。 B――李氏朝鮮は朱子学に則った、まったくの中央集権の官僚制だ。役人は赴任してきても、すぐに転勤だ。居着かないし、権力形成を殺ぐために居着かせない。司令官は自分の軍事組織をもたない。軍隊は恒常性をもたない。これじゃあ命がけの防衛はできないというわけだ。 A――中央が派遣する以外に軍隊組織はないから、多勢に無勢で、みんな逃亡してしまう。結局、人民の愛国的義兵、非正規軍が雨後のタケノコのように出現して、ゲリラ戦を展開した。 C――それだって、最初は私兵すなわち反乱だと言って、弾圧しにかかった(笑)。ようするに、姜沆は日本の封建制と世襲制に、朝鮮の中央集権の官僚制とは異質のシステムをみて、それが倭賊が強い理由だとみておる。 B――戦国日本とは違って、平和を謳歌していた李氏朝鮮は、じつは派閥間抗争の熾烈な世界だった。戦争はしないが、足の引っ張り合いをして派閥抗争に明け暮れていた。平和な世界というものは、どこでもそんなものだ(笑)。 D――日本の封建的世襲制は、平和な時代でも特異だね。中央に人材を集める科挙もないし。 C――そもそも中央たる京都が「空虚な中心」だった。実権は東武にある。将軍が支配者だが、対朝鮮外交でも「日本国王」たることを自ら否認する(笑)。これはアジアの中でも分かりにくい特殊な政治体制だな。 D――元禄以後、いわゆる藩政の時代になると、実力主義の時代ではなくなる。個人の図抜けた能力は必要ではない。組織が組織として動くからね。部長の息子が部長になる、課長の息子が課長になるのを約束されている、そういうシステムでも、よいわけだ。システムが完成したということだ。それが安定した近世社会の姿だ。 A――現代の企業組織でも似たことはある。社員・職員は互換性がある。だれが勤めても大差ない。社長にいたるまで互換性がある。これを、もう少しだけずらせば、世襲制でもよいわけだ。出世したいという欲念さえなければ(笑)。 B――いまは、国会議員の多くが二世、三世。こりゃ世襲だわな。日本の政治システムが民主主義だというのなら、世襲制民主主義(笑)。こんな民主主義は他にない。珍重すべき畸形種だな(笑)。 D――それは民主主義とは異なるものだ。田舎の町議会のレベルで国政議会があるということ。これは決して前近代システムの復活ではない。 C――いやいや、前近代的組織でも、出世したい奴には、その道は開かれていた。そもそも人材登用は、江戸前期、少なくとも家光までは、幕府中枢の通例であるし、どこの大名家でもあったシステムだ。「出頭人」というやつだな。たいてい一代限りだが、相当出世できた。その中でも父子連続すると、その後世襲も可能になる。 C――武蔵の養子で、小笠原家の家老になった宮本伊織がそうだな。小笠原家は古い家系だから譜代衆も多くあろうに、伊織は新参ながら出頭人、主席家老にまでなったようだ。 D――出頭人が出るのは、やはりどこの藩政も慢性的な財政危機だからね、以前と同じ事をやっていては、御家がもたない。経済官僚に人材登用が多かった。それは幕府も同じだね。側用人から出世してくるのが、けっこういたわけだ。 B――御家騒動というのは、だいたい新君主側近の新参の出頭人の藩政断行から問題が生じる。既得権を主張する旧勢力と対立する。しかし宮本伊織のばあい、もちろん本人の器量があるにせよ、小笠原忠政のかなり露骨な贔屓があった。そりゃ文句のひとつやふたつは、譜代衆から出ただろう。しかし、伊織のバックには、とんでもない怪物がいた(笑)。 A――親父の宮本武蔵。これじゃ、だれも文句は言えない(笑)。 |

*【荻生徂徠】
《選兵ノ法ト云ハ、鉄砲ノ上手ハ火器隊トシ、弓、鎗、太刀ノ達者ヲ殺手隊トシ、馬上ノ達者ヲ馬兵トシ、強健ナルモノヲ歩兵トシ、其ノ内ニモ又、力ノ強キ者ヲ先鋒、中堅二用ヒ、足ノハヤキヲ選ンデ走使ノ役トシ、水練、舟戦二習タルモノヲ水軍トシ、軍法二長ジタルヲ将官トスル類ナリ。(中略)而ルニ、当今有様ハ、家筋ニテ昔ヨリ定メタル組分ヲ子孫相続スルユヘ、武芸モ一致セズ強弱モ揃ハズ、其ノ頭モ家筋バカリニテ軍法ヲモ知ラズ、士卒ヲモ操練セザレバ、何ノ用ニモ立ツベキ様更ニナキハ、不吟味ノ至リナラズヤ》(『鈐録』 第三 職制并に選兵)  睡隠姜沆先生影幀 |
|
D――藩の財政ということでは、家臣の給与の話になるが、知行制が擬制化して実質俸給制になってしまうという変化があった。本来は、大名の家臣団は寄合い所帯だし、家臣にはまた自分の家臣があって、大名配下にも御家が多数あるという複合集団だね。そこで、領地を配分して、あんたはここ、あんたはここ、という具合に、家臣も大小はあれ領主だね。家老などは城主である例も多かった。この領域は自分の支配地だという、領知。それが最初の形態。ところが、そういう自分の領地というのが、だんだん怪しくなる。 B――同じ千石取りでも、特定の村と対応しなくなる。一つの村でさえ複数の領地に細分される。そうなると、知行も帳面上だけのことで、土地と石高の関係は数量だけになる。自分がある分担領域に責任と支配権をもつというのではなくなった。 D――それは一見すると、家臣団の自律性を奪うことだね。ところが、実際はそうでもなかった。それはむしろ家臣たちにメリットがあるシステムだった。というのも、同じ領国内でも村々によって年貢のアガりは一律ではなく出来高に差が出る、その不公平を平均するためには、個別領地との縁を薄くした方が安定した収入が得られる。三ツ四ツという「免」を平均免にして、そこから割り出す。知行高を擬制の石高にしてしまうという方式だね。この事務的な合理化で、知行は擬制となった。だから、知行とは無縁な俸禄と大差なくなる。 C――そのことは一国一城制や城下町への集住と関係するのかも知れない。もともと家臣団は寄合い所帯で、家老クラスは同盟者・与力で、大名の譜代・被官ではない。近世初期は、そういうわけで、大名の用人奉行が行政を担当した。 A――それは何というか、側近集団、社長秘書室が取り仕切る形だね。 D――だから奉行たちの身分はそう高いものではなかった。番頭クラスだね。ところが、領国内の支城に拠っていた家老連中まで、城下に住むようになって、家老が大名の権力システムの中枢に入り込むようになる。これは、家老たちの領主性を希薄化すると同時に、大身の連中が御家の中枢に居座る恰好。だから、それまでの領国内分権は止揚されて、集権化されたのだが、その実権は家老集団が握ることになった。 A――主君の決裁は最終的なものだが、最高とは言えない。家老が用意した結論を認証するわけだから。 C――それもだね、もっと言えば、家老たちにしても、部下たちが用意して稟議上申してくる結論の中から選ぶか、それとも追認だね。とすれば、組織的決定は、家老以下のレベルで、すでになされているケースだってある。とくに日常業務に関しては、一般家臣である「平士」のレベルで決まる。 B――主君もそういう決定権の組織性は無視できないし、これを覆そうとすれば、側近によほど優秀な連中を集めなければ対抗できない。 |
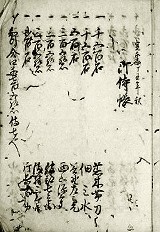 御侍帳 寛永14年 |
|
*【荻生徂徠】
《代官ト言役ハ(中略)文官ナル故、戦国ノ時分ニ是ヲ軽シメテ、腰抜役ト云タルヨリ、今地方ノ支配トナリ、小身者ヲ申附、然モ其下司ハ手代ト称シテ、殊外ニ賎キ者ヲ附置テ、年貢ノ取立ヨリ外ニ肝心ナルコトハナシト心得ルコト、以〔ノ〕外ノ事》(『政談』) *【マルクス】 《日本は、その土地所有の純封建的な組織とその発達した小農民経営とをもって、多くはブルジョア的偏見により書かれた我々の歴史書よりもはるかに、ヨーロッパ中世の姿に忠実な像を示している》(『資本論』) *【太宰春台】 《今ノ大将軍ハ、海内ヲ有チ玉ヘバ、是則日本国王也。サレバ室町家ノトキ、明ノ永楽ノ天子ヨリ、鹿苑院殿ヲ日本国王ト称シテ、書ヲ遺リ玉ヘリ。当代ニハ、東照宮ヨリ山城天皇ヲ憚ラセ玉ヒ、謙退ニ過テ、王号ヲ称シ玉ハズ。謙遜ハ誠ニ盛徳ノコトナレドモ、国家ノ尊号正シカラザレバ、文字ニアラハシ書籍ニ載ルニ及デ、何トモ称シ奉ルベキ様ナシ》(『経済録』)  後水尾天皇二条城行幸 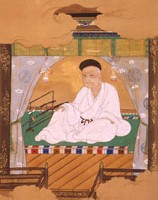 狩野探幽筆 東照大権現像 |
D――それから、武家支配は軍事政権で、軍人支配の政治システム。「士農工商」というが、朝鮮の儒家などから見ると、この「士」というのが変だ。決して本来の「士」ではない。そこで、「士農工商」じゃなくて、「国に四民あり、曰く兵農工商」と書いてしまう(申維翰『海游録』)。そういうわけだから、日本の封建制はアジア的視野からすると、かなり偏頗な形態だね。 A――中国モデルでは、「士」は科挙という試験にパスしたエリート文官で、皇帝から任命されて、彼らが全国各地を統治する。日本では武士という暴力団が、将軍という武家の棟梁から朱印状をもらって統治する、何という野蛮な東夷だ(笑)。 C――日本には語の正しい意味での「士」は存在せず、軍人である「兵」が支配している。文治ではなく軍事政権だ。かのマルクスは、封建制研究に関連して、いま封建制が残っているのは、日本だけだ、日本が具体例を提供してくれる、とかいうようなことを、どこかで書いていたね。しかし、残念ながら、日本の封建制はかなり例外的形態だ。 A――どうしてそんなデフォルマシオン(変形・歪形)が可能だったのか、という問題。 B――それは要するに、覇権者が王権を簒奪できなかったからだ。天皇制を廃棄できなかった。あるいは廃止しなかった。二重政権のままだ。それは、頼朝以来の武家政権の形態だね。 C――中国のように覇権者が王権を簒奪しないということで、大義名分論をかわした、回避できたということかね。最終的には、天皇から委任されたという形式をとって、実質覇権の政治支配を正当化できる仕組みだ。 B――そのばあい、古代天皇制あるいは近代天皇制のような、人民のだれもが天皇の臣下という構造を否定しているね。日本的封建システムだと、主従関係は直接的である。これを公式化して言えば、主人の主人は、主人ではない(笑)。 A――主人の言うことは聞いても、主人の主人の命令は聞く筋合いはない(笑)。 D――それは先に話が出た、福島正則改易の一件で、処分が決まって改易となると、まず先に家臣たちがとった行動は籠城だ。いつでも一戦交える用意があるぞ、という態勢、構えだね。城の明渡しに要求に対して、主君自筆の文書を見ない限りは、武装解除に応じない、という返事なんだ。主君の命令は聞いても、幕府の命令は聞かない。主君からそうしろと命令されない以上は、言うことは聞かない、そういうスタンスだ。 B――幕臣でないかぎりは、それが当然である。赤穂事件の連中も同じだね。彼らの主人は死んでしまった。となると彼らに命令を下せる人間はいなくなる。だれも連中の行動を阻止できない(笑)。しかしそれが実態だった。 D――万人を規制する普遍的な法支配は存在しない。主人の主人は、主人ではない。だから将軍の命令でも、直接には従ういわれはない。幕府の権力は、諸大名の家臣には直接及ばない。それと同じく、天皇の権力は、幕府の頭越しに諸大名へ作用しない。これも頼朝以来そうだったが。 A――この仕組みは天皇制という王権システムにとって、やっかいな阻害要因だね。何しろ棚上げされて、普遍的支配を貫徹できないのだから。 C――しかしそれは、各藩諸家のミクロ政治でもそうだったのじゃないか。最初、成り上がる過程では、主人は軍事組織の大将で、いわば親政決裁する形態だね。ところが大名になって、しかも太平の世になり数代経つうちに、諸家は家老支配になる。重臣たちの合議で事は決まる。主人は事後承認するだけで、実権は家老たちにある。 D――暗君には家老たちが諫言するが、そうしてもダメなら、主君を押込めたり、更迭したりする。そうなると、主従関係における忠誠も決して個人的なものではない。取締役会が社長をクビにできるのと同じことだな。御家という企業もしくは共同体を護るために、主君更迭をするわけだから、御家の方が主君個人より大事なんだ。 A――家臣たちの運命共同体。 B――だから主君への忠誠というのは、創業者のようにその主君がカリスマ性をもちえた場合に限る。凡庸な二代目以降の主人への忠誠は、ある意味では形式的なものだ。忠誠というフィクションを演じるのだな。 D――徳川幕府が中央集権的な強固な支配体制を構築したのは、たしかだが、それを将軍専制による一元的支配だとみると、間違いだね。まず大名だけで数百あり、それが一定の自律的政府であり、しかもまた、それぞれの大名家内部で、同じように「自分」をもつ自律的武士たちがいる。無数のブロックで構成されるが、全体というものはない。 C――そこで、言うべきは、近世の武士たちが封建道徳、とくに儒教的な道徳によって縛られていたというのは、歴史物語上のフィクションだということ。封建社会の支配イデオロギーとしての儒教というのは虚構だろうね。本当は、もっとミクロな権力関係、下部構造の方をきちんと把握しなければならない。 |
|
D――そこで、丸山真男の話になるが、日本の場合には、「君、君たらずとも臣、臣たらざるべからず」というのが臣下の道であった、上位者そのものには道理という規範が適用されない、云々(日本人の政治意識)と彼は言うがね、これは今日の以上の話からすると、とんでもないデタラメだな。 A――そういう一見わかりやすい略図は俗耳に入りやすい(笑)。丸山の権力関係論はまるで俗説だ。 C――だいたいがだ、文脈がちがう。「君、君たらずとも臣、臣たらざるべからず」というのは一般論じゃなしに、武家が天皇制を見る視線なんだよ。無能で堕落した天皇とその宮廷、どうしようもない連中だが(笑)、おれたちは臣礼をとるよ、というスタンスで書かれている言葉だ。そういう文脈を外して一般化してはいけない。 B――それで、丸山真男『日本政治思想史研究』(一九五二年)のことだが、これは戦後の思想史研究に大きな影響力をもったね。だれもが一度は読んだものだ。しかし、徳川支配の封建社会の成立と共に、朱子学が代表的な政治的社会的思想たる地位を占めた所以は、《朱子学の「自然的秩序観」が勃興期の封建社会に適合したこと、それだけでなく、それがとくに勃興期封建社会に適合したことに由来するのである》と書くところは、今にして思えば、ずいぶん粗雑な話だったな。 C――丸山のイメージでは、《身分関係が整然と確立し、すべての生活様式がその線に沿つて類型化された点で世界史上にも「模範的」な我国近世封建社会》となるが、そんなに秩序立った、かっちりした社会であったはずがない。これは偏見だね。 B――そういう秩序社会だから、《社会関係を自然必然的な所与と見る意識形態がいかに普遍化する素地をもつてゐるかは容易に推測しうる》というが、このあたりムチャな論理だな。だれが、社会関係を自然必然的な所与と見たのかい。とくに近世初期、丸山の言う勃興期封建社会は、実力主義のいわば野蛮な世界だ。大名に成り上がるわ、あっというまに潰れるわ、金融や請負や酒造で成金ができるわ、まだまだてんやわんやの状況だ。そういう近世初期をスタティックに見てしまうのは、まったくの間違いだ。 C――丸山が「勃興期封建社会に適合した朱子学」というのは、要するに林羅山のことだな。しかし羅山の思想を、こういう《自然ノ理ノ序アルトコロハ此上下ヲ見テシルベシ》といった部分で要約してしまうのは、およそ乱暴な話だ。同じことは、羅山は「自然」、徂徠は「作為」という図式的線引きにも言える。 D――自然から作為へという教条主義的なこの図式を、どれほど多くの者がオウムのように反復したか、知れない。しかしな、それを言うなら、作為から自然へという逆のコースなのだよ。近世初期ほど露骨な作為が横行した時期はあるまい。 A――この自然から作為へ、中世的世界像から近代的世界像へという図式は、フランツ・ボルケナウ(Franz Borkenau 1900~1957)から頂戴した。丸山自身、後記で《なお翻訳で読んだF・ボルケナウの『封建的世界像から市民的世界像へ』もすくなからず稗益した》と書いている。当時、ボルケナウはかなりウケていた。戦前に前半の邦訳が出ておったくらいだ。もちろん、後に丸山は、ボルケナウに対し若干批判めいたことを書くようになったが。 B――ここで丸山真男は「適合」という言葉で、スターリン主義的な反映論を回避している。しかし「適合」とは、いかにも日和見主義的な用語だった。 D――市民主義者、というのはとっくの昔に死語だがね(笑)、そういう意味では、丸山真男の市民主義というか、そのプチブル性がよく現れた用語だと言えたね。 C――いや、これは実は、新渡戸稲造『武士道』かもしれん。そっくりな箇処がある。しかも邦訳で、「適合」という言葉も使っている。 A――なるほど、そうかもしれん。いわゆる朱子学適合論は、新渡戸プラス、ボルケナウか。 C――ボルケナウはフランクフルト学派。同じ頃、マルクーゼやホルクハイマーがいた。丸山『日本政治思想史研究』のイデオロギー論は、同じくマンハイム(Karl Mannheim 1893~1947)だというが、立論のシナリオはボルケナウの図式をパクっておる。 B――もちろん、アドルノやホルクハイマーなどは丸山の視野に入っていない。 D――だけどな、「適合」と言う丸山真男自身にコンフォーミズムがあったぞ(笑)。「東大教授丸山真男」には僧形を甘受した儒家羅山のイメージもあるしな。その秩序志向ということでは、60年代末、丸山が反動勢力の頭目みたいなポジションだったな。それからずいぶん時がたった。今や日本の思想界は完全に反動化しておるから、丸山真男が偶像化されておるというのも当然なわけだ(笑)。 B――「多くはブルジョア的偏見により書かれた我々の歴史書」というマルクス先生の評言は、この丸山思想史論にも進呈したい(笑)。丸山の場合は市民主義的偏見だがね。近世初期、思想界は朱子学によつて殆ど一色にぬりつぶされた、と丸山は言うがね、どこからこんな話になるのやら(笑)。禅坊主はますます意気盛んだし、一向一揆残党の真宗は大勢力になっている。そういう仏教思想にくらべると、朱子学はごくマイナーな思想だった。 A――統治において仁政というが、だいたい大名間でさえも、「仁」と言っても「は?」、何のことやら通じなくて、「慈悲」と言ってはじめて通じる社会なんだよ。 C――その点でも事実とは違うが、そもそも「朱子学的思惟」が、社会関係の「自然」への基底づけだという、そういう一種の自然主義に朱子学を還元してしまうのも、同じように間違いだな。自然から作為へという図式があまりにもアプリオリすぎる。丸山の憶見だな。 B――近世政治思想史という点では、丸山真男の朱子学論はマズいな。朱子を自然主義で要約できるわけがない。それに第一、羅山は徳川政権に正統性を見ていない。 D――近世初期はゴリ押しの露骨な作為。何しろ三河の奥から出てきた覇権者が、全国支配しようというのだから、正統性もへったくれもない。覇権主義を合理化できるのは、儒教本来の革命思想だよ。そこで「天道」が武家の愛好するところとなる。しかし天道を「自然」と見るバカはいない。そのはずだが、ここに一人いて、しかもそれを模倣する無数の論者が現れた。それが戦後政治思想の目立ったシーンだった。 B――朱子学が幕藩体制の支配イデオロギーだったというのは、戦後的な偏見謬説だね。とくに丸山真男が朱子学適合論を書いて、何となくそういう理解が支配的になった(笑)が、これは正しくない。朱子学は決して近世思想の主流ではない。 C――そもそも、朱子学が官学となる基礎を造ったとされる林羅山が、そうじゃない。羅山は家康以来徳川将軍の侍講だったようだが、これについては後人の批判がある。山崎闇斎(1618~82)は、羅山が将軍にきちんと尭舜の道、聖人の道を教えなかったと非難している。 A――羅山は将軍が理解できないとバカにしている、羅山は不忠なり、とまで言いつのる(笑)。 D――しかしながら、それが事実だった(笑)。闇斎の弟子だった藤井懶斎(1628~1709)は、林羅山が徳川家光に教える機会を逃がしたとして、これも羅山を非難する。家光が羅山に聞いても要領を得ないので、沢庵宗彭の方へ行っちゃったじゃないか、とかいう話だね。 B――しかし羅山自身も、僧形までしたのに、これは何だということだね。『大学』など朱子学の講義は聴いてくれず、兵学軍学の話ばかり要求される。朱子学を講義するどころではない。 C――あの羅山にして、無用の人の意識があるよ。「廃人」だと。 A――やはり、儒者に期待されたのは、中国文献のどこそこにこんな話がある、という知識の切売りだね。御伽衆なんだから、基本的には僧形、文献知識を供給する茶坊主でしかない。 D――「物読み坊主」というのは、往々にして誤解されているが、仏僧のことじゃなくて、坊主の恰好をした儒者のことだ(笑)。法印だの法眼だのという僧侶の位階を受ける。狩野派みたいな絵描きも同じ。坊主の姿かたちをして、廃仏主義者なんだ。 B――朱子学が近世の政治思想、なかでも政治支配のイデオロギーになった、というのは正しくない。そんな面倒くさい議論は採用されず、もっとシンプルに覇権支配を正当化・合理化する論理はないのかという諮問だね。 C――ところが、朱子学、むしろ宋学といってよいが、これは禅の影響を受けた、きわめて個人主義的でアナーキーな思想だ。しかも朱熹となると、主知主義的認識論哲学で、「格物致知」のいわゆる客観主義的唯心論。これが統治原理になるはずがない。日本で儒学が政治思想になるためは、いったん朱子学から自由になって、「古学」として反動化しなければならないわけだ(笑)。しかしこれは近世初期ではなく、次世代の連中の仕事だね。 |
 丸山真男(1914~1996)
*【丸山真男】
《日本の場合には、「君、君たらずとも臣、臣たらざるべからず」というのが臣下の道であった。そこには客観的価値の独立性がなかった。人間の上下関係を規定するところの規範が、客観的な、従って誰でも援用できる価値となっていない。(中略)上位者そのものには道理という規範が適用されないのである。恩恵を垂れるということはあっても、これを下から要求することはできない。というのは、仁・徳が権威者と合一しているから、権威者の思し召し如何ということのみによっているからである》(「日本人の政治意識」 1948年) 《徳川封建社会の成立と共に、朱子学がいはば代表的な政治的=社会的思惟様式たる地位を占めた所以は、そこに含まれた自然的秩序観が勃興期封建社会に適合したばかりでなく、それがとくに勃興期封建社会に適合したことに由来するのである。身分関係が整然と確立し、すべての生活様式がその線に沿つて類型化された点で世界史上にも「模範的」な我国近世封建社会の下に於て、社会関係を自然必然的な所与と見る意識形態がいかに普遍化する素地をもつてゐるかは容易に推測しうる。「家」――最も厳密な意味での自然的秩序――の公法的重要性、身分の法律的乃至事実的世襲、格式門閥の広汎な支配、租税及刑罰に於ける連帯責任、これらは悉く社会関係を以て人間の自由意思を以て如何ともし得ない自然的運命的な関係と映ぜしめるモメントとなるのである》(『日本政治思想史研究』) *【新渡戸稲造】 《厳密なる意味において道徳的教義に関しては、孔子の教訓は武士道の最も豊富なる淵源であった。君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友間における五倫の道は、経書が中国から輸入される以前からわが民族的本能の認めていたところであって、孔子の教えはこれを確認したに過ぎない。政治道徳に関する彼の教訓の性質は、平静仁慈にしてかつ処世の智慧に富み、治者階級たる武士には特に善く適合した。孔子の貴族的保守的なる言は、武士たる政治家の要求に善く適応したのである》(新渡戸稲造『武士道』1899年) *【丸山真男】 《ここでの問題は朱子学自体ではなく、徳川幕府が戦国の下剋上の動乱状態を完全に鎮定して、将軍より武家奉公人に及ぶ武士団内部の階統を編成し、進んで封建的主従関係を被支配階級の内部にも拡張して、上下を貫通するヒエラルヒー的原理の上に鉄の如き統制力を揮つた近世初期に於ける朱子学なのである。「天ハ上ニアリ地ハ下ニアルハ天地ノ礼也、此天地ノ礼ヲ人ムマレナガラ心ニヱタルモノナレバ万事ニ付テ上下前後ノ次第アリ、此心ヲ天地ニヲシヒロムレバ君臣上下人間ミダルベカラズ」(三徳抄下)といひ「天ハヲノヅカラ上ニアリ地ハヲノヅカラ下ニアリ、已二上下位サダマルトキハ上ハタツトク下ハイヤシ、自然ノ理ノ序アルトコロハ此上下ヲ見テシルベシ、人ノ心モ又カクノゴトシ、上下タガハズ貴賎ミダレザルトキハ人倫タダシ、人倫タダシケレバ国家ヲサマル、国家ヲサマルトキハ王道成就ス、コレ礼ノサカンナルモノ也」(経典題説)といふ羅山における自然法の窮極的意味が現実の封建的ヒエラルヒーをまさに「自然的秩序」として承認することにあるのは当然であらう。さうして朱子学に内在するこの「自然的秩序」の論理こそ勃興期封建社会に於て朱子学を最も一般的普遍的な社会思惟様式たらしめたモメントであつた。(中略――中江藤樹「翁問答」)かうした説明のいづれもが五倫の、一方宇宙法則(天理)への、他方人性(本然の性)への二重の自然化といふ宋学的自然法思想にその窮極の論理を仰いでゐることには変りはないのである。かくして近世封建社会成立後、最初にその基礎づけとして登揚した思惟様式は自然的秩序の立場として総括しうるであらう 近世初期朱子学によつて殆ど一色にぬりつぶされた思想界も中江藤樹が晩年に陽明学を唱道し、やがてこの学派はその門弟、淵岡山や熊沢蕃山によつて飛躍的に発展せしめられ、更に山鹿素行と伊藤仁斎は夫々江戸と京都に於て殆ど同時に古学を創始するなど、漸く分化の兆候を示すに至つた。彼等の理論は朱子学の体系的構成の上に夫々注目すべき内面的変容を与へ、とくに蕃山や素行は初期朱子学者に乏しかつた政治的社会的現実の経験的考察に於てかなり貴重な成果をあげた。しかしながら社会関係の「自然」への基底づけといふ点では彼等は依然として朱子学的思惟の埒内を超えなかつたのである》(『日本政治思想史研究』) *【山崎闇斎】 《林氏〔羅山〕は何人ぞや。其の不孝は世を挙げて知る所なり。且つ四君に歴事して、尭舜の道を君前に陳ぜず。是れ君を敬せざる者なり。曾て吾が君は能はずと謂ふか、是れ君を賊する者なり。不敬と賊は、不忠これよりは大なるはなし》(「弁林道春本朝綱目」) *【藤井懶斎】 《大猷院殿〔家光〕、嘗て林道春〔羅山〕に問ひて曰く、「聖人の道は如何にせば、則ち行はれん」と。春、其の道を尽くさずして、反りて言ふ、「今の人は容易に行ふを得ず」と。殿下、此れより禅を彭沢庵に聞く。儒者皆、春に切歯す》(『睡余録』巻上) *【林羅山】 《余が如き者、草木と同じく朽ち、瓦石と斉しく棄てらる、天地の間の一廃人なり。円鑿方枘、時に遇はず》(羅山文集) [文字化け注記] unicode文字使用のため、文中「?」と表示される場合あり。当該Web表示制約文字は「木へん+内」(ゼイ、ほぞ)  狩野山雪筆 朱子像 |
|
*【山鹿素行】
《我れ等事幼少より壮年迄専ら程子朱子の学筋を勤め…(中略)漢唐宋明之学者之書を見候故、合点不参候哉、直に周公孔子の書を見申候て、是を手本に仕候て学問の筋を可申存》(『配所残筆』) 《若し聖人の道を不知して、儒の行は如此、聖人の家つくりは如此と形を立てば、儒者の宅は寺院の如く、儒士は僧沙門の体になりて、何のいたしなすこともなく、深衣を着しかんむりをいたゞき、記誦詞章を玩んで世務日用に施すべきなく、文武農工商に用ふべき道なく、只だ出家の女犯肉食して国の遊民たるにことなるべからざる也》(『山鹿語類』)  山鹿素行像
*【太宰春台】
《初め山鹿子、兵法を談ずるを以て赤穂侯に事ふ。良雄らこれに従ひて学ぶ。吉良子を殺さんと謀るに及ぴて、ことごとくその法を用ふ。ここを以て、計に遺策なく、能くその事を済す。然れども、怨む所を知らざるは、大義において闕くることあり。山鹿氏の教、乃ち爾り》(『赤穂四十六士論』) *【山鹿素行】 《私に云く、楠正成云ふ、一気に三あり、始中終是なりと云々。然れば、始気に三段、中気に三段、終気に三段あるべければ、其の察気を綿密ならしめずんば、真実の勝負をしる事かたかるべし。正成は此の気をよく知りけるにや、天王寺へ出張のとき、両六波羅より隅田、高橋五千余の軍兵を率し相向ひけるを、わざと渡部の橋を引かずして、軽兵少し計りさし出し、京都の軍勢を相待ちたり。是を敵の気をまはすと云ふなり。其の故は…》(兵法奥義)  湊川神社 嗚呼忠臣楠子之墓 元禄4年 水戸光圀建立  大楠公像 皇居前広場  楠 大石ニ化スル圖 曲亭馬琴 楠正成軍慮智恵輪
*【太平記】
《抑、元弘以来、忝も此君に憑れ進せて、忠を致し功にほこる者幾千万ぞや。然共、此乱又出来て後、仁を知らぬ者は朝恩を捨て敵に属し、勇なき者は苟も死を免れんとて刑戮にあひ、智なき者は時の変を弁ぜずして道に違ふ事のみ有しに、智仁勇の三徳を兼て死を善道に守るは、古へより今に至る迄、正成程の者は未無りつるに、兄弟共に自害しけるこそ、聖主再び国を失て、逆臣横(ま)に威を振ふべき、其前表のしるしなれ》(巻十六 正成兄弟討死事) *【山鹿素行】 《古今兵を論ずるの士は、殺略戦陣を専らとす。故に兵法は一技の中に陥る。天下の間は士農工商に出でず、士は農工商を司り、士の至れる者は帝王・公侯なり。士の業を兵法と曰ふ。若し兵法を以て、修身正心治国平天下の道を尽さずんば、兵法は用ふるに足らず》(兵法奥義) *【北条氏長】 《居城を主として我これに居り、人数を四方に分けて、その境目を守らしむるは方円なり。その道を行ひ、道理によってこれを下知するは、神心の曲尺なり》(『士鑑用法』) *【山鹿素行】 《事理は方円を出ず、方円は天地なり。天地の理を知るは、惑はず、懼れず、憂へず》(兵法奥義) *【五輪書】 《第二、水の巻。水を本として、心を水になる也。水は方円のうツわものに随ひ、一滴となり、滄海となる。水に碧潭の色あり、きよき所をもちひて、一流のことを此巻に書顕す也》(地之巻) |
B――そういう古典回帰を通じた朱子学批判、学問の筋を正すということは、山鹿素行(1622~1685)のような兵学者から顕在化する。朱子学から自由になるということは、中国の絶対性が崩れて中華思想から自由になるという環境ではじめて可能だね。そこで素行の「中朝」論がある。世界の中心が解体される。 D――その朱子学批判へのドライヴは、アカデミックな解釈学ではなく、むしろ「日用事物」の役に立つ学問への希求だよ。観念論ではなく現実主義、とくに統治技術としての政治学への欲求だね。朱子学批判は、観照主義的な認識論じゃなくて世俗的な実践論を、という要求なんだ。 B――林羅山と荻生徂徠の相違、これは自然主義と作為主義の相違ではない。丸山真男とその亜流、あるいは丸山史学批判者たち、こうした連中の視野から抜けておるのは、徂徠が兵学者でもあったということだ。道徳からフリーな政治というのは、モダンでもなんでもない、アモラルな兵法思想のポジションだよ。 D――だから、ここでの両者の対立は儒学と兵学ということだろう。もし徂徠思想に作為主義があるとすれば、それは軍学者のスタンスだね。軍事にあって、自然主義では通用しない(笑)。 A――山鹿素行の場合、軍事と政治は同じ実践ですな。これは占領軍の統治思想です。 C――占領軍の統治思想だから朱子学批判が可能なんだ。そこで、いまの問題に関連して言えば、武士道論には、軍学と儒学という区別は必要じゃないのか。軍学と儒学という異質な思想をごっちゃにしている論がいまだに多い。 D――ということだね。儒者は兵学を軽蔑する。話は飛ぶが、太宰春台(1680~1747)は『赤穂四十六士論』で、赤穂事件を、大義において欠けると、断罪している。そのなかで、山鹿素行が赤穂で仕官したとき、大石は素行に学んだ。吉良を襲撃したとき、ことごとくその兵法を使った。だから、計画は万全でうまく事をやりおおせたんだという。 C――春台は、彼の師匠荻生徂徠が「赤穂の士は義を知らず。その吉良子を殺すは、乃ち山鹿氏の兵法なるのみ」と言ったのを聞いたと書いているが、実際そう徂徠が言ったかどうか、わからんね。 B――《怨む所を知らざるは、大義において闕くることあり。山鹿氏の教、乃ち爾り》というところを見ると、山鹿素行は赤穂事件との結びつきで、かたや兵法において誉められ、かたや大義に欠けると批判される。 C――兵法軍事と大義は両立しない。だけど、それを認めてしまうのが儒者の敗北なんだ(笑)。 A――平戸の史料では甲州流の小幡(勘兵衛)景憲からの嗣書もあって、素行はいろいろ幅広く学んでいるが、ひとつは楠流兵法ですな。しかし楠流の伝説的元祖、楠正成が、これが問題なんだな。 B――楠正成を言い出すと、南朝正統論まで話が行ってしまうからね。日儒は、つねに天皇という王権システムを意識している。どう転んでも武家政権を正当化できない。水戸光圀(1628~1700)がそうだろう。武家の儒学は、南北朝以来、最初から天皇主義者なんだ。 C――水戸光圀は南朝正統論だね。南朝が正統だとすれば、それ以後の皇統は正閨じゃない。南朝正統説を強く出せば出すほど、天皇制の存在を否定することになる。幕末には皇統正閨論は不敬行為になるが、光圀が南朝正統論を大ぴらに言えたのは、徳川幕府が権力を奪取した革命政権だからだ。 B――『本朝通鑑』をまとめた林鷲峰(1618~1680・羅山の息子)なんぞは、光圀の意図に「おいおい、そこまでやるかい」という感じだね(国史館日録)。ラディカルな天皇主義が皇統を否定する。それが『大日本史』のパラドックスだな。 D――事実上は、足利幕府の成立で、もうすでに否定されているわけよ、だから『大日本史』の天皇は百代で終り。あとは武家王朝の時代なんだ。けれど、足利尊氏を逆賊にして、間違った歴史を糾すというかたちで、新しい幕府、徳川支配を位置づける。何しろ徳川は、足利に滅ぼされた新田の再来なんだ。 B――そこで、光圀にとって南朝正統論は必然だな。足利幕府の非正統性を強調することで、徳川幕府の正統性を主張しうる。しかし、ここはかなり危ない。両刃の剣だ。ラディカルな南朝正統論は、楠正成を称揚しても、足利尊氏も新田義貞も否定することになる。 A――水戸光圀は湊川(現・兵庫県神戸市)に、楠正成の墓碑を建ててしまう。それが「嗚呼忠臣楠子之墓」(笑)。元禄年間には、もうそんな気運だ。 B――楠正成は太平記読みのポピュラーな幅広い裾野があった。楠正成というのは、新田氏・徳川家にとって実にまずい存在なんだ。光圀はバカか(笑)、と見られるほど楠公に入れ込んでおった。 C――家康が「新田殿」になる。天皇への忠臣は一人でよい。それが新田氏・徳川将軍家だと。これは忠臣のポストの独占だな。しかし南朝正統論は、実は排他的な支配の自己矛盾だよ。 B――太平記読みから楠正成が流行する。そうすると、幕藩体制の支配理念は足元から崩れる。山鹿素行はそういう楠正成の政治的意味にかなり深くかかわるな。 D――義挙の後すぐに、大石良雄が楠正成と同一視されるね。これは大石良雄への山鹿素行の影響というより、世間にはもうそう見る視線があったということだ。 A――《楠のいま大石になりにける なほも朽ちせぬ忠孝をなす》だな(笑)。『江赤見聞記』だったか、こういう狂歌が当時あったそうだ。 B――大石良雄が山鹿素行に学んだとすれば、素行最初の仕官のときではなく、後の流謫中のときだろう。山鹿素行は赤穂で教えたが、軍記、とくに太平記の楠正成をめぐる一連の話で、《智仁勇の三徳を兼て死を善道に守る》というテーゼで浅野家中をアジったこともたしかだな。 C――後醍醐天皇はじめ宮方は徳なしとされるが、《死を善道に守る》というのは天皇制の道徳なんだよ。楠正成死して、聖主再び国を失い、逆臣がほしいままに威を振う、そういう時代になるという文脈だな。となると、そういう楠公神話の洗礼をたっぷり受けた浅野家の長矩が、吉良氏をどう見てたかということもある。吉良は足利氏一族につらなるが、それだけじゃなくて、家康が新田系譜を捏造するのに手を貸した裏切り者だ、これは逆臣足利よりもっとひどい(笑)。 A――とすれば、そんな奴が「高家」だといって、何を偉そうな顔をしておるか(笑)。 B――個人的にソリが合わなかったという他に、いわば赤穂の楠公信仰とでも言うべきものがあってだな、浅野内匠頭が常づね吉良を軽蔑しておったという可能性がある。とすれば、それが刃傷事件のそもそもの原因だ(笑)。 A――それはまた、赤穂事件に関する新説ですな(笑)。 D――山鹿素行の兵法のもう一つは、北条流兵法。素行が学んだという北条流兵法の北条氏長(1609~1670)のテーゼは、《兵法は国家護持の作法、天下の大道なり》(『士鑑用法』序)だね。北条氏長の政治論は占領軍の統治術だ。これに対し山鹿素行の論議は、氏長に比べると、言説がかなり抽象的になっている。 A――これは、武士道じゃなくて「士道」だという説もあるが。武士ではなくて儒教的な「士大夫」なんだと。そういう理念的なバイアスがかかるようになっている。 C――日本のばあいは「兵」はあっても「士」は存在しない。支配階級は「士」を擬装した「兵」でしかない。 B――北条流兵法というのは、北条氏長の出世人気で流行したようだが、氏長が「方円神心の一理」という原理を提起するね。これは兵法書通有の、前時代の秘教的概念と見られているが、そうでもあるまい。 C――「方円神心の一理」を悟らなければ、兵法もまた盗賊の法とならん、というがね、これは儒仏道の三教一致なんだよ。ミステリアスに考えるのは、当時の三教一致論を知らないからだ。だいいち、「方円」云々という言葉は、山鹿素行もこれを使用して、《方円の理を知る》と教えるが、武蔵も『五輪書』で使っている。ただし独特な用法だが。 A――「方円」は当時兵法の一般語彙だろう。氏長については、宮本武蔵と北条氏長が、相互に師事して互いの兵法を教え合った、という伝説まである。 D――それはないだろ(笑)。氏長の測量術は有名だが、一方でオランダ人から砲術を学んでもいる。そういうテクノクラートとしての測量術や西洋兵学の知見は、武蔵当時の兵学の状況として頭に入れておく必要がある。 C――しかし、山鹿素行へ赤穂配流を言い渡したのが北条氏長なんだ。氏長は大目付だからね。この師弟関係は、よくよくの因縁があるらしい(笑)。 |
|
B――ともかく、山鹿素行は、林羅山や北条氏長に学んだということになっている。素行は、儒学で兵学を確立した者というのが通例理解のポジションだな。しかしそこには、兵法という戦闘術が兵学という学問になるのが進化だという思い込みがある。 A――それは半端な学者のアカデミズムだ(笑)。儒者にとって躓きの石となるのは、やはり、「ようするに勝てばいいんだ」という戦国の論理ですな。 C――つまりは、孫子の《兵は詭道なり》というテーゼが躓かせるのだね。貝原益軒によれば、《合戦と云へば、とかく表裡たばかりを、軍の本意》という兵学者もいて、《兵は詭道なり。時の勢によりては、わが身方に対してもいつはりて表裡を行ひ、人の功をうばひ、或は国をみだして、逆にしてとるも、兵術においては害なし》とまで言うものもあるという(『武訓』)。こういう論理は悪取詭道だとして、これを克服しなければならないのが、太平の世の学者の運命だ。 B――結局、荻生徂徠までこの《兵は詭道なり》を克服しようとして、懸命に論じる始末。丸山真男を裏切って、徂徠は道徳的なんだ(笑)。 C――徂徠がやった解釈というのは、主客を逆にすることだ(『孫子国字解』)。詭すのは自分ではなく敵である。そうすると、兵は詭道なりというのは、敵に察知されず、見すかされぬように、千変万化定まりたることなきことが、徂徠の解釈する「詭道」である。それゆえ《詭道と云は、強ちにいつはりだますことばかりに非ず、千変万化して、敵にはからせぬことを云なれば、正道の戦も、千変万化の一つなり。或は正道を用ひ、或は表裡を用るこそ、真の詭道なれ》という。これはあからさまな詭弁だな(笑)。 A――とにかく騙すことは悪いことだ、という道徳があるからね。だれも彼も《兵は詭道なり》に躓く。 C――うむ、《moral》(道徳)であって《ethic》(倫理)ではない。倫理は善悪の彼岸にあるものだ。剣聖武蔵が偶像破壊されて、戦後「汚い武蔵」になったのも(笑)、まあ云えば、道学者流が戦前よりも支配するようになったということだよ。 D――しかし徂徠の取柄といえば、周知の如く『太平策』でかなり辛辣なことを言っている。治世、つまり太平の世になれた兵家者流に対する批判だね。武士道というのは、だいたいここでトドメを刺されている。なかでも《只戦ノ物語、切合ノ仕組ヲ覚ヱ、或ハ匹夫ノ先途トスル武芸ヲノミ武士ノ道ト心得、ソレサヘ其芸術ノ師、皆治世ノ人ニテ、治世ニテコシラヘタルコトナルトハシラヌヤウナル》とあるのは、おもしろい。太平の世になって拵えたものが武士の道だと勘違いされている。「文学」がない、歴史を知らないんだという。 B――あるいは、武士道というのは戦国の風俗だよ(太平策)というあたりね、このばあい武士道はすでにネガティヴな意味合いだね。武士道はナイーヴな戦国の風俗として、ある意味で軽蔑されるようになっている。 C――それも、軍略はあるが軍法がない、という原理的な批判からだね。さきほどの話のように、『鈐録』で彼は、文禄慶長の役、どうして朝鮮で明軍に負けたんだ、ということだね。明朝は万暦年中で治世の只中、こっちから高麗へ渡った将士は、みんな戦国の百戦練磨、「すり磨かれた生粋の武士ども」。軍勢も五分五分、しかし明兵と遭遇して、何れも敗北した。これはどうしてなんだと。 B――徂徠の世代になると、たしかに武士道がネガティヴな対象になる。「すり磨かれた生粋の武士ども」の戦国武士道の敗北じゃないか、というわけだ。『甲陽軍鑑』はむろん戦記軍記を読んで、その内容を知っているわけだ。となると、ネガティヴな対象としての武士道は、戦国武士道ということになる。 C――ところが戦国期には、「武士道」という言葉は一般にはない。だれもそんな言葉を使っていないし、そんな概念も知らない。 A――すると、武士道なるものは、いつ存在したんだ、ということになる(笑)。 D――武士道以前と武士道以後はあるが、武士道のポジションはない。ようするに、武士道という概念が確立するのと、武士道というものが否定対象になるのとは、ほぼ同時なんだ。たとえば戦後、軍国主義という概念が発生するのと、軍国主義というものが否定対象になるのとは同時、というのと似ている。 C――そういうわけで、今日の話の振出しに戻る。少なくとも、武蔵には「武士道」という言葉はない。武士道って一体何のことだい(笑)。武蔵サイトの我々からすれば、武士道って一体何のことだい、そんなもの知らないよ、というスタンスがちょうどよい(笑)。 |
*【孫子】
《兵者詭道也。故能而示之不能、用而示之不用、近而示之遠、遠而示之近、利而誘之、乱而取之、実而備之、強而避之、怒而撓之、卑而驕之、佚而労之、親而離之、攻其無備、出其不意。此兵家之勝、不可先傳也。 夫未戦而廟算、勝者得算多也。未戦而廟算、不勝者得算少也。況於無算乎。吾以此観之、勝負見矣》(始計篇) *【荻生徂徠】 《敵よりは是をたばかると思ふゆへ、いつはりとも訓ずるなり。(中略)兵は詭道なりと云は、軍の道は、とかく手前を敵にはかり知られず、見すかされぬ様にして、千変万化定まりたることのなきを、軍の道とするなり》《詭道と云は、強ちにいつはりだますことばかりに非ず、千変万化して、敵にはからせぬことを云なれば、正道の戦も、千変万化の一つなり。或は正道を用ひ、或は表裡を用るこそ、真の詭道なれ》(『孫子国字解』) 《兵家者流ノ卑キ方ニテイワンニモ、米穀ヲ蓄ルコトヲバシラズシテ金銀ヲ積貯へ、武士ヲ一城ノ内二籠メヲキテ皆柔弱ノ公家トナシ、吾国ノ総人数減少シタルコトヲ知ラズ、高禄ノ士モ肝心ノ場二至リテハ皆中小姓同前〔然〕ニナリナンコトヲ知ラズ。只戦ノ物語、切合ノ仕組ヲ覚ヱ、或ハ匹夫ノ先途トスル武芸ヲノミ武士ノ道ト心得、ソレサヘ其芸術ノ師、皆治世ノ人ニテ、治世ニテコシラヘタルコトナルトハシラヌヤウナル、是皆文学ナクテ、今ノ習俗ノ内ヨリ目ヲ見出シタル過也》(『太平策』) 《軍略は器量による。節制は修練にあり。異国の兵書も七書は軍略多くして節制少し。明朝の名将粛大猷・戚南塘が書は専ら節制を説いて、軍略をばいはず。又、吾国近代の名将は、何れも軍略の名人にて節制を知り給はず。是によりて、異国の書に吾国の軍立を評制して、軍に法なく人々自戦をなすといへり》(『鈐録』序) 《太閤高麗陣の節、明朝は万暦年中にて、治世の只中に候。此方より高麗へ渡りたる将士は、皆百戦の辛苦を歴て、すりみがゝれたるきつすいの武士どもに候。人数も、明兵も十分、和兵も十分(五分五分)、対様の勢にて候。されども明兵に出合ひ、何れも敗北致し候》(『鈐録外書』巻六)  荻生徂徠像 |
|
――さてさて、武士道なるものは、いつ存在したんだ、武士道って一体何のことだい、そんなもの知らないよ、というように、お話がかなり煮詰まってきましたところで(笑)、残念ながら、今回は時間切れです。この続きは次回にさせていただきます。 D――おやおや、もうそんな時間か。今日はなかなか面白い話ができた。途中で終るのは心残りだが(笑)、いずれまた、やりましょう。 B――今回は武士道以前の話が多かったが、そのうち機会があれば、『葉隠』など武士道以後の話になるかな。 C――『葉隠』は明治になって「発見」されたと言ってよい。近代の武士道論の主要テクストの一つになった。だから『葉隠』をもって武士道を代表させるわけにはいかない。まあ、武蔵サイトとしては、『五輪書』と『葉隠』とはどこがどう違うんだ、という話なら意味があるが。 A――では、そういうことも含めて、いづれまたの話題にしましょうな。 ――本日は長時間ありがとうございました。ではよいお年を。 (2004年12月吉日)
|
